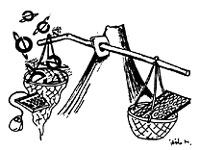去年7月のSHOWYOU20号で、私は、京都府の危機を訴えました。事業税等の大幅な減収により、このままでは京都府は事実上の倒産状態を意味する「財政再建団体」になってしまう危険性を指摘しました。そして、これを避けるには、もはや人件費の大幅なカット以外に策は無いと主張しました。この3月には平成12年度予算案が審議され、共産党を除く賛成多数で可決成立しましたが、私が指摘をした人件費の大幅カットということについては、まだまだ不十分であると思っています。
もっとも京都府も財政再建に手をこまねいているだけではありません。財政健全化指針を策定し、「入るを図りて出を制する」の格言通り、さまざまな方策を打ち出してもいます。今年は、取りあえず定期昇給を12ヶ月延伸をし、通年で57億円の削減が実現しました。しかし残念ながら、収支不足額が500億円規模であることを考えますと、一桁違うと言う他はありません。
私は税理士の仕事を通じて、中小企業の実態をそれなりに知っているつもりですが、それは厳しい経営環境に置かれています。バブル崩壊以来売上が極端に落ち込む一方、二信金の経営破綻の影響もあり、資金繰りには非常に窮しておられます。景気の良いときにはそれなりの給料を取っていた会社でも、こうした危機を乗り切るために自分や家族の給料を半減してまで頑張っておられます。中小企業の経営者は保証人になっているのは勿論のこと、自分の家屋敷までも担保に入れて会社の経営にあたっている訳で、文字通り命がけで経営をしているのです。
また、いわゆる大企業においても、40代になったとたん肩叩きにあい、系列の子会社に出向させられて給料は半減し、2、3年後にはその子会社が精算されて職も無くしてしまうというようなケースも見聞きする時代です。公務員だけが一人、給料も雇用も世間の風、何処吹くものぞとしていられるはずがありません。
しかしだからと言って、公務員の数を一度に半減したり、給料を半分にしたりすることを私は言っているのではありません。そんなことをしたら、かえって雇用環境が益々悪化するだけで、京都府の財政は良くなっても経済全体が冷え込んでしまいます。職員一人一人の生活自体も破綻をしてしまいます。私が言っているのは雇用はしっかり守りながら、非常事態を回避するためにみんなが少しずつ我慢し合おうということです。例えば、人件費を10%カットするだけで、年間300億円以上の節約ができることになるのです。これだけの全額のカットが出来れば後の200億円程度は、いくらでも調整することは可能です。今後こうした不況が続いたとしても京都府が沈没する心配は無くなるのです。
しかし、このことを実行するには大変な反対があり困難だとする声があります。まず、京都府が負担する人件費は約33,000人分ありますが、そのうち警察官が7,000人残りが京都市などの市町村の小中学校および府立高校などの先生で、知事部局(いわゆる府の職員)は7,500人にすぎません。それなのに府の職員のみならず、先生や警察官の給料まで減額することにみんなの理解が得られるのだろうか、特にスト権ばかりか、団体交渉権も持たない警察官などのことを考えると人事委員会勧告の趣旨に反するのではないかという意見があります。また、公務員の給料をいたずらに下げるより、まず組織を見直して、出来るだけスリムな体制を作ることのほうが、職員の士気を損なうことも無く利口ではないかという意見もあります。これは至極もっともな意見ですし、実際にこうした組織の見直しをしても、その効果が出るまでの間には5年から10年もかかるということです。例えば京都府では今年、京都市内に9箇所あった府税事務所を3箇所に削減することを決めました。これにより80人くらいの職員が減ることになりますが、実際に人件費が減るためにはこの人数の退職者が無ければなりません。悪いことをした人を懲戒免職するならいざ知らず、不要な人材を民間企業のように、首切りをすることは公務員には出来ません。また雇用の秩序を考えてもすべきで無いと思います。このため、組織のリストラは将来を見据えて必要なことですが、今すぐにその効果を期待することは現実には出来ないということです。
また財源確保ということで、東京の石原知事が、大手銀行を対象にした外形標準課税の導入を決めました。これによって1,100億円程度増収が見込まれるということでしたが、仮にこれと全く同じ税を京都で導入した場合はどうなるでしょう。試算としますと、税収は40~50億円増えますが、その増えた分の8割が地方交付税の交付が減額されるため、実際に増える金額は8億円程度だと言われています。新税導入も、京都のように交付税を受けている自治体ではその効果を期待するのはなかなか難しいということです。こうしたことを考えても今すぐに500億円の財源を調達し、しかも、それを今後10年間用立てるためには、人件費の最低10%の削減は避けて通れないことなのです。またその前提として我々の議員報酬のさらなる削減と定数の減員は当然のことです。
ところで、公務員の給料は、人事委員会の勧告によって民間給料との調達がなされています。ここで調べられている企業というのは、国の人事院の指導の下で行われていますが、昭和40年以来、従業員数100名以上の企業だけがその対象となっています。いわば中堅規模以上の企業ですが、実質は大企業だけが対象になっているということです。公務員はスト権を制限されて云々と言われますが、大企業ならともかく、中小企業の場合には実質上スト権も団体交渉権も何もありません。景気が良いときはまだしも、不況のときにはたちどころに給与が下がるどころか、首になることもざらにあります。このような中小企業に勤めておられる方が、実は日本人の大半であるということを忘れてはならないと思うのです。公務員はその職責を果たすためには有能な人材が必要ですし、そのためにはそれなりの給料も保証しなければなりません。しかし今日のような未曾有の経済状況が続いているときに、自分たちだけが雇用も給与も安定していることになんの疑問も持たないということ自体が、実は危機感の喪失であり、国家の危機であると思うのです。
日本は今、百年に一度の変革期に入っています。人口動向を始め日本の右肩上がりの経済成長を支えてきた仕組みは崩れ去り、経済も社会も新たな秩序を求めての模索の時期にさしかかっているのです。しかしそのこを決して恐れる必要はありません。冷静に考えれば、日本のような狭い国土の中で、1億2千5百万もの人口を支えてきたことが世界の中でも特異なことであり、ましてやこのまま経済も人口も右肩上がりで伸び続けること自体異常なことではないでしょうか。世間では少子化の影響で人口が減り、社会から活力がそがれてしまうということを、大変心配していますが、むしろこれは今までの異常な経済成長を調整する局面に入ったと考えれば決して心配することではありません。
例えば、今までの日本は、3人家族で300万円の所得の世帯であったものが、4人家族になり所得もそれに合わせて400万円になり、5人になれば500万円というように経済発展をし続けてきたのです。バブルのときは5人から6人に増え、所得も500万円から600万円どころか700万円にも800万円にもなると誰もが信じ、それを当て込んだ投資をしてきたのです。ところがバブルが崩壊してはっきり分かったことは、家族は5人から6人になるのではなく、5人から4人になってくるということだったのです。そこで、6人家族のために投資してきた生活をもう一度身の丈を4人家族で暮らすためのものに調整しなければならない事態になったのです。6人家族のために建てた家は売って、もう一度4人家族用の家に住み、一からやり直そうこれが、今民間で行われているリストラの意味です。6人家族から4人家族に身の丈を合わせるためには、家を売ったり多少の勇気が必要ですが、それさえ決断すれば、後は心配しなくとも家族みんなが力を合せれば十分暮らしていけるのです。しかも、もしこの決断が出来なければ、それこそ一家は離散し破滅に向かうことになってしまいます。丁度、日本も京都もこれと同じ状況に立たされているのです。
吉田松陰の言葉に「国家の大事といえども深憂するに足らず、深憂すべきは人心の正気足らざるにあり」というものがあります。激動の幕末を、国を救うために一命を賭して彼が訴えたものは、まさに国家存亡の危機に立っているのに、旧態依然とした幕府官僚の危機感のなさを打破することだったのでしょう。正気の充満したリーダーを育てれば必ず日本は救われる、じたばたすることはない。ということではなかったでしょうか。
今日本は、幕末と同じ国家の大事に遭遇しているのです。まさに人心に正気の満ち溢れんことを願うばかりです。

西田昌司議員が街頭遊説を始めてはや6年目を迎えます。毎朝、雨の日も風の日も続けておりますが忙しい朝の時間帯のせいか、立ち止まり聴く人はなかなかありません。そこで「我々昌友会だけでもじっくり西田議員の話を聴こうじゃないか。」、ということになりました。毎月1回六孫王神社におきまして、「昌友塾」と銘打ち身近な問題として教育や経済・日本のあり様を話し合っております。「二信金の破綻」をテーマに去る3月14日昌友塾を開催しましたところ、多数のご参加を頂きました。ご参加された方々のご意見を紹介いたします。
広森 日出夫(会社経営)
日本国民として誇りの持てる教育(歴史、文化、伝統他)についで塾を取り上げ、子供たちに伝えていただきたく思います。平和、権利、自由、人権について取り上げ、その基礎となるもの、「真にあるもの」について塾で討論したく思います。
《西田昌司:まさに、日本の国柄を考えるということだと思います。》
谷口 広和(会社員)
私が昌友塾に参加させていただくきっかけは当事、橋本内閣が景気が良くないのに、どうして経済対策をしないのだろうかと思い、西田先生に手紙を出したのがはじまりです。早速録音テープで御返事をいただき、なんと政治を身近に感じさせてくれる政治家なんだろうと感動したものです。もっと自分自身、政治のことを勉強しなければならないと思いました。まだまだ勉強不足ですが、先生、昌友塾の皆さん、よろしくお願いします。
先生は、大事にしなければならないのは、家族の絆、友達の絆、ご近所との絆であると熱弁されていますが、私は感動すら覚えます。
しかし、先生のおっしゃる府職員の給料を10%カットするという考えには反対です。
財政難の責任を府職員の人達だけにとらせるのはおかしいと思います。それならば、公的資金の入っている銀行の給料を下げたり、損失を出したトップ達の私的財産もとらなければならないし、身売りして買い取られた銀行からも公的資金を回収しなければならないのではないでしょうか。
私は府職員が責任をとらされる前に、責任をとらなければならない人達がたくさんいると思います。大事な事は、先生のおっしゃる大和魂ではないでしょうか。私が責任をとろうと、自分から進んで責任をとる精神、そういう人が増えていく事が大事なのではないでしょうか。
《西田昌司:リーダーの大和魂こそ、今一番求められているものです。》
柿本 大輔(高校生)

私のような高校生が、府議会議員の先生や立派な社会人の方々に意見するのはおこがましいと思いますが、未成年の主張と受け止めてください。
今回初めて「昌友塾」に参加しましたが、皆様方の前で私は唯々理解したような振りをするのが精一杯でした。京都みやこ信用金庫の破綻の原因、これから先の京都の経済、学校では学べない多くの事に触れられたと思います。
そこで、私一個人の見解を述べさせていただきますと、「子孫の為に美田は買わず」ならまだしも、負の遺産を押し付けるのはやめていただきたいと思います。大人達がバブルに踊った付けを私達に精算させるのは、お門違いではないでしょうか、というのが私の考えです。
学校ではこのような生きた社会科学習を一切しません。歴史の授業では、第二次世界大戦終了までしかやっていません。大抵授業では「日本は戦争ばかりしていて悪い国である。」程度の事しか私達は学習しないのです。これでは今の日本、延いては日本経済に興味を持てというのは無茶な話です。戦後から現在までの流れを知ってこそ、これからの私達の時代が作れる筈なのに、入試に出るから歴史の年号を覚える、これでは再び今のような不景気に陥った原因を繰り返すのは必至です。歴史の授業とは、そもそも過去と同じ過ちを繰り返さないために学ぶものではないでしょうか。
ここで私は提案をします。私と同じ年代の人達にも、皆様方のお話、ご意見を聞かせてやってほしいのです。そうする事によって、私達は、もしこのような不景気に陥った時、最小限のリスクで不景気を乗り越えられると思うのです。
《西田昌司:若い世代の参加を待っています。一緒にこの国を背負って行きましょう。》
田端 俊三(会社経営)
この塾に参加してつくづく思い知らされたのは、「われわれの社会の現状」を余りにも知らなすぎる自分でした。
教育、家族、経済など、私はその基本である「あり方について」ここで初めて考える場を得ました。もし、西田先生や塾の皆さんと出会っていなかったら、耳触りの良い話を信じ込み、「いまのままでいいじゃないの。なぁ、みんなもしんどいのイヤじゃない。・・・・・・」の調子でいたと思います。それを考えればぞっとします。
これからも、辛口で真剣な思いをぶつけられる場としての塾にしていけるよう協力したいです。
《西田昌司:素直な心で、真剣に現状を見る。そこから全ては始まるのです。》
中路 雅之(自営業)
西田さんの活動報告の後、各回ごとにテーマに沿って意見交換がされますが、出席者の見識の広さと理解の早さには驚きます。
新聞等の政治や経済、教育などの雑多な記事が、どう結びついてどう形を変えて我々に関わってくるのか、テーマ選択の理由やその論理と対応する速やかな行動力には言葉もありません。
今回の「信金破綻と京都経済」では、一言では済まない複雑な広がりを持つ問題ということに気がつきました。
この塾が西田さんの手を離れ、逆にオブザーバーとして招き、活動の提言などできるような会にまで発展されることを期待します。
日頃、芸能と三面記事を主たる会話としている身には、話の内容は理解の範囲を超えていますが、TV討論会の観戦者ぐらいの軽い気構えでまたおじゃましたいと思います。
《西田昌司:是非、昌友塾をそういう形で広げてください。私達一人一人が本気になれば、必ず社会は変わります。》
-インターネットで商売?-
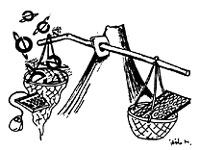
景気が低迷しているなかで、もうけるためには手段を選ばない人達が増えてきています。それもインターネットという怪物で「商い」をつぶそうとしています。
例を挙げると和装品です。和装品は長い歴史と伝統により産地や室町といった流通機関を築き上げてきたのです。それだけに複雑な商取引、生産形態を持ち、そのことが和装品の消費者不信を招いているのも事実です。だからと言って、染屋さん、織屋さんが問屋も小売店も経由せずに「うちで買えば市価の三分の一で買えます。」と、インターネットで直接消費者に着物を売ったらどうなるでしょう。流通機関をかき回したとも思われない。一枚でも着物が売れればそれでいい。結果がすべてで、生き残っていくためには・・・・・・。
また、最近話題のソニーの新ゲーム機「プレイステーション2」はインターネットで注文を受けたため小売店では「これが広がると既存店の首を締めかねないし、インターネット上で値引き交渉でも始まれば・・・・・・」と危機感を募らせています。
棟割長屋、井戸端会議が見られなくなった今、人はパソコンに向かいインターネット上で「商い」をしようとしています。本来、「商い」は作り手のピッチャーが使い手のキャッチャーにボールを投げるのと同じで、単に商品を動かすだけで利益を稼ぐものではないはずです。そこには「商人」としての使命感と責任感があるはずです。かつて孔子様は「おべんちゃらを言って商いをするのは恥ずべき行為」と言っています。江戸時代の儒学者・石田梅岩先生は、働くことと「商い」の使命感をもちなさいと教えています。梅岩先生は室町の呉服屋で丁稚奉公をしながら商いの実践を説いており、この教えは滋賀県の近江に伝わり西武、大丸、高島屋、伊藤忠などの近江商人の原動力になったそうです。
今の流通機構に問題がないわけではありませんが、さりとて不要とは思いません。インターネット商法が台頭してきた今、「商い」とは何か、室町の問屋筋をはじめ皆で考えようではありませんか。
それには近江八幡で作られた「天秤棒のうた」のビデオも参考となるでしょう。(レンタル店でも手に入ります。)
4月という語からは、新緑や息吹き等の冬の間に蓄えられたエネルギーが花開く希望という言葉を連想します。九条中学校にも今年も多くの”若い希望の芽” が入学してきます。昨年には『ふれ合いコンサート九条の心を歌う』と題して、地域の皆様やOBの方々とスクラムを組み、九条の地で育つ”喜びの歌”を合唱しました。この歌声は、地域と家庭・学校が一体となって、子どもを育み慈しむ喜びを体現したものと思っております。また、学校行事としての参加授業ではなく、ご両親に日頃の学校生活を見てもらうために、度々授業参観を行ってもらいました。これは生の姿を見て、親として家庭で何が出来るのか、保護者として学校にどう関わるのかを考えていただく目的でした。これからもこのような機会を設けていきたいと思っております。
ある会合で、どんな子どもに育てたいかという話題が出ました。その時には『人に迷惑をかけず、やりたいことをして欲しい。』という意見が大勢を占めたように思います。しかし、人に迷惑をかけず自分のしたいことをするというのは、生きていく上での社会のルールであって最低限の約束事だと思うのです。やはり『育って欲しい』中味には、子どもの大志や理想を期待したいものです。地域での社会のルールを学び、家庭では社会に貢献する人となるように大志を親子で話し合う。これも地域と家庭の役割の一つだと思います。
親としての望みや期待を話し合い、子どもに「生きる知恵」と「人としての道」を教え、親の姿勢を見せるのも、昔から日本の家庭教育の役割でした。いたわりや慈しみを土台に、『よりよく生きる』ことを子どもと話し合って欲しいと思います。”若い希望の芽”が、大志という社会に貢献できる力と人格を備えた大木となるよう、共に努力したいと思います。
編集後記
すっかり春めいてまいりました。私は先日、『結婚』という春を迎えました。西田議員にもご出席賜わり、ご祝辞を頂きました。今号に掲載した写真はそのときのものです。
私たちへのはなむけとしてイギリスのチャーチルの、『もし神が許されるなら、あの母の胎内から出てこの妻とともに人生を送りたい。』という言葉を頂きました。心に残るとても素晴らしい言葉です。
いつまでもこのような気持ちを忘れずに、幸せな家庭を築きたいと思っています。
私事で大変失礼致しました。
編集室 木村和久