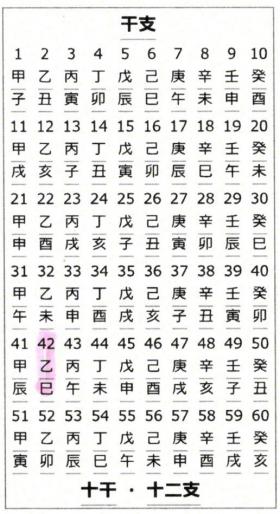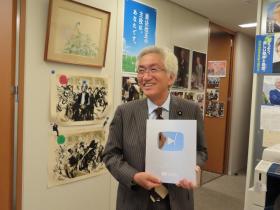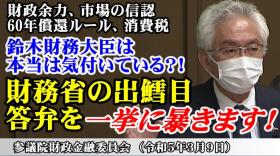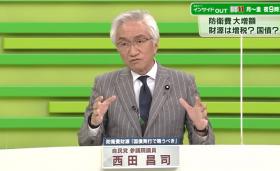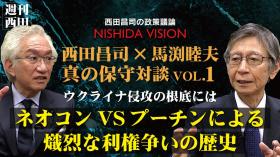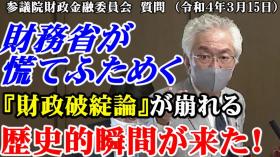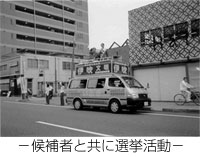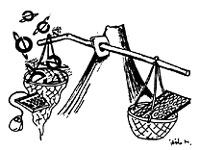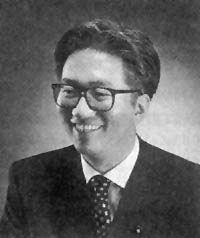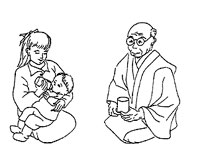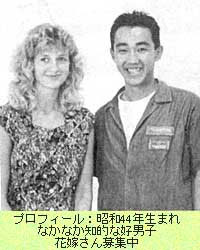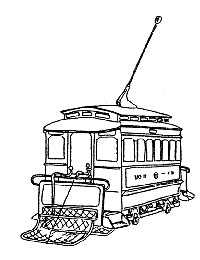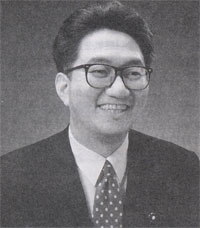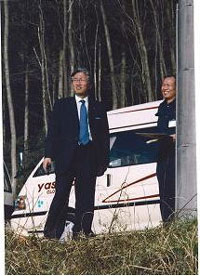先代社長の遺言を反故にして、会社を潰した重役たち
いわゆる政治資金パーティーの還付金問題について、国民の皆様に政治に対する不信の念を抱かせてしまったことに対して、先ず以て心よりお詫び申し上げます。
私自身の事実関係については後述いたしますが、この問題は、2年前の4月、安倍派の会長であった安倍元総理が、派閥パーティーの違法な還付に気付き、直ちに中止することを決断し、派閥の幹部にその旨を伝えていたと言われています。ところが、その年の7月に安倍元総理が暗殺されてしまった後、遺言となったその決断を反故にして、そのまま継続してきたことが、最大の問題点です。安倍元総理の遺言を守り、還付を中止していたら、このような事態にはならなかったはずです。
今回の事件は、会社に例えれば分かり易いのです。先代社長のおかげで業界トップになった会社がありました。その社長は、先々代以上前の社長から行われていた違法な取引を知り、直ちに中止するように重役会で命じました。ところが、その社長が急逝してしまいます。残された重役達は、社長の遺言を反故にして違法な取引をそのまま継続しました。その事実が発覚し、社会的な非難を受け会社は倒産してしまいます。その会社で働いていた社員の中にも不正に加担しているとは知らなかった人もたくさんいます。その一方で、その違法な取引を利用して成績をあげていた社員もいたでしょう。社員たちの責任は、それぞれのケースによって異なりますが、最も重い責任を負うのが、社長の遺言を反故にして違法行為を継続した重役たちであることは言うまでもありません。
今回、自民党の党紀委員会において、この重役たちにあたる派閥幹部には、離党勧告など、その責任に応じた処罰がなされることになりました。私自身は、党紀委員会ではなく、幹事長からの注意となりましたが、「私自身がもっと早くこうした事実を知っていれば、こんな事態にはならなかった。」と大いに反省するとともに、ご心配をおかけした皆様に心からお詫び申し上げます。
私の場合の事実関係
 参議院政治倫理審査会に出席し、説明責任を果たしました。また、派閥幹部に対しは厳しく責任を追及いたしました。
参議院政治倫理審査会に出席し、説明責任を果たしました。また、派閥幹部に対しは厳しく責任を追及いたしました。
私も昨年の報道によりこの事態を知り、派閥担当の秘書に問い詰めて、初めて事実を知りました。秘書によると、初めて派閥から還付金の通知があった時、「正式に派閥からの寄付金として処理してほしい」と派閥側に申し出たそうです。しかし、当時の派閥の事務局長からは「皆もそうしているから、西田事務所も従って欲しい」と不記載を要請されたそうです。この時点で私に相談や報告があれば、間違いなく派閥に抗議していたでしょう。しかし、従わなければ派閥での私の立場がなくなるのではないかと案じた秘書が、自分の胸の中だけに留め、翌年以降の派閥のパーティー券購入に充当することで派閥に還付金を返金し、相殺することを一人で悩みながら決めたようです。従って、私の事務所には事実上派閥からの還付金は1円もありませんし、捜査を担当した東京地検特捜部の検事もこのことは認めています。
しかしながら、私の秘書に対する監督不行届きは否定できません。そこで、こうした事実関係を確認した後、直ちに、参議院の特別委員長の辞任を申し出て、自分としてのけじめをつけることにしたのです。
会社を潰した重役たちの責任
ところが、肝心の会社を潰した重役たちは「知らぬ、存ぜぬ」を繰り返すばかりです。私は、事実上派閥の最後の総会となった日に、「あなたたちは、安倍元総理の後ろ盾で今の地位を築いてきた。しかるにその遺言を反故にして、『知らぬ、存ぜぬ。』では御霊に申し訳なくないのか。」と、厳しく派閥幹部を糾弾しました。けれども、それに返答する人は誰もいませんでした。
その後、与野党間で衆参両院での政治倫理審査会の開催が話し合われていましたが、派閥幹部たちは誰一人出席の意向を示しませんでした。そこで、私が、ぜひ政治倫理審査会に出席して弁明したいと申し出をしたのです。元より、私が出席しても、安倍元総理の遺言を反故にした経緯など知る由も有りませんから、事実解明などできません。しかし、私は「倒産した会社の一従業員」としての自分の立場を弁明することにより、重役たちの出席を促したのです。
何人かの、派閥幹部が出席し弁明しましたが、結局誰も納得できる説明をした人はいませんでした。彼らは、東京地検特捜部からも事情聴取を受けましたが、結局は起訴されませんでした。これをもって「自分は嫌疑なし、真っ白だ」という人もいました。しかし、刑事責任を問われなかったことと、政治家の責任が問われないのとは次元が違います。
政治家は国民の代表として選挙で選ばれたのです。しかし、国民からの信頼がなければ、その立場は無くなるのです。刑事責任の有無にかかわらず、国民からの信頼が大切なのです。政治倫理審査会は、まさに、そうした自分の立場を国民に弁明するために設けられた機会なのです。私が進んで出席を申し出たのも、国民に対しどうしても自分の立場を説明したかったからなのです。
同時に、安倍元総理が中止を決定した還付金が、何故復活したのか、その説明責任を果たさない派閥幹部たちに対しての、私なりの抗議の意思表示でもありました。
自民党の処分についての私の見解
 政倫審に出席後、BSフジ「プライムニュース」に出演いたしました。
政倫審に出席後、BSフジ「プライムニュース」に出演いたしました。
政治資金の不記載をした国会議員に対して、自民党としての処分が決定されました。事実上の派閥の責任者には離党勧告、その他の者は、派閥の役職の軽重や金額の大小に応じて、党員資格停止や戒告などの処分が下されました。
私は、こうした処分がなされる前に、派閥幹部たちは自ら出処進退のけじめをつけるべきだったと思っています。検察に嫌疑無しと認められたから自分は白だというのは、検察に対しては言えても国民に対しては言えないでしょう。そのためにはもう少し誠意ある説明を政治倫理審査会の場面でも示すべきでした。
常識的に考えれば、派閥幹部と言われた人達が還付金の存在を知らなかった筈は有り得ません。百歩譲ってそうだとしても、幹部としての政治責任は免れません。その事を自覚していれば党紀委員会の処分がある前に何らかのけじめを自ら示すべきでした。そうすればまた違う展開になっていたでしょう。そのことが私は残念でなりません。
個別具体的に還付金の実態は異なる
還付金について所得税がかかるのではないか、という指摘があります。これを私は参議院財政金融委員会で法務省と国税庁に質問しました。その答弁は、「東京地検特捜部は不記載の多額なものなど悪質なものについて立件していますが、その内容は政治団体の間での政治資金の収入と支出の不記載があった。」ということです。つまり、政治家個人ではなく政治団体に政治資金が帰属していると検察が認定しているということです。従って、「政治家個人の所得ではないため課税されません。」ということでした。これが、全国から百人を超える検事を集めて調べた結果、検察の出した結論だったのです。
私は政治団体ではなく政治家個人の帰属ではなかったかと疑われるケースもあるように思います。しかし、事件としては検察の事実認定には従う他ありません。その一方で、党紀委員会で処分を受けた方の中には、弁明書を提出して処分に対して異議を申し立てている人もいます。
確かに、それぞれ個別の事情があるのは事実でしょう。還付金について事務的なことは秘書に任せ、全く知らなかったという議員も多数います。また、還付金を派閥からの預り金と思い、そのように処理していたという議員もいます。現実は個々別々なのです。だからこそ、政治倫理審査会に出席し、私のようにその事実を説明すべきだったと思います。
政治の現実を知った上で議論すべき
 京都市長選挙での松井孝治氏の当選を岸田総裁に報告いたしました
京都市長選挙での松井孝治氏の当選を岸田総裁に報告いたしました
今回の事件で政倫審に出席を申し出た時、私は改めて自分の政治資金報告と野党の議員の政治資金報告とを見比べてみました。「政治にお金が掛かると言うが、一体何に掛かるのか」よく指摘されることです。
私は京都府議会議員を務めた後、参議院議員になりました。それにより、選挙区が大幅に拡大しました。人口10万人の京都市南区から人口250万人の京都府全域が選挙区になったのです。政治家は様々な行事や会議に案内されますが、参議院議員になってからは、その数は格段に増えました。平日は国会のため、秘書が代理で出席します。週末は私が出席しますが、複数の会合が重なる場合には秘書が代理で参加します。そのうえ、飲食を伴う場合には会費を負担することになります。こうした会合の案内が年間数百件以上あります。また、私はShowyouを年に4回発行していますが、年間約10万通を印刷し郵送しています。更に、私には公設秘書以外に3人の私設秘書がいます。こうした経常的活動だけで年間数千万円以上のお金が掛かることはご理解いただけると思います。そして、6年に一度ですが京都府全域を選挙区にした参議院選挙があり、そのための準備も必要です。こうした活動に要する経費は党からの助成もありますが、基本的に自分で用立てる必要があります。
しかし、野党の場合には基本的にこうした活動費を全て政党が賄っているところもあります。また、労働組合や宗教団体が実質負担している政党もあります。特にマスコミ出身の議員に多く見られるのですが、私のような日常活動が政治資金報告の中に、殆ど記載されてない議員が多々おられます。マスコミに出るだけでそういう日常活動が不要な方もおられるのです。
遵法精神の無い政治家が批判されるのは当然ですが、現実の政治活動を無視した改革論も問題です。パフォーマンスではなく、国民の代表たる政治家をどうすれば選出できるのか。本質的な議論が必要なのです。
樋のひと雫
-アンデス残照-
羅生門の樋
先月、ボリビアの研究会の打ち合わせがネット上でありました。現地に行けないのをコロナの所為にしていますが、彼らも日常が戻ってきたとのことで一安心しています。雑談の中で「アルゼンチンの様子はどう?」と聞きました。昨年の大統領選の際に「ペソを廃止し、中央銀行は廃止する!」等の過激な演説をしていたハビエルが当選したので、少し気になっていたのです。年末に大統領の就任式が有ったのですが、同時に軍事予算も不足して海軍の艦艇が動かないとか、戦闘機の代替え予算が不足している等の情報も聞こえてきました。農業や牧畜が主産業とは云え、チリと共に南米の大国と言われた国がこうも極端に困窮するのかと不思議な気がします。未だ中央銀行が存続しているという事は、ペソが持続しているという事でしょうか。ブエノスには10年近く通いましたが、街頭に「CAMBIO!CAMBOI!(両替)」の声が聞こえるのがブエノスらしいのですが…。
南米には自国通貨を持たない国もあります。エクアドルです。米ドルが通貨として流通しています。当然、自国の予算や経済活動もドルが基盤です。しかし、自国通貨を持たない国が、自らの金融政策の核を放棄して、経済活動をどの様なシステムで統御出来るのか不思議です。仕事で行った際に教育省の人間に聞いたのですが、余り理解できませんでした。ユーロでさえ域内の経済発展の格差を解消出来ずにいるのに、経済発展の道程まで米国に依存するのだろうかと不思議に思いました。まあ、キトの街並みは清潔で色鮮やかでゴミも落ちておらず、南米らしい喧騒もありません。しかし、物価も高く、スターバックでドルで払っていると思わず「THANKs」が出てしまいました。 ボリビアの友人との雑談の中で、アルゼンチンの海軍も我々の「海軍(NAVAL)」になるのではと話していました。操艦訓練も出来ない海軍は、いずれ名目のみとなり海上権益は他国に獲られてしまい、漁業すらできなくなります。今のフィリピンで漁民が漁を出来ない現状は、当時の左派政権が当時アジア最大であった米国の海軍基地の返還を求めた結果でもあると言えます。
政治の大衆迎合、ポピュリズム化が言われて久しいですが、今はこの域すら超えているように思えます。自国の長き将来を考え、子孫が平和に暮らせるにはどうすべきか。今の選択がどのような結果をもたらすのか、「政治家は大衆が生み出す」意味を考えるべき時ですかね。国民の一時の激情を煽り、喝采を受けることを良しとする風潮は、選挙を唯一の手段とする民主主義が内包する脆弱性の現れであるかもしれません。また、そうであるが故に、我々は手段の行使に際して、何よりも冷静で中庸の心を持って臨むことが、今求められているのかも知れません。
お金には価値は無い
 西脇知事・門川京都市長と共に松井孝治さんを応援いたします
西脇知事・門川京都市長と共に松井孝治さんを応援いたします
こんなことを言えば誰もが何を言っているのか、と反論されるでしょう。確かにお金があれば、大概のものを買うことができます。そういう意味では何にでも交換する能力がお金にはあります。しかし、お金そのものには何の値打ちも有りません。金貨の時代には貴金属としての価値がありましたが、今の紙幣はその金貨に交換してもらえませんから、本来は無価値なのです。
お金は正式には日本銀行が発行する日本銀行券、日銀券です。かつては、日銀券を日銀に持っていけば同価の金と交換するとの記載がありました。これを兌換紙幣と言いますが、今は兌換紙幣を発行している国は有りません。
かつては、兌換紙幣ですから紙幣そのものが金と同じ価値を持っていたのですが、不換紙幣になったため、紙幣にはその価値を裏付けるものがないのです。お金に値打ちが無いというのはこのことです。ただ、法律により強制的な通用力が定められています。日本で経済的取引を行う場合には誰も受け取りを拒否できないため、あたかも値打ちが有るように見えるのですが、現実は経済的取引の決済の手段として国家が強制通用力を定めているだけで、紙幣そのものに価値があるわけでは無いのです。
現実の取引には銀行預金が使われる
紙幣は燃えればただの灰になり、保管も大変です。そこで現実の取引では、紙幣に代わって銀行預金が使われています。特に大口の取引では殆どが銀行預金の振替により行われています。最近では、クレジットカードやスマホによる支払いなどもありますが、最終的には全て銀行預金の振替により決済が行われています。
お金を銀行に預ければ、預金残高は増えます。しかし、その増えた分のお金が手許からなくなります。また、銀行から預金を引き出せば、銀行の残高は減りますが手許のお金はその分だけ増えます。このことから、お金と預金は同じものと言ってよいでしょう。
お金は本来無価値なものと言いましたが、預金はどうでしょうか。これもいきなりは信じられないことですが、お金と預金は同じもの、と考えれば、預金も本来は無価値なものということになります。
紙幣は日銀の負債、預金は銀行の負債
そもそも紙幣は、発行している日銀にとっては債務です。経済取引には日銀券を使うことが強制されているため、日銀は自ら発行した日銀券で何でも買うことができるのです。これを通貨発行権と言いますが、世界中の中央銀行が持っている特権です。具体的には、日銀は銀行が保有している資産を買い取り、その代金として日銀券を発行するのです。しかし現実には銀行券の発行ではなくて、銀行の預金口座に金額を書き込むことにより行われます。通貨発行をする度に日銀の資産は増えますが、同時に負債としての通貨発行額も増えます。この様に、日銀は元手となる資産がなくても、自由に通貨発行を行い資産を買うことができるのです。日銀は通貨発行権を行使することにより、世の中に流通する通貨の量を調整することができるのです。それに合わせて金利の調整などの金融政策を駆使して物価安定を使命としています。
また、銀行預金は、現金が預けられたものと思われがちです。確かに、現金を預ければ預金残高は増えます。しかし、現金と預金の合計は変わりません。預けた人にとっては現金が預金に変わっただけのことですから、その人の個人資産の量は変わりません。一方で、銀行にとっては預金を預けられると資産としての現金が増え、負債としての預金が増えることになります。預金は銀行にとって負債であるということが大事な事実です。日銀券を発行している日銀にとっても負債であったのと同じように、預金は銀行にとっては負債なのです。
銀行がお金を貸すから預金が増える
 八幡市長選挙において川田翔子さんが維新候補を破り、見事に当選されました
八幡市長選挙において川田翔子さんが維新候補を破り、見事に当選されました
銀行預金は銀行がお金を融資することにより発生する銀行の債務です。銀行がお金を融資する時には、まず返済がきちんとされるか、融資先の返済能力が評価されます。資産や所得などを総合的に評価して返済可能と判断すれば、融資先の銀行口座に預金が書き込まれることになります。決して預金というモノが動くのではありません。銀行にとっては、貸付金という資産の情報とその対価として銀行預金という負債の情報が記録されたに過ぎません。
融資を受けた人にとっては、銀行預金という資産が増えますが同時に同額の借入金という負債を背負うことになります。ここにもモノの移動はありません。銀行預金という資産と借入金という負債の情報が書き込まれたに過ぎません。この様に銀行は元手無しで、融資先に信用を与えることにより、銀行預金を生み出すのです。このことを信用創造と言いますが、英語ではマネークリエーション(通貨創造)と呼びます。銀行は預けられた預金の又貸しをしている訳ではありません。まさに無からお金を作り出しているのです。
このようにして、銀行は信用供与さえすれば、いくらでも貸出により預金の量を増やすことができます。しかし、貸し付けた融資が焦げ付いたりすれば預金は戻って来ません。また、お金を借りたいという人がいなければ、融資はできず、預金の量は増えません。これも大切な事実です。
日銀の仕事は何か
経済取引の大半を占める銀行同士の口座振替は、それぞれの銀行が日銀に持っている口座の振替により行われています。そのため全国の銀行は日銀にお金を預けておかなければなりません。これを準備預金と言います。準備預金は毎日の取引の決済に必要なものですが、基本的には金利は付きません。従って、銀行は準備預金にお金を置いておくよりも、利息の付く国債などで運用することを考えます。
従って、政府が国債を発行すると、銀行は基本的に手持ちの準備預金を国債に変えようとします。利息の付かない準備預金を保有しているより、国債を保有する方が得だからです。この結果、銀行の準備預金残高は少なくなり、逆に銀行の保有する国債残高が増えることになります。準備預金残高が少なくなると、日々の銀行間取引で必要な決済資金が少なくなります。もし手持ちの決済資金が足らなくなった場合には、他の銀行からお金を融通してもらう必要があります。この時に付く金利は一夜限り(オーバーナイトローン)の超短期の金利で、これが短期金利の指標となります。
また、長期の金利は、国債等が市場で売られるときに日銀が誘導する金利になるように買入れ調整をします。これが、現在では0から1%以下になるように設定されています。
限界があるのは通貨発行量ではなく、資源と供給力
 参議院財政金融委員会で鈴木財務大臣に社会保険料の減額と消費税減税について質問しました(YouTube西田昌司チャンネルで公開しております)
参議院財政金融委員会で鈴木財務大臣に社会保険料の減額と消費税減税について質問しました(YouTube西田昌司チャンネルで公開しております)
日銀の通貨発行は原資を必要としていないため、その上限はありません。これが不換紙幣の特徴です。また、銀行の信用創造も元手なしで行われており、その上限も理屈の上では無いということがわかります。つまり、世の中に流通している紙幣も、預金も、その発行の上限は理屈の上では無い、これが事実なのです。しかし、だからといって、いくらでも通貨を発行したり、融資したりできるわけではありません。まず、日銀の通貨発行は日銀が銀行から資産を買い取ることにより行われています。また銀行の融資は貸付金と言う資産を取得することにより行われています。取得すべき資産がなければ負債である銀行券も銀行預金も増やすことはできないのです。
お金も預金も結局は何かを買うために使うモノです。将来の不安のリスクに備えるために貯めることも必要ですが、それも、結局は何かを買うための備えあってお金が有限でモノは無限にあると思っているからです。
平時は確かにその通りです。しかし、有事になればどうでしょうか。かつて、大東亜戦争の敗戦によりハイパーインフレが起きました。その原因は戦時中に国債を発行し過ぎたからだと教えられてきました。しかし、国債を発行したのは戦時中で、インフレは占領中のことです。国債発行で通貨量が増えたのも事実ですが、占領中にインフレになったのは明らかに物不足が起因しています。
戦時中と占領中の決定的相違点は、物不足、供給力不足です。確かに、戦時中も物不足でした。しかし、それにも増して占領中は敗戦により外地からの資源の輸入が完全に途絶え、更に空襲により生産拠点が壊滅的に破壊されて圧倒的な物不足が起きました。また、終戦による開放感が需要を伸ばしたことも空前のインフレの原因でしょう。
財務省は誤りを認めるべきだ
以上の事実を元に、もう一度日本の現状を見てみましょう。日本に足りないのは、お金ではありません。お金を生み出す需要なのです。バブル崩壊後、民間のコストカットから身を切る改革に至るまで徹底的な需要抑制策が官民挙げて行われてきました。そのため銀行の貸出しは減り、内部留保ばかりが増えました。その結果、投資不足になり、デフレを生み出しました。それにより政府は税収不足に陥り、赤字国債を発行せざるを得なくなりました。本来なら、政府が積極的に投資拡大をして需要を増やすべきところを逆に緊縮財政を行ってきました。その原因は、お金の本質を知らずに誤った政策を行なってきたからです。
需要を抑制し過ぎたために、日本はデフレになってしまったのです。需要があるから、銀行の貸し出しが増え、投資や消費が増え、経済が拡大するのです。需要の創造とそれを実現するための正しい財政と金融の政策が必要なのです。お金はいくらでも刷れますが、そのためには需要が必要なのです。また、需要が拡大してもそれを満たすだけの生産力がなければ、終戦後のようなインフレになってしまいます。
財務省はお金の本質を見誤り、その裏にある需要がお金を生み出す仕組みを無視してしまったのです。税による財源にこだわり過ぎたため、国民の要望の高いインフラ整備など、生産力向上のための投資や、子育てや教育支援など、次世代に対する投資が否定されました。その結果、日本は少子化に陥り、肝心の生産力にも支障を来たす事態になっています。真のデフレ脱却のためには今こそ、人と将来への投資を増やすべきなのです。
瓦の独り言
「干支と方角 面舵いっぱい!」
羅城門の瓦
甲(きのえ)辰(たつ)年。新年あけましておめでとうございます。
お正月には干支の話がつきものですが、干支と方角について一言。
昨年の12月に京都文化博物館で、「どんぶらこん」という面白い展示会がありました。
おとぎ話「桃太郎」をアジアの絵本作家に描いていただいた展覧会でした。その時に桃太郎の船に必ず「猿・きじ・犬」が同乗していたのです。鬼退治に出かけるのになぜお供が「猿・きじ・犬」なのでしょうか?おとぎ話を子供にしているときに「桃太郎の家来はなぜ猿・きじ・犬なの?」と聞かれて、若いお父さんやお母さんはどうこたえるのでしょうか。インターネットなどで調べれば答えは出てきますが、そもそも鬼退治の鬼はどの方角からやってくるのでしょうか?京都の人であれば「それは鬼門から来るのでは」との答え。その鬼門は「丑(うし)・寅(とら)」の方角です。(ですから節分の鬼は牛の角を生やし、虎のパンツをはいているのです)その丑寅の反対側にある方角は「申(さる)・酉(とり)・戌(いぬ)」なので、桃太郎が鬼退治に連れて行った家来は「猿・きじ・犬」なのです。
この様に日本古来、干支と方角は切っても切れない関係にあり、日常生活に浸透しています。例えば、船の航海でよく使う「面舵いっぱい!取舵いっぱい!」という言葉。図の羅針盤を見ていただくと、船頭が南側から北に向かって右旋回(東の卯の方向へ旋回)することを面舵といいます。昔は「卯舵」と言っていたが発音が訛って「面舵」になったとか。左旋回(西の酉の方向へ旋回)することを取舵といいます。「酉舵」の発音はそのままで「取舵」になったとか。また、船舶のタラップ(出入口)はおおよそ左側についており(航空機も)、出向するときは右方向へ大きく旋回していきます。これを面舵いっぱいといいます。
さて、来る2月4日の市長選挙には、われらが国政にお送りしている西田昌司参議院議員を中心に「松井孝治氏」を推薦されております。
さあ! 「突き抜ける世界都市京都」に向けて、面舵いっぱい!
岸田内閣は、歴代内閣の経済政策を180度転換している
10月23日に岸田総理は、衆参両院で所信表明演説を行いました。その中で総理が特に強調したのは、何よりも経済です。「30年来続いてきたコストカット経済からの変化が起こりつつあります。この変化の流れを掴み取るために、持続的で構造的な賃上げを実現するとともに、官民連携による投資を積極化させていく。経済、経済、経済、私は、何よりも経済に重点を置いていきます。」
このように、経済再生に断固たる決意を表明し、その上で、今回の総合経済対策は「供給力の強化」と物価高を乗り越える「国民への還元」を「車の両輪」として実行すると宣言されました。財政健全化と言う言葉は一言も発せず、岸田内閣が積極財政に舵を切っている事は明白です。にもかかわらず、相変わらず世間では、そのうち増税をするんだろうと疑心暗鬼になっています。その理由は、岸田総理が財政に対する従来の考え方を180度転換したということを、総理が自らの口できちんと説明されていないからだと思います。総理に代わり、私がまず大事な事実を皆様方に説明いたします。
国債発行による予算執行は民間への通貨供給である
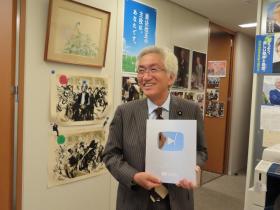 YouTubeチャンネル登録者数が10万人を突破!「銀の盾」が届きました
YouTubeチャンネル登録者数が10万人を突破!「銀の盾」が届きました
大切なことは、国債と税金との関係を正しく理解することです。世間では未だに、国債発行は、国の借金であり、次の世代にそのつけをまわすべきでないと信じている人がいます。しかし、これは国の財政を家計と同じと考えることからくる間違いです。
国家は、家計と違い、徴税権と通貨発行権があります。徴税権とは文字通り、税金を徴収する権限です。通貨発行権とは、具体的には国債を発行して予算を執行することなのです。国家には通貨発行権があることは学校でも教えていますが、それが具体的にどういう仕組みで行われるのか、ほとんどの人がご存じありません。
現実には次のような仕組みで行われます。まず、①政府が国債を発行し、銀行がその国債を購入する。②政府の預金口座に銀行がお金を振り込む。国債は銀行の資産に計上される。③政府が予算を執行する。そのお金が政府預金から民間部門の誰かの預金に振り込まれる。
そして、こうした過程の中で、日銀が民間銀行から国債を買い上げます。④日銀が買い上げた国債は、日銀の資産となり、代金として銀行の口座に日銀から預金が振り込まれる。
以上のことが繰り返し行われることにより、国債残高は増え、その増えた分だけ民間部門の預金残高が増えることになるのです。そして、現実には、以上の取引は、コンピュータの操作により行われています。つまり、お札も国債も動くことなく、キーストロークの操作だけで通貨が発行され、銀行預金の残高が増えるのです。
この事実から次のことが分かります。
a国債発行により予算を執行することは民間部門への通貨供給である。
b国債残高が増えた分だけ必ず民間部門の預金量が増える。また、①から④の行為は政府と日銀が協力すれば無限にできる。
cつまり通貨供給に制限はない。
国債の償還は借換債で行なっている
今度は国債の償還について考えてみましょう。国債の償還は、税金で行っていると考えている人が多いですが、実は違います。国債の償還は、借換債の発行により行っているのです。政府は国債の償還に必要な金額の国債を新たに発行し、その国債を銀行が買い上げる。つまり上記の①と同じことが行われているのです。違うのは、⑤それにより得た資金で政府は、国債の所有者、つまりは銀行もしくは日銀に国債償還の資金を振り込み、国債を回収する。現実は銀行と政府の間で新旧の国債が交換されただけです。従って民間部門の預金量に変化はありません。
この事実から次のことがわかります。
d国債の償還は税ではなく、借換債の発行(償還期限の延長)により行っている。
e国債の償還に財政の負担はない。国債の償還を借り換え済で行っているのは、日本だけではなく、全世界共通の仕組みであり、もし仮に税金で国債の償還を行うとなると、国債残高がその分だけ減ることになる。
Fつまり、国債残高が減れば民間の預金量が減ることになるのである。
現在1100兆円を上回る国債が発行されています。つまり、1100兆円通貨供給が行われたということです。事実、日銀の資金循環統計によると家計の金融資産は1100兆円を上回っており、上記の③が真実であることがわかります。
日銀保有国債には利払費も政府負担は無い
 空白区であった3つの選挙区支部長が決定いたしました(2区佐野英志・3区森干晟・6区園崎弘道)
空白区であった3つの選挙区支部長が決定いたしました(2区佐野英志・3区森干晟・6区園崎弘道)
安倍内閣以来の異次元の金融緩和の結果、現在、国債発行残高の1/2以上を日銀が保有しています。そのため、国債の利払い費も半分以上は日銀が受け取ることになります。そして、日銀に支払われた金利は、諸経費を除いて全て国庫に納入することが日銀法により義務付けられています。これから金利が上がれば利払い費が増え、それが原因で財政が破綻するのではないかと心配する人もいますが、現実は、少なくともに日銀が保有している国債の金利については、全額国庫納入が義務付けられているのです。
つまり、日銀保有国債については、償還のための費用も、利払いのための費用も、国家の財政には全く負担をかけないということなのです。これは理論ではなくて事実なのです。そのことを財務省も国会での私の質問で全て認めているのです。(この国会の質疑の様子は西田昌司チャンネルYouTubeで公開しています。ぜひご覧ください)この事実をまず皆様方に知っていただきたいのです。
税金は、国家が供給した通貨を流通させる装置
ここまでの事実が分かれば、予算の財源は国債発行による通貨供給であることが理解できるでしょう。しかし、税金が財源でないのなら、税金は必要ないのでは思う人もおられるでしょう。税金が財源でない事は事実ですが、通貨の流通のために税金は絶対に必要なのです。
かつては、政府の通貨発行は、その価値を保障するため金が必要でした。いつでも額面と同じ金と交換することを保証することにより紙切れである紙幣が流通できると考えられていたからです。そのため金の保有量を超える通貨発行はできなかったのです。これが金本位制です。しかし、現在は、金本位制を採用している国は有りません。金の保有量に関係なく、政府の必要に応じて通貨が発行される仕組みになっているのです。
一方で、政府は国民に納税の義務を課しています。その支払いは政府の発行している通貨(つまり円)でせねばなりません。金で支払うことも、ドルで支払うことできないのです。国債を大量に発行して通貨供給をすれば通貨の信任が崩れる(誰も円を使わなくなる)と批判する人がいますが、最終的に納税の義務を果たすためには、否が応でも政府の発行する通貨(円)を使用する以外ないのです。つまり、日本国で経済活動をする限り、政府の発行する通貨を使う以外ないのです。また、日本は世界一の経常収支黒字国です。即ち、日本は海外にお金を払うのではなく、海外が日本にお金を払う義務があるのです。その支払いも必ず円で決済せねばなりません。要するに、外国も円(日本の国債)を外貨準備として保有しなければならないのです。国債残高が膨れ上がれば円の信任がなくなり、誰も受け取らなくなると言うのもまったくのデタラメなのです。
通貨発行には限界はないが資源には限界がある
 P3参議院役員での記念撮影(大臣ではありません委員長です)
P3参議院役員での記念撮影(大臣ではありません委員長です)
以上の事実を1つずつへ確認すれば、通貨発行には量的な限界がない事はお分かりいただけると思います。しかし、通貨を支払って、モノを買ったり投資をしたりすることはできますが、そのモノの供給力には限界があります。通貨は、政府がいくらでも作り出すことができても、肝心のモノには供給力の限界があるということです。
先の大戦の最中、日本は国債を大量に発行して戦費を調達しました。国家総動員法により、あらゆる資源を戦争のために動員しました。つまり、通貨を大量に発行し戦費を調達したのです。一方で、当時の政府は「欲しがりません、勝つまでは」の標語を掲げ、消費を抑制しました。あらゆる資源を戦争に費やしている中で、通貨の大量発行により個人の消費が増えれば、大変なインフレになることが分かっていたからです。事実、戦時中は大きなインフレはありませんでした。
戦時中、大量に国債を発行したことにより、戦後は凄まじいインフレになったということがよく言われます。しかし、国債を発行していた戦時中には、インフレにならず、戦争に負け、「欲しがりません、勝つまでは」が無効化した時、大変なインフレになったのです。戦後は外地からも一切モノが入ってこず、さらに、大都市の工場の多くが焼き払われ、生産力が極端に低下していました。つまり、国債発行ではなく、物不足、資源不足、供給力不足が大変なインフレをもたらしたのです。
コストカット(身を切る改革)が日本の供給能力を極端に低下させた
まさに、極端に供給力が低下したのが敗戦直後の日本なのです。戦時中よりも貧しくなったのはそのためです。ものを作り出す力、供給力こそ国力であり、経済を発展させる源泉なのです。貧困のどん底にあった日本ですが、昭和25年の朝鮮戦争以後は、アメリカの占領政策の変更もあり、一挙に経済発展をして行きました。その原動力になったのが、銀行による融資の拡大です。それまではドッジラインという占領政策の下、銀行はお金を貸すことを制限されていましたが、朝鮮戦争以後は、それが撤廃され、銀行が積極的に融資をすることができるようになりました。銀行が融資をすればするほど、民間部門にお金が供給されます。銀行がお金を貸し出すことを信用創造と言いますが、英語ではマネークリエーションといいます。まさに銀行が融資によりお金を作り出していたのです。さらに、原材料の輸入や生産物の輸出も解禁となり、日本は製造業を中心に大いに発展したのです。銀行が融資をして資金を供給し、日本は世界一の供給力を持つ国になったのです。
ところが、バブル崩壊後、このシステムは完全に破壊しました。バブル後、銀行は貸し出しより回収に励み、民間部門の通貨量は極端に低下しました。一方で、プラザ合意後は円高が進み、製造業は中国を始め海外に移転し、日本国内の供給力は極端に低下しました。国内に残った製造業は、コストカットで海外に対抗する以外、道がなくなりました。これが30年にわたるデフレの原因です。
供給力を強化するという岸田総理の所信表明は、まさにこうしたデフレ路線からの脱却宣言です。官民あげて、コストカットばかりやってきたデフレ路線に終止符を打ち、積極財政で成長路線を目指すことを宣言したのが、今回の所信表明なのです。
樋のひと雫
-アンデス残照-
羅生門の樋
8月ラパスで全ボ研究大会がありましたがチッケトの手配が上手く行かず、今年も2日間ともネットでの参加となりました。先日改めて会議を開いたのですが、昨今の中南米の経済的疲弊がよもやま話の中心でした。特に、過っては南米の経済的中心だったアルゼンチンのデフレ問題では、ボリビアの「ペソ時代」を思い出すとのことです。貧困層の支持を得るためとは言え、何故あれほど金をばら撒くのでしょうね。中央銀行で増刷すれば、社会福祉を解決するのに役立つとでも思っているのでしょうか。「票を金で買う」、分かり易い話ではありますが…。
こんな話をしたあくる日、モロッコのマラケシュで大地震が起こったという一報で目を覚ましました。ネットで確認してもさほどの被害が報じられておらず、ひとまず安心しましたが、その後の報道では被害が拡大しています。数年前の4年間はモロッコのラバトに居りました。教育省のプロジェクトに数県が参加しており、マラケシュにも2ヶ月に1度ほど通っておりました。基礎教育の改善向上を図るためのモデル校を作る為にマラケシュの農村部の学校が参加してくれました。放課後、子ども達とサッカーをするなど楽しい時間を過ごしたことを思い出します。マラケシュ郊外の農村が壊滅的な被害を受けたとか、あの子たちが無事で居てくれることを願っています。テレビではレストランから逃げ出す人々やホテルの倒壊などが報じられていましたが、あのレストランよく行った店です。恐らく、旧市街の定宿にしていたホテルもダメでしょうね。街全体が赤色に染まるマラケシュの復興には時間がかかることでしょう。日本も資金を出すだけではなく、何か人々の目に見える支援が出来れば良いのですが…。
かつての湾岸戦争では、戦後にクウェートが世界の人々に支援を感謝する新聞広告を世界で一斉に出しました。その感謝広告の中に、「Japan」の文字は有りませんでした。最大の資金拠出国だったにもかかわらずです。金を出しても人を出さない日本は、クウェート国民の眼にどう映ったのでしょうか。ウクライナ支援ではG7の議長国として音頭を取るだけでなく、もう少し日本らしい支援は出来ないのでしょうか。例えば、自衛隊には医官がいます。彼らをそのままの形では派遣できないとしても、日本赤十字社に出向させ後方地域の病院で、傷ついた市民や子どもの治療に当たれないものでしょうか。“資金提供国”からの脱却を考える良い時期かも知れません。
あれから一年
本年7月8日、安倍晋三元総理が暗殺されてもう一年になります。あの日は参議院選挙の真っ只中で、京都に吉井 章候補の応援に来る直前の出来事でした。私は、総理が撃たれたと連絡を受けた時、冗談を言っているのかと、全く信じることができませんでした。残念ながら、これが現実だったのです。安倍晋三亡き世界が、もう一年も経過しているのです。
この日に合わせて、東京の芝の増上寺で一周忌法要が執り行われ、午後からは明治神宮記念館で安倍晋三元総理の志を継承する会が開催されました。岸田総理始め、歴代総理が追悼の演説をされました。その話を聞きながら涙ぐんでおられる昭恵夫人の姿を見るに付け、改めて安倍晋三亡き世界が現実であることを痛感致しました。
安倍総理の遺志とは何か

安倍総理(今後もこう呼びます)は、平成5年に国会議員になられます。私は、平成2年の補欠選挙で府議会議員になりましたが、参議院議員だった父の吉宏は、「安倍さんの息子さんはおまえと同じような話をしている。きっとお前と気が合うわ」と言っていたことを思い出します。
その後、私は自民党全国青年議員連盟の会長になり、党本部の青年局長に議連の要望を届けることになりますが、時の青年局長こそ、若き日の安倍総理だったのです。因みに次の青年局長にも要望書を届けますが、その人の名は岸田文雄であり、歴代総理とはかなり若い時代からご縁をいただくこととなりました。
その当時の安倍総理は、如何にも育ちの良いおぼっちゃまという印象でした。しかし、思想的には確固たるものをお持ちで、「自分は安倍晋太郎の息子では無く、岸信介の孫だ」とお話しされていたことを今は亡き、西部邁先生からよく伺いました。
西部先生は、昭和35年の日米安保条約改正の時、東大の全学連で安保闘争の中心メンバーでした。ところが、その後私と一緒に安倍総理と会食した時、「自分たちは間違っていた。安保改正をした岸総理は正しかった」とお話しされていました。その岸総理の志を継ごうとされる安倍総理の遺志とは『日本の自立』であったと言えるでしょう。
勿論、安保体制堅持ばかりでは真の独立はありません。しかし、「そのために現状から一歩でも前に出る」それが安倍総理の信念だったのでしょう。憲法改正のための国民投票法や特定秘密保護法や平和安全法制の制定など、国論を二分する議論がありました。「祖父である岸総理の60年安保改正に比べれば何でもない」安倍総理にはその信念があったと思います。
ロシアとウクライナの戦争
安倍総理のキャッチフレーズはご存知の様に「日本を取り戻す」でした。この言葉の裏には、日本は大事な何かを失っているという前提があります。その失ったものは、日本人の精神であり、価値観であり、家族や故郷だったのではないでしょうか。そして何よりもその自覚でしょう。正に歴史を失ってしまったことが日本人にとって致命傷であったのです。
ロシアがいきなりウクライナに武力侵攻しました。このことからロシアが加害者であり、ウクライナは被害者である、という前提で毎日同じ様な報道が繰り返されています。しかし、私は当初からこうした報道姿勢に違和感を感じていました。
喧嘩両成敗という言葉がありますが、戦争も同じで、どちらかが一方的に善でどちらかが一方的に悪というのは、現実の世界ではあり得ないことです。また、日本とロシアは国境を接していますが、未だ平和条約が締結されないまま北方領土が占領され続けていますが、安全保障のみならずエネルギーや海洋資源の供給源としても非常に重要な国です。
一方、ウクライナは歴史的にも地理的にもロシアに比べて遥かに遠い国です。そもそも、今回の武力侵攻に至る経緯そのものをほとんどの日本人は知りません。ただロシアが先制攻撃をしたこと、それがロシア非難の決定的原因になっているのです。
私は、かつての日本が大東亜戦争で真珠湾に先制攻撃したことを知っています。しかし、そこに至るまでにはABCD包囲網による石油禁輸措置が有り、日本が絶対に飲めないハルノートという事実上の最後通告をアメリカが突きつけていたことも知っています。そして、広島と長崎に原爆を落とし何十万の一般市民を殺戮したことも知っています。
先制攻撃だけでロシアを非難をすることは、自らの歴史に唾することになりませんか。また、真珠湾攻撃に先立ち、支那事変が勃発しました。現在では、蒋介石軍に参加していた共産党軍からの発砲が原因との説が有力です。本来、日支間では圧倒的軍事力に差があったにも関わらず、紛争が長期に及んだのは、米英によるいわゆる援蒋ルートの存在です。こうした事実を知っていれば、ウクライナに軍事支援する欧米政府のやり方には疑問を感じざるを得ません。先ずは、武器を援助するのでは無く、停戦に向けた交渉を行うべきなのです。
安倍総理のリアリズム

以上の様なことを自民党の部会で、また派閥の総会でも私は訴えてきました。ウクライナを善で被害者、ロシアを悪で加害者という一方的な決めつけをすることは、決して日本の国益にならないし、ウクライナやロシアの国益にもならないのです。
しかし、残念ながら誰一人その場で私の意見に賛同する人はいませんでした。しかし、安倍総理だけは、会合の後、私の側に寄り添いながら、「西田さんの言うことは分かるけれど、これが現実なんだよ」と、誰も自国の歴史と鏡合わせにしようとしない現実を悲しみながら、「いずれ分かる時が来るはずだ」と慰めてくれました。
ウクライナ紛争の原因は、2014年に勃発したマイダン革命という名の反ロシア勢力によるクーデターにあります。これにアメリカのオバマ政権が関わっていたことは今や公然の秘密になっています。その後ロシアとの紛争解決のためミンスク合意がフランスとドイツの仲介の下になされますが、この合意を実行してこなかったのがウクライナなのです。つまり、ウクライナ自身がロシア側を挑発してきたとも言えるのです。このことは、安倍総理自身も言及してこられました。
安倍総理は日米同盟という安全保障の基軸を守りながら、一方でロシア始め日本の安全保障上大切な国とは、しっかりと話をできる関係を築いてこられました。安倍総理亡き後の外交でもこうした発想で岸田総理にも臨んで欲しいものです。
コロナ禍で史上最高の税収増
先日、財務省から2022年度の税収が71兆円を超え、史上最高額を3年連続更新したとの発表がありました。コロナ禍で経済は低迷していた筈なのに何故税収が増えたのでしょう。その答えは、3年で100兆円を超える国債を発行して経済を下支えしたからに尽きます。
既に何度もShowyouにおいても説明していますが、国債発行による財政出動は国民に通貨を供給することです。国民側に何らかの形でお金が供給される訳ですから、当然国民の所得が増えることになります。その結果、税収が増えるのは当然のことなのです。一方で、財政出動をするのに増税して税金を取って行うと、税金の分だけ国民側の通貨、即ち預貯金が減ることになります。財政出動した分の所得が国民側で増えても増税分だけ国民の預貯金は減り、景気拡大の効果は相殺されます。
但し、大企業の内部留保など、過剰に貯まった金融資産に課税して、それを子育て支援の様に国民に分配すれば、間違いなく消費が拡大して景気は良くなるでしょう。これまで、1000兆円を超える国債発行によって民間側に大量の通貨が供給されてきました。そして、法人税率を度重ねて引き下げをしてきました。その結果、多くが大企業の内部留保として滞留してしまったのです。これこそ、日本の問題なのです。
国債発行は通貨供給であり、税金は通貨回収という事実を先ず理解しなければなりません。また、国債の償還は税金で行うのでなく新たに借換債を発行して行っており、孫子の代の負担になどなっていないことも事実です。3年に亘るコロナ禍はこうした事実を私たちに教えてくれました。コロナ禍での税収の増額はそのことを証明しているのです。
死せる安倍、生ける岸田を走らす

2年前、安倍総理を最高顧問に、私が本部長に就く財政政策検討本部が党内に設置されました。安倍総理はアベノミクスでデフレ脱却を目指していました。もはやデフレではない状況を作ることはできましたが、必ずしも経済成長路線へはまだまだ十分に転換できませんでした。その原因の一つが二度に亘る消費増税であったことは否定できません。また、法人税の減税が内部留保を増やすだけで投資に繋がらなかったことも誤算でしょう。アベノミクスの光と影を総点検し、それを糧にすることが重要なのです。
正に岸田総理は、こうしたことを糧に防衛力増強や子育て支援、財政より経済を優先させるという安倍総理の思いを着実に実行しておられます。マスコミなどでは相変わらず岸田バッシングが続き支持率は低迷しておりますが、正に、『死せる安倍、生ける岸田を走らす』なのです。皆さまの引き続きのご理解とご支援をお願いいたします。
瓦の独り言
「六地蔵巡りで思うこと」
羅城門の瓦
8月22日から23日にかけては、800年つづく京都の伝統行事である「京の六地蔵めぐり」です。
瓦は1981(昭和56)年から、欠かさずお参りをしています。というのは、長男が8月23日の朝、お参りから帰ったら直ぐに生まれたからで、「これはお地蔵さんの利益の賜物」と家族中が、信仰心を深めた次第です。伏見の六地蔵を出発して、鳥羽地蔵、桂地蔵、常盤地蔵、鞍馬口地蔵、とめぐり、上がりが山科廻地蔵です。コロナ禍の4年間は夜間のお参りが中止されていましたが、22日の深夜にかけて車で回れば3時間もあれば十分なお参りができます。あがりの「お斎(おとき)」は山科のラーメン屋でしめていました。
何気なく、毎年お参りをしていましたが、2020年度の京都・観光文化検定試験(通称:京都検定)に六地蔵巡りの鳥羽地蔵に関する問題が出てきました。「西国街道に面している鳥羽地蔵の寺院名は・・・」浄禅寺が正解なのですが、瓦はちょっとひかかっていました。六地蔵巡りのシーズンになると、言い出したくなり、言わせてください。
西国街道は東寺口から羅城門を通って西方向へいく街道で、そこには浄禅寺(鳥羽地蔵)は面していないはず。鳥羽地蔵の前の道は「鳥羽街道(鳥羽の作道)」で羅城門を起点に、南下して淀方面に至る通商交通の重要な街道である、と教えられていました。そこで京都検定の事務局(京都商工会議所)に問い合わせたところ、「公式テキストブック」に西国街道と記載されている。「間違いない」との返答でした。さらに調べると、編集者は「京の六地蔵めぐり」の公式パンフレットに記載の通りの設問をしているとのこと。「それではパンフレットの訂正が必要ですね。」と食い下がりましたが、そうは簡単にいかないらしいです。歴史・文化の問題は諸説色々ありますが、訂正が簡単な時と、そうでない時があるようです。
「それ、ちがうのんと、ちゃいますやろか?」と、京都人的に質問するときは「実は、こうなんでっせ。」と腹のうちには答えがわかっているような・・・。
でも、政治の世界で我が国の舵取りを任せている「自由民主党」にあって、我らが京都から国会へお送りしている西田昌司参議院議員におかれましては、「是は是。非は非。」と十分な論理をもって対処していただいていると、大船に乗った気持ちでいるのは瓦一人だけではないはずです。
(暑さが厳しい折、瓦の表面は灼熱地獄ですが、裏面は平温です。どうぞ、お体をご自愛ください。)
統一地方選挙のご支援に感謝
4月9日に統一地方選挙の前半戦が実施されました。皆様方のご支援に心から感謝を申し上げます。しかし、自民党の公認候補は府会が30名の公認に対して28名、京都市会は24名の公認に対して19名の当選に留まり、自民党にとっては厳しい結果でありました。また、京都で大きな勢力を保っていた共産党は、府会・市会とも議席を減らしましたが、維新の会が大きく議席を伸ばしました。京都は、自共の対立が大きな枠組みでしたが、今後はそれが自民対維新に変わることになります。特に、来年の正月明けに行われる京都市長選挙では、維新は必ず候補者を立てると明言しています。これに、京都党や共産党などがどう関わるかが注目されます。
我が党としては、国と京都府と連携できる候補者を選定して、必勝態勢で取り組んで参りますので、引き続きのご支援をよろしくお願い申し上げます。
維新の天下で大阪は貧困化
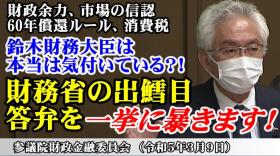 参議院財政金融委員会での鈴木大臣への質問はYouTube西田昌司チャンネルでご覧いただけます
参議院財政金融委員会での鈴木大臣への質問はYouTube西田昌司チャンネルでご覧いただけます
隣の大阪では、知事と市長の選挙が行われましたが、どちらも維新が圧勝しました。更に議会の選挙でも維新が圧勝し、引き続き大阪は維新の天下となりました。大阪では、維新が天下をとって10年以上になります。身を切る改革や大阪都構想が彼らの看板政策でしたが、その結果、大阪はどうなったのでしょうか。
そもそも、大阪都構想は2度にわたり住民投票をしましたが、いずれも否決されましたから実現していません。いずれにせよ、都構想は、大阪府と大阪市の二重行政を排除するということですから、要は身を切る改革同様で、大阪で使われている予算を削減するということです。大阪で使われる予算を増やせば、大阪の経済が活性化するというのなら理解できますが、それを減らせば経済は地盤沈下するはずです。事実、維新が大阪の天下を取った10年の間に大阪が貧困化していることは統計調査でも明らかになっています。
例えば、都道府県別世帯(2人以上勤労者世帯)月収では全国平均60万9千円のところ、大阪では54万8千円で全国40位です。また、一人当たり県民雇用者報酬の増加額(2011年-2019年)では、全国平均は+ 28万5千円ですが、大阪は+ 1万7千円しか伸びておらず全国46位です。また新型コロナによる重症者数死亡者数も人口あたり全国最多で、文字通り医療崩壊しています。このように、身を切る改革は、大阪府民市民の富を奪い、命を奪う結果となっているのです。
これだけ無惨な結果しか残していないにもかかわらず、なぜ大阪で維新が躍進することができたのか、私は不思議でなりません。
身を切る改革というパフォーマンス
身を切る改革は実際には全く意味のないものであったにも関わらず、大阪で支持されたのは、以前の大阪が市民の目からは、よっぽど豊満財政をしていたと見えていたからでしょう。事実、大阪市は京都市の左京区より小さな面積に280万人が暮らしていますから、財政は非常に潤沢で職員の給料も高く、いわゆる公務員天国の様なところもあったのでしょう。それに対する市民の不満があったことは事実でしょう。しかし、財政を切り詰めていくだけでは将来の発展はありません。それは前述の数字が示しています。
結局、大阪で維新が支持されたのは、デフレが続く中で、民間の景気がおもわしくない中、自らの報酬を引き下げるというパフォーマンスを見せることにより、公務員天国に対する市民の根深い批判を利用して市民の溜飲を下げたからでしょう。選挙のたびに身を切る改革と称して、自らの首を絞めることを平気で続けているのを支持する背景には、今は苦しいが、これを乗り越えれば楽になるはずだ、と言う期待と思い込みが大阪の市民にはある様です。まさに劇場型の政治に酔いしれている感があります。しかしながら、大阪では現実の経済が落ち込んでいるのですから、この事実が市民に伝われば早晩必ず支持は失われるでしょう。
近畿地方では生駒山からテレビの電波が流れるため、こうした維新の劇場型のパフォーマンスが関西一円に流されます。この結果、元々公務員の給与も高くなく公務員天国ではない他の地域でも、大阪で身を切る改革をするなら自分たちの街でもしようと、まるで流行に取り残されたという感覚を持つ人が出始めています。今回、京都などの大阪周辺地域で維新が勢力を伸ばしたのはそれが原因でしょう。
財政危機は存在しない!危機なのは経済だ!
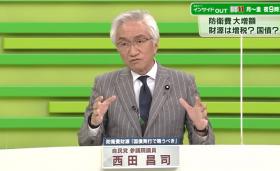 BS11「報道ライブ インサイドOUT」に出演いたしました
BS11「報道ライブ インサイドOUT」に出演いたしました
維新の会が身を切る改革を叫ぶのは、国債残高が増えればそれを返済する孫子の世代の負担が増えると考えているからです。しかし、これは全くの事実誤認です。既に私の国会での質問に財務大臣が答えていますが、国債の償還は借換債の発行で行なっていますから、孫子の世代の負担が増えることはないのです。さらに、国債を発行して予算を執行すればその分民間の預貯金が増えることも財務大臣は認めています。国債発行は孫子の代に借金を残すのではなく、逆に財産を残すことになるのです。
また、国債の利息もその半分以上を日銀が保有していますから、利息の大半は日銀に支払われることになります。日銀に支払われた利息は日銀の経費を除き全て政府に納付されることに法律で定められています。従って、日銀の保有してる国債については、基本的に財政に何ら負担を与えていないのです。このことも財務大臣は認めているのです。つまり、財政の危機など全く存在しないのです。
問題はこの20年に渡り、日本だけが経済成長して来なかったことです。その原因は、バブル崩壊後、いわゆる貸し剥がしが行われたことです。平成9年ごろから1年間で150兆円に上る金額が銀行に回収されました。銀行からお金を借りることにより企業は資金を調達して投資をします。その額が年々増加することが経済を成長させるエンジンになるのです。その額が一挙に3分の1も無くなってしまったのですから、経済はとんでもない不況になりました。民間借入金は、その後20年以上に渡って増加していないのです。これが日本の失われた20年の原因なのです。
新しい資本主義が経済を救う
民間がお金を借りて投資をしないのは、貸し剥がしのトラウマが原因の一つですが、長引くデフレの影響も大きいです。民間が投資をしない結果不況が長引き、物価が持続的に低下するデフレに陥っていました。物価が持続的に上昇するインフレ時には、商品の単価が上昇し売り上げが増える事が期待できますから、企業は積極的に借金をして投資をします。しかし、物価が持続的に低下するデフレ局面では売り上げの減少を恐れて、借金をして投資をすることを控えます。これが失われた20年を作り出したのです。
民間が投資をしないなら、代わりに政府が国債発行をして積極的に投資をすべきなのです。しかし、現実は逆のことをしました。民間が身の丈に応じた経営をしようとしているのに政府が借金を増やしてどうするのかという暴論が罷り通ったのです。正に身を切る改革を自民党も民主党も率先して行なって来たのです。
しかし、コロナ禍に陥ったことで緊縮財政は変更を余儀なくされます。先ずは、人の命を守ることや経済を破綻から救うことが優先されました。その結果、この3年間で100兆円にのぼる補正予算を執行することになりました。お陰でコロナも終息に向かい、コロナ融資で倒産も抑えられ、逆に税収は増えました。これは政府の財政出動が民間の預貯金を増やしたからです。
今までの、規制緩和をして民間の経済を成長させるといういわゆる新自由主義の経済政策から、政府が積極的に財政出動をすることにより民間経済に資金を投入して需要を拡大する脱新自由主義に方向転換をしているのです。岸田内閣の新しい資本主義とは正に脱新自由主義のことで、緊縮財政から積極財政への転換を意味しているのです。
維新の会は財務真理教か
にも関わらず、身を切る改革を維新の会は主張しています。確かに、地方自治体の公債は国債と違い、日銀の引き受けの対象にはなってません。しかし、この問題は、政府が国債発行を増やして地方交付税を増大すれば、地方は公債を発行する必要がなくなりますから、財政の破綻もおこらないのです。従って、積極財政を行う岸田内閣では地方の財政破綻などあり得ないのです。京都市なども一時財政の危機が心配されましたが、岸田内閣の積極財政のお陰でその危機は既に乗り越えています。
ところが、今回の統一地方選挙では、財政の危機を煽り身を切る改革を主張する維新の会や京都党が勢力を伸長しました。彼らの政策が根本的に間違っているということは、もうお分かりでしょう。岸田内閣の下では積極財政でコロナ禍を乗り越え、これから経済成長を目指そうとしているのに、身を切る改革という路線を京都が選択してしまえば、京都も大阪と同様にデフレに真っ逆さまです。
先日、月刊文藝春秋に、伝説の大物元大蔵事務次官の齋藤次郎氏が、安倍元総理の回顧録に対する反論を寄稿していました。内容は例の矢野元次官と同じくばら撒き財政の批判です。
この人は先輩から絶対に赤字国債を出すな、財政法を守れ、さもないと戦後のインフレのような事態になると厳しく指導されてきたということを力説していました。しかし、戦後のインフレの原因は空襲により工場が破壊された上、600万人以上の外地からの復員に代表される様に、需要の急激な拡大と供給力の低下によるものです。ましてや財政法を守れとは、GHQが日本の財政の自由度を縛るための典型的な占領政策だという事実も理解されていません。そもそも齋藤氏の意見が正しければ日本はとっくにハイパーインフレになっていなければなりません。正に、上司の意見だけに忠実に従ってきただけで現実を全く見ていないのです。そして、こうした財務真理教と言うべき論法に悪ノリしているのが維新の会の政策です。
来年の京都市長選挙が天王山
 統一地方選挙の必勝にむけて自民党京都府連総決起大会を開催いたしました
統一地方選挙の必勝にむけて自民党京都府連総決起大会を開催いたしました
来年の正月明けには、京都市長選挙が予定されています。積極財政で経済の回復を目指す岸田政権と西脇京都府知事としっかり連携出来る候補者選定を致します。断じて大阪の二の舞いを踏む事などあってはなりません。皆様に賢明なご判断をお願い致します。
樋のひと雫
-アンデス残照-
羅生門の樋
家の前を候補者の名前を連呼しながら、街宣車が走っています。日本のいつもながらの地方選挙です。地方選になれば思い出すことがあります。ボリビアにも地方選挙はありますが、大統領選とは異なり、もう少し静かです。「誰が立候補しその主張は?」等は、よそ者には余り聞こえません。
20数年前に教育基本調査でボリビアに行った際に、コチャバンバで一人の女性官僚に出会いました。訳せば「県教育事務所長」という肩書ですが、権限では日本の府県教育長より上です。人事、行政権、学習内容等全ての権限を握ります。表敬を兼ね調査地域や内容の説明と調査の便宜を要請するために、昼に所長室を訪れました。多くの事務所長は部下に詳細を検討させ、表敬だけを受けるのが常です。しかし、彼女は自国の発展や当時進行していた教育制度や教育内容の改革に、調査がどのように資するかを聞いてきました。15分で終わる「表敬」が、「ボ国社会の成長と教育改革の進展」についての話に及び、秘書に午後の予定を全てキャンセルさせ、私達は熱心に討議を続けました。ボリビア官僚の中にも「侍が居る」と思わせた出会いであり、私を永くボリビアにのめり込ませた契機ともなりました。
その後、途中退学を防ぐための義務教育の統合、学習内容の改定と新教科書の全国配布、先住民言語との二言語教育、大衆参加法による学校の門戸開放などが暫時進んで行きましたが、国内に政治的内紛が起こりました。大統領官邸前の広場で軍と警察の銃撃戦が起こり、それが契機となり大統領は亡命、暫定大統領が立ちますが、政治は一挙に混乱の季節を迎えました。この中で、彼女はその職を去っていきました。時の流れにifは有りませんが、当時の政権がもう少し安定していたら、次期の教育大臣や副大統領の芽もあったと思います。彼女が職を辞してから1年後に、コチャを訪れた際に電話があり、久しぶりに会いました。その時、彼女はコチャバンバ第二の都市、サカバ市議会副議長をしていました。元気溌剌な姿に勇気づけられましたが、「ああ、ボリビアは惜しい人物を失くした」という思いは消えませんでした。別れた後に、寂寥感だけが残ったのを今でも思い出します。
政府の赤字は民間の貯蓄の増加
 参議院本会議での岸田総理への代表質問はYouTube西田昌司チャンネルでご覧いただけます。
参議院本会議での岸田総理への代表質問はYouTube西田昌司チャンネルでご覧いただけます。
この3年間、コロナの感染対策と経済の下支えのために、莫大な予算が組まれてきました。通常の1年間の予算の倍額が使われたと言っていいでしょう。そして、その財源は国債の発行に依存しています。さらに、ロシアによるウクライナ侵攻や北朝鮮の度重なるミサイル発射や中国の海洋進出など、わが国は戦後最大の安全保障上の危機を迎えています。今まで防衛費はGDPの1%以内が基準となっていましたが、来年度以降はこれをNATO諸国並みの2%に倍増すべきだという議論が進んでいます。
こうした事態を受け前財務事務次官などは、「このままでは財政破綻する」と喧伝していましたが、ハイパーインフレの発生も、金利の暴騰も、その兆候すらありません。日米金利差の拡大により一時は円安に大きく振れましたが、今は比較的落ち着いています。これは如何ともし難い事実です。
そもそも国債発行は、予算執行を通じて、民間側の預金残高を増やします。これは理屈ではなく、事実としてそうなっています。このことを岸田総理も私の代表質問で認められています。
国債発行は事実上政府による通貨発行ですから、予算を執行すればそれが民間側に供給されるのは当然の理屈なのです。通貨発行権は、中央銀行である日銀が持っていると教わっています。確かに、日銀は民間銀行から国債を買い取ることにより、民間銀行に通貨を供給していますが、銀行にいくら通貨を供給しても、民間企業が借り入れを増やさなければ民間企業にはお金は供給されないのです。
この10年、日銀は国債を買い取ることにより銀行に通貨を供給してきましたが、民間の借入金残高が増えなかったため、民間企業への通貨供給は増えなかったのです。これはアベノミクスの誤算です。しかし、コロナ禍による財政出動の大幅な増加により民間部門にお金が供給されました。特にこの3年間、コロナ禍にもかかわらず毎年税収が増加したのは、国債発行による財政出動の大幅な増加が通貨発行の増加となり、民間企業の利益を増加させたためです。
国債の償還資金は税ではない
これは財務大臣も認めたことですが、そもそも国債の償還は税金ではなく、新たな国債を発行して得たお金で借り換えています。このことも如何ともし難い事実です。国債発行による財政出動が民間への通貨供給なのですから、税金の徴収は発行した通貨の回収です。この回収した通貨を再び財政出動すれば、民間にまた通貨が供給されますから、徴税による通貨回収をしても民間の通貨量は変わりません。しかし、徴税により回収した通貨を財政出動せず国債の償還に充てて国債残高を減らせば、その分民間に供給された通貨量は減ることになります。
つまり、国債発行による財政出動は通貨供給であり、税金の徴収は通貨回収なのですから、その回収した税金を財政出動すれば、回収した通貨が再び民間に戻り、民間の通貨量は変わりません。しかし、その回収した税金で国債残高を減らせば、民間の通貨量はその分減ると言うことです。
税金は財源ではなく通貨の供給量を調節する道具
つまり、税金は予算の財源というよりも民間の通貨量を調整する道具なのです。予算の財源は国債発行をすればいくらでも出来るのです。しかし、税金がなければ、通貨供給量が増えるばかりで回収ができませんから、経済は一方的にインフレになります。また、税金がなければ、供給した通貨が一箇所に集中し格差や社会の分断が生じます。したがって、財源は国債発行でできるから税金をなくせという事は有り得ないのです。大事な事は、税金と国債発行のバランスです。実体経済の状況を踏まえ、そのバランスを図ることが大切なのです。
税金は財源では無いから、国債発行でいくら財政出動しても良いというのも間違いですが、税収の範囲内でしか予算を執行をしてはならないというプライマリーバランス黒字化論もまた大間違いなのです。大切なことは、その国の経済の状況がどうなっているかなのです。
日銀保有国債の償還や利払いの国庫への影響
 門川京都市長から「令和5年度の国の施策・予算に対する緊急要望」をうけました
門川京都市長から「令和5年度の国の施策・予算に対する緊急要望」をうけました
また、国債の利払い費は政府の負担ですが、現在、国債残高の半分近くは日本銀行が保有していますから、利払い費の半分は日銀に支払われることになります。日銀法により、経費を差し引いた残りは国庫に納入することになっています。このことから、少なくとも日銀が保有する国債については、国債の償還も利払いも事実上、国庫に影響を与えていないということになります。
黒田総裁は、物価上昇が継続的に2%になるまで国債を買い続けることを政府と政策協定しています。この方針が継続される限り、日銀の保有国債は増え続けることになりますが、国債の償還や利払いが財政に影響を与えることはありません。
プライマリーバランス黒字化目標がデフレの根本原因
以上のことを踏まえると、国債の残高が増えてもその償還や利払いで国家が破綻するということは到底考えられないということになります。それよりも、問題であるのは、国債の増加によって政府の負債は増え、片や民間の貯蓄が増えても、この民間側に回ったお金が使われていないことです。経済を活性化させるには、国が財政出動をして予算を膨らませることで、民間にお金を回すことも必要ですが、民間にはそのお金を使ってもらわなければなりません。そのためにはデフレ状況、先行き不安状況を払拭して、お金を投資できる環境をつくることが大切です。
そのために重要なことの一つは、日本の長期の投資計画を国が示すことです。残念ながら、この国の長期計画はバブル崩壊後、財政再建を理由に廃止されました。新幹線や高速道路などのインフラ整備の長期計画が示されて、これを10年で完成させるという事業が実行されるとなると、間違いなく民間投資は政府の計画に沿って拡大されることとなります。政府が予算措置した以上に、民間がお金を使い、経済の好循環、そして経済成長へと向かい出します。
問題は、国が長期の投資計画を示せなくなったのは何故かということです。本来、インフラ整備は財政法で認められている建設国債の発行で出来るはずです。しかし、プライマリーバランスの黒字化が閣議決定されて以降、赤字国債だけではなく、建設国債も抑制されてしまい、結果的に長期の投資計画が示されなくなり、デフレから脱却できない状況に陥りました。
私は亡くなった安倍元総理と一緒に、自民党に財政政策検討本部を作って様々な議論をしてきました。その結論は、プライマリーバランス(PB)の黒字化目標が日本の経済を縛っていった根本的な問題であったということです。安倍元総理がご存命ならば、必ず、PB黒字化目標の撤廃を岸田総理に要求していたはずです。安倍元総理の意志を継ぐためにもPB黒字化目標は撤廃させねばなりません。
民間企業の負債が20年以上増加していないのは日本だけ
 山陰近畿自動車道早期実現促進大会にて「早期全線開通」に向けた要望をうけました
山陰近畿自動車道早期実現促進大会にて「早期全線開通」に向けた要望をうけました
財務省は国債残高がGDPの2倍もあるのは日本だけであり、財政再建の必要性を訴えています。しかし、国債発行は民間部門への通貨供給であり、国債の償還や利払で財政が破綻することが無いということも事実です。問題は国債残高が他の国より多いということではなく、民間企業の負債がこの20数年全く増えていないことです。
本来、民間企業は投資をして事業を拡大するものです。ところが日本では、バブル崩壊後の不良債権処理を強行して以来、もう二度と銀行からお金を借りて投資するのは懲り懲りだというのが民間企業の本音です。さらに、この間、国際的な法人税の引き下げ合戦が繰り広げられました。その結果、住民税も合わせた法人の実効税率は、かつては5割を超えていたものが3割を切っています。
実効税率が5割を超えていた頃は、利益の半分も税金を払うぐらいなら、投資を前倒しして特別償却を増やすとか、決算ボーナスを従業員に支払うとか、そうした節税が結果的に消費や投資を増やすことになりました。しかし、実効税率が3割以下になるとそういう動機が経営者にはなくなっているのが現実です。こうしたことにより、日本の企業は内部留保が増え続き、負債より貯蓄が多い状態が続いています。本来、経済を牽引するはずの民間企業が投資をせずに、利益を溜め込み続けていることが異常なのです。
消費税をEUの付加価値税の様に第二法人税にすべし
実は、EUの付加価値税(VAT)は第二法人税になっています。企業の売上から仕入れを引いた粗利に税率を掛けた額を税として納めるという点では、日本の消費税と基本的には同じ仕組みです。違うのは、その額を消費者に転嫁することを義務付けていないことです。その結果、VATは日本の消費税と違い、企業の利益から納める第二法人税になっているのです。
日本では法人の7割が赤字法人で法人税を納めていません。しかし、法律によって法人格を認められ経済活動を認められている以上、VATをモデルにして赤字法人でも一定の負担をしてもらうべきというのが、元々消費税の立法目的であったのです。ところが、成立の過程での様々な議論の結果、レジでの外税方式が主流になり、また転嫁が義務付けられたためVATとは似て非なるものになっているのです。
一方で、EU のVATは第二法人税になり、法人税の引き下げをしても事実上の実効税率は5割を超える水準を維持しているのです。このため、日本の様に企業の内部利益が異常に増加することも有りませんし、民間企業の負債も増え投資も進んでいます。また、VATの税率を上げても、直ちに物価が上がり経済の足を引っ張るということも有りません。消費税もVATの様に第二法人税にすべきなのです。
瓦の独り言
「おせち料理」
羅城門の瓦
「コロナ禍で中くらいなりおらが春」
みなさん。新春あけましておめでとうございます。おせち料理を前に、一献傾けられる幸せを皆様方と共有したいと思っている瓦です。さて、おせち料理といえばデパートの見栄えのよい重箱入りがもてはやされており、各市町村のふるさと納税の返礼品にも「おせちのお重」が入っているとか。
おせち料理は歳神様をお祝するもので、かつて(?)は各家庭で年末に作られていたものです。中でも「祝い肴三種」はかかせないものですが、関東と関西、さらには京都では肴三種が少し異なっているようです。(諸説いろいろありますが)
関東:黒豆、数の子、ごまめ(田作り)
関西:黒豆、数の子、たたきごぼう
京都: 数の子、たたきごぼう、ごまめ
どれが正しいといった論議は抜きにして、それぞれに由諸があります。
【数の子】:卵の数が多く、ニシンは「二 親」に通じ、五穀豊穣と子孫繁栄を願ったもの。
【たたきごぼう】:豊作と息災を願い、ごぼうは地中に深く根を張ること運が向いてくる。
【ごまめ】:カタクチイワシを田の肥料としていため「田作り」ともいわれ、五穀豊穣を願った。
などがあり、元旦の朝には瓦の自宅ではこれら肴の由来を家族でわいわい言いながら確認して食べています。一つ一つの料理は火を通したり、燻製にしたり、あるいは酢漬にしたり、味を濃くして日持ちする料理が多いのです。これは歳神様を迎えてともに食事を行う正月の火を極力捉えて、また、家事から女性を三が日は解放するためといった目的もあったとか。
おせち料理の味付けは各家庭で微妙に異なっていますが、祖母から娘へ、そして孫へと繋いでいくもので、そこにはデパートの見栄えする「お重」が入ってくる余地はなかったはずです。核家族になっても年末には親元のおせちをお重に詰めてもらい元旦を迎えたものです。
古臭いと言われようが正月三が日は歳神様と食事をしている意識をもって、日本の、いや京都の正しいお正月のおせちの伝統を引き継いでいきたいと瓦は思っております。
この伝統を引き継ぐことは、「伝えよう。美しい精神と自然」をキャッチフレーズにしておられる西田昌司参議院議員も同じ思いではないか、と思っているのは瓦一人だけではないと思っています。
どうか2023年・卯年も瓦の独り言をよろしくお願いいたします。
国葬をめぐる国民の分断
9月27日、安倍元総理の国葬が日本武道館で行われました。野党や一部のマスコミは、国民の半数以上が反対していると騒ぎたてましたが、現実はその逆です。安倍元総理に献花をしたいという二万人を超える一般の方々が炎天下の中、5時間以上も並んでおられる姿を見て、これが多くの国民の素直な気持ちなんだと私は確信致しました。
反対を叫ぶデモも一部にあったそうです。かつて、平和安全法制を巡って国会周辺でデモが有りました。マスコミは一般の市民が反対していると報じましたが、その実は、左翼活動家が中心となったものでした。今回の国葬反対騒動もこの時と同じ構造です。国民が国葬によって分断されたと報じていますが、事実はその逆で、マスコミが国民が分断された様に報じているに過ぎないのです。
テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」での玉川氏の発言
 YouTube西田昌司チャンネルで約40万回再生されています
YouTube西田昌司チャンネルで約40万回再生されています
その典型的な例が、テレビ朝日の玉川氏の発言でしょう。報道によると、この番組のコメンテーターを務める玉川徹氏が9月28日の番組で、菅義偉前総理が安倍晋三元総理の国葬で読んだ弔辞について「これこそが国葬の政治的意図」と発言をした上に「当然これ、電通が入ってますからね」と、大手広告代理店の名前を出し批判したそうです。
私も国葬に参列していましたが、菅前総理の弔辞は、実に心の籠ったもので、私も胸が熱くなりました。昭恵夫人も思わずハンカチで目頭を何度も押さえられていました。葬儀の場で拍手はご法度ですが、菅前総理の弔辞が終わった後、一斉に万雷の拍手が鳴り響いたのです。それほど感動的な弔辞だったのです。
玉川氏はそれを“電通の演出”と全く事実確認もしないままコメントした上で、「僕は演出側の人間でディレクターをやってきた。そういうふうに作りますよ」とも発言したそうです。翌日の番組で玉川氏は「事実ではありませんでした」と謝罪したそうですが、謝罪で済む話ではありません。
私はこうした経緯を知り、直ちに私のYouTube西田昌司チャンネルで、この問題の本質を掘り下げて説明しています。詳しくはぜひこちらをご覧ください。
放送法違反の疑い
電波は放送法によって放送局に割り当てられていますが、その理由は公共財である電波を公益のために使用させるのが目的です。そのため放送局が電波を使って放映する番組には真実は勿論の事、公正公平が求められるのです。
ところが、全く事実に反する事を平気で発言した上に、制作者が恣意的に番組作りをしているということを半ば公然と認めるような発言をしているのです。玉川氏は元々ディレクターで番組作りの専門家を自認しています。そもそも、報道の記者の経験も無い者に、コメンテーターをさせていること自体、テレビ局として大問題です。公の電波を扱う放送局としての見識が問われます。
ところが、玉川氏どころかテレ朝の社長ですら事の本質が分かっていません。テレ朝の篠原社長は、定例会見で玉川氏のフェイク発言を謝罪し「玉川氏を謹慎10日に、またその上司をけん責処分にした」と発言しました。事実で無い事を報道したことに対する処分は当然ですが、問題はそもそもテレ朝の番組作りの姿勢にあったのです。
テレビ局が、視聴者の歓心を得るために様々な演出を凝らしていることはよく知られた事実です。確かに、娯楽番組ならそういうこともある程度許されるでしょう。しかし、報道番組では過剰な演出は、偏向報道に繋がるためご法度のはずです。ところが、テレ朝にはその認識が完全に欠如しているのです。そして、このモーニングショーは報道番組ではなく情報番組という触れ込みをすることにより、過剰な演出も許されるという姿勢で番組作りをしてきたのです。しかし、これが詭弁でしかないことは言うまでもありません。
玉川氏は、かつて、キャスターの羽鳥氏を善玉に自分を悪玉にする事で番組にメリハリをつけてきたという趣旨の発言をしていました。報道記者の経験もない者をコメンテーターにさせるのは正にこうしたテレ朝の姿勢の表れです。真実や公平公正より視聴率を重視するテレ朝の姿勢がフェイクニュースを生み出したのです。こうした姿勢は放送法に抵触する可能性がある事をテレ朝は自戒しなければなりません。
国民を分断させるマスコミの過剰な批判主義
 安倍晋三 元総理の国葬儀が9月27日に執り行われました
安倍晋三 元総理の国葬儀が9月27日に執り行われました
こうした姿勢は、視聴率や販売部数によって会社の業績が左右する商業マスコミには常に付き纏う問題です。しかし、それ以上にマスコミの世の中に対する過剰な批判主義にこそ問題の本質があるのです。日本人は、長い年月にわたり島国の中で米作りをしながら生活してきました。また、大陸の様に異民族の侵略を受けて国が滅ぼされたこともありません。これは世界的にも非常に珍しいことです。そのお陰で民族間の対立がなく、お互いが協力し合うことを伝統としてきました。皇室を頂点に日本全体がまるで一つの家族の様に助け合うことを大切にしてきたのです。これが本来の日本の伝統精神でしょう。
ところが、こうした日本人の伝統精神が伝承し難い環境が戦後は作られたのです。一つは核家族化により伝統的な家族主義が崩壊した事です。もう一つは、批判主義こそ民主主義の原点とするフランクフルト学派の影響を受けた学者やマスコミの台頭です。家族主義という日本人の本来の感性では、対立ではなく、「お互い様」が共通の価値観であり、国民が分断されることはありませんでした。しかし、過剰な批判主義が幅を利かすと、「お互い様」より不平不満を追求する事が正義になってしまいます。批判主義は一見正しそうに思えますが、現実は世の中に要らぬ分断をもたらすだけなのです。何故なら、この考え方は世の中を分断し、不安定化させ、最後は革命に導くための思想と表裏一体の関係にあるからなのです。
フランクフルト学派とは
私は、西部邁先生のお陰で憲法や東京裁判史観を始めとする戦後レジームの間違いに気付かされました。先生と出逢い、全身が雷に撃たれた様な衝撃を受けました。それと同じことが、美術史の権威で東北大学名誉教授の田中英道先生の著書と出逢って起きたのです。先生はその著書の中で、西洋の近代主義の源流にあるフランクフルト学派の問題点を鋭く批判されています。私はフランクフルト学派という言葉を初めて知りましたが、これを理解することにより、目から鱗が落ちる様に、戦後の日本の問題の本質を改めて知る事ができました。
フランクフルト学派は、共産主義思想の源流とも言えるもので、人間は個人として独立した存在であるべきという思想を説くものです。しかし、現実は人間は個としては存在していません。誰にも必ず両親がおり、またその両親がいます。生まれ落ちてもひとりでは存在できず、両親を始めとする家族や家庭があって人間として生きる事ができるのです。そうした家庭や社会との延長線上に国家があります。そしてこのお陰で他民族から侵略されることなく生活を営むことができるのです。
ところが、国家を失ったユダヤ人にとってはこの喩えが当てはまらないのです。ローマに祖国イスラエルを滅ぼされたユダヤ人は、以来2500年以上にわたり流浪の民になり世界中に離散しました。ヨーロッパ各地にも多くのユダヤ人がいます。彼らは、各地の同胞のネットワークを通じて金融業や商業において成功していきます。ところが、異教徒である彼らには自由に住む土地が与えられず、ゲットーという限られた地域に封じ込まれていました。
そうした彼らの置かれた環境の中で、ドイツのフランクフルト大学のユダヤ人学者を中心として生まれたのがフランクフルト学派と言う思想です。社会や権威を否定する批判主義がその特徴です。自分たちを縛る国家や民族意識を否定し、むしろ人間をこうした集団から解放すべきだと考えるのです。国家からの解放、これは今日のグローバリズムに通じます。そして家庭からの解放、これは個人主義を生み出します。性別からの解放、これはLGBT思想につながります。そしてこの延長線上に社会主義や共産主義が生み出されるのです。家庭や地域社会など人間の精神的なつながりを否定して、単に物だけに注目しその所有から解放するのが唯物論で共産主義の本質です。
リベラル思想は共産主義と同根
 京都舞鶴港国際物流ターミナル整備事業竣工式典に出席いたしました
京都舞鶴港国際物流ターミナル整備事業竣工式典に出席いたしました
しかし、ソビエトの崩壊以来、共産主義を正しいと思う人は世界中に殆どいないでしょう。しかし、その同じ思想の延長線上にあるグローバリズムや個人主義やLGBT思想等は今日でも衰退することなく、むしろ勢いを増しています。これらの思想を叫ぶ人たちは、共産主義者ではなくリベラルと呼ばれます。リベラルとは本来、自由主義者のことです。共産主義とは全く相反する思想のように思われますが、実は表裏一体なのです。それは自由と言う言葉が何かから解放すると言う意味で使われているという事を知れば分かります。つまり、人間を何者にも縛られないものに解放すると言うのがリベラルの正体なのです。これは完全な伝統破壊の発想です。そもそも国家にも家族にも性別にも束縛されない人間などどこにも存在しないし、存在できないのです。この有りもしない、出来もしないことを求めて行動すると、その後に辿り着くのは社会からの疎外感だけです。自分たちは正しいことを追求し要求しているのに、それが受け入れられないのは社会が悪い、だから、この社会を壊すという革命思想に辿り着くのです。
しかし、それが人類に戦争や貧困、対立と憎悪だけをもたらしたというのが20世紀の結論であったはずです。多くの人は共産主義とリベラルとが実は表裏一体である事に全く気付いていません。私も田中英道先生のお陰で始めて気付きました。テレ朝などのマスコミも間違いなくリベラル思想に影響を受けています。しかし、この思想は社会の対立を煽るだけのものなのです。この事実を国民に知らしめるのが、これからの私の使命です。
樋のひと雫
-アンデス残照-
羅生門の樋
山の木々が晩秋の装いを見せる頃、ボリビアのコチャバンバでは街路樹のハカランダが紫色の花を咲かせます。コロン公園の近くのカフェのテラスから道行く人とこの花を見るのが慰めでした。コチャの友人に「日本は肌寒くなってきた。コチャの気候は凌ぎ易くなるな。」とSKYPEしたら、「ハカランダの落ち葉と塵が風に舞い、最悪だ」と返って来ました。想い出と現実、人の感じ方は様々だと思いました。
日本では安倍元首相の国葬が、賛成と反対の議論の中で執り行われました。もう少し論議を尽くせば‥という気持ちと、いくら論議をしても平行線だろうな‥という気持ちが相まって、TVの中継を見ていても何か落ち着かない感じがしたものでした。「招待状が来たが、私は行きません!」とネットで騒いでいた議員が居ましたが、人の死を葬くるのに、そこまではしゃぐかという気もします。生前にはいくら意見や政治信条の違いがあったにせよ、「人の葬送に対しては、心静かに敬意を表すぐらいの度量を持てよ。」と思います。
10月末にスクレで行う研究会の準備で、数人のコチャの友人と話し合う機会がありました。その際に、日本の首相が銃撃されたという話題が出たので、「ボリビアでも国葬(funeral del estado)は以前に在ったけ。」と聞きました。返事は一応に「Qué?(何それ)」でした。聞き方が辞書的だったと思い、「いや、国の功労者が死んだ際に云々」という説明をしていても、「No、 hay.No se!(無い。知らない)」でした。そう云えば、ここ暫らく大統領で任期満了した人が居たっけ。絶大な人気を誇った先住民出身の大統領もメキシコに亡命したし、その前の前は米国に亡命したし。辛うじて選挙内閣の暫定大統領だけが国に留まってる状況です。かっては、怒った民衆の手によって、現職大統領が官邸の前の公園の街灯に吊るされた歴史もあります。初めてボリビアを訪れた時に、ムリーリョ公園のベンチで「ああ、まさに、この場所で」と見上げていました。
政治姿勢や方法論、その成果に様々な異論があることは分かります。しかし、世界から見れば国葬が行われる国は、人々が安寧に暮らしている証左でもあると思うのです。
安倍元総理への応援要請
 自民党京都府連政経懇話会にお越しいただいた際の安倍晋三元総理(令和4年6月4日)
自民党京都府連政経懇話会にお越しいただいた際の安倍晋三元総理(令和4年6月4日)
7月8日は、午後12時半、四条河原町に、吉井あきら候補の応援に安倍元総理が駆けつけて頂くことになっていました。その週の月曜に出た各紙の世論調査では、吉井候補始め有力三者の支持率がほぼ拮抗しており、中には吉井候補が三番手になっている地域もあると報じられました。このままでは議席を失う可能性もあり、私は強い危機感を感じました。しかし、多くの人にその認識が有りません。私は携帯電話の電話帳に記載されている多勢の人に電話を架け実情を話し支援拡大の要請をしましたが、最初は誰もが吉井候補は大丈夫でしょうと言われます。事実を説明して漸く支援拡大に応じて頂きましたが、私は今回の選挙の厳しさを痛感していました。
すぐさま緊急選対会議を招集して、私と同じ様に携帯電話で知り合いに支援要請をすることを徹底することを伝えると同時に、安倍元総理へ電話をし、京都への来援をお願いしたのです。安倍元総理には既に他の候補の応援日程が入っていましたが、変更して来て頂くことになったのです。ところが、京都に応援に来る途中の奈良であの惨事が発生したのです。四条河原町で来援の準備中に「安倍さんが撃たれた」との一報が入りましたが、とても信じられず、「何故、安倍晋三が撃たれなければならないのか!」と私は叫びました。
その時はまだ詳細は分かりませんでしたが、京都に来られないことは確実です。そのため、街頭遊説を中止すべきではないかという意見も出ましたが、私は予定通り行うと決断しました。それは、新聞で大々的に安倍元総理の来援を広告しており、この事態を先ず市民に報告することが必要だと思ったからです。また、その後の選挙活動も自粛すべきとの意見もありましたが、それも退けました。
もし、安倍元総理と相談すれば「私のことで選挙活動止めてどうするのか。ウクライナ問題やコロナ対策など、現下の国難を乗り越えるには、選挙で勝利し政権基盤を安定させるしかない。選挙活動を止めるな!」と必ず言われると私は確信していたからです。
その後、安倍元総理の死亡が報じられました。私は「これは弔い合戦だ。勝利の報告を安倍先生の御霊に報告させて頂きたい!」このことを演説会で一心に訴えてきました。お陰様で、無事に二之湯先生の議席を吉井さんに引き継ぐことができました。皆様のご支援に心より感謝致します。しかし、一方で安倍晋三という政治家を失ったことは誠に残念であり無念です。悔しさと憤り、そして喪失感で一杯です。
京都で維新の進出を止めた意義
今回の参院選挙がいつにない激戦になった背景には、維新の会が候補者を立てたことにあります。維新は京都を最最最重要区として、連日大阪から知事や市長が公務そっちのけで来援し、「大阪の改革を京都でも」と訴えていました。大阪の改革とは身を切る改革のことです。しかしその結果、大阪では保健所や医療機関の職員が大幅に削減され、コロナ禍による死亡者数が人口当たりで日本最悪の結果になっているのです。
この事実をマスコミはまともに報道していません。それどころか、連日、吉村知事や松井市長のパフォーマンスばかりを報じて来ました。それが近畿地方全体に放送されるのです。関西系のテレビ局のワイドショーなどは完全に維新に電波ジャックされた様なものです。
更に、今回は国民民主の京都の衆院議員が維新の候補を全面的に応援しました。大阪の改革がコロナ対策で大失敗していることを、この方はなんと考えているのでしょう。こういう勢力が京都で増えれば、京都でも大阪の改革が押し付けられるでしょう。その結果、コロナのような感染症が出る度に、大阪の様に命を落とす人が増えることが危惧されます。
今回は、何とか維新の進出を押さえ込むことができましたが、来年の統一地方選挙や再来年の市長選挙でも、必ず彼らは候補者を立てるでしょう。京都を守るために、彼らの進出を絶対に抑えなければなりません。
安倍元総理の遺志
 岸田総理に財政政策検討本部からの「提言」を直接お渡しする
岸田総理に財政政策検討本部からの「提言」を直接お渡しする
安倍元総理は、平成18年の第一次安倍内閣誕生以来、「戦後レジームからの脱却」をスローガンに掲げておられました。実際、憲法や東京裁判史観のように占領中GHQによって作られた法律や制度、歴史観が未だに日本を縛り続けています。その結果、本来の日本人としての価値観や伝統や文化が損なわれています。日本が真の独立国になるためにはこうした占領政策の縛りを取り払わねばならないと考えておられたのです。
占領中に日本国憲法が作られましたが、その前文では「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」と誓い、9条では「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」と書かれています。今や憲法はGHQが作成したという事実は国民に知られる様になりましたが、占領初期においては自分で自分の国を守ることすらGHQは否定していたのです。このため、自分で自分の国を守るという独立国として当たり前のことが戦後の日本ではタブーになっています。
また、先の大戦についても、大東亜戦争という当時の政府の正式な呼称が占領中にGHQに否定され、太平洋戦争と呼ぶことになりました。さらに、東京裁判により日本が一方的にアジア太平洋に侵略したと一方的に非難され、それに関わった人間は戦争犯罪人として処罰されました。この東京裁判の処分を受け入れることにより、日本の占領が解かれたのですが、その後様々な公文書がアメリカから発表され、東京裁判史観は事実ではないことが判明しています。それにもかかわらず、日本では未だに東京裁判史観が正式な歴史として扱われているのです。逆に事実に基づく歴史を語れば、それは歴史修正主義者として非難される始末です。
安倍元総理はこうした事態を深刻に受け止め、戦後の日本を縛り付ける占領政策を一掃することを目指して「戦後レジームからの脱却」と訴えておられたのでした。私も府議会議員の時代から同じ問題意識を持って訴えてきましたが、国会議員でこれほど明確に訴えられた方は安倍元総理が最初だったと思います。
財政法も戦後レジームそのもの
 財政政策検討本部で最高顧問を務めていただいた安倍元総理
財政政策検討本部で最高顧問を務めていただいた安倍元総理
昨年、岸田内閣が誕生し、私は引き続き政調会長代理を拝命しました。自民党総裁選の決戦投票に残った岸田総裁と高市政調会長は、共に財政出動の必要性を訴えておられました。そこで私は、従来の財政再建推進本部を財政政策検討本部に衣替えすることを高市政調会長に進言したのです。その進言が認められた結果、私が本部長に任命されたのです。そこで私はかねてから積極財政を唱えられていた安倍元総理に最高顧問の就任をお願いしたのです。
この検討本部では、財政健全派の意見と積極派の意見の両論を対比させ、その根拠となる事実について検討してきました。これにより明らかになったのが、そもそも財政健全化を主張する方々の論拠が財政法の「歳出は税収の範囲内ですべき」という趣旨の規定にあるということです。財政法にこう書いてある以上、国債発行は慎まなければならないというわけです。
しかし、これは昭和22年という占領初期に作られたもので、その目的は防衛費などに国の予算を自由に使わせないための規定です。憲法9条を財政面で担保するためだったことが今や明らかになっています。つまり、財政法も憲法と同じく、日本の自立を阻むための占領政策の一環として作られたということなのです。安倍元総理や私たちは、財政政策検討本部での様々な議論の中で、財政法も戦後レジームであったことに気づいたのです。
「自分で自分の国を守る」「コロナ禍ようなパンデミックは全力で抑える」「経済的に危機になれば、その人を救う」など、国民生活と社会の秩序を守るためには、ありとあらゆる政策を駆使しなければなりません。それは言い換えれば経世済民であり、国家の使命です。経世済民のための予算を税収の範囲内で抑えなければならないというのでは、まさに国家としての使命を放棄していることになります。財政法に従うべきだということに拘っていれば、国家の使命を果たせないのです。このことに、安倍元総理始め財政政策検討本部の多くの議員は気が付いたのです。そこで、参議院選挙後、自民党が勝利して政権を安定させることができれば、この事実を党内で徹底的に議論して、財政健全化が全く意味のないものであることを国民に知らしめるために安倍元総理と相談していたのです。
その矢先に安倍元総理が凶弾に斃れました。この損失は計り知れませんが、残された我々が安倍元総理の遺志を継いでいかなければなりません。
身を切る改革は戦後レジームに縛られている
維新の会は、憲法改正に積極的な発言を繰り返していますから、自民党よりも保守的な政党だと思っておられる方が多い様です。しかし、彼らが看板政策としている身を切る改革は、経世済民という国家の使命より財政健全化を優先させることに外なりません。正に戦後レジームに縛られた論理なのです。
京都では幸い、選挙区で議席を与えることが阻止できましたが、比例票では3年前より倍増しています。このことに私は危機感を抱いています。経世済民とは世をおさめ民を救うという意味で、それを略して経済という言葉が生まれたのはご承知の通りです。そして、経世済民を行うことが世の中の持続的発展をもたらすのです。ところが、維新の会の言う身を切る改革は、これとは逆に経世済民を否定しているのです。
身を切る改革と同じことを、かつて自民党は構造改革と言い、民主党は事業仕分けという言葉で主張していました。いずれも、それは失敗に終わりました。それは、財政法という日本の財政の自由を奪い日本を貧しくすることを目的とした戦後レジームに従うことだったのですから、当然の帰結です。従って、維新の会の身を切る改革も同じ運命を辿っていくでしょう。
安倍元総理の遺志を伝えるとは、正にこうした歴史の事実を国民に知らせることに外有りません。安倍元総理の死により失ったものはあまりにも大きいですが、改めて、日本の真の独立のため全力で取り組むことを安倍元総理の御霊に誓います。
樋のひと雫
-ボリビア残照-
羅生門の樋
今、中米に過去にない実証実験(?)をやろうとしている国があります。エル・サルバドルです。人口650万人、コーヒ-生産以外では加工産業が発達し、中米では工業化に成功していると言われています。30年程前に10年余り続いた内戦に漸く終止符を打ちました。しかし、以降も経済的な苦境は続き最大の産業は「出稼ぎ」とさえ言われています。また中米の多くがそうであるように、マフィアの跳梁が激しく、つい4ヶ月ほど前には治安維持の為に非常事態を宣言し、夜間の活動が制限されています。その国で、自国通貨が仮想通貨に変更されました。この話を耳にして、エルサルにいる友人と話をしました。
「本当に通貨がなくなったの?」まず聞いたのがこれです。国家は中央銀行を通して通貨の総量を規制し、財政の規律を維持します。自国経済の発展や国民生活の発展に役立つように抑制します。この手段が無くなります。「ネットを持ってない人間はどうするの?」最近は日本でも仮想通貨は良く聞きますが、余り現実味がある話ではありません。時間によって大きく変動する価値では、安定した生活が送れるのかとつい心配になります。我々の様なガラケー人間はどうするの(まあこれは日本だけの話ですが…)。「農村部のネット環境って、そんなに進んでいたっけ?」ニカラグアに2年程いたのは数年前、エル・サルを訪問してからずいぶん経ちます。つい心配になります。仮想通貨使用にはChivo Walletというアプリが必要なこと、政府発表で500万人がインストール済ですが使用可能なスマホが限られ、当初は反対が随分あったこと。「国民の半数以上が銀行口座を持っておらず、海外(の出稼者)からの送金を受けることができない。口座があっても送金にはコストがかかる。」といのが政府が導入した説明だそうです。
つい最近もメールが来ました。実際に大手スーパ-やマクドナルド、スターバックスでは仮想通貨専用レジがあり、列を作っている。しかし、事務机を買おうとしたら仮想通貨での支払いを断られ、米ドルで支払ったとのことです。まだまだ現金が強いと云うことでしょうか。国民は30米ドルのボーナスが貰えるのでインストールしたのですが、日常は米ドル、クレジットカードだそうです。普段の生活は変わらないという内容でした。ラティーノは強かと思いながら、かの国の財政報告や予算書はどうして作るのだろう? また、疑問が湧いてきました。
ロシアが悪でウクライナが善?
 岸田文雄 総理大臣に今後の諸課題について直接提言いたしました
岸田文雄 総理大臣に今後の諸課題について直接提言いたしました
2月、突然ロシアがウクライナに侵略しました。武力による現状変更は許されないとして、すぐさま日本では反ロシアの非難決議が衆参両院で採択されました。更に、ウクライナのゼレンスキー大統領をリモートではありますが、国会で演説させるという前代未聞の措置がなされました。勿論、マスコミも反ロシア・反プーチンの大合唱ですから、国民の多くもロシアを非難し、ウクライナを支援しようという空気に包まれています。
しかし、こうした報道は本当に正しいのか、私は当初から疑問を感じていました。ロシアがウクライナに先制攻撃したことは事実であり、それ自体は非難されるべきでしょう。しかし、問題は何故ロシアがそうした行為をしたのか、そのことに対するロシア側の言い分が全く考慮されず一方的に報道されていることです。先に武力攻撃をしたロシアが一方的に悪で、攻撃を受けたウクライナが被害者であり、それを支援することが善という善悪二元論に基づいていますが、私はこうした報道に強い違和感を感じています。国と国との間に限らず、人間社会においては、どちらかが一方的に善でどちらかが一方的に悪ということは有り得ないと考えるのが、大人の常識ではないでしょうか。
東京裁判史観に洗脳されている
私はこうした報道を見ていて、直感的に真珠湾攻撃から始まる日米開戦のことを思い出しました。このことは、戦後は概ね以下の様に教えられてきたでしょう。日本がハワイの真珠湾に先制攻撃をして大東亜戦争が勃発した。それ以前にも日本は満洲国を建国するなど、中国大陸でも領土を拡大し、侵略を繰り返していた。更に、日独伊三国同盟を締結して全体主義の道を歩み出すことになる。日米開戦によりアメリカを始めとする連合国との間で第二次世界大戦に発展し、最終的に全体主義国家は連合国に敗れ平和が訪れた。日本は、アメリカに原爆を落とされるなど都市の多くは破壊され、多くの国民の命が奪われた。遂に、ポツダム宣言を受け入れ無条件降伏し、アメリカに占領されることになった。占領中、日本は民主化のために憲法を改正し、民主主義国家として再スタートした。
そして、こうしたシナリオの下に行われたのが東京裁判です。日本は東京裁判を受け入れ、戦犯として認定された人物は処刑されました。その結果、サンフランシスコ講和条約を結ぶことができたのです。これにより、日本は占領を解かれ独立を回復することができたのです。
しかし、以上の記述は戦勝国である連合国の立場での歴史観であり、連合国を戦後は国連と訳しています。まともな日本人なら、こうした歴史観は到底受け入れられないはずです。確かに、日本が真珠湾に軍事的に先制攻撃をしたことは事実です。しかし、それ以前にアメリカが日本への石油の輸出を禁止し、更に日本が絶対に受け入れられない「ハルノート」を突きつけるなど、アメリカの方が先に事実上の宣戦布告をしていたことは当時から知られていた事実です。
また、国民党の蒋介石に対して共産党の毛沢東と協力して日本と戦う様に仕向けたのが、アメリカであったことが今や事実として知られています。その証拠に、日本を占領したGHQのマッカーサー元帥は朝鮮戦争の最中にその任を解かれますが、その直後の昭和26年、アメリカ上院での委員会で「あの戦争は日本にとってはおおむね自衛の戦争であった」という旨の証言しているのです。東京裁判を行った側の人間が、東京裁判史観を真っ向から否定しているという事実を私たちは知るべきです。
こうした事実を知れば、現在のウクライナ侵略に対するロシアへの一方的非難に違和感を感じるのは、歴史を知るものならば当然のことではないでしょうか。今日のロシアへの一方的非難は、未だに東京裁判史観から抜け出せない日本の姿を象徴するものなのです。
参議院決算委員会での議論
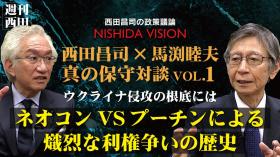 YouTube「週刊西田」の馬渕元ウクライナ大使との対談は、シリーズで15万回以上再生されています。是非ご覧ください。
YouTube「週刊西田」の馬渕元ウクライナ大使との対談は、シリーズで15万回以上再生されています。是非ご覧ください。
前回のShowyou109号で財務事務次官の財政破綻論が事実誤認であることと、それを糺すために財政政策検討本部を設置したことを述べました。世間では相変わらず、国債発行がこれ以上増えれば通貨の信認に影響するという報道ばかりが溢れています。
しかし、コロナ禍により疲弊した経済や社会を支えるためには財政出動する以外ありません。そのため補正予算が異次元の規模で編成され、令和2年度には三度に亘り補正予算が編成されその総額73兆円にもなりました。当初予算との合計は175兆円という予算規模になり、これは通常の予算の2年分に相当する額です。財務省のいうことが正しければ、これだけの規模の予算を執行すれば財政破綻の兆候が見られるはずです。しかし現実は、ウクライナ戦争による影響が多少はあるものの、物価も為替も金利も比較的に安定しています。事実は、財務省の説明とは違っているのです。
私は、4月11日の参議院決算委員会において次の様な質問をしました。
「国債の償還は現実には税金ではなくて、借換債で行われている。したがって次の世代の負担にはなっていない。さらに、日銀が保有している国債に対して支払われる利払費は、日銀の経費を除いて全額が国庫に納付されることを日銀が事実と認めた。このことは、現実には日銀保有の500兆円の国債については、利払いも償還も財政に影響与える事はなく、事実上借金ではないということと思うがどうか。」この質問に対して鈴木財務大臣は「一つ一つの事実を追いかけるとその通りだと思う」という趣旨の発言をされました。財務大臣が、日銀保有の国債は事実上借金でないということを認める画期的な答弁をされたのです。(この様子はYouTube西田昌司チャンネルでご覧いただけます)
この答弁は、国債残高が1000兆円と言われていますが、日銀保有債を除けば事実上500兆円しかなく、しかも国債の償還は借換債で行っているのですから、孫子の代へのツケにもならないと財務大臣が認めたことを意味します。つまり、日本は財政再建をしなければ破綻するという状態ではない。このことが事実と証明されたわけです。まさに、財務省やマスコミなどが報じてきたことが誤りであったのです。
何故、財務省は誤った判断をしたのか
昭和22年に施行された財政法の第4条には「国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる」と規定されています。これは、公共事業等以外は税金の範囲内でしか予算が組めないという規定です。
しかし、バブル崩壊後税収不足が続き、いわゆる「特例公債法」が作られました。これにより、毎年国会で法律を制定することにより、赤字国債が出せるようになりましたが、赤字国債が恒常化したため有効期間を複数年にする改正がなされ、現在の法律は令和7年度まで赤字国債が発行可能になっています。そして、この年度がPB黒字化の達成年限になっているのです。つまり、法律上は原則として赤字国債は出せないのです。財務省は、この法律に従って財政の健全化を主張してきたわけで、彼らの主張にも一理あるのです。
占領政策は、日本の貧困化と非武装が目的
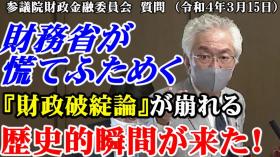 財政金融委員会での質問はYouTubeチャンネルで30万回以上再生されています
財政金融委員会での質問はYouTubeチャンネルで30万回以上再生されています
しかし、なぜ昭和22年に財政法が作られたのか、その淵源について考える必要があります。ご承知の通り、昭和27年4月28日まで、日本は敗戦によりGHQの占領下に置かれていました。昭和22年は物価が高騰し、大変なインフレの時代でした。その原因は、国債が戦費調達のために大量発行されたことによりインフレになったと言われていました。その対策として、その前年の昭和21年には財産税課税が実施され、国債は全額償還されたのです。同時に預金封鎖と新円切り替えが実施されました。しかし、インフレの原因は国債の発行ではありません。空襲による生産設備の破壊や敗戦による原材料の禁輸措置による供給力の極端な低下と、戦時中は統制経済により抑えられていた民間需要が急増したことによる、極端な需給ギャップが真の原因だったのです。
この法律の真の目的は別にあったのです。その一つが戦時利得者からの財産没収です。戦時中に政府は国家総動員法により物資を調達します。しかし、その対価の支払いを約束した補償等は当然支払われるべきものですが、GHQはそれを許しませんでした。それを戦時利得者として補償を払うどころか徹底的に財産没収をさせたのです。戦時利得者の利益没収を名目に最大90%の凄まじい税率の財産税が課されました。これにより日本人が貧困化し社会が混乱したことは想像に難くありません。
この法律の最大の被害者は、皇室です。これにより皇室財産のほとんどが召し上げられました。戦前は、皇室運営の財源は事実上国家の予算ではなく、御料林の経営による収益等、皇室財産の運用益によって賄われていたのです。その財源となる財産が殆ど全て取り上げられたのです。その結果、皇族としての生活が維持できなくなり、直宮以外の11の宮家が臣籍降下を余儀なくされたのです。
いずれにしても、終戦直後の占領時代においてはまともな議論をすることもできず、GHQの命ずるままに法律が作られたのです。そしてそれらは、皆、日本の民主化という美名の下で行われたのです。東京裁判もその一例であった事は言うまでもありません。
財政法は、当時の帝国議会では真の目的が何か殆ど議論がないまま制定されましたが、その後、昭和62年には、宮澤喜一大蔵大臣が財政法4条の制定目的について「戦争中に国債が自由に無制限に発行できることが、日本が戦争に入った大きな原因であると反省し、またGHQもそう考えたと思う」という趣旨の答弁しています。つまり、再武装させないために財政に縛りをつけたのが制定目的であったことを認めているのです。
東京裁判史観から脱却せよ
幸いなことに、戦後も昭和の時代までは、経済成長により毎年税収も増え赤字国債を発行する必要がありませんでした。また、東西冷戦が日本にとっては安定した平和をもたらしてくれましたから、防衛費も比較的少額で済みました。そもそも、自ら国を守ることを真剣に考える必要もなかったのです。東京裁判史観に基づくGHQの作った戦後の価値観を守っていけば、日本は平和で安全で豊かな社会を維持することができたのです。
しかし、平成元年(1989年)のベルリンの壁の崩壊により、事実上、東西冷戦は終り、世界の体制は大きく変化したのです。ウクライナ戦争は常任理事国が拒否権を行使すれば、何ら国連が全く機能しない事実を私たちに突きつけました。防衛力の増強は、喫緊の課題ですが、GDPの1%分以内に防衛費を抑制していては不可能です。また、コロナ禍により傷ついた国民経済を立て直すには、多額の財政出動が必要です。それを妨げるのが、財政法に支配されたPB黒字化論なのです。そろそろ、財政法が日本から財政の自由を奪い、弱体化させるために作られたことに気がつかなければなりません。ウクライナ戦争とコロナ禍はそのことを我々日本人に教えてくれているのです。
瓦の独り言
「遊郭の島原とウクライナ」
羅城門の瓦
今年もコロナ過に負けず都大路の桜は満開で、花街からは「みやこをどり」や「京おどり」の案内も目についていました。京都の花街といえば芸舞妓に出会える五花街が有名ですが、瓦としては花魁道中で有名な「島原」も忘れてはいけないと思います。ところがこの「島原」という名前は地図を探しても見当たりません。大門の在るあたりは「西新屋敷」という地名です。では、なぜ「島原」と呼ぶのか調べてみたら、なんと「島原の乱」に由来するそうです。
島原の乱は1637(寛永14)年、九州の島原、天草で発生した農民一揆とキリシタン弾圧に対するものでした。天草四郎率いる3万7千人の一揆軍は原城に立て籠り応戦したが、江戸幕府軍のまえにあえなく惨敗。全員が処刑されるといった悲惨な結果でした。
このニュースは京都にもいち早く伝わったそうです。この時、島原の遊郭は東本願寺北の六条坊門から朱雀野(今の場所)へ移転してきたところでした。その30年ほど前には二条城築城で立ち退き移転を強制されたとか。遊郭の移転となれば大騒動で短期間に何回も・・・。まるで戦乱を思わせる混乱ぶりは「島原の乱」の直後であったので、京都の人々は乱にたとえて「島原」と呼ぶようになったとか。
それほど島原の乱は、京都に住んでいる人たちに衝撃的な出来事として話題になり、遊郭の引越しには援助活動も行われたのではないかと思われます。このような経緯で遊郭の名前が「島原」になったとか。
さて、時は流れた今、「ウクライナ」の惨状がニュースに載らない日はありません。京都市はキーウ(キエフ)とは姉妹都市を結んでいます。ウクライナの惨状が伝えられた数日後にはコンビニのレジ横に「ウクライナ難民支援」の募金箱が置いてありました。ウクライナ産のチョコレートの定価に救援募金を乗せて販売したところ、すぐに売り切れたと聞いています。
江戸初期の京都人が「島原の乱」に思いをはせ、平和を願う気持ちは、400年たった今でも脈々とうけつがれていると思っています。
また、市民あげてのウクライナ支援は勿論のことですが、我々が国会にお送りしている西田昌司参議院議員のウクライナ問題に関する鋭い視点と、時間はかかると思われますが紛争終結に向けた活動を期待してるのは、瓦一人だけではないと思います。
財務省次官の間違った認識
 BSフジ『プライムニュース』~検証“バラマキ合戦” 財務省トップの警告は積極財政か緊縮財政か~に出演いたしました。
BSフジ『プライムニュース』~検証“バラマキ合戦” 財務省トップの警告は積極財政か緊縮財政か~に出演いたしました。
去年、衆院選が目前に迫る中、財務省の事務次官が月刊誌に、与野党の公約を「ばら撒き合戦」と断じた上で、このままではタイタニック号の様にいずれ氷山に衝突して沈没する、と財政破綻の危機を訴える原稿を寄稿しました。現職の事務次官が政治家を批判するというのは異例のことです。職を賭けて財政破綻の危機を諫言するという姿勢を評価する人もおられますが、これは全くの見当違いです。
彼は、カミソリ後藤田と呼ばれた名官房長官 後藤田正晴氏の「勇気を出して意見具申せよ」の訓示に習ったそうですが、大臣に直接物申す事は良しとしても、選挙を目前にした時期においての雑誌への寄稿は政治発言そのものであり、官僚の矩を超えている事は言うまでもありません。ましてや、その内容が財政についての事実誤認です。そもそも、国庫を預かる責任者が、実は日本は破綻寸前と公言することは国債の信任を否定することと同じ意味で、市場が混乱するリスクも有ったはずです。幸い市場は寄稿に全く反応しませんでした。市場の方がより現実を知っているのでしょう。
今回の衆院選挙では、自公で絶対安定多数を確保したものの、真の勝者は議席を4倍増にした日本維新の会です。その主張は身を切る改革であり、まさにこの寄稿と軌を一にするものです。しかし、身を切る改革の意味することは、結局、大衆受けを狙ったポピュリズムでしかありません。現職の財務事務次官の発言により、こうしたポピュリズム政党が躍進したとなれば大変な問題です。
財政破綻とは何を意味するのか全く説明していない
私は、最初にこの論文を読んだ時、このままでは国家財政が破綻すると言う表題について、自国通貨で発行した国債が返済不能になる事は無いと財務省も公式に認めているにもかかわらず、よくこんな出鱈目が言えるものだ、と強く憤っておりました。
更に、この原稿を書くに当たり、もう一度この論文を読んで驚いたことは、実は、国債の償還が出来なくなるとは一言も書いていないのです。そもそも、このままでは国家財政は破綻すると言いながら、この人が主張している事は「国債の残高がどんどん増加している」「世界のどの国よりも多い」「バラマキが続くからこの先も減る見込みがない」「国債の格付けに影響が生じれば日本経済全体に大きな影響が出る」など危機感を煽る言葉が並べられているだけで、国債残高が増えればなぜ財政が破綻するのかと言うことについては一切説明していないのです。これがこの論文の最大のウィークポイントなのです。
国民を不安に陥れる悪質な論文
 新設された財政政策検討本部において本部長に就任いたしました(左は安倍晋三 最高顧問、右は高市早苗 政調会長)
新設された財政政策検討本部において本部長に就任いたしました(左は安倍晋三 最高顧問、右は高市早苗 政調会長)
国債残高が増加すれば財政破綻すると言われれば、普通の人は国債が返済不能に陥ることだと思うでしょう。それは国家の破産であり、そうなれば経済が大混乱すると考えるでしょう。しかし、国債が償還できなくなるとは一言も書いていないのです。これがこの論文の狡いところです。
実は、国債の償還は税金で支払っているのではなく、新たな国債発行で得た資金で行っているのです。現実には古い国債を新しい国債に入れ替えしているに過ぎませんから、絶対に返済不能に陥るはずがないのです。自国通貨建てで発行した国債は返済不能になることがない。これは主権国家には通貨発行権が有るからです。これは、財務省のホームページにも記載されている事実です。
当然、この事実は財務省の人間なら誰でも知っています。だから、国債残高が増えれば大変だと騒いでも、返済不能になるとは一言も発していないのです。国債残高が増えると騒げば、返済不能になると大衆が思いこむことを承知でこのような発言をしているのです。
国家財政を家計に例える悪質な情報操作
この様な財務省の国民に不安に陥れる手法は、「国家財政を家計に喩えれば」として長年に亘り行われてきました。サラリーマンの家計では、働くことによってしか収入が得られません。借金をして収入以上の生活をしていれば、そのうち破産するのは自明の理です。しかし、政府は税収だけでなく通貨発行により歳入を得ることができますから、国家財政を家計に喩えるなど全くの間違いなのです。それを承知の上で、国家財政を家計に喩えて、税収以上の予算を執行していればいつか必ず破綻すると国民を誤解させ不安を煽ってきたのです。
私たちが国家財政を家計に喩えるのは間違っていると再三にわたり指摘した結果、財務省は今ではこうした表現はしないようにしていますが、いまだに家計と国家財政を混同して誤解している人が圧倒的に多いのが現実です。
国会議員や経済人の中にも誤解している人は大勢います。この論文が発表されて、財界人や経済学者の中からもこの次官のことを日本の財政危機を訴える気骨の役人と評価する人もいます。これは、彼の思惑通りの反応をしているにすぎないのです。
なぜ財務省は誤った情報を流すのか
 自民党本部で岸田総裁出席の緊急役員会の様子
自民党本部で岸田総裁出席の緊急役員会の様子
財務省の主要な権限は徴税権と予算査定権です。税金をかけたり予算を配分したりする権限を持っているからこそ、省庁の中の省庁と呼ばれる力を持っているのです。現実には、ナンバーワン省庁と言うだけではなく、国会議員よりも強い権限を持つに至っているのです。
彼は論文の中で「私たち国家公務員は、国民の税金から給料をいただいて仕事(公務)をしています。決定権は、国民から選ばれた国民の代表たる国会議員が持っています。決定権のない公務員は、何をすべきかと言えば、公平無私に客観的な事実関係を政治家に説明し、判断を仰ぎ、適正に執行すること。」と殊勝なことを述べています。
現実にはこの逆で、事実を述べず、もしくはねじ曲げて説明しているのです。こうした手段により、国民や政治家をコントロールすることにより、ナンバーワン省庁どころか、国権の最高機関である国会をもコントロールする力を持つに至っているのです。
国民の不安を煽り支配力を強める財務省
そしてこの力を維持するためには、常に国民や国会議員を財政の危機にあるという不安感で縛っておく必要があるのです。私も今までは、財務省のことをここまでひどく批判してきた事はありませんでした。彼らの発言は事実を誤認してはいるが、それも国家財政を預かる者の使命感がなせるものと思っていました。
しかし、今回の論文はそうした私の甘い考えを完全に否定しました。日本の状況を、タイタニック号が氷山に向かって突進しているようなもの、と喩え危機を煽る一方で、国債が償還不能になるという事には一言も触れない。その理由は、日本の国債が償還不能になるはずがないことを知っているからとしか思えません。
財政破綻が来るという恐怖心で国民を縛り、結果的に自らの支配力を強める手法は国家の財政を預かる役人の使命を完全に逸脱しています。こうしたことを繰り返しているうちに、国民だけでなく財務省は自らも洗脳してしまっているのです。
通貨発行とは国債発行のこと
ここで通貨発行について考えてみます。一万円札などの現金(通貨)はどういうルートで私たちの手許に来たのでしょう。銀行のATMで下ろせば現金が手に入ります。銀行預金を引き出せば現金となり、現金を預ければ預金になる訳で現金と預金は表裏一体の関係にあります。
では、預金残高はどうすれば増えるでしょうか。現金と預金は表裏一体ですから、現金を預けたら預金は増えても手許現金は減りますからその総額は変わりません。預金残高が増えるのは銀行から借金した場合しか有りません。逆に減るのは借金を返済した時です。この事をよく覚えておいて下さい。
同じことが国債発行でも起きています。給付金で考えてみましょう。政府が国債発行をして、国民一人当たり10万円の給付金を一億人に配ったとすると政府の借金が10兆円増えますが、同時に国民全体で預金や現金が10兆円増える事になります。政府の借金が国民の預金や現金を増やしたのです。これが通貨発行なのです。政府は、国債発行して予算執行することにより、国民に通貨を供給することができるのです。
では、国債の償還はどうするのか考えてみましょう。期限が来た国債は新たに国債を発行して得た資金で償還されます。事実上の借り換えで、税金で返済しているのではありません。税金で返済していれば国債残高は増えません。国債残高は国民に通貨供給した金額の合計が幾らかということです。これを減らすということは、国民から通貨を奪う事になります。財政出動は国民に通貨を供給することです。税金は供給した通貨の回収装置なのです。この二つの機能を組み合わせて国民生活を守ることが財務省の本来の使命なのです。
財政政策検討本部設置の意味
通貨発行権を行使するとは国債発行による財政出動をするということ。税金はそれを回収して社会の格差を是正し、社会を有るべき方向に誘導する装置。これが現実であり、事実なのです。従って、税金の範囲内で予算執行するべきという財政均衡論は間違いなのです。現に、世界中のどの国も財政均衡、つまり国債残高がゼロの国は存在しません。国債残高の多寡が問題なのでは有りません。国民生活が安定し国家が機能してしているかが問題なのです。
我国では20年以上にわたるデフレ状態が続き、格差が広がっています。更にコロナ禍による経済のダメージが続いています。外を見れば、中国が軍事力を強化し、領土拡大の野心をあらわにしています。政府がやるべき仕事の量は計り知れません。今こそ、通貨発行により政府がその責務を果たすべき時なのです。
それを行うために設置したのが財政政策検討本部なのです。財政均衡派、積極派双方の意見を聞き財政政策を正しい方向に向かわせます。乞う、ご期待。
瓦の独り言
「歌舞伎で日本人の感性を再認識!」
羅城門の瓦
新年寅年。あけましておめでとうございます。
コロナ過とともに新年を迎えましたが、世の中は普段に戻りつつあるかのようです。昨年末には「当る寅年吉例顔見世興行」も行われ、京都五花街の芸舞妓の「花街総見」も新聞記事に出ていました。
歌舞伎といえば、昨年末に中村吉右衛門さんがお亡くなりになられました。吉右衛門さんといえば「鬼平犯科帳」の火付盗賊改方の長谷川平蔵がテレビの時代劇の当たり役で、平成の30年間を務められました。また、瓦にとっては、歌舞伎の「楼門五三桐」の「石川五右衛門」役が忘れられません。歌舞伎を何も知らないとき、15分間の「楼門五三桐」が南禅寺の山門での出来事であることを教わりました。登場人物の真柴(ましば)久吉(ひさよし)、武(たけ)智光(ちみつ)秀(ひで)が羽柴秀吉、明智光秀であり、石川五右衛門の育ての親が明智光秀で、五右衛門が羽柴秀吉を親の仇と狙うといったストーリーで、歌舞伎では時の権力者に忖度をしてか、史実と異なった世界を演出していることも知りました。改めて、ユーチューブで吉右衛門さんの「楼門五三桐」を見直したところ、史実とは異なっているが、そこには日本人の感性、人の心情のやり取りが現れていることを再発見しました。
今、若い方に歌舞伎の「楼門五三桐(さんもん・ごさんのきり)」の漢字が読めるのか?理解できるのか? と首をかしげているのは瓦一人だけではないはずです。前回、「煙管」について書きましたが、昨年度末の12月14日に、「今日は討入り蕎麦を食べる日」と若い者(息子たち)に言ったら、「それ、何のこと?」との答え。
忠臣蔵などを扱った「歌舞伎」などの古典(?)から、さらにはさかのぼれば「源氏物語」から、日本人の感性や心情を見直す時が来ているように思っているのは瓦だけではないはずです。古臭いと言われようが、そこには失われつつある日本人の感性、義理人情があふれており、それを再認識して、次世代に継承していくのが、我々、瓦の世代の役目ではないでしょうか?
「伝えよう、美しい精神(こころ)と自然(こくど)」を信条とされ、我々が国会へお送りしている西田昌司参議院議員も歌舞伎を通しての日本人の感性、義理人情についても同じ思いを抱いておられる、と確信しているのは瓦一人だけではないはずです。
岸田文雄衆院議員との共通の問題意識
 岸田文雄総理大臣が参議院自民党役員室へ就任挨拶に来られました
岸田文雄総理大臣が参議院自民党役員室へ就任挨拶に来られました
10月4日、岸田文雄衆院議員が第100代総理大臣に選出されました。昨年8月、体調不良による安倍総理の突然の辞任を受け、自民党総裁選が実施されました。岸田候補は総裁選に立候補するも、菅候補に大差で敗れました。かねてから岸田氏は安倍総理の後継者と目されていたにも拘わらず、インパクトが弱いことが指摘され、この敗戦により総理の目はなくなったと一部に言われていましたが、正に不死鳥の如く蘇ったのです。
今から2年前、岸田衆院議員は外務大臣を退任した後、自民党の政調会長に就任されました。その際、自民党の役員連絡会で私は、「今のデフレから脱却するには国債発行を財源にした財政拡大以外に方法はない。そのためにも党内にMMT(現代貨幣論)の研究会を立ち上げるべきだ」と主張を繰り返していました。私の主張を受け止めて実行して頂いたのが当時の岸田政調会長だったのです。
今回の総裁選挙でも自分の特技は「聞く力」だとお話しされていましたが、正に事実だと思います。
そういったご縁で、岸田衆院議員とも親しくお話しする機会がありました。私がMMTを主張しているのは、新自由主義で歪んだ格差を是正し、デフレ脱却をすることが目的です。その当時から岸田衆院議員は私と同じ問題意識を持っておられました。私は次の総理には是非とも岸田衆院議員がなるべきだと、その時から思っていたのです。
「岸田文雄では自民党は変わらない」のウソ
今回の自民党の総裁選挙では、当初から河野太郎候補の勝利が喧伝されていました。しかし、結果は岸田候補の圧勝に終わりました。この結果について、マスコミ等では派閥力学の結果であり、これでは自民党は変わらないと論評していますが、全くの事実誤認です。
今回の総裁選挙には岸田文雄、河野太郎、高市早苗、野田聖子の4氏が立候補しましたが、政策面で分類すると、いわゆる改革派は河野、野田の両氏でしょう。彼らの掲げる改革とは小泉内閣以来の規制緩和路線で、小さな政府を目指す新自由主義に重きを置いています。また、マスコミ等が掲げる改革も彼らと同じ規制緩和と小さな政府路線です。これに対して、岸田、高市両氏が訴えていたのは政府が応分の役割を果たすために、財政出動を増やすと言うもので大きな政府路線なのです。
小泉内閣以来の自民党の路線の変更を訴えていたのが、実は岸田、高市の両氏だったのです。このように、明らかに岸田総理は今までの自民党の路線と違う方向に舵を切っているのです。自民党は大きく変わろうとしているのです。
新自由主義の問題点
 自民党京都府議会議員団からコロナ対策に関する緊急要望を受けました
自民党京都府議会議員団からコロナ対策に関する緊急要望を受けました
小泉総理以来、改革と言う言葉が自民党の政策キャッチフレーズになってきました。郵政民営化がその象徴でした。当時、郵政に具体的に問題点があった訳でもなく、ただ単に一度変えてみればいいんじゃないかと言う安易な改革至上主義が世の中に蔓延してしまいました。改革に応じないのは既得権益に固執する守旧派とレッテルが貼られ、次から次と規制改革が行われました。
その当時は、バブル崩壊による閉塞感が世の中に溢れていました。また一方で、バブル時代に日本に奪われた富を取り戻そうというアメリカの露骨な要求もありました。こうした中、あらゆる制度が改革されたのです。
いずれにしても、小さな政府路線は政府の財政規模を削減することになり、バブル崩壊で民需が減っている時代にこうした政策をすれば、デフレ化するのは必定なのです。その一方で、規制緩和によりビジネスチャンスを得た人もいるでしょう。しかし、規制を廃して市場競争を進めれば最後は、ただ一人の勝者が市場を牛耳るだけで必ずしも公益に合致したものとはなりません。
大店舗法の廃止で、全国で多くの商店街が破壊されました。勝ち組だったはずの大型スーパーの代表であるダイエーが経営破綻したのはその象徴です。また、インターネットの世界ではGAFA(Google、Apple、Facebook、Amazon)と呼ばれる企業群が国家権力を超える力を持ち始めています。その一方で国際課税の隙間を掻い潜る課税逃れが横行し、国家主権が脅かされています。明らかに市場原理主義、新自由主義は公益から離反しているのです。
岸田ビジョンの示すもの
岸田総理は、新自由主義路線を改め新たな資本主義を目指すと宣言しています。それは富める者と富まざる者との格差をなくし、誰もが豊かさを実感できる社会です。経済成長による利益が一部の企業や人にだけに恩恵をもたらすのではなく、政府の分配政策を通じて多くの国民に利益が及ぶことを目指しています。
企業の利益が株主への配当や役員報酬あるいは内部に留保されるのではなく、賃金の上昇を通じて多くの人々に分配されることにより消費が増え、それがまた新しい成長をもたらすという成長と分配の好循環を目指しているのです。
これは、昭和30年代、正に日本の高度経済成長をもたらした時代の姿によく似ています。この時代の総理大臣は池田勇人で、岸田総理の派閥の創設者です。池田勇人が掲げたのが所得倍増論でした。岸田総理は自らの経済政策を令和の所得倍増論と呼んでいますが、正に池田勇人の所得倍増論をモチーフにしているのです。それが成長と分配の好循環の意味するところです。
予算の単年度主義の弊害を是正
 総裁選挙管理委員として討論会を見守る西田議員
総裁選挙管理委員として討論会を見守る西田議員
岸田内閣の政策のもう一つの目玉は、予算の単年度主義の弊害を是正することです。日本では憲法上、毎年度ごとに予算を組むことになっています。毎年度ごとの予算を国会に提出して議論をする事は民主主義の基本です。一方で研究開発や国土強靭化などは長期的に予算を立てる必要があります。長期計画に基づき、毎年予算化していくのですが、景気の変動により税収も変動します。
その結果、せっかくの長期計画も税収不足になると予算化ができないのです。税収の不足分は国債を発行すれば良いのですが、毎年プライマリーバランスの黒字化が要求されるため、予算化しにくい現実があります。これが単年度主義の弊害で、日本をデフレ下にさせた根本的原因です。
岸田総理はこの単年度主義の弊害を是正すると公約しているのです。これにより、長期間を要する研究開発や新幹線ネットワークはじめ、国土強靭化などのインフラ整備が可能のなるのです。これは事実上、プライマリーバランスの黒字化目標を撤廃したことであり、財政再建路線からの政策変更です。
自民党と公明党は政策協定を結び、連立政権を20年間にわたり実践してきました。その間、バブル崩壊後の税収不足のため、長期計画が廃棄され緊縮財政が続けられてきました。これが経済のデフレをもたらした根本原因です。岸田総理の下での自公連立政権では、この方針が変更されることになるのです。公明党が要求してきた福祉政策もより一層の実行が可能となるでしょう。
立民と共産の選挙協力は共産党政権誕生の一里塚
今回の衆議院選挙においては、共産党は立憲民主党と選挙協力し、候補者を一本化して与党候補と対峙することを決めています。京都でも1区、3区及び6区がその対象です。3区や6区では、共産党が候補者を立てずに立憲民主党の候補を支援しています。共産党は明確に政権交代を主張していますが、これは共産党が野党連立政権に関わることを宣言しているということです。
つまり、立憲民主党の候補に投票することは共産党に投票するのと同じ意味を持つことになるのです。
恐らく殆どの国民は、共産党の政権など夢にも思っていないでしょう。しかし、共産党は国民の関心がない中で密かに政権の中枢に食い込もうとしているのです。それが共産党の作戦なのです。
もう殆どの人が忘れているでしょうが、かつて京都府では蜷川虎三さんが7期28年にわたって知事を務めていました。昭和25年に社会党の公認候補で初当選しましたが、その後支持母体は社会党から共産党に変わり、事実上の共産党政権が京都では誕生したのです。その間、京都府の行政組織を利用して、府下全域に共産党の勢力が拡大し、京都は停滞の時代に入ったのです。
南北に細長い京都府の発展のためには、南北に国土軸を形成することが必要です。北陸新幹線の小浜京都ルートは、山陰新幹線構想との連結により丹後から山城地域を結ぶ新幹線ネットワークを形成するためのものです。
共産党はこうした大型の公共事業にはいつも反対していますが、京都で共産党の支援を受けた国会議員が増えると、こうした新幹線計画も進まなくなってしまいます。
維新の会は、新自由主義に立脚したデフレ政党
京都は大阪に隣接しているため、維新の会もそれなりの支持者がいます。元々、自民党の大阪府会議員たちが作った政党ですから、自民党と良く似た政党だと思っている方もおられるでしょう。彼らの主張の1丁目1番地は、身を切る改革、つまり公務員や議員の定数、更にその給与を削減して行政の効率化をする。そしてその究極の目標は大阪都構想や道州制という統治機構改革です。
ですが、その大阪都構想は二度にわたって否決されました。統治機構改革は混乱をもたらすだけだと大阪の府民市民が感じたからです。そもそも身を切る改革は、デフレを加速するだけです。
かつては、自民党も彼らと同じようなことを主張し実行してきました。小泉政権時代から続く構造改革路線です。それが結局は給料を低下させデフレ下を作り出したのは先に述べた通りです。新自由主義がもたらしたこうした結果を反省し、国民への分配を増やし、給料を上げ、デフレから脱却させると言うのが岸田内閣の目指すものです。
維新の会にはこうした新自由主義についての反省が一切ありません。彼らの政策を推し進めればデフレが加速するだけなのです。
樋のひと雫
-アンデス残照-
羅生門の樋
ボリビアからは財団活動の再開や研究大会の開催日程が届きだしました。漸く日々の活動が少しずつ戻りだした感があります。しかし,完全にという訳ではなく,国際会議もリモートで行うなど,ボチボチの手探り感満載の試行錯誤からです。日本も新しい首相が決まり,総選挙の日程も決まりました。コロナ禍の中での新たな船出となります。今回の総裁選は,収まるべき処に収まった感があります。急激な変革ではなく,日々の漸進と中庸というある種の日本の国民性が現れているように思います。新しい首相には行きついた新自由主義の弊害を取り除き,富の再分配も含めた新しい日本像を期待したいものです。
ところで,アンデスの隣国ペルーでも新しい大統領が誕生しました。急進左派のカスティジョが,決選投票でケイコ・フヒモリ(西語ではjiはヒと発音します)を破りました。今回の選挙ではボリビアの友人の多くが,「アルベルトの娘が勝つ」と言っていました。彼女は3回目の選挙ですが,前回は都市部中間層の反発を受けました。今回は従来の支持層に加え,「ペルーを第2のベネスエラにするな」と云う多くの都市部住民の支持を得ていました。資源大国のベネズエラを極貧の国にした左派政権の誕生をペルーでは見たくないという心情でしょう。高名な経済学者たちも資源の国有化しか考えださない左派政権では国の発展は覚束ないと考え,今回は立場を超えた支持も表明していました。選挙前は誰も彼女の勝利を疑っていなかったと思います。
しかし,蓋を開ければ左派強硬派の勝利です。なぜ彼が勝ったのか,今でも謎です。カスティジョは地方の教員組案の活動家で,自慢は「今まで人と妥協をしたことがない」ことだそうです。筋金入りの組合活動家でしょうか。南米の多くの国では,教員組合は都市部教員組合と農村部教員組合とではその色合いが異なります。ボリビアでも都市部組合は過激でした。随分前ですが,組合のデモに反発した住民達が水を浴びせたことがありました。デモが終わってから行動隊が押し寄せ,家に小さなダイナマイトを投げ込まれるという事件もありました。幸い被害は無かったのですが,やはり過激ですよね。また,南米の多くの教員組合はメキシコのトロツキー研究所の影響を強く受けているという噂もあります(まあ,これは一種の都市伝説かも知れませんが…)。仕事で組合の幹部連中と会議をする際には,若い頃に読んだトロツキー選集の中の論文を話題にすると不思議と話し合いが順調に進んだものでした(オー,アミーゴとよく呼ばれました)。何が幸いするか分かりません。
選挙結果の分析は色々と聞こえてきますが,中南米の国々の指導者交代が,白人からインディヘナへという流れに有るのかも知れません。ここ10年ほどの間に中南米が本当の独立を果たすための胎動期に入っているのかも知れません。中南米がスペインから独立したのは200年も前ですが,独立運動を主導したのはスペインの植民地貴族であり,富を独占したのも白人の在地地主層でした。インディヘナ住民にとって収奪する人間は変わりがなかったのです。ボリビアの友人が「う~ん,ラテンの血かな」と云った言葉が何となく納得できる気がします。
しかし,傍から見ても不安ですよね。カスティジョには,何らの政治経験もなく経済政策や国の指針となる具体策が何も見えてきません。小麦や穀物等の輸入禁止やインフラの国有化など,「いつの時代の話?」と云うような選挙公約を掲げていました。選挙の狂騒が済んだ後で,コロナ禍の経済の混迷をどのように収めるかを考えている最中かも知れません。何と言っても,ペルーは南米の大国です。日本もTPP(環太平洋経済協力)では共に協力を推進する立場です。今さら,穀物の輸入禁止と言われても,「さてどうするねん」というのが正直なところでしょうね。中国や台湾の加盟申請に加えて,新外務大臣にとってかの国の貿易政策は頭の痛い問題でしょう。
一方,ケイコの方は2006年に政治活動を始めて以来今回は3度目の大統領選ですが,良きにつけ悪しきにつけ,父アルベルトの影が付きまといます。父親は在ペルー日本大使館占拠事件を鎮圧するなどテロ撲滅を掲げ,テロリストと一切妥協しなかった人物です。しかし,本来は貧困地域の生活改善,農村地帯の社会基盤の整備や収入の向上などペルーの社会発展と貧困撲滅に尽くした人物でもあります。辺地の村にも電気を通し,飲料水の整備,学校の設立(1日1校設立運動)など農村の生活向上や貧困問題に尽くしました。私が訪れた山間の僻地でも子ども達が学校に通えるようになったと言って長老から感謝されました(同じ日本人だからと謝辞を伝えてくれということでした)。他の州で私が訪れた村々でも学校建設への感謝や電気水道の確保などアルベルトへの感謝の言葉はよく聞きました。政権後期での側近の人権派への弾圧や汚職等で汚名も着ましたが,ペルーの発展に寄与した英傑であることには間違いがありません。その娘がなぜ落選?。「ラテンの血や」と言われれば,まあ納得です。
先日,アルベルトが根絶の対象としたセンデロ・ルミノソの指導者グスマンが刑務所で死亡したという報道が流れました。91年には農業開発に携わっていた日本人が3名彼らによって処刑されています。この影響で私にも初めてペルーを訪れた際に,リマを離れ地方に行く時に警護の人間が付きました。慣れないことで随分違和感を持ちましたが,報道を見てふと思い出しました。アルベルトも病気で収監されている刑務所から病院に移されたようです。また一つ現実が歴史の中へ過ぎ去って行こうとしています。
東京オリンピックを開催しても命は奪われない
このShowyouがお手元に届いている頃には、東京オリンピックは恐らく無観客で開催されていることと思います。私は、かねてより東京オリンピックの開催には基本的に賛成していました。その理由は、オリンピックでのアスリート達の極限に迫る姿は、必ずや全世界の人々に勇気と感動を与えることになると確信していたからです。そして、その感動がコロナに打ち克つ勇気を与えてくれると思っていたからです。更に、パラリンピックの選手のひたむきな姿を見れば、なおさらその感動が伝わるものと思っていました。
ところが、コロナ禍の下では、オリンピックやパラリンピック自体を開催すべきでないという世論が依然として多く、また、首都圏では感染者の増加傾向が見られたため、結局は無観客での開催となったようです。
先に行われた東京都議会議員選挙で自民党は惨敗しました。その原因の一つに、コロナ禍におけるオリンピックの開催の是非があったことは間違い無いでしょう。特に、共産党を中心に、「命とオリンピックのどちらが大切なのか」というキャンペーンが行われました。しかし、これは全くのデマゴーグです。
そもそも、新型コロナウィルスが原因で毎年の死亡者数が増えた(超過死亡者数)という事実はありません。確かに、欧米では新型コロナウィルスが死亡原因の上位に数えられていますが、日本ではそうした事実はありません。世界保健機関(WHO)によると、間接的なものも含め新型コロナウイルスが原因で亡くなったとみられる人の数を示す「超過死亡」が、昨年に世界で最低でも約300万人に上ったとの推計を公表しています。一方日本では、新型コロナウィルスによる超過死亡は無かったのです。世界的見地からすれば、日本は新型コロナウィルスによる被害を押さえ込んでいるということが事実なのです。
この様に「命とオリンピックのどちらが大切なのか」というのは、国民に不安を煽り政権への不満を呼び起こすための政治的プロパガンダなのです。
無観客開催で良かったのか
 3年ぶりに参議院憲法審査会が開催され、改憲議論が再開
3年ぶりに参議院憲法審査会が開催され、改憲議論が再開
自民党が都議選で敗北したため、オリンピックは事実上無観客での開催になってしまいました。国民の不安と不満に配慮した上で、オリンピックを開催するためのギリギリの選択だったのでしょう。しかし、私は具体的なルールを示した上で観客を入れるべきだったと考えています。
と言うのも、先に述べた様に、日本ではコロナ禍による超過死亡者は発生していないばかりか、選手始め海外からの入国者は原則としてワクチン接種が要請されており、リスクはかなり軽減されるからです。
そもそも、選手の活躍による感動を共有するためには、ある程度の観客が必要なのは当然でしょう。一年前は、大相撲やプロ野球も無観客試合を余儀なくされました。しかし、今年は、プロ野球や大相撲では人数制限をしながらも観客を入れて開催をしています。観客数に一定の制限やマスク着用などのルールを設けることにより、観客を入れることが認められているのです。
昨年は、ほとんどのイベントが中止されました。学校も閉鎖され、会社もリモート勤務になり、町中から人影が消えました。有名人のコロナによる死亡も報じられ、日本中がパニックに陥っていたのです。日本中が事実上ロックダウンされていたのです。
しかし、あれから1年以上経過して、様々な事実が明らかになりました。少なくとも日本ではスポーツ観戦が原因でクラスターが発生したと言う事実はありません。だからこそ、大相撲やプロ野球で観客が入れられたのです。何故、オリンピックでは無観客でなければならないのでしょうか。私には理解出来ません。
緊急事態宣言は誰のため?
今年の7月12日から8月22日まで、東京都では4回目の緊急事態宣言が出され、神奈川、埼玉、千葉の各県では蔓延防止措置が継続されることになりました。しかし、今年の正月から、首都圏では緊急事態宣言か蔓延防止措置が出され続けており、市民の間では自粛疲れの様相を呈しています。
そもそも緊急事態宣言は何のために行われたのでしょうか。日本の病床の8割は民間病院等が運営しているものです。欧米に比べ圧倒的に民間部門が対応しているのが日本の特徴です。これは医療の効率的運営と言う面では意味がありますが、新型コロナウィルスのような感染症対策には非常に脆弱です。かつては国民病と言われた結核が蔓延していました。そのため国立の感染病の施設が全国に配置されていたのですが、結核を事実上克服してからは、感染症の病床は極端に減らされてきたのです。逆に、生活習慣病などの平時の医療体制の充実のために、民間病院の病床が増えてきたわけです。
そうした状況の中で、新型コロナウィルスの蔓延が広がりました。感染症のための病床を用意していない民間病院が8割を占める日本では、新型コロナウィルスの蔓延が続けば、生活習慣病はもとより、今までの医療サービスを国民に提供できなくなります。これが医療崩壊です。こうした事態を避けるために、まずは人流抑制をすることにより、感染者数を徹底的に抑制するために緊急事態宣言が発せられたのです。
医療関係者や国民の協力、更にワクチン接種が進んだことにより、新型コロナのための病床の使用率も、医療崩壊の危機が叫ばれた状況からは随分落ち着いてきました。にもかかわらず、マスコミ等では、感染者数の日々の増減に一喜一憂する報道をしています。一時の医療崩壊寸前の状況は、ワクチン接種の状況も考えれば、危機は脱したと言えます。緊急事態宣言は既にその使命を終えたのです。
それでも、感染者数が少し増えれば、感染拡大の兆しありと騒ぎ、インド株などのウィルスの変異が報告されれば、ワクチンも効果がないのではないかと報道する始末です。これでは国民の気が休まることが有りません。
西村大臣の勇み足
このような状況の中で、西村康稔経済再生担当大臣が東京都への4度目の緊急事態宣言に関連し、新型コロナ対策の休業要請などに応じない飲食店に対し、金融機関から圧力をかけてもらう考えを7月8日に表明したことが報道されました。猛烈な批判の嵐に晒され、直ちに撤回が発表されましたが、その内容は、内閣官房コロナ対策推進室、国税庁酒税課から酒類業中央団体連絡協議会に『酒類の提供停止を伴う休業要請等に応じない飲食店との酒類の取引停止について(依頼)』という要請文書を出していたというものです。これでは、金融機関等に飲食店に対して「優越的地位の乱用」を要請したことになります。批判されるのも当然です。
しかし、何故このような発言をしてしまったのでしょうか。恐らく、営業自粛を無視して闇営業している飲食店が多いために、新型コロナウィルスの蔓延の防止ができていないと西村大臣は考えていたのでしょう。しかし、発言の前に、何故闇営業をしている店があるのかを考えるべきだと思います。
最大の原因は、営業自粛をしてもらえる給付金が少なす過ぎて店の家賃などの固定費が賄い切れないという、死活問題を抱えているからではないでしょうか。営業自粛をお願いするなら、補償額を増やすべきなのです。現実的には、補償額の算定には時間がかかりますから、とりあえずは融資によって運転資金を賄ってもらい、返済期限が来た時にはコロナ期間中の損失額が確定していますから、その金額を債務免除をする等により、実質的な営業補償に充当することなどが考えられます。
こういうことを念頭に入れておけば、「飲食店の経営自粛をお願いします。そのため金融機関などにも融資の協力をお願いしております。融資の返済についても営業補償も念頭にしておりますから、安心して融資を受けて下さい。」という発言になったはずです。これなら、誰も文句は言わなかったでしょう。
コロナ禍から学ぶべきもの
 京都府令和3年度予算要望を西脇知事から受ける
京都府令和3年度予算要望を西脇知事から受ける
二年前の参院選挙で、国家が果たすべき使命は災害や戦争、貧困、パンデミックなど個人の力ではどうしようもない危機から国民を守ることであり、それが経世済民の意味であると訴えてきました。奇しくも今まさにそうした危機の中に日本は有ります。今回のコロナ禍は、そうした危機に日本が立ち向かうことができるのかが問われているのです。
先日の熱海での大規模な土砂滑りなど、毎年の様に全国で災害により命や財産を失う人が後を絶ちません。災害に強いインフラ整備、国土の強靭化は喫緊の課題です。また、コロナ禍で職を失ったり、経営困難に追い込まれている方も大勢居られます。更に、民間病院が病床の8割を担っている現在の状況下では、感染症対策に大きな問題があることも分かりました。こうした課題を克服するには、政府が解決のために長期的な計画を立てそれを実行する以外に有りません。しかし、この当たり前のことが放置されてきたのです。
その理由は財政難です。日本政府は既にGDPの2倍以上の国債残高を抱えており、これ以上の借金は不可能だという財務省の見解が正しいものと信じられてきたのです。ところが今回のコロナ禍により、そういった財務省の見解が全くの的外れであったことが証明されました。
コロナ禍を乗り越えるために、個別給付金や雇用調整助成金やワクチン接種等を始めとする財政出動により、国債残高はこの間一挙に90兆円以上増えました。例えて言えば、1年で2年分の予算を投入しているのです。財務省の見解が正しければ、政府は非常識な財政出動のため、通貨の信任を失い円は売られるはずです。そうなれば円安になり、国債は引き受け手が無くなり大暴落、そのため金利は上昇し、ハイパーインフレで日本は経済も財政も破綻したはずです。しかし、その様な事実もそうなる兆しも全く無かったのです。
現実を正しく知れば危機は乗り越えられる
西村大臣が休業要請に応じない飲食店に、休業補償を増やすということより、圧力をかけることになった背景には、これ以上予算措置をするのは無理だと無意識の内に感じていたからではないでしょうか。そうした認識間違いが判断を誤らせたのです。
何年も私が主張してきた様に、日本の様な自国通貨を持つ国が国債をいくら発行しても、自国建の国債である限り、返済不能になることはない、つまり、財政破綻することは無いのです。これが事実である事をコロナ禍は教えてくれたのです。
これさえ分かれば、後は先に述べた様な予算を必要なところに必要なだけ投入すれば良いのです。そして、国民にコロナ後に明るい未来があることを示すのです。国民に明るい未来を示す事なしに、現状の我慢ばかりを強いれば不満は爆発します。
日本の財政が破綻しないという事実を正しく理解して、政府が必要な予算措置をすれば、コロナ危機は必ず乗り越えられるのです。
清水鴻一郎元議員出馬の経緯
 京都府第六選挙区支部長に新たに就任した清水鴻一郎氏
京都府第六選挙区支部長に新たに就任した清水鴻一郎氏
安藤裕衆院議員が次回衆院選挙に出馬せず、清水鴻一郎元議員に出馬要請した経緯については、私のYouTube西田昌司チャンネルで詳しく説明しています。是非、ご覧になって下さい。
瓦の独り言
-「キセルってなあに?」-
羅城門の瓦
若い方に「煙管」の漢字の読み方をたずねたら、「えんかん」という答えが返ってきました。年配の方だと「きせる」と読んでいただけるのですが・・・。
この煙管、京都の伝統工芸品のひとつで、最後の一軒になった煙管竹商「谷川清次郎商店」が今もつくっておられます。それどころか時代劇には必要な小道具のひとつで、年末吉例の顔見世興行になれば松竹さんが谷川さんのところへ新品の煙管を注文されます。「町やっこ」の小道具には太い棍棒さながらの喧嘩煙管が必要となります。「桜門五三桐」の石川五右衛門には銀の延煙管が必要です。(なぜ、新品が必要かって?歌舞伎役者さんに使い回しの煙管は使いません)
煙管の構造は、刻みたばこを詰める火皿に首のついた「雁首」、口にくわえる「吸い口」と、それらをつなぐ管の「羅宇(ラオ)」の3つに分かれます。「雁首」「吸い口」については耐久性を持たせるために金属製であり象嵌や金細工芸の加飾が施されており、真ん中の「羅宇」は圧倒的に竹が多く用いられています。
さて、若い方に「キセル乗車」について尋ねたら、知らないとの答えが返ってきました。煙管では「吸い口」とたばこを乗せる「雁首」に金属を使っていることから「入るときと、出るときは金を使うが、中間は金は使わない」といったことからきていると説明をしたら「不正乗車行為」のことですね、定期カードをうまく悪用することですね。と答えが返ってきました。「不正乗車行為」全般を指す言葉として「キセル」が誤用されているらしいです。本来はあくまでも「中間無切符」なのです。
この様に本来の意味が少し捻じ曲げられて使われたら違和感を感じるのは瓦だけでしょうか? 若い世代の方々の日常生活の中にも、誤用されている表現があるのを正していくのが我々シニア世代の役目と思っておりますが・・・。特に我々が中央へお送りしている西田昌司参議員は政治の世界での誤用をただし、本来の日本国の在り方を導いていただける「水先案内人」と思っているのは瓦一人だけではないと思っております。
感染者が増加しているのは何故か?
 参議院決算委員会で麻生財務大臣に質問(4月7日)
参議院決算委員会で麻生財務大臣に質問(4月7日)
3月末に「緊急事態宣言」がようやく終わったと思っていたら、今度は「まん延防止等重点措置」の発令です。多くの国民が何かチグハグな印象をお持ちでしょう。毎日マスコミが今日の感染者数を発表しています。これが増えれば、昨日より何人多いと注意を呼びかけ、少なくなれば、まだまだ油断は禁物と言い、国民は気の休まる時がありません。しかし、こうした報道に本当に意味があるのでしょうか?
昨年、新型コロナウィルスの感染が報じられた頃には、PCR検査をするキットも限られておりました。発熱などの症状があった人が保健所などに相談をしても、限られた人しかPCR検査を受けることはできませんでした。
ところが、今年になってからは民間のPCR検査が広がっています。病院に行かずとも安い金額で手軽に検査を受けることができるのです。私も何度か利用していますが、これは党大会などの大きなイベントがある時などに、念のために検査をするためです。私は勿論、陰性でしたが、中には陽性と診断された方もいるでしょう。すると、今度は保健所などに連絡して行政によるPCR検査を受けることになります。そこで陽性と診断された時、感染者としてカウントされ、その数が毎日報道されているのです。つまり、以前より圧倒的に大勢の人がPCR検査を受けているのです。検査を受けている人が圧倒的に増えているのですから、感染者数が増加するのは当然なのです。
感染者の大半が無症状若しくは軽症
マスコミの感染者報道によると、毎日の陽性者数の大半は、無症状か軽症で感染経路も不明なのです。濃厚接触者にPCR検査をして陽性になれば、無症状でも陽性者が増えることになりますが、その場合は感染経路ははっきりしているのです。勿論、濃厚接触がなくても発症して検査陽性と判定される人もおられます。その一方で、感染経路不明の陽性者が増えているのは、民間のPCR検査により、自主的に、念のため受けた人がかなりいるということです。
そのことを私は厚労省に指摘をし、どれくらいの民間のPCR検査が実際に行われているのかを確認しました。しかし、彼らも実際にどれくらいの数の民間のPCR検査が行われているのか分からないのです。この様に、感染経路不明の無症状者が増えている原因は、恐らく念のための民間のPCR検査が増えているからでしょう。つまり、毎日の感染者数の増減には統計学的な意味は無いということです。
マスコミは感染者数の増減報道だけでなく、なぜ無症状や軽症の感染者が増えているのかその原因を調査し、報じるべきです。そうしたことを一切せずに、単なる増減数だけを報じているのでは、市民にいたずらに不安感を煽ることになってしまいます。
むしろ、不安感を煽り、行動自粛をさせることが感染者数の減少につながると思っているのではないでしょうか。もしそうなら、これはマスコミのおごりです。正しい情報を市民に伝えることがマスコミの使命のはずです。不安を煽り意味のない行動自粛を要請するよりも、正しい感染対策をする方が遥かに効果があるはずです。
問題は病床使用率
 令和3年自衛隊入隊入校激励会に出席いたしました
令和3年自衛隊入隊入校激励会に出席いたしました
病床使用率とは、各都道府県が新型コロナウイルス患者向けに準備した病床に占める入院患者の割合のことです。政府の新型コロナ感染症対策分科会は各地の感染状況の深刻さを4段階のステージで示しており、どのステージにあるかを判断する指標の一つとして病床使用率を用いています。
感染者数を医療提供体制の逼迫度合いを検証するには、全入院患者と重症患者それぞれの病床使用率が判断材料となります。感染者が急増していることを示す「ステージ3」は病床使用率20%以上、爆発的な感染拡大が起きていることを示す「ステージ4」は同50%以上としており、緊急事態宣言は最も深刻な「ステージ4」相当で検討することになっています。
つまり、病床使用率が5割を超えてしまっては、感染者数が幾何級数的に拡大した場合、入院できない人が一挙に増え医療崩壊につながるというのが最大の問題なのです。そこで、病床使用率を増やさないために感染者数を増やさないように行動自粛が求められるわけです。感染拡大を防ぐためには、これも仕方がないことでしょう。
しかし、病床使用率を下げるためには、病床数を増やすことが重要です。もともと日本は、先進国の中でも医療が充実していると評価されていた国です。ところが、その医療施設の大半が民間病院なのです。他国では、医療施設はその大半が公のものであり、医療従事者も事実上公務員です。そのため、行政の判断により必要に応じて病床や医療従事者の確保がしやすい環境にあるのです。ところが日本では、民間病院が主軸になっているため、そうした確保が十分にできていないのが現実なのです。
そこで、東京都や大阪府の知事は、盛んに行動自粛を呼びかけ、不要不急の外出自粛とか、夜の会食は控えてなど、市民に行動自粛を求めて感染拡大を防ごうとしています。もちろん、そうした市民の協力も必要でしょうが、まず行政としてやらねばならないのは、病床の確保ではないでしょうか。少なくとも、国公立病院は率先して病床確保に協力すべきです。
また医師会も、全国の民間病院に呼びかけをして、病床確保の協力を要請すべきです。しかし、知事も医師会も危機感を煽り市民に行動自粛を呼びかけるばかりで、病床確保に努力をしている様子が伺えません。緊急事態宣言や蔓延防止措置を政府に要請する以前に、病床確保のためのあらゆる措置を政府に要求するのが筋ではないでしょうか。また政府も、国民に行動自粛を呼びかけるだけではなく、病床確保のためのあらゆる政策を総動員すべきなのです。
3密防止の意味
3密(3つの密)とは、密閉、密集、密接から名づけられた言葉です。この3つの「密」は、日本における新型コロナウイルスの集団感染が起こった場所の共通点を探した際に、この3つの密が共通となっているということが分かり、新型コロナウイルス感染症を避けるためにもこの3密を控えるようにすることを求められています。
これが意味するところは、会話等による飛沫感染の防止、飛沫よりもっと小さなエアロゾルによる感染の防止、さらにはウィルスの付着したものに触れることによる感染の防止を行うための指標です。
飛沫感染の防止のためには、マスクの着用が求められます。エアロゾルによる感染の防止のためには換気が大切です。ウィルスの付着による感染防止のためには、手洗いが重要です。ところが、3密防止が単なるスローガンになり、何のために行っているかが国民に示されないと無用の行動自粛を求めることになります。
例えば、マスクの着用です。室内で会話が予想されるような状態にある時は、マスクの着用は必然でしょう。しかし、通勤の時のように、屋外で会話をせず歩いているだけなら、マスクの着用は意味がありません。飛沫が出ないばかりか、エアロゾルも空気中に拡散するため感染のリスクは非常に小さいからです。基本的に会話をせずに屋外で行動する場合にはマスクの着用は意味がありません。
無意味な自粛要請より科学的根拠に基づく行動規範
 コロナ禍における緊急融資について商工会議所等、地元からの声をきかせていただきました
コロナ禍における緊急融資について商工会議所等、地元からの声をきかせていただきました
飲食店は、コロナの感染源で営業すること自体が許されないような扱いを受けています。アルコールの提供や営業時間も極端に制限が求められています。しかし、飛沫とエアロゾル、更に接触を避けることを重点に考えるなら、違うアプローチもあるはずです。
先ず飛沫防止です。お店によっては距離を開けたりアクリル板を設置したりしているようですが、何よりも大切なのは、会話する際には必ず会食用のマスクをつけることでしょう。
その上で、室内の換気を行い、手洗いや手指の消毒をしておけば感染リスクはかなり低くなるはずです。前号で私が示した会食用のマスクやうちわを使うことにより、飛沫やエアロゾルはかなり抑えられますから簡易なアクリル板の設置よりも効果があります。最近は、オゾンなどによる空気清浄器も有効性があると言われていますが、政府がしっかりと調査して認証すべきです。
また、人との距離を開けるというソーシャルディスタンスも会話やくしゃみなどによる飛沫感染防止のためです。マスクを着用していれば、飛沫感染のリスクはかなり低くなり、屋外であればエアロゾル感染のリスクはないでしょう。従って、プロ野球の様に屋外でマスク着用を義務づけているなら、観客数を減らす意味はほとんどないでしょう。更に、演劇やコンサートなどの屋外のイベントも同じことが言えます。屋内のイベントでも、マスクをして換気を充分行っていれば、感染リスクはかなり低くなるでしょう。
要するに、3密防止というスローガンの下、何でも行動自粛を要請するのではなく、「飛沫」、「エアロゾル」、「接触」、この3つのリスクを具体的に防ぐ手段を示すことが大切なのです。
国民に意味のない行動自粛を要請してストレスばかり与えるのではなく、科学的根拠に基づいた行動規範を示すことのが重要なのです。
都道府県間の移動制限禁止の是非
東京都の小池知事等は、都道府県間の移動制限を訴え、連休中の旅行も自粛してほしいと呼びかけています。確かに、東京や大阪などの感染拡大している地域に他の地域から旅行に行くことはリスクがあるでしょう。
しかし、東京都、大阪府、愛知県等では移動制限後にむしろ感染状況が悪化したのです。これは封鎖された感染拡大域内で外出することで、これまで以上に域内での感染確率が高くなってしまったのです。
こうした事実を踏まえて考えれば、PCR検査をして陰性だった方などは、東京や大阪などの感染拡大地域で我慢しているよりも、感染者の少ない地域でしばらくのんびり過ごしている方が、感染確率が下がると言うことです。一律に連休中の旅行を自粛するのではなく、こうした科学的根拠に基づいた行動規範を示すべきなのです。
ワクチン接種までの我慢
日本でもようやく、高齢者の方々からワクチン接種が始まりました。夏までには高齢者の大半の方には接種ができるようになるでしょう。このワクチンを打てば重症化リスクがかなり軽減されます。感染してもに普通の風邪並みのリスクになると言うことです。
このところ、大阪の感染者数が増加しているとの報告もあります。しかし、その陽性者の大半は軽症か無症状の若者です。若者は体力があり、ほとんどは軽症や無症状で収まりますが、高齢者や持病のある方に感染すると重症化リスクが高くなります。そのため、高齢者を優先的にワクチン接種をしているのです。
その後順次各年齢層の国民にもワクチン接種がされますが、高齢者へのワクチン接種が一通り済めば重症化リスクはかなり抑えることができるでしょう。陽性者が増えても、風邪と同じような症状で済めば、医療崩壊のリスクも消え行動自粛を求める必要はなくなります。その日が来るまであと数箇月です。その日が来るまで正しく恐れ、立ち向かいましょう。
樋のひと雫
-ボリビア残照-
羅生門の樋
前回は「ボリビア残照」としたのですが,いつになったら帰れるものやら。このコロナ禍で随分と自身の視野が狭くなった気がします。なんせ家と散歩に行く近所の公園が全てなのですから。
前回はボリビアの大統領選を書きましたが,原稿の締め切りの都合で紙面が出た時には既に決着していました。結果は何と市民によって追放された前大統領の後継者のルイス・アルセが当選しました。それも予想に反して,初回で53%の票を獲得し圧勝の様相です。今回の選挙が白人で親米派のメサ元大統領との一騎打ちだったことから,白人対原住民の構図も浮かび上がりますが,どうもこれはステレオタイプのマスコミ分析に聞こえます。「普通なら,メサやろ!」とツッコミたくもなりますが,ボリビア市民が持っている心情的反米意識とでも云える意識の深層に根差したものが関係しているように思えます。豊かさと自由に象徴されるアメリカへの羨望と現実の裏庭支配,この落差が人々の反感を買います。そして,この心の渇望が今回も投票の選択肢に影響を与えたのではないかと思えます。グアテマラやホンジュラスのような中米では米国への難民キャラバンという直接的な行動になりますが,南米は歩けるほど近くではありません。
ところで,前大統領のエボ・モラーレスがボリビアを追放されたのは,多選を禁じた憲法を無視して選挙に出馬した上に,選挙結果を不正に操作したことが発端でした。多くの市民が反エボの街頭行動に打って出て,本人曰く「メキシコへの政治亡命」に追い込まれることになりました。背景には,エボの出身母体であったアイマラ族の牙城であるエルアルト市民の反対運動が大きかったと云えます。随分前になりますが,ガソリン代値上げを図った時に怒ったエルアルトの住民が街頭デモで,エボの肖像画を焼き捨てるということがありました。ショックを受けた彼は2日後に値上げを諦め,国民に陳謝しています。エルアルトは此処30年ほどの間,国政を揺るがす暴動には必ずキーとなる都市です。
また,警察や軍がエボに対して辞職勧告を突き付けた時には,ベネズエラやアルゼンチンなどの反米左派の国々は右翼革命だと非難しましたが,未だ彼は「軍隊,何するものど」という気でいたかも知れません。これは余り知られていませんが,ボリビアには「ポンチョ・ロホ(赤いポンチョ)」と云われるアイマラ族の私設軍隊とでも呼べる武装組織があります。歴史的なものもあり警察や軍も一目置いています。民族的な対立や政変の際には必ず動いてきました。恐らく,彼らの支持があれば軍を抑えられると考えていたのではなかったでしょうか。しかし,今回は動かなかった。自らの出身部族からの支持が無いことが,メキシコ,キューバ,アルゼンチンへと放浪の旅に向かわせたのでしょう。
ルイス新大統領はMASの中では,中産階級出身者ということで余り人気が無いと言われていました。また,英国で教育を受け中央銀行で働いていたとも聞いています。恐らくメスチーソと呼ばれる混血系の出身でしょうから,前大統領のように必要以上に革命色を打ち出すことはないだろうと思います。「今回の選挙は社会主義の勝利だ」と叫んでいるのはブエノスに居たエボだけかも知れません。今回の選挙では多くの友人もメサ元大統領が有利だと言っていました。彼らの予想を覆したのは若者層の投票動向です。初代MASの大統領を追放したのも街頭に繰り出した若者層でした。彼らが描く国の未来とはどのようなものなのか,聞くのが今から楽しみです。
国難襲来す
昨年世界中を襲ったコロナ禍ですが、日本においても第3波に突入しています。政府はこれに備えて第3次の補正予算を策定していますが、東京や北海道、大阪では感染者数が増えて、医療崩壊が危惧されています。そのため、外出自粛が呼びかけられています。しかしそれは、経済活動を制限してしまいますから、所得が減り先行き不安になり精神的に落ち込む人も増えます。このことが結果的に多くの命を奪うことになりかねません。まさに国難の襲来です。
この国難を乗り越えるヒントとして、幕末の水戸藩士で儒学者の藤田東湖の言葉を紹介します。「国難襲来す 国家の大事といえども深憂するに足らず 深憂とすべきは人心の正気の足らざるにあり」
これは、黒船による開国要求により国中が揺れ動いた幕末の時代に東湖が弟子に示した言葉です。
黒船の到来は確かに国家の大事だが、ジタバタするんじゃない。本当に心配すべきは、人身にこれを乗り越えようとする気力や気迫が欠けることだと、東湖は弟子たちに諭したのです。
連日、ニュースやワイドショーなどで、コロナ禍の危機感を煽るような報道が相次いでいます。国民が不安になるのも当然です。しかし、この一年でわかってきたこともあります。まず、新型コロナウィルスは、高齢者や糖尿病などの持病をお持ちの方には重症化のリスクがありますが、それ以外の方には感染しても無症状か軽症状で収まるということです。
また、感染の最大の原因は、飛沫によるものです。会話やくしゃみなどをしない限り、むやみに飛散するものではありません。マスクをすれば飛沫の大部分は抑えることができます。手洗いの励行と合わせれば、感染のリスクはかなり抑えることができるのです。
会食もそれ自体で感染する事はありません。小さな声で会話をしたり、写真に示したような飛沫を抑える工夫をすれば、感染リスクはかなり抑えられるのです。また、重症化の原因が免疫の暴走であり、免疫抑制剤で重症化が抑えられることもわかってきました。
過剰に反応するのではなく、正しく恐れて楽しく暮らし、コロナ禍を乗り越えていきましょう。
 作り方をYouTube西田昌司チャンネルで公開しています
作り方をYouTube西田昌司チャンネルで公開しています
度肝を抜かれたテスラのEV
 宇治市長選挙で自民党京都府連が推薦する松村あつこ候補が見事当選されました
宇治市長選挙で自民党京都府連が推薦する松村あつこ候補が見事当選されました
政府は、10年後には新車の販売をEV(電気自動車)しか認めないと言う方針を発表しました。わが国では、エコカーと言えばハイブリッドが主流でEVはあまり見かけませんが、海外ではすでにEVにシフトしているのです。環境先進国のヨーロッパは勿論のこと、世界最大の自動車市場である中国でもいち早くEVシフトに着手しているのです。
ところで、EVはエコカーであるには間違いないが、車としての性能では未だガソリン車の方が上なのではないかとほとんどの人が思っています。実は私もそのひとりでしたが、それが誤りであることを思い知りました。実は、私の後援会の方が、アメリカのEVベンチャー、テスラのEVをお持ちになっておられ、試乗させていただいたのです。ハンドルを握りアクセルを踏んだ瞬間に、私は度肝を抜かれました。
先ず、その加速の凄まじさです。ガソリン車ではとても体験できない圧倒的な加速能力です。その実力はスーパーカー以上と言っても過言ではないでしょう。さらにモーター駆動ですので、振動も音も全くありません。抜群の静粛性です。そして、バッテリーが床下に配置されているため、低重心で重量バランスもよく非常に安定した運動性を有しています。しかも、大容量のバッテリーを搭載しているため、航続距離も500キロ以上とガソリン車並みの長距離ドライブが可能です。要するに、テスラは車としての性能が完全にガソリン車を上回っているのです。
それだけではありません。テスラ最大の特徴は、車自体が常時インターネットとつながっていると言うことです。このことにより、世界中のテスラ車の運転状況が常にテスラ社に送信され、その膨大なデータを分析することにより、完全な自動運転を行う技術とノウハウを獲得し、日々それを更新しているのです。車を買った後もソフトウェアが更新されるため、ユーザーは常に最新性能のEVを運転できるのです。こうした仕組みのお陰で、テスラは既に完全自動運転をアメリカの一部のユーザーに提供しているのです。夢の様な話がもう既に現実になっているのです。
自動車業界は現実を知るべき
しかし、こうした事実を殆どの日本人は知りません。それは、マスコミがその事実を全く報じないからです。言うまでもなく、自動車産業は日本の基幹産業です。自動車関連産業の就業人口は542万人にのぼり、文字通り日本の屋台骨なのです。そのトップはトヨタです。世界に先駆けてハイブリッド車を開発し、低燃費低公害と高性能を売り物に、世界一の自動車会社に成長しました。しかし、テスラのEVの実力はその分野においてもハイブリッドを完全に圧倒しています。
これに対抗できる様なEVがいまだに日本では開発されません。もっとも、日産は世界最初の量産型EVであるリーフを発売していますし、来年には、アリアという自動運転も含め唯一テスラと対抗できるEVを発売する予定ですが、肝心のトヨタからはその様な発表が有りません。
ハイブリッドはエンジンで発電した電気をバッテリーで蓄え、モーター又はモーターとエンジンで駆動する仕組みです。一方でEVはバッテリーで蓄えた電気でモーターを駆動させる仕組みです。圧倒的にEVの方が簡単な仕組みで、部品点数もハイブリッド車やガソリン車より4割少ないと言われています。
このため、既存の自動車メーカーにすれば、EVが普及するほど自らの系列の部品メーカーの経営に打撃が加えられますから、EVの普及は経営の屋台骨を揺るがすものとなります。純粋なEVよりハイブリッド車をトヨタなどが優先して開発してきたのはこのためです。しかし、化石燃料の使用制限は世界的な流れで有り、もはや止めようが有りません。いくら、性能面でEVと引けを取らないと主張しても、国際的ルールがガソリンの使用は認めないと変更されればどうしようもありません。ハイブリッドだけでは車を売ることができなくなる日がもうそこに来ているのです。
燃料電池や水素社会はEV化とは別の技術
トヨタは世界に先駆けて燃料電池車を開発し、水素社会の実現を提唱しています。以前は、一般にEVは航続距離が200km位でガソリン車に比べて短いのが難点とされてきました。それに比して燃料電池車は航続距離が500kmと非常に長く、一般のEVを圧倒しています。したがって、社会がEV化される時には燃料電池が主流となるだろうとトヨタは予想していたのです。ところが、現実にテスラなどはリチウムイオンバッテリーの温度管理を強化することにより、EVでも500km以上の航続が既に可能となっています。航続距離が長いことが燃料電池車の利点ですが、既にその優位性は失われているのです。
更に、燃料電池車に水素を補給するためには水素ステーションを全国に整備しなければなりませんが、その設置費用は非常に高額で一件当たり4~5億円とも言われています。そこにタンクローリーで水素を運搬しなければなりません。一方でEVの充電スタンドは比較的安価に設置でき、電力の供給は電線をつなぐだけで可能です。この様に、水素供給と電力供給のためのインフラ整備の面においても圧倒的にEVの方が勝っているのです。
スマホや液晶の二の舞になるな
元々、EVの要となるリチウムイオンバッテリーは日本で開発されたものです。また自動運転の元になるカーナビも日本が世界に先駆けて開発したものです。こうした技術力を持っているにも関わらず、次の時代をしっかり見据え、その時代にふさわしい商品開発を怠った結果、日本はEV後進国になってしまっているのです。
かつてNTTは世界に先駆けて、iモードというインターネットと接続できる携帯電話を開発したました。世界に誇るべき技術であり、国内でも圧倒的なシェアを持っていました。ところが、アップルがiPhoneと言うインターネットの接続で動画や音楽も自由に配信できる電話の枠を超えた通信機を開発するや、一気にシェアは奪われ、もはやガラケーと呼ばれています。
シャープはかつては世界最大の液晶メーカーでした。自らが培った液晶技術を長期間にわたり韓国のサムスン電子に提供してきた結果、人件費の安いサムスンに価格競争で敗れ、遂には台湾の鴻海(ホンハイ)精密工業に買収されてしまいました。
このように、経営判断のミスが企業に致命的な衝撃を与えるのです。これは単に企業の経営問題だけにとどまらず、日本の国力そのものにも影響を及ぼしてしまいます。このままでは、日本の主力産業である自動車産業もスマホと液晶の二の舞を演じることになりかねません。
環境の変化に対応する
スマホと液晶の失敗から学ぶべき事は、自らの技術に対する自信過剰が、潮流の変化に気づくのを遅れさせたことが致命傷になったと言うことです。世の中は常に変化しています。その変化に対応できなかったものは滅びるしかないのです。史上最強の生物であった恐竜が一瞬にして絶滅したのは、巨大隕石の衝突による環境変化についていけなかったためと言われています。温暖だった気候が一気に氷河期に激変したため、大型爬虫類は環境変化についていけなかったのです。
幕末の黒船襲来は劇的な環境変化でした。まさに国難の襲来です。しかし先人たちは、自らの国の形を変えることにより、この国難を乗り越えたのです。変化を拒み、頑なに現状維持に拘れば自ら滅んでしまうだけです。
自動車はロボットになる
 財務省は「万死に値する!」参議院財政金融委員会(YouTube西田昌司チャンネルでご覧いただけます)
財務省は「万死に値する!」参議院財政金融委員会(YouTube西田昌司チャンネルでご覧いただけます)
テスラという黒船の来襲に、今こそ日本の総力を上げて対抗しなければなりません。それは自動車というものを根本的に変えるものとなるでしょう。EVに自動運転が装備されれば、最早自動車では無くロボットと呼ぶべきものになります。
行き先を伝えれば、ハンドルを握ることもアクセルを踏むことも無く、目的地まで連れて行ってくれる。これは、アメリカでは一部の人にはこうしたソフトウェアが配信されて実現しているのです。これが完全に可能になれば、タクシーはいらなくなります。まさにロボットタクシーの時代になるでしょう。さらに、自家用車でも自分の使わない時間帯はロボットタクシーに貸し出し収益を上げることも可能になるでしょう。
自動運転EVは、都会より地方の方が親和性があります。地方の方が一戸建てが多いため、自宅で充電できるからです。また、その自宅の屋根に太陽電池パネルを設置すれば、充電も無料になり、災害時の停電にも備えることができます。
さらに、高齢者の免許証の返還が増えていますが、自動運転になれば、そもそも運転免許が不要になるでしょう。高齢になっても安心して車に乗れるのです。勿論、飲酒運転も問題でなくなります。
都会の狭い集合住宅に住むより、地方の一軒家で住む方がEVには適しているのです。東京一局集中を排して地方に活力を与えるためにもEV化を進めねばなりません。
瓦の独り言
-1月7日は「人日の節句」-
羅城門の瓦
新年 明けましておめでとうございます。
今年も瓦の独り言をよろしくお願いします。「めでたさも ちゅうぐらいなり おらが春」といった心境です。(新型コロナウイルスまん延のため)
さて、1月7日は「七草粥」の日ですが「人日(じんじつ)」の節句と言って、五節句(1/7:人日の節句 3/3:桃の節句 5/5:菖蒲の節句 7/7:笹の節句 9/9:菊の節句 )の一つです。古代の中国では奇数(陽)の重なる日はめでたい日とされていましたが、陰(偶数)に転じやすいので、邪気を祓う行事が五節句として行われてきました。こうした中国の風習が日本に伝わり、当初は貴族社会で行われていましたが、江戸時代には一般庶民までに広まり式日(現在の祝日)として制定されていました。でも、明治なって旧暦とともに五節句も廃止されましたが、今でも私たちの暮らしの中に息づいています。
ところで、1月1日ではなく、なぜ、1月7日なのでしょうか。不思議に思っていたら、wikipediaの説明を読んで納得しました。中国の前漢の時代(約2200年前)の占いの書に正月1日に鶏を、2日に狗、3日に羊、4日に猪、5日に牛、6日に馬、7日に人、8日に穀物を占って晴天ならば吉、雨天なら凶の兆しあり、とされていたそうです。ですから7日の「人の日」には邪気を祓うために「七草粥」を食べて、1年の無事を祈ったものだとされています。(諸説は色々とあります)
この七草粥に入れる野菜(セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、ススシロ)は旧暦とはいえ、若菜をつむには寒い季節です。「古今和歌集」の有名な一首に「きみがため 春の野にいでて 若菜つむ わが衣手に 雪はふりつつ」とうたわれ、愛おしい御方のために、寒い中を労力と手間を惜しまぬ気持と、特別な行事であったことがわかります。この七草の野菜は生薬としても重宝され、正月のお酒やごちそうで疲れた胃をいやしてくれる「食べ物」として重宝されています。時によれば「新型コロナウイルス」に打ち勝つ作用があるかもしれません。
「Go Toトラベル」や「Go To Eat」の先にある「Go To 日常」を早く取り戻すため、われらが中央政界へお送りしている西田昌司参議院議員も七草粥を召し上がられて、邪気を祓われて、奮闘されることを確信しているのは瓦一人だけではないはずです。
安倍総理の突然の辞任
 自民党京都府連として西村大臣に新型コロナウイルス感染症に係る緊急要望をいたしました
自民党京都府連として西村大臣に新型コロナウイルス感染症に係る緊急要望をいたしました
8月28日、安倍総理は記者会見で体調不良により総理を辞することを発表されました。このことを受け、9月14日に自民党総裁選挙が行われ、圧倒的多数で菅新総裁が誕生いたしました。そして臨時国会が召集され、9月16日に菅内閣が正式に発足いたしました。発足から、1カ月余りですが、縦割り行政の解消や携帯電話料金の引き下げ、デジタル庁の開設など、矢継ぎ早に政策を発表されています。
マスコミ各社の世論調査は70%を超える支持率があるとも報道されていますが、この高い支持率に一番驚いておられるのはおそらく菅総理自身でしょう。その背景には、安倍政権に対する評価の見直しがあるとわ私は思っています。安倍内閣の支持率は、コロナ禍の中で不支持率が支持率を上回る状態が続いていましたが、辞任発表後は大幅に回復しました。
これは、コロナ感染の不安だけでなく、外出自粛によるフラストレーションや経済の低迷など、国民の中に溜まった不満が安倍政権への批判につながったからでしょう。しかし、安倍総理の辞任の報に接し、安倍政権を冷静に評価すれば、民主党政権の混乱の時代とは比べ物にならないほど日本の国力再生に貢献した、と国民は感じたのではないでしょうか。
その安倍政権を内閣官房長官として支えてきた菅総理に対する期待が、今回の就任時からの支持率の高さに表れているのだと思います。その期待に応える働きを私も期待したいと思います。
縦割り行政の解消
菅総理は、ダムを管理している責任者がダムの種類によって違い、その結果、洪水を防げない事態になっていると指摘しました。例えば、発電や用水などの為の貯水は、利水する側の権益があるため、洪水に備える為でも簡単には事前排水ができません。しかし、一旦洪水になってしまったら、利水をする側の生命や財産も消滅する危険があります。ダムを管理する側の個別の利益よりも、真に国民の生命や財産を守ることを考えたダムの運用が必要だ、と菅総理は力説されていました。まさに縦割り行政の解消が必要だと言うのです。
これはその通りだと、私も思います。そうした個別の利益を超えた全体の利益を調整する仕組みが必要なのです。しかし、現実にはこれがなかなか難しいのです。それを象徴するのが、内閣府の巨大化です。
行政機関は各省庁別に権限と責任が分担されています。しかし、中には省庁間を超えて調整すべき仕事なども多数有ります。先に述べたダムの管理もこの対象になるかもしれません。そこでそうしたものは、各省庁から内閣府にその権限が移管され、最終的に内閣総理大臣がその責任者になっています。こうしたことがこの20年にわたり行政改革のもと行われてきました。あらゆることが内閣総理大臣の権限で行われる様になりましたが、現実には、内閣府特命担当大臣が任命されその任にあたるのです。防災担当大臣や少子化担当大臣、最近ではオリンピック担当大臣など次々に特命担当大臣が増え、現在では約20人の大臣のうち10人が特命担当大臣になっています。
内閣府の所管する事項を国会で審議するのが内閣委員会、その内閣委員会の所管する事項を党内で議論するのが内閣部会です。所管事項が増えすぎたため、党の内閣部会は第一と第二の2つに分割されましたが、国会の内閣委員会は分割できません。そのためこの委員会には多数の法案が集中するため法案審議は超過密スケジュールです。
もともと縦割り行政を排除するために作られた内閣府でしたが、特命担当が増えた結果、内閣府自体が肥大化して、機能不全に陥ろうとしているのです。こうしたことを考えれば、縦割り行政の解消のためには、省庁再編など組織をいじることよりも、そのトップに立つ役人や政治家が、国民目線に立ち、その都度適切な判断をする以外ないのです。この20年間行ってきた省庁再編などの行政改革は失敗だと言えるでしょう。菅内閣にはぜひこの点を理解した上での改革をしていただきたいと思います。
デジタル化の推進
 デジタル社会推進政治連盟主催の政策勉強会において現代貨幣論(MMT)について講演いたしました
デジタル社会推進政治連盟主催の政策勉強会において現代貨幣論(MMT)について講演いたしました
菅内閣のもう一つの目玉がデジタル化の推進です。コロナ禍の中で、リモート勤務やリモート授業の機会が増えましたが、それに必要なインフラが十分でないとの指摘もあります。また、給付金の申請等の行政手続もデジタル化が進んでいれば、もっと敏速に対応できたのではないかという批判もあります。確かに、日本はデジタル化の面ではかなり遅れているように思います。
私は、税理士の業務もしていますので、申告の面でのデジタル化の遅れは痛感していました。例えば、電子申告は国税では実現していますが、地方税では十分ではありません。地方によっては、電子申告で受け付けた書類をもう一度手入力で処理をしているところもあると聞きます。これではデジタル化で仕事の効率化どころか、無駄を作り出しているに過ぎません。
こうしたデジタル化の遅れの原因は、結局は予算不足ということです。日本は本来、デジタル化の技術の面では、最先端を行く先進国です。ところがそれを普及させるには、そのためのインフラ整備が必要なのです。電子申告が地方で普及できない最大の原因は、電子申告を受け入れるためのソフトウェアを地方自治体が持っていないことです。その整備には多額の資金を投じてソフトウェア開発をしなければなりませんが、財政力が小さな自治体には到底無理なのです。然らば、総務省が、そうしたソフトウェアを自ら開発して、各自治体に無償で供給すれば良いのですが、財務省から財政再建という圧力がかけられ予算化できないのです。
せっかくの技術力を持っていながら、予算がつけられなかったために日本はデジタル後進国になってしまったのです。今回、菅総理が肝煎りでデジタル化を推進するなら、まずはそのための予算を確実に増やす必要があります。
未だに新幹線ネットワークができない理由
予算不足でデジタル後進国となった日本ですが、同じことが新幹線ネットワークについても言えます。昭和39年10月1日、日本は世界に先駆けて高速鉄道の技術を確立しました。その後、昭和48年には全国に新幹線ネットワークを構築するため、11の基本計画が策定されましたが、そのほとんどが未だに建設の目処は付いていません。その理由は、国鉄の破綻と政府の財政再建優先の姿勢です。これが、あらゆるインフラ整備を遅延させてしまったのです。全国に新幹線のネットワークを建設するのには30兆から40兆円の建設費が必要だと言われています。莫大な金額のように見えますが、完成まで十数年かかることを考えれば、毎年の予算額はたかだか3兆円程度です。今年のコロナショックのために補正予算は一次二次合わせて約60兆円であることを考えてみれば、決して法外な予算額では無いと理解していただけるでしょう。
普段なら、これだけ大きな規模の補正予算は、財務省の猛反対に合っていたはずです。しかし、さすがに今回のコロナショックでは財務省も正面から財政出動を否定することはできなかったのです。
彼らが財政出動に頑なに反対してきた理由は、「孫子の代に借金をつけ回すな」と言うことに尽きます。したがって、今回のコロナショックのための補正予算は仕方がないとしても、いずれは、その返済のために税金を上げるか他の予算を減らすかどちらかを要求してくるでしょう。しかし彼らの主張に最早、合理性はありません。
国債は国家の資本金である
 京丹後はごろも陸上競技場リニューアル完成式典に出席し、ご挨拶いたしました
京丹後はごろも陸上競技場リニューアル完成式典に出席し、ご挨拶いたしました
今回のコロナショックで政府は様々な財政政策を実施しました。その一つに劣後債の導入があります。劣後債と言うのは返済期限が最も後になる債券と言う意味です。例えば10億円を借りても、利息の支払いだけで元金の返済は10年後や20年後など、かなり後で払うというものです。これにより、企業は元金返済の必要が事実上なくなりますので、会計上も劣後債は負債ではなく資本として取り扱われることになります。その結果、 経営者はコロナ禍においても資金繰りのリスクから解放され、安心して企業の経営をすることができるのです。
実は、国債はまさにこの劣後債と同じ性質のものなのです。国債を発行すれば、それは国家の借金であり、孫子に借金をつけ回すべきでないと、財務省は必ず言います。しかし、現実には国債の償還は税金でしているのではありません。そのほとんどは、新しい国債を発行することにより古い国債の償還をしているのです。いわば古い国債と新しい国債を交換しているのです。
つまり、国債の償還はせず利払いだけをしているのが現実なのです。孫子の代も利払いだけで、元金の返済はしていないのです。
そしてこの事実を見れば、国債は劣後債とそっくりであることがわかります。劣後債が事実上資本金として扱われるのは、返済を必要としないからです。利払いするのは配当金の支払いと同じことですから、劣後債はほとんど資本金と同じと言って良いでしょう。
国家にとって国債は、この劣後債よりもさらに資本金の性質を持つものです。劣後債は一応償還期限の定めがありますから、その時になれば元金の返済が必要となる可能性はありますが、国債に関しては償還期限が来るたびに新規国債を発行すれば良いだけで、それを制限するような法律は何もありません。正に、元金の返済を要しない国債は、国家にとっては資本金なのです。
安倍政権の失敗に学べ
約8年前、安倍政権が誕生した頃の日本は、まさにデフレのどん底でした。無駄削減に代表される民主党政権の緊縮政策がデフレを加速させたからです。それに反旗を翻したのが安倍政権です。異次元の金融緩和、機動的な財政出動、民間投資戦略、この3本の矢でデフレからの脱却を目指したのです。しかし、現実に実行されたのは異次元の金融緩和だけで、財政出動や民間投資は増えませんでした。むしろ、三党合意があったとは言え、完全にデフレから脱却する前に2度にわたり消費増税をしてしまったのです。「経済再生なくして財政再建なし!」と訴えた安倍総理でさえ、国債残高が増えることに反対する財務省を抑えきれなかったのです。
しかし、コロナショックによる経済対策は国債の増発でしか賄うことができません。そしてそれを実際に行っても、何ら問題が発生しないことが明らかになりました。菅総理には、こうした事実を踏まえて、大胆な財政出動をしてコロナショックからの回復に全力を挙げていただきたいと思います。
樋のひと雫
-ボリビア残照-
羅生門の樋
日本では大統領選と云えば米国のそれを指します。11月の選挙に向けて、「此処はどこ?」と思えるぐらいに毎日TVで米国大統領選を報じています。多くの米国政治の専門家がトランプだのバイデンだのと人柄や日々の所作まで喧伝しています。子供の頃の行動や家族関係まで曝け出す、その報道もどうかと思います。日本の命運を握る最大の同盟国の首長であれば致し方ないのかもと思いますが、我々には選挙権がないので所詮は他山の石とするしかないのですが。
大統領選と云えば、ボリビアでも大統領選がこの18日に行われます。他山の石どころか、遥かアンデスの石としか見えないのですが…。まあ、私には身近な話です。これは前大統領のエボ・モラーレスが憲法の規定を無視し、不正投票で続投したことが原因です。市民が蜂起し、警察や軍部の支持も失いメキシコを経てキューバに逃亡しました。現在はアルゼンチンにいて大統領選をコントロールしようとしているとか。本人は未だに権力をわが手にもう一度と画策しているつもりかもしれません。しかし、過去には怒った大衆が現職大統領を官邸前の公園の街灯に吊るした国です。昔とは事情が違うでしょうが、ラテンの血は流れています。そろそろ彼自身権力の亡霊とは手を切るべきだと思いますが…。
議会によって暫定大統領が選ばれ、大統領選となるはずがコロナの蔓延で時期がずれました。今ようやく新たな大統領を選ぶべく選挙が準備されています。因みに、暫定大統領は
出馬しません。出れば初の女性大統領が誕生した可能性もあったのですが、残念です。まあ例によって、似たり寄ったりで一度目で過半数は取れないでしょうから、決選投票になります。選挙騒ぎは続きます。別段、コロナが落ち着いたわけではありません。相変わらずマスクや消毒アルコールと云ったものは手に入りません。この選挙を契機として、何とか日常を取り戻そうと努めています。
ボリビアでは、大統領選と云えば異常に熱くなります。日本のように選挙カーが走り回るわけでもないのですが、3人集まれば候補者の話題になります。喧々諤々の話し合いが、取っ組み合いになることも珍しくはありません。国のトップを選ぶ直接選挙を経験したことのない身には、何故これ程熱く成れるのか、不思議な気もします。大統領が替われば、大臣も代わります。大臣が替われば省庁のスタッフ全員が代わります。門番まで替わると言われています。選挙の論功行賞で省庁の役職が割り当てられます。地方の自治体も同じです。村の役場まで総入れ替えです。産業の乏しい国では、省庁が最大の雇用先です。職を得ることに選挙が直結します。私がいた省も3人の副大臣が3ヶ月毎に代わりました。当然彼らの担当部局の人間も代わります。1年間ほどは人事の交替が毎日のようにありました。ある時大臣との会談が有り会議室に入ると、お茶を出してくれた子が1週間前まで私の部屋を掃除していた女の子でした。驚いて聞くと大臣室の渉外スタッフになったとか。清掃の制服を紺のスーツに替え、廊下を闊歩していました。
まあ、熱くなるのは当たり前かもしれません。そのため、投票の2日前から酒の販売は禁止され、24時間前はレストランやバーでも飲酒禁止の措置が取られます。レストラン等の店には警察官が査察に来ます。違反すれば店には1週間ほどの営業停止処分が科せられます。しかし、店も客も良くしたもので、前夜は特別の部屋が用意され、飲む客はそこに通されます。警察が来ると息を潜め、目で会話しながらワインやシンガニを傾けます。これが結構面白くて警察官がいる10分間ほどに飲むワインの味は、特に美味でした。警官が出ていくと全員で「Salud!(乾杯)」。外では警官が振り返りながら苦笑していました。
前代未聞、一国会に四度の予算
 参議院財政金融委員会にてコロナ債務免除を提言!反対する財務省を一喝!
参議院財政金融委員会にてコロナ債務免除を提言!反対する財務省を一喝!
第201国会は、6月17日に閉会致しました。今国会では、平成31年度の補正予算、令和2年度の当初予算、その後、第一次、更に第二次補正予算と、1国会で4つの予算を成立させると言う異例尽くめの国会となりました。これはもちろんコロナ対策のためなのですが、その結果、今年度は補正予算と合わせて事業規模230兆円、GDP(国内総生産)の4割に上るものとなりました。新規の国債発行額は当初予算と補正を加えた令和2年度全体で過去最大の90兆2千億円に上り、歳出の56.3%を占めることになります。
当初予算では63兆円の税収を予定していましたが、コロナショックのため税収が落ち込むのは必至であり、最終的には更に多額の国債を発行する事は必定です。更にこの先、第三次補正予算を組んでコロナ後の景気対策も行わなければなりません。国債の発行額は更に増えるでしょう。しかし、心配無用です。国債発行額が増えても何ら問題は有りません。通貨と国債の関係を理解していただければ、その理由が分かります。
不換紙幣になった通貨は無限に発行できる
通貨である円(日銀券)は、日銀にとっては負債ですが、返済期日もなければ金利も付きませんから、本来はただの紙切れです。そのため、かつては紙幣の信用を保証するために、兌換紙幣として、そのお札と同額の金と交換することが義務づけられていました。日銀は常に一定額の金の保有が義務付けられていたのです。これが結果的に、金の保有量が通貨の発行額に制限を加えることになりました。
その結果、日銀は自由に金融政策を行えず、昭和の初めには大恐慌をもたらしました。その経験から、通貨は金と交換義務の無い不換紙幣になったのです。不換紙幣になってからは金の保有量による制限もなくなり、通貨発行には何ら制限がなくなっているのです。
通貨の不換紙幣化が国債発行の制限を無くした
日銀による通貨発行は具体的には次のようにして行われます。日銀は国債や株式や社債等を市場から買い入れ、その代金として日銀券を発行することにより、市場に通貨供給をします。これが通貨発行です。この手続きを買いオペ(金融緩和)と言い、逆に買い入れた国債等を売ることを売りオペ(金融引き締め)と言います。その時の経済状況に応じて、 買いオペと売りオペを使い分けることにより、通貨量と金利を調整して金融政策を行っているのです。
現在日銀が行っている異次元の金融緩和は、大規模な買いオペです。今は、買い入れ額の限度を設けずに、市場を通じて銀行から大量の国債を買い取っています。その結果、銀行には国債の買取代金として多額のお金(日銀券、実際には日銀当座預金)が振り込まれています。
企業間取引の決済は、大事な銀行の業務です。銀行間でその決済に使われるのが日銀当座預金です。買いオペの結果、銀行の手許には多額の日銀当座預金があるため、銀行間取引を決済をするのに銀行は資金を借りる必要が有りません。そのため金利は限りなく低くなります。これがゼロ金利政策です。日銀が銀行に大量の通貨を供給した結果、お金がだぶつき金利がゼロになっているのです。
国債は政府の負債であると同時に、日銀にとっては金融政策を行う上で欠かすことのできない資産です。兌換紙幣の時代には、金の保有量により通貨発行額に制限が加えられていたため、買いオペにも限界がありましたが、今はありません。そのため、政府の国債発行に財政上の制約はなくなっているのです。この事実を財務省は無視しています。
子や孫に借金をつけ回すなの嘘
「無闇に国債を発行して子や孫に借金をつけ回わすな」はモラルとしては正しいです。しかし、事実は、国債発行は子や孫の代に借金をつけ回すことでは無いのです。
今回のコロナ対策の様に、国債発行により給付金を支給した結果、政府の負債は増えました。一方で、国民の現金預金が増えた事も事実です。つまり、新規国債発行をして予算を執行すれば、政府の負債は増えるが、その同額の預貯金が必ず国民側に支給されることになるのです。これは、給付金に限りません。公共事業であっても、年金の支給や医療などのサービスの提供でも全く同じです。つまり、国債を新規発行による予算執行により、政府の負債は増えてもその分同額の現金預金が、国民側で必ず増えるということです。これは、否定のしようの無い事実なのです。
国債残高は必ずしも減らす必要が無い
 西村大臣に緊急事態宣言解除後の経済活動の段階的な再開を訴えました。
西村大臣に緊急事態宣言解除後の経済活動の段階的な再開を訴えました。
国債発行により国民側に預貯金が供給されるのが事実だとしても、「国債は償還期日が来ればいずれは返済しなければならないはず。そのためには税金を徴収する必要が有る。結局、孫や子の代が負担することになるのでは無いか」と考える人もいるでしょう。しかし、それも間違いです。
何故なら、国債の償還は必ずしも税金でする必要が無いからです。償還額と同額の国債を発行して償還すれば良いのです。これは現実には、我が国始め、どこの国でも行なっていることです。
例えば、令和2年度の当初予算の内、公債金(新規国債発行額)は32兆円です。一方、歳出の内、国債費(国債償還額)は23兆円です。現実に国債の償還の為、新たな国債を発行しているのです。国債の償還より新規国債発行額の方が多いことから、国債残高は増え続けていますが、その分、国民側に現預金が供給されているということです。
事実、日銀によると2020年3月末での家計の金融資産残高は1,845兆円にも上っています。「豊富な個人金融資産のお陰で日本は国債発行が可能になっているが、高齢化で取り崩されれば預金は減り、いずれは国債を買い支えられなくなる」と言う人がいますが、これは本末転倒の暴論です。
事実は、国債残高が増えた分だけ、国民側の現預金が増えているのです。また、高齢化で預貯金を取り崩す人が増えるのは事実としても、それを取り崩して消費に使うわけですから、誰かの現預金が必ず同額増えるのです。これが事実です。テレビのキャスターなどもこうした発言をする人がいますが、全く勘違いをしています。
税金をなくせと言うのはモラル崩壊を招く
国債発行により予算が組むことができ、しかも、国民側に現預金を供給することができるのなら、「税金など取らず、予算は全て国債発行で賄えば良いではないか」この様に反論する人も出てくるでしょう。しかし、これは暴論です。
もし税金がなくなれば、そもそも納税の義務がなくなるわけですから、国家を国民が支えるという国民道徳は無くなってしまいます。そもそも近代国家は、自分の国は自分で守り、自分で支えると言う国民道徳がその前提にあります。そして、その運営のための経費は自らが賄う、つまりこれが税金なのです。そして、自ら国を守り、国を支えると言う崇高な義務を果たす市民には、主権者としての権利が与えられているのです。
こうした考え方に則り近代国家は作られたのです。国民から税を徴収して、それを財源に予算を執行するという発想からは、当然、財政は均衡すべきであるという考えになります。入を量りて出るを制すと言われる様に、予算執行に必要な税金を徴収するのが当然だということです。
近代国家では、国民は国家から安全保障や教育、医療や介護などの福祉サービスの提供を始め様々な便益を受けます。その結果、その便益に対する対価として税を負担するのは当然ではないかというモラルが生まれます。私もかつてはそう考えていました。しかし、モラルだけに縛られて財政の真実を見落としてしまうと、結局、国家は滅んでしまいます。モラルと同時に、財政に対する正しい認識が必要なのです。
モラルと同時に正しい財政論が必要
 岸田政調会長に鉄道関連予算の大幅な拡充を申し入れました。
岸田政調会長に鉄道関連予算の大幅な拡充を申し入れました。
「入を量りて出るを制す」は国民道徳としては正しいですが、残念ながら、財政論としては間違いなのです。そもそも、これに固執していては、国民を救う事はできません。
具体的に今日のコロナ禍のことを考えてみましょう。多くの国民がコロナ禍により経済活動の自粛を余儀なくされました。それが消費の急激な減退をもたらし、国民から所得そのものを奪っています。当然、税収も落ち込みます。財政均衡主義に立てば、税収が減れば予算も減らさねばなりません。
しかし、流石にこの状況下で予算を減らすことはできないでしょう。国民生活を守るためには、むしろ、積極的に必要な予算を出すべきだと誰もが感じているはずです。国民が苦しんでいる時には国家が救うと言うのは、国家の当然の責務です。国民が国家を支えるのは、国家が国民を守ってくれるからです。肝心な時に国家が国民を守ってくれなければ、国民が国家を作った意味がありません。
そこで、冒頭に述べたように巨額の補正予算が策定されたのです。巨額の国債を発行して財源としていますが、それが問題ない事は先に述べた通りです。しかし、国会議員や財務省の官僚、経済学者の中には、未だに通貨と国債との関係を理解していない人が、多数存在しています。兌換紙幣(金本位制)の時代と不換紙幣(管理通貨制度)の時代では通貨の本質が全く違うものになっていること(MMT現代貨幣論の本質)に気がついていないのです。
緊縮財政がコロナ禍と災害をもたらした
さて、今年も九州や岐阜県や長野県などで洪水による被害が報告されています。こうした災害は毎年のこととなっています。その様な中、九州の球磨川では洪水対策のためダムの建設が予定されていたにも拘らず、脱ダムの世論に押されて建設を諦め、その結果、甚大な被害を招いたのではないかということを報道で知りました。昨年は、八ッ場ダムを巡って同じ様な議論が有りましたが、この背景に有るのはこの20数年吹き荒れた公共事業は無駄なものとする世論です。
公共事業は国の債務を増やす元、これ以上、子や孫に借金を背負わすなと言う世論が、結局、その命を奪うことになったのです。国債を国の借金と決めつける誤解が招いた不幸です。二度とこの様な過ちを繰り返さないためにも、国債を正しく理解しなくてはなりません。
MMT(現代貨幣論)に限界は無いのか
国債は子や孫に借金をつけまわすものでは無く、現実は国民の現預金を増やすということ、国債償還は税金に依らずとも新たな国債発行で賄うことができるということ、また、不換紙幣の時代には、国債発行に制約が無くなっていることを述べてきました。結果として、財政論的には国債発行は無限にできるということなのです。
ただ、国債発行が無限にできても、納税を否定すれば国民道徳は崩壊し、国家は成り立たなくなる事も事実です。その意味において国債発行の限界は財政の破綻では無く、モラルの崩壊に有るのです。
また、国債発行が国民側の現預金を増加させるため、それが消費や投資にまわればインフレになる事も事実です。インフレ率に注意を払う必要が有りますが、インフレを恐れて緊縮財政を基本とした結果が、今日のデフレを長引かせたことを忘れてはなりません。
MMTはオールマイティでは有りませんが、少なくとも今日の長期停滞、とりわけコロナ禍を乗り越える大きな政策の道具であることには間違いありません。
樋のひと雫
-ボリビア通信-
羅生門の樋
街路樹の葉も落ちアンデスの神々の座も白く輝き、人々は訪れる冬に備える今日この頃・・・などの描写で始めるはずですが、今年はコロナ禍で久々に日本の梅雨を楽しんでいます。隣国ブラジルでは150万人、ペルーでは30万人が感染していると言われていますが、我がボ国は正確な人数は不定です。La RazónやPrensaという当国の新聞記事を見ていても、「本日の感染者数」という確かな人数が見当たりません。友人にメールで問い合わせても「No sé(知らん)」という答えばかりです。どうも、保健省も正確には把握できていないようです。尤も、4、200メートルの高地からアマゾンの源流まで、日本の4倍の国土に1千2百万人程が点在しているのですから、正確な把握は端から諦めているのかも知れませんが…。それでも、記事には30ほどの病院が院内感染で閉鎖されたとか、患者が診療所に押し寄せ、それが原因で感染が拡大している等の様子を伝えています。
友人たちのメールにも、「外出禁止令が出て個人IDカードの末尾の数字で外出が許される。」とか、「週に1度の買い物しか出来ず、食料品の確保も困難だ。」などの連絡も来ます。マスクや消毒アルコールが市中には無く、「自分は檻の中の熊だ」というのもありました。中には、半ばヤケクソ気味に「チューニョ(乾燥馬鈴薯)とチチャ(トウモロコシの発酵酒)を飲んでれば感染しない。」というのもあれば、行政機関の友人からは「登庁命令が出ているので行くが、もう会えないかも…」という悲惨なものまであります。友人達のメールを見ながら、世界から見れば安全な日本に居ることに、何か後ろめたさも感じます。
ボ国は年末から今年に入って国難続きです。昨年末には、憲法の規定に反しエボ・モラーレスが大統領の4選20年を目指しました。彼は憲法の改定を図りましたが、国民投票では否決された経緯があります。出馬を強行したこの選挙では、「民主主義の否定だ」として多くの市民が街頭に繰り出し、エボ支持のMAS(社会主義運動)派住民と各地で衝突しました。初めは反対派のデモを鎮圧していたコチャバンバ市の武装警察隊の一部が、「我々を市民の弾圧に使うな」と出動拒否の姿勢を明らかにします。この動きが各地に広がり、彼は首都ラパスを放棄し、本拠地のチャパレに逃れました。その後は軍部も反エボ派支持に回り、メキシコに逃亡することを余儀なくされ今はキューバに居ます。しかし、残されたMAS派はデモや道路封鎖を繰り返し、国を二分した対立は未だに続いています。
原住民出身の初の大統領として現れた時には、随分と清冽な印象を受けました。1回目の選挙で過半数の票を獲得したのも彼だけでした。原住民だけではなく、多くの国民から支持を得ました。最初の選挙の際には、コカ栽培農家組合のレクレーション係から昇り詰め、MASという政党を組織するほどの資産を形成したことには、とかくの噂が立ちました。それでも南米の政治家には見られない、鮮烈な変革への希望が伺えました。ある会合で「日本はボリビアの真の友人だ」と言って、ハグで私を迎えてくれたことを思い出します。
3期15年の中で、中南米の状況も随分と変化しました。急激な国際経済の変化もあり、師であるフィデル・カストロや盟友チャベスも去りました。原住民解放の中南米の反米主義も中国の資源獲得を目指した覇権主義の中で変質を余儀なくされています。いつの日かコロナ禍が収まれば、暫定大統領は選挙を行うことでしょうが、その時にはどのような人物が選ばれるのか、楽しみでもあります。その際には、再びボ国に戻りこの目で見たいものです。
緊急事態宣言の発令
 参議院決算委員にて安倍総理に消費税ゼロを緊急提言!(4月1日)
参議院決算委員にて安倍総理に消費税ゼロを緊急提言!(4月1日)
4月7日、ついに安倍総理から緊急事態の宣言が発令されました。これにより、東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県の知事は、住民に対して不要不急の外出自粛要請を法律に基づき正式に発することができるようになりました。この中で総理は、「日本は戦後最大の経済危機に直面している」との認識を示し、「国民の雇用と生活は断じて守り抜いていく」との決意を表明しました。また、「そのために事業規模108兆円の世界最大級の緊急経済対策を実施する」ことを併せて表明しました。
医療崩壊回避のためには、外出自粛もやむなし
昨年末に、中国の武漢で発生した新型コロナウィルスによる感染症は、本年になって一挙に世界中に伝染していきました。今やその感染の中心は、ヨーロッパやアメリカに移っています。 4月12日現在で、世界で160万人を超える人が感染し、既に、10万人以上が死亡しています。日本でも感染者数は7千人を超え死亡者数も100名を超えましたが、中国や欧米に比べるとまだギリギリのところで持ち堪えている状態です。
安倍総理は、「人と人との接触機会を最低7割、極力8割削減することができれば、2週間後には感染者数を減少に転じさせることができる」と述べ、国民への協力を要請しています。これ以上感染者数を増やせば、医療提供体制の崩壊を招くことになります。今回の総理の決断はやむを得ないものであると思います。
外出自粛と損失補償は一体として考えるべし
緊急事態宣言が出される前から、日本各地で自主的に外出自粛が実施されてきました。今回の緊急事態宣言においても、海外のような強力な強制力を持って国民に規制をするものではありません。いわゆる都市封鎖も行われません。しかし、日本においてはそうした法律の強制力はなくても、多くの人が外出自粛に協力してきました。このことは日本人の国民性とも言えるでしょう。しかしその結果、経済活動に制限がかかり、莫大な経済的損失が発生しています。特に、観光業や飲食業、イベント業などに関わる方々には壊滅的な打撃を与えているでしょう。
今回の緊急事態宣言により、映画館や劇場、百貨店などのような、多数の人が出入りする施設、店舗の使用制限や停止を知事が要請できることになります。このことにより、さらに大きな経済的損失が発生するでしょう。
こうしたことを受けて、全国知事会は、緊急対策本部を開き、国への緊急提言を決議しました。これは感染拡大防止の休業などで影響を受けた事業者への補償などを国に要請するというものですが、知事としては当然のことでしょう。
コロナショックはいわば天災です。この被害を食い止めるための方策は、今のところ行動自粛しかなく、国民の協力を求める以外ありません。従って、それに伴う損失を国が補償するのは自明の原理です。
まずは緊急融資が必要
 令和二年度の予算が成立し、安倍総理が議員会長室に挨拶にお見えになりました。
令和二年度の予算が成立し、安倍総理が議員会長室に挨拶にお見えになりました。
今回の緊急経済対策の中には、売上げが半減した中小企業に最大200万円、個人事業主には100万円、生活が困窮した世帯には30万円の給付なども掲げられています。しかし1番重要なのは、中小企業等に緊急融資を実施することです。無担保・無利子で5年間据え置きの事業用資金を直ちに融資する、このことが企業の倒産を防ぎ従業員の生活を守るために最も重要なことです。
一方で、融資よりも補償を求める声もあります。その気持ちは私も充分理解できます。しかし、現実に、営業の補償をしようとした場合には、様々な問題点も出てきます。まずは補償額の合理的な算定が非常に難しいと言うことです。自粛の影響で事実上売上げがゼロになったお店もたくさんあります。東京ではデパートも休業していますから、こうした事業の平時の売上げをそのまま補償するとしたら、莫大な金額が必要です。自粛期間中は、仕入れも停止していますから、粗利の補償だけでも良いと言う考えもあります。補償する対象と金額を算定するだけで、大変な時間を要してしまいます。その間に企業が倒産したら、全く意味のないことになります。
そこで、まずは企業を倒産させない。これを第一の目的にして、直ちに資金を提供することを最優先にしなければなりません。コロナショックの後、経済をV字回復させるためにも、今、雇用と企業の経営を絶対に守らなければならないのです。
日本政策金融公庫が中心となって、緊急融資を実施しています。これと同様の仕組みを民間の金融機関も利用できるようになります。是非、ご近所の金融機関にご相談ください。
返済できない場合はどうなるのか
それでも、融資には抵抗のある方がおられます。「今でも借金があるのに、これ以上借金を増やしてしまえば、結局返済できなくなり、経営は破綻する。」このような心配をしてる方も大勢おられるでしょう。
しかし、そのような心配は無用です。まずは、融資を受けてください。そして事業を継続し、家賃や給料を支払って下さい。そのことが経済の底抜けを止めてくれるのです。コロナショックは何年も続きません。必ず収束の時期が到来します。それまでの辛抱です。今回の緊急融資は、無担保・無利子で、5年間は返済据え置きです。安心して借りてください。
返済の時期が来た時、経済が順調で充分融資の返済できる状態なら、問題ありません。しかし、残念ながら、コロナショックの損失が大きくて、赤字が繰り越されて、返済能力が乏しい企業も存在することになるでしょう。この場合には、債務の返済の免除も当然あり得るはずです。
東日本大震災の時、二重債務は返済免除にした
今回の緊急融資は、東日本大震災の時の二重債務問題と非常によく似ています。あの時、大津波で多くの住宅や工場が押し流されました。事業や生活の再建をするために、残っていた借金に加え、住宅や工場を再建のための新たな借金を背負いこむ人も大勢存在したのです。
しかし、これでは生活の再建は不可能です。そこで、この問題を解決するために、事実上二重債務を国が肩代わりする仕組みを作ったのです。これは、当時自民党は野党でしたが、民主党政権に対して提案し実現したものです。
今回も、これと同じような仕組みを考えれば良いのです。事実、緊急融資は、コロナショックがなければ発生しなかったものです。国の自粛要請に従い、その結果、背負い込むことになった負債です。国がその責任を取るのは当然のことです。
本来は、国の自粛要請に従った損害は、国が直接補償すべきものです。しかし、先に述べたように、現実には中々その額を短期間で合理的に算定することは難しいのです。その補償に代わる方法として、まずは緊急融資を実施して倒産を防止する。その後の返済は、具体的な経営状況を見ながら、最終的には債務免除をする。これ以外、今回のコロナショックから国民生活を守る方法はありません。
いずれにしても、返済猶予は5年間ありますから、この間に必ず制度化させますのでご安心ください。そして、今回提案されている納税や社会保険料の支払いの猶予の制度についても、同様の措置が必要であると考えています。
消費税ゼロと公共事業は何故無いのか?
 国会議員全員に「コロナッショック緊急提言 MMT(現代貨幣論)ならそれが可能だ!!」を配布 ※HPからダウンロード可能です
国会議員全員に「コロナッショック緊急提言 MMT(現代貨幣論)ならそれが可能だ!!」を配布 ※HPからダウンロード可能です
今回の緊急経済対策は、108兆円の事業規模と言われていますが、その大半は緊急融資や納税猶予などの金融支援政策で、いわゆる真水と言われている財政出動額は19兆円程度です。これでは、コロナショックによる経済的損失を補填にするにはあまりにも乏しいと言わざるを得ません。
しかし、新型コロナの感染が収束するまでの間は、事実上経済活動が自粛されてしまうため、いくら真水を出してもそれを消費したり投資したりできる環境にありません。感染収束が確認され次第、第二の経済対策として、消費税ゼロや公共事業投資などの、需要や消費を直接伸ばすための予算を作成なければなりません。
財源はMMTを活用すれば全く問題なし
仮に、コロナショックでGDPの10%毀損されたとすると、60兆円近い真水が必要になります。さらに、緊急融資も最終的に債務免除にすることになると、その金額も赤字国債の発行になります。こうしたことを考えれば、事実上、一挙に100兆円近い国債を発行することになります。
緊急融資を返済免除にしたら、免除を受けた国民に政府からお金が支払われたことになります。それが給料や家賃となって第三者に支払われていくのですから、結局また国民にお金が支払われると言うことです。政府に国債と言う負債が発生するのは事実ですが、そのことによって国民サイドにお金が供給されるのです。
以上の様に、国債を新たに発行することによって、国民側にお金が供給されるのです。それは、税金を使って同じようなことをしようと思ってもできません。税は国民からお金を回収する仕組みだからです。お金を国民側に供給するには国債発行しか方法がないのです。
国債も負債である以上、返済しなければならないはずだと言う人がいます。それも間違っています。新規の国債発行が、国民側にお金を供給することなら、国債の償還は、国民側からお金を回収することになります。少なくともコロナショックで国民経済が瀕死の状態に陥っているときに、その国民が分からお金を回収すると言う事は、国民窮乏化政策以外何者でもありません。これがMMTから導き出される結論です。
経済がV字回復して、かなりのインフレ率になった時、国民側から資金お金を回収することを考えればいいのです。
瓦の独り言
-酒米のテロワール?-
「コロナが怖くて、カローラが乗れるか!」と息巻いていましたが「コロナ!クルナ」の心境に変わっています。 さて、前回の「瓦の独り言」で、酒造りで『選ばれものは「水」と「米」』の話をしましたが、今回は「米」、正しくは「酒米(酒造好適米)」について思うところを述べさせていただきます。
「山田錦で精米歩合が60%」の日本酒が一番おいしい、と思っておられる方々がなんと多いことか!昨今、日本酒が海外でも脚光を浴びて、ワインと同等に肩を並べています。しかし、ヨーロッパの方々(特にフランスの方)は日本人以上に舌の肥えた方がいらっしゃる。その彼らが「テロワール」という言葉をよく使います。フランスではワイン法(原産地統制名称法)のベースでブドウ畑の自然環境条件のことを言っているらしいのです。どうやら、フランスの方々は日本酒の重要なお米の育った環境を重視しているらしいのです。ところが、瓦は「山田錦」であればどこで採れても同じと思っていました。男爵イモも「北海道で採れようが、丹波で採れようが、同じではないか」といった感覚を持っていました。(味は違うはずだが・・・)
この酒米(炊飯して食べても決して美味しくない)の代表的な品種は10種類ほどですが、生産量の一番多いのが「山田錦」(推計3万5千トン)、で約60%が兵庫県で作られています。特に東条湖周辺のゴルフ場銀座付近が最上級の特A地区*に指定されています。ところが日本酒のラベルには「山田錦」と酒米の銘柄だけで、産地などの情報が書かれていません。(最近、書いておられる蔵元も出てきました) 特A地区の「山田錦」でも田んぼが変われば「酒の味」も変わるはず。取水する川の条件、収穫する年度の天候によっても「酒の味」が変わってあたりまえ。(ワインでは今年は当たり年なんて言ってますように)
さて、話を「テロワール」に戻しますが、「山田錦」の農家の顔が見えてくる酒造りに取り組んでいる蔵元が伏見に表れています。フランス人の「テロワール」に触発されて、蔵元の醸造技術はいくらでも研鑽できるが、原材料である「酒米」を他人まかせにしていたのではだめだと思い、自分から「酒米」造りにかかわっておられます。「精米歩合が60%の山田錦」で作った日本酒をブレンドして出荷するのではなく、酒米の個性に合わせた日本酒造りをしておられる。生産量は決して多くないが、繊細な京料理に相応しい個性あふれた日本酒が店頭に登場しようとしています。世界的なワインと肩を並べる、個性あふれる日本酒の登場を小躍りしているのは瓦だけではないはずです。
さて、政治の世界でも我が国の舵取りを任せている「自由民主党」にあって、酒米のテロワールの如く、個性を発揮していただいているのが、我らが京都から国会へお送りしている西田昌司参議院議員ではないか、と思っているのは瓦一人だけではないはずです。
(特A地区*に指定されている上東条地区は、瓦の母親の里で、瓦の農夫としての原体験はここから生まれています。)
預金は借金により増える
 自民党京都府連として門川大作氏への推薦を決定
自民党京都府連として門川大作氏への推薦を決定
MMTとは、端的に言うと「通貨(預金)は債務により生まれる」という事実に基いて、経済現象を説明したものです。それはまず、銀行預金が増える仕組みを考えれば分かります。銀行預金が増えるのは誰かが預金をするからだと考えがちですが、それは違います。手許の現金を預ければ確かに預金残高は増えますが、手許現金はその分減ります。現金と預金は基本的に同じものですから、銀行に現金を預けただけではその合計額は一円も増えないのです。これは理論では無く事実です。この事実を基に経済現象を考えてみましょう。
バブル時代の教訓
景気が良いとは世の中にお金が回っている状態のことです。「通貨(預金)は債務により生まれる」という事実を基に考えると、景気が良くなるためには誰かが借金をしてお金を使うことが必要なのです。これはバブル時代を思い出せば分かるでしょう。平成2年頃がバブルのピークでしたが、不動産を担保に借金をして株や土地に次々投資が行われました。当時、日本はアメリカを追い抜き世界一の経済大国になったと自惚れていました。
しかし、値上がりを続けていた不動産価格が下がり出すとバブル景気はあっけなく終わりました。不動産価格の下落により、返済不能の借入金が大量に発生したからです。銀行には多額の不良債権が発生し、これが社会問題となります。バブル後、しばらく塩漬けにされていた不良債権でしたが、 平成9年の北海道拓殖銀行の経営破綻を契機に一挙に顕在化することになります。
不良債権の損失計上にとどまらず、銀行は貸しはがしと呼ばれるほど厳しい債権回収を行いました。この結果、バブルのピークの頃、700兆円近くあった民間企業の借入金は、一気に200兆円近く減ることになります。これは、「通貨(預金)は債務により生まれる」の逆の現象が発生し、世の中から一挙に200兆円の預金が減ったことになるのです。この後日本は一気にデフレ化するのですが、その原因は200兆円の預金喪失にあるのは言うまでもありません。
国債発行による財政支出の意味
国債は政府の債務です。国債を発行して財政出動するということは、民間企業が借金をして投資や消費をするのと経済事象的には全く同じことです。 「通貨(預金)は債務により生まれる」この事実は当然国債にも当てはまります。政府の国債発行により民間の預金残高は増えることになります。
財務省に拠れば、国債残高は、2019年度末で897兆円となる見通しで、この額は一般会計税収の約15年分に相当し、国民1人当たりに換算すると713万円の借金を負っていることになると言います。超低金利政策によって金利は低く抑えられていますが、金利が上昇すれば利払い費が重くのしかかると、彼らは国民を脅し続けています。
しかし、この意見は全く的外れです。何故なら、政府債務が897兆円あるのは事実ですが、それと同時に民間預金が897兆円供給されていると言う事実を彼らは無視しているからです。財政再建派はこの事実が理解できていないのです。
国債を全額償還すれば国民は貧困化する

彼らの弁に従えば、いつかは国民から増税をして897兆円の資産を国民から徴収しなければならないことになります。しかし、もしこうしたことを実行したら経済は大パニックに陥るのは明らかでしょう。政府は国債という債務がなくなりますが、国民は897兆円の資産を奪われ、生活は困窮するのは明らかです。政府の債務は消えても国民は塗炭の苦しみを味わうことになります。
また、実際に国債を保有しているのは日銀と民間銀行ですが、約450兆円の国債を保有している日銀は、国債保有残高がゼロに成ります。代わりに約450兆円の日銀にとっては負債としての当座預金が減額されることになります。これは、日銀の通貨発行額が減額したという意味です。民間銀行が保有していた国債残高はゼロになり、日銀当座預金がその分増加します。国債残高の10%前後は外国人が保有していますが、彼らには国債の代わりに円建の預金が振り込まれます。
国債を保有していた銀行や外国人によっては、デフォルトの心配の無い安全な投資の機会を奪われ、代わりに金利の付かない預金と交換されてしまうことになるのです。これでは、銀行の安定経営にも支障がでます。
結局、政府の負債はゼロになってもその分国民の資産がなくなるのですから、国民が貧困化するのは必定です。つまりは、国債が償還された分だけ、国民が保有していた預金通貨が消滅することになるのです。財政再建のためだと国債残高を削減すれば、必ず、国民の預金残高も同じ額だけ減少するのです。
国債が増えれば預金が増え、逆に、国債が減れば預金も減る、これは理屈ではなく事実なのです。これを理解していれば、少なくとも景気が悪い時に財政再建だと言って国債を減らすような事はしてはならない、全くの愚策だと分かるはずです。
戦後の財産税課税は究極の国民窮乏化政策
実は、国債を全額増税で償還するという究極の窮乏化政策が実施されたことがあるのです。それは昭和21年に実施された財産税課税です。終戦当時、政府には国民所得の250%近い国債残高があったと言われています。
終戦直後に、日本はいわゆるハイパーインフレに襲われ物価が暴騰するわけですが、その原因は、戦費調達にための国債乱発による通貨供給超過が原因だと言うことが一般的には言われています。
しかし、真の原因は戦争による生産設備の喪失による供給力不足とや復員による急激な人口増加による需要急増であることは、前回述べた通りです。当時はこのことを無視して財産税が課され、国債は全て償還されたのです。インフレ対策として財産税課税がされたと言われていますが、これが全くの愚策である事は論をまたないでしょう。
財産税は、戦争利得者からの財産没収が目的だとも言われていますが、この裏にはGHQによる日本に対する徹底的懲罰指令があったことは間違い無いでしょう。経済状況を無視した国債償還は国民窮乏化政策でしかありません。昭和25年の朝鮮戦争までの時代は、アメリカは日本に懲罰を与えることを占領目的としていましたから、こうした政策がとられたのでしょう。
戦後79年経ちました。デフレでもなお国債残高を減らすべきだと言う財政再建至上主義者は、戦後の財産税が何をもたらしたのか、もう一度しっかり検証すべきなのです。
消費増税と法人税減税、所得税の累進課税緩和がデフレを加速
また、デフレを加速させた実質給料減額の原因も考えておく必要が有ります。私は、4つの要因があると考えています。
1つ目は、消費税の実施によるものです。消費税では、給与は仕入れ税額控除の対象になりませんが、外注費は仕入れ税額控除の対象になります。消費税においては、給与を支払うより外注費にする方が、納税額は少なくなるのです。
2つ目は、バブル崩壊後の企業のリストラによる給与のアウトソーシング化が進んだことです。これにより給与を固定費から変動費に置き換えることができ、企業は安定した利益を上げることができるようになりました。
3つ目は、経営者に成果報酬を認めるビジネスモデルが普及したことです。利益を出した経営者には、その分の報酬を上乗せすることが当然の権利の様に認められる仕組みが定着したのです。
4つ目は、所得税の累進構造の緩和です。かつては住民税を合わせれば、2,000万円を超えれば 6割を超え、8,000万円を超えれば9割近い額が課税されていました。そのため高額報酬をもらっても手取り額は殆ど増えなかったのです。その結果、経営者も高い報酬を望まなかったのです。広く薄く課税するという消費税の導入により、累進課税は年々緩和され、現在では最高税率は住民税を合わせても55%になっています。このため、高額報酬をもらっても半分近くは手許に残すことが可能になり、経営者の報酬を上げるインセンティブが増加したのです。
こうした税制の変更により、ビジネスモデルは一変したのです。成果報酬が認められるようになると、企業は給料をアウトソーシング化することにより、利益を上げることができ、それにより、経営者はより多くの報酬を得ることが可能になったのです。また、アウトソーシングにより給料は外注費に変わり、消費税額を少なく抑えることが可能になりました。一方アウトソーシングを受注した企業は、必然的に社員の給料を安く抑えなければ経営が成り立たちません。
この結果、一部の経営者が多額の役員報酬がもらう一方で、多くのサラリーマンの給料が安く抑えられる結果となったのです。これが国民消費を抑え経済をデフレ化させる根本原因を作っています。企業業績が良いにもかかわらず経済がデフレ化するのは、ここに問題があるのです。
また、企業の投資を増やすために法人税を減額し可処分所得を増やす政策が取られました。しかし結果は、全く逆のことになりました。住民税や事業税を合わせれば、かつては5割を超える実効税率がありました。そのため、税金を取られるくらいなら、従業員に給料ボーナスを払ったり、新しい車を買ったりするケースがよくありました。決算対策として、どこの企業でもこうしたことをしていたのです。
ところが法人税を下げ、実効税率が3割程度になると、あえて決算対策をする企業はほとんどなくなりました。従業員のボーナスも増えず投資もしない、その結果、内部留保が積み上がり、上場企業だけでその額は446兆円(2017年)に上ります。私は当初から、法人税を下げればこうしたことになると、党の税制調査会の役員会でも法人税減税を反対し警告を発していましたが、正にその通りになったのです。
政府の負債が増え、その分の預金資産を国民に供給しているにもかかわらず景気が良くならないのは、こうした税制とビジネスモデルにも原因があります。デフレからの脱却のためには、平成30年間の税制や財政を根本的に見直す必要があるのです。
 「故郷を支援する参議院の会」での取りまとめを世耕参院幹事長とともに安倍総理に届けました
「故郷を支援する参議院の会」での取りまとめを世耕参院幹事長とともに安倍総理に届けました
瓦の独り言
-新年のお屠蘇は「女酒」?「男酒」?-
羅城門の瓦
新年、明けましておめでとうございます。皆様方には令和の新春を日本酒でお祝いされていることと思います。 そのお酒は「女酒」or「男酒」? 何の話かと言えば、伏見の日本酒を「女酒」、灘(兵庫県)の日本酒を「男酒」と称して甘口だの、辛口だのと吞み助は言っています。この違いは、酒造りに用いる醸造用水によります。
伏見のお酒は、カルシウムやマグネシウムなどのミネラル成分が少ない「軟水」を使っており、比較的長い時間をかけて発酵させます。それゆえ、酸味は少なく、なめらかで、きめ細かい淡麗な味を生み出してきました。一方、灘のお酒は酵母(酒造りの原料)の栄養となるミネラル成分が多い「硬水」を使っており、発酵期間が短く、やや酸味の多い辛口のお酒になります。
現在では醸造技術が発達し、「軟水」「硬水」のいずれを用いても甘口、辛口のお酒が造り分けられますが、伏見の日本酒は「宮廷料理から発展し、進化した京料理に合う酒」として洗練されてきました。一方、灘の酒は江戸の人々の好み、武士の気質に合う「江戸の下り酒」として重宝され、江戸将軍の「御膳酒」は「剣菱」だったとか。
さて、酒造りの味を左右する「軟水」「硬水」の話ですが、水1ℓ中のミネラル成分(カルシウム、マグネシウム)の量を「硬度」と称して(JIS規定)「軟水」は(硬度0~60mg/ℓ)「中軟水」は(61mg/ℓ~120mg/ℓ)「硬水」(121mg/ℓ~180mg/ℓ)とされています。ちなみにミネラルウォーターのエビアンの「硬度」は304mg/ℓです。水による「硬度」の差は地下水が通る地層の違いによります。伏見の地層は花崗岩でできており、この層を桃山丘陵に降った雨水がゆっくりと西へ流れていき(中には60年もかけて井戸に来ている水脈もあるとか)、程よくミネラル成分が溶け出します。一方、灘の「宮水」は地層に貝殻層(目の前が海)があるのでカルシウムなどが溶け出して、比較的硬度が高い水になるといわれています。また、伏見の地下水は酒造りの天敵である鉄分がゼロかもしくは微量です。酒造りの用具にも酒がふれる箇所には鉄製品は使わないようにしておられます。
伏見の各酒蔵(現在は22社:城陽市含)は独自の酒醸造用の井戸を持っておられ、中でも伏見の名水めぐりは観光スポットとなっています。瓦は伏見の名水めぐりをしたことがありませんが、酒蔵見学の都度に、各蔵の醸造用の井戸水をいただいております。その時に、京都盆地の地下には「京都水盆」と呼ばれ琵琶湖に匹敵するほどの大きな水がめ存在している話が出てきます。しかし、酒造りにはその水を当てにしてはダメで、各蔵が自社の井戸を守ることが使命であり、またその井戸水を酒造りに生かすのも杜氏の使命と聞かされました。酒造りで『選ばれものは「水」と「米」』、とある杜氏が言っておられました。水を大切にしておられる言葉と、お米へのこだわりがひしひしと瓦に伝わってきました。(お米については紙面の都合で後日談にします。)
さて、政治の世界でも『選ばれものは西田昌司参議院議員』と思っているのはお屠蘇を飲みすぎた瓦だけではないと思います。
(瓦の独り言の参考文献:伏見酒造組合25年史・日本醸造協会誌(産技研蔵)など)
地球温暖化により台風被害が増加
 東京税理士政治連盟にて講演「MMTから見る日本経済の未来」について講演いたしました
東京税理士政治連盟にて講演「MMTから見る日本経済の未来」について講演いたしました
今年は、9月に台風15号が猛威をふるい房総半島に大きな被害が出ましたが、その直後の10月12日には、史上最大級の大型台風19号が伊豆半島に上陸し、関東から甲信越、東北と、東日本の大きな範囲で洪水の被害が出ました。
このような大型台風などによる豪雨災害の頻発の原因は、地球温暖化にあると言われています。20世紀後半から人類が化石燃料を大量に消費しだしたため、温室効果ガスとも言われる二酸化炭素の空気中の濃度が上昇し、それにより大気温が毎年少しずつ上昇し、日本近海の海水温も平年より高くなっています。その結果、海水から大量の水蒸気が大気中に供給され、台風が大型化し勢力を維持したまま日本を襲うようになり、また、豪雨が続いたりする様になったのだと言われています。
地球環境問題の解決には長期間を要する
地球温暖化による気候変動を食い止めるために、当初は化石燃料を使用しないクリーンなエネルギーとして、原子力発電が期待されていたのですが、福島第一原発の事故により、脱原発を叫ぶ人も増えています。
太陽光等の自然エネルギーに期待がかけられていますが、少なくともあと数十年は原子力エネルギー無しでは安定した電力供給はできません。台風被害で停電になり、冷房のない中熱帯夜を過ごされた千葉県民の方々の避難生活を見ても分かる様に、文明社会に慣れた我々には、1日たりとも電気無しでの生活などできないのです。
今直ちに原子力発電所を止めてしまえば、その分化石燃料による発電が増えますが、それ以前に、供給能力不足で電力供給の不安定化が露呈し、産業界だけでなく、私たちの生活の面においても大きな被害を受けることになります。現実的な議論が必要です。
新自由主義がインフラ整備を遅らせた
電力の安定供給のためには、供給能力の安定化とともに送電網の高度な充実が必要です。1つの送電線が倒木等により破損しても、別のルートで送れるネットワークを作っておく必要があります。また、送電線を地中化することにより、台風でも電柱が倒れない仕組みも大切です。
しかし、こうしたインフラの整備は、災害のない時代には、余計なコストと敬遠されてきました。特に電力の自由化が実施され、電力会社以外の企業との競争が激化すると発電コストを下げることばかりに視線が移りがちになります。その結果、安定した電力供給に不可欠な送電網の充実と言うインフラの整備が疎かになってきたのではないでしょうか。
これは私が常に批判し続けてきた新自由主義政策のもたらした結果ですが、大いに反省し検証しなければなりません。
八ッ場ダム(やんば)が水害から救った
 自民党京都府連として菅官房長官に京都アニメーション放火事件に対する緊急要望をいたしました
自民党京都府連として菅官房長官に京都アニメーション放火事件に対する緊急要望をいたしました
こうした中、上毛新聞に以下の記事が記載されました。
〈国土交通省八ツ場ダム工事事務所は13日、台風19号による大雨で試験湛水中の八ツ場ダム(長野原町)の水位が急上昇して満水位(標高583メートル)に近づいたため、同日午後4時から放流を実施した。今月1日の試験湛水開始から3、4カ月かけて満水にする計画だった。11日午前2時に518.8メートルだった水位は、13日午後2時半には約59メートル上昇して577.5メートルになった。
「この水が流れたらどうなっていたのか」。一夜で満水近くになったダム。会員制交流サイト(SNS)では下流域での水害防止に一役買ったのでは、と話題になった。〉
八ッ場ダムは、「コンクリートから人へ」という民主党政権の目玉政策として工事が中断されたのですが、もし八ッ場ダムが無かったら下流の地域は水没し、大惨事になっていたのではないか、と多くの住民の方は思っているのです。
かつての様なインフラ不要論は、国民の間では殆ど聞かれません。むしろ、早く自分の地域のインフラを整備して欲しい、と多くの国民は思い直しているのです。
それでもインフラの整備を批判する日経新聞
ところが、依然として公共工事不要論は根深く存在しています。日経電子版は次のように報じています。
〈堤防の増強が議論になるだろうが、公共工事の安易な積み増しは慎むべきだ。台風の強大化や豪雨の頻発は地球温暖化との関連が疑われ、堤防をかさ上げしても水害を防げる保証はない。人口減少が続くなか、費用対効果の面でも疑問が多い。
西日本豪雨を受け、中央防災会議の有識者会議がまとめた報告は、行政主導の対策はハード・ソフト両面で限界があるとし、「自らの命は自ら守る意識を持つべきだ」と発想の転換を促した。〉
相変わらずの経済合理性と自己責任論に終始しているのです。勿論、インフラ整備はその時の社会の状況に応じて現実的な対応をしなければなりませんが、少なくとも日本の様な先進国で国民を見捨てる様な発想はモラルとしてもあり得ません。
こうした議論の背景には、一部の住民のためにインフラ整備を続ければ日本は本当に財政破綻してしまう、そうなれば国家が破綻し、多くの国民が迷惑をすると思い込みがある様です。しかしこれこそ、同胞意識の無い利己主義そのものです。
こうした議論が今なお絶えないのは、公共事業などによる国債の残高の増加が国家財政を破綻させる、と言う思い込みがあまりにも強いことが原因です。
今こそMMT(現代貨幣論)を学ぶべき
MMTは、「貨幣は負債と共に発生する」という事実に基づいて経済現象を再定義することにより、今まで見えていなかった現実をあぶり出しました。
貨幣の供給とは、銀行が与信してお金を貸すことです。これは、日銀も認めている事実です。借入金(負債)を背負う代わりに預金(資産)が手に入るのです。逆に借入金(負債)を返済すれば預金(資産)は減少するのです。したがって預金の量は借入金の量に比例します。借入金が増える度に預金は増えるのです。
銀行は無から信用供与することにより、返済不能にならない限り無限に貸し出すことができるのです。銀行与信の限界は、返済不能な額まで貸し出せばそれが不良債権となり、銀行自体が破綻する恐れがあることです。
一方で、政府の国債発行による財政出動も、政府が国債(負債)を持つことにより国民にその対価として預金(資産)を与えるものです。これも日銀が認めている事実です。実はこれが、政府による通貨発行そのものなのです。政府に通貨発行権があるということを多くの国民は知っていますが、それが具体的に何を意味するかは殆どの人が理解していません。
政府の通貨発行権行使とは、政府が国債(負債)を持つことにより国民側に預金(資産)を与えることなのです。銀行の与信行為と本質的に同じことなのです。
信用創造の無理解が新自由主義を蔓延させた
 西田昌司 経世済民塾『ガルーダベース』を発足していただきました
西田昌司 経世済民塾『ガルーダベース』を発足していただきました
銀行からの借入金は返済するには返済原資としての預金が必要です。事業が失敗すれば預金を回収出来ず銀行に返済できません。これが不良債権です。銀行はそうした事態にならない様に慎重に審査しなければなりません。またそういう事態に陥らない様に、借り入れをする側もデフレのような景気の悪い状態では借り入れをしません。
ところが政府は、国債を返済する時も国債の借り換えで済ますことができ、返済のための通貨を回収する必要がありません。つまり政府は支払い不能に陥ることが無いと言うことです。このことは財務省も認めている事実です。つまり、政府は国債の返済ができずに財政破綻になると言う事は理屈の上でも現実にも有り得ないのです。
ところがこの30年、民間と政府の信用創造の仕組みの違いを全く理解せずに、バブル後のリストラをしている民間にならって、政府も負債を減らすべきだと言う財政再建論があまりにも幅を利かしてしまったのです。これが、新自由主義が跋扈した根本原因で有り、それが日本を構造的デフレ社会にしてしまったのです。
税金は必要、国債発行はインフレ率で調整
MMTは、政府が財政破綻になる事は無いと主張していますが、無限に国債を発行できるとは言っていません。国債発行により国民側に通貨供給をすれば、基本的にはインフレになります。そのインフレ率が高くなり過ぎない様にコントロールすべきだと言っているのです。何%のインフレ率が良いかはその国の状況によるでしょう。かつての日本は高度経済成長の時代には2桁近いインフレ率がありました。しかし今の日本のように成熟した国にはそんな高いインフレ率は必要ありません。3〜4%で十分です。
また、MMTが正しいのなら、税金無しでも国債発行だけで予算が賄えるではないかと言うのも暴論です。税金をなくしたら国家は国債発行で通貨供給はできても回収ができず、インフレをコントロールできません。インフレのコントロールのために税金は必要なのです。また税金がなければ、国民側の資産格差に歯止めがかからず社会が不安定になります。社会の安定のためにも税金は必要なのです。
戦後のハイパーインフレは事実誤認
MMTを理解していない人は、「インフレ率はコントロールできない」「通貨の信認を失ったら戦後の日本の様なハイパーインフレが起きる」と言います。しかし、これは事実誤認です。
そもそも日本はデフレで困っています。2%のインフレ目標でさえ日銀の金融緩和だけでは達成できていません。今こそ財政出動が必要なのです。昭和30年代には2桁近いインフレ率またそれに近い利子率だったのを現在のような低金利にしたのは、政府と日銀の財政金融政策だったはずです。バブルを作り、金融引き締めでバブルを退治し、それをやりすぎて極端なデフレにしたのも金融政策です。見事にインフレ率をコントロールしているのです。
また、戦後のハイパーインフレは、国債発行が過ぎたのが原因ではありません。終戦直前の空襲によるインフラの徹底的破壊が生産能力を極端に低下させ、一方で終戦による外地からの復員による人口増加が需要を増やし、その極端な乖離がハイパーインフレをもたらしたのです。現に戦時中にはハイパーインフレは起こっていません。今一度、戦後のハイパーインフレの原因は何だったのか検証すべきです。
樋のひと雫
羅生門の樋
もう3年が経とうとしているのに、ベネズエラの経済破綻はその出口すらも見えません。国を離れた市民は420~450万人とも伝えられています。推定人口が2800万人程ですから、その約七分の一が国を捨てたことになります。米国の肝いりで用意された国際援助の食糧も、その後どうなったのか判然としません。また、マドゥーロに敢然と反旗を翻し、欧米諸国から多くの支持を得たグアイド国会議長も、救国の騎士を気取った割には国民の支持が今一つです。こちらのマスコミも彼の周辺情報を伝えなくなりました。かつてボ国の行政官とグアイドの話になった時に、彼は「どちらも、どちらだ。」と吐き捨てるように言いました。その時は、中南米を裏庭支配する米国へのアレルギーかと思ったのですが、今となっては、さすが民情に通じていると感じます。欧米のマスコミが、国内でNOと言える中間層が国を捨てたために、世論形成に不都合が生じているのではと書いていましたが、それだけでは反対勢力が伸びない理由としては納得できません。
しかし、内戦でもない国で400万もの人間が逃げ出すという状況は、我々には想像すら困難なことです。例え、この数値が推計であったとしてもです。また、この国の経済破綻とそれに伴う飢餓が、たった一人の人間の無能力と権力欲によって引き起こされたという事実は、何か中世社会に生きているのではと錯覚させる悪夢のようにも思います。そして、容易に国を捨て近隣国に去るというボーダーの低さにも驚きを感じます。スペインの植民地支配の歴史を共有し、スペイン語という共通の言語を持っている。特に南米では、ベネズエラの英雄S・ボリーバルと共に独立戦争を闘ったという経験を共有しているとしてもです。
最近公園近くのカフェで、ベネズエラの若者が話しかけてきました。異国の人間に話すことで、少しでも肩の荷を軽く感じることが出来るのでしょう。国の話や残った家族の様子、自分が働いていた商店や街の様子など、取り留めのない会話を1時間程しました。最後に「今の国には住めない。帰るかどうかも判らない。」と話して別れました。別れた後にも、「お前にとって、国とは何か」と彼が問い掛けているように思いました。
「国」とは自分にとって、古里であり山川であり、祖の眠る地である。謂わば、内に在る歴史であり文化であり、生きている基盤ともいえるものです。更に「国家」とは明日の安心と今日の安全をもたらし、自らに庇護を与える、人と共生するための構造であると。そして、国と国家は一体不可分な関係にあるものと信じてきました。先の若者は国家の統治機構が崩壊した中で、国をも離れました。
国家が民を養うことが出来ず、その統治能力を失った時、自分はどのような道を選ぶのだろうか。何十年も前、若い頃に読んだ句がふと頭に浮かびました。しかも読んだ当時とは違った感慨を伴って。
「マッチ擦る つかのま海に霧ふかし 身捨つるほどの祖国はありや」(寺山修司)
人が国を捨てる際の感情とは、その覚悟とは…。果たして、自分には出来るだろうか…と。
421,731票(世に居なさい)を獲得
 三期目の当選を祝して万歳三唱
三期目の当選を祝して万歳三唱
この度皆様の御支援のお陰で、三期目の当選を果たすことができました。全行政区でトップの得票をいただき、合計421,731票を獲得することができました。心から御礼申し上げます。また、421,731は世に居なさいと読めます。これを神の啓示と思い、皆様のご期待に応えるために全力で働くことをお誓い申し上げます。
経世済民とは
私は、今回の選挙で「経世済民」ということを終始訴えてきました。「経世済民」とは世を経(おさ)め民を済(すく)うという意味です。福沢諭吉がエコノミクスという英語をその頭の二文字をとって経済と訳したのです。経済という言葉は、現代ではお金儲けという意味合いで使う人がいますが、本来の意味は、世の中が安定し誰もが幸せを実感できることが大切だ、ということです。
そういう意味で現代社会を顧みれば、東京一極集中と地方の疲弊や、空前の利益を大企業が上げる一方で国民の実質給与が下がるなど、所得の偏りが目立ちます。民主党政権時代の様な極端なデフレ不況からは脱出したものの、国民経済にはまだ課題が残っているのも事実です。
新自由主義が日本をデフレ化
この様な富の偏在の原因は、新自由主義による経済政策が行われたことにあります。バブル崩壊後、本来は政府が積極的に財政出動をして景気を立て直す必要があったにもかかわらず、逆に公共事業費などの予算を削減しました。その当時は、民間がリストラをして借金返済している時に、政府ばかりが国債を発行して予算を拡大するのはおかしいという誤った声が高まり、小さな政府を目指さざるを得ない状況にあったからです。
民間企業の方が政府より効率的な経営をしているはずだから、民営化できるものは出来るだけ民営化する方が良い。また、民間企業が投資しやすい様に規制を緩和する。そうすれば政府が予算を使わなくとも民間活力の活用により景気は回復する。こうした政策の典型が東京駅の再開発による高層ビル群の出現です。
規制緩和が招いた東京一極集中
東京駅周辺の容積率や高さ制限を撤廃した結果、ここでも高層ビルの建築が可能になりました。交通インフラの揃っている場所で規制緩和すれば、政府は一円の予算も使わずに駅前の再開発ができました。しかし、これにより雇用が地方から吸い上げられますから、地方の人口は減少します。
東京に人口は益々集中しますが、ここには子育て環境が整っていません。否、元々は整っていたのですが、規制緩和でタワーマンションが一棟建てば、それだけで千人単位の人口が増えます。そうなればたちまち待機児童が何十人も発生します。保育施設をいくら作っても、マンションが建つ度に待機児童は増え、イタチごっこになっています。規制緩和により屋上屋を重ねる様な、意味の無い投資が東京では進んでいます。
地方の衰退
 府内各所で多くの皆様のご支援を頂戴いたしました。誠にありがとうございました。
府内各所で多くの皆様のご支援を頂戴いたしました。誠にありがとうございました。
行政の効率化の名の下で、地方ではこの20年間に320万人いた地方公務員が270万人に削減されました。一方で非正規職員は60万人も増加しています。これでは正規から非正規に雇用が移っただけで、事実上の賃下げです。こうしたことから、地方では経済的理由により結婚したくてもできない、子どもを作りたくても作れないと言う人が大勢います。
規制緩和と行政の効率化という新自由主義に基づく政策が、東京一極集中と地方の衰退を産み出し、東京においても地方においても、子どもが作れないのです。これが少子化の最大の原因だと、私は思っています。
正に、効率化を重視した新自由主義の政策が、次の時代を担う命が生まれない世の中にしてしまったのです。そしてこのことが将来に不安を生み出し、デフレ化を促進しています。
次世代に希望をもたらすMMT
私は、選挙を通じて、この様な将来不安やそれに伴うデフレ化から脱却するには根本的発想の転換が必要だと述べてきました。そして、そのための手段としてMMT(現代貨幣理論)を主張してきました。
MMTは、国債発行が民間貯蓄によって買い支えられているので無く、国債発行は民間貯蓄を増加させるものであるという事実を示したものです。これは、コペルニクス的転回です。今まで、財政再建が叫ばれていたのは、国債発行により子や孫の時代に借金を残すなという趣旨からでしたが、現実には借金ではなくて資産を残してきたのです。
新自由主義政策が跋扈(ばっこ)してきたのには不良債権処理、即ち、債務の縮小が急務とされた時代背景があります。確かに、あの時期、バブル期に膨らんだ借入金を整理して身綺麗になることが民間企業の再生には必要でした。それと同じことを政府にも求めたことが、赤字国債の整理をして財政再建を促すことに拍車を掛けたのです。
国債は返済不要
国債が民間貯蓄を増やすものであるなら、国債の償還は民間貯蓄を減らすことになります。例えば、国債発行残高は1000兆円と言われますが、それをどうしても返済するなら増税して1000兆円を民間から回収すれば良いのです。そうすれば政府の借金は無くなり財政は健全化しますが、民間貯蓄は1000兆円減ることになります。これでは、国民は貧困化し経済が大混乱することは、誰の目にも明らかでしょう。
一旦発行した国債は償還すれば必ず国民は貧困化するのです。一度に償還しないで長期間、例えば10年20年でも答えは同じです。民間貯蓄が国債償還分だけ減少することに変わりはありません。これでは政府は財政健全化しても国民経済は貧困化し破綻してしまいます。
税金の範囲内で予算を組むことは間違い
税収の範囲内で支出を抑えること(PB:プライマリーバランスの黒字化)を財務省は財政健全化の目標にしてきましたが、これは全くナンセンスなものだったのです。何故なら、予算を半減すればPBはたちどころに黒字化しますが、それでは必要な予算を支出できず、国家の責務を果たせません。また、大幅な増税をすればPB黒字化は果たせますが、これでは経済が破綻します。一見正しそうに見えますが、その意味するところを突き詰めて考えれば、国債の償還と同じく、経済そのものを破綻させるものなのです。
税金の範囲内で予算を賄うことを考えると経済が破綻するのです。何故こうしたことになるのでしょうか。それは経済活動の元となる通貨量は需要の多寡によって供給されるべきものだからです。
MMTでは、通貨の大宗を占める銀行預金は銀行の貸し出しによって創出されるという事実を重視しています。資金需要に応じて銀行が貸し出しすることが、経済を成長させる鍵となるのです。
デフレでは銀行は貸し出しできない
 「現代貨幣理論(MMT)」の第一人者である米ニューヨーク州立大学のステファニー・ケルトン教授との意見交換会
「現代貨幣理論(MMT)」の第一人者である米ニューヨーク州立大学のステファニー・ケルトン教授との意見交換会
デフレとは物価が継続して下落し続ける状態です。単価が下がるため同じ数量では売上が減り続けることになり、借入金の返済が出来なくなることを恐れ、企業は低金利でも借り入れをしません。この様にデフレでは消費や投資を控えるため、景気は益々悪くなるのです。
だからこそ、政府の国債による財政出動が必要になるのです。国債は返済不要だからデフレのリスクを気にせずインフレに戻るまで財政出動することができるのです。
ところが、国債を民間企業の借入金と同じ様に財務省は考えてしまい、大胆な財政出動を抑えているのです。これが、真のデフレ脱却ができない理由なのです。
日銀の国債保有は事実上の国債償還
増税により国債償還することがいかに国民経済を貧困化させることになるかは、お分りいただけたでしょう。国民経済を貧困化させずに国債償還させる方法があります。それは、日銀が国債を民間銀行から買い入れすることです。日銀が国債を保有することは政府が保有していることと事実上同じですから、その時点で国債は償還されたことになります。民間銀行から国債を買い入ると、民間銀行には日銀当座預金が提供されます。日銀は無制限に当座預金を提供できますから、国債も無制限に買い入れできるのです。
しかし、金利が低い時は良いが高くなると利払い費が嵩み財政に影響があるのではと、心配される方がいますが、それも心配無用です。
何故なら、日銀に支払った利息は日銀の利益になりますから日銀法の規定により、剰余金として、事実上全額国庫に納付されることになります。また、民間銀行が持っている国債の利息は、銀行の利益になりますから法人税等が課税され事実上半額は政府に納付されます。
国債の約4割強を日銀が保有し、1割を海外投資家、残りは民間銀行等ですから、利息の大部分は国内に支払われ、その大部分が政府に納付されるのですから、政府の財政には全く影響は無いのです。
国債残高ではなくインフレ率を指標にすべき
国債の残高がGDPの何倍かということは問題ではありません。円建てで国債を発行している限り、いくらでも日銀が買い入れできますから、返済不能などは起こり得ないのです。問題は国債発行して予算を伸ばせば、その分確実に国民サイドに所得や貯蓄を提供していますから、インフレになるリスクがあるということです。
確かに、今の国債残高を倍増する程の財政出動をすれば、高インフレになるでしょう。しかしながら、私の主張は全国の新幹線で30兆円、国土強靭化などを合わせても、高々100~150兆円です。これを10~15年で実行せよということですから、毎年の予算を10兆円程度、10年~15年の間、増額するだけです。日本のGDPは約540兆円ですからその2%程度の歳出増加です。これでハイパーインフレなどになる筈がありません。
家計や企業の借入金と国債を混同して、財政再建至上主義に走る財務省の目を覚まさせることが、三期目の私の使命です。
瓦の独り言
-ほとけさんも東京へ出張?-
羅生門の瓦
6月の初旬、気持ちのいい朝なので、東寺さんの境内を歩きました。修学旅行生らしきグループが講堂の中へ入って、すぐに出てきました。「仏さんが、東京へ出張中や。」との声。瓦も気になって、講堂へ入ってみたら、なんと立体曼荼羅(瓦もよく理解できていませんが)を構成している21体のうち15体が東京国立博物館へ出張しておられました。
立体曼荼羅は、あの薄暗い講堂の中へ入ってこそ、何とも言えない、秘密めいた(真言密教だから?)、ため息の出る空間でしか体験できるものではないでしょうか。東京国立博物館の中であの薄暗い講堂の空気が感じられるのか疑問です。
そういえば、昨年も仁和寺さんの仏さんが東博(東京国立博物館の略)へ出張されていたことを思い出しました。 両寺院とも、大伽藍を構えたお寺で、仏さんが多少、出張されていても社寺の運営に影響がないのでしょう。でも、信仰心に対する影響は?毎日、拝んでおられる信仰心の熱い人にとっては? 本来、仏さんは、その場所で、あるがままに拝んでこそ意味があるのでは、と変な理屈をつけているのは、瓦だけでしょうか?
でも、東博のパンフレットからは仏像彫刻のすばらしさを推奨するような空気が感じられました。そうか!博物館は美術工芸品を展示して、そのすばらしさ、美的感覚を堪能してもらう施設なのだ。だから、東寺の仏さんも「仏像彫刻」のすばらしさを東京の人々に知ってもらうために、出張しておられるのだ。 ・・・何か、この話にしっくりこないのは瓦だけでしょうか? 東博の学芸員の方によると、立体曼荼羅の仏さんが寺外へ出るのは困難とされていたが、1971年に2体が初めて東博へ、1995年には4体が、2011年には8体が、そして今回の2019年に15体が展示されました。
仏像彫刻は美術工芸品である前に、人々の「祈り」と信仰の対象であるべきものでは?それは東寺の仏さんのように1200年もの長きに渡り、人々の「祈り」の対象であったはずです。東寺の講堂の中で1200年もの長き祈りが、日本人の文化・風土を作り上げたのではないでしょうか?また「祈り」により、人々に明日への希望を与え続けてくれたはずです。(名物の美味しい食べ物はその土地で食べてこそ、美味しいのです。)
真言密教の「真髄」を感じようとすれば、京都の東寺へきて拝観(祈りの場には使いたくない言葉ですが)してこそ感じられるのではないでしょうか?
誰もが未来に夢を感じられる政策を実行していただける、西田昌司参議院議員も瓦の意見に賛同していただけるものと思っています。
(三期目、トップ当選!おめでとうございます。)
世界で話題のMMTとは?
 参議院決算委員会での安倍総理への質問
参議院決算委員会での安倍総理への質問
MMT(modern monetary theory 現代金融論)が今、世界で注目されています。元々は、トランプ大統領と大統領選を競った民主党の大統領候補サンダース氏が、自らの経済政策の柱として訴えたことが端緒です。MMTの最大の特徴は、貨幣の本質を金貨のようなモノではなく、銀行による信用創造だとすることです。
確かに、貨幣には金貨などが使われており、紙幣が流通するようになっても、金と交換できる兌換紙幣として使われていました。しかし、ドルが金との交換を止めてから、もはや世界中に兌換紙幣はありません。金の保有量とは無関係に、中央銀行の管理の下、紙幣は発行されています。紙幣自体には何の値打ちもありませんが、国家がこれを税金の支払い等の手段として認め、強制的に流通させることによって、支払い手段としての価値を持つようになっているのです。
銀行預金は借金する程増える
ところで、現実の取引で支払い手段として使われるものは、紙幣などの現金ではなくて、圧倒的多数が銀行預金による口座振替です。つまり、銀行預金が使われている貨幣の大部分を占めているのです。
では、銀行預金はどのようにして増えるのでしょうか。普通に考えれば、皆さんが銀行に現金を預けることによって、銀行預金が増えると思うでしょう。もちろんそのようにしても銀行預金は増えますが、預金が増える理由のほとんどは、銀行の融資によるものです。
銀行が融資することを信用創造といいます。銀行が借り手に信用を与える(与信)ことにより、借り手の口座の預金残高が増えるのです。したがって、銀行は皆さんから預かった現金を元手にして貸付をしているのではないのです。従って、理論の上では、銀行は借り手への与信により無限に銀行預金残高を増やせるのです。
現実には、その預金残高に合わせて中央銀行に準備金として預金を預け入れることが必要ですし、BIS規制(国際決済銀行は自己資本率が8%以上)も有ります。また、借り手が返済不能になることもありますから、信用創造にも一定の限界は有ります。しかし、銀行預金の量は信用創造によって決まると言う事実は動きません。このことは、4月4日の参議院決算委員会で、私の質問に対して黒田日銀総裁が明言しています。
借り手不足が信用創造を阻む
銀行預金が銀行による信用創造、つまり銀行からの借金であるという事実は、今日の日本経済の問題が何であるかを示しています。しかし、残念ながら日銀がいくら異次元緩和をして、銀行に資金提供をしても民間企業が借りないのです。民間企業はいくら金利が安くても先行きが見えない状況下では、不要の資金は借りません。返済できるという確信が無ければ借入というリスクはとらないのです。信用創造の要は、最後は借り手の意思によるのです。
国債の発行は国家による信用創造
銀行預金は銀行が貸し付ければ事実上無限に増えるという事実は、国債の発行が多過ぎて国家が破綻するから財政再建をしなければならないという論法が、完全に間違っていることを証明しています。国家が国債を発行することは確かに国の借金ですが、それは同時に国民に同額の預金を提供したことになります。これは、銀行預金と借入金の関係と同じです。
民間の預金がある内は良くても、後々高齢化により取り崩されて行けば、その内、国債の消化はできなくなる、などということは無いのです。政府は安心してデフレを救うために長期計画を立て、それを予算化すれば良いのです。
政府による国家の長期計画が必要
 建国記念の日(紀元節)を祝う集いでのご挨拶
建国記念の日(紀元節)を祝う集いでのご挨拶
民間企業が銀行から借り入れをしないのは、バブル期の後遺症も原因の一つです。銀行の不良債権処理の際の貸し剥がしがトラウマになっているのです。その上、政府自身が日本の将来を、少子高齢化と債務超過で財政が行き詰っていると不安を煽っているのです。政府は財政再建のためにと財政出動を控えておきながら、民間企業にはアニマルスピリッツを発揮して投資をしろとは、虫のいい話です。
民間企業に投資を勧めるのなら先ずは隗より始めよ、政府が長期計画を示し、それに従って予算計上をする必要があります。
預金超過が金融政策を無効化
また、もう一つの事実は上場企業は殆ど無借金、中小企業も半数は預金残高の方が借入金残高より多い、事実上の無借金であるということです。この要因は、先に述べたように、バブル期のトラウマや先行き不安の外に、労働分配率(企業の儲けに締める人件費の割合)が20年以上に渡って低下していることに要因があります。
預金超過ですから、日銀がいくら金融緩和しようが、銀行から借り入れをする必要がないのです。このことは金融政策が無効になっていることを意味します。
銀行は経営悪化
一方で、銀行は事実上のゼロ金利にも拘らず、貸し出し額が増えません。そのため、利鞘(ざや)が稼げず、経営基盤は急速に悪化しています。最近、地方の銀行の経営統合の報道が相次いでいるのはこのことと関係しています。
この状況下で、もしも大災害などの不慮の事態が発生すれば、間違いなく日本経済は大打撃を受けます。会社の倒産などが多発すれば、銀行は大量の不良債権を抱え込むことになります。銀行の倒産を防ぐため、日銀も政府も金融機関の支援をするでしょう。金融機関を助けるために融資も必要となります。しかし、本質的には金利の上昇を認める以外ありません。ところが、金融不況を救うためとは言え、不況時に金利を上げることは国民経済そのものを毀損することになります。日本は正にどちらにも進めない現状に陥ってしまうのです。このように、アベノミクスは最大の危機に直面しているのです。
銀行の与信機能の正常化が急務
こうした事態を避けるためにも、金融政策に余力を残しておく必要があります。平時に銀行に体力を蓄えさせ、金融危機の際には金利を引き下げる余力を残しておくことが大切です。つまり、ゼロ金利政策から早く脱却する必要があるのです。そのためには、借り手の需要を増やして一日も早く金融システムを正常に戻す必要があります。
労働分配率の低下が最大の問題
 白峯神宮での節分祭
白峯神宮での節分祭
こうした状況に陥った最大の原因は、労働分配率低下による個人所得の減少とそれに伴い個人消費が減少したことです。これはバブル期の不良債権処理から始まっています。この時期、企業は次々とリストラを行いました。職員の人員整理は勿論のこと、正社員の非正規社員への置き換えや自社生産の外注化など、徹底的なコストカットが行われました。会社の生き残りのためには仕方なかったことかもしれません。しかし、それを一過性のものではなく、ビジネスモデルとしたことが、後に少子化という大きな社会問題を作ったのだと私は考えています。
アベノミクス効果で、企業の業績は確実に改善し、景気は戦後最長の拡大期間を更新していると言われていますが、国民にはその実感がありません。その原因は、企業の業績拡大に比して勤労者の所得が増加していないという、まさに労働分配率の低下にあるのです。
法人税を増税し、子育て世代に分配すべし
安倍総理が、毎年春闘の時期になると率先して経済界にベースアップを要求しているのは、このためなのです。その結果、ベースアップは着実に行われるようになりましたが、企業の業績に比べればまだまだです。コストカットのビジネスモデルを修正させるには、法人税を増税し、それを子ども手当として国民に給付すれば良いのです。これは実質的に給与アップと同じことになります。そうすれば、安心して子どもを生み育てることができるため、少子化に歯止めをかけられるはずです。
また、上場企業に滞留している銀行預金を国民に分配することにより、個人消費は必ず伸びます。それが経済活動を拡大させるため、結果的に企業の利益も増えるのです。
信用創造の大本は希望である
貨幣の大部分は銀行預金であり、その根源は銀行の貸付である。これは事実です。問題は借り手に借りようとする意思がなければ銀行は貸し出せないということです。借りようとする意思は未来に対する希望です。将来に対して希望があるからこそ、銀行からお金を借りてでも事業をしよう、投資をしようとするのです。
今、日本にかけているのは将来に対する希望なのです。政治の使命は国民に日本の将来に対する希望を明確に示すことです。日本は財政破綻などしないのですから、政府が積極的に自信を持って将来に対する投資を行えば、それは必ず国民の希望につながります。
戦争や貧困や災害などあらゆる危機から国民を救うのが国家の使命です。国債発行をしても財政破綻はありませんから、十分に予算をつけるべきなのです。それが国民に将来の希望と安心を与え、消費や投資が増え、日本全体が豊かになるのです。財政再建を理由に国民の危機を救わないという論法は、モラルとしてもありえないのです。
樋のひと雫
-アンデス有情-
羅生門の樋
日本で桜の花が咲き乱れる頃,此処ボリビアでは街路樹は葉を落とし,晩秋の空気の中で街は冬の準備を始めます。もっとも,標高の高いラパスでは一日の内に四季があると云われ,朝はセータ,日中はTシャツ,日が落ちるとコートが必要になります。日本のように年間で四季を感じることは余り有りません。
トランプ大統領の国境の壁建設で話題となったホンジュラスのキャラバンは,グァテマラからの参加もあり,依然メキシコ国境には滞留者が増え続けています。犯罪組織の興隆で平穏な市民生活が困難になるという状況は,日本から見れば信じ難いものでしょうが,こちらの人間にとっては「あゝ,そこまで,やはり‥‥。」というのが正直な感想です。
20年近く前に,初めて首都のテグシガルパを訪れた時に,30mほど離れたマクドナルドに行こうとホテルの玄関に立った際,「危険だから車で行ってくれ」とガードマンに制止されました。お陰で5日間の会議では,文字通りホテルに缶詰めになりました。それから所用で何度も訪れましたが,街の喫茶店やレストランの前には,必ずショットガンを持った警備員が2・3人は立っています。銃を持った人間をガラス越しに眺めながらのコーヒは,決して気の休まるものではありませんでした。昼間でも大通りを歩く人の姿は見られません。まるでゴーストタウンの様に息を潜めての生活は,私から見れば,異様の一言でした。知人も近頃は「あの国は終わった」と言っていましたが,妙に納得できる自分に驚きます。警察は有って無く,軍部ですらコントロール出来ない治安の悪化は,まさに亡国への坂道です。
しかし,住み慣れた家を捨て,国を出られるキャラバンには,未だしも希望と夢が持てます。ベネズエラでは,為政者の怠慢と無策の中で,国を出ることが出来る人間は全て出たとも云われています。残された庶民の生活は,天文学的インフレの中で,今日の食事にもこと欠く困窮の極にあると伝えられています。この極度の食糧難の中でも,権力者と富裕層は高級レストランで米ドルを使い,多くの庶民はゴミ箱を漁っているとTVニュースが伝えたのが1ヶ月ほど前でした。
その後,西側のマスコミを追放したマドゥーロ政権ですが,南米で唯一の支持国であるボリビアには,政府の発表は伝わって来ます。未だに解決しない大規模な停電も,最初の頃は“米国のサイバーテロ”の所為にされました。5日前の新聞には,通信大臣が「大口径の狙撃銃によって攻撃され,ダムに大爆発をもたらした」と発表しています。漆黒の闇の原因が,「ITから人に変わった?」と思っていたら,先日の発表では,ロシアから百人の軍人と35トンの物資が派遣されたと報じていました。恐らく自国の軍部のクーデターを恐れた政権の保身策でしょうが,これも末期症状を呈した政権の疑心暗鬼の始まりとも見えます。
米国による経済制裁とロシアによる軍介入と聞けば,何やら1960年代のキューバ危機を思い出します。しかし,ケネディやフルシチョフ,フィデル・カストロといった理想と現実を見据える眼を持った政治家ではなく,ディールだけの商売人と覇権主義者,己可愛さだけの独裁者に庶民の声を聴く力は有るのだろうかと思います。「国が(電力不足で)麻痺していて何も生産出来ない。どうして生きていけば‥。」という庶民の嘆きは,果たして彼らに届くのだろうか。虚しさだけが募るボリビアの晩秋です。
平成と共に始まった政治家人生
 檀家総代をつとめる長国寺『御会式』での一枚
檀家総代をつとめる長国寺『御会式』での一枚
今年は平成最後の年となりました。5月からはいよいよ新しい御代が始まります。そこで改めて平成の30年を振り返ってみたいと思います。平成元年に参議院選挙があり、父の吉宏が府議会から参議院に転出しました。その後継という形で、私は翌年平成2年に府議会議員に出馬し当選させて頂きました。府議を5期務めた後、参議院議員の父の引退により事実上の公募形式で平成19年の参議院選に出馬することになりました。自民党惨敗の選挙でしたが、皆様のご支援のお陰で初当選をさせていただきました。
私の政治家人生は平成と共に始まったのです。
バブルに始まりデフレに終わる平成
平成はまた、バブルの始まりでもありました。京都でも土地の値段が異常に高騰しました。今から思えば、それがバブルだったのですが、当時の日本は、アメリカを抜いて実質的には世界一の経済大国になったと自惚れていました。こうした繁栄がこれからも永遠に続くものと誰もが信じていたのです。
ところが、株価は、平成元年の大納会で終値の最高値38,915円87銭を付けたのをピークに暴落に転じ、平成5年末には、日本の株式価値総額は元年末の株価の59%にまで減少しました。内閣府の国民経済計算によると日本の土地資産は、バブル末期の平成2年末の約2,456兆円をピークに、平成18年末には約1,228兆円となりおよそ16年間で資産価値が半減したと推定されています。
土地の値段が下がりだすと、それを担保に借り入れをしていた企業は銀行から返済を迫られ、土地の投げ売りが始まりました。そのため更に土地の値段は下がり続けます。土地は絶対に下がらないという土地神話は崩壊したのです。日本では、土地を担保にした融資により企業は投資をしていましたから、土地神話の崩壊は極端な信用収縮を引き起こし、日本はデフレに突入していくことになります。
20年前より100万円低い世帯所得
バブル時代の融資が土地の値段の下落により不良債権となってしまい、銀行の経営を圧迫し、この時期に銀行の合併統合が全国で行われました。京都でもいくつかの金融機関が統合されて無くなってしまいました。また、その煽りを受けて倒産する企業が後を絶ちませんでした。自殺者が急増したのもこの頃です。戦後は、大体2万人前後で推移してきた自殺者が、平成10年から一気に3万人を突破し、以後14年連続で続くことになりました。
また、バブル以前は、戦後の繁栄が続いており、給料は毎年上がり、生活は年々豊かになることを誰もが信じていました。しかし、バブル後は、そうした将来を皆が描けなくなりました。先行き不安で投資も減り、終身雇用が当たり前だと信じていたものが、解雇されたり、正社員になれなかったりしたため、国民の平均所得は下がり続けています。
幸い、第二次安倍政権以降は自殺者も3万人を下回りその数も減り続けて、現在では2万人程度になっています。また、国民所得も上昇に転じました。しかし、一世帯当たりの平均額は過去最高額が平成6年の664.2万円で、平成28年が560.2万円ですから、20年間で100万円下がったことになります。まさにこれがデフレなのです。国民の貧困化はバブル崩壊がもたらした最大の負の遺産なのです。
ゴーン式経営を見直せ
日産をV字回復させたとして、カリスマ経営者と称賛されていたゴーン会長の逮捕のニュースに世界中が仰天しました。毎年の報酬額を実際は20億円であったものを10億円としか公表していなかったことが直接の容疑のようです。しかし、本当はV字回復の手法にこそ、彼の罪があると思います。
日産は、かつてはトヨタと並んで日本の自動車業界の二大企業として君臨していました。しかし、自動車業界は市場がグローバル化し大競争時代に突入していました。その対応に出遅れた日産は、ゴーン容疑者が来る直前には2兆円を超える有利子負債を抱え、6,844億円という莫大な赤字を計上し、倒産の危機に陥っていました。その状況を打開するために、提携先のルノーから送りこまれてきたのがゴーン容疑者でした。彼はコストカッターという異名の通り、徹底的なコスト削減を行いました。その結果、一年で黒字回復させるなど経営手腕が高く評価されてきましたが、結局その本質は、非情なまでのリストラです。
経営危機に陥っていた日産にとってリストラは背に腹は変えられないものだったでしょう。日産に限らず、バブル崩壊で景気が下落し、銀行から債務返済を迫られた企業は、当時皆リストラを行いました。リストラをしなければ会社そのものが倒産の危機にあったからです。それまで日本の雇用慣行は終身雇用と年功序列が常識でした。この制度により安定した生活を従業員に保障することができたのです。
しかし、当時の経済情勢でこの制度を維持することは会社の命取りになることでした。コストを削減するために、正社員をどんどんリストラし、代わりにコストの安い外部に委託するいわゆるアウトソーシングや繁忙期には非正規雇用を増やして対応する等のことが日産に限らず、日本全国で行われていたのです。
アウトソーシングと非正規雇用を常態化するな
 京都府議会議員・京都市会議員の皆様と一緒に「安倍晋三総裁を囲む懇談会」を開催させていただきました
京都府議会議員・京都市会議員の皆様と一緒に「安倍晋三総裁を囲む懇談会」を開催させていただきました
アウトソーシングと非正規雇用は、経営危機から脱出するための非常手段であったのはずが、経営危機を脱出してからも常態化してしまいました。終身雇用制度の時代、人件費は会社にとっては固定費(売り上げの多寡と関係なく発生する費用)でしたが、アウトソーシングと非正規雇用にすれば、人件費は変動費(売り上げに比例して発生する費用)になります。人件費を売り上げに応じて払うことになれば、企業側にとって非常に有難いことです。しかし、従業員にすればたまったものではありません。非正規雇用では、生活が安定せず給与総額も低く抑えられてしまい、まともに結婚もできません。本来一時的な経営危機回避のための手段であったものが常態化したために、日本人の平均所得は下がってしまったのです。
三方良しの経営を目指せ
人件費を低く抑えれば利益が出るのは当然ですが、その経営手腕の成果として高額の報酬を要求することは当然だとする風潮が世界的になりつつあります。ゴーン容疑者もそのひとりでしょう。しかし、こうした考え方は本来の日本人の価値観とは相容れないものです。利益は独り占めするものではなくて、皆に分配する、分かち合うことこそが日本人が求めるものでしょう。
かつての日本人の経営者は分かち合いの精神を大切にしてきました。近江商人の「売り手よし、買い手よし、世間よし」の三方良しはその典型です。こうした経営哲学を持つ経営者がたくさんいたことが戦後の復興を成功させたのです。残念ながらバブル崩壊以降は、利益さえ出せば良いと言う利己主義経営者が幅をきかせています。
強欲資本主義は社会を破壊する
 東京政経セミナーの講師として菅官房長官をお招きいたしました
東京政経セミナーの講師として菅官房長官をお招きいたしました
かつて 「金で買えないものはない」と豪語したIT企業の経営者がいました。確かにお金で大概のものは買えますが、お金さえあれば何でもできると考えているのであれば、それは単にお金に振り回されているだけです。何の為にお金を使うかという目的意識こそが重要です。それが、自分が贅沢三昧する為なのか、従業員を幸せにする為なのか、どちらに自分の満足感があるのかを自問自答すべきです。
人間は、本来他人から感謝されることに喜びを感じる生き物です。哺乳類の中でも小柄で弱い人間は、仲間と協力し合って初めて生存することができたのです。仲間と守り合う本能が社会を作り、人間を進化させたのです。社会を維持するには独り占めではなくて分かち合いの精神が必要です。利益を独り占めしようとすることは、本来の人間の本能と相反するものであり、社会を破壊するものです。
平成の時代は、バブル期の見せかけの繁栄とその崩壊後のデフレ不況により利己主義が蔓延し、この当たり前のことが見失われてしまったのです。
財務省からアベノミクスを救う
平成元年、将来の社会保障の財源を確保するため、消費税が導入されました。しかしその後日本は、バブル景気に踊りバブル崩壊後はデフレ不況で苦しんでいます。結果として、税収が減り社会保障等の支給が増える一方となり、財政のバランスが悪くなったのは事実です。財務省は財政再建をするために消費税の増税を急ぎ、一方で歳出を抑えようとしています。
しかし、本当に問題なのは、デフレのため国民の平均所得が減ってしまったことです。その一方で、ゴーン容疑者に代表されるような大金持ちが生まれています。多くの上場企業は事実上無借金経営となり、いくら金利を下げても銀行の融資は増えず、金融政策が無効化しています。今必要なのは、こうした持てる者と持たざる者の格差を解消させることです。具体的には内部留保の多い企業から増税し、それを子育て世代に分配すれば事実上の賃上げが可能です。また、新幹線に代表されるインフラ整備など各省が必要な長期計画を発表し、それを予算措置すれば、間違いなく民間投資も増えてきます。
ところが財務省は、財政再建至上主義に陥っているため、財政支出を伴うことを極端に拒否するのです。官庁の中の官庁とも言われるほど優秀な人材が集まり、国政の中心を司っているにもかかわらず、その態度は、国民生活を救うという官僚の本来の使命を忘れています。財務省の立場からしか物を考えない、ある意味利己主義に陥っているのです。
更に、財務省の抵抗のために、金融政策と財政政策と民間投資からなるアベノミクスの三本の矢がうまく機能しなくなっています。これを正しい方向に導くために私は、昨年の11月に、「財務省からアベノミクスを救う」と言う本を出版いたしました。この本で述べているのは、財務省の言う財政再建論より国民経済を救う方が先だということです。是非ご一読ください。
3期目の改選を迎えて
バブルに始まりデフレに終わった平成の御代でしたが、次の御代にはこうした混乱から立ち直り、再び皆が希望を持てる時代にしなければなりません。私も今年の7月には3期目の改選を迎えます。こうした課題の解決に向け全力で取り組む覚悟です。本年も皆様方のご支持、ご支援をよろしくお願いいたします。
瓦の独り言
-ロングライフデザインって?-
羅生門の瓦
新年あけましておめでとうございます。今年は己亥で、諸突猛進のイノシシ年です。イノシシのごとく勢いよくはありませんが、つぶやかせていただきます。
市バス停留所に「さ、洗い流そ」と舞妓さんの広告*が出ています。よく見ると「牛乳石鹸赤箱」の宣伝で、端っこに「Long Life Design 2016」とGマークがありました。Gマークといえば皆さんよくご存じだと思いますが、我が国の良きデザインに与えられている称号です。 このGマークですが、第2次世界大戦後(通称:戦後)我が国のものづくりの指針を示したもので、当時はGHQが持ち込んだデザインのコピーが横行していたとか。これではいかん!と1957年(昭和32年)に意匠奨励審議会(当時はデザインという言葉が無かった)が発足ました。それまでに1951年(昭和26年)には松下電器産業内において、1953年(昭和28年)には東京芝浦電気内に意匠課(まだデザイン課ではない)が出来て我が国のデザインを牽引していったとか。
その中で、「ロングライフデザイン」とは長きにわたって、我々に愛されているモノで「長きに渡って作られ、使われ、愛され続けているもの」につけられる称号です。(最近では、製品だけではなく、サービス、システム、ソフトウェアも含まれるとか) この、ロングライフデザインには10か条の制約があります。修理、価格、販売、作る、機能、安全、計画生産、使い手、環境、デザインです。
なら、冒頭に述べた、「牛乳石鹸赤箱」は100年近い歴史が、それなら「金鳥蚊取り線香」も。100年にはならないが、「ホンダスーパーカブ」、「キッコウマンの醬油さし」「コニシボンド」など、など。我々の身の回りにはまだまだ、たくさんの製品が・・・。
さて、誠に失礼なたとえですが、政治家(国会議員)には「ロングライフデザイン」という言葉はふさわしくないのでしょうか?「長きにわたって愛され」「長きにわたって使われ(失礼)」 これは昨日、今日に出来た政党(カンバン換え)からの政治家には当てはまりません。(瓦以外の皆様方もそのように思われるのでは・・・)
では「何年くらい国会議員を続けるのか?」。20年、いや30年(人間には寿命が・・)
これに対して、瓦は答えを持ち合わせていませんが・・・。
でも、我々が国会にお送りしている「西田昌司参議院議員」には「ロングライフデザイン」になっていただきたい。今年の夏の改選で3期目に入られます。以後、4期、5期と続けていただきたいと思っているのは瓦一人だけではないはずです。
(*:ここ原稿を脱稿したのち、市バスの広告看板は高校駅伝に代わってしまいました。
また、今回はつぶやきが多くて申し訳ありません。)
ドイツのインダストリー4.0とは
 ベルリンのブランデンブルグ門の前にて
ベルリンのブランデンブルグ門の前にて
ドイツはインダストリー4.0と呼ばれる第4次産業革命を目指す産業政策を推進していることでも知られています。これは、第1次産業革命は18世紀の後半イギリスから始まった蒸気機関の利用による産業の自動化、第2次産業革命は20世紀初頭の電力の活用、第3次産業革命は、1980年代以降のコンピュータの活用による自動化と定義した上で、第4次産業革命はインターネットでモノを繋ぎAIがそれを自律的にコントロールする、究極の自動化を目指すものです。
この背景にあるには、Google、Amazon、Facebook 、Appleなどの米国のインターネット企業の猛威に対抗するため、ドイツの製造業の競争力を更に強化しなければならないというドイツの強い危機感の表れでもあります。
日本のソサエティー5.0とは
実は、日本でもドイツと同様の背景から、ソサエティー5.0が提唱されています。5.0としたのは、狩猟社会を1.0、農耕社会を2.0、工業社会を3.0、情報社会を4.0とした上で、これに次ぐ第5の新しい社会を「Society 5.0(ソサエティー5.0)」と名付けたのです。具体的な実現方法として、日本版インダストリー4.0ともいえる『コネクテッドインダストリーズ(Connected Industries)』が経済産業省より提唱されています。少子高齢化による労働力不足をインターネットとAIの活用により活路を見出そうとしているのです。
ベルリンでの視察
 ポツダム会談の行われた建物 スターリンを招くために赤い星型の花が植えられている
ポツダム会談の行われた建物 スターリンを招くために赤い星型の花が植えられている
最初の訪問地であるベルリンでは、ドイツ工学アカデミーのカガーマン元会長と会談をしました。カガーマン元会長は、ドイツのインダストリー4.0の提唱者で産業界の重鎮でもあります。「インダストリー4.0は究極の産業効率化であり、日本もソサエティー5.0を掲げ同様の政策を推進しています。これは人口減少社会に対する備えです。ドイツも少子化が問題と聞いています。その意味でもインダストリー4.0は重要ですが、移民政策はこうした効率化政策と逆行するのではないですか」という私の質問に、苦い顔をしながら「それは本質的な質問ですが、インダストリー4.0は移民政策とは関係なく、産業政策として必要なものなのです」と答えられました。
移民政策を巡り社会が対立
実は、ドイツは中東からの大量の移民を巡り、社会が混乱対立しているのです。第2次大戦後、ドイツは東西に分断されました。その中で西ドイツは日本と共に、敗戦国にもかかわらず経済大国へと発展していきました。その陰には、敗戦による分断により衰えた国力、特に労働力を補うため、積極的にトルコなどからの移民を受け入れてきた背景があります。その結果、現在のドイツは人口約8200万人の2割近くが移民だと言われています。
1990年に東西ドイツは統一されると、旧東ドイツの国営企業の破綻整理により大量の失業者が溢れ出します。これによりドイツの労働環境は一変しますが、これは統一のコストとして受け入れざるを得なかったのです。
一方で、冷戦後は中東などで相次ぐ紛争が起き、これに伴い大量の難民が発生しています。2015年には100万人を超える移民をドイツは受け入れています。EUの誕生により、 ヨーロッパが1つになり、人口5億人を超える巨大な市場が誕生しました。また通貨がユーロに統一されたため、ドイツはかつてのマルクより有利な条件で輸出ができるようになりました。その為、EU内で1番得をしたのはドイツだと言われています。そうした批判を避けるためにも、ドイツは移民の受け入れを継続せざるを得なかったのです。
しかし、移民の数が2割にも達するとなると、「言葉や文化の違いだけで無く、移民により職が奪われたり給料が低く抑えられている。移民を止めるべきだ」という右翼政党が台頭し出しているのです。
2017年9月の連邦議会選挙の結果、かつては支持率が7割以上あったとメルケル政権の連立与党のキリスト教民主・社会同盟と社会民主党の議席は激減し、移民廃止を訴える政党が第三勢力に躍進しています。EUの覇者となったはずのドイツでも、移民をめぐり社会は大混乱しているのです。
職業教育の充実と中小企業の支援
こうした状況に中、移民や失業者を社会で受け入れるためにも、職業教育を充実しなければならないということが言われています。マイスターという言葉がある様に、元々ドイツは職人などの生産現場の責任者の地位が高く評価されてきました。
インダストリー4.0が進むと産業の効率化により、既存の職業の雇用数は必然的に減少し、失業者が増えることになります。こうした人をもう一度大学などで再教育をして、今後必要となる新たな職種の担い手となる再教育、つまり一般の大学生だけでなく、一旦社会に出てから再教育するという、教育の二元化をドイツでは目指しているとのことです。
日本も中小企業の役割は大きいですが、ドイツはそれ以上です。中小企業こそ、革新的技術の主人公だと認識されています。特に事業を始める際の資金援助も手厚く、革新的技術を持つ人が事業化しやすい環境を作っています。こうした事は、今後日本でも積極的に取り入れていくべきだと強く感じました。
メディコンバレーとは
アメリカ・カリフォルニアのハイテク産業の集積地、シリコンバレーを念頭において命名されたメディコンバレーとは、デンマークのコペンハーゲンおよびスウェーデンのスコーネ地方に広がるバイオテクノロジー・医薬・医療関連企業の一大集積地のことです。
これを統括するのがメディコンバレー・アライアンスで、たった5人のスタッフですが年間30件ものイベントを行うなど、企業間のネットワーク作りの援助をしています。この地域にはデンマークとスウェーデンの生命科学産業の約6割の企業が集積しているため、企業相互のネットワークが構築されれば、それが新たな投資や開発を生み出す元になっているとのことでした。
生命科学の分野ではこの20年の間に合併買収が繰り返し行われてきましたが、デンマークでは、自国の企業が米英の企業に乗っ取られない様に、株式を財団化する事で防いできたそうです。一方スェーデンでは、そうした措置を取らなかったため米英企業に合併買収されてしまったということです。
デンマークは面積では、スウェーデンやノルウェーより小国ですですが、元々は北欧三国の盟主だったと自認しており、国際的企業も多く存在していますが、流石に商売上手だと感心致しました。
マックス・プランク協会への視察
 ハンブルグ総領事公邸前にて 加藤総領事とともに
ハンブルグ総領事公邸前にて 加藤総領事とともに
マックス・プランク協会は非営利の独立研究機関として、世界的に有名な物理学者マックス・プランク(1858-1947)にちなんで1948年に設立されました。同協会は、基礎研究を専門に行う83の研究所(うち5研究所と1支部はドイツ国外に所在)で構成されており、ミュンヘンに本部を置いています。
研究分野は自然科学、生命科学、人文科学及び社会科学にわたっています。設立以来、17人のノーベル賞受賞者を輩出し、国際的にも高く評価されています。
約17,000人の職員のうち5,470人が研究者で、そのほかに4,500人の奨学生と客員研究員が所属しています(2013年)。年間予算は約15億ユーロ(2013年)で、出資比率は連邦政府38.9%、州政府38.9%、その他22.2%です。
130円/1ユーロで換算すると約2000億円もの予算で、基礎研究、特に未知の分野の研究に特化して研究支援をしています。日本の理化学研究所とも関係が深いとの話でしたが、理研の予算が年間約1000億円弱ですから倍の予算規模で遥かに凌駕しています。
マックス・プランク協会の特徴は優秀な人材を広く海外から集めていることです。ドイツ人の研究者は40%以下で、国際性が非常に高いのですが、世界から優秀な研究者を集めることにより、特許が取れればそれは協会、即ちドイツのものとなり、国益に資するという戦略です。
研究者の裾野を広げるべき
「10年間何をしてもいいから、自分のしたい研究をしてみないか」同協会のこの言葉は世界中の研究者にとって大変魅力的な言葉です。日本においては、理研などの特定の機関には研究開発予算が注ぎ込まれていますが、研究者の裾野を広げるためには、地方の国立大学等の予算拡充をしなければなりません。
しかし、現実には国立大学は法人化され、民間企業のような経営感覚を求められ、更には大学で成果を上げることが求められるようになりました。その結果、基礎研究のようにすぐに成果の出ない部門の研究が排除されがちになっています。また、任期の限られた特任教授のような制度では、長期的な研究も保証されません。優秀な研究者を育てるにも、成果主義がそれを阻んでいるのです。
また、これは理科系の学部だけではなくて、文化系の学部でも同じことが言えます。文化系では、資格を取ることが大学の看板のようになり、真実の学問を追求すべき大学本来の姿から程遠くなりつつあります。これも悪しき成果主義の影響です。
ドイツのように、社会人の再教育もこれからの大学には求められます。その成果として資格の取得は、最も分かりやすいのは確かです。しかし、その一方で大学の原点である真実を求める心を養うことが忘れられてはなりません。行き過ぎた成果主義にはしる事のないよう肝に銘じなければなりません。
今回の視察では、その他にも様々なことを学びましたが、しっかりと日本に反映させたいと考えています。
樋のひと雫
〈ボリビア通信〉
羅生門の樋
今、ベニー県のトリニダという処にいます。アマゾン川の源流が近くを流れ、オリエンテと云われる熱帯の地方です。ここで全ボリビアの教育関係の全国大会があり、招待されました。しかし、熱帯という雰囲気はなく、朝夕は涼しくモト・タクシー(バイクタクシー、熱帯地方では乗用車より一般的です)の運転手などは防寒着を着込んでいます。これも異常気象の現れでしょうか。
昨年の今頃のコラムでは、ベネズエラが300%近くのインフレで、商店には品物が無く、路上強盗や殺人の増加で治安の悪化が著しいと書きました。今では、これらの状況を知らせてくれた友人とも連絡が取れません。家族ために国を出たいと話していましたが、無事に何処かに居ることを願うばかりです。
世界通貨基金(IMF)は今年末までのインフレ率を3万%と予測しています。ちょっと想像もつかない通貨の下落です。日本で云えば、3万円が1円になるのですから、500円のコーヒを飲むのに1500万円が要ることになります。まあ、物が無いのですから、飲めるかどうかわかりませんが…。マドゥーロ政権は十万単位で通貨の切り下げを行ったということですが、いつ紙くずになるとも知れない通貨を誰も欲しがらないでしょうね。
ところで、テレビを見ていて気になることがあります。昨年の映像では、国外脱出する人々は小ざっぱりとした上着で大きな荷物を持っていました。ちょうど我々が小旅行に行くような服装です。しかし、最近のニュースでは、かなりやつれた表情でTシャツの上に薄汚れたブルゾンを羽織った若者や幼子を抱えた家族が連日映っています。昨年までの脱出組はある程度の余裕を感じられましたが、昨今の映像からは、切羽詰まった様子が伺えます。今までは、パスポートを持たない人間を入れていなかったペルーも、最悪の人道危機(la peor crisis humanitaria en América Latina)が迫っていると云う認識から国境を開きました。今や、南米の多くの国が「ベネズエラの経済難民」を受け入れています。(こんなところは、共通言語を話すという強みでしょうか。日本人が他国に移民するという緊張感とは違ったものがあるのでしょう。)政権の失政と経済の混乱から逃れてきた人々を「難民」と呼ぶべきか否かは分かりません。しかし、日々の生活を破壊され、命の危険と隣り合わせの生活から逃れてきた人々に、安定した場所を提供するとう話を聞くと何かホッとした気持ちになります。
しかし、現大統領のマドゥーロは相変わらずの演説好きで、支持者だけの会合を連日開き、現実味のない夢を語り、満面の笑みを浮かべ拍手を得ています。隣国コロンビアとの危機を煽り、自らの統治能力の無さから国民の目を逸らそうと躍起の様子です。己の失政への国民の不満を外に向ける。為政者の昔からの常とう手段です。連日テレビに流れる演説の姿を見ていて、解りやすいと言えば、これほど解りやすい人間も稀だなと感心しています。
平成最悪の豪雨災害
 二之湯府連会長と由良川流域の被害状況の説明を受ける
二之湯府連会長と由良川流域の被害状況の説明を受ける
平成30年7月初旬、平成最悪の豪雨災害が西日本を襲いました。死者がすでに210人を超え、未だに行方不明の方が数十人おられます(7月17日現在)。京都府下でも5人の方が命をなくされたことを始め、土砂崩れや浸水等で府下各地域で 2,500を超える住宅被害も出ています。お亡くなりになった方のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された全ての皆さんにお見舞いを申し上げます。
特に被害が大きかったのは、京都府の北部地域でした。私も、災害から一週間後に、同期の参議院議員、牧野たかお国交省副大臣に同行して、現地を視察してきました。自民党京都府連も会長の二之湯智参議院議員を本部長に災害対策本部を立ち上げ、現地を視察されました。牧野副大臣には、一日も早い復興のため予算をつけるよう、要請をいたしました。
避難所に行けない場合は、必ず二階に逃げる
まず最初に、3人の死者が出た綾部市の災害現場に参りました。黙祷の後、国土交通省の職員や、山崎綾部市長などから災害報告を受けました。お亡くなりになられたのは、お年寄りのご夫婦です。当時、近所の公民館が避難所として指定されていましたが、深夜では、とてもお年寄りだけで向かうわけにはいきません。避難所に行くべきかどうか、逡巡している最中に土砂崩れが襲ったのです。また、その隣のお家も崩壊し、お一人がお亡くなりになりました。しかし、2階で寝ておられた方は救助されています。1階と2階の差が生死を分けたのです。
ご夫婦が住まわれていたお家は、藁葺き屋根にトタンが葺かれた丹波や丹後の山村ではよくあるお家です。通常藁葺きの家には、2階はありませんが、大きな屋根裏があり、納戸として使われています。大屋根は壊れていませんでしたから、せめて大屋根の裏にでも避難されていれば命は助かったと思われます。
これからも今回のような大雨が降る可能性は否定できません。この災害を教訓に、是非とも裏山等のある地域の方は大雨の際には、早めに避難所に行くべきです。しかし、真夜中の避難は事故の恐れがあり危険です。その時は、必ず、二階や屋根裏などの高い場所に避難(垂直避難)して下さい。垂直避難が命の分かれ目になります。
山地河川 由良川の宿命
 牧野副大臣・本田衆議院議員と国道27号土砂崩落現場の被害状況の説明を受ける
牧野副大臣・本田衆議院議員と国道27号土砂崩落現場の被害状況の説明を受ける
今回大きな被害が出たのは、京都では北部地域です。この地域では、ここ最近豪雨災害が相次いで起こっています。特に、北部の中心河川である由良川流域では、太古の昔から水害が絶えませんでした。
山地河川では、山間の谷底に土砂が溜まってその周りに僅かな平野部分が存在します。谷が埋まってできた平野の上に、人が住んでいるということです。谷間を流れているため、もともと堤防がありません。由良川の場合、山地河川という地形を考えると、河川の流域の中で人々は生活しているということになります。
由良川の場合、下流部は、狭隘な地形で平地が狭く、連続堤防を築くと土地利用に大きな影響を与え、人が住む場所がなくなってしまいます。そこで、昭和57年の台風10号規模の降雨で浸水する恐れのある地区を対象に、輪中堤を築堤したり宅地の嵩上げ等の水防災対策が実施されてきました。
輪中堤と言うのは、集落全体を堤防で囲い込む堤防です。住宅がある程度集まっている地域にむいています。嵩上げは、文字通り、地盤を上げることで、住宅をジャッキなどで垂直移動させ、その下に基礎を築くことになります。集落から離れたところにある家屋にむいています。
平成32年度の完成目指して
現地に視察に行きまして、地元の市長さん達からも被害の状況と災害復旧に対する要望をお聞きしました。福知山、綾部、舞鶴の各地域では、ここ数年、毎年のように浸水被害が出ることに対して、住民の方からも苛立ちの声が上がっていました。
こうしたことから、由良川の築堤工事が急ピッチで進められています。平成32年度には、輪中堤も含め完成する予定です。ここ数年の浸水被害を契機に、インフラ整備も進み、被害を抑えることができた地域も沢山あります。しかし、一方で、すでに輪中堤が完成した地域でも、山側から流れてきた中小河川の排水ができず、いわゆる内水の浸水で被害が出ている地域がありました。こうした被害をなくすためには、輪中堤から由良川に排水する排水機場の設置やポンプ車の設置が必要です。しかし、由良川の水位が上昇すると、内水の排水により下流の洪水を招くことになり、排水ができない場合もあります。内水の排水を適切に行うためには、結局、上流でダムを作り水量を調整する以外ありません。上流には、大野ダムがありますが、この貯水量を増やす方法を考えなくてはなりません。やはり、ダムが洪水対策の切り札なのです。
防災インフラなしでは都市化できない
また、先述した様に、由良川は山地河川です。丹波から丹後の山間部を流れ、中流から下流域では平地ができていますが、それは氾濫原ですから、流域全体が河川域の中なのです。常に洪水の危険があり、太古から氾濫を繰り返してきました。しかし、そのおかげで肥沃な平野ができ、作物などもよく採れたのです。かつては、住宅地は山側の高台にあったのですが、都市化のため平地にも住宅が建てられ、浸水の常習地になってしまったのです。
日本は国土の7割が山岳地帯で、平野部のほとんどは河川の氾濫によってできた氾濫原です。平野部には都市が開発されていますが、それら元々は河川域の中だったのです。最近の大雨は異常気象とも言えますが、その氾濫原を都市化している以上、洪水は宿命とも言えます。むしろ都市化したからには、洪水対策のためのインフラ整備が不可欠なのです。
河川域住宅を作らせなかったら洪水被害はなかった、と言う人がいます。しかし、人口減少時代に突入したとは言え、1億2,000万を超える人口を、河川域以外で生活させることは、事実上不可能です。土地の利用制限などの検討が必要なことも事実ですが、洪水被害から住民を守るためには、インフラを迅速に整備することこそ必要なのです。ところが、バブル崩壊以後は、そうしたインフラ整備を悪とする世論が世間を席巻しました。
「公共事業はムダ」が整備を遅らせた
バブル崩壊後、民間企業は経営再建のため経費削減に励んでいました。バブル時代の贅沢三昧の反省もあり「清貧の思想」も流行りました。こうした時代背景の中で、行政においてもムダを削減する改革をすべきだと、声高に叫ばれるようになりました。また、政府の予算の無駄遣いを排していけば財政再建にもつながる筈と、特に公共事業予算は無駄の象徴のように言われ、削減され続けました。その極めつけは、民主党政権時代の「事業仕分け」でしょう。政府の役人を前に並べて、徹底的に予算の無駄遣いをチェックする姿が、政権交代の象徴として連日テレビに放映されていました。
群馬県の八ッ場ダムは、こうした騒動に巻き込まれた典型例です。首都圏を洪水や渇水から守るために計画されてきたものが、民主党政権になり、工事全体の7割が完成していたにもかかわらず工事は中止されてしったのです。ダムは環境破壊や無駄な公共事業の典型で、植林など緑のダムを作れば環境にも優しく費用も安く済む筈だという発想の「脱ダム宣言」によるものでした。
しかし、それを科学的に裏付けるデータも無かったのが実態です。そのため、流域の自治体から工事中止を批判する多くの抗議を受け、訴訟沙汰にもなってしまいました。こうした混乱の中、工事中止が妥当か再調査をせざるを得なくなりました。結果は、ダム建設の有効性が認められ、工事が再開されることになりました。結局、3年間の工事延長とそれに伴う工事代が嵩むだけだったのです。
防災のために必要なものは全てやる
 竹下亘総務会長ほか、自民党本部役員と京都府中部医療総合センターを視察
竹下亘総務会長ほか、自民党本部役員と京都府中部医療総合センターを視察
今回の豪雨では、山陰線が運休となり、京都縦貫道も通行止めになったため、京都中部医療総合センターに、医師や看護師などが出勤できないという事態も生じました。幸い、このことにより医療に支障が生じることはありませんでした。しかし、災害拠点病院であるだけに、将来に不安を残しました。
こうした事態を重視して、自民党の災害対策本部から、竹下亘総務会長らもこの病院を視察しました。私の方からは「高速道路は一般道より高規格の筈、大雨だからと一律に通行止めにするのではなく、災害対策や医療関係者は通行できるよう弾力的にルールを考えるべきだ」と申し上げ、竹下総務会長からは「同感だ、党で議論し、政府と検討する」と返答がありました。
また、亀岡始め南丹や京丹波では、大雨のため縦貫道だけでなく国道も通行止めとなったため、一時孤立してしまいました。桂川亀岡市長からは、「防災のためにも京都と結ぶダブルルートの建設を」と要望がありました。私の方からは「ダブルルートは北陸新幹線を亀岡ルートから京都ルートに変更した際の亀岡との約束。防災の上からもトンネルで京都と結ぶべき」と補足の説明をしておきました。竹下総務会長からは「政府与党あげて一日も早い災害復旧のため全力を尽くす」と約束していただきました。
今回の豪雨災害は、京都だけでなく、西日本全域に大きな被害をもたらしました。これを教訓に、二度とこうした災害が起こらない様に知恵と予算を出さねばなりません。安倍総理も「できる事は全てやる、お金のことは心配するな」と話しておられます。一日も早い復旧と防災インフラの整備は政治の責任です。私も全力でその使命を果たしていきたいと思います。
瓦の独り言
-やっぱり言いたい!今のきもの-
羅生門の瓦
暑中お見舞い申し上げます。蒸し暑い京都の町で、暑苦しい話で失礼します。
京都の観光地である東山界隈や市内の繁華街では『きもの』を着た女性をよく見かけます。しかし、この『きもの』の多くはポリエステルでインクジェット加工や派手な捺染加工をしたものです。レンタル着物の色柄については『きもの』文化を語る京都人からはおおよそかけ離れた商品です。このレンタル着物着用している女性の大半は海外の方で、『きもの』を着て京都市内を散策し、写真を撮ってSNSに投稿しています。いわばコスプレ感覚でレンタル着物を着用しています。これは、これでいいのでしょうが、海外の国賓が来られた時に「あれが日本古来の伝統工芸品である『きもの』ですか?と質問を受けたときに、瓦は「ノー」としか言えませんでした。
正絹の『きもの』は価格、メンテナンスの問題で敬遠され、ポリエステルの『きもの』が業界に投入されて40年近くたちますが、爆発的なヒット商品になっていません。価格、風合い的には問題のない商品もあるのですが、京都人には『きもの』とはみなしてもらえません。瓦の家内もポリエステルの『きもの』は認めてくれず、和ダンスには入れてもらえません(?)
このようなときにポリエステルのレンタル着物が登場し、『きもの』文化を語る人々の間でホットな戦いが行われています。業界の関係者の中には「『きものブーム』の起爆剤になれば」「いきなり絹ではなく、ポリエステルで練習してからホンマ物にたどり着く」「車を運転する初心者に、いきなりクラウンではなく、カローラ(?)から始めては」といった意見が出ています。しかし、今回のレンタル着物に代表されるポリエステル・インクジェットの『きもの』は、単なるコスプレ感覚と見過ごすわけにはいかないような気がします。日本人として『きもの』へのあこがれ、民族衣装としてのアイデンティティ。『きもの』の中には日本人ならではの文化が凝縮されています。また、『きもの』における染織技術は世界のどこにもない誇るべき技術です。
「利休道歌」の中に、「規矩作法守り尽くして破るとも離るるとても本を忘れるな」という「守・破・離」という一文があります。今のレンタル着物はいきなり「離」になっているのではないでしょうか。「守」である基本、すなわち「きもの文化」を正しく学ぶ、そして理解して今様の『きもの』に至るのであれば・・・と瓦は思っています。
経世済民の意味
 BSフジ「プライムニュース」に出演いたしました
BSフジ「プライムニュース」に出演いたしました
経世済民とは世を経(おさ)め民を済(すく)うというのが元々の意味で、これを略して経済と呼ぶようになったのです。今では、経済はお金儲けと同義語のように扱われていますが、経世済民を実践すれば結果としてそれがビジネスにつながるのです。
現に、江戸時代には亀岡出身の石田梅岩のように、商人でありながら人の生き様を考え、後に石門心学と呼ばれる様な思想家も誕生しました。この教えは「実の商人は、先が立ち、我も立つことを思うなり」と簡単な言葉で商人の道を説いています。近江商人の「売り手良し、買い手良し、世間良し」もこれと同じ様な意味です。儲けだけでなく、社会全体の利益を考える精神を昔から日本人は大切にしてきたのです。
グンゼの創業の精神
京都府綾部市が創業の地であるグンゼなどは、その典型例です。ウィキペディアによると、以下の様に書かれています。
社名の「グンゼ」は創業時の社名「郡是製絲株式會社」に由来する。「郡の是」とは、国の方針である国是、会社の方針である社是のように、創業地の何鹿郡(現・京都府綾部市)の地場産業である蚕糸業を、郡(地域)を挙げて振興・推進していこうという元農政官僚で殖産興業の父と呼ばれた前田正名の趣旨に基づいている。
創業者の波多野鶴吉が、前田正名の講演を聞き感銘を受け1896年(明治29年)8月10日に、創業地の産業である蚕糸業の振興を目的に、郡是製絲株式會社として設立した。蚕糸・紡績業が国家事業として力が注がれていた明治期にあって、早くから海外に生糸を輸出し、高い評価を得るとともに、海外の拠点開設も早い段階で行われていたことから急速に業績を拡大していく。また、製糸工場では女性の労働者が中心であり、地域の養蚕農家の子女を集めて操業していた。女工哀史という歴史があるように、当時が劣悪な労働環境で働かせる工場が多かった時代に、同社は女工ではなく『工女』と呼んで大切にし、工場内に女学校まで設立して人間教育に務めた。同様に、大資本を背景に財閥オーナー企業で創業する場合が多い明治期に、創業時から株式会社制度でスタートした同社は極めて稀有な企業であり、低賃金労働による搾取も感じられない、現代の『CSR』(企業の社会的責任)という言葉をそのまま体現したような会社だったといえる。創業者の波多野鶴吉の掲げた『創業の精神』がそれを示している。
社会環境の変化により製糸業からは撤退しますが、創業の精神を守り綾部に登記上の本社は残しているそうです。京都府民にとっても誠に誇らしい限りです。
景気回復の一方で格差が広がる
安倍総理は、デフレ脱却のためアベノミクスを掲げ、経済再生と財政再建を両立させると述べてこられました。確かに、民主党政権時代に比べれば株価が3倍近くなりました。上場企業も史上最高益を更新しています。失業率は2%台に、有効求人倍率も1.4倍となり、人手不足が心配されはじめました。景気は間違いなく回復しはじめているのです。にもかかわらず、その実感がないと言われます。その理由は、地域や会社による格差が広がりつつあると言うことです。
東京をはじめとする大都市圏では、確かに景気回復が実感できるでしょう。しかし地方では、そのような実感はなく、通りの人影も少なく、お年寄りばかりが目立っています。大企業では好業績を背景に給料も上がっている様ですが、中小企業は大企業からコストカットを要求され、なかなか給料を上げられない状態です。従業員の数は全体の7割を中小企業が占めていますから、中小企業の業績が回復しない限り、景気回復を国民全体が実感できないのです。都市部と地方との格差や大企業と中小企業の格差、これを小さくすることが何より肝心なのです。
新自由主義の蔓延
 千本釈迦堂「おかめ福節分会」で豆撒きをいたしました
千本釈迦堂「おかめ福節分会」で豆撒きをいたしました
私は、4年前に旧東海道や旧中山道などを歩きました。全国の商店街を歩いて気付いたことは、昭和の時代の商品の看板しかないということです。それは、平成になってからはシャッター街になり寂れてしまったことを象徴しています。地方都市では平成になってから投資をほとんどされていないと言うことです。
その原因がバブル崩壊以降アメリカ型の新自由主義にある事は間違いありません。かつて、東京の物価は世界で1番高いと言われてきました。消費者は高いものを買わされている。その原因は輸入規制をして安い外国製品を排除してきたからだ。輸入の自由化をすべきだ。また、大型店の出店規制をしている大店舗法を廃止すべきだ。こうした規制を緩和すれば消費者は安い商品を買うことができ、国民の利益になるはずだ。こうした意見の背景には、アメリカからの圧力もあったわけですが、結局マスコミも規制緩和に賛成し、国民の世論となりました。
利己主義の蔓延
あの当時は、物価が下がるということを誰もが良い事と思い込んでいたのです。最後は、自分の給料も下がると言うことになるとは思いもつかないまま、誰もが賛成していたのです。正にこの空気がデフレを作ったのです。
また、バブル後の世界は、東西冷戦の終焉によりアメリカ一強時代の幕開けでもありました。バブル崩壊で自信をなくしたところにアメリカ型の経済思想が一挙に押し寄せました。それが新自由主義と呼ばれるものです。
元々アメリカでも家族的経営が重んじられてきましたし、企業の社会的責任ということも重視されていました。しかし、次第に株主資本主義が幅を利かせる様になりました。それは、会社は結局は株主のものである。従って利益を上げ配当することが会社の責務であり、社会的責任は政府に多額の納税をすることにより政府が必要な政策を行えば良いというものです。正に企業を金儲けのための手段としか考えない思想です。そしてアメリカが東西冷戦の覇者となったことにより、こうした考えが世界中に蔓延していったのです。こうしたアメリカ型の資本主義が新自由主義と呼ばれるものです。しかし、これは企業を利益を生み出すための装置と考えるものであり、結局は自己主義そのものです。
間違ったバブル後の財政政策
問題はこうした考えが、政府に対しても要求されてきたことです。政府の使命はまさに経世済民です。戦争であろうと災害であろうと貧困であろうとあらゆる危機から国民を救う、これが政府の使命です。したがって、バブル期の経済不況の際には、徹底的に財政出動をして国民生活を守るべきだったのです。当初はこうした考えから財政出動がされていました。しかし、バブル期の不良債権は一説には数百兆円とも言われるほど莫大なものでした。政府の財政出動はあまりにも乏し過ぎたため効果が発揮できませんでした。逆に、民間企業が借金を返済して身の丈に合わせているのに、政府だけジャブジャブお金を使うのはおかしいと言う声の方が大きくなったのです。
その結果、財政出動は継続されなくなってしまいました。政府の責任放棄ですが、あの当時の世論がそれを望んだのです。また、政府もそれを利用して経世済民より財政再建を優先したのです。ここにも利己主義が蔓延しているのです。
構造的デフレ
デフレ後の日本では、民間企業が投資をせず、政府も投資をしない、その一方で規制緩和をして輸入を拡大するなど、こうした政策が同時に行われました。ただでさえ需要が減少して物価が下がっているところに、安い輸入品を入れればどうなるでしょうか。
物価が安くなることを消費者が喜ぶ一方で、生産者は職を失い、失業者が増加します。その結果、賃金は下落し国民全体の消費は減退します。そうなればますます安い物でなければ売れなくなり、物価が下がり続け、給料も下り続けます。正にデフレスパイラルに陥ってしまいます。
また、高齢化時代を迎えた日本では、毎年一兆円を超える社会保障給付額が増え続けていきました。ところが、デフレ不況のため税収は下がり続けます。この差額が構造的な財政赤字を生み出していきます。
一方で、不良債権処理を終えた後、民間企業は国内投資より海外投資を伸ばすようになります。圧倒的に海外市場の方が大きいからです。世界経済の成長のおかげで、企業は史上最高益を更新していきますが、海外の所得のため日本には税金が入りません。また雇用も海外に流れ、国内では失業者が増えます。また、コストカットが常態化し、中小企業や労働者には利益が還元されません。この様にしてデフレの仕組みが出来上がってしまったのです。
和の精神がデフレ解消への道
日本のデフレは、政府と民間、都市と地方、大企業と中小企業、消費者と生産者など本来お互いが支え合うべき存在が対立し、バランスを崩していることが原因です。これを解消するには利己主義を排除することが大切です。自分の利益だけではなく社会全体の利益を考える。日本人が昔から持っていた和の精神を取り戻すことが必要なのです。
そのためには、『隗より始めよ』の言葉の通り、まず政府自身が率先しなければなりません。政府自身が経世済民の使命を果たし、それを実践する以外にないのです。
山田知事から西脇知事へ
 西脇隆俊 新知事と門川京都市長と共にしっかり連携
西脇隆俊 新知事と門川京都市長と共にしっかり連携
去る4月8日に行われた選挙で、山田啓二知事の後継として西脇隆俊氏が選ばれました。今回の選挙は、事実上共産党の支援する福山氏と西脇氏の一騎打ちでした。共産党対自民・公明をはじめとする多くの政党の支持を得た西脇氏との戦いですから、誰もが大勝するものと思っていたのです。しかし、結果は、西脇氏約40万票に対し福山氏が約31万票も獲得しました。福山陣営は、当初より共産党の名前を隠し、立憲と書いたプラカードを候補者の周りで掲げるなど、立憲民主党支持者からもかなりの支持を得ていたようです。来年の統一地方選挙や参議院選挙に向けて、立憲民主党の動きにも気をつけていかねばならないことを痛感しました。
また、4期をもって勇退される山田啓二知事に対しては、林田知事の誕生以来懸案となっていた京都縦貫道の完成をはじめ、活力ある京都を作るために大きな成果を残して来られました。心から敬意と感謝を申し上げ、今後のご活躍をお祈りいたします。
京都においても西脇知事が山田府政を継承し、経世済民の実践を期待します。
樋のひと雫
羅生門の樋
去年の桜は“忖度”で蕾が開き、今年は“公文書偽造”で満開になりました。どうも、日本の季節は政局と共に移ろうもののようです。昨年帰国した時には、空港横の騒音とゴミの土地が、良く売れたものだと思いましたが、今年も未だこの問題で揺れていようとは……。
しかし、去年と今年では、どうも様相が異なるようです。それも、行政文書の書き換えと云う忖度の次元の話ではなく、国の統治機能に係る問題が。どうも、日本の官僚群の劣化が、根っこにあるように見えます。それも、“権勢におもねる”という品性の堕落が……。
人々は様々な職業に就き、日々の糧を得ます。同時に、職に従事する者の責任と誇りを培います。そこに職業人としての道徳も生まれます。語弊があるかも知れませんが、過っては“政治は三流、官僚は一流”と言われ、官僚達が優秀であるから、日本の政治は過たないと言われてきました。焼け野原の飢餓から国民を救い、戦後復興から高度経済成長を経て、日本の飛躍を導いたのは、紛れもなく日本の官僚達でした。そこには、国を背負って立つ者の職責の自覚と信念、誇りがあったはずです。今回の公文書偽造には、自らの信念で「国会答弁に沿うように書き換えた」のではなく、権勢におもねるが故に、公文書に手を加えたように見えます。この姿勢には、国民から負託を受け、国のかじ取りを行うという覚悟が見えず、職責の放棄と言われても仕方がありません。
公の職に就く者の矜持に、“青史を刻む”というものがあります。これは自らの統治形態や執行を正確に記録に残すことであり、その国の有り様を後世に伝えるための国の重要な責務の一つです。また、この文章の記録こそが、官僚としての職務遂行の正当性を表現する重要な手段でもあるのです。過って、官僚は時の為政者や権力者の圧力にも抗して、職務を遂行してきました。記録こそが意思決定の中で信念を貫き、時として弾圧を受けようとも、国の将来を過たずという覚悟の表明でもあるのです。
この職務遂行の過程は、文字によって残され、その時々の判断だけでなく、後世に“歴史の審判”を受けることになります。これは、時の流れの中で、因果の見極めを受け、自らの信念と判断の正当性を歴史の評価に委ねることを意味します。これが公文書を残すという意味でもあり、その期限はギリシャやローマ時代にまで遡ることが出来ます。
時の権力者におもねる様に公文書を書き換えるなら、それは官僚としての自らの立場と責任の放棄であり、信念の喪失であると云えます。そして、書き換えられた公文書は、もはや“青史の記録”ではなく、回想録の中で我田引水されるような修飾文の一節にしか過ぎなくなります。公文書の偽造というのは、現在の法律に照らした罪であるばかりでなく、日本の歴史に対する罪でもあります。これを機会として今一度、青史を刻むという職責の重さと覚悟を自らに問いかけて欲しいものです。
国民を犠牲にしても核兵器開発を行う北朝鮮
 衆院選直後、「大型補正予算」の要望に総理官邸を訪問
衆院選直後、「大型補正予算」の要望に総理官邸を訪問
このところ、日本海側に漂着する北朝鮮の木造船のことが、頻繁に報じられています。実は北朝鮮の沿岸部の漁猟権は、中国に売られていると言われており、そのため彼らが漁をするには、沿岸を離れ日本海を遠く沖合にまで出なければなりません。しかし、冬の日本海をあのような小舟で漁に出ることは自殺行為です。漂着した船以外にも、多くの船が難破していると言われています。文字通り命がけなのです。そこまでして取ったイカですが、彼らは冷凍設備を持たないため、船上で内臓を取り出して天日干しをし、スルメにして中国に売っているそうです。そうやって稼いだ僅かな外貨も国民のために使われるのではなく、核兵器開発に使われていることを思うと、北朝鮮国民には同情の念すら感じます。
国連の非難決議や経済制裁など国際社会からの非難にもかかわらず、北朝鮮は核兵器開発をやめません。何故、この様に頑なな姿勢を金正恩委員長は取り続けるのでしょうか。経済制裁の結果、国民の困窮は日毎に悪化しています。
国民を犠牲にしてまで核兵器開発に血道をあげるのは国家としてあり得ない行為です。正に、北朝鮮は世界に例を見ない異常な国家なのであり、そういう国が、現実に我々の眼前に存在しているのです。
冷戦終結により後ろ盾を失った北朝鮮
約30年前に東西冷戦は終結し、ソビエトは崩壊しました。東ヨーロッパ始め世界中で共産主義体制が崩壊し、それぞれの国で民主化が進んで行きました。ソビエトは、ロシアを始め15の国に分裂し、中国も共産党の支配は続くものの自由化は進んでいます。こうした状況の中、北朝鮮だけはその体制を一層強固なものにしています。それは、自らの後ろ盾を失い世界から孤立していくことに危機感を感じていたからに違いありません。
東西冷戦の終結により、西側諸国と東側諸国の経済的取引が活発になりました。特に米国と中国とは互いに最大の貿易相手国になっています。アメリカにとって中国は最大の輸入国であり、貿易赤字の大半も中国によるものです。そうした貿易のアンバランスはあるものの、経済的取引が活発になればなるほど、それぞれの国は相互依存するようになって行きます。最早、米中はお互いに相手国の存在が無くては自国の経済は成り立たない状態になっています。これが両国共に戦争への抑止力となっています。同じ様なことが米露の間でも言えます。冷戦時代の厳しい対立の状態から比べれば、確かに、冷戦が終結して世界は平和になったのです。
しかし、このことは、北朝鮮にとっては自分の後ろ盾を失ったことになります。米中、米露が密接な関係になることは、米朝関係有事の際に、中国やロシアが助けてくれない可能性が有るということを意味します。東西冷戦の時代には、中国やソ連の核の傘で北朝鮮は守られていました。しかし、冷戦後、両陣営が相互依存の状態になると、状況は全く異なります。例えば、中国が北朝鮮を守るかどうかは、米中関係の維持とどちらに価値があるかということを中国がどう判断するかに拠るのです。
冷戦終結により戦争の抑止力は低下した
かつて、イラクのフセイン大統領は大量破壊兵器を持っているという口実でアメリカの攻撃を受け、国の体制が転換させられた事件がありました。これは、北朝鮮にとっては大きなトラウマになっているはずです。同じことが北朝鮮に対しても行われないとは限らない、それをどう回避するか、彼らは必死で考えていたはずです。そこで、たどり着いた結論が核兵器開発だったのです。核兵器保有国になりさえすれば、中ソの後ろ盾がなくても絶対にアメリカから攻撃を受けないはずだ、そう信じて彼らは核兵器の開発に血道をあげてきたのでしょう。まさに東西冷戦の終結と言う本来世界が平和になるはずの事態が、北朝鮮の核兵器開発につながると言う皮肉な結果をもたらしたのです。
このように考えると、冷戦の終結は一見平和と経済発展をもたらしたようですが、その一方で各国の安全保障をより複雑なものにしています。かつては東西の対立が激しく、何万発もの核ミサイルで対峙しており、今より随分国際情勢は緊張感がありました。しかし、逆に小さな紛争が核戦争につながりかねないという恐怖心があったために、結果的に平和な時代が続きました。冷戦終結後は、世界中、様々な国で取引が出来るようになり、経済は発展しました。しかし、その一方でそれぞれの国同士の関係が複雑になったため、戦争に対する抑止力は間違いなく低下しています。現に、湾岸戦争を始め、冷戦終結後に世界各地で様々な紛争や戦争が起きています。北朝鮮の核兵器開発は到底認められるものではありませんが、彼らの行動の裏にはこうした世界情勢の変化があったことも知っておく必要があります。
占領の真実を知るべき
 麻生財務大臣に「参議院自民党の予算編成」を申し入れ
麻生財務大臣に「参議院自民党の予算編成」を申し入れ
こうした世界情勢の変化に対応するため、日本でも安倍政権の下、特定秘密保護法や平和安全法の整備など、安全保障に関わる法制が整備されてきました。しかし、こうした法整備が、憲法違反だとする野党や学者も存在します。そこで、そういう憲法の解釈をめぐる混乱を一掃するためにも、憲法改正が提起されているのですが、改正にはまだまだ反対の人が多数存在していることも事実です。
自衛隊が必要だとは殆どの国民が感じています。しかし、一方で9条には「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」と明記されています。この条文を素直に読めば、憲法と自衛隊との間に矛盾があることを誰もが感じてしまいます。しかし、憲法と自衛隊の矛盾は、日本を占領していたGHQの政策が180度転換したことによるものです。憲法は日本に主権のない占領時代にGHQの指示により作られたものです。また、自衛隊も同様にGHQの指示により作られたものです。この事実だけは改めて確認しておく必要があります。(詳しくは、2015年7月10日発行のshowyou83号に詳しく書いておりますので、私のホームページ等でぜひご覧ください。)
第二次大戦後、日本が一度も戦火に見舞われることがなかったのは平和憲法のおかげだと言う人がいます。しかし事実は先に述べたように何万発もの核兵器で東西両陣営が対立していたことが皮肉にも戦争の抑止力になっていたのです。核兵器の廃絶を訴える団体が、今年のノーベル平和賞を受賞しました。そうした理想を否定するものではありませんが、歴史の事実は事実として受け止めなければなりません。
自らの国の歴史をもう一度総括すべし
 北陸新幹線(敦賀・大阪間)早期完成を目指す建設促進決起大会にて挨拶
北陸新幹線(敦賀・大阪間)早期完成を目指す建設促進決起大会にて挨拶
第二次大戦、特に日本にとって大東亜戦争とは一体何だったのか、このことについて日本人自身が振り返り総括をしたことは、ただの一度もありません。戦勝国による総括がされただけです。それが東京裁判であり、そうした歴史観に基づいて憲法を始めとする占領政策が施行されてきたのです。この占領の間に日本は歴史的にも思想的にも完全に戦前と戦後とに分断されてしまいました。その結果、日本人は自らの歴史を自らの歴史観で考えることができなくなり、更にアメリカが与えた歴史観しか持ち合わせていないため、世界の情勢を多角的に考えることができなくなってしまいました。
また、武力放棄をすれば世界が平和になると教え込まれたため、国防意識があまりにも脆弱です。その結果、冷戦が終われば、世界は平和になり経済は発展するという表面上の理屈にのみとらわれて、日本の安全保障環境が悪化する事態も起こり得るということを見落としていたのです。この点では北朝鮮の方が、冷戦終結の意味することを的確に捉えていたと言えるでしょう。
北朝鮮が核保有国になった時、日本の安全保障はどうなる
先日の北朝鮮による発射実験では、大気圏再突入は失敗したといわれているものの、距離的にはアメリカ大陸まで到達できるだけのミサイル技術を確立したようです。残念ながら、このままでは、北朝鮮が事実上核保有国になる可能性を否定できません。その可能性も現実として考えておかなければなりません。
北朝鮮が事実上の核保有国になり、その射程がアメリカ大陸まで届くということは、日本がアメリカの核の傘で守られるとは限らないということを意味します。
核の傘とは、核保有国が同盟国に核兵器の抑止力を提供し、安全を保障するという意味です。日本に北朝鮮が核攻撃をすれば、アメリカが報復の核攻撃をすると言うことです。そのことが抑止力となり、日本は核攻撃を受けないはずだ、まさにアメリカの核兵器という傘が日本への核攻撃を防いでくれると言うことです。これは、アメリカの圧倒的な核攻撃力が核の傘の前提になっています。しかし、北朝鮮が核保有国になれば、この前提は崩れてしまう可能性があります。
今までは北朝鮮がたとえ核兵器を持っていてもそれをアメリカまで到達させる能力はありませんでした。しかし、それが出来るミサイルを完成させたなら、アメリカに直接核攻撃をできる能力を持つことになります。もちろん、本当にアメリカを核攻撃すれば、アメリカはその何倍もの核攻撃で報復し、北朝鮮は消滅してしまうでしょう。従って、北朝鮮がアメリカに先制の核攻撃をすることはまずないでしょう。
しかし、日本への核攻撃の場合は違ってきます。日本が核攻撃を受けた場合、日米安保条約によりアメリカが北朝鮮に対して報復の核攻撃をすることになります。そうなると、当然北朝鮮はアメリカに対しても核攻撃をすることになるでしょう。当然、アメリカは何倍もの報復核攻撃をし、北朝鮮は消滅してしまうでしょう。しかし、その前に北朝鮮の核攻撃により、アメリカのどこかの都市が大きな被害を受ける可能性が出てきます。アメリカが日本を核の傘で守ったことが、結果的にアメリカ国民の命を奪うことになるわけです。同盟国を守るため、何十万人ものアメリカ国民が犠牲になる、こういう選択をアメリカが本当にするでしょうか。もし、自分がアメリカの大統領ならどうするか、皆さん方はどう思われるでしょうか。
いずれにしても、北朝鮮の核武装はこうした問題を我々に突きつけているのです。まさに、「自分の国は自分で守る」こうした安全保障の原点について、日本人は自ら問い直さなければならない時代が来ているのです。そのことを国民にしっかり訴えなければなりません。それが政治家の責任であると思うのです。本年もよろしくお願い申し上げます。
瓦の独り言
-吉例顔見世興行の最適数に学ぶ-
羅生門の瓦

3回×540席×26日間 ≒ 2回×1200席×18日間
この数式の答えは約42、000で「當る干支年 吉例顔見世興行」の観客数です。
京の年末行事である南座の顔見世は、耐震工事のため、一昨年から会場を変えて興行が行われています。昨年はロームシアター京都(旧京都会館)のメインホールで12月1日から18日までおこなわれました。また、11月25日にはロームシアター京都に「まねき看板」が上がりましたが、歌舞伎400年の歴史の中で南座以外に「まねき上げ」が行われたのは初めてでした。
さて、この数式の左辺は一昨年の顔見世興行の観客数です。会場は先斗町の歌舞練場で540名しか入れないので、一日三回公演でした。期日は26日間でしたが、役者さんの方から日に三回公演はせわしない、とブーイングが・・・
右辺は昨年の観客数ですが、ロームシアター京都のメインホールは4階席を除いても1600名は収容できますが、主催者の松竹㈱さんによると舞台を十分楽しんでいただくには1,2階と一部の3階席で1200名しか使わないとか。さらに興行日数も少なく18日間です。これは、昼・夜の部に空席を造らないためだそうです。全国から来られる年末の吉例顔見世興行の観客数を約4万人強と踏んでおられ、切符が取れない、取れない、といった状況で千秋楽を迎えるのが好ましいのでは・・・
これをビジネス感覚で数式をたてると、1回の公演で大人数を入れ、ロングランの上演をする。昨年のロームシアター京都の場合ですと、2倍近い八万人の動員も可能です。しかし、吉例顔見世興行は人が演技をする「歌舞伎」です。映画ならいざ知らず、歌舞伎の動員には「最適数」なるものが存在しているのでは・・・
歌舞伎の興行における最適動員数は、金儲けの世界には通用しませんが、我々の日常生活に通づるものがあるような気がします。右肩上がりの時代には数値を追い求めましたが、現在では数値よりも「質」(クオリティ)を求める時代です。 「伝えよう、美しい精神(こころ)と自然(こくど)」をキャッチコピーとしている西田昌司参議議員の政治姿勢にも何か通じるものがあるようなきがします。これは瓦の独りよがりの思いではないと思っていますが・・・
これが「當る戌年 瓦の初夢」です。 最後になりましたが、本年もよろしくお願いいたします。
*冒頭の数式は、瓦が勝手にたてた数式であることをお断りしておきます。
予想外の大勝
 伊吹文明候補の開票結果報告会でご挨拶
伊吹文明候補の開票結果報告会でご挨拶
10月22日の衆院選は、与党の勝利に終わりました。京都府下においても、1区、4区、5区、6区では選挙区で当選し、2区、3区においても比例復活で当選を果たしました。結果的に全選挙区で衆院議員を誕生させることができました。皆様のご支援に心より御礼申し上げます。
今回の選挙は、直前に小池東京都知事が希望の党を旗揚げし、それに民進党が合流して政権奪取を公言していました。更にマスコミ挙げて反安倍一強の大キャンペーンの中、苦戦が予想されましたが、結果は与党の大勝で大いに安堵しました。その原因は以下の様なことが考えられます。
希望の党の失速
昨年の東京都知事選挙や今年夏の都議会議員選挙で大勝した小池都知事でしたが、希望の党には三匹目のドジョウはいなかったようです。希望の党の失速の原因は、小池都知事のいわゆる「排除の論理」とする意見があります。しかし、私はもう少し根本的なところに原因あったと思います。先ず第一に彼らには理念も政策もありませんでした。選挙に勝つことだけが結党の目的でした。これは、かつて民主党が非共産反自民で野党結集し政権交代可能な二大保守政党を目指すとして、小沢一郎氏の自由党と合流した時と瓜二つでした。
あの時は興奮熱狂の中で政権交代を果たしましたが、消費増税を巡り、程なく内紛が起こりました。政策や理念の違う人を排除するのは政党としては当然ですが、そもそも、選挙目当てで離合集散を繰り返していては政党ですら無く、只の徒党です。マスコミは安倍一強に抗するためには野党は共闘すべきという理屈を並べ立てますが、そもそもその論法に乗ったことが失敗の元であったのです。
自ら蒔いた種で自己矛盾に陥った
 衆議院選挙で小泉進次郎氏とともに必勝コール
衆議院選挙で小泉進次郎氏とともに必勝コール
次に、首班指名は国会議員でないと出来ません。従って、小池氏は都知事である限りその資格はありません。にもかかわらず、反安倍勢力を結集せよ!とは無理がありました。首班指名は選挙結果を見て考えると小池氏は言いましたが、選挙の顔と首班が異なるのは正に羊頭狗肉と言うものです。小池氏が衆院選に出れば首班の問題はなくなりますが、一方で東京都民に説明が出来るでしょうか。市場の豊洲移転の問題など、自分で蒔いた種を放置したままでは東京五輪の開催すら不可能になります。
そもそも、都民ファーストと希望の党は政策的に矛盾しています。都民ファーストの政策は、都内の私学の授業料補助や都内の保育士の給与助成など隣接県から人を招き入れる恐れがあるものばかりです。これらは都の利益だけで他府県に配慮の無い排他的政策ですから国政政党の政策ではあり得ません。地域政党と国政政党では政策の矛盾があったのです。
政党助成法の主旨に違反する脱法行為
政党助成制度は国会議員が5人以上の政党が対象であり、希望の党は対象外です。一方で、民進党は野党第一党であり、政党助成制度などにより100億円近い資金を保有していると言われています。民進党が事実上解党し、希望の党に合流すると言われていました。次期衆院選に党公認候補を出さないということは、少なくとも衆院議員はいなくなるということです。解党なら助成金は国へ返還すべきです。
民進党公認予定者に政党助成金から資金を交付したにかかわらず公認せず、希望の党から公認してもらい事実上希望の党からの交付金に転用することは脱法行為と言えます。 政党助成金の詐取の疑いもあります。彼らは、日頃は税金の無駄遣いと些細なことでも問題視するにもかかわらず、自らの行為は頰被りではあまりも無責任です。
今回の解散はモリカケ隠しだったのか
今回の解散は森友加計隠しだと言われていますが全くのデタラメです。解散したら説明せずに終わりという事にはなりません。ただ、事実関係が明らかになっている事を国民に説明せず、さも問題があるという野党やマスコミにも問題があります。ここでもう一度事実関係を整理しましょう。
先ず、森友問題について説明します。国有地を時価より極端に安く売ったのは安倍総理の政治力が働いたのではと言われていますが、全く事実ではありません。事実は、森友の小学校建設を大阪府が認めたため、それに伴い国が行政的に処理したに過ぎません。小学校の敷地の中からゴミが出てきましたが、これは法律上、国に賠償義務があります。法律に基づきゴミ処理費用を算定し、今後一切国の責任を問わないという条件でゴミ処理費用を値引きして売買したものです。ここに総理の関与は全くありません。これについては既にshowyou90号で詳しく説明していますのでご覧下さい(ホームページ参照)。
京都産業大学より加計学園の計画が優っていたという事実
 選挙応援中のハイタッチ
選挙応援中のハイタッチ
加計学園については、総理のお友達だから優遇されたかの様な報道ばかりされていますが、事実ではありません。正当な審査の結果です。
実は、加計学園騒動が起きた後、いらぬ疑惑を払拭するためにも、京都産業大学にもう一度獣医学部開設の打診をしたのです。しかし、大学からは出来ないとの返答があったのです。最大の理由は教員が確保できないことです。具体的に教員を確保する計画ができてなかったのです。加計学園が東大を中心に長年教員確保のための連携を図っていたのに対して、京産大側は準備不足だったのです。そのことを京産大も京都府も分かっているので何ら加計学園に異議を申し立ててません。このことからも、加計学園が総理のお友達だから選ばれたわけでは無いことがわかるでしょう。
憲法改正を掲げれば猛反発するマスコミと野党
こうして見ると、安倍一強批判はかなり事実誤認であっとことが分かります。実は、10年前にも反安倍の大キャンペーンが起こりました。平成19年の参院選の際の「絆創膏大臣」「なんとか還元水大臣」「消えた年金」など、今から考えれば、些細なことだった筈です。しかし、これが殊更に批判され、反安倍のムードが作り出されました。結果、自民党は大敗しました。今回のモリカケ騒動もこれによく似ています。
その裏にあるのが憲法改正に反対するマスコミなどの意図的な報道です。10年前、第一次安倍内閣で憲法改正のために必要な手続法である国民投票法が成立しました。これにマスコミや野党は猛反発したのです。今回も、安倍総理が2020年までに憲法改正を目指すと明言したことから、反安倍の大キャンペーンになったのです。
立憲民主党は本当に躍進したか
希望の党が失速の一方、立憲民主党が三倍増の大躍進と報じられていますが、改憲賛成派の方が圧倒的に多数を占めることになったのも事実です。改憲については、丁寧な議論が必要ですが、かつての様に改憲をタブー視していた時代では無いと国民は感じているのです。先の国会では、参院では憲法審査会が実質一度も開けませんでした。参院の民進党が憲法を論じることにさえ非常に消極的だったからです。
彼らは、平和安全法制や特定秘密保護法を憲法違反だとして徹底的に反対してきました。しかし、この法律が無ければ、日米韓の情報共有もできず、今日の北朝鮮危機に対応する事は不可能でした。国民もそれを納得したからこそ与党の大勝に繋がったのです。そのことを立憲民主党はどのように理解しているのでしょうか。
憲法改正反対は北朝鮮を利するだけ
自分で自分の国を守るのは独立国なら論をまたない自明の理です。それが、憲法上否定されているとの主張は、GHQによる占領を前提としていたからです。また、日本が第二次大戦後平和だったのは、9条のお陰ではありません。東西冷戦の巨大な圧力が世界中の紛争を抑止してきたからです。冷戦が終わり、ソビエトは崩壊しました。そして、ロシアも中国も西側諸国との貿易を増大させ相互依存が進んでいます。
一見、平和に見える国際社会ですが、逆に紛争の種は沢山出てきているのです。冷戦の圧力が無くなった結果、中国は海洋進出に乗り出しました。北朝鮮が核ミサイルを開発するのは、ソビエトが崩壊したことと、米中の接近のため自らの後ろ盾を失うつつある現実を直視しているからです。
こうした国際社会の変化を直視せず、ひたすら護憲を叫ぶ勢力が増大することは、日本の安全保障を危機に晒すことになります。護憲勢力の増大は北朝鮮が一番喜ぶことです。
立憲民主党の躍進は判官びいきによるものと私は考えます。与党が大勝に奢らず、謙虚に改憲の議論をすることも必要ですが、同じことを野党側にも望みます。
樋のひと雫
〈南米ベネズエラ事情〉
羅生門の樋
アンデスの空は雲一つない深い紺碧に被われ、街角のハカランダの木々は小さな紫色の花を咲き誇っています。春から夏へと時が移ろう中で、人々の服装も薄物に代わりました。しかし、盛夏に向かう季節の中で、酷寒の季に向かう国もあります。ベネズエラです。
友人は、「強盗と殺人が日常茶飯事で、怖くて街にも出られない。店の棚には空気と値段表しかない状況が続いている。殺人率がとび抜けて世界最高で、インフレも500~600%程が実感だ。」と言っていました。外貨を持っている人間はいち早くチリやコロンビアに逃げ出しましたが、最近では、国民の国外逃亡を恐れた政権が、海外渡航を禁止するようになり、国民は人質に取られているのと同じような状況に追い詰められています。
石油の埋蔵量世界一を誇る此の国が、何故これほどの貧困と社会の混乱に陥るのか、それも此処2・3年の間に……。今一つ理解できない処です。
前大統領のチャベスは原油価格の高騰を背景に、得たオイルマネーを民衆にばら撒き、近隣の反米左派政権には膨大な資金を投入し続けました。ボリビアではこれを“チャベスの贈り物”と呼び、エボ政権の民衆操作を助けました。トイレットペーパーすら輸入に頼る自国の産業育成を忘れた亡国の政策でもありました。
跡を継いだニコラス・マドゥーロが国会で野党が多数を占めると、支持者だけの“制憲会議”をねつ造し、立法を自らの下に置きました。既に司法と行政を我が物としていた彼には、“独裁体制”が整ったことになります。これに対する民衆の暴動が各地で起きています。軍の一部は離反の動きを示していますが、未だ小さなグループです。トランプ大統領の“軍事介入も辞さず”というツイートだけが大きく取り上げられていますが、内戦の芽はあります。
さて、数少くなった近隣の反米左派政権はこれらの動きをどの様に見ているのでしょう。表面的にはトランプへの反発だけで、ベネズエラ国内の動きには沈黙しています。この沈黙が何を意味しているか、どうもよく分かりません。選挙で否定されたとは言え、大統領の終身制を目論むエボ政権などは、他山の石として見ているのでしょうか。
しかし、一つだけ納得できることがあります。仮に、ベネズエラで反チャベス派が政権を奪取すると、膨大な“チャベスの贈り物”が国の借金に変わることです。自国の経済の立て直しの原資として、ベネズエラは返金を迫るでしょう。これが反米左派政権諸国にとっては、国の財政を圧迫し、延いては、インフレと政情の不安定化をもたらし、政権の終焉につながりかねません。中南米の反米政権は、ベネズエラの石油や財政的支援を、自らの政権の人気取りに使ってきました。この“贈り物”が、今や“財政的な時限爆弾”と化しつつあります。理念高き中南米の反米左派政権も、ベネズエラの民衆を救おうと動く国は有りません。
「選挙」という政権選択の機会を持つ、中南米職で「独裁」という亡霊が再び目覚めようとしているのでしょうか。選挙で敗れても「前大統領」という栄誉に包まれますが……。
マドゥーロが、南米のチャウチェスクになる日も、そう遠くないと感じる今日この頃です。
何故、テロ等準備罪の創設が必要なのか
 参議院本会議にて組織的犯罪処罰法改正案(テロ等準備罪)の中間報告に賛成討論
参議院本会議にて組織的犯罪処罰法改正案(テロ等準備罪)の中間報告に賛成討論
今国会の最重要法案であったテロ等準備罪を創設する法案は、参議院でも無事可決成立することができました。私は参議院法務委員会の筆頭理事を務めており、事実上この法案の与党側の責任者でしたから、無事成立したことに心から安堵しています。
この法律が提案された背景には、ご存じの様に世界中でテロが頻発するなど、国際的な治安の悪化があります。日本も2020年に東京オリンピック・パラリンピックが計画されていますが、1972年のミュンヘンオリンピックではテロが起きました。国内でも1974年の三菱重工爆破事件や1995年のオウム真理教による地下鉄サリン事件などでは、多くの犠牲者が出ました。
こうした事態に備えるために、TOC条約(国際的組織犯罪防止条約)を締結し、各国の組織的犯罪情報を共有する必要があります。国連加盟国196カ国の内187の国と地域が加盟しています。このTOC条約を締結するためには、条約が求めている義務(重大犯罪の実行の合意の犯罪化)を履行するための国内法の整備が不可欠です。 今回のテロ等準備罪の新設はそのためのものです。
野党はこの法律を廃案にすべきものとしていましたが、その理由はおおよそ次の3点に絞れます。一つは、この法律は国民の内心を縛るもので、戦前の治安維持法に通ずる悪法だとするもの。二つには、組織に属するなら民間人でも捜査や処罰の対象になるというもの。三つ目に、国連人権理事会特別報告者が、国民の人権を侵害する悪法と非難しているというものです。この理由が全く的外れであることを以下に一つずつ解説します。
戦前の治安維持法とは全く違う
戦前の日本では治安維持法があり、国体(天皇制)や私有財産制を否定するものに対しては、特別高等警察がその取締りを行い、時に厳しい拷問をし、容疑者を死に追いやったと言われています。プロレタリア作家の小林多喜二もその一人です。現代の常識でこれだけを見れば、とんでもない人権弾圧事件となるでしょう。しかし、そもそも、この法律の背景にはロシア革命があります。これによりソビエト連邦が成立し、こうした革命思想が世界中に広まりつつあったのです。自分達の正義のためには暴力革命も認めるという思想は世界中を混乱に陥れました。
現代では暴力革命を認めるという人は日本ではほとんどいないでしょう。また、共産主義を支持する人でも暴力革命を支持することはないでしょう。しかし、当時は、極端な貧困と格差、そして、戦争により、本当にそれを目指していた勢力が存在し、蔓延していたのです。
あの時代の治安維持法の是非は、こうした時代背景の中、総合的な歴史の判断にゆだねられていたのです。
従って、少なくとも現代の日本にはそぐわないものであるのはいうまでもありません。そもそも、今回のテロ等準備罪が治安維持法とはその立法趣旨が全く異なっているのです。前者が組織的犯罪集団による重大犯罪を取り締まるものであるのに対し、後者は「国体ヲ変革シ又ハ私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シ又ハ情ヲ知リテ之ニ加入シタル者」を取り締まるものです。何れにしても一般人には全く無関係のものなのです。
一般国民を守るためのものであり、取り締るものではない
 参議院法務委員会での「テロ等準備罪」審議の様子
参議院法務委員会での「テロ等準備罪」審議の様子
テロ等準備罪では、一般の方々は処罰対象になりません。 (1)犯罪主体をテロ集団、麻薬密売組織などの組織的犯罪集団に限定し、さらに、(2)重大犯罪の計画、そして(3)犯罪の実行準備行為があって初めて、処罰対象となります。
この様に法律の対象となる団体が「組織的犯罪集団」に限られているので、労働組合やNPOなど正当な活動をする団体が処罰の対象となることはありません。もちろん、居酒屋で「上司を殴ると意気投合」しても処罰されませんし、一般のメールやSNS上のやり取りで処罰されることもあり得ません。
しかし、正当な活動をしている団体の目的が「一変」して「組織的犯罪集団」になることがあるとの指摘があります。これは、例えば普通の宗教団体がオウム真理教のように重大なテロを起こすような団体に変わることもあり得ることを念頭に置いたものですが、「組織的犯罪集団」に当たるかどうかは、その団体が設立時に正当な団体であったかどうかではなく、テロ等準備罪の適用時点において、犯罪を目的とする集団になっているかどうかで決まります。
また、たとえその場合でも宗教団体の中で組織的犯罪集団化したグループが処罰の対象になるのであって、一般の信者全てではありません。このことからも犯罪に関係しない人、いわゆる一般人が取締りの対象になることはあり得ません。
国連人権理事会特別報告者の批判は事実誤認
国連人権理事会の特別報告者ジョセフ・ケナタッチ氏が、テロ等準備罪の創設に対し、同法案が「プライバシーと表現の自由の権利に対する過度の制限につながる可能性がある」という懸念を指摘したということが報道されました。これを受けて、民進党や共産党などは、国連もテロ等準備罪に懸念を表明していると騒いでいますが、これは事実誤認です。
先ず、この指摘は国連ではなくケナタッチ氏の個人的見解です。しかも、ケナタッチ氏が批判しているテロ等準備罪の資料は実際の法案とは全く違うものです。NGO(非政府組織)が英訳したもので判断した様ですが、そのNGOが何者でどの様な英訳だったのか、全く不明です。日本政府に情報を求めず、一方的かつ断片的な情報だけを頼りに批判するのは国連の職務に携わる者としても公平性に欠けています。
外務省は、こうしたことから「日本の国内事情や『テロ等準備罪』の内容を全く踏まえておらず,明らかにバランスを欠いており,不適切であると言わざるを得ない。現在我が国で行われている議論の内容について,公開書簡ではなく,直接説明する機会を得られてしかるべきであり,貴特別報告者が我が国の説明も聞かずに一方的に本件公開書簡を発出したことに,我が国として強く抗議する」としています。
いずれにしても、国会で審議している法案が何者かにより英訳され、それに対し一方的に批判をしている訳ですから、その背後にかなり政治的な意図があると思わざるを得ません。
民進・共産の一体化
以上の様に、民進党や共産党の反対は「反対のための反対」であり、その目的は民進党と共産党(民共)協力をして、打倒安倍政権の政治勢力を拡大することです。
「アベ政治を許さない」という言葉をスローガンに、この数年多くの政治運動が展開されています。平成25年の特定秘密保護法、平成27年の平和安全法制の時もいわゆる市民団体を巻き込んだ形で反対運動が展開されました。国会の周りにも連日鳴り物入りの抗議行動が行われました。それは今回の反対運動とも共通します。民共が一体となって一部のマスコミも巻き込みながら「アベ政治を許さない」をスローガンに活動する目的は、安倍総理の『戦後レジームからの脱却』を阻止するためです。
戦後レジームからの脱却とは何か
 お茶の京都博「宇治新茶・八十八夜茶摘みの集い」
お茶の京都博「宇治新茶・八十八夜茶摘みの集い」
安倍総理は、憲法改正を最大の政治課題としてきました。これは、自衛隊と9条との矛盾の解消を始め、敗戦後の占領時代に作られた様々な制度や価値観をもう一度見直そうとするものです。占領時代の遺物を見直し独立国家に相応しい体制を作ることは当たり前のことです。
ところが、これに真っ向から反対をしているのが「アベ政治を許さない」という勢力です。彼らは、戦前の日本を全否定し、戦後の歴史観や価値観を肯定します。つまり、占領中にGHQにより作られた歴史観や価値観を何の疑問もなく受け入れています。この姿勢は独立国家としてはあまりに情け無いことです。
TPOにより変わる判断
私は、大東亜戦争を全て正しいとは思いません。他に選択肢が無かったのかも含め、異議を唱える所も多々あります。しかし、逆に戦勝国たる連合国が全て正しいのかといえばこれも否でしょう。欧米の帝国主義に対して断固異議を唱えていたのが日本であったのです。しかし、その日本が、自国の防衛のため結果的には帝国主義的な行動に出ざるを得なかったことも事実です。台湾割譲、日韓併合、満州国の建国などは今の価値観からはとても納得できないものでしょう。しかし、当時の世界の中では果たしてどうか。こうしたことを考えるのが歴史を学ぶことです。物事を判断するには全てTPO、つまり、その時、その場所、その状況が具体的に示された中で、考えるしかないということです。
TPOにより価値判断は変わり、人の行動は変わるものなのです。先の大戦も当時の世界情勢とセットで評価をすべきです。
しかし、GHQの占領時代にはそうしたことが全く配慮されず、一方的に日本の行動が断罪されました。その象徴が東京裁判です。そして、その東京裁判史観に基づき、占領政策が正当化されていったのです。
これは、言論の自由が無かった占領中には仕方ないことです。しかし、占領が終わり、独立してからは、せめて歴史の検証をすべきだったのです。しかし、日本は独立後、一度もその検証することなく占領政策を継続してきたのです。
安倍総理は真の独立国家を目指すべき
「アベ政治を許さない」という勢力は、こうしたGHQの占領政策を基本的に是とする人達です。戦後の価値の継承者ともいえます。これに対し、安倍総理が掲げた『戦後レジームからの脱却』は正に、それを乗り越え独立国家としての日本人の価値を取り戻すことを目指すものです。
今回のテロ等準備罪を始め、大きな対立をもたらした安倍内閣の一連の政策は独立国家としては当然のものです。しかし、占領時代の政策を是とする立場からはアベ政治は明らかに逸脱しています。確かに、占領中は一見すると民主化が進められた様にも思えますが、国防の義務も無かった代わりに国民には主権など無かったのです。只々、GHQの命令を受け入れるしか無かったのです。それを平和主義と言うにはあまりに情け無いでしょう。
安倍総理の言う『戦後レジームからの脱却』は正にこうした占領政策からの脱却だと私は解釈しています。
憲法改正への道
安倍総理は憲法改正を最大の政治課題に掲げておられます。特に、9条と自衛隊の矛盾をなくすために自衛隊を憲法上明記すると言われています。私も勿論賛成です。しかし、もっと重要な問題は、戦後72年の間に日本人が歴史観を喪失してしまったことです。戦争の悲劇は語り継がれましたが、占領時代の矛盾と悲惨さは殆ど伝えられていません。それを何の疑問もなく是とするなら、アベ政治は許されないかも知れません。 しかし、もう少し、歴史をしっかり見つめるなら、占領政策に異を唱えないことの方が異常だと気付くはずです。
皆さんのご良識を信じます。
瓦の独り言
-老舗(しにせ)-
羅生門の瓦
京都新聞の朝刊に「京都ぎらい」でベストセラー作家(?)になった井上章一氏が「現代洛中洛外もよう」を連載されています。今は地理的な内容ですが、いずれは「老舗」についても触れられるのではないかと思います。その前に瓦がつぶやかせていただきます。
瓦は昨年、とあるセミナー①で京都流(?)の「老舗」について語りました。
他都市の商工会議所さんなどでは「創業100年、三代、同業で継続、現在も盛業」の4条件を挙げられますが、京都では創業は200年以上か、又は江戸時代以前が老舗と名乗れます。だって、創業500年以上の企業が京都市には多数あります。明治時代の創業100年なんて「ひよっこ」みたいなものです。と、言ってしまいました。すると、セミナー終了後、次のような質問を受けて、「いらんことを言いすぎた!」と後悔しました。
「Yタクシー会社ですけれど、来年に創業100周年を予定してるんですが、パーティ-などをすれば京雀に笑われますかね?」といった質問でした。
Yタクシー会社さんの創業者・粂田幸次郎氏は、1916年に京阪伏見桃山~明治天皇御陵間に路線バスを走らせ、1917年に「日光社(フォードの輸入代理店)②」を創業されています。そこからハイヤー事業部を立ち上げられ、今のYタクシー会社あると聞き及んでおります。
慌てて、「いえいえ、自動車運送業自体の歴史が浅いので創業100年で十分です。ましてや今年(2016年度)の祇園祭に御稚児さんを出されるおうちですので・・・」としどろもどろにお答えしました。
その後、Yタクシーの後ろには「おかげさまでD百貨店創業300周年・Yタクシー会社100周年」を意図した広告が出ていました。これを見たとき、「さすが京都人!うまいこと宣伝したはる。」と思いました。
とある京都人は「老舗は自らつけるものではなく、世間からいただく称号」とおっしゃっておられます。非常にうんちくのある言葉だと思います。
さて、井上章一氏は老舗をどの様にとらえておられるのか? 「洛中のものだけが「老舗」を語るのはおかしい!」と反論されるのか? 瓦は楽しみにしています
*「とあるセミナー①」:Yタクシー会社の運転手さんをはじめ、会社の方々に「京都の伝統産業」と銘打って、京都伝統産業ふれあい館の宣伝をしたセミナーです。
*「日光社(フォードの輸入代理店)②」:我々、南区民にはおなじみの九条車庫向かいの日光社さんです。
発端は異常な土地の値引き
 国会での「森友学園問題 証人喚問」籠池理事長への質問
国会での「森友学園問題 証人喚問」籠池理事長への質問
森友学園騒動は、今年の2月に朝日新聞が「森友学園が大阪の国有地を適正価格の1割で購入していた」と報道したことが発端です。財務省は、この報道を受け、売買価格を公開、「国有地9割引」について「埋設物の撤去・処理費用である8億円を控除した」と説明しました。しかし、あまりにも大きな値引きであるためその背景には政治家の圧力があったのではないかという疑惑が沸き起こったのです。そして、その小学校が元々安倍晋三記念小学校という名前であり、名誉校長が総理夫人であったことから、官邸からの圧力があったのではという騒ぎになったのです。
当初は私も、何故これ程値引きがされるのかについては疑念を持っていました。しかし、調べていくと、安倍総理始め、政府には全く問題がないことが判明しました。
土地取得の経緯
森友学園の小学校が建設されている国有地は、元々騒音対策として国が買い取った土地だったのですが、その後旅客機の技術の進歩で騒音が緩和されたため、不要になり売却されることになったものです。
国有地を売却する際には、先ず、地方公共団体など公益に関わるものが優先されます。そこで、平成25年6月から3カ月間、地元自治体である大阪府と豊中市に取得要望の有無が確認されましたが、両者からはその希望が無い旨の返答がありました。そんな中で、森友学園から買取の申し出があったのです。学校法人は公益団体として地方公共団体に準じて優先的に売却されるのですが、買取の申し出が一者だけであったため森友学園に売却されることになったのです。
森友学園は小学校の敷地として取得したいものの、手許不如意のため10年間の定期借地権を設定して土地を借り、10年後に買取をしたいということを申し出ました。ここから近畿財務局との交渉が始まり、その過程で、後にこの土地には大量のゴミが埋設されていることが判明します。
一方で森友学園は、平成26年10月に大阪府に小学校新設の認可申請書を提出します。大阪府の私学審議会の定例会が平成26年12月18日に開催されますが、ここでは森友学園に小学校を開設するだけの資力があるのかということが指摘され、複数の委員が疑問を呈しています。そのため、この時点では答申が保留されたのです。ところが、翌年の1月27日に私学審議会臨時会が開催され、条件付認可適当という決定がなされたのです。しかも、その条件は寄付金の状況を報告することなど形式的なもので実質的に条件と言えるものではありません。これを受けて森友学園と近畿財務局との間で平成27年5月29日に国有財産売買予約契約と国有財産有償貸付合意の契約が結ばれました。
土地の値下げはゴミが原因
森友学園の問題が注目されることになった原因は、国有地の異常な値引きです。約9億円の土地が8億円も値引きされたと聞けば、誰もが疑念を持ちます。しかし、その交渉の過程を調べていくと、減額が必ずしも異常ではない、むしろ国の損害を低く抑えるためには仕方がなかったということもわかります。
森友学園が近畿財務局と土地の賃貸交渉をしている矢先に、大量のゴミが埋設されていた事が判明します。森友学園が立て替えたゴミの処理費約1億3千万円を国が支払い、一旦解決するのですが、更に深層部からもゴミが出てきたため最終的には約8億円もの処理費を国が負担することになるのです。小学校の開設を当初は平成28年の4月としていたため、それに間に合う様に森友学園側でその処理を行うという事で、実際には8億円を支払うのではなく値引くことになるのです。この金額の妥当性については、私が予算委員会でも質問しましたが、民間事業者が行う場合の処理費と比べても問題ない金額である事が分かっています。
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは
 籠池理事長の証人喚問での偽証についての記者会見
籠池理事長の証人喚問での偽証についての記者会見
それよりも大事な事は、この値引きにより国側は国有地売却に関する瑕疵担保責任を免責されたという事です。瑕疵とは隠れた傷という意味ですが、ゴミの埋設など表面上では分からない隠れた傷が有った場合には、通常売り手側がその責任を負うことになります。これが瑕疵担保責任です。それが免責になったという事は今後もっと他に国側が責任を負うべき事態が発生しても国側はその責任を負わないという意味です。つまり、8億円の値引きで国側は今後一切の責任を免れたのです。それでも8億円は余りに大きいのではないかという方もおられるかもしれませんが、私は妥当であったと思います。
実は、豊中市の別の国有地の払い下げでゴミの埋設が原因で売却額の2倍のゴミの処理費が発生する事態がありました。元国有地で今は新関空会社が所有する土地を、給食センターを建設するため、およそ7億7,000万円で豊中市が購入したのですが、試掘調査で、地中から大量のコンクリート片などが見つかり、撤去に14億3,000万円の費用がかかることになったのです。
これを森友学園のケースに当てはめれば、瑕疵担保責任の免責を受けていなっかたならば、国側は売却額の2倍の18億円を払うことになりかねないということです。
問題はゴミの処理をしなかった森友学園にある
国側は瑕疵担保責任の免責の引き換えに8億円の値引きをしたのですから、本来、森友学園はゴミの処理をしなければなりません。森友学園は1億円で土地を購入したつもりですが、ゴミの処理をきちんとすれば8億円かかるはずで、結局土地の購入費は9億円になるのです。
ところが、森友学園はその処理をしなかったようです。私が予算委員会で公開した籠池夫人のメールにはゴミの処理費が3億5千万円かかるが、そのお金が無いという意味の記載があります。この事から、小学校の敷地の部分はゴミの処理をしたようですが、グランドの部分はそのまま放置していた事が窺えます。ゴミの処理費に莫大な資金がかかるという事で8億円も値引きさせておきながら、小学校開設の資金を節約するためゴミの処理は必要最低限に抑えていたという事でしょう。
小学校開設の認可は正しかったのか
以上の経緯からも国有地の値引きは妥当であり、少なくとも国側には瑕疵は無いという事が分かります。それよりも問題は、小学校開設の認可があまりにも早いということです。そもそも大阪では、幼稚園しか経営していない学校法人が借金をして小学校を設置することは禁じられていました。ところが、平成23年7月に森友学園から大阪府にこうした設置基準を緩和するよう要望が出されます。これを受けて翌年の4月に大阪府の私立学校設置基準が緩和されます。この規制緩和により、幼稚園にも小学校開設の道が開かれたのですが、実際に設置を希望したのは森友学園だけだったのです。
また、小学校の校舎の敷地を借地で賄うことは設置基準に反する行為であった事が、最近判明しました。上述した様に、認可適当と答申した時には土地は国から借りる前提でしたから、完全に設置基準に違反しています。ところが、いずれ買うことになっているから問題ないという見解を、最近大阪府が示しましたが本当に妥当でしょうか。
元々、幼稚園だけを経営する学校法人に借金で小学校を設置することを認めてこなかった理由は、経営基盤の安定した学校でなければ子供の教育を任せられないからです。ところが、森友学園はこの時、幼稚園の定員に対して5割くらいしか在園者がおらず、幼稚園の経営事態が危ぶまれていたのです。私学審議会の議事録にもその事が指摘されています。また、小学校を建てるには最低20億円から30億円は建設費が必要だと言われています。そのお金を用意できていたのでしょうか。小学校の建設を請け負った業者が総額約24億円のうち約20億円が未払いだとして提訴していることからも、必要な寄付金が集まっていなかったことは明白です。
大阪府議会で百条委員会を設置すべき
 「故郷を支援する参議院の会」で安倍総理へ要望
「故郷を支援する参議院の会」で安倍総理へ要望
この様な森友学園の財政状況は私学審議会でも危惧されていた事がその議事録からも確認できます。何故、条件付きとはいえ認可適当と答申したのでしょうか。また、その条件が本当に条件として正しかったのでしょうか。謎は膨らむばかりです。この解明には大阪府議会で強い調査権限を持つ百条委員会を設置する必要がありますが、維新と公明党の反対で未だに設置できていません。松井知事は国会の証人喚問に応ずると言っていますが、その前に自ら百条委員会を設置して説明責任を果たすべきなのです。私学審議会の担当者が処分されたと報じられていますが、それこそトカゲの尻尾切りでしょう。
森友学園の問題は、資金も無いのに小学校を建てるという無謀な計画こそが事の始まりです。普通なら、この計画を私学審議会に相談した段階で駄目出しがなされ、認可されることは無いでしょう。大阪府の対応や判断に瑕疵があった事は否めません。
視聴率重視で真実を報じないマスコミ
では何故、これほどまでに騒動になったのでしょうか。それこそマスコミの誘導があったからです。私が予算委員会でも指摘してきた上記のような事実は殆ど報じられる事は有りませんでした。真実を追求することより、視聴者の関心を引くため、殊更に政治家の関与があったはずだと煽り立てました。特に総理や昭恵夫人がこの件で関与する余地など全く無いにも拘らず、関係があるかの様な報道に終始しました。
確かに、籠池理事長夫妻の強力な個性や総理に寄付して貰ったという爆弾発言にマスコミが飛びつくのも分かります。しかし、そもそも総理の寄付の有無など問題の本質では有りません。更に、密室で人払いをして寄付をしたという証言など全く証拠にもなりません。実際、総理が森友学園に寄付すること自体、法的にも道徳的にも全く問題はありませんし、何故密室で渡さねばならないのでしょう。籠池理事長の証言は明らかに不自然なのです。
ワイドショーだけでなく、報道番組でさえも籠池理事長の一方的発言だけを報じるマスコミの姿勢は、公器としての使命を失ったというほかありません。報道のワイドショー化は自らの権威失墜になることをマスコミは知るべきです。
樋のひと雫
羅生門の樋
4月の初め、久しぶりに成田に着きました。エントランスでは満開の桜にではなく、「モリトモ…モリトモ…」というTVのアナウンサーの声に迎えられました。ネットのニュースで知っていましたが、ここまで日本で盛り上がっているとは思いませんでした。北アフリカで見ていたTVニュースは、イラクのモスルでの戦闘が朝から流れています。日本ではそのまま流れないような映像を見続け来た身には、ある種のカルチャーショックです。幼い子供が砲煙の中で横たわっている図は、「世界は広い」では済まされない肌寒さを感じさせます。
私の目には、大阪の一幼稚園の補助金の不正受給と学校建設の不正許可申請の問題に見えるのですが…。一国の総理大臣の去就を取り沙汰されるような問題に見ないのです。まあ、「妻や私が関係していたら…議員も辞めます」という質問を強く否定した言葉のみが脚光を浴びた結果でしょうが。この一言に飛びついた野党も「無関係を証明せよ」などと云う質問で、「強く伺わせる」などと自分の感想を修飾しながら、あたかも「疑惑」が存在するかのようなイメージを作り上げる。しかし、ディベートとしては面白いのですが、政治の場で論客として語る論理でしょうかね。
この問題で、党首論争を行うと蓮舫さんが云ったとか言わないとか。まあ、野田‐安倍論争で総選挙に至った再現を期待したのでしょうが、彼女の二重国籍問題ってケリが着いたのでしょうかね。何かあやふやなままで終わっていますよね。まあ、これも含めてやってみるのも面白いでしょう。ディベートのテーマは「疑惑と責任」というのが適当でしょうか。
「日本のマスコミは政治ではなく、政局を取材する」とは、よく耳にする言葉ですが、これなどはTVの視聴率も稼げるのではないでしょうか。
我々庶民の間には、どのような清廉な権力も永くその座に居れば腐敗するという考えが根底にはあります。「そう云えば長いよな」、「何か有るのでは」という漠然とした気持ちがあります。そのような勘繰りが土台に有って、イメージが形作られていく。このような構図が描けるのも「モリトモ問題」かも知れません。「忖度」という概念は日本人の精神に流れる優しさや奥ゆかしさを表現するものだったのですが、「媚へつらう」という意味に堕落したのが残念でたまりません。
建前から本音へ
 KBS京都「京biz X」に出演、北陸新幹線ルート決定についてお話しました
KBS京都「京biz X」に出演、北陸新幹線ルート決定についてお話しました
昨年のアメリカ大統領選挙は大方の予想に反して、トランプ氏の勝利に終わりました。大統領選での移民やイスラム教徒への過激な発言は、アメリカの内外で波紋をもたらしています。多様な価値観を認める自由の国であったはずのアメリカが、移民を否定し世界より自国の利益を優先するという政治姿勢には反対の声が国内からも上がっています。大統領選挙が終わったにも拘らず、新大統領を否定するデモが行なわれる等、まるでアメリカが二分されたかの様です。
この背景には、アメリカの本音と建前が見え隠れしています。自由社会はもちろん大切だが、そのためにアメリカの国益が失われてはならない。アメリカの国益を守ることが大統領の責務だというアメリカ人の本音の代弁者として、トランプ氏は大統領に選ばれたのです。既存の政治家が言えなかった国民の本音を率直に述べることにより多くの国民の支持を得た一方で、建前を重んじる既存の政治勢力との対立を生み出すことになったのです。これをどう統合するかがこれからの課題ですが、私は、政治家の本音の言葉こそが、国民の心を動かす原動力なのだと改めて感じました。
TPP条約成立の意味
先の国会ではTPPの条約や法案が成立致しました。ところが、トランプ氏は大統領就任直後に直ちにTPPからの離脱を宣言すると明言しています。トランプ氏に翻意させるのは難しいと安倍総理も認めています。TPPの条約発効には日米の批准が絶対条件ですので、このままではTPPは発効しないことになります。
それならば国会での審議自体が無意味だと野党は主張しています。しかし、TPPの代わりに日米FTA(自由貿易協定)をアメリカが要求しTPP以上に厳しい条件を突きつける可能性もあります。それを防ぐにもTPP条約が国会でも認められた日本の限界点だということを示す必要があるのです。その意味ではTPP条約の批准は大事なことだったのです。
核の傘は存在するか
またトランプ氏は、日本も韓国も独自に核武装すべきであると述べたり、同盟国にアメリカの軍隊の駐留費の負担を要求する等、日本にとっても看過できない発言をしています。後にこの発言を取り消していますが、日本の安全保障の前提に関わることです。
駐留経費については既に思いやり予算という名で在日米軍基地職員の労務費、基地内の光熱費・水道費、訓練移転費、施設建設費など多額の負担をしています。この事実を知ればトランプ氏も納得するでしょう。問題は核武装です。
日本は世界で唯一の被爆国として、核兵器を持たず、作らず、持ち込ませずという非核三原則を事実上国是としています。広島長崎の惨状を見れば核兵器の廃絶を訴えることは被爆国としては当然のことです。しかし、朝日新聞の報道によると世界で一万発近い核兵器が有ると言われています。保有国は米露英仏中のほかイスラエル、インド、パキスタン、そして北朝鮮も8発程度持っていると言われています。そして北朝鮮は、核弾頭を搭載可能なミサイルの発射実験を世界中の非難にも拘らず平気で繰り返しています。我国にとって大きな脅威であることに間違いありません。
アメリカなどの核保有国は核攻撃に対して報復核攻撃が可能です。このことが逆に核攻撃に対する抑止力となります。この報復核攻撃を日本などの同盟国が核攻撃を受けた場合にもしてくれるのなら、非核国でも核保有国並みの核抑止力を持てることになります。
こうした核の傘が有効に働くには、アメリカが必ず報復核攻撃をしてくれるという大前提が必要です。しかし、冷静に考えればこの大前提は次の様な問題をもたらします。同盟国への核攻撃に対して、アメリカが報復核攻撃をすれば、それがアメリカへの核攻撃を誘発することになります。同盟国のために開いた核の傘が、自国民への核攻撃のリスクをもたらすことになるのです。その様なリスクをアメリカはとるでしょうか。民主主義国家であればあるほど自国民にリスクをもたらす選択はできないでしょう。つまり、核抑止力は核保有国にしか存在しないと考えておくべきではないでしょうか。
岸内閣では核兵器を持つことは合憲と判断
 京都国際マンガミュージアム開館10周年記念式典に麻生大臣がお越しくださいました。
京都国際マンガミュージアム開館10周年記念式典に麻生大臣がお越しくださいました。
(麻生大臣は『マンガ・アニメ・ゲームに関する議員連盟』の最高顧問です)
昭和32年の参院予算委員会で岸総理は、核兵器を保有することは憲法違反かどうかという質問に対して、「自衛権を裏づけるに必要な最小限度の実力であれば、私はたとえ核兵器と名がつくものであっても持ち得るということを憲法解釈としては持っております。しかし今私の政策としては、核兵器と名前のつくものは今持つというような、もしくはそれで装備するという考えは絶対にとらぬということで一貫して参りたい。」と答弁し、自衛権で核保有可能だが、不保持の方針を示しています。
この頃は東西冷戦の下、核開発競争が激化した時代です。自国民を守るために核兵器の保有を合憲と答弁したのは、報復核は自衛権行使の含まれるという意味です。先の臨時国会で民進党は、稲田防衛大臣が大臣就任以前に核武装について発言したことを、内閣不一致だと責め立てましたが、これでは核武装についての議論すらできなくなり、思考停止に陥ります。50年前の方が核武装についても政治の場できちんと議論されていたのです。
佐藤内閣の非核国三原則
昭和39年に中国が核実験に成功したことから、佐藤総理は核武装の必要性を感じ、ライシャワー駐日大使に申し入れをしたと言われています。アメリカは基本的に日本の核保有を認めていません。もし認めれば、いずれ日本から広島長崎の報復がされるかもしれないと彼らは潜在的に恐れているのです。翌年の日米首脳会談でジョンソン大統領は日本の核武装に反対しながらも会談後に発表された日米共同声明では「米国が外部からのいかなる武力攻撃に対しても日本を防衛するという安保条約に基づく誓約を遵守する決意であることを再確認する」ということが発表され、これによりアメリカの核傘に入ることになるのです。
しかし、先に述べた様に現実にアメリカが日本のために報復核攻撃をするかどうかは不明ですし、事実、すると明言したことは一度も有りません。先の大戦以後日本が一度も戦争に巻き込まれなかったのは、核の傘というより冷戦体制の下、米ソ超大国の過剰な核武装が逆に巨大な抑止力を生み、結果的に戦争を押さえ込んだのです。
しかし、その冷戦体制も終焉してから28年になろうとしています。米ソ二大超大国の対立による抑止力の時代からアメリカ一強時代になりましたが、その時代も終わろうとしています。事実、トランプ氏はアメリカはもはや世界の警察官ではないと言い放っています。
戦後の終わり
日本の核武装を容認したトランプ氏もその発言を取消しています。その真意は不明ですが、背景には先に述べたように日本の核武装をアメリカは恐れている節があります。しかし、今年の夏にはオバマ大統領が初めて広島に訪問し、原爆で犠牲になられた方の慰霊をしました。そして、この冬には安倍総理が真珠湾を訪れました。大東亜戦争の始まりと終わりの地に両国の首脳が訪問したことは正に真の意味で戦後が終わったことを印象付けるセレモニーでした。これを契機に両国民のわだかまりが解消できればと願っています。アメリカが日本への猜疑心を払拭し日本が自立することを認めることと、日本が対米自立を目指すことが、日米が真の同盟関係に成るための一歩です。
残念ながら、今年で先の大戦から72年、冷戦が終わって28年になりますが、未だに日本はアメリカのよる占領政策の延長線上でしか議論ができないのです。トランプ氏の核武装容認論を契機に、自分の国は自分で守るという当たり前のことを議論すべきです。その時こそ日米が英米と同じく対等の同盟関係を築くことができるのです。
日露新時代の誕生
 自民党京都府連政経文化懇談会を開催し、多くの皆様にご来場いただき誠にありがとうございました。
自民党京都府連政経文化懇談会を開催し、多くの皆様にご来場いただき誠にありがとうございました。
昨年暮のプーチン大統領との会談がどうなったかは、この原稿を書いている時点では明らかでありません。しかし、安倍総理とプーチン大統領とは世界の首脳の中でも、政権基盤が長期的に安定しているという点では抜きん出ている存在であることは間違いありません。今までは日本の総理大臣が政権交代も含め毎年変わり続けていたため、両首脳が胸襟を開いて話す環境にありませんでした。政権奪還以後5年目に入り、内閣支持率も5割を超えています。今こそ平和条約締結に向けた協議に入るべきです。
勿論、領土問題はその後も交渉をし続けねばなりませんが、領土問題が解決しなければ平和条約を結ばないでは両国にとって不幸です。敗戦により日本はアメリカに占領されました。サンフランシスコ条約で本土の主権を回復しましたが、20年後にようやく沖縄が返還されました。この例の様に、日露平和条約締結後に北方領土返還ということもあり得るべきです。まずは、先の大戦後の不正常な日露関係に終止符を打つべきです。
かつては冷戦体制のため、日ソ交渉はアメリカ側にいる日本にとっては大変高いハードルがありました。今は既に冷戦も終わり、トランプ氏はプーチン大統領とも個人的に親しいとも言われています。日本が日露平和条約を結ぶ大きなチャンスです。
占領体制と冷戦体制に終止符を打て
トランプ大統領の誕生は、これまでの既成の枠組を一挙に変えることになるでしょう。暴論や極論も多々有り不安も付きまといますが、今こそ日本は戦後を乗り越えるチャンスなのです。日本でも政治家は、占領時代や冷戦時代の常識や枠組に縛られず、本音でものを言わねばなりません。少なくともつまらぬ言葉狩りで政治家の議論を封殺している様では、日本はトランプ大統領を始めとする新時代の政治家に対抗出来ません。
今年もこうした思いで正論を述べて行きたいと思います。本年もよろしくお願い申し上げます。
瓦の独り言
-組紐と真田紐(似て非なるもの)-
羅生門の瓦
新年、あけましておめでとうございます。今年度も「瓦の独り言」でつぶやかせていただきます。
昨年は、「紐(ひも)」で明け暮れました。まだ上映中の「君の名は」で「組紐」が空前のブームです。また、NHKの大河ドラマ「真田丸」では「真田紐」が注目を浴び、京都市内の真田紐師・江南(和田伊三男氏)のお店では猫の手を借りたいほどの忙しさだとか。
この二つの紐を混同されている方が多いと思いますが、実は作り方も、用途も異なったものです。
「組紐」は三つ編みのように数本の糸を丸台などの道具を使って、斜めに糸を交互に組んでいくものです。一方、「真田紐」は機(はた)(織り機)を使い、経糸(たていと)と緯(よこ)糸(いと)で平たい紐状の織物を織っていきます。経糸に比べて太い緯糸を強く打ち込むことにより、経糸が見えず緯糸が畝のように見える幅の狭い(最狭で6ミリ程度)織物です。
歴史的にも異なり、「組紐」は奈良時代から宮中を中心に使われ、特に重要書類などを保管する豪華な蒔絵の飾箱にかけられたものです。今でも、祇園祭の「くじ改め」の時に使われる飾箱に掛かっているのが「組紐」です。また、御婦人方の着物の帯締め、紳士の羽織紐も「組紐」です。
かたや「真田紐」は真田幸村が考案したようなネーミングですが、実は源平合戦の時代にはすでに用いられていました。「平氏」の甲冑は宮中の組紐が使われており、「源氏」の甲冑には庶民が荷駄の括紐として使っていた「真田紐」が使われていました。馬上の合戦でも「平氏」の甲冑はゆるみが多く、堅固な「源氏」の甲冑の前には歯が立たなかったとか。戦国時代には刀の下げ緒やサヤなどに使われており、「真田紐」は庶民(?)の紐でした。関ヶ原の合戦以後、九度山に幽閉されていた時に真田幸村が生産し、行商人たちに持たせて各国の動きを探っていたことにより、日本中に「真田紐」が広まったのは事実です。
この「真田紐」を千家茶道の祖である千利休が茶道道具などの桐箱に使いました。彼は権威を嫌い宮中の飾箱や「組紐」をさけて、あえて白木の桐箱に庶民の「真田紐」を用いたのです。(この反骨精神は、瓦職人の楽吉左エ門に茶碗を造らせた気持ちと同じだ、と瓦は思っています。)今でも各流儀や宗家などの独特の文様の「真田紐」を「茶道具お約束紐」「習慣紐」と呼んでいます。
さて、われらが国政を信託している西田昌司参議員の発言の中には自民党とは異なった意見が時折見受けられます。一見では「野党と同じでは?」と思う節もあろうかと思いますが、実はこの「組紐」と「真田紐」のように根本的に異なっていることに気が付いておられるのは瓦一人だけではないはずです。本年度の瓦の目標は「似て非なるもの」の根底をつかむことに心がけますのでよろしくお願いいたします。
故郷喪失の現代人
 -参議院予算委員会にて整備新幹線について安倍総理に質問しました-
-参議院予算委員会にて整備新幹線について安倍総理に質問しました-
今から150年前、明治維新の頃の日本の人口は約3300万人で、その内、東京の中心部には67万人がいたに過ぎません。京都の中心部に23万人、大阪の中心部に29万人、後は名古屋と金沢に10万を上回る人が住んでいましが、その他は数万人程度の町しかありませんでした。それが今や、総人口約1億2600万人の内、東京、名古屋、関西の三大都市圏の人口で全体の50%を超えています。
明治維新以後、近代化の中で日本の人口は約4倍になり、それに応じ経済も成長してきました。しかし、同時に故郷を喪失してきたことが、大都市圏への人口集中からも読み取れます。勿論、都市部で暮らしそこを新たな故郷としている人もいるでしょう。しかし、都市か地方を問わず、大切なのは定住することです。そこで何代にも渡り暮らしていれば、そこに思い出ができます。又、地域の人々との繋がりも深まります。思い出と人の繋がりは家族とも共有することになりますから、家族との一体感も大きなものとなります。長期間同じ場所で家族と共に暮らすことが故郷意識を育む源になるのです。現代人の故郷喪失は定住できない生活様式がからくるものであり、その原因は戦後の急激な高度成長時代にあるのです。
江戸時代以前の日本
何代にも渡り同じ地域で暮らすには、生業が必要です。明治維新の頃は人口の約8割が農民です。土地が無ければ成り立たない仕事ですから、地域に密着し何代にも渡って暮らしてきたのは当然です。
江戸時代には東北地方を中心に冷害による飢饉に襲われ、人口の増加はほとんど無く停滞していたと言われています。今日、地球温暖化が問題視されていますが、幕末には地球規模で寒冷時代が終わり、気候が安定してきだしたとも言われています。また、農業技術の進歩や、養蚕の振興などにより農村部は豊かになり人口が増加に転じます。明治以後の殖産興業政策は、製造業の近代化大型化を促し、より多くの雇用を創出しました。これを賄うために、農家の次男坊三男坊が都市へと転出し、日本は都市で経済発展を遂げることになったのです。都市の経済成長は農村部の人口増加が有ればこそだったのです。農村部が貧しくて都会に出たというよりも、農村部が豊かになり人口が増えたことが都市への人口移動を可能にしたと言えるでしょう。
戦前は農村が中心
明治維新以降、日本は殖産興業政策を推し進めます。近代化には工業製品の輸入が必要ですが、その代金を支払うためには外貨を稼がねばなりません。当時、日本が海外に輸出できるのは生糸と茶などの農産物や昆布などの海産物が中心です。特に生糸は戦前の日本の輸出品一位の座を長く保持してきました。第一次産品で外貨を稼ぎ、機械や軍艦などの代金支払いに当ててきたのです。
戦前までは都市部の発展だけでなく、同時に農村部や海辺でも産業基盤がしっかりと確立していたのです。特に、都市部が戦争で破壊された終戦直後は、経済の中心は都市部ではなく農村部だったのです。
高度成長時代も目標は国土の均衡ある発展
昭和39年の東京オリンピックを契機に、首都圏のインフラ整備が一挙に進みます。東海道新幹線や高速道路の整備が進み、特に太平洋側ではこうしたインフラ整備に合わせて、産業集積が進みます。高速道路や新幹線の全国整備もこの時代に決定されます。
昭和37年、池田内閣で全国総合開発計画が策定され、地域の均衡ある発展を基本目標に掲げ、都市の過大化防止と地域格差是を基本課題とし、目標達成のためには工業の分散化が必要であり、各地域で拠点開発を行うという目標が掲げられました。
戦後の高度成長時代には既に都市部への人口集中が問題となり、農村部との均衡が問題となっていたのです。単に経済成長をさせるのでは無く、日本全体を如何に均衡ある発展をさせるかということが政治の課題だったのです。
次いで昭和44年佐藤内閣の下、新全国総合開発計画が策定されました。新幹線、高速道路等のネットワークを整備し、大規模プロジェクトを推進することにより、国土利用の偏在を是正し、過密過疎、地域格差を解消するということが掲げられました。目標年次は昭和60年でしたから、北陸新幹線も本来ならこの時期に完成していたのです。しかし、残念ながら、昭和52年に第3次全国総合開発計画に変更され大型プロジェクトは事実上棚上げされてしまいます。
オイルショックとバブル崩壊で成長神話崩壊
その原因は、ニクソンショックによるドル切り下げや第一次石油危機などにより経済が危機に陥ったことや、急速な経済成長の結果、地価が高騰し狂乱物価と言われたほどインフレが深刻化するなど、社会経済環境が悪化したことが挙げられます。
過大投資がインフレを招き、経済を毀損するのは事実です。インフラ整備への投資が悪いのではなく、経済の実態を見ながら経済を過熱化させずに節度ある投資をすれば良かったのです。しかし、何よりも新幹線の事業主体であった国鉄が毎年巨額の赤字を垂れ流し、事実上経営破綻したことが新幹線整備を遅らせた最大の原因です。
昭和62年、国鉄が事実上経営破綻し、国鉄は分割され民営化されました。そして新幹線の整備は国の予算により一般の公共事業枠の中で行われるようになります。
昭和の終わりから平成の始めは好景気が続きましたが、結局これはバブルだったため、その後の日本はその反動のため長期低迷が続きます。民間企業は生き残りを賭け人員を整理し事業を縮小していきます。バブルに浮かれた反省から清貧の思想が流行り、世の中全体が経済成長よりも債務整理を優先すべきという風潮に流されて行ったのです。こうしたことの結果、公共事業不要論が横行し、公共事業の予算は激減してしまいました。
公共事業費削減が新幹線開業の妨げ
その結果、新幹線の整備は中々進まず、昨年漸く北陸新幹線の東京・金沢間が開業しましたが、工事着工から26年かかっています。国鉄時代にでは、東海道新幹線は着工から5年、山陽新幹線でも8年で全線開業していますからその差は歴然です。整備新幹線は公共事業方式になりましたが、鉄道予算は極めて少ないのです。本年度の公共事業予算6兆円のうち1000億円しか有りません。そのうち新幹線は755億円でそれを北海道や北陸や九州の各新幹線に配分しているのでから、この調子なら私たちが生きているうちには北陸新幹線が京都まで来ることは有りません。北陸新幹線全線の早期開業には予算の大幅アップが欠かせません。
そもそも、現在着工している新幹線は採算性も認められているのですから、1日も早く全線開通させる方が理にかなっています。これは高速道路などの建設についても同じことが言えます。予算をつければ短期間で開業できるにも拘らず、それができないのは予算のシーリングがあるからです。
予算シーリングは臨機応変に考えるべし
財務省は来年度予算を作る際、各省庁から概算要求を受けた内容を査定して全体の予算を積み上げます。どの省庁も必要な予算を要求しますから、これを全部受けていたらキリが有りません。そこで、経済や財政の状況を考えた上で、毎年前年比何%プラスというような全体予算の骨格がつくられます。これがシーリングです。この仕組みは一般論としては正しいことです。しかし、現実は一般論では語れません。個別の具体的状況をしっかり認識して臨機応援に予算措置をすることが肝要です。
その中でも、公共事業費は、将来に対する投資ですから早く完成しなければ意味が有りません。そしてその財源は基本的に税金ではなく建設国債です。その事業がもたらす経済効果の結果、国全体の所得が大きくなり、将来の税収が増える、その将来の税金で国債を償還するということです。従って、将来の経済効果が期待できるものならばさっさと作るのが正解です。
全ての新幹線基本計画を実行すべし

私は、北陸新幹線の与党敦賀以西検討委員会の委員長を務めていますが、北陸新幹線だけで無く全国に新幹線のネットワークを築くべきだと主張し続けています。元々、昭和48年に全国で11の新幹線基の基本計画が決定しています。リニア中央新幹線もその中の一つです。(図①)
この計画が実現出来れば全国の各地域が新幹線で結ばれることになります。経済成長に寄与することは勿論のことですが、何よりもそれぞれの地域に住む人達にどれ程喜ばれることでしょう。
現在の新幹線は東京に接続する路線を中心に整備されてきました。その結果、東日本は比較的に充実した新幹線ネットワークを構築できましたが、西日本はまだまだです。四国や山陰、また新潟から東北の日本海側などは全く高速交通ネットワークの恩恵に預かっていません。 そして、新幹線ネットワークから取り残された地域では過疎が進んでいます。今年の参院選挙では鳥取と島根、徳島と高知が合区されたのはその象徴です。代表無くして課税無しと言われますが、一県一代表すら出せなくなっては民主主義の根幹を揺るがす事態です。
西日本での新幹線整備の遅れが、東京一極集中と地方衰退に拍車を掛けてるのは歴然たる事実です。地方創生という安倍内閣の看板政策を実現するためにも全国新幹線基本計画を1日も早く実現する必要があるのです。
実現には国家プロジェクトが必要

全ての新幹線基本計画を実現するにはかなりの国家予算が必要ですが、先ず何年で完成させるかという事を決める事です。また、どの新幹線基本計画から始めるかという優先順序を決める事も大事です。何れにせよ、先ず与党が実現に向け議論を始めることが必要です。
私が、北陸新幹線で舞鶴・学研・関空ルートを提案しているのは正にこのためなのです。舞鶴の意味は将来の山陰新幹線延伸のためです。学研都市は将来の中央リニア新幹線との接続のためです。そして関空は将来、和歌山から淡路島を通り四国新幹線に延伸するためです。(図②)
そうした構想を語ることが西日本全体で新幹線基本計画を実現するための世論を形成し、基本計画を国家プロジェクトに格上げすることになるからです。公共事業不要論が罷り通っていたこの20年の国論を変えねばならないのです。
今こそ故郷再生
これまで何度も述べてきました様にバブル後の規制緩和政策の行き過ぎが、東京一極集中を招き、地方の衰退をもたらしました。地方創生のためにもその是正が必要です。
しかし、もっと大切な事は、地方創生というより故郷を守るという当たり前の感覚を取り戻す事ではないでしょうか。
それにはまず我々政治家は選挙区では無く、故郷を思う心を持つべきです。それが政治の原点なのです。
樋のひと雫
羅生門の樋
今、南米では大きなうねりが起ころうとしているように感じます。2年ほど前から反米左派政権は退潮を始めました。農産物や地下資源の輸出に頼る工業生産手段を持たない国々にとって、最大のパトロンであるチャベスの死は、経済的な困窮の引き金でした。ブエノスアイレスに行くと街角に立つ「カサ・デ・カンビオ(両替屋)」の呼び込みの数は昨年より増えています。ペソ安は昨年より進んでおり、未だに左派政権の経済失政の重荷を負っています。また、ベネズエラの友人の話では、物価の高騰は相変わらずで、買おうにも物そのものがないという話です。チャベスの後継者を自認する現政権は、それでも往年の夢を未だに見ているかのように他国の経済支援を謳っています(実際はどうか分かりませんが)。圧倒的な人気を誇っていたボリビアのエボ政権も、4選目の大統領就任を目論見、多選を禁じた憲法の改定を行おうとしましたが、国民投票でNOを突き付けられました。あれだけ元気が良かった反米左派政権も、オイルマネーの瓦解がその退潮を速めているかのようです。
しかし、この変化は単に経済事情だけが原因でもなさそうです。その震源地はキューバです。今年3月のオバマ訪問は、キューバ国民だけでなく多くの反米政権下の民衆にも衝撃だったようです。それまでの経済開放で、何となく理解していたものが、映像で流れると改めて社会主義の終焉を感じたと友人は話してくれました。「あのキューバでさえ、社会主義を捨てざるを得なくなった。」「オバマが飛行機を降りてきたとき、キューバでなくなった。」と言っていた言葉が印象的でした。一片のニュースが、多くの民衆の意識にも変化をもたらせたようです。
さて、ボリビアではどうでしょう。各地で反米政権が求心力をなくしている中で、「反帝国主義学校(Escuela Antiimperialismo)」なるものを創設し、ペルーやエクアドル、ベネズエラなど5か国から軍人を募り教育するそうです。内容は余り公表されていませんが、文脈からすると米国から各国の主権を守るようなことが書かれていました。このような動きの中で、政権中枢の副大臣(総務、警察担当)が8月にデモ隊に殺されました。ラパスとオルロを結ぶ幹線道路を封鎖していた鉱山労働者と話し合うために出掛けたのですが、労働者に捕まり殺されたようです。元々、COBという鉱山労働者の組合は、現政権の有力な支持母体です。今まで政権も様々な融合処置を与えてきました。組合幹部とのボス交で話しは落ち着きましたが、政権のタガが緩み出したことを民衆の目に晒しました。かつて、実力で軍事政権を倒したCOBは、統制力も大したものでした。大規模なデモは行っても正面からの衝突は避けていました(政権や警察も遠慮をしていましたが)。
この殺人が意図的なものか、偶発的な事故なのかは分かりません。(未だ、情報が全て公表されている様には思われません。)しかし、今まで民衆の意識が理念や権威で繋がっていたものが、漂い始めた気がします。主義や理想と云ったものが、現実の前に色褪せたとき、人々の意識の漂流する先には何が見えてくるのか。近い将来にその答えが見えてくるのかもしれません。
イギリスのEU離脱
 -安倍総理に参議院選挙「後」の経済政策について提言をいたしました-
-安倍総理に参議院選挙「後」の経済政策について提言をいたしました-
イギリスでは、国民投票によりEU離脱が決定いたしました。このことを受け、ユーロやポンドは売られ、株価は世界的に大幅に下落しました。正に、世界経済は混迷の時代に突入しています。
ヨーロッパの国境を無くし、一つの市場として発展していくという理想にヨーロッパの人間でない日本人は何の疑問も無く共感していたようです。その為、日本国内では、国民投票で離脱派が勝つことは予想外であり、何故イギリス人が離脱を選択したのか理解できない、という戸惑いの報道に終始しています。挙句の果てには、あれほど民意を重視していたマスコミが、軽々に国民投票などすべきでない、とヒステリックに報道しています。これには私も呆れましたが、EUについては当初から様々な問題があったのです。
EUとはアメリカに対抗するためのグローバリズム
イギリスのEU離脱には様々な原因がありますが、根底に有るのは、冷戦後世界の主流となったグローバリズムに対する疑問です。元々、イギリスは大陸のヨーロッパとは違う海洋国家です。冷戦後、アメリカ一極体制に対する防波堤としてEUに参加したものの、ユーロによる通貨統合を拒否しポンドを守ってきました。
冷戦後のグローバリズムとは、ヒト、カネ、モノが国境を越え自由に移動できる仕組みを作れば、世界経済は大いに発展するはずだとする考えです。この考えを進めると言葉や人種、宗教、文化など人間社会の根本的枠組みを無くすことになります。これにより、国家の主権より企業活動を優先できることになりますから企業にとっては便利な制度です。そして実際、企業の業績も大きく伸長しました。
しかし、その結果、人間社会には大きな爪痕を残すことになりました。先ずは移民の問題です。EU域内では自由に行き来することができるため、東ヨーロッパやイスラム諸国からイギリスなどの西側先進国に大量の移民が押し寄せて来ました。結果として、彼らは先進国の国民の雇用を奪うことになりました。また、短期間に大量の移民が押し寄せたため、地域の伝統社会とも軋轢を生み出すことになりました。そのため、グローバル企業にとっては業績を伸ばすことのできる良い制度でも、先進国の国民にとっては自分たちの雇用を奪い伝統的社会を破壊する酷い制度でしかなかったのです。そうした潜在的な国民の不満が今回の国民投票により示された訳です。従ってこれは、イギリスに限った話ではありません。他の国でも国民投票をすれば同じような結果になる国もあるでしょう。これは、企業が国境を越え自由に活動できるグローバリズムという名の経済至上主義に対して人間社会が反旗を翻したと解釈すべきです。
日本における新自由主義も根は同じ
 -木村弥生衆議院議員の京都3区支部長就任に伴い、記者会見を行いました-
-木村弥生衆議院議員の京都3区支部長就任に伴い、記者会見を行いました-
こうした経済至上主義は日本においても社会を席巻しました。バブル後の規制緩和路線はその典型で、企業活動に妨げとなる法律やルールを撤廃すれば民間投資が進み経済は成長するはずだと、多くの学者が喧伝しました。またマスコミもそれをもて囃しました。その結果、起きたのが地域間格差です。規制緩和により容積率の引き上げられた首都圏を始めとする都市部ばかりに投資が集中し、他の地域の雇用を奪う結果になりました。企業にとっては効率的投資のできる良い制度でも、人間社会にとっては社会を分断する悪しき制度であることは今や誰の目にも明らかでしょう。
アベノミクスは輸出促進一辺倒ではない
さて、イギリスのEU離脱や中国経済の減速などにより世界経済は混乱し、日本の株価も下落しました。マスコミや野党は、円高と世界経済の低迷で輸出企業の業績が下がるのはアベノミクスの失敗だったと主張していますが、全くの見当違いです。そもそも、日本をデフレの底に落とした民進党などの旧民主党の方々にアベノミクスを批判する資格はありません。
そもそも、アベノミクスの原点は、一つに日銀の異次元の金融緩和、二つに機動的財政出動、三つに民間投資による成長戦略です。輸出促進という点では世界経済低迷の影響を受けた部分があることは否定できませんが、二本目の矢である機動的財政出動はいわゆるグローバリズム路線とは一線を画すものです。これは、民間企業に自由に投資をさせるだけでなく、政府が各地域、各産業など、国全体を見渡してこれから必要となる投資を積極的に行うという意味です。この様に安倍総理は財政出動の役割の重要性について明言しているのです。
野党やマスコミこそグローバリズムに飲み込まれていた
事実、安倍総理が四年前に政権を奪還した時には、積極的に財政出動をして景気を押し上げていたのです。その時これをばらまきと否定していたのが、当時の民主党でありマスコミ出会ったのです。「コンクリートから人へ」や「事業仕分け」に象徴されるように、財政カットが民主党やマスコミの一貫した姿勢です。彼らは、財政出動を利権や癒着の温床と決めつけ、これを削減することが正義だと思い込んでいるようです。勿論無駄な財政出動は必要ありません。しかし、東京ではインフラ整備が完成していても、地方ではまだまだ不十分です。地方には人が少ないから無駄な投資だという彼らの理屈は、結果的には東京への一極集中に拍車をかけるものでした。
そもそも財政出動を無駄なものとする考え方自体が、グローバリズムにより刷り込まれたものであり誤りです。先述したように、冷戦後の世界潮流として、企業活動に不利益な国境や規制を取り払うという経済至上主義が世界中に蔓延しました。そしてこの考え方の延長線上に、法人減税や財政出動を減らすことにより、官から民へ資金をシフトさせることを正当化してきました。政府より企業の方が効率的な投資をするはずだから、企業が自由に使える資金の量を増やせば社会は効率化し経済は成長するはずと思い込んでいたのです。
しかし、これが間違っていたのは今や自明です。企業は儲かることにしか投資しませんから、投資先は偏ったものとなりました。成長率の低い先進国から成長率の高い後進国へ投資が移り、先進国の中でも都市部にのみ投資が集中しました。
その結果、先進国は投資が不足しデフレに陥りました。また都市部と地方との間で投資の格差が起き、同じ国の中でも分断現象がおきました。また後進国も多額の外資による投資で経済成長はするものの、他の国にもっと良い投資先が見つかれば直ちに外資が引き上げられ、経済は大変不安定になりました。こうした事はこの20年の国の内外を省みれば明らかです。残念ながら、野党もマスコミもこうした事実を全く理解していません。
アベノミクスの本質は財政出動を認めたことにある
 -参院選の選対本部長として二ノ湯候補の応援に府下各地を回りました-
-参院選の選対本部長として二ノ湯候補の応援に府下各地を回りました-
構造改革が叫ばれ、官から民へと言う考えは自民党政権の時代にもありました。しかし、これが東京一極集中と地方の疲弊をもたらし、日本全体をデフレ化させたのです。野党時代に自民党の政策の誤りを安倍総理を交えての勉強会で、私は再三にわたり指摘をしてきました。
その結果、アベノミクスの二本目に矢として機動的財政出動が記載されたのです。そして、政権奪還した直後は、財政出動が実質的にGDPを押し上げたのです。金融緩和により円高が是正され、輸出企業の業績を回復させたことと共にアベノミクスの成果を証明するものでした。残念ながら、積極的財政出動は1年目にしか行われず、その後は消費税の増税を行うなど財政再建路線に方向転換してしまいました。その結果、完全なデフレ脱却には至らなかったのです。安倍総理はその時の反省から、消費増税を2019年の10月まで再延期することを決断されました。
10兆円を超える補正予算とシーリング解除が必要
しかし、増税の延期だけでは経済は好転しません。世界経済の混迷により外需が期待できないため、内需拡大をもたらす事業が必要です。私が提唱する新幹線ネットワークの構築はその典型です。また、高速道路の拡充も必要です。昨年、京都縦貫自動車道は完成しましたが、暫定二車線区間がかなり有ります。高速道路で対面通行をすれば正面衝突のリスクが高まり、事故の死亡率は格段に増えます。追越車線がないため高速道路が低速道路になっています。道路整備はまだまだ不十分です。 こうした事業を完成させるには、5年から10年はかかるでしょう。補正予算でスタートダッシュは出来ますが、長期にわたる事業を完成させるには、補正予算ではなく、毎年の当初予算のレベルを上げなければなりません。これを妨げているのが、予算を対前年比でコントロールするシーリングという仕組です。無駄を排除し予算の規律を高めるためには意味が有りますが、財政出動によるデフレ脱出が必要な時期には不要です。
参院選与党勝利により株価は上昇しています。市場は大胆な財政出動を期待しています。市場が驚くほどの超大型の補正予算と新幹線ネットワークの様な国民に夢を与える政策の提言が今こそ必要なのです。
瓦の独り言
-インバウンド2,000万人を超える-
羅生門の瓦
「インバウンド」って、聞きなれない言葉なのでネットで調べてみました。日本から外国へ出かける(海外旅行)ことを「アウトバウンド」とよび、その反対です。つまり日本へ外国人が訪れることですが、これが年間2,000万人を超えるというのです。そういえば、京都市内の観光地はもとより百貨店、スーパーマーケット、スーパー銭湯、居酒屋、さてさて「ねこ喫茶店」まで、あらゆる場所で外国の方に出会います。それも中国、韓国などのアジア系の方だけではなく欧米系の方が増えています。
観光庁(平成20年に設置)によると、訪日外国人の一人当たりの旅行支出額は176,168円、旅行消費額は3兆4,771億円と言われています。そう言えば中国人の購買現象を「爆買い」と称して流行語大賞にもノミネートされたとか。
南区においても地下鉄「九条駅」の近くのホテルから朝に大きなスーツケースをガラガラと引いた一個連隊が京都駅に向かう光景をよく目にします。このスーツケースのガラガラ音が本願寺さんの周辺では騒音(?)らしく、お年寄りが迷惑しているとか。
さて、このインバウンドで京都を訪れている外国人は何を期待しているのでしょうか?2つのグループがあると思います。「お稲荷さん」「金閣寺」「清水寺」などの観光地を訪れて、焼き鳥、焼き肉、ラーメンを食べるグループ。名所旧跡は行き飽きた、無理に予約してでも京懐石料理を食べたいと思うグループに分かれます。後者のグループには欧米系のデープな考えの外国人(仏・独)が多く、場合によれば日本人より日本のことに詳しかったりして・・・。後者のグループの観光客を満足させることが重要であることはだれの目にも明らかなのですが、その手法がわからない。特に、「京ものに触れたい」「京都の伝統産業を知りたい」と希望される。でも、どこへ行けばいいの?誰に紹介してもらうの?
そこで、この要望に応えるため、京都市(京都伝統産業ふれあい館)では「京都工房コンシェルジュ」なるサイトを立ち上げました。瓦もお手伝いをさせていただいております。これは京都にお越しの内外のお客様に、気持ちよく「伝統産業の工房」を見学していただき、また体験もしていただくものです。訪問先の工房にはそれなりの対応(語学、習慣etc)が可能となっております。
これからは、数の勝負ではなく、質の勝負です。質で勝負するには十分な論議、準備が必要なことは言うまでもありません。(憲法改正もしかりです) これは、われらが信託し、国会に送り出している西田昌司参議院議員も同様なお考えを持っておられる、と思っているのは、瓦一人ではないはずです。
スティグリッツ、クルーグマン両教授の指摘
 京都市長選挙 門川大作さんが見事に当選され、
京都市長選挙 門川大作さんが見事に当選され、
喜びの万歳三唱
3月16日に世界経済について有識者と意見交換する「国際金融経済分析会合」が官邸で開催され、講師としてノーベル経済学賞の受賞者であるジョセフ・スティグリッツ米コロンビア大教授が招かれました。また、22日には同じくノーベル経済学賞を受賞したポール・クルーグマン米ニューヨーク市立大学大学院センター教授が招かれ、両教授から来年4月の消費税の延期が提言された旨、報道されました。会談内容は非公開であるにも拘らず、この様な報道がなされた背景には、両教授ともにデフレ下での消費増税にはもともと消極的な立場であったことが挙げられます。増税延期への布石と解釈したマスコミ報道ですが、両教授の真意は別のところにあります。
クルーグマン教授が後日公開したブログの中で述べられていることは、消費税の増税延期のことではなく、財政出動の必要性についてです。「デフレから脱出するためには3年間財政収支のことを気にせず政府が財政出動することが必要である。日本は自国通貨の国債であり、国債残高が多かろうがギリシャの様に破綻することはない。低金利の現況においては国の債務残高よりも将来デフレが続いているのかどうかが遥かに重要である。今は財政収支など気にする様な状況ではない」。
スティグリッツ教授も同様の主張をされています。「緊縮財政を止めるべき。財政赤字に対する厳重な制約が失敗であった。増税と歩調を合わせた支出拡大が経済を刺激する。必要なことはインフラとテクノロジーへのより積極的な投資である」つまり、二人の主張は、財政赤字など気にせず積極的に財政出動をすべきであり、予算のシーリングを緩和して持続的な長期投資をすべきだということです。これは私が何年も訴え続けてきたことと全く同じです。
財政出動に対する誤解
したがって、今回のマスコミでは消費増税の再延期が既定路線になったかの様な報道は、私には両教授の主張とは違う方向に世論が誘導されていると思えて仕方ありません。
なぜなら、その背景には、依然として0財政出動イコール無駄なバラマキという誤解が根強く存在しているからです。
バブル崩壊後、民間や政府に消費や投資よりも節約を優先する風潮があまりにも蔓延してしまったことがその原因です。確かに、無駄を排しできるだけ節約することは日本人の美意識にも叶います。しかし、その結果誰もがお金を使わなくなれば経済は成り立たなくなることは自明の理です。この様に個別的には正しいけれども全員がそれをすれば社会が成り立たない様な個と全体の矛盾を合成の誤謬と言います。まさに財政出動イコール無駄なバラマキというのはその典型でしょう。
デフレからの脱出には脱出速度が必要
 TOKYO MX「西部邁ゼミナール」に
TOKYO MX「西部邁ゼミナール」に
出演いたしました
さて、クルーグマン教授は、デフレからの脱出には、脱出速度が必要であると述べています。人工衛星を打ち上げるには、地球の重力圏から逃れるだけの速度が必要です。これを地球脱出速度と言い、これより速度が遅いと何度打ち上げてもロケットは地球の重力圏から脱出できず、地球に舞い落ちてしまいます。同じ様にデフレ脱出には短期的に徹底的な財政出動が必要であり、少ない財政出動では何度やってもデフレに舞い戻りデフレ脱出に失敗するということで、誠に分かりやすい例えです。
元々アベノミクスは大胆な金融緩和と機動的財政政策と民間投資を喚起する成長戦略の三本の矢から成る総合的な経済政策が売り物でした。しかし、現実は日銀の金融緩和は継続していますが、機動的財政出動は政権復帰時の一年だけでその後は減り続け、公共投資は民主党政権以下の水準に戻っています。その結果、民間投資も中々伸びない状況が続いています。これはデフレ脱出速度が足りなかったということです。最初は勢いよく発射したロケットでしたが、このままではデフレの引力圏から脱出出来ず、またもやデフレに落ち込んでしまいます。デフレ脱出のためには第二段目のロケットに点火をする必要があるのです。
財務省の判断の誤り
財政出動が2年目以降は継続されず、逆に消費税を5%から8%に増税した結果、アベノミクスにブレーキがかかり、デフレからの脱出速度が不足しているが日本の現状でしょう。この背景には、財政出動の継続を拒み財政再建のため増税を急ぎすぎた財務省の判断ミスがあることは否定できません。
3年前、消費税8%への増税の是非を自民党税制調査会で議論していました。この時も私は「今は増税の時期ではない、完全にデフレ脱出してからにすべきだ。もしどうしても増税するなら、増税額以上の財政出動をすべきだ。さもないとデフレに舞い戻る恐れがある」ということを再三主張してきました。正に今日の日本の状況は私が心配をしていたとおりになっています。
アベノミクスでロケットスタートを切った第二次安倍政権でしたが、消費増税が早すぎたため、そして財政出動を継続しなかったために、景気回復は足踏み状態になっています。これが安倍総理には大きなトラウマになっているように思われます。10%への再増税を1年半延長し衆院の解散で信が問われましたが、さらにまた再延長があるのではないかという憶測から衆参ダブル選挙も噂されています。
先進国の「日本化」
ところで、ノーベル賞の両教授は共に積極的な財政出動が必要と述べています。その理由は単に経済政策としてだけでなく、そもそも先進国が需要不足に陥っているからなのです。特にクルーグマン教授は、先進国の「日本化」を指摘しています。
先進国では、経済のグローバル化により民間投資は海外に流出し、国内では民間投資が減少します。一方、高い生活水準を保つために年金や医療介護は勿論のこと、教育やインフラ整備など公的分野での投資が必要になります。本来こうした公的分野での投資が民間投資の減少による需要不足を補うことになるのです。
90年代以降日本ではデフレが進行していますが、その最大原因は経済のグローバル化による民需の喪失を公需で穴埋めしなかったためです。ゆえに、その様にデフレが長期に渡り進行している状態を「日本化」と言い、それが世界に広まりつつあるとクルーグマン教授は指摘しているのです。
リーマンショック後の世界経済を牽引してきたのは中国でしたが、その成長に翳りが見えてきました。牽引車が失速すれば世界経済は景気の停滞局面には入らざるを得ないでしょう。これを放置すれば世界は長期デフレに陥り、正に「日本化」してしまいます。
それを止めるには政府が財政出動をして公需を増やすしかないのです。世界を「日本化」から救う為に、先進国が協調して財政出動をすることの必要性をクルーグマン教授は説いているのです。
今こそ生活水準を欧米並に引き上げるチャンス
 西田昌司京都政経パーティーを開催いたしました。
西田昌司京都政経パーティーを開催いたしました。
各方面より多数のご参加を賜り、誠にありがとうございました。
日本では元々欧米先進国に比べ、こうした公的分野への投資は少なかったのですが、戦後の経済成長が民間部門の国内投資を増加させてきたお陰で、需要不足になることなく経済は拡大してきたのです。したがって経済がグローバル化して民間部門の投資が少なくなってきた今こそ公的分野での投資を増加させ生活水準を欧米先進国並に上げるチャンスです。
例えば、街づくりです。欧米先進国で日本の様に東京一極集中している国は有りません。そもそも、日本ほど大都市に人口が集中している国は有りません。これはアジア的な現象です。インフラが大都市にしか整備されず、産業が大都市に集中した結果です。これは豊かさでなく貧しさの象徴でしょう。この結果、地方が寂れ故郷や家族の喪失感を感じている人も多いのではないでしょうか。今こそ、東京一極集中を是正し財政出動で故郷と家族の再建に取り組むべきなのです。
私が提案している北陸新幹線の舞鶴ルートもそのための具体策です。これは、日本海側と京都、学研都市、大阪、関空を結ぶことで東京に対抗できるメガリージョンを創設するためのものです。
伊勢志摩サミットに向けて
冷戦崩壊後の、資本の自由化は大きな富を各国に与えた反面、多くの傷跡も世界中に残してきました。資本を自由にするだけでなく、それを世界各国が管理することも必要です。各国協調で財政出動するということは、行き過ぎた資本論理に対して国家が警鐘を鳴らすという意味であり、正にサミットに相応しい議題です。伊勢志摩サミットでは、世界経済のデフレ化を止めるために世界各国が協調して財政出動をすべきだと議長国日本の安倍総理から提言されることを多いに期待したいと思います。
そのためにも先ず、「隗より始めよ」です。日本が率先して財政出動をすべきです。積極財政を阻害するPB(プライマリーバランス)論やそれに基づく予算のシーリングなどのデフレ下では無用の論理に振り回される必要はありません。スティグリッツ、クルーグマン両教授はこのことを総理に提言されたのです。
樋のひと雫
羅生門の樋
先日オバマ米国大統領がキューバを訪問し、ラウル・カストロ国家評議会議長と国交再開に向けた握手を交わしました。ラウルがオバマの右手を高く掲げている写真を見て、世界の変化を感じられた方も多かったのではないでしょうか。1959年フィデル・カストロとチェ・ゲバラに率いられた民衆が腐臭を放つバチスタ政権を倒した後、農地解放を契機としてフィデルはアメリカと袂を分かちました。そして、彼は社会主義政権樹立を宣言すると共に、当時のソビエト連邦の庇護下に入ります。'61年の国交断絶と'62年1月の米州機構からの除名を経て、米国がソ連によるミサイル配備を阻止しようとした'62年10月のキューバ危機は余りにも有名です。10月22日の米国の海上封鎖から始まり、28日のソ連輸送船団の撤退までの1週間は、世界核戦争を現実のものとした日々でした。(映画の素材にもなりましたので観られた方も多いのではないでしょうか。)
人民の解放と社会主義建設を担う老練な政治家と自由主義の旗を掲げた新進気鋭のカリスマの激突は、共に譲ることの出来ない陣営の未来を掛けた戦いでもありました。双方に非難の応酬と表面的には軍事の駒を進めながら、外交戦術を駆使する。自らの決断の一つひとつが、数十億の人類の生存を担っているという政治家の葛藤の闘いでもあったと思います。また、この超大国の衝突の中で、当時35歳のフィデルは米国に屈することなく、生まれたばかりの新生キューバを守り抜きます。後々50年以上にわたる経済封鎖と云う犠牲を払いながら。
2大強国の争いの中で、国の行く末と民衆の生存権を守るために苦悩する若き指導者の姿を見るのは私一人ではないでしょう。オバマのハバナ訪問を、疲弊した経済を立て直すために弟のラウルは歓迎します。オバマの人権の尊重と政治犯の釈放という発言に対して、ラウルは刑務所の見学を提案しますが、兄のフィデルは「帝国主義の贈り物は要らない」と答えました。何度も米国による暗殺を逃れ、激動の世界情勢の中でキューバを守ってきた老政治家の矜持の一言であったように思えます。
初めてハバナを訪れた時、電力も乏しい暗い街並を見ながら飲んだCuba Libre(キューバ特産の酒ロンをコーラ割ったもの)を思い出します。コーラが自由の味なのかと自問しながらホテルで飲んだカクテルは、農奴然とした生活から解放された民衆が、次に人間としての自由を求めて創った味だったのかも知れません。
地方を歩いて分かる悲惨な実態
 「成人年齢に関する特命委員会」がまとめた報告書を安倍総理に提出いたしました
「成人年齢に関する特命委員会」がまとめた報告書を安倍総理に提出いたしました
多忙な国会の合間をぬって、一昨年は旧東海道と旧中山道を踏破し、昨年は奥の細道を自転車で完走しました。大自然の美しさに圧倒され、思わず顔がほころんだりする場面もある一方で、何度も転び、トラックに轢かれそうになったことも有りました。そんな中で、最後まで完走できたのは、この日本の故郷の美しさに魅せられたからです。だからこそ、そこに人がいない、まるで廃村の様な寂れた風景には胸が痛みました。
一昨年の春に、有識者らでつくる政策発信組織「日本創成会議」の人口減少問題検討分科会(座長:増田寛也 元総務相)が、2040(平成52)年に若年女性の流出により全国の896市区町村が「消滅」の危機に直面する、という試算結果を発表しました。これは絵空事ではありません。長寿化のお陰で今は辛うじて人口維持が出来ていても、お年寄りばかりでは子どもは生まれません。このまま2、30年も経てば全国の至る所で町が消滅することを地方の町々を見て実感致しました。
東京一極集中が東京をも滅ぼす
しかし、これは地方の問題だけではありません。実は東京もいずれは同じことになるのです。東京をはじめとした首都圏には仕事を求めて全国から人が集まっています。しかし、その人達が急速に高齢化しているのです。その大きな理由は、かつて地方から上京してきた若者たちが年齢を重ねたことに加え、故郷の老親を呼び寄せているからと言われています。
昨年の産経新聞の報道では、総務省が発表した住民基本台帳に基づく人口動態調査(昨年1月1日現在)によると、国内の日本人は前年よりも27万1058人減少して1億2616万3576人となったそうです。6年連続の減少で、減少数は調査を開始した昭和43年以降で最大となり、9割近い市町村で人口が減る一方、東京都は0.57%増となるなど一極集中がさらに進んでいます。
実は、東京へ人口が集中すればするほど日本全体の人口は急激に減少するのです。その理由は東京では子どもが生まれないからです。平成26年の数値ですが、東京都の合計特殊出生率は1.15人で全国平均の1.45人を大きく下回っています。このままこの状態を放置すれば東京は日本全体の人口を減らし続けるブラックホールになってしまいます。
更に、東京では今後急速に高齢化が予想されるため、介護施設などをまだまだ建設し続けなくてはなりません。日本創成会議によると東京都と周辺の3県で、2025年に介護施設が約13万人分不足するとの推計を発表しています。また、保育所などの待機児童も23区だけでも8000人近くいます。一方で、地方の町では既に高齢化が進み介護施設にも将来は空きが予想され、待機児童も存在しません。東京では今後、介護や子育ての施設がまだまだ必要となりますが、地方ではそれらの施設が余っているのです。
つまり、東京と地方の人口構造のアンバランスが、不必要な投資を余儀なくさせているのです。無駄な公共事業をするなと言いますが、これこそ無駄な投資そのものです。東京と地方の人口アンバランスを是正すればこれらの投資はいらなくなるのです。
東京一は枝葉、地方が根幹
元々、首都である東京はインフラ整備も進んでいますから、他都市より人口が多いのは当然のことです。しかし、現代の東京はその限度を超えています。折角インフラ整備が出来上がっても、人口過密が進めば許容量が不足し、鉄道なども二重路線の建設を余儀無くされてしまいます。これも本来無駄な投資なのです。しかし、人口過密のお陰で利用客には事欠きませんから、無駄な投資でも儲けることができるのです。人口過密が、二重路線という無駄な投資を経済合理性に叶うものに変えてしまうのです。しかし、この経済合理性も短期的なことに過ぎません。長期的に見れば、東京一極集中が地方を破壊し、人口減少を加速させ、最終的には東京自体が超高齢化で自壊してしまうのです。
日本全体を木にたとえるなら、東京は枝葉で地方は根幹です。東京という枝振りが良ければ日本という大木は成長している様に見えますが、肝心の根が腐り幹に穴が空いていれば、いずれはどんな大木も倒れてしまします。東京に人材や食糧やエネルギーを供給してきた地方が破壊されれば、東京も存在できないのです。東京と地方の過密と過疎を解消しない限り、デフレからの回復もないのです。
予算カットと規制緩和が東京一極集中を招いた
 藤井聡内閣参与と共に稲田朋美 自民党政調会長に10兆円規模の補正予算の申し入れをいたしました
藤井聡内閣参与と共に稲田朋美 自民党政調会長に10兆円規模の補正予算の申し入れをいたしました
では、何故ここまで東京一極集中が進んでしまったのでしょうか。それはバブル崩壊後の政策の誤りにあります。この時期を契機に公共投資が否定され、予算が大幅にカットされたからです。その背景には、企業が身を切る努力をしてリストラしているのに、政府ばかりが借金で事業を増やしているのはおかしいという意見がマスコミを通じて多数派になってしまったことがあります。
この意見は素朴な庶民感覚としては納得できるかも知れませんが、国家全体の経済を考えれば全くの誤りです。民間がリストラしている時に政府も事業のリストラをすれば景気が一挙に悪くなるのは自明の理です。結果、この後日本は長いデフレのトンネルに入ってしまうことになります。
政府が公共事業などの予算をカットする一方で、民間投資を促進するために規制緩和が推奨され、東京の一極集中は加速度を増して進むことになったのです。
東京駅に見る規制緩和の実態
東京駅の改修が2012年完成しました。この保存・復元工事にはおよそ500億円の費用がかかったそうです。JR東日本はこの費用を建物の容積率、いわゆる「空中権」を売って調達したということです。容積率とは敷地に対してどれくらいの規模の建物を建てられるかを示すもので、復元された東京駅の駅舎は定められた容積率の20%ほどしか使われていません。使われなかった建物の容積率は「空中権」と呼ばれ、ほかの建物に移すことができるという。この制度を利用して、JR東日本は自社の空中権を周辺の超高層ビル会社に売却することで費用を調達したそうです。
東京では規制緩和により、容積率が大幅に増加しました。丸ノ内ではかつては31メートルで10階建のビルしか建っていませんでしたが、現在では軒並み高層ビルに建て替えられています。そして、こうした規制緩和のお陰でJR東日本では労せずして500億円を調達して東京駅の建て替えができたのです。また、周辺のビルも容積率が緩和されたおかげで床面積が倍増しています。このため、東京のビジネス街に勤務する人口は増え、都心は活力に満ちています。
しかし、この東京への投資は本来地方でされるべき投資だったのです。インフラ整備が地方では止まってしまったため、地方での民間投資が進まなくなってしまいました。一方、東京は規制緩和により床面積が増加しました。地方で本社を建て替えようとしていた企業は、インフラ整備の進まない地元より便利な東京に進出すことを選んだのです。この様に規制緩和が地方から投資と雇用を奪ったのです。そして東京一極集中が、結局は日本の経済をデフレ化させたのは上述の通りです。東京と地方のインフラ整備の差がこの20年であまりにも拡大したことと、東京での規制緩和が地方から人も金も吸い取ってしまい、日本全体を壊滅に向かわせているのです。
今こそ、国策としての国土整備計画が必要
こうした状況を踏まえた上で今すべきことは、地方で暮らすためのインフラ整備を緊急で行うことです。私が提唱している北陸新幹線の小浜から舞鶴・京都・大阪・関空という新幹線ネットワークを始め、全国でのインフラ整備を10年内で完成させるという計画を作ることが重要です。かつて東海道新幹線や山陽新幹線は着工から5年で完成しています。経済力では現代よりはるかに劣っていた時代であるにも関わらず、国策として政府が位置づけたからできたのです。
また、隣の中国では、国の高速道路の総延長は、2013年末の時点で約104,500kmです。近年は、年平均で約6,000km以上の高速道路が建設されています。因みに日本の高速道路の総延長は9,165㎞であっという間に日本の10倍もの高速道路網を完成させているのです。これも国策として中国政府が取り組んでいるからできたのです。
お金はあるのに財政出動できない
 山陰近畿自動車道早期実現促進大会にて国会議員代表の挨拶をいたしました
山陰近畿自動車道早期実現促進大会にて国会議員代表の挨拶をいたしました
バブル以降、公共投資が激減したため高速道路や新幹線が10年内で完成すると誰も思わなくなっています。この考えが地方を崩壊させています。国策として政府が資金投入すれば、10年内で完成できるのです。そして、それが実現すると分かれば、民間投資は必ず増えます。10年内で完成するなら、それに合わせて多くの企業が首都圏以外に工場移転なども考えるでしょう。
ところが、完成までに20年もかかる様なら民間投資には何の効果もありません。そもそも、20年経てば地方はもう消滅しています。完成した時には利用する人がいないでは、全くの無駄になります。公共投資は10年内で完成させてこそ意味があるのです。
バブル以降の公共投資不要論が地方を破壊し、経済をデフレ化しました。それが財政まで悪化させ、財政再建を口実に更なる公共投資の削減を繰り返すという悪循環に陥っています。このジレンマに陥った原因は、赤字国債と建設国債を同じ扱いにしているPB(プライマリーバランス)黒字化論にあります。
PB(プライマリーバランス)黒字化論の誤り
PB黒字化論とは、その年の予算はその年の税金で賄うべきだという考えです。確かに、月給以上の生活をすれば借金ばかり増えて破産してしまいます。福祉の給付のための費用は赤字国債でなく保険料か税金で賄うべきです。そのために税と社会保障の一体改革が行われています。しかし、家を修繕したり建て直したりといった支出を月給の範囲内でやっていたらいつまで経っても修繕できないばかりか、できた時には死んでいるという事態になります。普通はそんな馬鹿なことをせずに住宅ローンを利用して早期に修繕し、その後月給で返済するという手法をとるのです。
つまりPB黒字化論は、生活費と家の修繕を一緒にして、とにかく借金はするなと言っているのと同じです。この理論はもともと民主党時代に経済があまりに悪化してしまったために財務省が持ち出した理屈です。民主党時代に事業仕分けをやり過ぎ、日本をデフレのドン底に落とした結果、税収は益々減り、国債ばかりが増え、財政は悪化しました。まさにパニックに陥った挙げ句の果ての出鱈目理論です。
アベノミクスの原点に返れ
このデフレ政策からの脱却を訴えたのがアベノミクスです。金融緩和と財政出動、そして民間投資の相乗効果で経済を成長路線に導くというのがその主旨です。確かに金融緩和で円安誘導され、輸出企業を中心に業績回復してきました。株価も回復してきました。しかし、地方の崩壊と東京一極集中には未だ歯止めがかからず、経済のデフレ化も止まっていません。今こそアベノミクスの原点に返り、きちんとした財政出動をすべきなのです。
瓦の独り言
-京都vs金沢-
羅生門の瓦
2015年3月14日に北陸新幹線が開業して、金沢が脚光を浴びています。瓦も所要があって昨年の秋に金沢駅に降り立ちました。JRの金沢駅が非常に素晴らしく、駅ナカの美術館といわれ、構内の随所に伝統工芸品がちりばめられています。金沢の伝統工芸オールスターの展示です。
金沢は小京都と呼ばれた時期もありますが、今や何のその。地理、風土、文化などが非常に京都とよく似ています。京都に鴨川が流れその周辺に文化ゾーンがあれば、金沢には犀川が流れています。錦市場と近江町市場、京の五花街とひがし茶屋街の花街。金沢卯辰山工芸工房と京都伝統産業ふれあい館。京友禅と加賀友禅。京焼・清水焼と九谷焼。さらにその近くに楽焼と大樋焼まであります。京都が誇る伝統工芸品74品目。友禅、象嵌、表具、仏壇、縫・・・それらに全て「京」の冠をつけていますが、金沢の伝統工芸品と重なってきます。しかしながら作風はおのずから異なっており、金沢は加賀前田藩を原点としていますが、京都は平安京の官営公房がルーツとなっています。(これは瓦の独断) 金沢が武士の文化といっていますが、京都は公家の文化です。でも、京都は日本の伝統工芸の源であり、伝統工芸の職人さんたちもプライドを持っています。
しかし、あの金沢駅と京都駅を比べたとき、ぶっきらぼうな(?)京都駅が北陸新幹線京都まで延長時に自他ともに称賛される駅舎になれるでしょうか? と瓦は自問していますし、金沢駅を観られた方は同じ思いをされるのではないでしょうか? ましてや駅舎が新高岡駅のように在来線と離れてしまうようなことが・・・(東海道新幹線の新大阪駅は失敗では、本来は梅田の大阪駅に接続されるべきだったのでは・・・)
でも後ろ向きなことは考えないで、我々が誇る西田昌司参議院議員の北陸新幹線のルートに夢を乗せましょう。関西国際空港に降り立ったインバウンドのお客様を京都から舞鶴へ、そして金沢へお連れして、日本の良さを思う存分味わってもらいましょう。これが瓦の初夢です。
(今回の瓦の独り言は多分に独断と偏見が入っていることを、お許しください。)
新幹線ネットワークでメガリージョン創生を!!
安保法制が成立
 藤井聡 内閣参与と共に、安倍総理に10兆円規模の補正予算の申し入れに官邸を訪問しました
藤井聡 内閣参与と共に、安倍総理に10兆円規模の補正予算の申し入れに官邸を訪問しました
第189通常国会で、安保法制がようやく整備されました。これにより日米同盟は強化され、他国が日本に攻撃することを抑止する力は格段に増加しました。野党は、アメリカの戦争に日本が巻き込まれると主張していますが、そもそも、アメリカに先制攻撃をする国など今の時代考えられません。また9.11テロなどのアメリカへのテロ攻撃に対する報復に日本が参加する事はありませんし、できません。なぜならそれは日本に対する攻撃ではないからです。いずれにしても、これからこの法制の具体的な適用のあり方については、運用規定が整備され、国会での今後の議論の中で明らかになるでしょう。
かつて60年安保の改定の時には、国会の周りのデモ隊が総理官邸に突入し、死亡者まで出るという事態が生じました。今回の法整備をこの時と対比してみると随分違いがあります。あの当時は、戦後15年目、独立後8年目でまだまだ戦争の余韻が残っていた時代です。そのため、安保改定に反対する意見も、文字通り反戦平和、非武装中立と言うかつての社会党のような考え方の人もたくさんいました。また、そもそも独立国であるにも拘らずアメリカ軍が駐留していることに対して反対だという意見もありました。
しかし、過去を見つめ直してみると、反戦平和は良いとしても、非武装中立で国が守れるはずがないのは今や常識であり、それを主張する政党は国会には存在しません。また、アメリカ軍の駐留も、日米地位協定を見直す必要はありますが、それに伴う防衛力の強化は必要です。
憲法学者の違憲発言のため国民が混乱し、この法制に対する理解が未だ十分でないのも事実でしょう。しかし、その一方で、自国を守るためのこうした法整備が必要であると感じている国民が7割近くもいると新聞の世論調査にもあります。まさにここに国民の本音があるのです。
GHQの命令で占領中に憲法と自衛隊が作られた
安保法制の理解を広げるためにも、憲法が作られた経緯を国民にきちんと説明しておく必要があります。その1つは、昭和21年にGHQが憲法を作り与えた時、彼らは日本の完全なる武装解除を目的としていたという事実。その2は、昭和25年に自衛隊が作られたのは、朝鮮戦争の勃発によりGHQが占領方針を180度転換し再軍備を命令したからであると言う事実。つまり9条があるにもかかわらず自衛隊があると言う根本矛盾は、GHQの占領政策が変更されたために生じたという事実をきちんと国民が知らない限り、安保法制の理解は進みません。
残念ながら、今回の安保法制の審議の中でも、9条と自衛隊の矛盾の原因がGHQの占領政策の変更の為であると言うことを誰も指摘しませんでした。またこの事実を、現在も学校教育の中で子供たちにきちんと教えていません。今後も歴史の事実を国民に丁寧に説明していくことが必要です。
岸から池田へ 安保から経済再生へ
安倍総理は祖父の岸総理とよく対比されます。岸総理が行った安保改正も、当時は国民の反発を招きましたが、結果的には日本の安全保障に寄与し、その後の日本繁栄の土台を作ったと現代では評価されています。今回の安保法制も後世必ずや国民の理解と評価を得るもの安倍総理も確信されているでしょう
ところで、岸総理は国民の反発を招き死亡者まで出た騒動の責任を取って辞任され、その後任に池田総理が就任されました。池田総理は岸総理の安保改正最優先から経済再生を最優先に舵を切り、所得倍増方針を掲げて後の高度経済成長の土台を作りました。安保で国を安定させ次は国民生活を豊かにする、こうした政策順位の変更は学ぶべきところがあります。
安倍総理は、対立候補がない中、自民党総裁に再選されました。当然、政権も継続するのですが、先人にならい、政策の優先順位は安保から経済再生に変更する必要があります。安倍政権は強権的だと言うイメージを払拭するためにも、ここは経済再生を最優先に舵を切るべきです。
中国の景気後退とVWショック
 参議院本会議にて安全保障関連法案に賛成票を投じる
参議院本会議にて安全保障関連法案に賛成票を投じる
こうした中、世界経済を牽引してきた中国経済がここへ来てバブルである可能性が高まってきました。急激な景気拡大や市場を無視した生産拡大のツケが一気に回ってきているようです。また天津での工場爆発などは、その原因が未だ不透明であり、政権内部の権力抗争と言う見方も出ています。こうした中国経済の不安定要素が世界経済を後退局面に追いやっています
またEUの牽引役だったドイツにもフォルクスワーゲンショック(VW)が大きな影を落としています。今年はトヨタを抜いて世界一の自動車生産メーカーに踊りでたVWですが、アメリカの環境保護局の調査により、ディーゼル車の排ガス規制を不正なソフトで擦り抜けていたと言う信じられない事実が発覚しました。何故このような不正に手を染めたのか、実態解明はこれからですが、少なくとも数兆円規模の損害が発生するのは確実です。VWの屋台骨を揺るがすのみならず、関連するドイツの自動車業界は勿論のこと、EU全体にも大きな影響を与える事は必至です。
今こそ内需の拡大が重要
以上のように世界経済全体に暗雲が立ち込めています。輸出関連企業にとっては大変大きなマイナス要素です。しかし、幸いなことに日本の輸出依存度はGDPの10%少々に過ぎません。世界でも稀に見る内需依存国家なのです。逆に言うと内需が低迷してきたことが日本経済デフレ化の原因だったのです。
内需うちで最大のものは個人消費であり、GDPの6割近くを占めます。これが低迷していた原因は、給与が低迷してきたからです。安倍内閣では春闘において政府自らが給与のベースアップを経団連に要求するなど、国民所得の増加を目指しています。特に内部留保が300兆円にものぼる上場企業の利益の社会還元は、デフレ脱却の上においても焦眉の急です。そのためには、企業が自ら進んで国内で積極的に投資を行い雇用を増やす環境を作ることが重要です。
安倍総理への提言
こうした思いから、9月の半ばに安倍総理の下へ内閣参与をされている藤井聡京都大学教授と共に、経済再生を最優先にする必要性を提言して参りました。総理も小一時間耳を傾けて下さり、我々の提言に概ねご理解をいただきました。その内容は、10兆円規模の補正予算の必要性とこれを一過性のものとする事なく、長期的な投資計画の必要性を説くものです。
地方創生が安倍内閣の重要政策課題であるのは周知の通りです。しかし、地方から首都圏への人口流入に歯止めがかかりません。これでは東京が栄え、地方は疲弊する一方です。ところが、その東京も出生率が極端に低いため、長期的には人口の超高齢化が起こり、首都圏では介護が受けられない人、いわゆる介護難民が増加することが予想されています。また首都圏での人口移動と出生率低下は日本の人口減少を加速させてしまいます。つまり、首都圏への人口流入は長期的には日本全体の疲弊に繋がるということです。
こうした事を踏まえ、地方創生と少子高齢化の歯止め、東京への人口流入の規制は一体として行う必要があり、その結果が経済の再生に直結すると言うことを総理に提言をしてきたのです。その具体策が、新幹線ネットワークによるメガリージョン構想です。
新幹線ネットワークによるメガリージョン構想
 自民党本部にて「新幹線ネットワークによる近畿メガリージョン構想」についての記者会見を行いました
自民党本部にて「新幹線ネットワークによる近畿メガリージョン構想」についての記者会見を行いました
地方創生と東京一極集中の排除、さらには消費増税を控え経済再生が必要にも関わらず世界経済が減速していると言う事実、こうした問題をすべて解決してくれるのが、新幹線ネットワークによるメガリージョン構想なのです。
その概要は中央リニア新幹線を現在の東京名古屋間だけでなく大阪まで同時開業させる。それにより東京圏と名古屋圏と関西圏を1時間程度で繋ぎ、首都圏の経済集中を解消させる。更に北陸新幹線を関空まで繋ぎ、近畿縦貫新幹線とする。これにより近畿の日本海側から太平洋側への南北アクセスが格段に向上し近畿は一体化する。この結果、東京から関西までが巨大な経済地域として一体として発展することが可能になる。正にメガリージョン(広域経済圏)が誕生することになるのです。
どの地域からも1時間で東京に行けるわけですから、企業はもはや東京に進出する必要がなくなります。住環境の優れた地元で人材を採用すれば、子育ても楽になり少子化も解消します。また新幹線ネットワークが完成すれば、かつての過疎地域も観光地として復活します。そうすれば、民間企業の投資が進み、内需が増え、雇用を生み、給与が増え、個人投資が増え・・・と、雪だるま式にGDPは拡大するでしょう。
舞鶴から関空まで繋ぐ近畿縦貫新幹線
私は、この北陸新幹線を小浜から舞鶴を経由して京都駅さらには天王寺から関空まで繋ぐ近畿縦貫新幹線にすべきだと主張しています。
私が舞鶴を経由することを主張している理由は、若狭や丹後地域が東京へのアクセスに6時間もかかる、日本で最も不便な地域の一つだからです。地方創生をするなら最も不便な地域から始めるべきだと言うことです。一方でこれらの地域には、海上自衛隊や第8管区海上保安本部という海の守りの最重要施設が有ります。原子力発電所もこの地域に集中しています。国家にとって最重要施設が集中している地域をしっかり守ると言うのは国家の責務です。さらに水産資源や観光資源にも恵まれた地域です。
特に観光はこれから成長が最も期待できる産業です。日本三景のひとつである天橋立を始め、温泉や海の幸など観光資源には事欠きません。唯一の難点が東京へのアクセスの悪さだったのです。北陸新幹線がここを通ればこうした問題は一挙に解決します。更に舞鶴から豊岡、鳥取米子から下関へと将来の日本海新幹線への一歩に成ります。
概して山陰地方は過疎地ですが、かつては日本の文化の中心であった地域で、歴史的遺産にも恵まれています。寂れたのは交通事情の悪さからですが、新幹線ができれば一挙に発展が期待できます。
関空に繋げば近畿は世界と直結
また、北陸新幹線を関西空港に繋げば京阪神地域から関空までの時間は30分程度になり、交通アクセスは格段に高まります。近畿全域が海外に直結することになり、その経済効果は計り知れません。
関空から和歌山を通り紀淡海峡を渡れば淡路島、そこから四国を横断し佐多岬から九州熊本に至る四国新幹線も将来の視野にはいります。紀淡海峡の一部を堤防で繋げば、南海大地震の際に予想される大津波を防ぐことも可能となり、大阪湾沿岸地域の防災上も非常に大きな効果を発揮するでしょう。
新幹線ネットワークに財政出動をすべき
以上のように新幹線ネットワークが誕生すれば、巨大な民間投資を呼び込む事は間違いありません。それにより内需が拡大し、経済は長期的な成長路線に戻るのです。そのために必要なのは、政府による財政支援です。
中央リニア新幹線はJR東海が全額負担で建設をすると言っていますが、東京大阪間で10兆円近い建設費がかかります。民間事業者であるJR東海の経営体力の問題から東京名古屋間を先行開業して、その後名古屋大阪間に着手する予定です。しかしこれでは名古屋までの開業が2027年、大阪は2045年になります。あまりにも時間がかかりすぎです。
東海道新幹線は着工から5年で完成しています。東京オリンピックまでに開業させるという強い意思と、日本の戦後復興のシンボルにする国家事業だからできたのです。しかし当時はその建設費を国内で調達できず、世界銀行から借り入れをして行ったのです。
それに引き換え現代では、日銀当座預金残高が330兆円にも達しており、投資や融資に使われていない巨額の資金が眠っているのです。政府がこの資金を使い、国家事業として政府が行えば短期間で東京大阪までの開業は可能です。また北陸新幹線は3兆円位の事業費と言われています。これも公共事業費の枠組みを増やせば短期間で建設が可能です。
10兆円そこそこの政府の支出で10年内に新幹線ネットワークが完成します。東京名古屋関西が一体となるメガリージョンが完成すれば、その何倍もの経済投資効果が生まれます。これこそがアベノミクス第2章の幕開けとなるのです。
樋のひと雫
羅生門の樋
現在、南米では、ベネズエラとコロンビアの動向に注目が集まっています。ベネズエラのマドゥーロ大統領が、突如として国境付近に住むコロンビア国籍の住民を追放し、国境を封鎖してしまいました。その理由は、ベネズエラのガソリンや生活物資を密輸出していると云うものです。中南米ではブラジルを除き、多少の方言はあってもスペイン語一つで用が足ります。そして、国境はあっても事実上は機能していません。国境付近の村々では人々は自由に往来し、日用品や食料品を買い求めに行きます。通貨さえ、普通に流通しています。
私もペルーでの仕事を終えると、エクアドルにコーヒを飲みに行ったものです。その際にも検問所で止められることはありませんでした。人々は、エクアドルに午前中に買い出しに行きます。多くの村人には、それが普通のことであり、日常の風景です。
ベネズエラの国境封鎖と住民追放は、国内の経済政策の失敗が引き起こしたインフレと日用品の品薄から来る国民の不満を、「コロンビア人による密輸出」に理由を求めたにしか過ぎません。誰が見ても明らかな、この単純な仕掛けは、彼を支持する多くの民衆によって「正当性」を与えられています。大体、国境付近の住民による買い出しぐらいで、食料品やガソリンが底を尽くという話自体が滑稽であり、それを口実にすること自体が、大統領の政治力の無さと知能の低さを疑わせるに十分です。
ベネズエラのチャベス前大統領は、極端なポピュリズム政治を行い、貧困層の支持を得るために金をばら撒きました。これには多くの大衆が熱狂し、彼が行う経済や外交政策に反対する者は、大衆自身の手によって封殺されもしました。また、彼はボリバル主義を唱え、キューバ、エクアドル、アルゼンチンやボリビアと云った反米左派政権のパトロンとして、膨大な資金援助を行ってきました。彼の亡き後は側近であった現大統領が同じ政策を取り続けています。
しかし、世界の経済動向を無視したこのばら撒き政策も破綻を来します。原油価格の下落は、地下資源依存の国家経営を直撃し、日用品や食料品の価格さえ高騰しています。石油施設を国有化し、オイルマネーを国庫に入れ、これを元に産業を興すべきところを、目先の権力維持に使ったチャベスの罪でもあります。ベネズエラは日用品すら輸入に頼っています。産業を興し国民を飢餓や貧困から救い、生活を安定させるはずの石油資本の国有化は、いつしか政権維持の為の原資になってしまいました。しかし、これを認め、多選のための憲法改革を支持したのも民衆でした。世界一位の石油埋蔵量を誇るベネズエラの悲劇がここにあります。
ポピュリズムの政治は、国家百年の計よりは目先の利益を追求します。耳に心地よい言葉は民衆を惑わし、そして時として、大衆の声は目先の利に左右され、思わぬ暴挙も生み出します。永い目を持ち、少しの冷静な判断があれば、国を守り国民の安寧を守る方法などは、その大筋では大きな違いなど無いはずです。今国会で見られたような、国と国民を守る具体論無き、為にする違憲論争などは、「日本型ポピュリズム」の象徴かも知れません。
何故、憲法学者は違憲と言うのか
 テレビ朝日『ビートたけしのTVタックル~カジノは日本を救う?滅ぼす?~』に出演しました
テレビ朝日『ビートたけしのTVタックル~カジノは日本を救う?滅ぼす?~』に出演しました
平和安全法制の審議をしている最中、衆議院の憲法審査会で自民党が参考人として招致した学者が、平和安全法制は、憲法違反だと主張しました。
集団的自衛権を認める平和安全法制は憲法違反であり、やるならまず憲法改正をすべきだと言うのが、彼らの主張です。憲法は集団的自衛権を認めておらず、憲法が認めていないことを法制することは立憲主義に反すると言うのです。なるほど憲法には次のように書かれています。
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
しかし、そもそもこの条文からは集団的自衛権はおろか、個別の自衛権すら認められているようには見えません。ましてや、自衛隊など認められるはずもありません。事実、昭和21年の日本国憲法制定時、「日本国憲法は、自衛権を否定するのか」との共産党からの質問に、吉田総理は、「戦争放棄に関する規定は、直接には自衛権を否定していないが、第9 条第2 項において一切の軍備と国の交戦権を認めない結果、自衛権の発動としての戦争も、交戦権も放棄したものであります。」(昭和21 年6 月26 日)と答えています。
つまり、憲法制定時には、自衛権すら我国は否定してきたのです。それなのになぜ自衛隊が存在するのか。このことを疑問に感じていた人も多いはずです。私もその一人でしたが、この根本的な矛盾についてもう一度考えてみたいと思います。
自衛隊ができた経緯
憲法制定時には、自衛権も放棄したと国会で答弁していた吉田総理でしたが、昭和25年1月、日本の独立を見越して「独立を回復した以上は自衛権は存する。武力なしといえども自衛権はある」と自衛権の存在を一転して認めることになります。さらに同年6月、北朝鮮が韓国に38度線を越えて侵攻したことにより、朝鮮戦争が勃発します。日本に駐留していた米軍が北朝鮮に出撃したことにより、日本の防衛は空洞化してしまいます。そこでGHQは日本に再軍備を要請することになります。
日本は当時まだ占領中ですから、GHQの命令は絶対です。 しかし、ついこの前までは自衛権すらないと明言し武力放棄を宣言していたため、さすがに軍隊を持つと言うわけにはいきません。そこで苦肉の策として軍隊ではなく警察予備隊として自衛隊が発足したのです。
憲法と自衛隊の矛盾はGHQの政策変更が原因
矛盾があるのは、GHQの占領政策が占領前期と後期では180度転換したためだったのです。
占領前期は、日本を完全に軍事的に解体し無力化することと、アメリカに弓を引いた政府の責任者を戦争犯罪人として処刑し、日本を懲らしめることを目的としていました。東京裁判での戦犯処刑の他にもたくさんの懲らしめが有ったのです。これは最近私も知ったのですが、昭和21年から28年まで政府の予算に終戦処理費が計上されています。これはGHQの駐留経費に使われていたものです。昭和21年と22年は予算のうちの3割以上を23年は2割以上を終戦処理費が占めていました。戦争中よりも敗戦後の方が生活が苦しかったとよく言われますが、予算を国民のためではなくGHQのために使っていたのですから当然です。まさに日本はGHQに懲らしめられていたのです。
ところが、昭和25年以降はアメリカの占領政策は懲らしめから保護援助に一転します。その背景にあったのが朝鮮戦争に象徴される東西冷戦の激化です。かつてのナチスと日本の支配地で次々と共産主義国が成立し、アメリカは強い危機感を抱き、世界中でこれ以上共産主義勢力を増やさないためにも、日本をアジアにおける反共の砦として保護し援助する必要があったのです。GHQの占領政策の変更と朝鮮戦争の特需を契機として、日本の経済はようやく復興へ向かうことになったのです。
安保条約の成立の経緯
 地方・消費者問題に関する特別委員長として、本会議にて委員長報告をいたしました
地方・消費者問題に関する特別委員長として、本会議にて委員長報告をいたしました
アメリカの占領政策の変更を、吉田総理は日本の独立のチャンスだと考えていました。東西冷戦が激しさを増す中、ソビエトをも含めた全面講和は事実上不可能と考え、アメリカを始めとする西側諸国との単独講和を選択したのです。しかし、独立するとなると占領軍は撤退をし、自分の国は自分で守ることが必要となります。残念ながら、当時の日本は復興が緒に着いたばかりで、自主防衛の負担には耐えられないと吉田総理は考えていました。また、アメリカも東西冷戦が激化する中、日本に米軍基地を保有することは軍事的にも有利だと考えていました。
こうした思惑の一致から、占領が終わったにも拘わらず米軍が日本に引き続き駐留することを認めた日米安全保障条約が成立するのです。当初は日本の希望で米軍が駐留すると言う片務的な条約でした。しかし、昭和30年の改正で日本が基地を提供しアメリカが日本の安全に寄与すると言う双務的な体裁に変えられ今日に至っています。
以上のように憲法と自衛隊の矛盾はGHQの占領政策の変更が原因なのです。
立憲主義を主張する学者の根本的矛盾
では、この根本的矛盾を憲法学者達はどのように説明しているのでしょう。彼らは、独立国である以上自然権として自衛権はあるといいます。自然権として、とは生まれながらにしてという意味ですが、独立国として当然の権利だというのです。これは政府の見解と同じですが、ここに私は無理が有ると思っています。
といいますのも、先に述べたように、そもそも憲法制定時に吉田総理が自衛権も放棄するという旨を国会で答弁しているのです。憲法制定時に自衛権を放棄すると明言したものが、その後自然権として自衛権はあると言うのは明らかに矛盾するものです。立憲主義を主張するなら、この時点で憲法を変更しなければならなかったはずです。再軍備と言う重大な憲法違反事象について、立憲主義者たちは自然権と言う言葉を持ち出して事実上解釈変更を認めているのです。
にも拘わらず、自然権としての自衛権を個別的と集団的に区分して、個別的自衛権は認められるが集団的自衛権は認められないと言うのは、まさに机上の空論と言うほかありません。再軍備と言う根本矛盾に目をつむって、自衛権を個別的、集団的に区分して個別的は合憲だが集団的は違憲だという議論は滑稽ですらあります。
政府の誤り
残念ながら、そうした解釈を実は政府自身もしてきたのです。平和安全法制の制定は自然権としての自衛権を行使できるための法制備ですから、独立国である以上当然のことです。本来、日本が主権を回復した時点で、こうした法整備はしておくべきだったのです。
しかし、法整備をするためには憲法の抱える根本矛盾を理解しておかねばなりません。つまり憲法は占領を前提として作られたいわば占領基本法であり、その制定過程も含め独立国としての憲法たり得ないということです。ところが、それを国民に説明していないばかりか、いまだに学校の現場では、我々は戦争を反省し戦争を放棄したのだ、平和国家として生まれ変わったのだと教えているのです。これでは国民が平和法制の必要性を理解できないのも当然です。
自衛隊の発足により事実上占領基本法たる憲法は廃棄されていた
 西田昌司国政報告会2015を開催いたしました。多くの皆様にご来場いただき、誠にありがとうございました
西田昌司国政報告会2015を開催いたしました。多くの皆様にご来場いただき、誠にありがとうございました
一方で、占領終盤になって独立国である以上自衛権は存するという吉田総理の発言は、占領基本法たる憲法を廃棄するという宣言とも受け取れます。事実、再軍備をし、サンフランシスコ講和条約が発効したのですから、この時点で占領基本法たる憲法は事実上無効になったとも解釈できます。問題はその無効宣言を発していなかったことです。独立を回復した時点の国会で占領基本法たる憲法の無効宣言をすれば、元の明治憲法が蘇ります。そして、明治憲法が軍部の独走を許したことを踏まえて不備な点を改正すべきだったのです。正に、大東亜戦争に至る国の歴史そのものを日本人自らが見つめ反省すべきであったのです。
国民が占領時代の事実を知ることが全ての始まり
しかし、無効宣言をするには、国民が憲法制定の経緯やその目的など、GHQが占領時代に行ってきた事実を知らねばなりません。国民の理解を得るためには国会における議論が必要なのです。残念ながら、この総括をしてこなかった結果、逆にGHQが占領時代に行ってきた政策が正当化されて国民に伝えられているのです。これでは日本は永久に占領政策から脱却できませんし、真の独立を果たすことなど不可能です。
野党は何時から自衛隊を合憲とみなしたのか
平和安全法制を違憲だと言う野党もさすがに自衛隊は合憲と見ているようです。もっとも、再軍備をしたときには社会党など当時の野党は、自衛隊は憲法違反だとその存在を終始認めない立場でいました。そのため各地域で行われた成人式の式典に自衛官が参加しようとすれば、それをボイコットするなど自衛官を侮辱する卑劣な行為が行われていました。ところが、平成6年に村山内閣が発足し社会党の委員長が総理大臣になると、さすがに彼らも自衛隊を合憲と認めざるを得なくなりました。独立国の総理大臣になれば、自衛権を認めないわけにはいかないのは当然です。これを契機に自衛隊は野党も、また、その周辺の学者も合憲と判断する様になったのです。
現実の政治の前では、憲法よりも自然権としての自衛権の方が優先するという結果になったわけです。それなら、野党が自衛隊を違憲としてきた過去を反省して総括をすべきだったのです。国民にも日本国憲法の問題点を理解する良い機会であったはずなのです。しかし、ここでもまた日本国憲法の欺瞞性が議論される事はありませんでした。
平和安全法制は独立国なら当たり前
自分の国は自分で守る。そのためには時として友好国と協力し合うことも必要である。これは独立国ならどの国にも当てはまる当たり前の話です。しかし、具体的にどのケースがこうしたことに当てはまるかは、ケースバイケースで判断すると言うのが現実でしょう。それを重箱の隅をつつくような議論をしてもほとんど意味はありません。
むしろ議論をすべきは、いろいろな事態を想定して議論をしておいても、その想定を超える事態が生じることが現実の世界ではままあると言うことです。その様な想定を超えた非常事態に対処するのが政治の責務です。独立国が有する自然権としての自衛権を行使するには、まさにこうした事態に対応できる法制度を持っておかねばなりません。今回の平和安全法制の整備は、正にその第一歩になるものです。独立国ならどこの国でも整備しているものです。
戦後の総括こそ必要
平和安全法制の整備は独立国として当然のことですが、それを国民に理解してもらうには、日本国憲法がその制定過程においてもまた内容においても、独立国の憲法としては不適格だと言うことを国民にしっかりと伝えなければなりません。このことを国民に伝えずして、立法化は難しいでしょう。また、たとえ立法化できても、日本国憲法の根本的矛盾を国民が理解しない限り、真の独立国になる事はできません。平和安全法制の整備が真の独立国になるためのものだからこそ、憲法の制定を始めとする占領時代にGHQが行ってきたことを国民の前で総括をしておく必要があるのです。
瓦の独り言
-舞妓さんは頭の先から爪先まで伝統工芸品-
羅生門の瓦

京都岡崎の赤い大きな鳥居の近くに、京都の伝統工芸品の粋が観られるところがあります。それが「京都伝統産業ふれあい館」、「知る人ぞ知る」伝統工芸品のミュージアムです。
794年に平安京が建設され都として栄えた京都は、日本の政治、文化、産業の中心地として発展してきました。数々の工芸品は、こうした歴史的背景のもと、町衆の暮らしの中で大切に育てられたいにしえの心と共に生み出されてきており、「京都伝統産業ふれあい館」は今なお受け継がれ、京の町に息づいている美と技の世界をより多くの人々に感じていただくための、伝統産業と文化と人との出会いの場を提供しています。
館内では伝統工芸品74品目ひとつひとつにスポットをあて、約500点を展示していますが、日曜日(4月から第三日曜日のみ)になると舞妓さんの「おどり」が観られます。舞妓さんの衣装は頭の簪から、爪先の足袋まで京都の伝統工芸品をまとっておられます。「おどり」も大事ですが「御衣裳」の解説を聴いていただくことにも重点をおいています。特に「花かんざし」「京足袋」を作っている業者さんは京都市内で1軒だけになってしまっています。この業者さんが、廃業すれば京都の伝統文化である「舞妓」さんが存続できなくなってしまいます。このような危機感をもって舞妓さんの「おどり」を観ていただくと、また京都の伝統文化に関する異なった視かたが出来るのではないでしょうか?
なぜ、こんな文章を瓦が書いているのか、いぶかる方がおられると思います。実はこの舞妓舞台の解説をしているのが瓦自身に他ならないのです。是非、舞妓舞台を見ていただいて、西田昌司先生も憂いておられる「京都の伝統産業」の在り方を考えていただければ幸いです。
*京都伝統産業ふれあい館の開館時間 午前9時~午後5時
*入場料 無料(なななんと、舞妓舞台も無料です)
*連絡先〒606-8343 京都市左京区岡崎成勝寺町9番地1「みやこめっせ」地下1階
*☎075-762-2670
*交通アクセス
・地下鉄「東西線」「東山駅」から徒歩8分
・市バス「岡崎公園 ロームシアター京都・みやこめっせ前
*舞妓舞台 毎月第3日曜日 (14:00~15:00)3回
大阪都構想は大阪市の解体
 府連会長として公認候補者を連日激励訪問いたしました
府連会長として公認候補者を連日激励訪問いたしました
隣の大阪では橋下市長が松井知事と大阪都構想を掲げ、来る5月17日に住民投票を行います。しかし、大阪都構想とはいうものの「大阪都」にはなれません。名称は大阪府のままで、大阪市が5つの特別区に解体されるだけです。大阪都構想は、大阪市解体構想と呼ぶ方が正しいでしょう。
5つの特別区にはかつての大阪市のような権限はもちろんありません。東京の特別区の権限は、政令市はもちろん中核市や一般の市よりも権限は大幅に制限され、世田谷区の様に市になることを望んでいる特別区もあります。大阪都構想においても、特別区は政令市の大阪市より権限も財源も小さくなるという事実を先ず知ってください。失った権限と財源は、大阪都ならぬ大阪府に吸い上げられることになります。これは東京都の23区も同じことです。つまり、特別区の自治権は大幅に制限されるということです。
普通に考えれば、大阪市民にとっては何のメリットもないように思えます。政令市である大阪市は、府県並みの自治権を付与されています。大阪都構想は、それを大阪府に返上し、政令市より格段に権限の少ない特別区に再編するということです。
大阪市民にとっては大阪市の権限が大阪府に召し上げられるだけで何らメリットがないものであるにも関わらず、アンケートによれば賛否が拮抗しているのは、多くの大阪市民にこうした事実が伝わっていないことに原因があります。
そして、それを助長するのが都構想という名前です。大阪も都に成れば東京都の様に発展するというのは、全くの事実誤認です。また、大阪都構想という名前こそ、そうした誤解を誘導するためのものと言っても良いでしょう。
東京の特別区は戦時体制が生んだもの
東京都もかつては東京府と呼ばれ、その中核には東京市がありました。それが昭和18年に東京市が23の特別区に解体され、その権限は東京府に移管され東京都となったのです。23の特別区の権限は、東京市時代より格段に制限されることになりました。かつて東京市が持っていた権限は、東京都が吸い上げることになったのです。
昭和18年と言うと大東亜戦争の真っ只中です。このことからも分かるようにその目的は戦時体制の強化です。当時は東京都長官と呼ばれていたのですが、官選による知事が置かれ、自治権は大幅に制限されることになったのです。終戦後は、都知事はもちろん公選で選ばれています。
しかし、依然として特別区の権限は、一般の市より格段に落ちる権限しか与えられていません。そのため、特別区の自治権を他の市並に回復させるよう主張する区長もいます。その意味では、東京の特別区は戦時体制の名残りとも言えます。
大阪市の分割ではなく、集積をはかれ
大阪都構想の原点に有るのは、都政と府政のシステムの違いにより、東京は発展し、大阪は衰退したという考え方でしょう。また、大阪市民の中にもそのように考えている人もいるようです。しかし、それは全くの誤解です。
事実、大阪市は昭和40年代ぐらいまでは、西日本の経済の中心でもあり、東京に引けを取らない大都市でした。それが東京に大きく水を開けられたのは、東京が都であるのに対して、大阪が府であったからではありません。その原因は、東京では昭和39年の東京オリンピックを契機に急速に都市基盤整備が進んだからです。一方、大阪も昭和45年に万国博覧会が開催されるなど、西日本の中心として発展をしてきました。しかし、万博の会場が吹田市であったように、核になる大阪市の行政区域が小さすぎたのです。
因みに、大阪市の人口は平成27年3月の推計値で268万人、面積は233㎢で人口は大阪府全体の約3割で面積は約1割です。対する東京は人口915万人、面積は622㎢で人口は東京都全体の七割で面積は3割です。人口も面積も大阪市は東京23区の1/3程度しかないのです。都市としての集積不足が大阪市の最大の欠点であるのです。そのため、大学も大阪市内には少なく、阪大も豊中や箕面にあります。
従って、大阪都構想よりむしろ、大大阪市構想つまり、堺や吹田や豊中や東大阪などの市町村を合併して、政令市としての大大阪市を目指す方が理にかなっているのです。
当初の大阪都構想もこうした観点から、周辺の都市を巻き込んだもので特別区を20区にし、人口面積とも格段に集積が進んだものであったようです。
ところが、肝心の堺市が大阪都構想に反旗を翻したため、実現不能になったのです。その理由は、折角政令市になったのに権限が政令市より少ない特別区になることを拒んだためでした。これは、堺市民にとってはもっともなことでしょう。
堺市が大阪都構想に参加しなくなったため、大阪都構想は当初とは全く違うものになってしまいました。周辺の都市を集めて集積を高めることができず、単に大阪市を5分割するだけのことになってしまったのです。
大阪市の分割で大阪は衰退する
 京都府商工会連盟政経セミナーにて「京都の地域創生」をテーマに講演をいたしました
京都府商工会連盟政経セミナーにて「京都の地域創生」をテーマに講演をいたしました
この結果、大阪都構想は都市の集積ではなく分割だけを行うことになったのです。大阪市は政令市として、府県並の権限と予算を持っていましたが、それが分割され、権限も予算も以前より少なくなることは、制度上明らかです。また、伝統ある大阪市が分割され、予算規模も権限も小さな特別市区になれば、少なくとも大阪市民にとってメリットがあるとは思えません。権限と予算を減らされて大阪市内が発展するはずがないことは、火を見るよりも明らかです。
二重行政の排除は正しいのか
そもそも、二重行政の排除が大阪都構想の最大の眼目になっているようですが、これも疑問です。その象徴が、関西国際空港対岸にある「りんくうゲートタワービル」と大阪湾開発のシンボルとされた「WTCビル」(現・大阪府咲洲庁舎)であると維新の会が声高に主張しています。これは、バブル時代に府と市が競って建設計画をスタートさせた巨大な箱モノで、府が推進したりんくうタワーは約660億円、市のWTCは約1200億円もの総工費が公金によって建てられたそうですが、両者を運営する府と市の第三セクターは2005年ごろ、ともに破綻をしてしまいます。銀行への借入金を役所が肩代わりし、府も市も莫大な公金をムダにしてしまったそうですが、これこそ二重行政のシンボルであると維新の会はいうのです。
しかし、こうした箱物の破綻は本当に二重行政が原因なのでしょうか。市と府が似たようなものを作ったから破綻したのではなく、バブル景気を前提に計画し、それが破綻したことが真の原因ではないでしょうか。これは、学研都市に国が建設した「私のしごと館」の破綻と同じです。二重行政ではなく、バブル景気の崩壊が破綻の原因です。
二重行政の排除は大阪市内の投資を削減する
政令市には府県並の権限があると言われています。例えば商工政策です。大阪市が中小企業に助成をし、更に大阪府も助成をする。これが二重行政です。また、府民ホールを大阪市内に作る。これもまた二重行政です。これらを排除するということは、大阪市内での大阪府の投資を排除するということです。仮に二重行政排除が正しいとしても、その結果もたらされるのは、今まで、大阪市内で行われてきた大阪府の行政サービスや投資が削減されるということであり、市民にとっては全くの損になります。その代わり、大阪市以外の投資が増えるかもしれませんが、果たしてそれが府民の利益でしょうか。元々、大都市は賑わいの中心として存在しています。その施設を利用するのは必ずしも市民とは限りません。府民は元より他府県からもその賑わいに魅かれ人々が訪れます。それがまた賑わいを創り、結果的に大都市の経済は発展し、税収も増えるのです。
元々、大阪は近畿の中心として発展してきたのです。そのため、他の都市には無い様々な施設が揃っていました。またそれが二重三重にあることから更に大きな賑わいを創り、その結果、周辺の都市をも豊かにしてきたのです。二重行政排除はこうした投資が削減されることであり、大阪市民にとって損であることはもちろんのことですが、その周辺住民にとっても損なのです。
大阪都構想で近畿は賑わいの核を失う
 テレビ愛知「激論!コロシアム」~成人年齢で大バトル!18歳に少年法は必要か!~に出演しました
テレビ愛知「激論!コロシアム」~成人年齢で大バトル!18歳に少年法は必要か!~に出演しました
この様に、大阪都構想は二重行政排除という行政の効率化にばかり主眼が置かれ、肝心の経済の活性化ということに対する視点が欠けているのです。そもそも維新の会は道州制を主張していたはずですが、その裏にあるのは近畿州の州都としての大阪を考えていたはずです。道州制が出来る前に州都になるはずの大阪市を解体してどうするのでしょうか。
間違いの元は道州制
もっとも、その道州制自体が間違った発想です。何故なら、道州制も大阪都構想と同じく、二重行政の排除が目的だからです。道州制は、財界からもその導入が主張されてきました。彼らは、都道府県を廃止し道州制にすれば、行政効率が上がり行政コストが削減できると主張してきました。彼らは、4兆円もの行政コストの削減が可能だとも言ってきたのです。しかし、行政コストを4兆円削減するということは、その分それぞれの地域で使われる予算が4兆円減るということです。地域で使われる予算を増やせば、経済が活性化することは分かりますが、予算を減らして活性化などあり得ません。この議論の裏にあるのは、4兆円の予算を削減できればその分法人税を下げることができるという財界の思惑があるのです。
確かに、法人税を下げれば、その分企業に資金は残ります。しかし、それを企業が国内で投資や雇用に使ってこそ経済の活性化に資するのです。ところが、現実には企業の内部留保は増える一方で、国内の雇用も投資も増えていません。まさに、これがデフレの原因なのです。
合成の誤謬(ごびゅう)
大阪都構想にせよ道州制にせよ、つまるところは行政の効率化がその目的です。そして、そのモデルになるのは企業経営です。バブル崩壊以後、民間企業は経営の効率化を行ってきました。できるだけコストを削減してきたのです。これは、企業経営としては正しいことです。しかし、誰もがコストを削減して内部留保を貯めれば経済は停滞しデフレになります。一つ一つは正しくても、それをみんなが行えば間違った結果になることを合成の誤謬と言います。この合成の誤謬を行政にまで及ぼすというのが大阪都構想であり、道州制なのです。
大阪市民に告ぐ
以上述べてきました様に大阪都構想は、全くの的外れであり、特に、大阪市民にとっては百害あって一利なしです。この被害は近畿一円、ひいては日本全体に悪影響をもたらします。しかし、京都市民である私にはそれを止めることはできません。出来るのは大阪市民だけなのです。大阪市民よ、目を覚ませ!この記事を是非とも、一人でも多くの大阪市民に伝えてください!
樋のひと雫
羅生門の樋
日本で統一地方選挙が行われていた頃、中米パナマではキューバのラウル・カストロ議長と米国のオバマ大統領が半世紀ぶりの首脳会談を持ちました。新聞報道の写真を見て、人民革命も遠くのものになってしまったと独り感慨に耽りました。
子供の頃には「キューバ危機」が起こり、世界大戦に向けた時計が針を進めました。学園紛争の頃はキューバ革命の英雄チェ・ゲバラの写真が各大学に掲げられたものでした。ベルリンの壁が崩壊し、ソ連が消滅した後も、フィデル・カストロは反米の姿勢を崩さず、毎年の独立記念日には8時間にも及ぶ演説をぶっていました。ここ10年の間でも、中南米に多くの反米政権が誕生し、その精神的支柱がキューバの存在でした。ベネズエラのチャベス大統領も毎年のようにキューバ詣を行い、フィデルから喝を入れられていたように思います。
最大の援助国であったソ連が崩壊し、砂糖の輸出相手を失ったキューバは、外貨獲得の手段も失いました。また、半世紀に及ぶ米国の経済封鎖は庶民の生活を抑圧し、唯一と言っていい経済支援国のベネズエラも、チャベスの死に伴う政権の劣化と原油価格の低下で経済的困窮が始まりました。今のキューバに経済的な支援を行う国はなく、現実的には米国との対話がキューバを経済的困窮から救う唯一の方法かも知れません。
当時のケネディ大統領の反キューバ政策に対抗する為に、フルシチョフ第一書記と手を握る。これも当時のフィデルにとって祖国を守る唯一の現実的方策でした。そのために、盟友のゲバラとの路線対立をもたらし、チェはボリビアで死ぬことになります。
「豊かさか貧困か」。キューバを訪問するたびに考えさせられます。深夜に着くハバナの飛行場は照明も少なく薄暗いです。クーラーを持たない庶民は、夜遅くまで家の前で涼んでいます。50年代のキャデラックの部品は全てが手作り、大通りのビルの壁も薄汚れ、官給所の棚には余り商品も並んでいません。でも、人々の表情は明るいです。配給に並んでいる人の中で争いは見たこともありません。中南米で見かける物乞いもいませんし、夜遅くに出歩いても強盗に出会うこともありません。共産主義国家を自称しながら、富の偏在と格差を生み出す、どこかの国とは大違いです。クバリブレとピニャコラーダを飲みながら、サルサを踊る。その顔には貧困は見られません。カリブの太陽の日差しは強くても、人々の心と生活に影を作らないようです。
本当にフィデルは共産主義革命を目指したのか。農地の大半を外国資本が占有し、政権は彼らと結託する。人々は農奴の如き生活を送り、基礎教育も受けられない。理想に燃えた青年たちが祖国の解放を夢見たのも頷けます。革命が成った時、フィデルが米政権と話し合おうとした機会を米国が拒絶しなければ、今の中南米の政治情勢もずいぶん変わったものになっていたでしょう。
これからは米国の商品や物が奔流のように押し寄せます。人々がこれらと上手く折り合えるように願います。「祖国か死か」。ゲバラが行った国連での演説は、今もキューバの2ペソ硬貨にチェの肖像と共に彫られています。
自民党の圧勝に感謝、安倍内閣の正念場
 自民党京都府連会長として伊吹先生、谷垣幹事長とともに必勝コール
自民党京都府連会長として伊吹先生、谷垣幹事長とともに必勝コール
今回の総選挙では、京都において6選挙区すべてで議席を得るという目標は達成されませんでしたが、全国的には、お陰様で自民党の勝利で終えることができました 。ご支援いただいた皆さんに心から御礼申し上げます。今回の選挙でアベノミクスは信任され、安倍内閣は今後4年間の長期的な政権の基盤を得ることができました。しかし、これからが安倍内閣にとって本当の正念場です。
財政出動の長期計画を示せ
まず、安倍内閣がしなければならないのは景気対策、とりわけデフレからの脱却です。選挙戦でも私は訴えてきましたが、日銀の金融緩和だけではデフレは脱却できません。今こそ財政出動が必要なのです。それも短期的な景気対策ではなく、長期的な財政出動の計画を国民に示す必要があります。
例えば、国土強靭化に毎年10兆円ずつ、10年間で合計100兆円の財政出動をすると政府が発表するとどうなるでしょうか。その財源はもちろん国債発行で賄います。すると国からの発注を期待して建設業者の方々はその準備を行います。まずは、人材を確保しておかねばなりません。既に、アベノミクス効果で失業率は改善されていますから、人材を確保するには今まで以上に高い賃金を出さねばなりません。デフレ脱却のためには賃金の上昇が不可欠ですが、政府が仕事を発注することが雇用を増やし賃金を上昇に導くことになるのです。
財政出動が民需を誘導
さらに10年間で100兆円もの工事が発注されると、それをこなすためにはブルドーザーなどの重機を用意しておかねばなりません。長期間にわたり公共事業等の発注が少なかったため、建設業者の中には重機を持たずにリースで賄っている所もあります。しかし、仕事が増えれば重機はリースでは賄いきれません。そこで、先に重機を新しく購入する所が増えてくるでしょう。けれども、これが1年限りの公共事業だとすれば、リースのままで済ますことになるでしょう。つまり、政府が公共事業の長期計画を発表することにより民間の投資が増えることにもなるのです。これが正にアベノミクスの3番目の矢になるわけです。
重機を揃えるには多額の資金が必要となり、銀行に借り入れを申し込まねばなりません。ここでアベノミクスの第1の矢である金融緩和が非常に有効に働きます。銀行は既に多額の資金供給を日銀から受けています。そのため銀行には潤沢な資金がありますから、低い金利で企業の融資に応じることができます。
このようにして、政府の長期的な公共工事計画が民間の投資を促し、雇用を改善し、賃金を上昇させ、デフレ脱却へと経済を導くことになるのです。
「三種の神器」の様な民需は無い
 BSフジ『プライムニュース』~女性宮家創設の是非、皇室存続のため必要なことは~に出演いたしました
BSフジ『プライムニュース』~女性宮家創設の是非、皇室存続のため必要なことは~に出演いたしました
デフレ脱却のためには内需が必要であり、そのために民間企業の投資を促進することが成長戦略として謳われています。しかし成熟社会となった現在の日本では、企業の投資は国内では減る一方で、その代わりに海外に向っていきます。こうした企業の投資行動の変化がデフレをもたらした原因の1つです。この十数年、民間投資促進のために規制緩和を行ってきましたが、残念ながら、その効果がなかったことは今や明らかになっています。
かつての日本では衣食住の充実が内需の中心となっていました。特に、戦争で住宅が空襲にあった都市部などでは、著しい需要がありました。昭和30年代には、白黒テレビ、洗濯機、冷蔵庫などの家電製品が三種の神器と呼ばれ、国民の憧れの商品となっていました。更に、昭和40年代にはカラーテレビ、クーラー、自動車という耐久消費財が新三種の神器と喧伝される様になりました。このように次々と国民の憧れる新商品が登場してきましたが、平成の時代においては、もはやそのような商品が登場してこない状態が続いています。これは商品の開発力が落ちたと言うよりも、国民が豊かになり、本当に渇望するような商品がなくなってしまったからです。一方で海外に目をやれば、アジア、アフリカ諸国を中心に、まだまだ三種の神器や新三種の神器を渇望する人々はたくさんいます。この結果、日本のメーカーも国内よりも海外の市場を重視し、海外に工場進出をすることになったのです。日本の様に成熟した社会においては、かつての三種の神器のような憧れの商品は存在し得なくなっているということです。
社会保障費も内需の一つ
しかし、民需ばかりが内需ではありません。先に公共事業の長期計画が内需を拡大すると述べましたが、医療や介護といった社会保障や福祉の分野でも同じことが言えます。また、教育や安全保障の分野も然りです。社会保障や教育、安全保障の充実は国土強靭化と同様多くの国民が必要としていることです。正に、内需そのものなのです。
そう考えると、国内において国民が必要とする需要は無尽蔵に存在しています。これを要求しているのは国民ですが、発注するのは政府の仕事です。政府が予算化しない限り国民の要求は満たされないのです。正に政府の財政出動こそが必要なのです。 そして、これが実現できればデフレからの脱却が実現するのはもちろんのこと、我々個々人の生活自体が安全で豊かなものになるのです。そのためには、経済政策についての発想の転換をしなければなりません。
経世済民の意味を考える
企業が利益を上げることが経済政策だと思い込んでいる人がいます。企業が利益を上げるからこそ、多くの人を雇用し給料を支払い、税金も納める。それが国家や国民全体の利益につながる、そのように信じている人も多いです。確かに、かつては企業の利益と国家や国民の利益とが合致していました。しかし、社会が成熟し国内の民需が少なくなり企業が海外進出を積極的に行うと、そうした前提は崩れてしまいます。
企業の海外進出が盛んになった結果、企業の利益は何倍にも膨らみましたが、国内での雇用は少なくなり、国内で納める税金の額も半減しています。これは、企業が利益を上げることが必ずしも国全体の利益につながっていないと言うことです。
そこでもう一度経済の意味を考えてみましょう。経済とは経世済民、すなわち世を経め(おさめ)民を済う(すくう)と言う意味です。企業が利益を上げることではなく、国家や国民全体を幸せにすると言う意味です。この言葉の本来の意味の通り、どうすれば国民を幸せにすることができるのかを考えてみるべきです。
成熟社会では公需が内需の中心
 安倍総裁も京都に応援に駆けつけて下さいました
安倍総裁も京都に応援に駆けつけて下さいました
確かに、日本は物質的には豊かになりました。しかし一方で、光の当たらない分野も沢山あります。過疎化による地方の疲弊もあれば、都市化による環境破壊や子育て難民など人口過密による問題も山積しています。そういう意味では、地方も都市も人間が住むべき故郷が崩壊しているとも言えます。この解消には、インフラを整備して国土の均衡を図ることが必要です。また、子育てや介護などの充実も不可欠です。更に、安心して暮らすには防災減災は勿論のこと、防衛力の増強による安保政策の充実や沿岸部での治安を確保するために海上保安庁の巡視船を増やすことも必要でしょう。こうした事は国家が本来なすべき仕事です。これを実現するためには毎年継続し、計画的に予算を計上していかねばなりません。また、そのためには、その財源として国民に税の負担を願わねばなりません。
しかしこの20年、「官から民へ」の掛け声の下、政府の予算は一方的に削られてきました。本来のすべき仕事をせずに予算ばかりが削減されてきたのです。特に、民主党政権では事業仕分けの名の下に、徹底的に政府の予算が削減されてしまいました。企業の海外進出等により、ただでさえ内需が不足している時に政府予算を削減したのですから、デフレが一挙に加速し日本は不況のどん底に落ち込んでしまったのです。
民主党が言うように子育ての支援なども必要なことでしょう。しかしそのためには、財源をしっかり確保しておかねばなりません。本来、国民に税の負担をお願いしなければならないことを事業仕分けでやろうとしたところに問題があったのです。給付には負担が伴うのは当然のことです。国民の負担を隠し、給付ばかりを宣伝したところに彼らのあざとさがあったのです。また、そうした政策が破綻するのも当然のことです。
目先の財政健全化よりもデフレ脱却を優先すべき
以上述べてきた通り、これからは民需に代わって公需が内需の中心として位置づけられることになるでしょう。そのためには国民に相応の負担を願わねばなりません。消費税の10パーセントへの引き上げは、当然、早晩実施しなければなりません。しかし今はまだデフレの最中です。増税を延期したことは安倍総理の慧眼です。従って、増税の前に景気対策を徹底的に行わねばなりません。それには、長期計画に基づいて政府の財政出動を毎年継続して行っていくことが最も重要なのです。そのための財源は国債発行で賄えばよいのです。
これ以上国債発行すればハイパーインフレになると心配する人がいます。しかし、これだけ金融緩和をしても尚、ゼロに近い低金利で推移している現実を見れば、その心配は全くありません。それ程、日本のデフレは深刻なのです。財政出動により雇用が増え給料が上がり、消費が増えGDPが拡大しますから、最終的に税収も大幅に増加します。これにより国の財政も健全化するのです。
これは、実際にマクロ経済モデルを計算してみれば明らかです。先の臨時国会でも麻生財務大臣にデータを示して指摘いたしました。この様子はYouTube西田昌司財政金融委員会2014.10.16で是非ご覧になってください。
目先のプライマリーバランスにとらわれて財政出動を拒んでしまうと却ってデフレからの脱却が遅れ、結果的に財政の健全化もできなくなります。今こそアベノミクス2本目の矢を大胆に放つときなのです。
瓦の独り言
-今年はリンパ400年-
羅生門の瓦
新年、明けましておめでとうございます。皆様、穏やかな新年をお迎えになられたこととお喜び申し上げます。
さて、今年は琳派(リンパ)400年記念祭と称して京都の文化人が騒いでいます。瓦もリンパ、リンパと叫んでいるのを昨年から耳にしており「リンパ腺」のことか、と思っていたぐらいです。講演会などによると、2015年は本阿弥光悦が徳川家康から洛北鷹峯に土地を賜り「光悦村」を拓いて400年ということです。
「琳派」という言葉はどこかで聞き覚えがあります。また俵屋宗達の「風神雷神図」(改元のかぜ薬にも使われたモチーフ)屏風は美術の教科書にも出ており、皆さんもご存知と思います。この宗達のお友達が本阿弥光悦で、その孫が宗達から100年後に絵師となった「尾形光琳」です。「琳派」の名称はその光琳の「琳」をとって名付けられた言葉でごく近年(大正時代?・昭和30年代?)になって定着(?)していったようです。
絵画だけでなく、着物、帯、陶器、漆器などあらゆる工芸品にデザインとして用いられており、「琳派模様のきもの」などと日常生活のうえで使っています。いまさら琳派、RIMPAと呼ばなくても京都人の中には琳派の作品に対する馴染みや思想はしみついているのではないでしょうか。その一つが「小倉百人一首かるた」の図案です。あれは尾形光琳の筆によるもので江戸時代の元禄年間にできたといわれています。その「小倉百人一首かるた」を今でも作っているのが伏見の大石天狗堂です。いまでも全国の市場シェアーを100%占めているとか。さらには、かるたの競技大会でも公認かるた札は大石天狗堂の札のみです。また、花カルタも琳派文様とか?瓦はこちらの方がなじみ深いのですが・・・。猪に鹿に蝶、雨札の小野道風とかえる、伊勢物語に由来する杜若の札など、まさに王朝文化(?)をほうふつさせるデザインです。そういえば「琳派」は公家の王朝文化に由来しているとか。
では、今年は琳派400年ということで、新しい花札を買ってきて勝負と行きましょうか! あれ?だれも相手してくれないの?(だって、最近の若い方は花札のルールを知らないようで・・・)
東海道と中山道を歩いて分かった日本の実態
私は、今年の1月にふとしたきっかけで旧東海道を歩き始めました。最初は年内に京都にたどり着ければいいと思っていたのですが、歩き始めると生真面目なのか、せっかちなのか7月20日に京都の三条大橋に到着してしまいました。そうなると今度は旧中山道を歩いてみようということになり、10月初旬に滋賀県の草津宿に到着、合わせて1000キロを超える道程を踏破することができました。日本地図を見ながら、よくぞこれだけの距離を歩いたものだと感慨無量です。
以前より私は列島強靭化政策を唱えていました。その理由は、国土軸の再整備こそが日本全体の発展と防災のためにも必要だという思いからです。この政策を推進するためには、地方の実態をきちんと把握しておく必要があります。
ここ20年の市場原理主義政策により、政府の予算は削減され続けてきました。また、地方分権のためだと財源や権限が国から地方に移されてきました。しかし、結果は一番大きな地方である東京ばかりにお金が集中し、首都圏だけが栄えることになったのです。このままでは地方が消滅してしまいます。その現実を確認するには、百聞は一見にしかず、先ず自分で一度全国を歩いて見るのが一番だと思ったのが、街道歩きを始めた一番の理由でした。
徳川幕府は東海道や中山道を始め全国に街道を整備し、宿駅伝馬制度を設けました。旅人が宿泊できる宿場を設けると同時に、各宿場の間を飛脚や馬が往復することで、日本中に物資や情報が届けられるようになったわけです。その中でも東海道や中山道は江戸と京を結ぶ、まさに当時の物流の中心であったわけです。その栄枯盛衰の姿をこの目で確かめることにより今の日本に何が必要なのかが分かるはずだと、国会や地元行事の合間を縫って歩き始めたのです。
地方にこそ、国の宝は残っている
 参議院原子力問題特別委員長に就任いたしました(第187臨時国会 参議院国会役員集合写真)
参議院原子力問題特別委員長に就任いたしました(第187臨時国会 参議院国会役員集合写真)
これは出発前から予想された事でしたが、実際に歩いてみると東京を始めとする大都市部では、当時の面影を残すものは殆どなく、むしろ殺風景なその姿に驚かされました。産業道路に吸収され往時の面影が全くないばかりか、自動車優先でそもそも人が歩くことさえ困難な道路も沢山有りました。首都圏や大都市部では、工場やマンションなどの巨大な建物が林立しているわけですから、経済的には発展している地域といえます。しかし、私はそこに日本を感じることができず、無国籍で無機質な荒野を歩いている気がしたのです。
その一方で、都市部から離れた地域にはかつての日本の姿が残っています。特に、旧街道から離れた場所に国道が通った地域では、経済的発展からは取り残されたかも知れませんが、そこには日本の原風景や往時の人々の暮らしを感じさせるような場所がたくさんあります。特に、東海道では富士山の見える箱根や駿河路、中山道では山々に囲まれた木曽路などは観光地として現在も賑わっています。しかし、そういう有名な観光地以外の所では、建物が残っていても人が住んでいないため、このまま放置すればあと10年もすれば朽ち果ててしまうだろうと思われる場所もいくつも有りました。それどころか、地域にお年寄りしか居ないため、その宿場そのものが消滅してしまうのではないかと思えるところもありました。この10年の間にやるべきことをしておかないと、まさに日本の宝とも言えるものが、どんどん消滅してしまうということです。
人の往来を増やすことが地域再生の鍵
 BS日テレ「深層NEWS ~激論!生殖医療法と家族のあり方~」に出演いたしました
BS日テレ「深層NEWS ~激論!生殖医療法と家族のあり方~」に出演いたしました
では、日本の原風景を残しながら、経済的にも潤い、そこに人が住み続けることができる仕組みを構築するには、どうすれば良いのでしょうか。
元々、宿場が栄えたのは人の交流の拠点であったからです。人の交流こそが地方再生には必要なのです。物流は新たにできた国道や鉄道などに任すとしても、人の交流を増やす方法を考えなければなりません。
江戸時代にお蔭参りが流行り、庶民が講でお金を集め伊勢神宮に何百万人もが押し寄せたと言われています。文政13年(1830年)のお蔭参りでは、参詣者数427万6500人と言われていわれていますが、当時の日本総人口は3228万人(1850年)ですから、その一割を超える人が、お伊勢さんにお参りしたことになります。これだけの人が移動し交流をすれば、莫大な経済効果があったことは想像に難くありません。もし今、1億2000万人の1割の1000万人がかつての街道を歩いて交流すれば、街道は栄え地域再生されることは間違いありません。
現代の旧街道は歩きにくい
しかし、東海道や中山道を踏破して感じたことは、当時に比べて随分歩きにくくなっているということです。まず、道標が整備されていません。旧街道は、道幅も狭く大きな道路が近隣にできると埋没してしまいます。中山道の様に山岳地帯を縦断する街道では、一度道を外れると大変なことになってしまいます。標識がきちんと掲げられている地域では安心して歩けますが、残念ながら街道全域に完備されてはいません。私も、何度も道に迷いながら歩きました。特に山岳地帯では正しい道なのか確信が持てず、不安になったものです。多くの国民に街道を安心して歩いてもらえる工夫が必要です。
箱根の様に、国道が隣接し茶店も残り旧街道として整備されていれば、険しい山道も安心して登れます。それが、同じ峠道でも、中山道の碓氷峠や和田峠の様に、国道から離れ茶店どころか自動販売機すら無く、未整備の道が延々20キロも続く道では、誰もが安心して歩くことができるとは言えません。私の場合は、それに加え野生の猿や鹿が出てきて肝を潰しました。実際、箱根峠では旧街道でも何人かの人と出会うことがありましたが、碓氷峠や和田峠では誰一人出会うことはありませんでした。また、大木が倒れて峠道を塞いでいたり、雨が降って沢のようになっている箇所もありましたが、江戸時代は中山道も物流の中心をなす国土軸であったわけですから、峠道もきちんと整備されて今よりはずっと歩きやすかったはずです。街道を歩くには茶店の存在が不可欠ですが、今は、その茶店がありません。都市部にはコンビニがその機能を担ってくれていますが、山岳地帯には全くありません。
私が街道を歩いたのは殆ど真夏の季節でしたが、一番辛かったのは強力な陽射しです。自動販売機でスポーツドリンクを買って水分補給をしても炎天下では文字通り焼け石に水です。かつては街道沿いには松や杉などの並木が両側に植えられ、旅人を強い陽射しから守ってくれたと言います。こうしたインフラが整備されていたからこそ、安心して街道を歩くことができたのです。
地方再生には国の権限強化が必要
 東海道五十三次の終点、三条大橋で支援者に迎えられる
東海道五十三次の終点、三条大橋で支援者に迎えられる
安倍総理は内閣改造で石破幹事長を地方創生担当大臣に指名し、地方の再生が内閣の最重要課題であることを示されています。地方再生はこの20年間ずっと言われてきたことですが、現実には首都圏の一極集中が止まりません。これを実効あるものにするには、今までの様に国の予算と権限を地方に回すというようなやり方ではできません。交通網などのインフラ整備の状態や地理的条件が全く違う地域が多く存在している中、そのような政策をすればますます格差は拡大するばかりです。むしろ、首都圏から財源を吸い上げ地方に配分することが必要なのであり、そのためには国の権限を強化しなければなりません。石破大臣にはぜひともそのことを総理に進言していただきたいと思います。
街道の再生で故郷に人を呼び戻す
街道を再整備すれば、間違いなくそこを人が歩き出します。人が歩けばお金が動きます。お金が動けば経済が活性化します。経済が活性化すればそこに人が住みます。人が済めばそこに町ができます。江戸時代の宿場町はこうしてできあがったのです。
江戸時代には人口は約3000万人と言われていましたが、現代の日本はその4倍の人口を擁しています。旧街道を再整備して誰もが歩ける道を再生したなら、多くの人が歩き出すことになるでしょう。特にこれからは仕事を引退した中高年の人口比率がますます増えます。それらの人々の数は江戸時代の日本の人口よりもはるかに多いでしょう。こうした方々が気軽に安心して歩くことになれば地域経済が活性化するのは間違いありません。それは江戸時代の例が証明しています。そればかりか、歩くことにより健康状態も必ず改善されるはずです。それにより医療費などの負担の軽減にもつながるでしょう。これらの金額は、旧街道の整備に必要な予算額よりもはるかに大きなものになるはずです。
旧街道を整備して国民が歩き出すことにより、国家も国民も故郷も健全化するのです。是非とも地方再生の目玉として実施をしていただきたいものです。
樋のひと雫
- 民族の独立 -
羅生門の樋
先月にスコットランドの独立を問う住民投票が行われ、スコットランド人は10ポイントの差で英国に留まることを選択しました。投票までの2週間ほどはワイドショーも盛大に取り上げていました。欧州を身近に感じない身には、何か遠くの出来事のようにも感じていました。でも、「独立を住民投票で決める」ということには、驚きと違和感を持ちました。第2次大戦後、「民族自立」の名の下に多くの植民地が独立し、欧州の帝国主義も終焉を迎えました。これには多くの民衆の血が流れました。そして、幾多の建国の英雄も生まれました。我々の世代にとって、「民族の自立」とは、民衆が血と肉体を以て民族の誇りと歴史を取り戻すものという映像が付きまといます。平和裏に、しかも投票権を保障された独立へのプロセスを、テレビ報道で見ることに、戸惑いと民主主義の底の深さを見た思いです。
一方で、この投票という行為は、第2次大戦後の国連を頂点とした世界秩序をも打ち崩す、新たな世界のカオス(混沌)の扉を開くことになるかも知れません。東西両陣営によってタガをはめられていた世界は、朝鮮やベトナム等での局地戦はあっても、それなりに秩序を維持してきました。その後の経済の発達と社会の進歩は、東側陣営の崩壊を促しましたが、EU経済圏の創出等もあり、大きな秩序の崩壊は免れてきました。
このような中で、既存の国家の存立すら住民投票に依るという行為は、更なる扉を開けることになるかも知れません。来月にはスペインでカタルーニャ州の独立を問う投票が予定されているそうです。スペインではバスク地方の独立運動は、以前から激しい武装闘争を展開してきました。スペイン政府は新たな火種を抱えたことになります。それも、武装闘争なら直接行動の手段も取れますが、投票を求める民衆には警察権力も軍も動員できかねます。
また、一見強固に見える秩序は、クリミア半島での住民投票によるロシア帰属を実質的に容認するかの如くです。国連を中心とした世界秩序は、どこかで軋みを生じ始めたように思えます。そして、中国でのチベット族やウイグル族の問題や宗教問題を内包した東アジアにおける少数民族問題など、現政府に対する犯行を「テロリスト問題」で解決してきた国々には、民衆統治の在り方を根底から考え直す機会になるかも知れません。
ただ、独立を問うテーマが、税の不公平な分配であるカタルーニャの住民投票は、スペイン建国の歴史がどうあれ、豊かな地方の住民エゴが臭います。民衆の自立が住民投票という手段を持った今、世界のカオスを開く扉の鍵がまた一つ増えたように思えます。
安定した外交安全保障政策
第186国会は、6月20日に150日間の会期を2日間残して事実上閉会いたしました。平成19年の初当選以来、通年国会と言われるほど国会の会期が延長されることが常態化していましたから、こんなに早く国会が閉会した事は私にとっては初めてのことです。また、内閣が提出した法案の成立率は9割を超え、近年まれに見る高い水準となりました。この事は、一昨年の衆議院総選挙で政権を奪還し、昨年の参院選で衆参の捻れを解消したことにより政権が非常に安定したことを示しています。
また、安倍総理は政権奪還以来、毎月のように外遊に出かけられ、各国の首脳と個人的にも信頼関係を高めておられます。近頃、中国の海洋進出が周辺諸国の安全保障に大きな影響を与えていますが、こういう時だからこそ各国の首脳と共通の問題意識を持つ事が非常に重要になるのです。その結果、集団的自衛権行使についての閣議決定も中国や韓国などが安倍政権について批判的立場を示していますが、その他の国については概ね理解を得られているようです。マスコミは集団的自衛権の閣議決定の批判ばかりしていますが、これでは中韓の立場を代弁するようなもので、あまりにもバランスを欠く報道です。
滋賀県知事選の敗戦の理由
 西田昌司国政報告会2014を開催いたしました
西田昌司国政報告会2014を開催いたしました
たくさんのご来場誠にありがとうございました
嘉田滋賀県知事の不出馬を受けての知事選挙は、当初は自民党が推薦する小鑓(こやり)候補の優勢が伝えられていました。しかし選挙戦の後半になると、逆に元民主党衆院議員の三日月候補が優位に立ち、デッドヒートを展開しました。そして、結果は、小鑓(こやり)候補のまさかの敗戦でした。その理由をマスコミなどは、安倍政権の集団的自衛権行使可能の閣議決定が強引であったためであるとか、東京都議会の野次問題であるとか、様々な原因をあげています。確かにそうしたことも原因の一つであったかもしれませんが、私はもう少し本質的なところに原因があったと考えています。
そもそも安倍政権が誕生した理由は、民主党政権の失政に対する失望とその修正を国民が求めたことにあります。外交安全保障の分野では、安倍政権は民主党の失政を正し、安定した外交安全保障政策を行っています。特定秘密保護法や集団的自衛権の行使についてマスコミが批判していますが、これは独立国としてはどの国でも行っていることで、批判には当たらないものと考えています。
一方、最近発表される経済政策が、あまりにも新自由主義に向いているのではないかということを私に質問される方が大勢おられます。確かに、ホワイトカラーの中に残業代をなくしてしまう職種を作るといういわゆるホワイトカラーイグゼンプションや人手不足を背景にした外国人労働者の受け入れ促進策など、社会を混乱させる要因と成り得る政策には私も非常に懸念しています。これはかつて、小泉内閣で掲げられてきた新自由主義的政策ではないか。こうした政策が日本の社会を混乱に陥れ、それに対する批判により政権を下野したはずではないかという意見には、素直に耳を傾けるべきだと私も考えています。
小泉元総理と安倍総理は同じと言った竹中平蔵氏
 参議院自民党政策審議会にてJAL問題の本質について説明いたしました
参議院自民党政策審議会にてJAL問題の本質について説明いたしました
先日、京都で竹中平蔵氏の講演会があり、「原子力政策以外は小泉元総理と安倍総理は同じ」と竹中氏は発言したそうです。これが本当なら由々しき事です。そもそも竹中氏は小泉内閣の構造改革の司令塔として新自由主義路線を牽引してきた人物です。言わば自民党が下野した最大の原因を作り出した人です。そのため、未だに党内では竹中氏に対しては厳しい批判の声が聞かれています。
その竹中氏が、第二次安倍政権が発足するや、産業競争力会議の委員として総理に政策提言する立場になることには大勢の方が心配していました。私もその一人で、安倍総理に対して、新自由主義的政策とそれを主唱してきた竹中氏の登用を避けるべきとの諫言も敢えてしてきたのです。
総理は、竹中氏の非登用は拒まれましたが、新自由主義ではなく「瑞穂の国の資本主義」を目指すとし、アメリカ型の新自由主義とは一線を画すと明言されたので、私たちは政策の行方を見守ってきたのです。しかし、当の本人である竹中氏が小泉元総理と安倍総理が同じと言うに至っては何をか言わんやです。
アベノミクスは何だったのか
 BSフジ「ブラマヨ弾話室~ニッポンどうかしてるぜ!~」に出演いたしました
BSフジ「ブラマヨ弾話室~ニッポンどうかしてるぜ!~」に出演いたしました
日銀による金融緩和と機動的財政出動、さらに民間の成長戦略を同時に行いデフレからの脱却を目指すとしたアベノミクスでしたが、デフレ対策として一番効果があったのは財政出動です。逆に言えば、財政出動を削減してきたことがデフレを創出したのです。デフレ対策を行うには何がデフレの原因だったのかを検証しておく必要があります。
戦後日本が復興し出したのは、昭和25年の朝鮮戦争による特需がきっかけと言われています。その後東西冷戦により、世界は二分されてきました。この環境は、昭和が終わるまでずっと続いてきました。冷戦時代に日本は西側にいたお陰で経済的にも大いに発展することができました。
しかし、平成の時代は、冷戦も終わり世界は一つになり、旧共産圏の国とも貿易ができるようになりました。地球規模のグローバル市場が誕生した結果、昭和の時代とは全く異なる経済の仕組みが誕生しました。
先ず、企業活動が全世界に及ぶことになった結果、先進国から発展途上国に投資が増え、製造拠点が国外流出することになりました。そのことにより、企業活動の業績は飛躍的に拡大しましたが、母国から雇用も税金も海外に流出してしまいました。結果、先進国は国内での民間の消費や投資が減るため、民需主導では常にデフレ圧力を受けることになったのです。これは日本だけに限らず、全ての西側先進国が経験をしてきたことなのです。
こうしたことの理解がないまま、民需主導の構造改革が20年にわたり続けられた結果が、あのデフレをもたらしたのです。本来、アベノミクスはこうしたことの反省として民需主導の新自由主義から決別するための経済政策だったはずなのです。
歴史の事実を検証する
このように考えるとアベノミクス最大の問題点は、経済政策の歴史的検証が十分行われていないことだと分かります。だからこそ、デフレ政策を推し進めた竹中氏が未だに尚政府の諮問委員として重用されているのです。実は、こうなることを恐れ、私は自民党が下野していた時代に、構造改革に対する検証を党内でしっかりと議論をして整理をしておくべきだと、再三にわたり主張してきたのです。それがあと少しで構造改革派を封じ込められるという矢先に、自民党が政権に復帰してしまいました。
民主党にこれ以上政権を任すわけにはいかず、政権復帰は歓迎すべきことでしたが、経済政策の総括が不十分なまま政権に復帰したことは、やはり問題であったといわざるをえません。
同じことが、安全保障政策についても言えます。集団的自衛権の行使を可能とする閣議決定は当然です。しかし、問題はそもそも占領中のGHQによって日本が作り変えられたという事実を国民が知らされていないことです。このことをただの一度もまともに議論し、報道したためしがありません。国会もマスコミも大いに反省する必要があります。こうしたことを議論し、国民にお知らせするのが私の責務と考えています。今後ともご支援をよろしくお願い申し上げます。
瓦の独り言
- え! こんな浴衣が! -
羅生門の瓦
七月。洛中では祇園祭一色で、可哀想に「きゅうり」が食べられないとか。洛外に住んでいる瓦にとってはあまり関係がないことですが、やはり宵山になると浴衣を着てそぞろ歩きに出かけます。
昨年の宵山でびっくりしたことがあります。ミニスカートのような浴衣を着たギャルたちです。(ご令嬢とは言いたくありません) ショッキングピンクやブルーのけばい色彩に金髪、派手なアクセサリー。おまけに花魁のように背中を見せたような着こなし。まるでキャバクラ(瓦は行ったことがないのですが・・・)から抜け出してきたような衣装でした。こんな浴衣を着て歩いていたら祇園さんのばちがあたるで、と心の中で叫んでいました。あー、こんな浴衣がはやるのかいなあ~、と嘆いていました。
ところが、六月末日の新聞の「浴衣本物志向に」の見出しを見てホッとしました。「今年は白を基調とした落ち着いた色合いが・・・」「若い人も目が肥えてきて、大人っぽい浴衣を選ぶ傾向・・・」「既製品ではなく、反物から仕立てる動きも・・・」
かつて、浴衣は既製品ではなく、母親が娘、お婆ちゃんが孫のために反物から仕立てたもので、さらに歴史をさかのぼると「浴衣一枚縫えるようになって、やっと一人前の女性」と認められたのだとか。でも十年ほど前から既製品の浴衣が出回り、ユニクロまでが浴衣を販売しだしました。(ところが、ここ二、三年ユニクロは浴衣を販売していません。業界筋ではコスト面だけではなく本物志向に照らして、撤退したとか)綿の素材が中心ですが、麻もありましたし、高級な小千谷縮、有松絞も夏の浴衣に仕立てられていました。藍染が中心で白と紺色のコントラストに何とも言えぬ大人の女性の色気を感じていたのは瓦だけではないはずです。Tシャツ感覚で浴衣を勧める時代は終わったのではないでしょうか。いや、終わらせるべきです。浴衣といえども、和装です。堅苦しいことは言いませんが、それなりのルールで着てほしいものです。
[浴衣とは和服の一種である。通常の和服とは違い、長襦袢を着用せず、素肌の上に着る略装である【Wikipedia】]
安全保障法制推進本部の設置
安倍総理は、7年前の第一次内閣の時から戦後レジームからの脱却をスローガンとして掲げておられました。その意味は、戦後の占領時代に作られた、憲法を始めとする価値観や制度から脱却するということですが、同時にそれは、自分の国を自分で守ることを議論することさえタブーになっていた、戦後の政治体制に対して大きな疑問を投げかけるものでした。そのため、戦後の価値観を守ることが使命だと自認していたマスコミ各社に袋叩きにあい、支持率が瞬く間に低下し、結果的に辞任に追い込まれることとなりました。
しかし、今日、中国の経済力・軍事力の発展に伴い、領土的野心をむき出しにしてくる様子や北朝鮮の軍事的独裁体制を目の当たりにしてみると、危機感を覚える人も多いことでしょう。国民の誰もが今のままでは日本の国を守ることができないと感じ出しています。こうした中、第二次安倍内閣においては、経済の再生と同時に、外交安全保障の再生も大きな課題となっています。そこで昨年末の臨時国会においては、国家安全保障会議の設置と特定秘密保護法を成立させ、友好国と情報を緊密に交換しながら、常時、国家の安全保障について議論できる組織を作ることができました。しかし、これで国の安全保障が十分担えるわけではありません。結局一番の課題は憲法、特に9条に関わる問題を整理することなのです。
何故自衛隊は存在するのか
 参議院予算委員会にて安倍総理にデフレ脱却を中心に質問をいたしました
参議院予算委員会にて安倍総理にデフレ脱却を中心に質問をいたしました
現行憲法の最大の矛盾は、武力放棄を規定しながらも自衛隊と言う実質的な軍隊を有していることです。自衛隊は当初は警察予備隊として昭和25年に発足しましたが、その原因は朝鮮戦争です。北朝鮮が韓国に侵攻してきたため、日本に駐留していた米軍の多くが朝鮮半島に派兵されることになりました。日本の治安を司る米軍を補完するために、GHQは日本に再軍備を要請したのです。当時は占領中ですから、GHQの指令には従わざるを得ません。つまり、軍事力の放棄も再軍備も日本の意思ではなくGHQの意思によりなされたものなのです。
巧妙なGHQの占領政策
占領当初、GHQが目的としていたことは、日本の解体であり、非武装化です。そのための手段として日本国憲法が与えられたのです。しかし、一方で占領政策を円滑に行うには、日本人の自発的協力が必要です。日本を本当に解体するには皇室の廃止が必要ですが、それには大きな抵抗が伴い、多くの血を見ることは容易に想像できます。それを回避するために生まれたのが、日本人が自主的に改憲をしたという物語です。そのためには、皇室の継続を保障することは絶対的必要条件です。当初は、皇室の廃止もGHQは考えていたと言われていますが、結局、彼らも憲法の第1条に天皇を国民統合の象徴と書かざるを得なかったのです。しかし、この条文があるために日本人は明治憲法を自発的に改憲したということに納得してしまったとも言えます。
GHQの政策変更により変わった憲法解釈
 テレビ朝日「ビートたけしのTVタックル」~安倍総理の描くニッポンのかたちとは~に出演いたしました
テレビ朝日「ビートたけしのTVタックル」~安倍総理の描くニッポンのかたちとは~に出演いたしました
ところが、GHQの占領政策は朝鮮戦争により大きく転換したのです。そして、それに伴って日本政府の自衛権についての憲法解釈も180度転換しました。
第90帝国議会の衆議院帝国憲法改正案特別委員会(1946年6月26日)吉田茂内閣総理大臣答弁では、「戦争放棄に関する本案の規定は、直接には自衛権を否定はして居りませぬが、第9条第2項に於て一切の 軍備と国の交戦権を認めない結果、自衛権の発動としての戦争も、また交戦権も放棄したものであります。 従来、近年の戦争の多くは自衛権の名に於て戦われたのであります。満州事変然り、大東亜戦争然りであります」と自衛権すら完全に否定していました。
ところが、朝鮮戦争が始まる1950年には次のような答弁に変わります。まずマッカーサー元帥が年頭の辞で「日本国憲法は自衛権を否定したものでは無い」と表明します。これを受けて吉田総理は1月の参議院本会議で「いやしくも国家である以上、独立を回復した以上は、自衛権はこれに伴って存するもの。安全保障もなく、自衛権も無いが如きの議論があるが、武力無しといえども自衛権はある」と180度内容が変わります。そしてその年の6月に朝鮮戦争が勃発、8月には警察予備隊が発足します。このようにアメリカの占領政策の変更を受けて、日本は憲法解釈を変更し、自衛隊を持つに至ったのです。
砂川裁判の判決 -自衛権は独立国として固有の権利であり、自衛隊は合憲-
独立国に自衛権があるのは当然です。しかし、それを占領当初は憲法を盾に自衛権はないという解釈をしてきました。それが180度転換されたのですから、混乱が生じるのも無理はありません。こうした状況の中、1957年、米軍基地の中にデモ隊が乱入するという事件(砂川事件)が起きました。この事件の裁判により自衛権や安保条約の是非についての司法判断が出ました。1959年12月、最高裁は「憲法第9条は日本が主権国として持つ固有の自衛権を否定しておらず、…」という判決を出し、自衛隊は合憲とされることが確定したのです。
日本を軍事的に解体し、自衛権も放棄させるために作られた憲法でしたが、独立を果たした以上は、自衛権は固有の権利として認められるという解釈が合憲であることが確定したのです。憲法を解釈で変更するのは違法だという人がいます。しかし、それが違憲かどうかを判断するのは最終的には裁判所です。その最終判断はすでに50年以上前に合憲と確定しているのです。
個別的自衛権と集団的自衛権
 総理公邸にて参院副幹事長と総理との懇談会に出席いたしました
総理公邸にて参院副幹事長と総理との懇談会に出席いたしました
個別的自衛権とは、自国に対する他国からの武力攻撃に対して、自国を防衛するために必要な武力を行使する、国際法上の権利のことです。集団的自衛権とは、ある国が武力攻撃を受けた場合、これと密接な関係にある他国が共同して防衛にあたる権利であり、ともに国連憲章において主権国家に認められているものです。砂川裁判では個別的か集団的かという区別をせず、主権国家は固有の自衛権を持つと判断をしています。従って、主権国家の固有の権利として集団的自衛権を持っているのは自明のことです。
問題は、今までに政府が、集団的自衛権は持っているが、それを行使することはできないと答弁をしてきたことです。このような意味不明の答弁をしてきたのは、主権国家の意味をまともに考えることを避けてきたためです。
昭和27年のサンフランシスコ講和条約により日本は独立を回復し、昭和31年には国連にも加盟しているのですから、国際的にはその時から個別的自衛権も集団的自衛権も日本には認められているのです。
しかし、敗戦のトラウマと占領政策により日本は、自分の国は自分で守るという主権国家としての当然の義務と権利を半ば放棄してきたのです。そのことはその当時の政府の答弁にも現れています。その結果、積極的に国を守ることを放棄して、アメリカに守ってもらうことの方が正しいという詭弁を弄してきたのです。
憲法は占領基本法であることを国民に伝える
私はかねてから、現行憲法は無効であり、それは占領基本法に過ぎないということを主張してきました。それは占領時代には、日本国民の主権は認められておらず、実質的にGHQが占領目的の遂行のために作られたという事実を考えれば当然のことです。しかし、この事実がまだまだ国民に共有されていません。そもそも、未だにこの憲法が日本国民の手によって作られたと学校の現場では教え続けています。それは、政府が憲法問題の本質について整理してこなかったからです。その結果、憲法が規定する内容に違和感を覚えながらも、それを平和憲法として受け入れてきたために、憲法についてまともに議論すらできなかったのです。
安倍総理は、日本の外交安全保障を強化するために、様々な改革に取り組んでおられます。しかし、それはまさに戦後の常識に異議を申し立てることです。それを国民に理解してもらうには、占領中に行われてきた事実をもう一度国民にじっくり説明する必要があります。勿論、それは一朝一夕にはいきませんが、諦めず説明して行くことが大切です。そして、多くの国民がそれを理解した時、日本の戦後は終わるのです。
樋のひと雫
羅生門の樋
お昼のワイドショーを続けて見る機会がありました。これも毎日が日曜日になった故ですが。しかし、驚きました。テーマが北朝鮮問題や日韓・日中関係など、外交問題まで茶の間の話題になっていることです。つい先日まで居た南米にも、同じような番組はありましたが、内容は料理やゴシップ、ファッションばかりです。まあ、お国柄と言えばそれまでですが。こんなところにも、日本の教育水準の高さが窺えることに、変に感心をしました。
番組を見ていて思ったのですが、日本はいつまで卑屈な姿を続ければいいのでしょうかね。習政権の安重根記念館建設や朴政権の告げ口外交にして、有効な手立てのないことは分かりますが、「遺憾の意」を表するだけでは、何か見ていて苛立ちを覚えます。日米韓三首脳の会談で、一国の首相の挨拶を無視する態度も、あれでよいのですかね。会談の窓口は開けていると言っても、手をこまねいているだけでは、事態は進みそうもありませんね。まあ、話し合いなんてものは、必要性を感じなければ出来るものではないでしょうが。出演している識者の多くは、もっと日本が努力すべきという論調ですが。別段話し合いの必要性を感じない相手に、何を努力するのでしょうね。話し合いなんてものは、互いの存在の必要性や利益の伸長があって初めて成り立つものでしょうから。必要や利益がなければ、話し合う気力も起きないでしょうね。
ところで、世間を騒がせ始めた集団的自衛権ですが、解釈でどうにかなる問題でもないでしょう。ここはやはり、正論として憲法改正論議の中で深めるべき問題ではないですかね。それも、真摯に日本の五十年、百年先を見据えて、独立と尊厳を如何に守るかを考えたいものです。集団的自衛権を認めれば、すぐにでも戦争に出かけるようなマスコミの煽り論調もいい加減にして欲しいものです。それに、集団的自衛権を発動する事態(朝鮮半島の問題でしょうが)が起こっても、今の日本人の感情では、素直に韓国に同情して参戦できますかね。安倍首相の挨拶を馬鹿にしたような朴大統領の横顔を見た日本人にとって、我々の血を流してでも友情を守るという感情は起きないでしょう。ひょっとしたら、在日米軍の基地使用にも反対運動が起きるかも。なんせ、米軍が交戦するための基地使用には、日本の同意が必要なはずですから。もしも北朝鮮に、「拉致した日本人は全員送還します。詫び状も書きます」なんて言われたら、完全中立を支持しますよ、今の日本人の感情では。韓国の反日感情も高まっているそうですが、火を点け、油を注いでいるのは、我々から見ればお宅の方だと思うのですが。こんなことを、ワイドショーを見ながら思いました。
中小企業や地方にも景気対策の実感を
安倍内閣が発足して2年目を迎えます。この1年を振り返りますと、めざましい成果がありました。先ず、デフレ対策です。いわゆるアベノミクスにより、円高が収まり外国為替相場は、民主党政権時代には70円台になっていたものが100円前後で推移しています。これにより海外への輸出が大幅に伸び、企業収益も回復してきました。また、この1年で株価は1.5倍に上昇し、現在は1万5,000円台を推移しています。大手企業では年末のボーナスも上昇したところが多く見られています。
しかし、中小企業や地方経済には、アベノミクスの恩恵を受けられていないところもまだまだたくさんあります。今年は、こうした方々や地域にも、景気回復を実感していただけるようにすることが、まず第一の課題です。
日本版NSCと特定秘密保護法が成立
 フジテレビ「新報道2001」に出演いたしました
フジテレビ「新報道2001」に出演いたしました
年末に日本版NSC(国家安全保障会議)設置法と特定秘密保護法が成立いたしました。私は、この特別委員会の理事を務めて参りました。そもそもこの法律は国民の生命財産を守るためのもので、特に国家的な安全保障の危機やテロの脅威から国民を守るためにどの国においても同じような法律があります。ところが、マスコミはこの法律を国民の知る権利を侵害するものだとか、戦前のような国に戻ってしまうとか、全く出鱈目な報道を繰り返してきました。その結果、国民に不要な心配と誤解を与えています。
国家安全保障会議というのは総理大臣と官房長官、さらに外務大臣と防衛大臣の4大臣が常時国家の安全保障に関することについて意見や情報を交換することにより、不測の事態に備えようとするものです。そして、国家安全保障会議が有効に機能するためには友好国と適宜情報の交換をしなければなりません。そうした機密情報は安全保障の観点から機密を守る必要があるのは当然のことです。一方で、そうした機密も一定の期限が来れば、当然国民に公開をしなければなりません。そこで、原則5年が経てば情報公開するということになっています。しかし、5年経った段階で、情報を公開すべきでないと担当大臣が判断した場合には30年までの更新が可能となっています。また、30年経った段階でも内閣が必要と判断した場合にはその延長が認められています。こうしたことを、マスコミや野党は、特定秘密が恣意的に秘匿され、結局は国民に公開されないのではないかと盛んに喧伝しているのです。
民主党時代にこそ情報が恣意的に秘匿
しかし、これは全くの誤りです。そもそも特定秘密の指定は大臣が恣意的に行うものではありません。外交、防衛、特定有害活動の防止、テロリズムの防止に関するもので法律によって限定的に列挙された事項について、特段の秘匿の必要性があると認められたものに限られています。この法律ができるまでは秘匿の必要性についての基準がなく、各省が独自の判断をせざるを得なかったのです。そして、その中には恣意的な情報の秘匿もありました。その典型が民主党政権時代に起きた尖閣事件です。中国船が海上保安庁の巡視艇に衝突したのですが、外交問題になるのを恐れた民主党政権は、そのビデオを隠蔽したのです。それを海上保安庁の職員がインターネット上で公開したことにより国民の知るところとなりました。当時、民主党はこれに対して激怒し、特定秘密保護法を作ろうと目論んでいたのです。民主党は、今回の特定秘密保護法で恣意的な情報隠蔽が行われる恐れがあると盛んに喧伝していますが、まさにそれをしたのは当時の民主党政権だったのです。しかし、今回の法律が制定されれば、逆にこうした恣意的な隠蔽ができなくなります。何故なら、尖閣事件の情報などは特定秘密の対象にはならず、原則公開されるべき情報だからです。もっと早くこうした法整備をしておけば、あの海上保安庁の職員も辞めなくて済んだのです。
秘密指定が30年を超える場合がある理由
 参議院特別委員会での「特定秘密法」採決の様子
参議院特別委員会での「特定秘密法」採決の様子
また、特定秘密の指定が30年を超えるケースですが、具体的にはこういうことが考えられます。ある国から日本の安全保障に関わる重大な情報を提供されたとしましょう。その情報提供者が20歳の若者だったとして、30年経ってこの事実を公開した場合、その時点で若者は50歳になっています。しかし、たとえ30年が経っていても、場合によっては情報公開により、この人物の命を危険にさらしてしまうことも予想されます。これではこうした情報は日本には提供されなくなるでしょう。そこで30年を超えても特定秘密の指定を例外的に延長できることも考えておかなければならないわけです。このように、すべては国家や国民の生命財産を守るために必要なものであり、独立国家ならばどの国にも存在する仕組みです。むしろ、こういう仕組みがなかったこと自体が日本の問題であったわけです。
平和主義を唱えるだけでは国は守れない
そもそも、この法案に反対している民主党などの野党やマスコミは、日本の安全保障についてまともに考えたことがあるのでしょうか。国会の外で反対のデモをしている労働組合の方々や、この法案に反対している文化人と称される方々は、この法律が憲法違反だと言っています。憲法はその前文で、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。との述べています。しかし、この前提がもはや空文化している事は誰の目にも明らかでしょう。
中国が領土的野心をあからさまに表し、北朝鮮はいまだに拉致した日本人を返さず、核ミサイルを装備しようとしている、韓国も竹島問題では頑なに主張を譲りません。これほど安全保障上の危機を迎えたのは、戦後初めてのことです。
憲法に掲げる平和を愛する諸国民など存在しないのです。自分の国は自分で守る事は当然であり、今回の法整備はそのためのものなのです。マスコミや民主党などの野党は、国家の安全保障についての基本理念が完全に欠落をしています。彼らは、本当に平和を愛する諸国民の公正と信義に身を委ねていれば日本は大丈夫と信じているのでしょうか。彼らが国民を守るための政府のこうした法整備に反対することは、全く馬鹿げた矛盾した行為です。結局、彼らは憲法に掲げる平和主義を唱えているだけで、現実世界を無視し思考停止をしているだけなのです。
政党の体をなしていない維新の会やみんなの党
 自民党京丹後総支部の皆様と石破幹事長に鳥取豊岡宮津自動車道の早期開通について要望をいたしました
自民党京丹後総支部の皆様と石破幹事長に鳥取豊岡宮津自動車道の早期開通について要望をいたしました
日本維新の会やみんなの党とは衆院で修正協議をして共同提案者となることができましたが、民主党は全く議論に応じませんでした。一度は政権を取り国家の安全保障の重要性を認識したと思っていましたが、結局彼らは何も学んでこなかったのです。また、残念だったのは、共同提案者になったはずの維新の会やみんなの党においても参議院の審議には非協力的であり、採決の際には棄権をしたことです。その後、みんなの党の分裂が発表されましたが、結局、彼らは政党の体をなしていなかったということです。議員個人が各自バラバラなのですから、政党同士の議論などできるはずがないのです。
余裕のある審議日程を
ただ、我々与党も反省すべき点があります。それは、審議日程があまりに窮屈だったことです。この法案を早期に成立させるべきであるからこそ、もう少し審議日程を確保すべきだったと思います。安倍内閣はこの1年で経済政策、外交政策、安全保障政策で数多くの実績を残してきました。これは評価されるべきことです。民主党政権とは段違いの成績です。民主党時代に損なわれた国益を取り戻すために、安倍総理が全力で国政に取り組んでいることは衆目の一致するところです。しかし、あまりにやるべきことが多過ぎて法案審査が窮屈になったことは否めません。しかし、功を焦る必要はありません。先ずはデフレ脱却に全力で取り組むべきだと思います。
デフレからの脱却が最優先課題
2年目の安倍内閣の最優先課題は、間違いなくデフレからの脱却でしょう。特に、今年は4月から消費税が8パーセントに上ることが決まっています。毎年、社会保障の給付額が1兆円以上増え続けていくことを考えれば、消費税の増税はやむを得ません。しかし、増税後、消費の落ち込みが長引けば経済に悪影響を与えてしまいます。これを回避するためには、予算面で徹底的なデフレ対策が必要です。
デフレとは物価の持続的な下落のことです。そして、その原因は需要不足です。日本を始めとする先進国では一定水準の経済的豊かさを獲得すると内需は減少する傾向にあります。これは、豊かになれば欲しいものがなくなるということです。一方で、世界中にはまだまだ貧しい国がたくさんあります。これらの国は、先進国より貧しい分だけ需要が豊富にあります。貧しいからこそ欲しいものがたくさんあるということです。そのため、投資は先進国から発展途上国に移ることになります。その結果、先進国の雇用が減り、それがますますデフレを加速させることになるのです。デフレは先進国が陥る経済の病なのです。
確かに民需は減少傾向にありますが、日本にはそれを補って余りあるほどの公需が存在します。耐震、防災、インフラの更新の必要性などは誰もが認めるものでしょう。こうした事業を継続的に行うことが、デフレからの脱却に必要不可欠なのです。こうした予算をしっかり確保することが大切です。
本年も、安倍総理を支え全力で頑張ります。ご支援ご協力をよろしくお願い致します。
瓦の独り言
-お正月のお菓子は「葩餅(はなびらもち)」-
羅生門の瓦

みなさま、新年あけましておめでとうございます。
お正月のお菓子に「葩餅(はなびらもち)」があります。これについては、過日、京都伝統産業ふれあい館で亀屋末富の山口富蔵社長のセミナー「京のお菓子とお正月」で説明がありました。恥ずかしい話ですが、それまで瓦は「葩餅」については詳しく知りませんでした。だって洛中のお正月の和菓子であって洛外(南区?)ではなじみがありませんでした。(一昔の京都市中とは、北は今出川通から下、南は七条通から上、東西は鴨川と大宮通の間を指すらしい・・・)
年末年始の期間限定和菓子ですが、白味噌餡と甘く炊いた牛蒡(ごぼう)を柔らかな求肥または御餅で包んだ生菓子です。「花びら餅」とも書いてあるお店もありますが、新春を祝う菓子としてもてはやされています。しかし、30年ほど前まではあまり売れるお菓子ではなかったようです。
「葩餅」は平安時代の新年の行事「歯固の儀式」に由来します。歯固は塩漬けした鮎など堅いものを食べて長寿を願う意味が込められており、宮中雑煮とも言われていました。明治時代に裏千家家元十一世玄々斎が初釜の時に使うことを許され、御所出入りの御ちまき司・川端道喜に花びらもちの創作を依頼したとか。その時に試行錯誤の末、現在のような白味噌と牛蒡(ごぼう)の入った桃色の生菓子になったそうです。(Wikipediaより)
いらい、裏千家の初釜のお菓子は「葩餅」と決まりましたが、近年、これを庶民がお正月のお菓子として、買い求めるようになり全国の和菓子屋さんで作るようになりました。やはり京都が本場で、中でも川端道喜の「葩餅」が本家本元。現在でも裏千家の初釜には川端道喜の「葩餅」が用いられており、一般には手に入らないようです。でも、毎年、12月の数日間だけ「こころみのもち」と称して本番前の試作品を作る習わしがあるとか。これが一部に、予約販売として売られています。本番と同じものらしいのですが、大きさは昔は六寸(18㎝)、今でも四寸(12㎝)はあり、他の店よりは大きいらしいです。瓦も今年は食べてみようかな~と思っていたら、予約が終わっていました。
この「葩餅」、京都ならではの和菓子です。東京では「花びらもち」と称して販売されているようです。でも、歴史と伝統を受継ぐ「葩餅」は京都でしか食べられない和菓子です。京都が誇るべき文化です。そういえば、京都が全国に誇るモノ、いや人物がいます。
「伝えよう、美しい精神(こころ)と自然(こくど)」を信念に京都の、いや日本の正しい文化、生活のありようを説いている人物がいます。それは西田昌司参議院議員です。これからは京都が誇るものに西田昌司参議院議員と「葩餅」をセットにして「どうや!すごいやろう」と、全国の友人に瓦は自慢していこうと思っています。
消費税増税が決定
景気対策をすることを条件に、来年4月からの消費税増税が決定しました。まだデフレ状態が続く中、増税は時期尚早ではなかったのかというご心配の声も数多く頂戴いたしております。私自身、消費税増税はデフレから完全に脱却した後に行うべきだということを再三申し上げてきましたから、そうしたご意見には同感するところが多いのが本音です。
そこで、私なりに考えをまとめて述べてみたいと思います。
給料が下がり続けたことがデフレの原因
 南区西田昌司後援会の皆様が国会見学にお越しになりました
南区西田昌司後援会の皆様が国会見学にお越しになりました
我が国では、この20年間デフレが続いてきましたが、それは、経済のグローバル化による内需不足が原因だと私は考えています。かつて、日本の貿易相手国は欧米先進国が中心でした。家電製品や自動車などの工業製品を西側諸国に輸出し、エネルギーや原材料などを中東やアジア・アフリカ諸国などから輸入するというのが日本の貿易の姿でした。要するに輸出入の対象は物であったわけです。ところが今は、家電製品にしても自動車にしても日本で生産して輸出するより、現地で生産する方が圧倒的に多くなっています。その理由は、貿易相手国がかつての西側諸国から中国を始めとするアジア各国に移っていったからです。その結果、製品の輸出よりも現地生産が増えることになったのです。
西側諸国は先進国ですから、所得水準も高く日本製品を買うだけの資力があります。一方で、中国などのアジア各国は発展途上国で所得水準が低いため、高価な日本製品を買うことができません。発展途上国でたくさんのものを売るためには、その国で現地生産して製品価格を抑える必要があるのです。こうしたことから、日本の企業は発展途上国に工場を建設し、多くの製品を海外で生産することになりました。
企業は売り上げを伸ばし、企業規模は飛躍的に拡大しました。しかし、海外で獲得した利益は現地で課税されるため、日本には税として納められません。また、現地雇用が増えるだけで、国内の雇用は、むしろ減少することになります。雇用が減少しだすと給与も下がりだします。賃金の安い海外雇用が増えると、国内の賃金を下げる圧力が増加するからです。海外の安い賃金に対抗するため正規社員の雇用を減らし、非正規や派遣社員を増加させたことにより、雇用は守れても給料が下がる結果をもたらしました。
また、中小企業などへの下請け額も、常に値下げ圧力がかけられてきました。毎年数パーセントずつカットされている企業もあると聞きます。その結果、大企業は大きな利益を得ても、中小企業の業績は悪くなる一方です。大企業の正規社員は労働組合に守られて賃金カットされないでしょうが、非正規社員は勿論の事、中小企業においては経営者も社員も給料が下がり続けています。これが、GDPの大半を占める個人消費を落ち込ませデフレを作り出したのです。こうしたことを考えると、賃金の上昇を目指すという安倍総理の考え方は、全く正しいものだと思います。
法人税の減税で給料は上がるのか
そこで安倍総理は、復興税の前倒し廃止や法人税の基礎税率を減額することにより、企業に給料を上げてもらう政策を提案されています。しかし、減税で給料が本当に上がるのか、そこが一番懸念されるところです。
実は、バブル経済が終わってから景気対策のために法人税等の減税が実施されてきました。しかし、その結果景気は良くなったのでしょうか。バブル後GDPはずっと500兆円前後で成長はありません。また、税収も減税した分だけ減ってしまい、現在の税収は40兆円代で、これはバブル前の昭和61年頃の税収とほぼ同額です。もし、こうした減税を実施していなかったら税収は60兆円を超えると言われています。この原因は先に述べたように、企業が国内投資よりも海外投資を優先してきた結果なのです。このことは経済がグローバル化した時代においては、企業減税をしてもGDPの増加や給料アップにはつながらないということを示しています。
また、雇用の大半を占める中小企業の雇用条件は年々悪化しています。従業員の雇用を守るために、経営者が給料をほとんど取っていないという話もよく聞きます。それだけ努力をしても満足に従業員に給料が払えず、ボーナスもほんの一時金しか出せない企業もたくさんあります。国民の給料を上げるためには、まさにこうした中小企業の給料を上げることが肝心なのです。
経済のグローバル化が進んだ結果、大企業は業績が良くなればその分を海外投資に向けてしまい、給料や中小企業への発注の増加になかなか繋がらなかったのが事実です。これをどうやって変えられるのでしょうか。私は、企業減税をして給与増加を企業にお願いするという方法では、強制力がないため改善できないと考えています。
脱グローバリズムがデフレ脱却への道
 自民党京都府連災害対策本部長として台風18号における災害状況の視察を行いました
自民党京都府連災害対策本部長として台風18号における災害状況の視察を行いました
私は、経済のグローバル化、これが国内での投資を減らし給料を削減してデフレを作り出してきた原因であると述べてきました。世界が一つの市場となった現代社会においては、投資効率の一番いいところにお金は使われてしまいます。その結果、先進国から発展途上国に投資先が奪われてしまうのです。
TPPに対して私が反対してきたのも、まさにこうした理由からです。TPPは関税を撤廃するというものですが、現実には物ではなく資本の移動が大きな課題になっています。世界中のどの国へも、自由に投資ができる環境を作るという事はまさに究極の経済のグローバル化です。先進国から発展途上国にどんどん投資が流れ出すということです。その結果、企業にとっては効率的な投資が可能になり業績は上昇することでしょう。しかし、日本を始めとする先進国は雇用が海外に奪われデフレが一段と加速してしまうのです。
物の取引が主体であった20世紀と、資本取引が主体となった21世紀とでは、自由貿易の意味が変わってしまっていることを知らねばなりません。これを理解しないで自由貿易を推進すると、企業栄えて国滅ぶ、ということになりかねないのです。
民から官へ
「官から民へ」という政策が、投資と雇用を海外へ流出させてしまいました。これを防ぐには、「民から官へ」と政策変更する以外ありません。確かに、民間需要は国内より海外の方により多く存在します。これに頼って経済政策をすれば、必然的に投資も雇用も海外に移転してしまいます。しかし、国内には、防災や減災、国防や治安維持、社会保障やエネルギー・食糧の確保などに莫大な需要が存在します。これらは民間任せで行うべきものではなく、政府が主体的に行わねばならないものです。言わば、公需と呼ぶべきものです。東北の大震災や福島の原発事故、尖閣問題を考えれば、どなたも納得できるでしょう。そして、これら公需に応えるには、税や社会保障の負担を増加させる必要があることもお分かり頂けるはずです。
国税と地方税とを合わせた租税負担の国民所得に対する比率である租税負担率と、年金や医療保険などの社会保障負担の国民所得に対する比率である社会保障負担率の合計を国民負担率と言います。日本は4割程度ですが、これは先進国の中では異常に低い数値です。英独では5割程度、仏は6割、北欧諸国は更に高くなります。例外は米国です。日本より低い負担率ですが、国民皆保険等がなく民間保険任せのため、その負担が加算されておらず、日本の参考にはなりません。
安心安全のための需要は正に公需です。そのためには政府部門の支出が必要です。それを賄うには日本の国民負担率は、世界水準から見ても低すぎるということなのです。官から民ではなく、民から官へと発想の転換をしなければならないのです。
大きな政府が国民をデフレから守る
 読売テレビ「そこまで言って委員会」に出演いたしました
読売テレビ「そこまで言って委員会」に出演いたしました
ところが、この20年近く、我が国ではこの逆の政策を行ってきたのです。その結果、防災や安全保障の観点からも脆弱な国になってしまいました。更に、社会保障やエネルギー・食糧の確保の観点からも国民は不安を感じています。これらは予算措置が十分されていないからです。「官から民へ」のスローガンの下、こうした政策をないがしろにしてきたのです。このことが、日本の国力をどれだけ毀損してしまったか、大いに反省しなければなりません。
また、こうした小さな政府論は、経済の面でも大きなダメージを与えてしまいました。減税を先行させ民間企業の活動に制限を加えない政策は、市場原理主義と呼ばれましたが、経済がグローバル化した中では、雇用と投資を海外に移転させることになりました。正にデフレを呼び込んでしまったのです。
政策の総点検が必要
さて、以上の点を踏まえた上で、増税と景気対策はどう整合性を持つでしょうか。この20年に及ぶ小さな政府論が、国力を弱めデフレをもたらしたことは間違いありません。国民負担率を増加させ、公需のための予算を増やすことが国力を取り戻すために必要なことは言うまでもありません。そして、それが、雇用と投資の海外移転を防止する唯一の方法なのです。長期的には国民負担率の増加による大きな政府が望ましいと私は思います。
しかし、他方でデフレが続いている現下の状況では、増税が望ましいはずがありません。公需に対する政府の予算措置は必要ですが、それは国債で賄うべきです。そして、デフレから脱却した然るべき時期に、負担率を上げるべきなのです。
残念ながら、このような、長期的な視点と短期的な視点との政策の整合性についてしっかりした議論がまだ十分行えていません。そのため、短期長期の視点が示されないままに、バラバラの議論がされているのです。
これを整合性のあるものにするのが、自民党の仕事です。そのためには、党内で徹底した議論を行う必要があります。また、これまでの政策の総点検を行わねばなりません。今まで自民党が行ってきた政策に対して批判をすることも時として必要になります。
政府の中に入れば、こうした議論はしにくくなります。今後も、一国会議員の立場で、真摯な議論を行い、安倍内閣の政策が誤り無く行えるように努力をして行きたいと考えています。皆様方のご支援ご協力を宜しくお願い申し上げます。
樋のひと雫
羅生門の樋
ついに決まりましたね、消費税の値上げ。今まで“アベノミクス”に好意的だったマスコミも、「?」的な報道が多かったように思います。そらまあ、誰しも増税は嫌なもの。出来ればないにこしたことはありません。
これらの報道の中で、「お上から税をとられる」という庶民感情を逆なでするかのように、某新聞が「企業か人か。コンクリートか人か。」という二元論でコメントを書いていました。“コンクリートから人へ”と云って政権を担当した党もありましたが、今でもこの論の立て方があるのだと驚きました。この言葉には、コンクリート=予算のばら撒き=企業中心、人=福祉の充実=市民中心というニュアンスがあるのでしょうが、善悪二元論で世論を主導しようとする考え方には失望しました。
思えば、東京オリンピック、この前後から始まった高度経済成長では、随分コンクリートが出来ました。高速道路、新幹線、大型橋梁、高層ビル。これらの恩恵を被って来たのは我々国民でした。しかし、漫談家ではありませんが,「あれから五十年‼」。今では、橋脚には亀裂が入り、トンネルの崩落もありました。そろそろ高度経済成長の恩恵のツケを払う時期に来ているのではと思います。友人の技術者が言っていました。「コンクリートの寿命は50年。保守しようとすれば建設する以上の費用がかかる」と。
50年後の孫の世代に、安全と安心な国を残そうと思えば、現在出来ることをしておかないと。朽ち果てたコンクリートを産業遺産ならぬ、産業廃棄物として子孫に残す訳にはいきません。その為には、財政規模の拡充も必要でしょう。3パーセントの消費増税が、現在の福祉だけに使われるのではなく、子や孫に安全で美しい国土(くに)を残すような使い方をしてもらいたいものです。
ところで、先の選択肢を「人が安全に暮らすコンクリートの建設、人に安心をもたらす企業の育成」と置き換えてみてはどうでしょう。今まで二元的に考えていたものが、存外目的を共有できるものになるかも知れません。二元論的思考や二律背反的疑問の立て方は、50年前の“ヤルタ・ポツダム体制の冷戦時代の世論”を想定したものでしかありません。この論理構造自体も、疲労破壊する時期に来ているのかも知れません。
安倍内閣の信任
先の参議院選挙では、39万票を超える多くのご支持を賜り、無事に二期目の当選をトップで果たすことができました。ご支援を頂いた多くの皆様方に、心より御礼を申し上げます。
今回の選挙は安倍内閣最初の国政選挙です。自民党が65、公明党が11、合わせて76の議席を獲得し、衆参のねじれ状態は解消しました。これで、安倍内閣が信任されたわけです。これからは、選挙中訴えた政策の実現のために全力で働く覚悟です。
経済のグローバル化がデフレの原因
 万感の思いで万歳三唱です
万感の思いで万歳三唱です
特にデフレからの脱却は最優先の課題です。そもそもデフレになった原因は、世界中を席巻した新自由主義に基づく、経済のグローバル化にあります。バブル崩壊後、銀行は、不良債権の発生に伴い、資金の貸付より回収を優先しました。また企業も積極的に投資する気運が失われました。これにより市場に流通していた資金は大幅に減退したのです。これでは、当然、景気は後退します。本来、このような事態になれば、景気を下支えするために政府の財政出動が行われるはずでした。しかし、これが十分に行われませんでした。その理由は、当時流行した小さな政府論です。「官から民へ」が合言葉になり、徹底した行政改革が求められたのです。バブル以後、民間企業がリストラをしているにもかかわらず、政府がリストラもせず財政出動するのはおかしいという感情論が、世の中を支配しました。減税が行われ、政府や地方自治体の予算は年々削減され少なくなりました。民間企業に主体的に投資をしてもらう方が、より効率的な社会を作れるはずだと考えられたからです。そして、規制緩和が叫ばれ、構造改革が進められました。その結果が、20年にもわたるデフレにつながったのです。
雇用と税金が海外に移転
民間企業が積極的に国内に投資することを前提とした構造改革でしたが、結果は違うものになりました。中国をはじめとするアジアの新興国が台頭した時代においては、人件費の安い海外で生産しないと企業は競争に勝てません。そのため、企業は国内投資より海外投資を優先させたのです。国内の雇用は海外に奪われてしまったのです。
たとえばトヨタ自動車の生産台数は、2002年には国内348万台に対し、海外215万台であったものが、2012年では、国内349万台に対し、海外524万台と生産の6割を海外で行っているのです。海外に進出して売り上げを伸ばした結果、企業の収益は飛躍的に拡大しました。しかし、税金は事業を行っている海外で課税されることになります。また、2006年には国内生産が420万台近くあったことを考えれば、国内生産台数が10年前と同じではあるものの、実質的には雇用も海外に流出をしているということです。
私はトヨタ批判をしているのではありません。経済がグローバル化する中では、企業は海外移転をせざるを得ないということです。つまり、民間任せでは雇用も投資も海外に流出してしまうということです。そして、それがデフレの原因なのです。
デフレ脱却には政府の財政出動が必須条件
 安倍総理にも応援に駆けつけていただきました
安倍総理にも応援に駆けつけていただきました
こうした事態を踏まえて、私は下野した時代から、安倍総理の下で勉強会を立ち上げ、デフレ脱却について次の様な提言をしてきました。
今までの様な市場原理主義では投資も雇用も海外に流出してしまいます。一方で国内には、減災防災を始めとするインフラ整備、国防、福祉などの莫大な需要が存在します。しかし、これは民間だけでできる仕事ではありません。政府がすべき仕事なのです。今こそ、政府が財政出動し、こうした仕事を行うべきなのです。これにより、それぞれの地域で新たな需要が創出され、その結果、雇用が増えていきます。雇用が増えれば賃金が上昇し、賃金が上昇すれば消費が増え、経済はデフレから脱却できるのです。
まさにこうした政策が、アベノミクスの第2本目の矢となって、今放たれているのです。アベノミクスの効果を疑問視する方もいますが、こうした予算を実施していけば、確実に実体経済は改善されて行きます。さらに、これは1年や2年で終わるのではなく、5年10年と、長期的に実施して行かねばなりません。
今回の参議院選挙の勝利により、衆参のねじれが解消しましたから、安倍政権の長期的な安定が保障されました。これにより、アベノミクスの長期的実施が可能になったのです。デフレ脱却のための万全の体制ができ上がりました。
民主党の崩壊
今回の参議院選挙で、自民党は大勝利をおさめました。しかし、それは自民党の勝利というよりも、民主党の自滅だと思っています。
6年前の参議院選挙で、自民党は大敗北を喫しました。以来、参議院においては民主党が多数を占め、この6年間は、常に民主党が政治の主導権を握ってきました。そして、遂に政権をも担うことになったのです。
民主党政権は、衆参とも民主党が多数を握り、安定した政権基盤の中で出発したはずでした。彼らは、自分たちの思い通りに政策を実行することが出来たのです。その結果が、今日の日本の混乱です。経済はデフレの谷底に落ち、安全保障はボロボロ、まさに国難とも言える事態です。
その政策の誤りを、野党時代、私たちも指摘してきました。しかし、彼らは一切聞こうとしませんでした。うまくいかないのは、自民党時代の政治が悪かったからだと、開き直りに終始しました。そのため民主党には、未だに政権の失敗に対する反省が一切ありません。これでは、国民に見放されても仕方がありません。今回の選挙は、こうした民主党時代に終止符を打つものでした。
民主党が自滅したことにより、再び自民党に政権が戻り、参議院においても安定多数を獲得しました。衆参安定多数のゆるぎない政権基盤を持つ安倍政権には、絶対に失敗は許されません。そのためにも民主党の失敗を他山の石としなければなりません。また、そもそもなぜ自民党が下野したのかもしっかりと反省をしておかねばなりません。
大勝利に隠された下野の原因
 ビートたけしの「TVタックル」~参院選緊急生放送~に出演いたしました
ビートたけしの「TVタックル」~参院選緊急生放送~に出演いたしました
今から12年前、小泉旋風の下、自民党は参議院選挙で大勝を致しました。そして、その後の衆議院選挙では郵政改革を争点にして、300議席を超える大勝をおさめました。自民党は、何でも思い通りに政策を実行できたのです。また、事実そうしてきました。
当時、京都府議会議員だった私は、新自由主義に基づく構造改革路線を批判してきました。その理由は、デフレと格差を作ることが予想されていたからです。そして、それは現実のものとなりました。
小泉総理から、事実上の禅譲という形で発足した第一次安倍内閣は、当初は高い支持率でスタートしました。防衛省を作り、教育基本法改正し、憲法改正のための国民投票法を成立させるなど、短時間で目覚ましい成果を上げました。しかし、こうした戦後レジームからの脱却を目指した安倍総理に対し、これに反対するマスコミや野党は、「消えた年金」や「絆創膏大臣」などでバッシングを繰り返しました。その結果、6年前の参議院選挙で自民党は大敗北を喫したのです。今考えれば、安倍バッシングは根拠のないものだったことは明らかです。
しかし、こうしたバッシング以前に、国民は慢性的な不安や不満を抱えていたのです。それは、バブル崩壊後の日本経済の低迷からくるものです。今日より明日に良い日が来るとは信じられない。雇用は減り、給料は下がる。その一方で大儲けをしている一部の人達がいる。東京は栄える一方で、地方は衰退していく。まさに、構造改革の副作用が、社会のあらゆるところに出現していたのです。
第一次安倍内閣が目指した戦後レジームからの脱却は、私は今でも、方向性としては正しかったと確信しています。しかし、小泉総理から引き継いだ経済政策に問題があったのです。
しかし、小泉総理の下、衆参両院で大勝利を収めたため、構造改革路線を否定するような議論は、自民党内ではできなかったです。多くの国民がデフレと格差に苦しんでいるにもかかわらず、その現実に目を背け、政策の方向転換を行わなかったのです。こうした政策の誤りと自民党の傲慢さに、国民は嫌気がさしたのです。
民主党が掲げたマニフェストが出鱈目ということは、国民もうすうす気がついていたはずです。しかし、出鱈目であっても、一度すがってみよう、そう思うほど、国民生活は疲弊していたのです。もちろん、国民を騙した民主党の罪は重いです。しかし、その原因には自民党の失政があった、そのことを私たちは認識すべきです。
今こそ、戦後レジームからの脱却を
この様に、過去の失敗の反省の上に第二次安倍内閣はあります。また、第一次安倍内閣から掲げられていた戦後レジームからの脱却は、今日においても非常に重要な課題です。鳩山総理の普天間での迷走に端を発して、中国は、領土的野心をむき出しにしています。自分で自分の国を守る、そのことがこれほど重要性を帯びている時代は他にないでしょう。そのための障害となっているならば、憲法の改正も辞さない、安倍総理のこうした姿勢は、高く評価されるべきものです。
一身独立して一国独立す。これは、福沢諭吉の言葉です。アジア各国が、西洋列強の植民地と化していく中、日本が唯一の独立国たり得たのは、こうした先人の不断の努力と気概の賜物です。ところが戦後60年、私達はこうしたことを忘れ、むしろ、タブーとしてきてしまいました。
中国は、経済的にも軍事的にもアメリカと並ぶほどの大国となりつつあります。中国の海洋進出は著しいものがあります。日本ばかりか、アジア各国が、中国の領土的野心の拡大には大変警戒をしています。そうした国が頼りにしているのはアメリカです。しかし、アメリカは、中国との衝突を避けようとしています。太平洋の権益を米中で分けようとしているのです。もはやアメリカにも、中国を押さえ込むだけの力はないのです。先日の長時間に及ぶ米中首脳会談はそれを物語っています。
このような時代の中で、日本が国の自立を守るためには、戦後のタブーに縛られず、国防についてのまともな議論を行うことが必要です。
皆さん方から頂いたこの6年の任期を、デフレ脱却や戦後レジームからの脱却など、日本国の自尊自立のために全力で働きぬく事をお誓い申し上げます。今後ともご指導ご鞭撻をよろしくお願い致します。
瓦の独り言
-土用は年に4回ある?-
羅生門の瓦
まずは西田昌司参議院議員の2期目、トップ当選、おめでとうございます。
今日、7月22日は「土用の丑」。ウナギで一杯やっております。ところが今年は「土用の丑」が2回あって、ウナギが2回食べられるとか。
暦の本を紐解くと、(こんなこと、知らんかったんかいな。と、諸先輩に笑われるかも)土用は、春夏秋冬のそれぞれの四季にあって、立夏,立秋、立冬、立春までの18日間を言っているのです。でも、夏の土用が有名で、暑気払いに平賀源内が「丑の日」にウナギを食べる習慣を広めたとか・・・。今年の暦では7月22日が「一の丑の日」、立秋前の8月3日が「二の丑の日」となっています。2回もウナギが食べられてうれしいのは、食いしん坊の瓦だけではないはずです。
ところが、土用の間は、土公人という土の神さんが地中を支配しているために、土を動かしたり、穴掘りをすることは忌み嫌われています。しかし、それでは一般の仕事などに支障が出るため、間日(まび)という日が設けられ、その間日(まび)には、土公人は文殊菩薩さんに招かれて天上界へいっておられるとか。迷信とはいえ、なんとも、素晴らしい習慣ではありませんか。「ダメだけれども、ある条件下であれば、このことだけはOK。」この発想にふれたとき、瓦は西田昌司参議院議員の主張とかぶる個所があるような気がしました。
自民党内でTPPに反対をしているが、共産党のように「なんでも反対」ではなく、「条件が合えば、ある部分はOKです」と、いった主張。本音は決してぶれていないが、周囲の状況に応じですぐに判断される素晴らしさ。これに感動しているのは、瓦一人だけではないはずです。さらに、このような間日(まび)を設けるのは「土用は季節の移り目であり、農作業などの大きな仕事をすると体調を崩しやすいので要注意」といった先人の戒めが込められているのではないでしょうか。このような日本人の生活の知恵に驚愕しているのも瓦一人だけではないはずです。
アベノミクスで景気回復? 勝って兜の緒を締めよ
安倍総理が掲げるアベノミクスの期待により株価が上昇し、リーマンショック以前の水準にようやく回復しました。また、為替は95円台になり、円高も解消しつつあります。しかし、実際にはまだ予算も法律も執行されてはいません。まさに、安倍政権に寄せる期待が景気回復の原動力になっているのです。
ただし、それは、民主党政権への過大な期待の結果もたらされた、失望の大きさによるものであると、認識しておかなくてはなりません。現実の経済が回復しなければ、国民の期待は失望へと変わり、怒りとなって戻ってくることを考えると、勝って兜の緒を締める謙虚さと慎重さが必要です。
アベノミクスはアソノミクス
 ビートたけしのTVタックル~春の3時間スペシャル~に出演しました
ビートたけしのTVタックル~春の3時間スペシャル~に出演しました
安倍政権が最初に取り組まねばならないのは、何と言ってもデフレ対策です。私はこうしたことを所管する参議院財政金融委員会の理事を務めていますが、そこで麻生財務大臣にデフレ対策についての所見を伺いました。麻生大臣は、金融緩和と財政出動と民間投資の三本の矢の必要性を説明されました。しかし、これは麻生大臣が総理の頃に行ったリーマンショックに対する景気対策そのものです。これがリーマンショック後の経済を下支えしたのですが、民主党の事業仕分けにより潰されてしまい、デフレに歯止めがかからなくなったのです。従って、アベノミクスと呼ばれているものは、実はアソノミクスではないかと私は考えています。
では、何故もっと早くこうした政策が自民党政権時代にできなかったのでしょうか。私のこの質問に対し麻生大臣は、実は小泉政権の時代にも同じことを提案していたが当時はそれが認められなかった旨を述べられました。率直に自民党政権の政策の誤りを認められた訳です。
日銀の誤りを認めた黒田日銀総裁
白川総裁に代わり新しく日銀総裁になられた黒田東彦氏も参議院財政金融委員会で、今から思えば、2000年、2006年に量的緩和を止めたのは早過ぎた、と率直に誤りを認められました。その上で、安倍政権の掲げる2%の物価上昇になるまで量的にも質的にも金融緩和を続けると明言されました。このように、麻生大臣、黒田総裁とも過去の政策の誤りを認めた上で、デフレ対策を徹底的に行うことを約束されたのです。
まさに、我が意を得たりです。かねてから、私はこの20年間の自民党の構造改革路線には反対をしてきました。そして、下野してからは特に、その総括をすべきと主張してきましたが、少なくともこのお二人はそうした思いを持っておられるということです。
政治家は自省が必要
 参議院予算委員会にて質問
参議院予算委員会にて質問
人間は誤りを犯すものです。そのことは誰でも知っています。しかし、立場が大きくなればなる程、自らの過ちを認められなくなります。特に政治の世界では尚更です。自ら行った政策の誤りを認めれば、その責任を追求されます。それを避けるためには、誤りを認める訳にはいかないのです。 役人の世界も同じです。役人はその背中に省庁を背負っています。その組織を守るためにも政治家以上に誤りを認めたがりません。
しかし、本当に背負わなければならないのは省庁ではなく、国そのものであるはずです。自分自身だけでなく、時には組織や先人の立場をなくすことがあっても、その誤りを認めなければ国家が滅んでしまうことになるのです。
こうした中、麻生大臣や黒田総裁の発言は先の過ちを認めるものであり、大いに評価したいと思います。それは、安倍総理にも共通する姿勢で、第一次安倍政権での失敗を繰り返すまいという決意が、政権運営に現れていると思います。それが、高支持率に繋がっているのでしょう。
TPPは国内空洞化を招く
私はTPPに反対しています。その理由は、そもそもTPPの目指す自由貿易をすれば、先進国は雇用の空洞化を招き、国民の所得が減るからです。昭和の時代の自由貿易は、日本で作ったモノを輸出することが主流でした。輸出が増える程企業は儲かり、雇用が増えるため、国民も豊かになり、外貨も稼げて国も富むことになりました。ところが、平成の自由貿易ではこうはなりません。平成の自由貿易は、モノではなくモノを作る製造設備そのものを輸出しているのです。そのため、海外でモノが売れてもそれは、海外生産したモノが売れているにすぎないのです。海外生産を増やした結果、企業の生産量は飛躍的に増大し、利益も増えました。しかし、製造拠点が海外に移転した結果、国内での雇用は減り、正規雇用が減りますから給与も減ります。国全体としては、海外からの配当が入りますから経常収支の黒字は増えます。しかし、国内の雇用が減り、国民の所得も減るため、GDPは減る可能性があります。これが国内空洞化です。
TPPは企業の論理
国内が空洞化するのは日本だけではありません。TPPを始め、極端な自由化を要求しているアメリカもその例外ではないのです。アメリカンドリームとは、一所懸命働けば、家を建て家庭を持ち、大きな車に乗り、週末は家族とホームパーティーを楽しむという中産階級の生活を誰もができるということです。ところが、アメリカではレーガン時代から始まった規制緩和政策のお陰で貧富の差が拡大し、中産階級が少なくなってしまったのです。 規制緩和の結果、製造業は日本などのアジア勢に敗退し、ウォール街の金融業界が支配する国になってしまったのです。中産階級の利益の代弁者として、脱ウォール街を唱えて当選したオバマ大統領も、今やウォール街の論理にしっかり取り込まれています。そうした企業の勢力を背景に、日本のTPPへの参加が要求されているのです。正に、企業の論理の代弁者としてオバマ大統領は日本に要求しているのです。
TPPはこれからも議論が必要
TPPについて、安倍総理は交渉参加を表明されました。しかし、自民党のTPP対策委員会では、TPPで守るべき国益と懸念される問題点について総理に報告をし、安倍総理もTPP参加交渉の中でこうした国益を守り抜く旨の決意を表明されました。日本の交渉参加については参加国の承認が必要で、実際の交渉は参議院選後になるでしょう。これから、この交渉の推移をしっかり注視していかねばなりません。
防衛力強化を急げ
中国は経済力で既に日本を追い抜き、やがてアメリカをも凌ぐ国となるでしょう。それに伴い軍事費も増大し続け、日本の安全保障にとっても大きな懸念材料です。安倍総理がTPPの交渉参加を決断した背景には、こうした状況の中で日米関係を重視されたのでしょう。 しかし、今後アメリカは膨張する中国を押さえ込むのではなく、取り込むことを選択する可能性があります。それは大東亜戦争の事例が示しています。当時アメリカが、その市場の大きさに目が眩み、日本より中国を選択したことが、日米開戦に繋がって行くのです。結局、その中国は毛沢東の共産党に占領され、アメリカは何も得ることができなかったのです。アメリカにとっても苦い経験であるはずですが、私たちも、アメリカ頼みの安全保障だけでは国を守れないことを考えるべきです。安倍総理は防衛力の増強を掲げておられますが、そのためには、集団的自衛権の行使を始め、今までとは次元の違う安全保障政策を行う必要があります。
日本の自立を阻むもの
 自民党大会にて安倍総裁と握手
自民党大会にて安倍総裁と握手
日本が防衛力を増強することにより、アメリカは日本での駐留経費を減らすことができます。日本の財政負担は増えますが、これは独立国としては当然の負担です。むしろ、それを今までしてこなかったことが問題なのです。また、防衛力の増強にはアメリカから兵器の輸入も必要になるでしょう。軍事産業はアメリカの基幹産業ですから、これにより、アメリカは雇用を伸ばすことができます。こうしたことは、日米両国にとってもお互いにメリットがあるはずです。
ところが、これに反対する国があるのです。まず、中国や韓国、北朝鮮が反対するでしょう。彼らは、かつて日本に事実上支配されてきたことを引き合いに出し、また軍事力で侵略するのかと大反対をするでしょう。それは、彼らからすれば当然のことでしょう。しかし、日本にそんな意思があるはずも有りません。自衛はどこの国にも当然に許された権利です。それを否定する権利はどの国にもないのです。
しかし、一番反対するのはこうした国ではなく、日本人自身ではないでしょうか。マスコミは憲法違反だと徹底的に反対するでしょう。
一方、アメリカも日本の自立を望まないとしたらどうでしょう。日本を自国の影響力の下に置くことがアメリカの利益と考えれば、そういうことになるでしょう。事実、そのために占領中にアメリカが日本にあの憲法を与えたのです。こう考えると、日本の真の自立にはまだまだ時間がかかりそうです。
参議院の安定多数が絶対に必要
ロケットスタートに成功した安倍政権ですが、まだまだ難問山積です。これらを一つひとつ解決してゆくためには、衆参両院で多数を獲得し、政権を安定させる必要があります。
私も、安倍総理を支え、国難を乗り切るために二期目を目指して全力で頑張る覚悟です。今後とも、ご支援をよろしくお願い申し上げます。
樋のひと雫
-本音と建前・理想と現実-
羅生門の樋
3月初旬にベネズエラのウゴ・チャベス大統領が死去しました。日本では馴染みが薄いかも知れませんが、中南米では今後の政治の行方を左右する一大事です。彼は経済破綻国家キューバを初め、余り強固とは言えない経済状況の中南米反米左派政権の最大のパトロンであり、自国の石油収益を惜しげもなくこれらの国々に与え続けました。我がボリビアもエボ・モラーレス大統領が盟主と仰ぎ、経済援助や政治上の指導も受けていました。
自国では多数の貧困層に政権基盤を置き、かなりあざといこともやっています。ゴルフは富裕層のものと云うことで、ゴルフ場を潰して貧困者用のアパートを建ててもいます。ボリビアでも同じことが起こるのではと、ラパスのゴルファーの間では随分話題にもなりました。
昨今では、各国の左派政権が経済的に行き詰まり、自国通貨の保護に躍起になっています。例えば、アルゼンチンではドル不足から輸入品の価格が高騰しています。ドル建て預金も出来ません。なのに、ブエノスアイレスに出かけようとした時に、現金(ドル)でホテルを予約しようとしたら、代理店で「ドル送金が出来ないから」と断られました。また、ボリビアでは最近になって、銀行ではドルからボリビアーノ(ボリビアの通貨)に換金してくれません。「国民以外はドルを換金することは出来ません」と断られます。観光に力を入れていると云うのに、ドルが使えない。抜け道がありました。ホテルのボーイにチップを渡して、銀行の窓口に同行してもらい換金を依頼します。これって国とグルになった小遣い稼ぎ、と思わずツッコミたくなります。
建前と理想の南米型左派政権は最大のパトロンを喪って、今後はどのような通貨政策を採るのでしょう。ベネズエラの国民は、自分達の財産(石油収益)が他国の政権維持のために使われることに、何時まで我慢できるのでしょう。難しいところです。各国は現在の為替レートを維持するために随分無理をしていますが、その反動が何時現れるのか。怖いところです。3千パーセントと言われたインフレ時代は、つい30年ほど前のことでした。
チャベスが夢見た南米独立の英雄シモン・ボリーバルの理想が蘇るのか、世界通貨ドルとの争いに敗れるのか。自国資源を国有化するナショナリズムが勝つのか。悩ましいところです。この様子、どこか日本のTPPやEPA、RCEPの問題と似ていませんか。世界諸国との貿易関税の壁をなくしたら、YENもなくなっていたなんて、悪夢です。
昨年の総選挙で民主党政権が終わり、ようやく、政権奪還ができました。ご支援いただいた皆様に心より御礼を申し上げます。全国においては自民圧勝の中、京都の民主党は、あれだけの逆風の中で2区と6区は選挙区で、3区は比例で当選するなど、依然として民主党の底堅さが目立ったのも事実です。更なる党勢の立て直しを痛感しました。私の期待するところも含め、これから安倍内閣が行うべき方向性について述べてみます。
まず景気対策
 安倍総理とともに自民党公認候補者の応援演説
安倍総理とともに自民党公認候補者の応援演説
選挙期間中から、安倍総理が真っ先に掲げていたのは景気対策です。そのために、日銀と協調して大胆な金融緩和を行います。具体的には、日銀が民間銀行等の保有する国債を市場を通じて購入するということです。その金額を増額することにより、民間銀行にお金を潤沢に供給しようとするものです。このように日銀が市場を通じて国債を買い取る操作(オペレーション)を買いオペと呼びます。よくデフレを脱却するには、日銀がお金を刷れば良いということが言われますが、この買いオペが正に日銀がお金を刷ること、つまり通貨供給なのです。また、この逆に市場に日銀の持つ国債を売る操作を売りオペと呼びます。
日銀は「物価の安定」と「金融システムの安定」が仕事ですが、物価の安定という意味は、決してデフレの状態ではありません。毎年1-2%くらいは物価が上昇している状態、つまり軽いインフレの状態が正常な状態なのです。現在は物価が毎年下落している状態、つまりデフレの状態ですから、決して正常ではありません。そこで日銀も買いオペを行い、通貨の供給を増やしています。しかし、残念ながら現在もデフレが続いているのです。
そこで安倍総理が主張してきたことは、もっと大胆に供給量を増やすべきだ、そのためには買いオペの額を増やすべきだということです。日銀は伝統的にインフレに対する警戒心が強いものです。特に、20年前のバブル経済の後遺症から、バブルにならないようにしようとするあまり、大胆な金融緩和ができず、結果的に長期間にわたるデフレを作り出してしまったのです。正に、熱ものに懲りて膾を吹くという愚をしてしまったのです。今までの枠にとらわれない、大胆な金融緩和を安倍総理が主張するのは当然のことなのです。
民主党によりデフレが長期化
こうした日銀の政策だけで無く、政府の側にも政策の誤りがありました。民主党政権での事業仕分けや「コンクリートから人へ」の政策により、公的需要が極端に減少してしまいました。彼らの言い分は予算の無駄を削減するというものでした。その影響で科学技術開発の予算が大幅に削減され、公共事業も大幅にカットされました。小惑星探査機「はやぶさ」の偉業や、山中教授によるノーベル賞受賞が示すように、科学技術開発はこれからの日本の経済の推進力になります。また、中央自動車道のトンネル崩落事故に見られるように、インフラの整備や維持には大きな予算が必要です。ところが、民主党政権ではこうした予算を無駄と称して削減をしてきたのです。これが全くの間違いであった事は、今更指摘するまでもないでしょう。これから安倍政権においては、こうした予算は大幅に増額されることになるでしょう。
バブル後の政策の誤り
 京都府内を中心にたくさんの候補者の応援に駆けつけました
京都府内を中心にたくさんの候補者の応援に駆けつけました
公共事業費は、実は自民党政権においても、バブル後一時的には景気対策のために増やされたものの、毎年削減されてきたのです。その理由は、この頃からいわゆる小さな政府論が幅を利かすようになったからです。これは日本だけではありません。
不況の時には金利を下げ、公共事業費を増やし、好況時には金利を上げ、公共事業費を減らす、これが伝統的な経済政策でした。1930年代の世界大恐慌はこうした政府による需要調整政策により脱出できたのです。しかし1970年代以降、アメリカにおいて、政府は需要を調整する必要がなく、市場に任せるべきとする自由放任主義が主流になってしまいました。そして、アメリカが冷戦の覇者となってからは、そうした考え方が世界の潮流となってしまいました。特に、日本においては、バブル後、アメリカ型の社会の仕組が急速に取り入れられてきました。規制緩和が唱えられ、市場原理主義が経済政策の主流となったのです。こうした考え方の下、毎年公共事業費は削減されてきたのです。その結果が今日のデフレを産んだことを考えると、自民党にも大いに責任があります。結果的には、そのデフレによる不満が爆発して自民党は下野させられたのです。
経済政策の大転換
何れにせよ、こうした歴史の事実を踏まえて、安倍総理は大胆な金融緩和と財政政策を提案しているのです。残念ながら、現在は深刻なデフレのため、金融緩和をしても民間企業はすぐには投資をしません。そこで、まず政府が積極的に公共事業投資等を行うことにより、民間企業の需要を喚起させる必要があるのです。長引くデフレから脱出するためには、市場にインパクトのあるものでなければなりません。それが10年間で約200兆円規模の公共事業投資を行うという提言です。
これをバラマキだと批判する人がいますが、その方たちは、この20年にわたる不況の原因に未だ気づいていないのです。不況の時に仕事を供給するのは政府の当然の責務です。民主党政権は、このことに気づかず、公共事業が抑制され続けてきました。その結果、生活保護費ばかりが増えることになってしまい、その額は今や4兆円を超え、防衛費に並ぶ程までに膨れ上がりました。これこそ、異常なことです。
また、年末の中央自動車道のトンネル事故が示すように、インフラはしっかり維持管理をしなければ大事故につながります。これも、公共事業費を抑制してきたつけと言えます。
公共事業で財政は破綻しない
公共事業を増やせば国債が増え、財政の破綻を招くという人もいます。しかし、これも間違っています。発行した国債は、民間銀行が喜んで引き受けてくれます。何故なら、不況で融資先の乏しい銀行にとっては、国債は魅力的な資産だからです。その証拠に国債の九割以上が、国内の金融機関などにより保有されています。そして、その金融機関の預金の原資は、殆ど全てが国民の預けたものです。外国からお金を借りて国債を発行しているギリシャなどとは、根本的に違うのです。外国から資金の引き上げの無い日本では、国債の破綻など有り得ないのです。財政破綻を唱える人は経済の基本的知識が無いか、財務省に踊らされているか、どちらかです。
財務省の誤り
財務省は、税金の徴収と予算の作成が仕事です。「入るを量りて出ずるを制す」彼らは常に税金の範囲で予算を支出するのが当たり前だと考えているのです。
しかし、これは、必ずしも正しくないのです。確かに、社会保障費など今の世代が給付を受けるものについては、負担と給付が均衡する必要があります。ところが、インフラの整備は、元々税金で行うものではありません。住宅は住宅ローンで買い、将来の所得で返済するように、インフラの整備も国債で行い、将来の税金で返済すべきなのです。しかも、 公共事業投資は確実にGDPを押し上げますから、その分将来の税金も必ず増えるのです。これは伝統的な経済学の常識です。
にもかかわらず、ここ20年にわたり、公共事業で需要調整をすべきでないというアメリカ型の経済学が主流を占めるようになりました。この学説に従い、財務省は公共事業を抑制し続けたのです。その結果、GDPが伸びず、深刻なデフレに陥ってしまったのです。これは、明らかな誤りです。
対米従属意識が根本的原因
戦後の日本では、アメリカに従うことに慣れすぎ、何でも鵜呑みにする傾向があります。これは、マスコミにも政府にも、多くの国民にも言えることです。特にバブル後は、日本人が自信喪失したこともあり、その傾向が際立っていました。こうした対米従属意識が、誤った政策を助長してきたのです。
安倍総理の使命
 KBS京都「報道特別番組2012総選挙・乱戦 京都の結論!」
KBS京都「報道特別番組2012総選挙・乱戦 京都の結論!」
に出演しました
こうした誤りを認めた上で、安倍総理は政策を大転換しようとしているのです。それは、経済政策だけにとどまりません。これまでは、自分の国は自分で守るという当たり前のことが、十分にできず、むしろ、タブーになっていました。しかし、尖閣問題が示すように、防衛力の強化は必然です。また、そのためには、憲法改正も視野に入れなければなりません。
これらのことは、戦後の枠組みを乗り越えることを意味します。戦後の枠組とは、憲法を始めとする対米従属意識からくる戦後の価値観や仕組のことです。マスコミは、この戦後の枠組の守護神を自認してきたわけですから、当然、大反対をするでしょう。また、先の安倍政権の時代からマスコミが安倍バッシングを執拗にしてきたのも、そのためなのです。
すべては参議院選挙の勝利から始まる
衆院選で勝利を収めましたが、依然として、参議院はねじれたままです。先に述べてきたような改革を行うには、参議院においても多数を占めなければなりません。また、戦後の枠組からの脱却は、国民に十分説明し、納得をしてもらわねばなし得ません。
そのためには、今までのようなキャッチフレーズによる政治を止め、粘り強く国民に訴えていかねばなりません。正に、政治家が本当の使命を果たす時がきているのです。私も、安倍総理と共に、こうした使命を果たすために頑張ります。今後とも、ご支援をよろしくお願い申し上げます。
瓦の独り言
-畳の目-
羅城門の瓦
新年あけましておめでとうございます。
「冬着たりなば春遠からじ」 やっと、3年4ヵ月の冬の時代から抜け出せました。
冬至も過ぎ、新春のお正月頃からは、畳の目ほどに日が延びていきます。座敷に差し込む日差しも、畳の一目づつ長くなっていきます。(この言葉は、故西田吉宏参議院議員から聞いた記憶があります。) 急激な変化は求められませんが、着実に暖かくなってゆきます。
ところで、畳の一目の大きさをご存知ですか? 知っておられる方はおそらく畳屋さんか、大工さんかそれとも茶道の達人では・・・。瓦も、知らなかったのですがある人から、「京間畳の短手の目数は縁内64目で、これは大和の国64州を象ったものと言われています。」と教えられました。でも家の畳の目を数えると62と半分でした。でもこの半分も茶道の世界では「半目」または「小切目」といって意味があります。64目ある畳は「丸目の京畳」といって、お道具を置くときに畳の目数を目安としますが、関西と関東では畳の大きさが異なるので、畳の目数、目の大きさが気になります。
畳の話になりますが、「京間:長さ六尺三寸 ≒ 191cm」「江戸間:長さ五尺八寸 ≒ 176cm」。京畳の目数は約64弱、江戸畳の目数は約58ほどです。すると目の大きさは、
京畳 : 191÷2÷64目 ≒ 1.5cm
江戸畳: 176÷2÷58目 ≒ 1.5cm
同じで、そして1寸(3.03cm)の半分、つまり、半寸だったのです。
茶人にとっての座標は、なんと畳の目で、畳の縁から16目に座るとか、花月札は3目に送るとかですが、京畳、江戸畳も目の大きさは同じなので、なにも問題は起こりません。
これからは、この畳の目の大きさのように全国どこでも同じ大きさで、ぶれない政治を期待しているのは瓦一人ではないはずです。
本当の京畳、江戸畳の目の大きさのように、京都であっても、東京であっても、この畳の目の大きさのようにぶれない政治をしていただけるのは西田昌司参議院議員、この人のほかにはおられないと思っているのは瓦一人ではないはずです。
安倍晋三総裁の誕生の舞台裏

自民党の総裁選挙で安倍晋三新総裁が誕生しました。
私は、今回の選挙で安倍候補の推薦人に名を連ねておりました。安倍候補にご支援をいただいた皆様に、心より感謝申し上げます。
私は、かねてから安倍元総理の再登板を期待していましたが、実は、今回の総裁選出馬には最後まで反対をしていたのです。その理由は、今回の総裁選に選ばれた人が事実上次の総理になるのですが、3年間野党の党首として自民党を引っ張ってきた谷垣禎一総裁に、まずその資格があると思ったからです。苦労してきた人を差し置くようなことになれば、国民の理解が得られないだろうということです。
前回の安倍内閣の時代から、戦後レジームからの脱却ということを安倍元総理は訴えてこられました。その意味は、占領時代のように何でもアメリカ任せではなく、自分で自分の国を守り自立するということです。このことは、私が京都府議会議員の時代から訴えていたことと全く同じです。また、今の日本に一番必要なことでもあります。それが推薦人になった理由です。しかし、この本当に大切なことを国民にしっかり理解されないまま、前回、安倍元総理は病気のため退陣せざるを得ませんでした。こうした状況の中で出馬し、もし敗北すれば、安倍元総理は政治的生命を失う恐れがありました。従って、今回は出馬せず次回を目指すべきだと私は主張したのです。安倍元総理もこのことに理解を示され、出馬を最後まで慎重に考えておられました。
谷垣総裁の苦渋の決断に敬意と感謝
しかし、状況は一変しました。多数の候補者が出馬表明をする中、突然、谷垣総裁が不出馬を表明されたのです。それは、自民党の分裂を回避するための苦渋の決断だったと思います。谷垣総裁のこの決断が無ければ安倍総裁の誕生は無かったでしょう。政権奪回のため、自ら捨て石となられた谷垣総裁に対しては、敬意と感謝の念を禁じ得ません。これは、全ての自民党員の気持ちでしょう。事実、総裁選の投票後、谷垣総裁に対する拍手が誰よりも大きく、鳴り止まなかったことがそれを表しています。こうした状況の下、安倍元総理は出馬を決断されたのです。しかし、出遅れは否めず、苦戦が予想されました。
平成の元寇に神風が吹いた

ところが、神風が吹いたのです。民主党の外交の不手際により、中国の船が次々に尖閣諸島に押し寄せて来る「平成の元寇」とも言うべき事態に、国民が目を覚ましました。自分で自分の国を守らなければならないという当たり前のことに気がついたです。そして、それは安倍元総理がかねてから主張してきたことです。こうした国民の意識の変化が追い風となり、安倍元総理に対する期待は、一挙に高まりました。事実、大阪の難波での街頭演説では、安倍候補に対する拍手は他のどの候補よりも圧倒的に多く、その場にいた私自身が驚いたくらいです。まさに、時代が安倍晋三を政治の中央に押し戻したのです。
防衛力の増強が不可欠
尖閣問題や竹島、北方領土などの状況を見れば、防衛力の増強は当然のことです。民主党政権により毎年防衛予算が削減されてきましたが、これを改め、早急に防衛力の整備を図らねばなりません。また、合わせて海上保安庁の能力も高めなければなりません。特に、海保の巡視艇に体当たりした中国船の船長を逮捕したにもかかわらず、当時の仙谷官房長官の命令で、事実上釈放させられた事件は、海保の隊員の士気を著しく傷つけています。
その上、その責任を、那覇地検の次席検事になすりつけるなど政治家として、全く許せません。こうした政治家の責任放棄を糾弾するとともに、現場の隊員が誇りと自信を持って職務を遂行できる体制を整えねばなりません。
実効支配の意味
野田総理は、口を開けば、尖閣諸島は我が国固有の領土であり、我が国が実行支配をしており、中国との間に領土問題は存在しないと言います。確かに、日本の立場はその通りですが、問題は実行支配が揺らぎだしているということです。
元々、尖閣諸島は無人島ですが、1895年にどの国にも属していないことを確認して、我が国の領土に編入されました。そして、開拓が行われ、1941年まで日本人が住み続けて来ました。文字通り実効支配をしてきたのです。
その後、敗戦により沖縄県の一部として、1972年までアメリカに占領されてきました。沖縄返還まではアメリカが実効支配をしてきたのです。1969年の国連の調査により、この地域に石油資源がある可能性が指摘されてから、突然、中国と台湾が領有権を主張し出しましたが、日本の実行支配が揺らぐことはありませんでした。海保の巡視艇が警察権を行使してこの領海を守ってきたからです。
ところが、今は、それが揺らぎ始めています。中国の公船がこの海域に頻繁に出入りしています。勿論、日本の海保の巡視艇もこれに抗議し、中国船の排除に務めていますが、中国公船が退く気配は有りません。日本の領海にもかかわらず、中国の公船が自由に往来していることは、形の上では、日本と同じ立場になっているのです。これこそ、中国が目論んでいることです。警察権の行使を日本と同じ様にしていると彼らは主張したいのです。普天間基地移転問題の迷走から始まる民主党の外交防衛政策の出鱈目が、尖閣諸島領有の危機をもたらしたのです。
領土を守るにはパワーが不可欠
中国は、尖閣諸島は日清戦争で日本が奪ったものだと主張し、韓国は竹島を済州島と同じく韓国固有の領土だと訴えています。勿論、彼らの主張は歴史の事実としても間違っています。しかし、いつから彼らはその主張をし出したのでしょうか。
中国や台湾に関しては、尖閣地域での石油資源の存在が言われ出してからですが、ここまで実力を行使するようになったのは民主党政権になってからです。戦前は、日本の日清戦争の勝利が示すように、国力の差は歴然としていました。戦後も超大国アメリカが占領し、沖縄返還後も日本が国力で圧倒していたのでおとなしくしていたのです。
民主党による外患誘致
ところが、一昨年中国はGDPで日本を追い抜き、世界第二位の経済大国に成長しました。軍事費も毎年増強しています。中国は日本に対して自信を持ち始めたのです。
その上、民主党が間違った外交メッセージを出し続けたのです。安保条約を結んでいるアメリカとの関係と、領土的対立のある中国との関係を同様に扱うという出鱈目をしてきたのです。政権交代直後の小沢幹事長の大訪中団はその象徴です。
その上、防衛予算を少なくし、米軍の普天間基地をできれば国外に移転するというのは、尖閣諸島のみならず沖縄をも中国に献上するに等しいメッセージです。案の定、中国はこの時とばかり、領土的野心をあからさまにしたのです。これでは、民主党による外患誘致だと言われても仕方ありません。
誤った歴史認識による売国行為
竹島も同じことが言えます。韓国は、サンフランシスコ条約が発効して日本が主権を回復する直前に、竹島の占有を始めました。その後も韓国の実行支配を放置してきたことは、自民党にも責任が有ります。
しかし、それ以上に民主党の責任は重大です。1965年の日韓基本条約締結時に戦後賠償問題は完全に解決したにもかかわらず、更なる補償をするかのような発言を民主党の首脳が繰り返し行ってきました。従軍慰安婦問題はその典型です。そもそも、この問題はその存在自体が事実ではありません。
この問題は1983年、吉田清冶(元軍人の作家)が『私の戦争犯罪』を出版し、この中で、自分が済州島から慰安婦を拉致したと書いたことが発端です。しかし、調査の結果、済州島から拉致した事実は見つからず、1989年には、韓国の済州島新聞がこれを捏造と報じました。そして、1996年、遂に吉田清冶自身が「創作」を交えたことを認めました。つまり、嘘だったと認めた訳です。
ところが、この間の1993年、「日本政府が強制したということは認めたわけではない」が、日本軍の要請を受けた業者によって女性が意志に反して集められ、慰安婦の募集について「官憲等が直接これに加担したこともあった」という河野官房長官の談話が発表されたため、韓国側に要らぬ言質を与えてしまったのです。誠にこの罪は重いです。
外国に媚び、国を売る民主党
しかし、民主党の韓国に対する対応はこんなものではありません。民団に選挙応援をしてもらうために、永住外国人に地方参政権付与することを公約に掲げ、野田総理自身が選挙後、千葉県の民団の大会でそのお礼に駆けつけるなど、民団との異様な関係を続けています。また、従軍慰安婦に補償をすべきと、ソウルでの反日活動に参加していた岡崎トミ子参院議員を国家公安委員長に任命したり、前原外務大臣や菅総理、更に野田総理まで韓国人からの違法献金をうけていました。
その後も、民主党の違法な外国人献金は後を絶ちません。
外国に媚る姿勢は民主党の宿痾とも言えるでしょう。こうした民主党の姿勢が、韓国や中国に付け入る隙を与えてしまったことは紛れもない事実です。
一日も早く、安倍政権の誕生を!

安倍総裁が目指すものは、こうした民主党の失政を糾すだけではありません。自民党政権下で行ったものでも、誤ったものや時代にそぐわないものは直さなければなりません。自分で自分の国を守り、自国を愛する。この当たり前のことができなかったことが、全ての問題の原点です。戦後のタブーを乗り越えていかねばなりません。
更に、経済をデフレから脱却させなければ、国民に希望を与えることができません。若者に仕事を、お年寄りに安心を与えるためにも、消費税増税の前にデフレ対策を徹底しなければなりません。
そのためには、一日も早い政権の奪還が必要です。皆様方のご支援、よろしくお願い申し上げます。
樋のひと雫
-総裁選対代表選-
羅城門の樋
今秋は同時期に総裁選と代表選が行われ、次の日本の政治を決する顔を選ぼうとしています(SHOW YOUが出る頃には決まっているでしょうが)。今回の戦いは対照的でもあります。総裁選の方は、告示の日から5人の候補者が多くのTV番組に出て、自己の政治信条と政策方針を国民に訴えました。日本記者クラブでの3時間に及ぶ討論会をNHKが中継したのはその良い例でしょう。片や、代表選の様子がTVに流れるのはニュースの1コマだけでした。如何に政党内の内部選挙であっても、国民生活に直結する政権政党の代表を選ぶ姿としては如何なものでしょうか。
時あたかも中国では反日暴動が広がり、在留邦人の安全も侵されようとしていた時です。総裁選では外交や国防の在り方にも一論を割き、各人がその具体論にも触れています。「海兵隊の創設」が論議された総裁選は、今までになかった出来事です。時代の進捗、隔世の感を抱かせるに十分なものでした。それに引き替え、代表選は党内融和の話ばかり、議員の為の議員の選挙。中国各地の日本企業の破壊など、何処吹く風の話ばかりです。どちらが政権政党か、聞いていると憤りさえ覚えました。
この時期、NHKでは吉田茂のドラマを放映していました。戦後日本の復興を経済再生に焦点化し、日本丸の操船をした傑出の政治家です。しかし、彼の対米単独講和が日本の独立の片翼を阻害したのも事実です。戦後復興を果たした今も、日本の外交はODAの援助金を配るだけの外交に陥り、国防という観点からは程遠い地平にいます。某候補者が言っていました。「外交とは片手で握手をし,一方では拳を握りしめること。これなくして外交はあり得ない」と。蓋し、名言です。理念と方法がなければ、国の安全と国民の命は守れないでしょう。
ユニクロの上海支店では「釣魚島(尖閣諸島)は中国固有の領土」という貼り紙を掲示したそうです。自社の利益だけを考えると、このようなことになるのでしょうが、同じ在外邦人としては恥ずかしい限りです。自分の利益のためには国を売るという姿勢に眉をひそめるのは私ばかりではないでしょう。これは自己保身の端的な例ですが、「国は在外邦人を守る」という信頼があればまた違った対応もあったでしょう。
「近いうち」に行われるはずの総選挙では、「大阪都を作るかどうか」の問題ではなく、「日本人の国家観」を問い直す一票を投じたいものです。
小沢元代表離党
三年前、民主党政権を樹立した小沢元代表が、衆参合わせて50名にもなる国会議員を引き連れて民主党を離党しました。小沢元代表は「今の民主党は政権交代をした民主党ではない。結党の精神に戻るべき」と離党会見で表明しましたが、これこそ笑止千万です。
国民の生活第一を掲げはしたものの、結局は選挙目当てのバラマキ政策で国民を騙し、赤字国債の増発で財政を悪化させ、挙句の果てに消費増税を打ち出した民主党に、戻るべき原点など有りはしません。政権を取ることだけを目的に、政界を掻き回してきた小沢元代表に耳を傾ける国民は、もう誰もいないでしょう。
民主党には、人材も政策も無かった
 ――参議院予算委員会(6月13日)にて中国スパイ事件ならびに丹羽宇一郎駐中国大使の発言について追及しました――
――参議院予算委員会(6月13日)にて中国スパイ事件ならびに丹羽宇一郎駐中国大使の発言について追及しました――
これは、小沢元代表に限ったことではありません。元々、民主党は政権を取ることだけを目的にした集団です。理念も政策も最初からまともに議論してきた訳では有りません。有権者に対する受けを狙っただけの出鱈目が、マニュフェストとして掲げられていただけです。
丁度、設立して間もない会社が、製品の開発もしていないのにカタログだけを展示して、高配当を謳って出資を募るようなものです。
実社会なら詐欺的商法として逮捕されてしまいます。これが民主党の実態だったのです。いくら学歴があろうが、いくら見栄えが良く人気があろうが、詐欺師は詐欺師です。もうこれ以上騙されないようにお願いします。
 ――TOKYO MXTV「西部邁ゼミナール」に谷垣総裁とともに出演しました――
――TOKYO MXTV「西部邁ゼミナール」に谷垣総裁とともに出演しました――
消費増税と社会保障一体改革法
この法律は、毎年一兆円以上増える社会保障費を賄うためのものです。我々の世代の医療、介護、年金を我々が負担するのは当然のことです。このことの必要性を自民党は以前から主張してきましたが、民主党は「その必要は無い、無駄を省けば更に、子ども手当てや高速道路の無料化まで出来る」と主張してきたのです。これが出鱈目であったことが今回改めて明らかになりました。更に、最低保障年金、年金の一元化、後期高齢者保険制度廃止など前回の選挙で彼らが主張してきたことも、全て出来ないことが明らかになったのです。
デフレ対策のためには政権奪還が必要
デフレとは物価が継続的に下がる事を言います。これは、企業にとっては売り上げの減少を意味します。従って、売り上げが減り続ける状態では、企業は投資をしたくないのです。このため、日銀がいくら金利を下げ、民間銀行にどれだけ資金供給をしようとも、デフレ下では民間企業は投資を行いません。この様に企業の経済活動が低下した結果、GDP (国内総生産)が低下し、税収も落ち込んだのです。従って、増税の前にまずデフレから脱却する必要があります。
目の前にお金をぶら下げても、民間企業が借りなければ意味がありません。金融政策には限界があるのです。そこで為すべきは、政府による財政出動なのです。民間企業の投資意欲が少ないこの時こそ、政府が積極的に投資をしなければなりません。特に震災復興や防災のための支出、東京一極集中を排除して地域の均衡ある発展を促すための支出などは、誰も反対をしないでしょう。こうした支出を列島強靭化と称して、十年間で200兆円位の投資をすべきと自民党は主張しています。これだけの投資をすれば日本の経済はデフレから一挙に立ち直ることができます。
そのための財源は建設国債で賄えば良いのです。建設国債は子や孫のために資産を残すための借り入れですから、赤字国債のような借金の付け回しではありません。またこうした投資により、GDPが増え税収が自然増加しますから、財政が悪くなることもありません。
しかし、これを実行するには予算編成権と予算執行権を持たねばなりません。つまり、政権を奪還しなければ出来ないのです。
日本の国債は破綻しない
去る5月16日、日銀による民間銀行からの国債買い入れ(買いオペ)が不調に終わりました。日銀の6,000億の買い入れ申し出に対して、民間銀行は4,800億程しか応じなかったためです。民間銀行は、国債を保有していれば、1%弱の利息を得ることが出来ます。日銀に国債を売れば日銀当座預金に入金されますが、これには0.1%しか利息がつきません。そのお金を民間企業に融資をして、1%以上の利息を稼ぐことが出来れば得ですが、今はその需要がないのです。国債を持っている方が有利であるために彼らは売らなかったのです。つまり市場が国債を要求しているのです。国債の買い手がないのではなくて国債の売り手がいない状態なのです。これは、ギリシャの国債とは逆さまの状態なのです。今ほど、国債を有利に発行できる時はないのです。
私はこの事実を国会で質問しました。ところがこうした事実をマスコミは全く報道しておりません。国民に正しい情報が伝わっていないのです。
「増税の前にやるべき事がある」は間違っている
小沢氏や大阪維新の会などは盛んに、増税の前にやるべきことがあると言っています。国民に負担を求める前に、もっと無駄を削減せよ、公務員を減らせなどと言っています。一見正しそうに聞こえますが、これは全く間違っています。
まず第一に、国民が負担した税金は社会保障費などで全て国民に還元されるのです。誰かが得をするわけではありません。無駄削減も同じことを民主党が言いましたが、一体いくら出てきたのでしょう。また、同じ手で国民を騙せると思っているのでしょうか。出来るなら具体的に示してもらいたいものです。
公務員の数は英米仏の半分以下
彼らは、公務員の数や給与を削減すると言います。しかし、日本の公務員の数は世界でも格段に少ないのです。国、地方、自衛隊、国立大学など政府系の独立行政法人等の職員も含めた公務員の数は、日本では国民千人につき30名程度です。他の先進国で、アメリカやイギリスやフランスなどでは、千人につき70名から80名を超えています。日本は少なすぎるくらいで、これ以上の削減は国家の破壊につながります。公務員の給与も民間同業種に比べて10%近く削減をしています。つまり、公務員叩きは選挙目当ての出鱈目なのです。
無駄削減はデフレを加速させる
自民党は、増税の前に列島強靭化などの積極財政を行い、デフレを退治すると主張しています。民主党や小沢新党、大阪維新の会などは、相変わらずの無駄削減です。デフレで民間企業が投資を控えている時に政府が支出を減らせば、間違いなくデフレは加速します。GDPは落ち込み、税収も激減し、国民経済は破綻してしまいます。
民主党の失政を総括
民主党が、出鱈目のマニフェストで国民を騙して選挙をしたことが、全ての失政の始まりです。子ども手当も高速道路の無料化も、財源のない絵空事だったのです。しかし、何故、彼らはそうした事をマニュフェストに掲げたのでしょうか。野田総理はその当時は分からなかった、自分たちは未熟だったと詫び、消費増税をお願いしています。小沢元代表はマニュフェストの間違いを認めず、消費増税に反対しています。どちらが正しいのでしょうか。実は、どちらも間違っているのです。
野田総理の言う、民主党は与党経験がなく未熟だったという言葉は、ペテン師の言い訳に過ぎません。彼らが、財源を無視した政策を言えるのは、未熟ではなく不道徳だからです。嘘をつくことが平気でなければ、ここまでの出鱈目が言えるはずがありません。それを未熟だったと言うこと自体、責任逃れであり、彼らが本当は何も反省していないことを証明しています。
小沢元代表に至っては、論外です。実際に政権をとっても財源が見つからず実行できなかったことを、もう一度公約に掲げるとは、厚顔無恥も甚だしい。国民を舐めきっています。
事実を報じないマスコミの責任
 ――西田昌司国政報告会2012を開催しました。会場一杯の皆様にご来場いただき誠にありがとうございました――
――西田昌司国政報告会2012を開催しました。会場一杯の皆様にご来場いただき誠にありがとうございました――
マスコミは、民主党が出鱈目のマニフェストを掲げていたにもかかわらず、一度民主党に任せてみてはどうかと政権交代を煽りました。その結果が、今日の日本の無惨な姿です。その反省もないまま、今度は、何の実績もない大阪維新の会の言動ばかりを取り上げ、国民に期待を持たせようとしています。
新たなスターを育て部数や視聴率が上がれば、マスコミの商売としては成り立つかもしれません。それがタレントなら良いでしょう。しかし、それは政治の世界では通用しないのです。政治家をスターにして囃し立てれば、マスコミの商売は良いかも知れませんが、国は滅んでしまいます。政治の不道徳の影には、こうしたマスコミの出鱈目がその一因となっています。私は、こうした事実を報じないマスコミとも断固戦っていく覚悟です。
今後とも、ご支援をよろしくお願い致します。暑さが厳しくなりますが、皆様ご自愛ください。
瓦の独り言
-1次産業に学ぶこと-
羅生門の瓦
無農薬、稲木による天日乾燥で稲つくりをして3年目になります。初めは田の神様も味方してくれてか、それなりに収穫がありました。しかし、昨年は雑草の猛攻撃。それにいもち病(今年になって分かったのだが・・・)の発生。稲木に刈り取った稲を三段干にしたら、一番下は鹿さんが引っ張っていきました。
みるに見かねて、近郷の稲つくりのベテランがアドバイスに・・・。今年はその方の指示に従い、最小限の農薬も使うことにしました。土起し、代かき、田植えと1週間ごとに指示をいただき、今は田の水の管理をしています。
そこで瓦が気づいたことは、「稲は水さえやっておけば勝手に米が出来る」は大きな間違いで(鳥羽のお百姓さんが聞かれた笑える話だが・・・)、事細かな工程管理がなされています。これは瓦が知っている蚕の繭が出来るまでと、繭から生糸が生産されるまでと同じです。農業という1次産業にも、生産の工程管理(瓦は2次産業に身をおいていたことがあるので、ついついこの言葉を使ってしまいます。)が必要で、これが日本の米作りを支えていたのだなあ、と再認識いたしました。
しかし、農業という1次産業では「自然の営み」に従うことが大前提です。「自然に合わせてやらないと仕事にならない。木をひとつ動かすにも時期がある。自然の営みを無視しては出来ない。」
と佐野藤右衛門さんも「日本人の忘れもの」(京都新聞:平成24年6月10日朝刊)で述べておられます。 ところが、瓦は2次産業に身を置いていたものだから、人間の力で何とかなる。工程管理、スケジュールは人間が組んだものだから、発想の転換で何とでもなる、と人間の力を過信していました。
今、農業という1次産業をかじってみて、改めて自然の営みの大きな力を感じました。人間は台風を予知できても、台風を避けることは出来ないように。自然を相手にしていては、杓子定規に事は運びません。また理屈もこねられません。ある意味、ケセラセラ、なる様になるは・・・。と、考えなければならないことが多々あることを、米つくりが教えてくれました。
今、3次産業の連中が、1次産業にスポットを当てて「1次×2次×3次=6次産業」が見込まれるといっています。恐らく、彼らには自然の営みは計算に入っておらず、人間の叡智を持ってすれば何でも出来ると思っているのでは。この21世紀は人間が自然を支配する時代だと思い上がっているのでは・・・。でも、この数式で、1次産業が倒れたら、0次産業になってしまい。この数式は日本の産業構造を予言しているのでは。1次産業を捨て食料自給率がゼロになってしまったら・・・。と、思っているのは瓦一人では無いはずです。
唐突な増税論
野田総理の唐突な消費税増税が、大きな政治問題となっています。今回の消費税増税の理由を野田政権では、毎年社会保障費が1兆円増加する、その財源を賄う為には何としても消費税増税が必要なのだと説明しています。これは全く正しい話です。実は私達自民党も先の参議院選挙の時、同じことを主張していたわけです。しかし、それを必要ないと言ったのは民主党なのです。あまりにも無責任が過ぎます。
出鱈目マニフェストのつけ。
 ――参議院予算委員会(3月19日)にて鹿野農水大臣を追及しました――
――参議院予算委員会(3月19日)にて鹿野農水大臣を追及しました――
そもそも、消費税増税の理由が社会保障費の増加のためということは、つまるところ、社会保障費をはじめとする経常経費、つまり毎年必要となる経費には、恒常的な財源が必要であるということです。
だからこそ、我々自民党は消費税の増税が必要だと言うことを言ってきたのです。ところが民主党はかつての衆議院選挙ではその必要はまったくない、消費税の増税は必要でないばかりか、無駄を削減すれば子ども手当や高速道路の無料化なども十分できるのだと言ってきたのです。しかし、問題はそうしたバラマキは毎年ずっと必要となる予算ですから、経常的な支出です。その実現には恒常的財源が必要だったのです。そのことを私たちは政権交代前から民主党にただしてきましたが、彼らはそれに一切答えず、とにかく自分達が政権を取れば出来るのだと言ってきたのです。しかし、結局、恒常的な財源を見つけられず、赤字国債でバラマキ政策は続けられてきたのです。当然のことながら赤字はどんどん増大する。
まさに借金のツケ回しを民主党政権がしてきたと言うことです。さすがにこれ以上続けられないと今回慌てて消費税増税を言い出したのです。これについて彼らは政権をとるまで分からなかったと言っていますが、これが出鱈目です。経常的支出には恒常的財源が必要だということは、当たり前のことです。このことだけでも民主党には政権を担当する資格がないのです。
 ―― 自民党富山県時局講演会にて講演をいたしました ――
―― 自民党富山県時局講演会にて講演をいたしました ――
AIJと同じく詐欺だ
これはAIJ事件と非常によく似ているのです。AIJ事件と言うのは要するに、高配当を謳って民間企業の厚生年金基金から2000億円に上る資金を集めました。ところが、実際には高配当どころか巨額の損失を出していたのです。その一方で虚偽の報告をし、損失が出ているにもかかわらず高配当して、そのうちの何割かは自分達の手数料だと言ってもらっていく。まさに偽りの報告を継続的に行い、次々新しい年金基金からの資金を獲得することによって損失の穴埋めをし、高配当を維持してきたのです。まさにこれはタコが自らの足を食べるのと同じです。AIJには、以前からそういう噂があったのですが、ようやく、金融庁の調査で明らかになったのです。これは、投資に失敗したのではなくて、初めから出来もしないことを言い、それをカモフラージュするために、次々と粉飾をし、終には破綻したのです。まさにこれは詐欺だと思います。民主党のマニフェストのバラマキ政策は、まさにこのAIJと全く同じ構図にあるのです。
ところが、このことについて民主党政権は全く反省がありません。「AIJ問題と同じだ」と、私は参議院の財政金融員会で安住財務大臣に指摘しました。「そんなことはない、AIJは過大な被害を出したけれども、われわれのマニフェストは公約が未達成だっただけ」という開き直りをしましたが、とんでもないです。まさに、バラマキで借金のつけ回しをして、そして経済を大きく棄損し、挙句の果てに増税で国民に負担を押し付けるとは、AIJ以上に酷いものです。これはAIJに年金を任せられないように、民主党にも政権を任せられないのです。
税金ではなくGDPを上げろ
今必要なことは、増税ではありません。税収が落ち込んだ一番の原因は、一つは民主党の政策の誤りであり、その誤りにより、GDPすなわち国民の所得の総計がどんどん小さくなってきた、そのために税収が落ち込んできてしまったのです。落ち込んだ税収を取り戻すために税率を上げても、一時は税収が増えるかもしれませんが、国民の手取りの所得がどんどん少なくなりますから、当然のことながら、経済が小さくなり、結局は増税により一旦増えた税収もやがては小さくなっていくのは必定です。いま私たちがすべきことは増税ではなくて、その落ちてきたGDPをもう一度大きく上げるということが必要なのです。そして、GDPがきちんと上昇しだした後、社会保障費の増加に対応するため消費税を上げれば良いのです。
GDPは三面等価
GDPは三面等価であると言われます。これを大まかにいうと、1つは生産の面です。第一次産業、第二次産業、第三次産業などどこがどれだけの生産をしているかその合計です。次は支出の面。これは個人や企業の消費や政府の支出の合計が支出面です。そして3つめは分配の面、これはまさに所得ですが、皆さんの給料や企業の利益と減価償却費、そして消費税などの合計になります。これらがすべて同じ金額になる。同じものを表しているというのが三面等価という意味なのです。
給与を下げるのは誤り
そこでGDPを上げるには、分配の面で言うと個人の給与や企業の利益をどう増やしていくか、このことが大事なことになります。所得を増やす面でいうと、大事なことは国民の給与を絶対に減らしてはならないということです。ところが民主党は給与をどんどん減らす政策を平気でしています。その一番の典型が、公務員給与を7.8%下げるというとんでもない法律を提出し成立させたことです。これは残念ながら自民党なども賛成をしてしまいました。私一人が反対ボタンを押しましたが、その理由は公務員の給与を下げていくと間違いなく民間の給与も下がるからなのです。それは、公務員の給与を基にして決められている民間企業がたくさんあるからです。中小企業など、給与規程が十分に整ってないところでは公務員の給料規定をそのままベースにしています。それから、大学や幼稚園や保育園など、民営であっても公的な仕事は公務員給料に準じて支出を行っています。JAなどもそうでしょう。実はそういうところが数え切れないくらいたくさんあるのです。この方々の給料は、公務員給与が下がると一緒に削減されていくことは必定です。そして、その結果何が起こるかというと、こうした方々の消費で支えられている地方の経済が一挙に縮小するのです。これでは経済が成長するはずがありません。
金融政策だけではデフレは脱却できない
経済成長のためには、本来は、民間部門でお金をどんどん使っていけばいいわけです。しかし現実には、実質はゼロ金利だといわれるくらい低金利で日銀が民間銀行にお金をたくさん供給してもそのお金が貸出されません。金融界では「馬を水辺に連れて行くことができても馬に水を飲ますことはできない」という格言があります。つまり、いくら水辺に馬を連れていっても水を飲むかどうか馬の意思によるということです。お金をいくら目の前にたくさん出しても、借りるかどうかは民間企業や銀行の意思によるこういうことです。なぜ馬が水を飲まないかといえば、水を飲んでおなかを壊してしまうかもしれない。なぜ民間企業がお金を借りないかといえば、お金を借りても返済できるかどうかわからない。その自信のなさから、水辺に馬を連れて行っても水を飲まない、たくさんお金を供給しても、お金を借りないということになるのです。
積極財政が国を救う
つまり、デフレ下では民間の企業に対していくら金利を下げても、お金を供給しても景気はよくならないということです。残っているのは最後の借り手である政府が、民間が借りないお金をたくさん使って、公共事業や政府支出を増やし雇用を創出することによって民間に直接お金を供給していくということが必要なのです。こうしたことを3月27日と29日に行われた参議院の財政金融委員会で詳しく説明しながら安住財務大臣、白川日銀総裁と議論してきました。私のホームページ等、インターネットに出ておりますので、是非この様子を皆様方に御覧頂きたいと思います。
マクロとミクロが分からない民主党政権
経済はミクロとマクロがあると言われています。ミクロとは個々の家計や企業の経済のことであり、マクロとはそれら全てを見渡した国全体の経済のことです。このマクロ経済の管理をするのも政府の使命です。個々の企業や家計がお金を使わず不況になるなら、逆に政府がその分お金を使うのは、マクロ経済の管理者として当然のことです。それを民間企業と同じく政府も借金が多いので節約しますというのは、政府は民間企業と同じミクロの立場にある訳で、マクロ政策の放棄です。
民主党はこの政府の役割を全く分かってないのです。国民がデフレで困っている時に政府がその役割を果たさずにいることは、戦争での敵前逃亡と同じです。
ルーズベルト大統領に学ぶ
 ―― 西田昌司京都政経パーティーを開催したところ、多くの方々にご参加いただきました ――
―― 西田昌司京都政経パーティーを開催したところ、多くの方々にご参加いただきました ――
お金がないなら節約するというのは、大変分かりやすく、それ自体は正しいとことです。しかし、国中がそうした節約に徹すれば、誰もお金を使わなくなり、経済はデフレに陥り、へたをすれば大恐慌になってしまいます。
1929年の世界大恐慌の時、ルーズベルト大統領はまさにこの事態に対処するため最後の借り手である政府が積極的に投資をして世界を救ったのです。まさにデフレとの戦いに勝ったのです。ところが民主党はデフレとの戦いから尻尾を巻いて逃げだして、そして増税という安易で間違った政策に飛びつこうとしているのです。戦争やあらゆる脅威から国民を守ることが政府の仕事であると同じように、デフレとの戦いから国民経済を守る、国民の生活を守る、その不退転の決意と覚悟が今必要なのです。この覚悟も決意も知恵もない民主党・野田政権には、政権を担当する資格はないということです。
おそらく早晩解散総選挙ということになるでしょう。
どうか皆様方にはこうした民主党・野田政権の国を滅ぼす誤った政策をしっかりと御認識下さい。そしてもう二度と政権担当能力のない、出鱈目な方々には政権を渡さないで頂きたいと思います。
これからも国民の生活を守るために全力で頑張っていきます。
皆様方のご支援をよろしくお願い致します。
瓦の独り言
-桜に思う-
羅生門の瓦
さまざまの 事おもひ出す 桜かな 「芭蕉」
この俳句ほど、今年の日本人の胸の奥をしめつける歌はないのでは。とくに東北地方の方々にとって、今年の桜は感極まるものがあるのでは。インターネットのプログなどにもこの歌の書き込みが多くなっています。
さて、桜前線が北上してくると、それぞれのさくらごよみ桜暦が思い出されるのではないでしょうか?思えば、何年たつのでしょうか? 「サクラチル」に涙して、一念奮起。次の年には桜吹雪の中を謳歌していたことを思い出すのは瓦だけではないはずです。
「待つ花」である桜は、入学式、卒業式といった人生の節目と大きくかかわってきています。それなのに、今、大学での秋入学が、叫ばれています。春に卒業した高校生は、秋までどのようにして待機するのか?大学だけではなく秋入学の制度が小中学校をはじめ全ての学校に適応されたら・・・。桜の樹の下でのランドセル姿が見られなくなる。厳しい冬を耐えてこその春であり、入学式を迎えるのです。開放的ではあるが暑い夏の後の入学式はなんとなく締まりません。大学側の言い分では、優秀な海外の留学生を確保する目的とか・・・。
しき嶋の やまとごころを 人とはば 朝日ににほふ 山ざくら花 「本居宣長」
の歌をめでる人々にとって、秋入学制度などありえない、と思っているのは瓦だけでしょうか? いずれにしても日本人にとって「桜」は特別な花で、人生の節目と大きくかかわっていると思います。
さて、西高瀬川の祥鳥橋下流にある「木下桜」(瓦がかってに呼んでいるだけ)。今年、どんな花を咲かせてくれるのでしょうか
鳩山、菅より酷い野田内閣
 ――参議院予算委員会「政治とカネ」の集中審議にて質問をしました(12月6日)――
――参議院予算委員会「政治とカネ」の集中審議にて質問をしました(12月6日)――
九月に発足した野田内閣ですが、何の実績もないまま、参議院で、山岡、一川両大臣に対する問責決議が可決されました。新年からの通常国会は、この両名の罷免がない限り事実上開催できなくなりました。元々、山岡氏は選挙違反で捜査中であり、これを国家公安委員長に任命したことだけで問題です。さらに山岡氏はマルチ商法の広告塔だったのですが、その人物を消費者大臣にするというのは常識では考えられないことです。
また、一川氏も就任当初から防衛政策に関しては素人と公言するなど、大臣としての適性にかけていたことは誰の目にも明らかでした。また、忘れている人も多いでしょうが、鉢呂経産大臣も就任直後に舌禍で辞任しています。今回の決議は、両大臣の問題というより、不適格者を任命した野田総理自身の任命責任が問われるべきものです。ところがそれに対する反省が全くないのです。
そもそも、野田内閣が発足したのは、民主党の党内事情からです。ポスト菅の大本命であった前原氏が、外国人や黒い人脈からの献金で自滅し、親小沢対反小沢という根本対立が民主党には有り、党内融和を図るという言わば消去法で選ばれたのが野田氏です。その一方で、民主党には綱領が有りません。つまり、海図もエンジンもない船の船長に選ばれたのが野田総理だということです。
鳩山さんや菅さんも酷かったですが、間違いであったにしろ、彼らには主張が有りました。 ところが、野田総理にはそれさえありません。従って、何を質問しても役人の書いた答弁書を棒読みするだけです。
これを野田総理は安全運転と称しているようですが、これでは政治家同士の活発な議論などできるはずもありません。また、自らの外国人献金など、政治とカネの問題などは、いくら事実関係を指摘しても、最後は知らなかったということでごまかしてしまいます。これでは、言論の府としての機能を国会は果たせません。正に、民主党政権の酷さはここに極まれりです。
 ―― 自民党新潟県政経文化セミナーにて講演をいたしました ――
―― 自民党新潟県政経文化セミナーにて講演をいたしました ――
全ての問題はデフレ
野田総理は、震災復興を口実に増税をしようと企んでいます。確かに、予算のうち税より国債の方が多いというのは問題です。それが地方と合わせて1000兆円もあると言われれば、不安に思われる方もいるでしょう。しかし、それでも、日本が破綻することは絶対に無いのです。その理由は、日本の国債が円という自国の通貨で発行されているからです。最後は日銀が国債を引き受けることができるので、絶対に国債は返済不能にはならないのです。
日銀がいくらでも国債を買うとなれば通貨の信用が落ちてしまうと言う方がいますが、円高で困っているのですから多少円安になることはむしろ歓迎すべきことです。
そもそも、円高の原因は、デフレにより実質金利が、欧米より高いことにあります。日本では、金利が例え0%でも、デフレで物価が下がるため、その分だけ実質金利がついてしまいます。欧米では、金融不安を払拭するため大量の通貨を市場に供給し、さらに金利もどんどん下げ続けています。金利は、0%より低くできませんから、日本と欧米の名目上の金利差はほとんど無くなっています。その上、日本だけがデフレですから、実質の金利は日本の方が欧米より高くなっているのです。そのため、ドルやユーロより円が買われ、円高が続いているのです。これが円高の根本的原因なのです。円高により、輸出企業は大変な損害を受けています。円高を抑えるためにもデフレ対策が必要なのです。
緩やかなインフレが正しい経済政策
デフレは、需要が減り物価が下がることです。そのため、国民の給与が下がります。その結果、益々需要が減り、物価が下がり、さらに給与が下がるという悪循環が繰り返され、経済は破綻するのです。
インフレは、需要が増え物価が上がることです。物価が上がりますが、需要が増えるため雇用や給与も増えるのです。急激なバブルでは物価上昇に給与が追いつかず大変ですが、毎年2-3%程度なら全く問題有りません。日銀総裁も、私の国会での質問に対し、緩やかなインフレが望ましいと答えています。
デフレ脱却のためには日銀がもっとお札を刷れば良いのだと言われます。その通りですが、日銀がお札を刷るとはどういうことでしょう。日銀がお札を刷れば、いくらでもお金は出せます。しかし、まさかヘリコプターからばらまくことなどできません。その印刷したお札を銀行に渡し、それを銀行が民間に融資することによって始めて、通貨が世間に行き渡るのです。つまり、お札を刷るとは、銀行がどんどん貸出をする、そして、その資金を日銀が供給するということなのです。
ところが、デフレでは、日銀がいくら銀行に資金供給しようとも、貸出が増えないのです。民間銀行が150兆円を超える預金超過であることがそれを証明しています。デフレとは需要不足による物価の下落ですから、それも当然のことなのです。この状態では、いくら日銀が資金を銀行に供給しても銀行から企業に貸出は増えません。
この状態で政府が取るべき政策は、国債を発行して、震災復興や防災、インフラの更新や増強などの公共事業を向こう10年で200兆円ほど行って、需要を創り出すことなのです。これを実行すば、確実にデフレから脱却し、経済は再び成長軌道に乗るのです。
インフレにすれば税収は増える
日本はデフレが続いていたため、平成3年と23年のGDPは共に470兆円で、この20年名目上のGDPは全く増えていません。その上、この間景気対策で減税もしたため税収は逆に減り、60兆円から41兆円に減ってしまっています。減税をすれば、民間投資が増え、景気が良くなると思われていたのですが、現実には減税分は海外での投資に使われ、国内の需要を増やすことにならなかったのです。
こうした政策が取られた原因は、バブル以後、公共事業を抑え民間投資を優先する方が正しいと思われてきたからです。確かに、公共事業の急激な増加がバブルを招いた原因の一つであることは事実です。しかし、それに懲りて今度は公共事業は全て悪で無駄だと決めつけるのも問題です。必要な公共事業を行わなければ国土がもちません。
もし、この20年間、毎年名目上3%程度のインフレになっていたら、GDPは平成3年の1・8倍の850兆円に、税収は更に増え2倍の120兆円になっていたはずです。そうすればGDPも未だ中国に抜かれることなく世界第二位の歴然たる経済大国だったでしょうし、財政再建のために増税をする必要も無いのです。この数字を見ても分かるとおり、全ての問題はこの20年のデフレなのです。インフレは物価が上昇しますが、給料もあがります。それに伴い、GDPも税収も増えるのです。増税より先に、デフレからインフレに変えることが必要なのです。
TPPはデフレを加速する愚策
こうした経済の認識が無いまま、民主党の野田内閣は増税をし、TPPへの参加を強行しようとしています。全くの愚策です。デフレで増税をしたら経済は破綻してしまいます。更にTPPの参加はデフレを加速させてしまいます。TPPの問題点については何度も述べてきました。日本にとっては百害あって一利も無いものです。事実上の関税自主権を放棄するTPPより、他の自由貿易協定の方がマシなのは当たり前です。しかし、そもそもの問題は、日本を貿易立国にすると叫んでいる野田総理を始めとするTPP推進派の能天気です。
政府の試算でもTPPでは0.5%、他の自由貿易協定でも1.2%程度しかGDPの押し上げ効果は有りません。つまり、どのような自由貿易協定でも大してGDPは増えないのです。その理由は、輸出を増やすと言っても、製品を大量に輸出することはできないからです。今や現地生産現地消費が輸出の基本なのです。アメリカやアジアで売られている自動車や家電品は、日本ブランドではあっても多くが、Made in USAやMade in Chinaであり、Made in Japanではないのです。海外での生産が進んだ結果、いくら日本製品が売れても、国内の雇用が増えません。むしろ、雇用を海外に取られまいと給与が減額されてきました。事実、この20年、平均給与は下がり続けているのです。その結果、海外展開をした大企業は最高益を更新し続けましたが、国内の雇用が減り、国民の給与が下がったため、GDPも減ってしまったのです。このように、バブル以後の民間経済を主体にした構造改革、市場原理主義が国内を空洞化させ、デフレを招いたのです。
バブル以後の総括が必要、解散でただせ!
 ―― 西田昌司第2回東京セミナーを京都大学教授の藤井聡先生をお招きして開催いたしました ――
―― 西田昌司第2回東京セミナーを京都大学教授の藤井聡先生をお招きして開催いたしました ――
TPPや、自由貿易協定の推進論はこうした市場原理主義に基づいた政策です。それが誤りであったことは、この20年間の日本の惨状を見れば明らかでしょう。
こうした政策は、日本だけではなく全世界で行われてきました。そして、それが失敗であったことはリーマンショックが証明しています。ところが、このことが野田総理を始め、TPP推進派には分かっていないのです。
何とかにつける薬はないと言いますが、国会での議論も、いくら問題点を指摘しても、全く理解していません。そのことをマスコミも報道しません。世界の流れだから仕方がないと勝手に思い込んでいるのです。今、私にできることは、こうした事実を少しでも多くの国民に知っていただき、国会を解散させ、国民に信を問うこと以外有りません。本年もよろしくお願い申し上げます。
樋のひとしずく
-ボリビア通信-
羅生門の樋
“Felicidades Navidad y Nuevo Año” 新年の挨拶の習慣のない南米では、これが年末年始の挨拶です。意味は「メリークリスマス、新年おめでとう」ですか。街角や喫茶店でこの挨拶があふれます。日本では今年ほど「絆」という言葉が氾濫した年はないでしょうね。未曾有の自然のエネルギーの前には、人間の英知や営みなどは“たかが知れたもの”と思い知らされました。その無力な人間が自己の存在の儚さを自覚し、相互に寄りあい助け合う、この人間愛の築く過程を絆と呼ぶのでしょうね。実に愛のある言葉だと思います。この絆は人と人との断ちがたい関係という意味だそうで、何も自分が不安だから、人を求めるという意味ではなさそうです。先日も「鍋料理を作って家族の絆を」というスーパーの宣伝があると伝聞しました。
ところで、「私は素人」と言った防衛大臣が問責を受けましたが、ここボリビアの国防大臣に30歳過ぎの眉目秀麗な女性が就任していました。彼女は並みいる将軍を抑え、過去にクーデターで軍事政権を樹立した軍部を掌握しています。5月にはチリ国境で軍と国境警備隊との間で衝突がありましたが、これを大事に至らせずに納めています。また、8千人が被害を受けた大規模な土砂崩れの際にも、軍を投入し、その先頭に立って救助活動を指揮しています。そして、10月初めに平穏な生活を壊されたくないと道路建設に反対していた女子供を含む先住民のデモ隊400人が夕食の準備をしていた時に、内務省管轄下の500人の武装警察隊が襲うという事件がありました。(インディアン部落を襲う騎兵隊という、まるで西部劇のようです。)この際に彼女はその日の内に、「国民を守るのが国防大臣の職責である」と大統領を批判し大臣の職を辞しています。
彼女も国防には「素人」で、一介の学者にしかすぎません。しかし、その判断力や職に対する責務は、どこかの国の防衛大臣に学んで欲しいところです。「襟を正して」と庇う任命権者と「これからもきっちり」と職に留まりたいと言う大臣。これはどんな「絆」なんでしょうか。国の未来と民の生活を守るという「覚悟」の鍋を、二人には味わってもらいたいものです。
問題山積の野田政権
 参議院予算委員会にて管総理大臣の外国人献金問題、市民の会への献金について追及しました
参議院予算委員会にて管総理大臣の外国人献金問題、市民の会への献金について追及しました
菅内閣がようやく退陣し、野田内閣が誕生しました。前政権があまりにも酷かったため、その反動もあり、内閣発足直後の内閣支持率は、予想外に高いものでした。しかし、発足直後に鉢呂経産大臣が自身の不適切な発言により辞任するなど、大臣の適格性が疑われる人が数多くいます。その他にも新政権には問題が山積しています。
一番の問題が、鳩山、菅、両政権の反省を全くしていないということです。政権交代後、二年間で三人の総理が誕生したことは、民主党には政権担当能力がないということを証明していますが、その原因はマニフェストの破綻にあります。選挙前に彼らが言ってきたことが、ことごとく出鱈目であったということです。したがって、野田総理はまずこの問題について国民に謝罪すべきです。ところが、マニフェストの精神は間違っていなかったと未だに強弁しています。このことだけでも、解散総選挙をすべき事態なのです。にもかかわらず、復興が第一であり選挙をしている場合ではないと、震災対応を口実に国民に信を問うことから逃げています。
さらに先日、小沢一郎氏の元秘書三人が、三人とも政治資金規正法違反で有罪判決を受け、ゼネコンからの裏金まで裁判所に認定をされました。彼らが控訴したため、刑が確定するにはまだ時間がかかりますが、裁判所が判断を下したことは非常に重いことです。石川知裕衆議院議員の辞職勧告さえ民主党は拒否をしていますが、一般企業ならクビになって当然です。野党時代に、あれ程政治とカネの清潔さを強調していた民主党は何処に行ったのでしょうか。
小沢氏に限らず、鳩山由紀夫、菅直人という歴代民主党代表の政治とカネの問題も、未だにまともな説明がなされていません。また、前原氏が外国人献金で外務大臣を辞任されましたが、菅前総理や野田総理までも外国人から献金を受けていたことが発覚しました。これもまだ何の納得いく説明はされていません。この様に、歴代民主党政権が抱えてきた問題は何一つ解決していないのです。むしろ疑惑は増すばかりです。
ところが、これらの疑惑について、野田総理は何一つ積極的に解決をしようとしていません。党内融和を優先し、対立をさけるため、疑惑を隠蔽しているのです。歴代民主党政権の中でも、際立った非常識内閣であると言わざるを得ません。
 財政金融委員会にて管総理大臣(当時)の政治資金管理団体「草志会」収支報告書の虚偽報告について追及しました
財政金融委員会にて管総理大臣(当時)の政治資金管理団体「草志会」収支報告書の虚偽報告について追及しました
財務省言いなりの増税
質問にはまともに答えない野田総理が、唯一主張しているのが増税です。震災復興のための財源として増税を主張していますが、全くの出鱈目です。そもそも、復興財源は国債で賄うのが筋です。その理由は、巨額の復興費用を税で負担すれば、現役世代だけに過大な負担がのしかかり不公平になるからです。総理自らが千年に一度の大震災と言っておきながら、負担だけは現役世代にだけ求めるというのは全く矛盾しています。
さらに、税負担にこだわった結果、本来復興予算を計上すべきものがカットされ、十分な予算が組めていません。我々が再三要求してきた二重ローン対策などはその最たるものですし、インフラの復旧にはもっと多くの予算が必要です。
そもそも、十兆円規模の復興予算では少なすぎます。それを復興債という国債で賄っておきながら、十年間で返済するために増税するということ自体がナンセンスです。普通、建設国債は、公共施設の耐用年数を勘案して六十年で償還することになっています。千年に一度の大震災を考慮するなら償還年数を伸ばすことはあっても、それを短縮する理由などあるはずがありません。せめて、普通の公共事業並みの六十年償還にしておけば、増税の必要は全く無いのです。
にもかかわらず、十年償還にこだわるのは、震災復興を口実に増税への道筋をつけようとうる、財務省の悪知恵に乗らされているからなのです。
ところで、国債には建設国債と赤字国債があります。建設国債はインフラの整備をするための国債で、その発行に法的制限はありません。一方、赤字国債は、本来税で負担すべき経費を捻出するために特例的に認められたもので、発行には国会の承認が必要です。復興債は、被災地のインフラを整備する建設国債そのものです。インフラと言う財産も残すため、借金のつけ回しにはなりません。子ども手当のようなものに当てる赤字国債こそ、子孫への借金のつけ回しであり、問題にすべきなのです。
日本は絶対にギリシャにはならない
国債は国の借金だ。国債を増発して次世代につけを回してはならない、これ以上増やしたら、ギリシャのように財政が破綻してしまうと野田総理は言います。しかし、これは大間違いです。日本は絶対にギリシャにはなりません。
ギリシャと日本の決定的な違いは、通貨発行権の有無です。ギリシャは、EUに経済統合した結果、自国の通貨発行権を失ってしまいました。EUの中央銀行に加盟国の通貨発行権が委譲されたため、独自に通貨を発行して資金を調達することができません。その上、ドイツを始めとする外国に国債の多くを引き受けてもらっています。ギリシャが国債を償還するためには、増税をして国民からお金を吸い上げるか、政府支出を削減して資金を調達するしか方法が無いのです。正に、ギリシャの国債は文字通り国の借金なのです。
ところが、ギリシャと違い日本には、通貨発行権があります。また、日本の国債は95%が国内から調達されており、全て円建で発行されています。したがって、日銀が通貨を発行して国債を引き受ければ、国がデフォルト(支払い不能)になることは絶対に起きないのです。このことは、揺るぎない事実ですから、皆さんもご安心ください。
日銀協調による国債発行が日本を救う
では、日銀が引き受けてくれるなら、国債は無限に発行しても問題はないかと言えば、残念ながら少し問題があります。政府の資金を国債で賄い、政府支出を増やし続けると、民間におカネが流れ続け、貨幣価値が下がり、インフレになります。また、円の貨幣価値が下がるため円安になります。
しかし、考えてみて下さい。現下の問題はデフレと行き過ぎた円高だったはずです。日銀引受による国債発行は、この問題を一挙に解決してくれるのです。実際には、日銀の国債直接引受はできないため、日銀が既存債を民間銀行から買い、その資金で新規国債を民間銀行が引き受けることになります。民間の投資先が無いため、新規発行した国債は民間銀行が喜んで引き受けるでしょう。
そして、国債発行により調達した資金で国が被災地の震災復興のみならず、全国の防災、橋や上下水道などのインフラの更新など、必要な投資を前倒しで一挙に行えば、景気は間違いなく上向き、デフレから脱出できるのです。
増税の筋道を立てたい財務省
こうした状況にもかかわらず、野田総理が増税を主張するのは、財務省の思惑に乗せられているからです。今年の税収見積りは約41兆円で、昭和61年と同じ水準です。昭和61年のGDPは350兆円で今年が470兆円であることを考えると、税の負担率が低すぎることは明らかです。これは、この間に官から民へのスローガンの下、減税が繰り返されたからからです。官の支出を削減し民間に資金を提供すれば、より効率よく投資が進み、経済は発展するだろうという構造改革論がその背景にはありました。
しかし、民間に回した資金は、海外に投資されたり企業の内部留保になったり、国内投資には使われなかったため、GDPの伸びもバブル以後低下し続け、減税した分だけ税収が落ちたということです。構造改革は失敗だったのです。
こうした減税の失敗を修正したいと財務省が考えるのも当然です。しかし、デフレの状況下での増税はデフレの加速を招くため、あり得ません。そのことは彼らも百も承知のはずです。にもかかわらず彼らが増税を主張するのは、財務省にとっては税収確保が至上命題だからです。そこで、震災復興を名目に増税のシナリオを作り、野田総理に吹聴したのです。
この二十年間の構造改革路線による減税と公共事業の一方的削減が、日本をデフレに陥らせ、財政規律を悪化させた根本的原因なのです。このことは勿論自民党に責任があります。しかし、民主党は元々構造改革に反対だったはずです。それが今や、自民党時代以上にデフレ政策に邁進している姿は、滑稽ですらあります。結局、彼らは何も分かっていないのです。
野田売国政権の打倒
 高知自民党政経塾にて特別講師として講演をいたしました
高知自民党政経塾にて特別講師として講演をいたしました
野田総理は、TPPの交渉に参加することに意欲を示しています。TPPが売国そのものであることは、65号(ホームページをご参照下さい)で述べました。これは農業だけでなく、社会の制度がアメリカ化させられることであり、日本経済に壊滅的打撃を与えるでしょう。
普天間問題の迷走のつけや、トモダチ作戦の見返りにアメリカに何でも迎合すれば、日本は日本でなくなります。断固阻止をせねばなりません。皆様方のご支援をよろしくお願い申し上げます。
瓦の独り言
-本物である伝統工芸品-
羅城門の瓦の独り言
いまだ復興のきざしが見えない東日本大震災で被災された方々、お亡くなりなられた方々に哀悼の意を表します。
その被災地から、伝統産業に携わっている皆さんに嬉しい話が2つ届きました。一つは桐のタンスの話です。大津波に飲み込まれましたが、桐のタンスがしっかりと中の大切なきもの守ったという話です。外は泥だらけであったが、開けてみれば中の着物にはしみ一つ付いていなかったそうです。火事の際桐のタンスや金庫内の桐の箱は中のものを守ってくれる話を瓦は聞いていましたが、桐材が水にも強いことを再認識しました。文献によると桐材は湿度に敏感で、津波に飲み込まれた桐タンスの中は完全な密閉状態になって、中の大切なきものを守ったのでした。
二つ目は漆器の話です。被災地での食器に本漆の漆器にまさるものはなかったとか。飲み水さえままならぬ状況で、食後の後始末は布で拭いておくだけで十分だったとか。そういえば漆には抗菌作用があることを瓦は聞いた覚えがあります。永平寺の修行僧も食後の器はふきんで清拭きをしておくだけという話も納得がいきます。おそらく彼らも越前塗りを使っているのではないでしょうか。
これら二つの伝統工芸品は、100年以上受け継いできた技術、技能に培われた本物に他ならないからこのような嬉しい話が聞けたのです。伝統工芸の名を借りた、薄っぺらいまがい物では着物も守れず、被災地でも日常生活の器にはなり得なかったでしょう。これからの日本の生活用品の中には歴史と伝統に裏づけされた本物の伝統工芸品が必要となってくるのではないでしょうか? また震災後の混沌とした政治の舞台にも本物の政治家が必要である、と強く認識しているのは瓦、一人だけでしょうか?
そういえば、この原稿の下書きは、瓦が40年前にドイツのミュンヘンの百貨店で買い求めたモンブランの万年筆で書いています。書き味は変わらず、本物はいつまでたってもいいものですね。
最低限のモラルすらない

菅内閣が発足して1年が経ちますが、彼らはこの間何をしてきたのでしょうか。2年前、政権交代で鳩山政権が誕生しました。選挙の際、様々な事をマニフェストに掲げ、国民の高い期待の中で発足したにも関わらず、一月も経たないうちから躓き始めていました。普天間問題はその典型です。出鱈目発言を繰り返す鳩山総理でしたが、最後はその自らの発言の責任を取る形で辞任されました。ところが、菅総理にはこうした責任感すら持ち合わせていないようです。鳩山前総理がまともに見えるくらいです。
鳩山内閣の後をうけて、菅内閣が発足した当初、菅総理が訴えたのは、消費税増税でした。そして次は、TPP、税と社会保障の一体改革、大連立構想など、次から次へと思いつきの発言を繰り返し、どれをとっても何一つ成果は上がっていません。
菅総理の頭の中にあるのは、それらの政策の具体的中身ではなく、政権の支持率アップでしかないのです。自らの不用意な発言が、国民の不信を煽り支持率が低下する。すると、次の関心を引く課題を見つけて、何ら具体的検討もないうちに思いつきで発言する。この繰り返しの中で起こったのが、あの大震災だったのです。既に震災前の時点で政権は機能していなかったのです。
震災復旧、復興の遅れは民主党の政治主導にある
 西田昌司国政報告会2011を開催しました。
西田昌司国政報告会2011を開催しました。
当日は会場一杯にご参加を賜り、誠にありがとうございました
そんな中で、M9.0という未曾有の大震災が東日本を襲いました。本来、政権の担当能力が無い人に、震災対応が出来るはずもないのですが、野党である我々には、政治的対決を控え政府の対応を見守ること以外ありませんでした。しかし、結果は無惨なものでした。本来、震災復旧の仕事は行政府が主体的に行うものです。つまり、各省庁が、積極的に対応すべきものです。その中で、現行の法制では対応出来ない問題や、必要な予算については国会の中で議論が必要となるのです。政府と国会とはあるべき仕事が違うのです。
震災復旧が進まないことから、政治は一体何をやっているのだ、という発言をされる方がいます。確かに、気持ちとしては私も全く同感です。しかし、実際は違うのです。何故なら復旧の遅れの根本的原因は、行政の停滞にあるからです。そして、その原因は民主党の掲げる「政治主導」という愚策にあるのです。
行政府は本来、自律的組織です。つまり、大臣が居なくても機能を果たせる仕組みになっているのです。それぞれの部署で、必要な政策を自律的に行うことができるのです。そして大臣の判断を得なければならないものについてだけ、報告すればそれで良いのです。ところが民主党政権の下では、あらゆることを一々報告せねばなりません。これでは行政の停滞を招くのも当然です。
また、震災の対応も「責任は俺がとるから、必要な政策を思い切りやれ」、今までの自民党政権なら、そうしてきたでしょう。ところが、これが菅内閣では、「本当にそれでいいのか、失敗したら責任をとってもらうからな」ということになります。これでは役人は働けませんし、必要な情報も大臣に届きません。復旧の遅れは、民主党のこうした姿勢にあるのです。
震災復旧だけでなく列島強靭化が必要
今回の大震災の復興には、多額の資金が必要なのは誰の目にも明らかです。京都大学の藤井聡教授のお話によると、5年間で100兆円規模の予算が必要だとも言われています。また、これから日本列島のあらゆる地域で大地震が予想されています。特に、藤井教授の研究によると過去二千年間の東日本太平洋側のM8以上の地震4例中4例とも首都直下型地震と連動(10年以内)し、4例中3例が東海・南海・東南海地震と連動(18年以内)しているということが明らかになりました。これに早急に対応しないと日本国家の存続そのものが、危機にさらされることになります。これに備える為には、水道・電気・ガスなどのライフラインの強化、耐震化、更に高速道路や鉄道網の整備、インフラの早期更新など列島強靭化が必要です。これにも10年間で100兆円くらいの投資が必要です。合わせるとこの10年間で200兆円という莫大な資金が必要になるのです。
この資金の調達には国債発行しかありません。税で賄うには余りにも巨額すぎます。そもそも、今後100年の日本復興のための投資ですから、我々の世代だけで負担する必要はなく、将来の国民と一緒に負担すべきものなのです。ただでさえ、公債残高が多いのにこんなに巨額な国債を返済できるのか、孫子の世代は借金のつけ回しで大増税になるという人がいます。しかし、心配は無用です。ちゃんと返済できるのです。そればかりか、この巨額の公共投資が日本をデフレから救い出し、活力を与える起爆剤になるのです。
公務員給与削減はデフレを招く
菅総理は、公務員給与を3年間10パーセント削減することを提案しています。それを復旧財源に当てるということですから、賛成をされる人もいるでしょう。しかし、これはそういう世論を意識してのパフォーマンスなのです。そもそも、自衛隊始め、不眠不休で復興の現場で働く彼らの給与を削減すること自体筋違いです。また、いくら削減しても復興財源には、ほど遠い金額しか得られません。真の目的は、公務員にスト権などの労働三権を与えることであり、今回の措置は、その前段階である労働協約締結権(労使の話し合いで給与を決めること)を与えることと引き換えにした労働組合との裏取引なのです。
公務員には、職務の公益性のため労働三権がありせん。その代わりに、人事院が民間給与と比較をして給与が保証されています。この制度を無視して人事院勧告もない中、給与の減額をすること自体が法律違反です。また、労働協約締結権を付与すれば組合は圧倒的力を持つことになり、国家は解体の危機に瀕します。
更に、国家公務員の給与を削減すれば、地方公務員にも当然波及し、それに連動して最終的には民間の給与も下がるのは自明の理です。国民全体の給与が下がれば消費が低迷し、デフレが更に加速します。震災前から言われていた喫緊の課題は、デフレ脱却であったはずです。公務員給与削減は経済の破綻を招く致命傷になるのです。
財政再建はGDPの増加が絶対条件
財政再建には税収の増加が必要です。そのために絶対に必要なことは増税ではなくGDP(国内総生産)の増加なのです。例えば、皆さんが借金をして家を買ったとしましょう。月給が三十万円の人が、二千万円で三十年返済のローンで住宅を買ったとしましょう。残業手当が少なくなった程度なら、生活を切り詰めて返済をすることもできるでしょう。しかし、毎年給与が下がり出したら、もう返済はできません。そもそも毎年、給与が下がるという前提で、誰が住宅を買うでしょうか。消費が冷え切ってしまうため、借金返済ができないだけでなく、経済は大破綻をきたすでしょう。給与削減とはこういう結果をもたらすものなのです。
今すべきは給与削減ではなく、増やすことなのです。毎年給与が増えれば、住宅ローンも難なく返せます。同じく、毎年GDPが増えれば国債も十分返せるのです。200兆円の公共事業投資は間違いなく日本経済に活力を与えます。現在の500兆円を下回っているGDPも30年後には、1000兆円になることも可能です。すると、税金も現在の倍の100兆円の税収が毎年国庫に入れることも可能となり、国債の返済も問題なくできるのです。勿論、社会保障などのために税制の改革は必要ですが、今すべきことは先ずデフレ脱却をして、GDPを増やすことなのです。
延命のための反原発解散
 頑張れ日本!全国行動委員会京都府本部トーク・セッションに出席しました
頑張れ日本!全国行動委員会京都府本部トーク・セッションに出席しました
全てが出鱈目な菅総理には、流石に与党民主党からも退陣を要求する声が出始めました。しかし、内閣不信任案は、鳩山前総理によれば、菅総理のペテンにより否決されてしまいました。
今や、与野党問わず、菅総理を支持する人は殆どいなくなっています。そんな中、国会の会期が70日延長されました。当初自民、公明、民主の幹事長は50日の延長で合意していましたが、菅総理が70日にこだわり、八月末まで延長されることになったのです。20日間伸ばしてもお盆にかかり、実際の審議日数は大して増えないのに何故菅総理はこだわったのか。それは、自らの政権の延命だけで無く、反原発を旗印に解散をして、政権の起死回生を図るためなのです。
九月になれば、被災地で延期されてきた地方選挙も実施できることになります。選挙は解散後40日以内の実施ですから、八月末まで会期を伸ばすことにより、九月の地方選挙に合わせて解散することが可能となるのです。そして、反原発を争点にして選挙を行えば、イタリアでの選挙の様に自分も勝つことができる、そうすれば長期政権も可能だ。かつて、小泉総理が、郵政解散で勝利したことを念頭に、そんな夢みたいなことを考えているのでしょう。
国民を舐めるのもいい加減にしていただきたい。そもそも、今回の原子力災害は、菅総理の初動体制の間違いが大きな原因と指摘されています。さらに、全てを東電の責任に押し付け、政府が責任ある対応をしないことから、終息に時間がかかっているのです。こうしたことを横に置き、突然の浜岡原発の停止要請です。これが引き金となり、いずれ日本中の原発が止まることになるでしょう。反原発をして自然エネルギーに変えるのもいいですが、それには数十年はかかります。
その間のエネルギーはどうするのか、全く見通しがついていません。この夏も節電だけでどう乗り切れるのでしょう。電力不足で職や命を失う人も出てきているのです。これは全て菅総理の責任なのです。菅総理は、反原発の前に反パフォーマンスをすべきです。そして、全ての責任をとって政治家を辞めること以外取るべき道は無いのです
樋のひと雫
-ボリビア通信-
羅城門の樋
ラパスの街かどのカフェで二人の老夫人に声をかけられました。「日本は落ち着きましたか」「ええ、ありがとう。再建に向けて頑張っています。」と答えましたが、これで良いのだろうかと疑問もよぎりました。昨夜も首相が「1.5次補正予算」と言ったというニュースを目にしたところでした。この「1.5と2次」の違いは何だろうと思った時に、先ほどの婦人達がツナミに始まって「フクシマはどうなった、放射能は大丈夫、農作物は?」矢継ぎ早の質問をして来ました。少しうんざりしながら、「今の日本は、放射能よりもっと暗い霧で覆われていますよ」と言って、「しまった」と思いましたが後の祭りでした。怪訝な顔の二人に1時間、即興の図と手ぶりで日本の政局について講義をする羽目になりました。お陰でコーヒーは冷たくなり、もう一杯頼むことに。
説明していてふと気付きました。今の日本に政治はあるのかと。こちらでは「政治(politica)」即ち「統治(gobernar)」です。(政治状況situacion politicaという言葉はあっても、日本の政局とは少し事情が違います。)そのため、ガソリンの値段まで大統領令(decreto)で決まります(尤も、ストで2日後には取り消すこともありますが‥‥)。当然、良し悪しは別にして、国情の説明がマスコミを通してなされます。少なくとも国民に向けた説明と言葉の責任を負います。日本の首相のように「一定の目途」と言って、この期間を誤魔化すなどという姑息な「言葉の遊び」は見られません。
外から見ていると、今の日本には政治と政局の境界が見え難くなっているように思えます。「辞める」と言った人間と将来の枠組みや条約を話し合う国はないでしょう。統治能力を喪った首相が何を言っても、それは政策ではなく政局の言葉遊びにしか見えません。この災害が国難であるなら、日本の再生に向けた真の言葉=国策を提示することが統治者の責任であると思うのですが。空虚な言葉を投げ合うのではなく、日本の将来を討議する統治能力のある政治家の声が聞きたいものです。
被災地で分かったこと
 自民党参議院議員有志での被災地激励
自民党参議院議員有志での被災地激励
(宮城県内)
4月4日、私は、東日本大震災で被災された仙台地方にお見舞いに行き、そこで現地のJAの役員の方や避難所の被災者の方、そして仙台市長にもお話を伺ってまいりました。阿武隈川の河口に近い宮城県亘理町から仙台市の若林区まで、いずれの地域も大津波の爪痕がすさまじく、言葉を失ってしまいます。
家族も仕事も財産も失った避難所の方々のお話を聞くにつけ、今までの制度では対処のしようのない未曾有の大惨事なのだということをつくづく思い知られました。だからこそ、その仕組みを変える政治の力が必要なのです。
復興には多額の資金が必要、子ども手当は止めるべき
被災地の報道がされるたび、多くの国民が心を痛めてきました。なにか自分に出来ることはないか、少しでも支援をしたいと、義援金も短期間のうちに二千億円近いお金が集まっていると聞きます。しかし、復興のためにはその何十倍もの資金が必要になります。そのことを考えると、まず、不要不急の子ども手当などのばらまき4K政策(子ども手当、農家の戸別補償、高速道路無料化、高校無償化)は直ちに止め、復興資金に回すべきです。これだけで約3兆円の資金が捻出されるのです。
こうした我々の主張にもかかわらず、去る3月31日、参議院本会議で民主党などの賛成により子ども手当は6ヶ月延長されてしまったのです。全く愚かなことです。
災害から命を守るインフラの整備が必要
 統一地方選挙にて
統一地方選挙にて
自民党公認候補者を激励しました
仙台市の若林区を視察した時、不思議な光景を見ました。全域大津波で農地も住宅も流されているのに、ある特定の地域だけは無害ですんでいるのです。その境目となったのが、この地区を南北に走る仙台東部有料道路という高速道路だったのです。
この道路は盛り土の上に建設されており、それが堤防の役目を果たしていたのです。そのため、ここより東の海沿いの地域は津波で壊滅状態であるにも関わらず、西側の地域では殆ど被害がなかったのです。
仙台地区は昔から大津波の被害が言い伝えられ、貞観大津波(西暦869年)では仙台平野は見渡す限りの大海原になったと言われています。その時に、津波が襲ってきた陸地との境目が浪分神社として伝わっています。今回の地震はその時の地震(M8.3~8.6)より大きなものだと言われていますが、この高速道路のお陰で、浪分神社付近は無傷だったのです。
リアス式海岸と違い、なだらかな海岸線の地域では津波は何十メートルにはならず、防波堤が有効だということです。堤防をきちんと整備するか、こうした盛り土式の高速道路を利用して、そこより陸側にしか住宅を建てさせないという規制があれば、田畑は流れても住宅は守れるのです。つまり、仙台平野ではインフラと都市計画をきちんとすれば、今回のような大津波でも人の命を守ることはできるということです。
民主党は、「コンクリートから人へ」と公共事業などのインフラ整備を、その中でも防災や耐震化の予算までも削減をしてきましたが、こうした政策が間違いであったことは誰の目にも明らかでしょう。しかし、これもいまだに彼らは認めようとしません。
福島原発は人災ではなかったのか
今回の震災を悲惨なものにしたもう一つの原因は、福島原発の放射能漏れでしょう。こうした種類の原発事故は過去に例がなく、政府の対応を一概に責めることはできない、むしろその責任の一端は長く政権与党をしていた自民党にもあると私は思います。そのため、その対応については慎重に見守ってきたつもりです。しかし、震災からひと月近くなり、政府の対応の実態が明らかになるにつれ、民主党菅政権の初動ミスがもたらしたものであることが判明してきました。
福島原発は、地震や津波で爆発したのではありません。その後の初動体制の誤りが引き起こしたものです。11日の午後2時46分の地震直後、緊急炉心停止を自動的に行い核分裂は止まりました。地震直後に停電になりましたが、非常用のディーゼル発電により冷却も無事行なわれました。1時間後に大津波で全電源喪失になりましたが、バッテリーで8時間冷やし続けたので午後10時半までは安全な状態だったのです。
問題はこの8時間の間に、新たな電源が用意できなかったことと、その場合には海水投入しか手がないにもかかわらず、その処置が遅れたことです。特に、最後の手段である海水投入には、その前提として炉内の圧力を下げるため、ベントと呼ばれる蒸気排出が不可避です。ところが、この処置がバッテリー枯渇後12時間以上かかったことが、爆発に至る致命傷になったと言われています。そして、その原因が菅総理の原発への乗り込みの強行によるものではないかと疑われているのです。この事実関係は、今後国会を通じて明らかにしなければなりません。
しかし、いずれにしても菅総理は原発に行く必要がなかったのです。ベントが遅れたことが仮に東電側の事情によるものであっても、放射能の被ばくのリスクを冒してまで、国家の最高責任者が出向くこと自体が危機管理としてもあり得ません。
復興の予算は建設国債で賄える デフレ脱却のチャンス
震災からの復旧復興には莫大な予算がかかりますが、その財源には建設国債で十分賄えます。震災直後にドル円相場が急騰し76円台を記録しましたが、これは大災害にもかかわらず日本の経済に対する信頼が依然として高いことを物語っています。日本は世界一の債権国です。この震災前に民間銀行の預金超過額が150兆円以上あり、海外からの資金援助を受けずとも自国の資金で十分賄えます。もともと、民間投資が少なかったことが、預金超過を生み、デフレをもたらしていた原因だったのですから、巨額の公共投資が今後発生することにより、需給バランスが改善されデフレ脱却が可能になるでしょう。
また、この震災復興には民間でも資金がかなり必要となりますから、その分金融がひっ迫することが考えられます。そこで、日銀が資金需要を見定めながら民間金融機関が持つ既存国債を市場から買い取ることにより資金を供給し、金利の上昇を抑えることが必要です。そのためには必要ならば日銀券を追加で発行することも必要でしょう。このように日銀が協調すれば国と民間の資金需要が賄うことができ、震災復興もデフレ脱却も同時に行うことが可能となるのです。
復興資金を増税によって賄うという案は、震災復興の足を引っ張ることになり反対です。復興が進み、景気が過熱し、物価や金利が上昇する傾向になってきたら、国債発行を抑え増税を考えれば良いのであって、順序が違うのです。日銀との協調をすれば増税しなくても資金は十分に調達できるのです。
エネルギー政策の見直しが必要
むしろ、心配すべきは電力不足のほうです。復興需要が急増しても、電力不足により生産が追いつかなくては需給バランスが崩れ物価が上昇します。しかし、これは経済成長によるものではなく、スタグフレーションと呼ばれる景気後退現象ですから警戒しなければなりません。
日本には休止中の火力発電所が多数あります。西日本と東日本の周波数の違いがなければ、これを再稼働させれば、電力需要は賄えるとも言われています。今までは、ランニングコストの安さとCO2の削減のため、原発の稼働率が高められてきたのです。しかし、震災後は当然見直しが必要となります。また、エネルギー、特に電力を湯水のように使うことは最早許されないでしょう。国民一人ひとりが、ライフスタイルの見直しをしなければなりませんし、民主党が唐突に打ち出したCO2の25%削減という公約の撤回は当然です。
日本を救うには政権奪還以外ない
3月11日以降は震災による政治休戦となり、国会においても殆ど議論ができなくなりました。政治的な対立より挙国一致で震災からの復旧復興に当たるべきだ、そのためには大連立をすべきだという声も聞かれます。もちろん復興に協力するのは当然です。しかし、そのためには民主党の政策の誤りを指摘せざるを得ません。ところが、彼らはいまだにその誤りを認めていないのです。
日本を震災から復興させ、原発事故を終息させるためにも、民主党から政権を奪い返すしかないのです。今回の統一地方選は国民のそうした意識の表れでしょう。
今こそ、日本人の精神を取り戻そう
 財政金融委員会にて野田財務大臣・
財政金融委員会にて野田財務大臣・
白川日銀総裁・自見金融担当大臣に対して、
震災対応の予算について質問しました
今回の震災では、今まで当たり前と思っていたことがことごとく崩れ去りました。 安全も繁栄も永久に続くと思っていたことが、砂上の楼閣に過ぎないことをまざまざと見せつけられました。自然の猛威に怯え、未来に対して希望を見出すことができず、立ちすくんでいる人もいます。
しかし、こうした大震災に我々の先人は何度も襲われてきたのです。そして、その度に立ち上がり復興をしてきたのです。従って、我々にそれができないはずがありません。恐らく、これからもこうした震災に何度も襲われることになるでしょう。それでも、その度に立ち上がる以外ないのです。それとも、この国を棄てて、何処かに移民すべきでしょうか。それはできない選択です。私たちが日本人である限りこの国とともに生きるしかないのです。この国の国土がもたらした恵みも災厄も全てを受け容れることにより、先人は日本人の精神を鍛え育んできました。
無常観もその一つでしょう。『‥奢れるひとも久しからず、ただ春の夜の夢のごとし‥』平家物語の一節が頭に浮かびます。物質的な繁栄や地位や名誉など、自然の猛威の前では何の意味もない。与えられた環境の中で謙虚に素直に一生懸命に生きる以外ない。それこそが日本人が大切にしてきた心ではないでしょうか。その心がある限り、日本は何度でも復活することができるのです。
瓦の独り言
-震災後の日本文化羅生門の瓦の精神復興は京都から-
羅生門の瓦
東日本大震災の影響で、国の重要無形文化財「相馬野馬追」の開催が危ぶまれています。舞台となる福島県の相馬地方が被災し、多くの「騎馬武者」が愛馬を失い、また武者の中にはいまだ行方不明者もおられるとか。1000年の歴史を誇り、江戸時代の大飢饉、大東亜戦争中でも規模や形を変えて続けられてきました。「一騎になろうとも、伝統を守ることが地域復興への貢献」とくつわを並べて出陣の策を練っておられます。
また、国の伝統的工芸品である福島県の大堀相馬焼(陶磁器)、宮城県石巻市の雄勝硯(文具:硯)の2つの産地が大きな被害を受けておられます。(この2つの産地に対して(財)京都伝統産業交流センターの理事会から義援金送ることになりました) 中でも雄勝硯を作っておられる4名の伝統工芸士さんは家も、道具も失われました。しかし、伝統工芸は手仕事が主で、道具と原料が在れば必ず再興できると、生産に意欲を燃やしておられるとか。
しかし、「着倒れのまち」京都市内では西陣織、京友禅をはじめとした伝統工芸品にも自粛という悪いムード(瓦一人が思っているだけかも?)が漂い始めています。確かに「きもの」は震災にあわれた方々にとって当面は不要の品物かもしれませんが、復興のあかつきには「日本人の誇りである着物をもう一度着たい」という思いは持っておられるはずです。そのときに日本の伝統文化のメッカである京都が沈んでいたらどうするのですか!伝統工芸品の「ものつくり」が出来ていなければ、どうするのですか!お茶やお花の家元がある京都市の街全体が沈んでいていいのでしょうか?祇園祭をはじめとする京都の3大祭りを凛として行うのが京都市民の務めではないでしょうか
結びになりますが、日本の精神文化を支えているのは京都であることを自負し、伝統工芸品を生産されている方々は当面、非常に厳しい状況が続くと思われますが、歯をくいしばり「ものつくり」に邁進してもらいたい、と思っているのは瓦一人だけではないと思っております。
またもや始まった内紛
 参議院本会議にて仙谷官房長官に対する
参議院本会議にて仙谷官房長官に対する
問責決議案の賛成討論をいたしました
民主党政権が発足して一年余りが経ちます。昨年6月の鳩山総理の突然の辞任により誕生した菅政権ですが、誕生からまだ半年余りにもかかわらず既に崩壊が始まっています。小沢さんを標的にすることで国民の支持を取り戻そうとしているようですが、これはパフォーマンス以外の何ものでもありません。現に、私は1年以上も前からこの問題を追及してきましたが、当時民主党はこれを全く無視していたのです。今回の内紛劇は、まさに民主党の正体を表していると思います。つまり、民主党の目的とは、自民党を倒して政権交代をすることだけであり、そこに政治理念などほとんど無いのです。要するに、アンチ自民に過ぎないわけです。
小沢待望論はカン違い
 参議院内閣委員会にて
参議院内閣委員会にて
岡崎トミ子国家公安委員長に対して
質問しました
政治とカネの問題があるにも関わらず、小沢さんに期待する人もいるようです。小沢さんは、この20年間ずっと政局の中心にいた人です。そのイメージは、破壊者であり、それがイコール改革者なのだと言われてきたのです。しかし、その政治手法は、師匠である田中角栄そして金丸信という方々と同じで、カネと数によって力をつけていくという古いタイプの政治家です。それでも、政治というのはしょせんパワーゲームなのだから、力のある政治家が出て来てくれないと今のこの時代は乗り切れないという意見もあり、それが小沢さんに期待したり擁護したりする一番大きな理由なのでしょう。問題はその力をどういう方向に、何のために使うのかということです。残念ながら菅さんや鳩山さん同様、小沢さんもまったく中身がありません。ただ今あるものを潰せばいい、自民党がやってきたことを潰せばいい、ただそれだけなのです。現に小沢さんが主導してきた改革は全て失敗しました。カネのかからない政治と政権交代可能な仕組みとして、彼自身が主張してきた小選挙区制導入による政治改革の結果、民主党政権が誕生したのですが、その張本人が相変わらずカネまみれであることはまさに喜劇です。
昭和と平成の違い
大事なことは現状認識です。戦後の昭和は、社会資本が破壊された貧しい時代から始まりました。敗戦により事実上軍隊を放棄させられた代わりに、政府は経済再生に集中して予算を計上していくことが出来たのです。人口も戦後のベビーブームで増えて行きます。そのお陰で毎年、経済は成長しますから、必要な税金も自然に増え続けたのです。政府に必要な税は、経済が成長することによって賄うことができたのです。つまり、右肩上がりが当たり前というのが昭和だったのです。
ところが平成になった途端、この仕組みが破綻してしまったのです。その一番の原因は、人口構造が変わってきたということです。昭和の時代は人口がどんどん伸びてきましたが、平成の時代には少子化と高齢化が重なり、経済成長が当たり前ではない時代がやってきたのです。これは、先進国が抱える共通の問題なのです。先進国になると人口は伸びなくなり、成長は止まるのです。唯一の例外は移民により人口が伸び続けるアメリカだけなのです。
しかし、日本を移民国家にする訳にはいきません。また、移民国家のアメリカは、白人より有色人種の人口が増え、国家の形自体が変質して行くという根本的な問題を抱えています。
人口問題だけではなく、もう一つの大きな違いは、平成に入り隣に中国という巨大な国が出現したということです。
人口構造の変化と、中国をはじめとする後進国が巨大な市場となり、巨大な製造拠点となったことによって、産業の空洞化が始まっているのです。日本で物を作るよりも中国で同じ物をもっと安く作れるのでは、日本の国内の製造業は太刀打ち出来ません。従って規制緩和をすればするほど企業は競争を勝ち抜くために中国などの安い労働市場に工場を建てることになり、国内の空洞化はますます進むのです。
また、巨大な中国の出現は経済だけでなく軍事的な脅威になっているのです。経済力が増大したことにより中国は軍事力も増大させ、日本近海においても領土的野心をはっきりと示すようになりました。尖閣問題はその表れです。今までの軽武装路線では国を守ることが出来なくなっています。これも昭和との大きな違いです。
デフレの脱却と自主防衛
中国の出現により日本は産業の空洞化が起き、大学を卒業しても就職出来ない人が半数近くいるという空前の就職氷河期を迎えています。また、安い中国製品の増大が物価を押し下げ、その結果、給料も下降し、消費が低迷するデフレ社会に突入しています。これでは、経済は悪循環になるばかりで、人々の生活は成り立たなくなります。
この現状を抜け出すには、まず政府が率先して仕事を作り出すための予算を計上する必要があります。中国などへの工場進出を止めるためにも道路網を整備して、国内に工場を建設出来る環境を作ることが必要です。しかし、民主党にはこういう認識がなく、いまだに公共事業を削減するばかりです。
また、中国の軍事的脅威に備えるにも防衛費の増強は不可欠です。しかし、この認識も彼らにはありません。むしろ、中国やロシアの脅威からアメリカに守ってもらうため、唐突に環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)への参加を叫び始めました。
TPPは売国そのもの
TPPの意図は、環太平洋諸国で関税を撤廃して自由貿易体制を作るということですが、日本には何の利益もないものです。まず第一に、TPPに参加しても日本の輸出は増えません。そもそも、TPP参加国は小国ばかりで、日米のGDPがその中の90%以上を占めています。民主党はアジアの成長を取り入れるために必要なのだと主張していますが、日本製品を購入するだけの経済力がある中国や韓国はTPPには参加していないのです。つまり、日本の製品を買ってくれるのは事実上アメリカしかいないということです。そして、そのアメリカがTPPへの参加を要求しているのは、日本の製品を安く買うためではなく、アメリカの農産物を日本へ輸出するためなのです。また、仮にアメリカとの関税が撤廃されても為替操作により、ドル安円高に誘導すれば日本製品の価格は値上がりしてしまい、輸出の増大は期待できません。さらに、輸出の花形である自動車などは、既にアメリカでの現地生産が進んでおり、ホンダなどではその80%が現地生産をしています。従って、関税を撤廃しても殆ど輸出の増大は期待できないのです。逆に、関税が撤廃されればアメリカから安い農産物が輸入され、日本の農業は壊滅的打撃を受けるのは必定です。
では何故、こうしたTPPを民主党は主張しているのか。それは、普天間問題と尖閣問題の失政を隠すためです。普天間問題で民主党はアメリカとの信頼関係を完全に失いました。日米関係がぎくしゃくし、日本の安全保障に隙を見つけた中国が、この時とばかり仕掛けたのが尖閣問題です。今なら尖閣諸島を力づくで奪うことは可能だと、大量の中国漁船が押し寄せたのです。案の定、中国漁船の船長を逮捕しても中国の圧力に屈して、民主党政府は中国漁船の船長を釈放してしまいました。そして、このままでは中国に対抗できないと思い、アメリカにすがりつくしかないと考えたのです。
しかし、普天間問題でアメリカとの信頼関係は地に落ちています。そこで民主党が持ち出したのが、TPPです。アメリカの要求に一方的に応じるだけで、日本には利益がないにも関わらず、藁にもすがる思いで飛びついたのです。
これは国内市場をアメリカに売り渡す売国政策そのものです。彼らは自らの失政を棚上げして開国か鎖国かと叫んでいますが、全く愚かなことです。
明治維新の意味
 12月7~15日まで
12月7~15日まで
ODA調査会派遣で
ベトナム・ラオス・カンボジアを訪問しました。
写真はビエンチャンにて、
NGO「ラオスのこども(草の根)」視察の様子です
そもそも、明治維新により開国した理由は自国を守るだけの軍事力が無かったためです。鎖国により外国との交渉を遮断したが故に、侍というのは結局、軍人ではなく警察官としての力しか持たなくなった訳です。外国の脅威から守るだけの力が無かったが故に開国せざるを得なかったのです。開国は、兵力を賄うための経済力増強のための手段だったのです。つまり、富国強兵ということです。
明治以降は、外国から国を守るということが政治の最大の使命であったのです。このことが、戦後忘れ去られ、経済成長だけが政治の課題かのように言われて来たのです。
しかし、今や平成の時代になり、巨大な中国の出現により、それはもう通用しないことが明らかになったのです。中国に備えるためには、自主防衛は当然のことであり、デフレ脱却のためには財政支出こそ今一番必要な政策なのです。
日本は、年末・年始、そして統一地方選挙に向けて、政局は大きく揺れ動くことでしょう。民主党の内紛が一つのきっかけになるわけです。
しかし、彼らの内紛からは何も生み出されません。大切なのは、歴史的に大きな視点から現状の問題を見据えることです。改革のための改革ではなく、日本に誇りと自信を取り戻し、次世代でも日本は世界の中でしっかりと自立していける国の仕組みを作ることです。そのためには、先ず自主防衛を国是とすることです。そしてデフレを脱却し、経済を再生するためには、民間任せではなく、政府が責任をもって財政出動をすべきなのです。
今後とも皆様方のご支援よろしくお願い致します。
瓦の独り言
-自然から学ぼう-
羅城門の瓦
平成22年の漢字は「暑」だったことはご存知と思います。昨年の夏は本当に暑かった。9月、10月になっても夏日が続いており、秋が無くって冬になったような気がします。そういえば昨年は春も無かったような・・・。
こんな天候不順の中で、瓦は米作りに挑戦しました。真冬並みの寒さの中で田植えをしてもらいました。(お金を払えば機械で、農業団体がやってくれます。)。無農薬栽培を目指しての真夏の草取り、我田引水を目のあたりにして自分の田圃(たんぼ)への水の確保に四苦八苦しました。そのころNHKのBS「ウルトラアイ」で田圃の四季を放映しており、それと見比べながらの米作りです。全くの素人で、教科書も無ければ、誰かに弟子入りして教えてもらったわけでもありません。わからなければ、隣の田圃のお爺さんに教えてもらうのが積の山です。(過疎と高齢化が進み、普段でも人に会わない山村で、相談相手を探すのも大変。)実践あるのみ! 刈取りもコンバインなる機械を使わず、自力で簡易バインダーを使って刈取りを行い、稲木での天日干しを行いました。その間、山里の鹿さんとの戦いでは、敗戦で結局はネットを破られて、新米を横取りされました。でも「キヌヒカリ」という美味しいお米が1反から6俵(60?/俵)取れました。豊作でしたら10俵、並作でも8俵ですが、瓦は満足しています。だって、教科書も無く、見様見真似で、自然の摂理にかなうようにしての結果です。汗と涙の結晶で、お米がまずい訳がありません。
イタリアのルネッサンスの人であるレオナルド・ダビンチが「自然から学ばずに、書物の著者から自然を学ぼうとする者は、自然の子ではなく、自然の孫にしかなれない」という名言を残しています。哲学的な内容と次元が違いますが、瓦は米作りから自然を学んだような気がします。週末になれば、田圃のアゼに立ち、稲と対話をしてきました。偉そうな言い方になりますが、農業の実践から自然というものを学んだような気がします。昨年の末、どこかの首相は「行」という漢字を選んでいましたが、何もしていない「有言不実行(?)」の内閣を率いている方が「行」という漢字を振り回すのに疑問を抱いているのは瓦だけではないはずです。今の為政者の方はもっと自然から森羅万象を学びとっては・・・・。
我らの西田昌司参議院議員は「伝えよう、美しい精神(こころ)と自然(こころ)」と唱え、実践しています。
【上記のレオナルド・ダビンチの言葉は元京都大学総長、元京都市産業技術研究所所長の西島安則先生に教えていただきました。】
民主党が招いた尖閣問題
 参議院予算委員会にて質問の様子(8月4日)
参議院予算委員会にて質問の様子(8月4日)
那覇地検は逮捕していた中国人船長を処分保留のまま釈放し、「日中関係を考慮すれば身柄の拘束を継続して捜査を続けることは相当でない」とする異例の記者発表を出しました。
検察の仕事は、法と証拠に基づき容疑者を起訴することです。そこに外交的判断が紛れ込む余地はありません。私は今回の事件では、指揮権の発動が事実上あったと思います。むしろ積極的に指揮権を発動しても良かったと思っているくらいです。中国で拘留されている4人の邦人の解放と引き換えならば、政治的判断として当然あり得る話ではなかったでしょうか。もちろん、その責任は政府が負わねばなりませんが、外交交渉としてはあり得たはずです。
ところが、このようなことが全く考慮されることなく、検察独自の判断で船長を釈放したというのならば、民主党政府は外交を放棄していると言わざるを得ません。中国の強硬姿勢に押され、4人の解放の糸口を何もつかめぬうちに船長を釈放するというのではお話になりません。しかもその責任を一地方検事に押しつけるとは言語道断です。
案の定、その弱腰で卑怯な姿を中国側は見逃さず、船長が釈放されたら更に謝罪と賠償を求めるという暴挙に出たのです。船長を釈放さえすれば丸く収まるだろうという民主党政権の甘い考えは、中国を増長させるだけの結果に終わったのです。
伏線その1 小沢訪中団
 西田昌司国政報告会を開催しました
西田昌司国政報告会を開催しました
(於シルクホール9月17日)
会場一杯の皆様にご来場いただきまして
誠にありがとうございました
昨年12月、民主党の小沢幹事長(当時)は、600人を超える大訪中団を率い訪中しました。国会議員も140人を超え、一人ひとりが胡錦涛国家主席と握手をするなど、まさに朝貢外交さながらのその様子をご記憶の方も多いでしょう。菅総理でなく、小沢総理なら今日の事態は避けられたのではという人もいますが、それは間違いです。というのも、こうした対中朝貢外交が、中国に誤ったメッセ-ジを与えているからです。実際、その答礼に訪日した習近平副主席に対して、いわゆる一ヶ月ルールを破ってまで天皇陛下への謁見を宮内庁に要請したことからも分かる様に、中国からの要求には何でも応じるという姿勢を示したのは小沢さん自身なのです。これが、中国の増長に拍車をかけたのは間違いないでしょう。
伏線その2 日米中正三角形の鳩山外交
政権交代後、鳩山総理(当時)は東アジア共同体論を展開し、日米中が正三角形のように対等に協力し合う関係を目指す旨の外交姿勢を強調しました。
これは麻生内閣の「自由と繁栄の弧」と似て非なるものです。麻生政権では日米関係が主軸であり、アジア外交においても自由主義という価値観を共有できる国々が協力し合うべきだという姿勢を示し、事実上の対中封じ込め外交を基本政策としたのでした。これは、この20年にわたる中国の軍事力の増強に対する日本の警戒感の表れでもあったのです。
ところが、鳩山政権では対中無防備外交を展開し、対中追従姿勢を繰り返し表明してきました。これでは中国が増長するのも無理からぬことです。
伏線3 普天間の問題
さらに今日の事件を決定づけたのが、例の普天間問題です。普天間基地を何ら代替案のないまま「出来れば国外、最低でも県外」に移転すると明言したものの、迷走の果てに、自民党と同じ辺野古に決定とはまさに愚か者です。沖縄や米国との信頼関係は著しく損なわれ、今や米国内には対日不信が大きく蔓延しているのです。
せめて、防衛力を増強すればいいものを、自衛隊ですら事業仕分けの対象にするような姿勢では、日本の安全保障は風前の灯です。普天間問題でのデタラメな対応が、今回の事件の決定打となったのです。
ところが、こうした事態を招いた張本人である鳩山総理にはその責任を感じている様子が全く見られません。それどころか菅総理の対応を批判し、「自分ならもっと上手くやれた」と言い出す始末です。民主党の首脳は誰一人として当事者意識を持ってないということです。
無責任で不見識な人間が政権をとるとどうなるのか、そこにあるのは国家崩壊以外ありません。今、まさに日本は国家崩壊の危機にあるのです。
事業仕分けの前にデフレを止めろ
国家崩壊の危機的状況にあるのは、安全保障上のことだけではありません。国民生活の屋体骨である経済や財政も大変な状態です。無駄を排除して財政再建をする、その目玉として、事業仕分けをまた行うつもりのようですが、これは全くの見当違いです。
そもそも、今回の事業仕分けをする事業自体が、民主党政権が必要と認めたものでしょう。それを仕分けすること自体、論理的に矛盾します。それでも百歩譲って、事業の成果を見てさらなる効率化をはかる、というならばそれも良し。しかし、それにより一体いくらの予算が削減されるのでしょうか。政権交代の時でさえ、事業仕分けで何兆円もの予算の財源が出ると言いながら、実際には数千億円でした。しかもそれは、学校の耐震工事など本当は必要な予算まで無理矢理削って作り出した虚構です。事業仕分けというパフォーマンスばかり考えずにまず、現下の経済情勢を正確に理解してくれなくては困ります。
デフレというのは、インフレに対することばです。インフレは物価が上がることを意味しますが、デフレは物価の下落を示す経済用語です。
消費者の立場からすると、物価は上がるより下がる方が好ましいと考えることが出来ますが、一国の経済全体で考えたとき、デフレはインフレ以上に悪い最悪のものなのです。
デフレでは経済活動は破綻する
経済活動を考えてみましょう。材料を仕入れてそれを売る、これが商売の基本です。100円のものを200円で売ることが出来るから商売が成り立つのです。これがデフレになると、物価が下がりますから100円で仕入れたものを50円で売ることになります。これでは、商売が成り立ちません。今日より明日の方が安くなるという物価下落に歯止めをかけないと、誰もものを買わなくなります。するとこれが益々物価を押し下げます。こうなるとブラックホールに吸い込まれたも同じで、正常な経済活動が出来なくなるのです。
最初は物価が下がって喜んでいた消費者も、いずれ自分の給料を払ってくれる会社がデフレにより事業が成立せず、破綻をし、失業という憂き目にあって初めて、デフレの恐ろしさに気が付くのです。つまり、デフレとは、経済活動そのものを殺してしまう恐ろしい病気なのです。
財政の再建ももちろん大切なことですが、国民生活の根本である経済活動が破綻しては、再建の仕様がありません。財政再建以前にまずやるべき事は、デフレを止めることなのです。これを国民共通の理解にしておかないととんでもない間違いをすることになります。
実は、戦後日本においては、基本的にインフレがずっと続いていたのです。つまり経済発展に伴って物価も上がってきたのです。もちろん給料もその分上がってきました。インフレがあまりに過ぎると狂乱物価になり国民生活に悪い影響を与えることから、政府の政策としてはこれを抑制することが、まず第一に行われてきたのです。まさにインフレ対策が経済政策だと思われてきたのです。日本では、戦後デフレに陥ったことは事実上一度もなく、デフレ対策についての知識が政府にもマスコミにもないのです。これが誤った経済政策を進める原因になっています。
デフレ時にインフレ対策を行う愚
民主党の唱える事業仕分けや無駄削減、コンクリートから人へなどは、インフレ対策の典型例であり、後世必ず失策として批判の対象になることは間違いありません。
これらの対策は、インフレの時には有効であるかもしれません。それは政府予算を削減し、過熱する経済活動を抑えるものだからです。しかしそれを景気が悪く民間投資が滞っているときに行うというのは全く間違いであり、経済音痴であると言わざるを得ません。
公的需要を掘り起こせ
民間需要が落ち込んでいる今、まず第一にすべきことは公的需要による経済再生です。たとえば、学校などの耐震化は待ったなしで必要です。これらの事業を前倒しで行うべきです。水害を防ぐためにはダムも必要でしょう。また、橋なども完成後40~50年経つと架け替えをしなければなりません。これを放置すると大災害につながります。また地中に埋めてある上下水道管などのライフラインも取り替えの時期にきています。こうした社会資本の更新だけでも少なくとも100兆円以上の予算が必要なのです。そうした将来必ず必要な事業(公需)を民需の落ち込んだ今こそ、積極的に前倒して行うことが、デフレ対策としては最適なのです。この財源は子ども手当のようなバラマキをやめるだけで、毎年5兆円以上が生み出されるのです。
国民生活より政権の延命が大事な民主党
 自民党京都府連定期大会において、
自民党京都府連定期大会において、
来春の統一地方選挙公認候補者43名を発表しました
ところが、この当たり前のことが民主党には分からないのです。そもそも、経済政策も外交政策も幼稚な知識と経験しかないため、国家全体のことが全く彼らには見えていないのです。しかも、政府与党として、自らが全ての責任を取らねば成らないという自覚が未だにありません。
まさに国民の生活、国家の安全より自分のことが第一なのです。彼ら民主党政権こそ国民の敵なのです。日本再建のためには彼らを倒す以外ないのです。
樋のひと雫
羅生門の樋
先の民主党代表選であるマスコミが「資質なき者と資格なき者との戦い」と評していたのが印象的でした。片や「市民政治家」一方は「剛腕政治家」。しかし、これらはイメージでしかありません。その剛腕の中身は何でしょう。その市民活動出身の中身は何でしょう。民主党が政権を取った時、彼らは副総理であり幹事長でした。あの宇宙人総理が普天間基地の問題で「県外だ、国外だ」とマスコミを賑わしていた時、彼らは一度もその問題に触れた発言をしていません。「火中の栗は拾わず」が心情の権勢追求の政治家が、その姿であったのかも知れません。
思えばあの時、政権交代という機を生かし、新しい日本の一歩を築くチャンスだったのかも知れません。秘かな期待もありました。アメリカ合衆国から見た「米日同盟」ではなく、日本から見た「日米同盟」への転換を図るという意味で。
あの時、論議すべきは「基地問題」ではなく、日本の防衛の在り方を根本的に見直し、国民的論議をする大きな機会だったと思います。沖縄はアメリカの地政学では、対中国とりわけ、台湾海峡を巡るアジアの安定や東アジア情勢を安定化する意味で大いに重要な位置にあるでしょう。しかし、現在の日本の地政学的意味からすればどうでしょう。昨今の尖閣諸島の問題、朝鮮問題やシーレーンの確保といった問題からすれば、また、専守自主防衛という観点からすれば、どうでしょう。中国が航空母艦を中心とした外洋艦隊を持つ時代になりました。隣国が沿岸防衛から外洋覇権を窺う時代になったのです。我々の国防にも変化があって当然です。
日本人を拉致した北朝鮮の人間の嘆願書を書くような市民活動家の心情では、一国の国防を論議する覚悟を期待するのは無理でしょう。また、尖閣諸島は領土問題だと発言するような仕分け大臣には、台湾を守っても日本を防衛する気も無いでしょう。そう言えば、マニフェストには外国人に地方参政権を与えるという話が載っていました。山陰や北陸に集団移住し、彼らの市や町が誕生した時、果たして日本はどの国から見た「地政学的意味」を持つことになるのでしょう。
不可解なV字回復

鳩山内閣が突然政権を投げ出し、菅内閣が発足致しました。鳩山内閣では2割を切るほどに低迷していた支持率も6割を超えるV字回復を果たしています。しかし、鳩山内閣が抱えていた問題は何一つ解決していません。文字通り表紙の挿げ替えに過ぎない菅内閣が何故これほど評価をされているのでしょうか。実はここに、現代日本において政治そのものが崩壊していることが象徴されているのです。
マニフェスト政治の出鱈目
そもそも昨年の政権交代は一体何だったのでしょう。民主党は自ら示したマニフェスト(政権公約)が国民に評価されたと言っていましたが、そのマニフェスト自体が全く出鱈目であったことは今更言うまでもありません。子ども手当が辛うじて支給額を半減して実施されたものの、これとて来年度はどうなるかは確証がありません。それ以外は高速道路の無料化・ガソリン税の値下げを始め、普天間基地移設の問題に至るまで目玉政策と言われたものは全て反故にされてしまいました。これは明確な公約違反であります。 しかし、国民が本当にマニフェストを重要視していたのなら、いくら鳩山さんから菅さんに総理の首が挿げ替っても、支持率がV字回復するはずがないのです。恐らく、国民はマニフェストの内容よりも政権交代そのものを選択したのではないでしょうか。だからこそ、鳩山内閣から菅内閣に替わっただけで支持率がV字回復したのです。政策云々より、もう少し政権交代の結果を見てみたいというのが国民の本音だったのでしょう
普天間問題
普天間基地の代替施設を「最低でも県外、出来れば国外に持っていく」と明言して、彼らは政権を取りました。しかし政権を取った途端に「考えれば考えるほど抑止力というものの重要性が分かった」と言い、結局自民党と同じように辺野古の周辺に代替施設を作ることになったと平気で言う様にはあきれてものも言えません。この問題で行き詰まって鳩山さんが退陣することになったのですが、これは鳩山さん個人の問題ではなく、民主党政権全体の問題です。しかも、菅さんは鳩山内閣の副総理であり連帯責任は免れません。ところが、菅さんはこの鳩山さんの方針を踏襲すると言っています。普天間問題については、全く反省の弁がないのです。これで沖縄県民が納得するはずがありません。自民党政権なら2014年に普天間返還が実現出来たものが完全に隘路に入ってしまいました。民主党はこの責任をどう考えているのでしょうか。
政治とカネ

政治とカネの問題も民主党の責任感・倫理観のなさを象徴しています。この問題は鳩山・小沢両氏の巨額政治献金の虚偽記載ですが、これも今分かったことではありません。私は、昨年の衆議院選挙が始まる前から、ずっとこの問題を国会の場で追及し続けて参りました。 当時、マスコミが殆ど取り上げなかったことをいいことに、 この問題について民主党は党内で一切調査もせず、無視してきたのです。 去年の総選挙後、この問題がようやく国民の知るところとなり、鳩山内閣への政治不信が募り、お二人とも政権の重職から退くことになりました。 その事を受けて支持率が上がり、国民に「鳩山さんと小沢さんを外したから、民主党はクリーンになった」という印象を与えたつもりかもしれませんが、 それはとんでもない話です。鳩山・小沢両氏が政治的な責任を取って、総理大臣や幹事長を辞職するのは当然です。 しかし、その前に「あれは秘書がやったことだ」とか、「私は知らなかった」とか言う彼らの言葉を、菅さんは納得しているのでしょうか。 恐らく、国民は誰一人として納得していないでしょう。 菅さんも自身がもし野党の党首であれば、辞めたからと言って追及の矛先を納めるはずがなく、少なくとも国民の前でまず説明責任を果たせと要求するでしょう。 そう考えれば辞任は当然で、説明責任を果たすためにも菅さん自身が納得できるまで鳩山・小沢両氏から聞き取りをすべきです。 そして当然のことながら、それを予算委員会という公の場で国民に知らせることが必要です。 そしてその後、二人とも議員を辞職すべきなのです。 ところが、そういう考えが彼らには全くないのです。
新たに発覚した荒井大臣の問題
また、今回初入閣をされた荒井国家戦略大臣の事務所費問題も大きな疑惑です。 そもそも北海道の議員がなぜ東京のしかも都心から離れた府中に事務所を設ける必要があったのでしょうか。 事務所の実態がなかったことは本人も認めておられていますが、実態のない事務所になぜ事務所費があるのか。 また、その中身も少女マンガ・キャミソール・背広代とおよそ政治と関係のない生活費が計上されています。 これは政治資金の流用以外の何ものでもありません。 こうした疑問に荒井大臣はまともに答えず、民主党の幹事長代理が記者会見をする様は異様であります。 党として、臭い物には蓋をしようとする隠蔽体質がここにも現われています。
食言を排せ
まさに、民主党には倫理観が全くない。ないというよりも、ダブルスタンダードだということなのです。 自分には優しく、他人には厳しい。野党の時には綺麗事を並べたて、それがブーメランとして自分に返って来たら、 それを全く知らぬ存ぜぬで過ごしてしまうつもりなのです。 この様な民主党も問題ですが、あえて申し上げれば、彼らの言い訳に納得してしまう方にもやはり問題があると思います。 こうしたことを許さないためにもマスコミには正しい報道をして頂かなければならないと思います。 そして何より、政治と国民との信頼関係を築くためには、政治家が、自分が発する言葉に対して、責任を持つということです。 出来もしないことを軽々公約したり、思いつきで沖縄県民の心をもてあそぶ様なことを言うのはもっての外です。 まさにこれは食言です。食言とは言葉を食べる、つまり、自分の吐いた言葉を食べて全くその責任を取らず、言葉をまき散らしているということです。その典型が民主党のマニフェストなのです。前回の衆議院選挙で彼らがしたことはまさに食言です。もう食言政治からは決別しなければなりません。そのためには、政策ももちろん大事ですが、それ以上にその政治家が本当に信頼に足りる人間なのかという根本的なところを見て頂きたいのです。
食言政治の元は小沢一郎にある

しかし、今日のような小選挙区制度においては、政治家は人格や人柄よりも、目先の政策ばかりをマスコミに要求されてしまいます。なぜなら、マスコミは今回の選挙はこれが争点だと報じなければ商売にならないからです。その結果、政治家もマスコミの要求する政策についての解答を常に用意しておかざるを得なくなります。 そして、それが与野党の相違点としてマスコミによってクローズアップされ、それが選挙の争点として大々的に国民に訴えられていくのです。本来、与野党が必ずしも対立する必要がないものでも、こうしたマスコミ報道の結果、争点に作り変えられていく傾向が小選挙区制度になって、ますます増えたのではないでしょうか。前回の衆院選は、まさにその典型です。そもそも小選挙区制度で二大政党制を作り出すことにより、政権交代が可能となり、これにより国民は政治家を政策で選ぶことが出来ると主張してきたのが、 小沢一郎さんなのです。しかし、冷静に考えてみれば、確かに小選挙区制度は政権交代がされやすい制度ですが、政権交代をして果たして何が解決出来るのでしょう。 間違った政策でも国民が選べば政権交代が行われます。しかし、それで問題が解決されるはずもなく、ましてや国民が幸せになるはずがありません。そもそも、今日のようなテレポリティクス(テレビなどのマスコミにより作られた政治)が蔓延している時代には安直なイメージばかりが先行し、政治はどんどん空洞化してしまいます。まさに、言葉の消失です。 そこに小選挙区制度が導入されると政治は政権交代することだけが目的化されてしまうのです。冒頭、申し上げたように、前回の衆院選は、まさに「政権交代」だけが目的の選挙だったのです。こうして考えると分かるように、この20年近く言われ続けてきた政治改革は、元を正せば発信源はすべて小沢さんです。 彼が田中派の分裂により自民党を飛び出した時から、小選挙区=政権交代=政治改革ということが訴えられ、その言葉に国中が振り回され続け、遂には小沢さんの言う政治改革が実現したのです。果たして、その結果はどうだったのか、もう言うまでもないでしょう。結局、小沢さんの権力奪取の手段として、政治改革という言葉や小選挙区制が使われてきたに過ぎないのです。食言政治家達により作りだされた菅民主党政権には、最早政権を担う正統性がありません。直ちに解散して総選挙を行い、国民に信を問わなければならないのです。
たくさんの署名をありがとうございました
民主党政権に対して解散総選挙を求める運動を行いました京都府下はもちろんのこと全国から多くの皆様にご協力を頂き、西田昌司事務所だけで15,514名の署名を頂きました。
集まりました署名は谷垣総裁へ手渡し、その後、平河クラブにて記者会見を行いました。
マニフェスト違反だらけの民主党政権

民主党の政権ができて6ヶ月以上が経ちましたが、この間彼らは何をしてきたのでしょうか。政権を取る前の選挙では、彼らはマニフェストに様々なことを、国民との約束だと言って書いていました。ガソリン代を下げる、高速道路を無料にする、子ども手当も、他に負担を求めずに無駄を無くしてこれを実行する。しかし、こうしたものは全て、今回実現できなかったわけです。そして逆に、彼らが今国会の中で法制化しようとしているのは、選挙戦では一言も触れなかった、永住外国人に対する地方参政権の付与や選択的夫婦別姓です。選挙前と後で、これほど言っていることとやっていることが異なるのも本当に異常です。特に外国人の参政権の問題については、日本人固有の権利である主権というものを外国人に売り渡してしまうことであり、憲法上も認められるものではありません。また、選択的夫婦別姓も、確かに、女性が社会進出をする際、旧姓名を使う方が便利であることも事実でしょう。しかし、今では通称名を会社の中で使うことも随分認められておりますから、本当の意味での不便なことはなくなっているのではないでしょうか。それよりも、姓を選択できるというこの考え方自体に問題があると私は思っております。
夫婦別姓論の間違い

選択的夫婦別姓の問題は、普通は結婚すると、奥さんが旦那さんの姓に変えますから、女性ばかりがなぜ自分の姓を捨てて男性の姓を名乗らなければならないのかという不公平感がその元にあるようです。しかし、男性の方にとりましても、実は同じ事が言えるのです。といいますのは、私の姓は西田でありますが、この西田という姓を私が選択した訳ではありません。たまたま西田の家に私が生まれてきただけなのです。そしてもっといえば、どの時代に、どの親の下に、どの国に生まれてくるか、そのような、人間のその後の運命を決定づけるようなことさえ、だれ一人選ぶことができない。それが人間なのです。 選択できないものを引き受けて生き抜いていく、そして次の世代にバトンタッチする、それが我々の生きているという意味なのではないでしょうか。そう考えてみると、夫婦別姓の話も、私はそれを選択できるようにしようとすること自体、本質的にほとんど意味がないものであると思うのです。むしろ、選択できないものを選択し、なんでも自分の思い通りにしていこうという考え方自体に問題があるのではないでしょうか。そして、そういう考え方を推進していくと結局は家庭や地域社会、そして国家を破壊してしまうことになると思うのです。つまり、国家にしろ地域社会にしろ家庭にしろ、どれも自分達が選んだのではありません。その時代やその国家に私たちは投げ込まれた訳ですから、有無を言わず引き受けていく以外に無いわけです。その引き受けることを選択していないから嫌だという論理を用いてしまうと、国家も家庭も壊れてしまうということです。このように、民主党政権が行おうとしている政策は、一見すると、理想的で理に叶っているように思えますが、それは綺麗事にすぎず、現実の社会には合いません。彼らの政策は、非常に、欺瞞、偽善に満ちた、でたらめだと言わざるをえないと思います。そういうことが、今回の民主党政権の半年の間に分かってきたことではないでしょうか。
核密約の問題
核密約の問題もその一つです。岡田大臣が、核の密約があったという外交文書を公開しました。これを行ってきた自民党政権の責任はどうなっているのだと彼らは言っています。確かにそれは一理あるでしょう。しかし、よく考えてみると、自民党自身が戦後の占領時代からの仕組みをそのまま引き継いできたわけです。日本に主権がない間に、様々なことがアメリカの占領の下でされてきましたが、核の問題もまさにそのひとつです。しかし実際問題、アメリカの核兵器のない中で果たして、日本の安全を守ることができるのでしょうか。問題は、こうした歴史的事実が明らかになった中、我々がしなければならないことは、先人を非難することではなく、むしろ、我々が事実を知った上で、どうしていくのかということです。もうこれからは、核は一切「持たず、作らず、持ち込ませず」という非核三原則を押し通していくことだけでは通用しないということです。そんな綺麗事で果たして、日本を守ることができるのでしょうか。そして、そもそもアメリカの核の傘の下で日本は守られているということになっているけれど、アメリカが日本を守ってくれるという保証があるのだろうかということまで言及しなければなりません。アメリカの核の傘ということは、日本が第三国から核攻撃をされた時、アメリカがその報復として核攻撃をしてくれるということが前提です。しかし、もしそうなれば、攻撃を受けた第三国がアメリカに対して核攻撃をすることは必然であります。つまり、日本の安全のために、核攻撃を受けることをアメリカは覚悟しなくてはならないわけです。果たしてそれをアメリカに期待することができるのでしょうか。私は、甚だ疑問に思っております。このように考えてみると、実は、核の傘の下で日本が守られているということ自体、我々はもう少し現実的に考えていかなければなりません。我々は野党になった今、民主党がせっかく核密約を暴いてくれたのですから、民主党がこの核の問題を議論しようというなら、我々自民党も、実際に日本の国を守るためには、核を持つことも含めた議論をしなければならないのではないかという本音の話を進めて行かなくてはならないのではないでしょうか。
普天間問題の本質

普天間の問題も同様のことが言えます。鳩山総理は、日本とアメリカは対等なのだから、本来アメリカの基地が沖縄にあることがおかしいのだという趣旨の発言を繰り返しされています。これは私も全くその通りだと思っております。ところが、自民党の中では、そういった鳩山総理の発言に対して、そんなことを言ったらアメリカとの日米の信頼関係が崩れるのではないか、日本はアメリカに守ってもらっているのだからもう少しそのことを意識して発言すべきだ、という意見が出てきます。しかし、私はあえて申し上げたい。それは、むしろ自民党の議論の方がおかしいのです。鳩山総理の発言の方がむしろ理屈の上では正しいのです。アメリカと日本は対等だとしたら、日本がアメリカに一方的に守ってもらっていることの方がおかしいということです。しかし、本当に日本とアメリカは対等だとするなら、アメリカに一方的に守ってもらうのではなくて、日本自身が、日本の国を守れるようにしなければなりません。沖縄の海兵隊はいらないかもしれないけれど、その代わりに、日本の自衛のための軍隊、これをきちんと配備をしていかなければなりません。そして、そのためには、もちろん予算も、今までの防衛予算は5兆円弱でありますが、これが10兆円~20兆円近くかかるかもしれませんが、その負担を国民にお願いしなければならないでしょう。当然の事ながら、憲法を改正し、国民に国防の義務があるということも明言しなければなりません。しかし、そういう覚悟が鳩山総理にあるのかといえば、残念ながら全く無いわけです。つまり、鳩山総理や民主党政権がいっているのは、自民党政権の矛盾点をついてはいるものの、自分達はこの国をどうするのかという覚悟も、自分で自分の国を守る気もないということです。結局、戦後の占領体制の枠組みの中に自らを押し込んでいるだけのことです。それでは日本の国は、自分で自分を守ることもできないし、アメリカに守ってもらうこともできなくなり、自民党政権以上に安全保障の面で、脆弱な体制を作ることになってしまっています。まさに国家の危機に陥っていると言うことです。
バラマキによる財政破綻
これは安全保障面だけではありません。今回の予算の中で示されているさまざまなバラマキ予算によって、国家の財政がほとんど破綻の危機に瀕しています。選挙前のマニフェストでは、無駄を無くせば財源はあるといっていたはずです。しかし結局、無駄は探したけれども無かったというのが現実でした。とりあえず、いわゆる埋蔵金などを使って予算を組んでいますが、これは一過性のことで、継続して財源にすることはできません。にもかかわらず、子ども手当や高校の無償化など、恒常的財源が必要な法案を作ってしまったのです。増税はしない、しかし、バラマキはする。これでは、民主党政権が一日長く続けば続くほど日本の財政は破綻をし、国益は損なわれます。これが、今回の民主党政権がもたらした結果なのです。我々は、こうした事実を国民にしっかり伝えて、来るべき参議院選挙で、しっかりと民主党政権に対するNOという答えを国民に示して頂くための努力をしていかなければなりません。
敵は民主党だ
自民党の中にも、谷垣総裁の批判を公然とされる方が一部におられます。私ももちろん谷垣総裁に意見を申すこともあります。しかし、今一番大事なのは国家の一大事だという認識を持つことです。内紛をしている場合ではありません。敵は谷垣総裁ではなくて、鳩山総理であり、小沢幹事長なのだ、民主党政権なのだ、ということを自民党がしっかりと認識して国民に訴えていく。このことが何よりも重要だと思っております。今後とも、皆さま方の御支援、宜しくお願いいたします。
瓦の独り言
羅城門の瓦

百貨店よどこへ行く
河原町四条の阪急百貨店が,今年の秋に閉店するというニュースを聞いて驚きました。調べれば1976年の秋にオープンし、ピーク時には171億円の売上げがあったとか。瓦の若い頃(?)の80年代には阪急百貨店はファッションの先端をいっていた記憶があります。向かいの高島屋とは扱っている商品が違っていたような・・・。(決して高島屋をけなしているわけでは在りません。誤解の無いように)その後、90年代以降の消費者行動が低価格化、カジュアル化へと移って行き、その変化に追いつけず、さらには周辺の専門店の増加、京都駅ビルの開業等々で斜陽化が進んで行ったとか。そういえば京都の阪急百貨店のデパ地下から食料品が消えていったとか。また、東京の有楽町で西武百貨店が閉店するというニュースも聞きました。エルメス、グッチなどのブランド商品コーナが百貨店から消えて行き、そこにユニクロなどの大衆商品が陳列されだしています。かつて百貨店は庶民のあこがれの的でした。ウインドウに飾られている、手の届かない商品を眺めては、何時かはあの商品を買いたいな・・・。といった思いを持っていたのは瓦だけはないような気がします。百貨店が店を閉める、大衆に迎合して大衆品を中心に販売する。これでは百貨店に対するあこがれは無くなります。「手の届かない、あこがれを眺めつつ、手に入れる為の豊かさを求める気持ち」この思いをどこで見つければいいのでしょうか? これも小泉内閣の構造改革のしわ寄せでしょうか? そうであれば一抹の寂しさとともに、たかが百貨店の閉店ですが怒りがこみ上げてくるのは、瓦一人では無いと思っています。
鳩山首相による巨額脱税事件

鳩山首相が、月1,500万円の資金提供を6年間にわたり実母から受けていたことが明らかになりました。現在わかっているだけで、総額11億円にも上る巨額な資金提供です。これは毎日50万円ずつ、母親から小遣いをもらっていたようなもので、まさに違法子ども手当だと言われても仕方ありません。しかし、いくら恵まれた環境とはいえ、毎日50万円、月にすれば1,500万円、年間で1億8,000万円もの巨額な資金を、少なくとも6年間にわたってもらつ続けたとなると、贈与税が課税されない訳にはいきません。年間1,000万円を超える贈与には、最高税率の50%が課税されますから、鳩山首相は、贈与税の本税だけでも約5億5,000万円の税金がかかりますし、これに無申告加算税や延滞税が約3億円課税されることになり、合わせて、実に9億円近い税金が未納ということになります。ところが、5年を超える部分は時効が成立し、実際の納税額はこれより少なくなる可能性もあります。これも国民には納得いくものではないでしょう。普通、1億を超える脱税事案では、起訴され犯罪として取り扱われることが多いのです。しかし、大臣には憲法75条による不起訴特権があり、総理大臣が認めない限り訴追されないのです。また同じ憲法には、国会議員の不逮捕特権もあります。つまり鳩山首相は、総理大臣であり続ける限り、事実上、起訴も逮捕もされないのです。だからこそ、鳩山首相は、国会の場で、自らの問題を国民に説明する義務があるのです。ところが民主党は、こうした声を全く無視して、一方的な国会運営を行い、強行採決を繰り返してきたのです。これは鳩山問題を封じ込めるための、数による暴挙であり、決して許されるものではありません。
小沢幹事長の裏献金疑惑
また、巨額の政治資金疑惑は鳩山首相のことだけではありません。民主党の小沢幹事長の政治資金管理団体「陸山会」の4億円に上る裏献金疑惑は、鳩山首相の事案よりも悪質です。これは、平成16年に陸山会が4億円近い不動産を取得したにもかかわらず、その事実がその年には全く報告されていないという問題です。不動産取得の事実は、小沢幹事長が自ら記者会見をして示した領収書などの資料により明らかなのですが、そのお金が誰から提供を受けたものなのか一切説明されていません。そのうち1億円は水谷建設からの裏献金であったことが報じられていますが、その詳細については現在、東京地検の特捜部が捜査に着手していると言われています。今年の3月31日に虚偽記載の時効期限が訪れます。早急に立件されることを期待しています。
小沢独裁政治

私が一番異常に感じるのは、党として一切説明を果たさないばかりか、私の国会での質問も数を頼りに野次を飛ばし質問を妨害しようという、民主党の姿勢です。公党として自浄能力がなく、いわば小沢幹事長の私党になっている姿はまことに恐ろしい気が致します。政策の決定においても、小沢幹事長の鶴の一声で全てが決められ、国会は中国の全人代と同じくそれを追認するだけの機関になっています。小沢幹事長による独裁政治が着々と進められています。これでは議会制民主主義は崩壊し、小沢氏による恐怖政治が行われてしまいます。事実上、鳩山首相を超える大きな権限を持ちながら、政府高官ではないため一切国会での質問に答える義務のない小沢幹事長に誰も逆らえなくなっているのです。私たちはこうした事実を国民に訴え、断固闘わなければなりません。
自民党の再生には政策の総点検が必要

このように民主党政権には問題が山積しております。これが今後国民に明らかになるにつれ、その虚像が崩壊し、国民の信頼が失墜することは間違いないでしょう。しかしその一方で、自民党がしっかりと再生していかなければ、政権の受け皿がありません。 党の政権構想会議などあらゆる場で私が訴えていることは、民主党の政権の問題点だけでなく、まず自民党自身が立党以来の政策を総点検すること、特に平成になってからのいわゆる構造改革路線についての総括を行わない限り自民党は再生できないということです。
野党としての立場を生かせ
自民党は立党以来、ほぼ一貫して政権政党であり続けました。結党された昭和30年は、終戦からまだ10年で占領政策の延長線上に政治があった時代です。そのため、自主憲法制定など日本の自主独立を党是として掲げながらも、東西冷戦の下、安保体制の維持や共産主義勢力の台頭から日本を守るという冷徹な現実を受け入れざるを得ませんでした。 つまり、政権与党であるがゆえに現実路線を取らざるを得なかった訳です。それが、50年以上も続いてきた結果、ただ現実に縛られるだけで、その根本的矛盾を乗り越える努力を怠ってきたそしりは免れません。 私はこの際せっかく野党に転落したのだから、こうした立党以来の根本的問題を、もう一度考えるべきであるとあえて申し上げているのです。
普天間問題は自主防衛への一里塚とすべき
鳩山首相は、日米は対等だとお話しになります。全くその通りです。しかし、そのためには日本はアメリカに一方的に守られるのではなく、日本が自力で自分の国を守れる体制を作る必要があります。米軍基地がなくても、日本を守れる体制を作るために、普天間基地は国外へ移設せよと言うなら筋が通りますが、そうした自主防衛の気力も覚悟もないまま、普天間返還だけを叫んでも、日米の信頼関係が崩れ、沖縄県民に失望をもたらすだけです。 鳩山内閣のこうした姿勢は無責任極まりないのですが、一方で、自民党はこうした鳩山内閣の無責任を批難するだけでなく、自主防衛の必要性について、野党になった今こそ議論をすべきなのです。今、自民党がこのことを訴えなければ、この国は永久に自立することが出来なくなってしまいます。
事業仕分けこそ事業仕分けせよ
民主党は脱官僚を旗印として、予算査定をする事業仕分け、地方や業界の要望を官僚に受けさせない陳情禁止、国会での答弁を政治家以外にさせない官僚の答弁禁止など様々な政策を行うとしています。特に事業仕分けなどが連日テレビのバラエティ番組などで放送されるにつれ、官僚のオタオタした姿が映し出され、なにか溜飲が下がる気がしている人も多いようです。 しかし、こうした官僚バッシングで一体何が解決したのでしょう。私は、こうした民主党の政治手法に非常に強い嫌悪感を抱いております。誰かを悪者にしてそれをたたくというやり方は、一時的には大衆に受け人気を博することになるかも知れません。またそれが本当に悪者なら仕方ないかも知れません。しかし、現実の社会で一方的な悪者の存在などあるのでしょうか。「泥棒にも三分の理」ということわざがあるくらいです。 官僚が泥棒よりひどい存在であるはずがありません。三分どころか、八分も九分も官僚にも理があるでしょう。それをあたかも官僚が全て悪の根源かのような発想で、泥棒以下の存在かのように一方的にバッシングするのは極めて幼稚であると同時に、それにより自分達が英雄視されるだろうという心の浅ましさが感じられ、私は全く賛同できません。これは、フランス革命やロシア革命でも行われてきた大衆を扇動するための見せものです。また実際の制度面からも、官僚制度が機能しなくなってしまえば一番損をするのは国民です。従って、冷静な議論が必要なのです。今回の事業仕分けは元々、財務省が内部でしていたものを大衆に公開しただけのもので、財務省の書いたシナリオに踊らされているに過ぎません。予算を削るということだけが主眼で、国にとって何が大事かということは論外になっているのです。財務省内部で行われていた時は、もう一度各省庁の専門家と改めて議論ができたのですが、大衆公開のショーになってしまっては、こうした肝心の議論ができません。これでは百害あって一利なしで、これこそ事業仕分けすべきです。
脱官僚で集中する小沢幹事長の権力
また、官僚への陳情禁止は、省庁ではなく民主党の小沢幹事長に陳情を集中させ、権力と情報を一元的に掌握しようとするもので、まさに中国共産党の仕組みそのものです。これがまかり通れば、小沢幹事長が気に入らなければ何もできなくなり、独裁国家になってしまいます。実際、私のもとへ来られる多くの首長や、議員の皆さんも非常に憤っておられます。さらに、国会での官僚の答弁禁止は、鳩山、小沢両氏の疑惑封じのためのものです。実際、私が追及し続けてきたこれらの疑惑は、国会での官僚の答弁により明らかになってきたのです。公正中立な事務局としての官僚の発言が禁止され、政治家のみの答弁になると、これから政治家の疑惑について一切国会での解明はできなくなるでしょう。今回の官僚答弁禁止は、まさにこれを狙ったものであると言わざるを得ません。この様に、民主党の提案している脱官僚政策は、全て詭弁であり、本当の目的は全て小沢幹事長の利益のためだけにあると言って差し支えありません。こうした問題を抱えているため、鳩山内閣の寿命は案外短いかも知れません。しかし、本当の問題は小沢幹事長なのです。日本を独裁国家にさせないため、全力で頑張ります。本年も皆様のご支援を心よりお願い申し上げます。
樋のひと雫
羅城門の樋
新年おめでとうございます。昨年末の「仕分け」はまさに政治ショーでしたね。子供のいじめの一つに「劇場型」というのがあります。一人の子供を何人かがいじめる。それを多くの子供が見ているという構図です。歯切れのいい言葉とテンポで畳み掛ける。役人が窮すると「削減で良いですね」。見ていて痛快に感じる自分が怖かったです。 「仕分けの結果と将来展望を踏まえて、政治判断する」なら、なぜ行ったのでしょうね。「政府に入れなかった議員のガス抜き(不満解消)」「頑張ってますよ」のパフォーマンス。しかし、あれって「削減」という印籠に悪代官が土下座する、どこかのTVドラマに似ていましたね。その意味では、日本人好みの「民主劇場版黄門さま」ですかね。まあ、副将軍の上には,大将軍や闇将軍が大勢いるから、誰が政治判断するのでしょうか。 防衛省の広報企画に入場料をという意図や科学技術は2位でよいと言うレンポウ先生の発言は、本当に日本の将来や国の守りを考える政治家の言葉とは思えません。「やっぱり、1位は中国なんだ。彼女の父祖の国だから。」と言ったのは隣で見ていた人の声。自分の意見が絶対に正しいと思っていたキャスター時代となんら成長していない姿だけが、妙に印象的でした。 ところで、科学技術開発競争は2位でよいと言った東大の先生。あなたの大学は全大学研究費予算の半分を使っているんですよ。その先生が「2位で良いのでは」は、聞こえません。あなたは学生たちに「2位で良いから」と思って講義をしているのですか。自分の研究は2位で良いと思いながら、今まで研究費を使っていたのですか。研究者の良心ってそんなものですかね。それとも、1位になれないヒガミかな。 見ていて思いました。「無駄」の根拠は、効率だけ。将来のための投資や国の在り方の論議もなく、国民が納得する尺度や像も提示できない「仕分け」って、どんな意味があるんだろうって。厚生大臣が「容認できない」と言い、防衛大臣が「責任ある立場の意見ではない」という程度の見識では、せめて、国の根幹だけは堪忍してほしいなあ。
麻生総裁の辞任表明を受け、私は次期自民党総裁には、平沼赳夫衆院議員が最適であるとの思いから、同志の国会議員とともに、平沼議員の復党運動を行って参りました。
残念ながら、それはかないませんでしたが、その趣旨は次に示してある通り、自民党が保守政党としての本来の姿に戻ることが、党再生のための第一歩であるという思いからです。
尚、総裁選に関して、私が立候補を画策しているかの様な報道がありました。私が関知しないところでそのような動きがあったようです。光栄なことではありますが、元より私がその任にあるはずがなく、報道は事実ではありません。
私は、平沼議員の復党が不可能となった時点で、直ちに地元の谷垣禎一衆議院員の推薦を行い、私の思いを託すことに致しました。
敗北原因の総括

自民党再生のためには、今回の大敗北を真摯に受け止め、その原因がどこにあるのかをしっかり総括しなければなりません。個別には様々の要因があったと考えられますが、根本的には一連の構造改革に対しての総括がなかったことが原因だと私は考えています。そもそも構造改革とは何だったのでしょうか。私は次の様に考えています。官から民へという言葉が示す様に、構造改革論は行政の効率化であり、小さな政府論に通じるものです。官による行政の無駄を廃し、民間手法による効率的経営を行うということを目的とした考え方でしょう。こうした考えの下に様々な行政改革が行われたのですが、郵政民営化はその象徴だったのです。また、この時期同時に言われた地方分権論もこうした構造改革論と軌を一にするものと私は考えています。地方分権論は、国から現場に近い地方に権限と財源を渡すことにより、効率的な行政ができるはずだと推進されてきました。つまり、構造改革論と同じく、行政の効率化を目的とするものです。そして地方分権をすれば地域間競争に拍車がかかり、さらなる効率化が進むと考えられてきたのです。そして、こうした考え方の下、民間においても規制緩和が行われ、市場原理主義による経済の効率化が行われてきました。つまり、構造改革の本質は、社会全体を競争原理により効率よくするということでした。
構造改革の背景
こうした構造改革論は、東西冷戦の終結により、旧東側諸国も含め、世界が一斉にアメリカ型の社会や経済の仕組を取り入れようとした動き、いわゆるグローバリズムと軌を一にするものです。これは日本だけの流れではありませんでしたが、その当時の日本はバブル崩壊により、全く自信をなくしていた時代でした。そのため、政治経済や文化等あらゆる面でグローバリズムに呑み込まれてしまったのです。いやむしろ、国民皆がこぞってその流れの中に飛び込んでいったと言っていいでしょう。
構造改革のもたらしたもの

しかし、急激な規制緩和、市場原理主義、行政予算の削減の結果、社会はいわゆる勝組負組に二極化されてしまいました。自己責任や市場原理という言葉がもてはやされましたが、それは詰まるところ、利己主義を社会に蔓延させただけのことでした。家庭や地域社会も経済ルールの中に取り込まれ、破壊されてしまいました。一部の勝組といわれる人々の中では、さらに多くの財と成功を求め、強欲民主主義が幅をきかせました。しかしその一方で、帰るべき家庭と故郷を失い、希望をなくして社会に不安を持つ人も多数出現してしまったのです。社会には不安と不満、そして欲望が渦巻き、国民の心はバラバラになってしまったのです。この不満のマグマが一挙に爆発したことが、今回の自民党大敗北の根本的原因であると私は考えています。麻生内閣では、せっかく構造改革からの方向転換を行いながら、国民に対してその十分な説明ができなかったばかりか、その総括が党内でなかったため、自民党がバラバラになり、それが国民の怒りに拍車をかけることになりました。正に自民党は自爆をしてしまったのです。従って、まずこうした一連の改革に対し、改めて総括を行う必要があります。
? 再生のための方策
<結党の精神に戻り、真の保守政党を目指す>

先に述べた通り、今回の大敗北の原因は自民党自らがグローバリズムに呑み込まれ、社会の秩序を破壊したことが原因です。換言すれば、自民党は保守政党でありながら守るべき国柄を示せなかったということです。自民党再生の第一歩は、保守政党として我々が守るべき国柄は何かということについて、明確に示すことから始めなければなりません。これについては当然一言で語り尽くせるものではなく、党を挙げて国民とともに大いに議論をしなければなりません。ところがこの国柄を論じることが戦後の日本ではタブーになっていたのです。その結果、日本人は自らのアイデンティティーを失いグローバリズムに呑み込まれてしまったのです。
歴史文化伝統の継承
その原因は、言うまでもなく敗戦により歴史観が分断されたためです。戦後60年以上たった今こそ、タブーを恐れず、先の大戦についての議論をすべきです。そのためには、当然開国から維新に至る経緯についても正しく示すことが必要です。近現代の歴史を、タブーを超えて議論することにより、次代に伝えるべき文化や伝統が見えてくるはずです。
自主的で主体的防衛外交政策の確立
グローバリズムと距離を置きながら、国柄を守るためには、それを担保する防衛政策と国民の覚悟が必要です。日米安全保障体制を堅持しながらも、対米依存ではない自立した防衛のための議論と装備が必要です。特に軍事的に膨張する中国、北朝鮮には毅然と対応する必要があります。
経済・財政
行政の効率化を目指す構造改革が声高に叫ばれたもう一つの理由は、財政再建という課題があったからです。無駄を削減することは必要ですが、無駄とは何かということについてしっかりとした議論をせずに構造改革が叫ばれた結果、行政は大混乱に陥ってしまいました。今日、民主党が主張する無駄を廃すれば十数兆円の財源が出るはずだというマニフェストが、荒唐無稽であることは言うまでもありません。しかし、自民党が言い出した構造改革論にも同じような過ちがあったわけです。そもそも財政再建を論ずる以上、我が国の国民負担率が先進国中、極めて低いという事実を共通の認識にしておく必要があります。仮に国民負担率を10ポイント上げれば、十分な社会保障を行った上でも財政再建ができるはずです。しかも10ポイント上げても依然として先進国中最低レベルの負担率なのです。国民負担率増加論では選挙に勝てないという思いから、この議論を避け、予算削減によって財政再建をしようとしたところに無理があったと考えるべきです。
リーマンショックの教訓
昨秋のリーマンショックは、グローバリズムの破綻を証明するものでした。ここから得られる教訓は、市場原理主義は世界経済を破壊するということです。グローバルマネーをいかにコントロールするかが、世界共通の課題となることは明らかです。グローバルマネーから如何にして国民経済を守るか、それがこれからの世界経済の大きな問題です。そのためにはグローバル市場ではなく国内市場にいかにして資金を回すかが重要な視点になるでしょう。 世界中に市場をもつ企業にとっては、国内外問わず自由に投資できる環境がある方が有利であるように思えます。しかし、その結果がもたらすものは、国内経済の空洞化です。なぜなら、国民の富を世界市場に任せれば、先進国は成長率が低いため、資金は成長率の高い海外に流出するからです。そしてそれが世界を巻き込んでバブルを引き起こしやがてはじけ散る。これを避けるためにはグローバルマネーを如何にコントロールするかがリーマンショックから学ぶべき教訓です。そのための方策のひとつとして国民負担率を上げ、それを社会保障や地域づくりに支出するということは、グローバリズムから国民経済を守る上でも有効な手法です。なぜなら、市場に任せておくだけでは国民の富が必ずしも国内に還元されるとは限りませんが、国民負担率を上げた部分は必ず国内に還元されるからです。このことを我々は共通認識すべきです。
地方自治の充実
私は財源や権限を国から地方に渡すだけの分権論、そしてその延長線上にある道州制には反対です。 そもそもこれらの議論は、国は国、地方は地方のことを考えれば良いという発想が基となっていますが、それは利己主義を正当化させるようなものです。事実、国は国だけでは成り立たないし、地方も地方だけでは成り立ちません。まずこうした利己主義に基づいた発想はやめるべきです。その上で国や地域が相互扶助する仕組みを作るべきです。そのためには地方独自財源の増加より、地方交付税の増加の方が正しいはずです。なぜなら、地域によって財源が偏在し、地理的条件も異なる現実を放置したまま、国の財源や権限を地方に渡し道州制にすれば、地域格差が拡大するのは自明の理だからです。大切なことは、生まれ育った故郷で家族や友人と共に何代にもわたって住み続けられる仕組みを、国と地方が協力して作ることです。故郷を守ろうという愛郷心は何代にもわたって暮らすことが前提であり、それが自治の精神の基です。単なる財源や権限の移譲論では自治の精神は育たないのです。
人口減少問題について
まず確認すべきは、地球全体では人口増加となり、食料や資源、エネルギー等の確保が、今後世界で最大の課題となるということです。 こうした時代に日本の人口が減少するということは、確保すべき食糧、資源、エネルギーが少なくて済み歓迎すべきことなのです。逆に人口増加を前提とした成長型社会は、早晩破綻を来すことになります。成長型社会からの脱却こそがこれからの社会の真の課題です。 この点からも日本のおかれている状況は必ずしも不利ではなく、むしろ全世界に先駆け、脱成長型社会を構築できるチャンスなのです。そして、そのモデルを示すことが、これからの世界に対して日本ができる最大の国際貢献なのであり、世界に真の平和をもたらす鍵でもあります。
草の根保守の再結集
自民党は衆院選の大敗北を受け、自信を喪失しています。しかし、大敗したとは言え、小選挙区では2,700万人を超える方が自民党候補に投票して下さっているのです。この方々は、それぞれの地域で家庭を守り、地域を守る方々です。我々自民党が、真に耳を傾けなければならないのは、こうした方々の声なのです。 故郷や家族を守るために真面目に働いてきた方々が、この間の改革騒動の中でどうなってしまったのか、よく考え反省すべきです。この方々が自民党に望んでいるのは、自民党が真の保守政党として、自分たちの家族や故郷、そしてその延長線上にあるこの国を保守するための政策であり、そのための覚悟なのです。そしてそれを今、我々は試されているのです。
瓦の独り言
秋の夜長に長久堂のきぬたをたべながら
羅城門の瓦
「み吉野の山の秋風さ夜更けてふるさと寒く衣打つなり」参議雅経:百人一首 「声済みて北斗にひびく砧かな」芭蕉:都曲砧(きぬた)は俳句では晩秋の季語になっています。「砧を打つ」とは、麻織物などを柔らかくするための加工の一種で、砧という道具をつかって織物を打つ作業です。また、絹織物などは光沢のある着物にするために棒状に巻いて砧打ちを行いました。
では、なぜ「砧」が秋の季語になって、秋の夜長のもの悲しくも、その音を聴くもののあわれを誘うのでしょうか? 昔、庶民は麻織物しかきられなかった。麻の織物はゴワゴワして、織目も粗く、夏は涼しくて良いのですが、冬になると風通しが良すぎて困る。そこで麻織物に砧を打って、織物の目を詰めて冬に備えたとか。
砧打ちは、柔らかくするだけではなく、冬支度がメインであり、「あ~もうじき冬がくるんだな」と哀れを誘うところからきているのではないかと瓦は考えています。
さて、京都の和菓子に長久堂の「きぬた」があります。お店が四条河原町から消えてしまいましたが、上賀茂にありました。何のへんてつもない白い棒菓子で、和三盆がまぶしてあります。しかし、中を切ると綺麗な緋色の羊羹が飛び出し、その周りを白い求(ぎゅう)肥(ひ)がバームクーヘン状に巻かれていて、いかにも絹織物をイメージさせてくれます。明治初期のパリ万国博に川島織物の綴れ織物と一緒に出品され見事に受賞し、それから宮内庁御用達になったとか。
ここに出てくる2つの「砧(きぬた)」はどうもイメージが異なっているような気がします。しかし砧打ちは元は庶民の手作業だったはずです。それを長久堂の初代「長兵衛」はふるさと丹波で絹を柔らかくし、艶を出すための砧を打つ音を聴き、銘菓「きぬた」を思いついたとか。そこには京都人の感性がキラリと光っているような気がします。
京都は衣食住の文化を各地に発信し「くだらないモノ・・」といった文言まで出来ています。しかし、京都は地方にある事・生業を吸収し、それを京都なりにアレンジをし、また各地に発信するといった大きな文化の加工場もしくは「るつぼ」ではないのでしょうか。東京の百貨店で京野菜がブームになっています。しかし、その品種にはルーツが京都以外にあるものも存在する、と聞き及んでいます。
長久堂の「きぬた」を食べていたら、いつの間にか文化論を振り回している瓦ですが、政治が大きく変わろう(?)としていても、京都市民の文化力はそのままであり、それを政治の流れに左右されたくないという思いは瓦だけではない、と思っています。
疑惑にしらを切る小沢氏と民主党

去る5月11日、民主党の小沢代表は突然代表の辞任を表明し、党員投票もないまま、その週のうちに鳩山代表が選出されました。当の小沢代表は、辞任理由につき何ら説明することなく、西松問題についても一切無関係であると強弁されました。しかし、検察は6月19日の初公判の冒頭陳述で、西松が公共事業の受注について小沢氏側の天の声を期待して献金をし、しかもこれが小沢氏側からの要求であることを明確に示しました。この期に及んでも、小沢氏も民主党もしらを切っています。全く国民を愚弄しています。 実は私は、西松問題以外にも、小沢氏の政治献金による蓄財問題であると国会でも訴えてきました。この問題を5月13日に予定されていた麻生総理との党首討論で取り上げてもらうことを予定していただけに、小沢氏の突然の辞任は非常に残念でした。しかし、小沢氏の辞任によって、この問題が解決したわけではありません。むしろ、小沢氏だけでなく民主党自体隠ぺい体質だけがしっかり証明されたということです。(この問題の詳細については、月刊WiLL 7月号や私のホームページをご覧下さい。) この問題については、引き続き追求していきたいと思っています。
身内に甘い鳩山代表の友愛
鳩山氏は、民主党代表に就任するに当り、友愛という言葉を掲げられました。しかし、この唐突な言葉に違和感を感じた方も多いのではないでしょうか。身分制度の厳しかった封建時代ならいざ知らず、今日の日本でそのような対立があるのでしょうか。むしろ、民主党がお得意の一方的な官僚バッシングのような、ためにする対立論こそが問題です。その意味で、友愛という言葉は、民主党にこそ自戒と反省の意味をこめて使われるべきです。しかし残念ながら、当の鳩山代表にはその意思はないようです。 むしろ、総選挙を意識して、小沢前代表の問題で党内がごたごたせず、挙党一致で闘うという意味で友愛という言葉が使われているのではないでしょうか。 真に友愛という言葉を掲げるのなら、政局のために、いたずらな対立ばかりを強調する国会運営は直ちに改めるべきです。また、民主党自らが、小沢前代表の西松問題や、多額の政治資金による不動産取得、さらには凜の会による郵便料金の不正軽減の口利きなど、多くの疑惑について国民の前に明らかにし、自浄能力のあることを示していただきたいと思っています。
麻生総理は基本的に正しかった

去年のリーマンショック以来、世界的な景気の後退が問題となっています。日本もその例外ではなく、これに対応するため、20年度の補正予算、21年度本予算、補正予算を合わせて総額90兆円にも上る景気対策が講じられています。お陰で、一時は7,000円を割る程だった株価も10,000円を超えるところまで回復してきています。この予算が順次執行されるに従い景気の下支えとなり、さらに上昇に転じて行くものと確信を致しております。しかし、その一方で何故このような世界的恐慌が引き起こされたのかを検証し、教訓としなければなりません。 それが、かねてより私が主張している様に、市場原理主義を掲げてきたグローバリズムにあることは、誰もが同意されることでしょう。そうであるなら、それと軌を一にして行われてきた官から民へという構造改革論も当然見直されなければなりません。 官から民へという言葉は、できるだけ官の仕事を排し、民間に任すことにより、予算を小さくし、それにより国債の発行を抑え、財政再建を目指すという意味で使われてきました。その前提にあったのは、国債の発行は悪であり、子や孫に借金のつけを回すべきではないという考えです。これは、一見正しい様に思えますが、実は国債の本質を誤って捉える間違った考えです。 確かに、子や孫が借金を返済し、利息を払うのも事実ですが、その元金と利息を返済してもらうのもまた私達の子や孫なのです。海外から借金をしているのなら、私達の子や孫が、一方的に借金返済の負担をすることになりますが、日本のようにその殆どを国内で賄っている債権国の場合は、国債は国の借金であると同時に、国民の財産なのです。その事実をマスコミも政治家も正しく国民に伝えていません。従って債権国にとっては、国債発行自体はさほど大きい問題ではないということです。 もちろん、国債を際限なく発行しても良いと申し上げている訳ではありません。ただ、マスコミが言う様な、今にも日本がつぶれてしまうという類の問題ではないという事です。むしろ、景気下降時には、積極的に国債を活用すべきであるということです。国債残高が増えることを恐れて、国がすべき仕事をせずに民間に任すというのは全くの誤りであるということです。そして、景気が回復した後には、税制改革をし、財政規律の回復をすることを麻生総理は明言しているのですから、この点においても麻生総理の政策は基本的に正しかったと言えるでしょう。また、医療費を毎年2,200億円削減するという小泉内閣以来の骨太方針も本年度から事実上廃止し、老後や医療の安心安全も確保されています。 また、ソマリアへの海賊対策の新法の制定をはじめとした国際貢献はもちろんのこと、安全保障に関しても、中国や北朝鮮の脅威に対しては敵地攻撃も検討するということを防衛大綱に記述させるように自民党は提言しております。このように、麻生内閣では構造改革路線から事実上の方向転換をしているのです。
鳩山総務相の更迭は誤りであった
ところが、そのことがきちんと総理の口から説明がされていません。構造改革路線が誤りであったことを明言することは、自民党の総裁である麻生総理としては、憚られることであることは私にも理解できます。しかし、このことをきちんと言及してこなかったツケが、今出てきているのです。 鳩山総務相の事実上の更迭はそのことの象徴でしょう。かんぽの宿のオリックスへの売却を巡る西川社長への対応は、多くの国民からすれば鳩山総務相に分があったはずです。これは、郵政改革の是非そのものが問われる問題です。麻生総理も、元々郵政民営化を始めとする構造改革路線には懐疑的であったはずです。だからこそ、その路線転換をされてきたのです。ところが、自民党の中には、未だに構造改革路線が正しいと思っている自称改革派が多数存在するのも事実です。総選挙を目前にして、構造改革路線の明確な否定をすることにより、彼らが反旗を掲げ、党が分裂することも考えられました。そのことを恐れ、麻生総理は路線変更の明言を避け、鳩山総務相を更迭せざるを得なかったのでしょう。しかし、これでは、せっかく多額の景気対策予算を計上し、事実上、政策転換していることが意味を持たなくなります。政策の自己矛盾に陥ってしまい、正に民主党やマスコミのかっこうの餌食になってしまうのです。その意味でも、総務相の更迭は残念でありました。麻生総理は党内の分裂を恐れず、自らの主張を貫き、その上で信を問うべきであったと思います。
それでも民主党には任せられない

これにより、自民党の支持率は再び急降下してしまいました。その結果、次の総選挙で民主党が政権をとることになるかも知れません。しかし、それは国家崩壊をもたらすことになるでしょう。以下にその理由をかいつまんで述べます。
○民主党には安全保障政策がない 北朝鮮の核・ミサイル、中国の空母建造など、日本近隣での安全保障は、かつてない緊張下にあります。にもかかわらず、民主党の岡田幹事長は、防衛費をさらに削減することに言及してます。小沢前代表の「米軍は第7艦隊以外いらない」という発言も含め、民主党にはこの国の安全保障を任せられません。
○民主党の政策には財源がない。 民主党は20兆円を超える独自の政策を提案しています。しかしその財源については、行政のムダを排除すれば足りると言うだけで中身を示していません。ムダを排除することは正しいですが、それが20兆円ともなると具体的にどの事案や政策を削減すべきか示さねばなりません。政府の支出する予算は、一般会計、特別会計を合わせて213兆円ありますが、そのうち国債返済、社会保障費、地方交付税、財政投融資といった削減が著しく困難か、削減しても財源とならないものが182兆円ですから残りは30兆円しかありません。そこからどうして20兆円が減額できるのでしょう。その30兆円の中は、教育費5兆円、防衛費5 兆円を始め国民生活に欠くことのできないものばかりです。教育費、防衛費を削減するのでしょうか、全く不可解です。
○民主党政権で景気は急降下 せっかく麻生内閣が多額の財政出動をして景気の下支えをしてきたのを、民主党は完全に否定しています。先に述べたように、民主党の政策は、財政出動を増やすことを否定しています。民主党の政策を実施すれば、国内消費が減少することになり、結果として、内需が減少し景気は急降下してしまうでしょう。 その他民主党の政策の矛盾点は多々ありますが、つまるところ、民主党の政策は、この国の根幹を崩壊させてしまうということです。皆様の賢明なご判断をよろしくお願い申し上げます。
瓦の独り言
-いい塩梅(あんばい)-
羅城門の瓦

新型インフルエンザについては終結宣言が出たのかどうか判りませんが、マスコミもあまり騒がなくなりました。しかし新型インフルエンザの風評被害(?)は京都市の観光関連業界を直撃し、5月の修学旅行のキャンセルは530校と聞き及んでいます。旅館、ホテル、飲食店、土産物店、交通機関をはじめシーツの洗濯店にまでおよんでいます。これらの業界に対しては緊急対策会議が開かれ、なにがしかの緊急支援策が打たれます。 これを聞いたある方が次のようなコメントを発せられました。「確かに風評被害はひどいかもしれないが、この様なことは観光業関連業者は予測すべきではなかったのでしょうか? かつて、サーズ騒ぎの時、感染者の方が嵐山を訪れた事がある。といった報道が流れただけで、翌る日から嵐山には人が寄りつかなくなったとか。地震、暴動テロ、伝染病などで観光地は直撃被害を受けることは想像されます。それに備えて、備蓄をするなり、客が大勢来ているときにもうけるなりして・・・。」 なるほど、と納得しながらも瓦は思いました。観光客がどっと来ても、収容能力には限りがあるのでは・・・。本物の京都の「おもてなし」をするのにはお客さんの数には限りがあるのでは・・・。でなければ、昨年の11月の連休を思い出してください。市内は他府県ナンバーの車であふれ、嵐山、清水は雑踏で歩くことさえままならなかったことを。せっかく年間観光客5,000万人を突破したというのに、昨年の11月の様な状況を繰り返すのではリピーターを増やすことは出来ないのではないかと思います。 同じようなことが、農業関係の方にもいえるのではないでしょうか。凶作でも困るが作物が採れすぎて豊作貧乏も困る。しかし、農業関係者には凶作時には共済組合から何らかの支援が・・。豊作時にはご近所に配ったり、寄贈したり、といろいろ手が打てますが、入洛される観光客が多すぎるのにはどのように対処したらいいのでしょうか?いま瓦の頭には「塩梅」という言葉が浮かんでいます。多すぎても、少なすぎても、採れすぎても、ダメ。そこで塩梅の良い数字が出てくるのでしょうね。この言葉は梅干しを漬けるときの塩加減とか・・・。さて、今年も店頭に青梅が出回り、梅酒や梅干しを漬け込む季節になりました。瓦も壺を洗ったり、ホワイトリカーを買いに走ったりしなければ・・・。
お知らせ
京都南区西田後援会からのお知らせ
第40回 後援会旅行会~おいしいとこどり東北3日間の旅~
平成21年9月6日(日)~8日(火)
※お問い合せは西田事務所まで(075-661-6100)
公設秘書の逮捕は微罪ではない

3月3日、民主党代表の小沢一郎 衆議院議員の大久保隆規 公設第一秘書が、東京地検特捜部に政治資金規正法違反の容疑で逮捕され、24日には起訴されました。しかし、小沢代表は国民に謝罪らしい謝罪をせず、終始検察側に対する批判をし続けています。当然のことですが、国民からは代表を辞任すべきという批判の声が上がっていますが、小沢代表は4月5日現在、代表の座に居座り続け、辞任する意思は全くないようです。
民主党の一部の議員からは、辞任すべきとの声が上がっているようですが、大半の議員は口を閉ざしたままで、小沢代表の続投を事実上黙認しているようです。私は、今回の事件を国会の中からつぶさに見て参りましたが、小沢代表の厚顔無恥には呆れてしまいます。しかし、それ以上に民主党の当事者意識の欠如には、信じられない思いがしています。
小沢代表が辞任しないのは、彼一流の検察批判論理です。つまり、政治資金規正法違反は微罪で、政治家の公設秘書が逮捕された例はこれまで一度もなく、通常であれば行政指導すればよく、修正の申告をすれば済むはずだ。これを逮捕したのは、政治的に自分を陥れるためのものであり、これは次期衆議院選挙での民主党政権誕生を阻止しようとする国策捜査なのだとの主張を繰り返し、自分は被害者なのだという言い方をしています。確かに、直接の逮捕起訴容疑は政治資金規正法違反という“微罪”かもしれません。しかし、それでは何故西松建設は偽装してまでも10年間で3億円を超える多額の献金を続けてきたのでしょうか。その背景には、公共事業工事をめぐって小沢代表の強力な政治力を期待して、もしくは妨害を恐れてということは誰の目にも明らかです。これは、今後の公判の中で明らかにされることでしょう。
この国民の疑問に対して一切まともな説明をせず、自分が被害者のような論法を繰り返すとは国民を愚弄するにも程があります。
一方、民主党は、鳩山幹事長以下小沢代表のこうした説明を全面的に受け入れ、その責任を追及する姿勢を全く示しておりません。これは政権を目の前にして党が一致結束することが重要だと考えてのことなのでしょうが、これも世間の常識からは完全に逸脱しています。
他にもある小沢代表の疑惑
そもそも、今回の問題以外にも小沢代表とカネをめぐる疑惑は後を絶ちません。
小沢代表が設立した新生党は、新進党を経て自由党に名前を変え、民主党と合流する際、解散したにもかかわらず、税金で賄われている多額の政党助成金は民主党に引き継がれず、国にも返還されませんでした。
それらのカネは、最終的に小沢代表の関連政治団体にプールされています。また、それら関連団体から「陸山会」への資金が流れていました。しかもその資金を含め小沢代表は、個人名義で10億円以上の不動産を買い漁っているのです。
政治団体は人格がないため、個人名義で登記したと小沢代表は説明していますが、これは政治資金による蓄財そのものではないでしょうか。
民主党は小沢代表の私党

しかし、これこそ小沢代表と民主党の実態なのです。そもそも小沢代表が自民党を離党したのは、政治改革をめぐる党内議論で自分の主張が受け入れられなかったからだと言っていたはずです。
政権交代が可能な二大政党制を作り、そのためには小選挙区制を採用し、それにより中選挙区制のように身内同士で争う無駄を無くし、その結果として政治にカネがかからなくなる。これにより政党中心の選挙ができ、有権者は政策で候補者を選ぶことができる。政治とカネの関係をクリーンにするために企業からの献金は政党以外禁止する。こうしたことを主張してきたのは小沢代表ではなかったのでしょうか。
ところが、その張本人がこの制度の盲点をつく仕組みをあみ出し、長年にわたり脱法行為を繰り返してきたのです。公共事業に関する疑惑を差引しても、この事実だけで小沢代表の政治家としての資質に疑問が生じるのは当然のことですし、ましてや次の総理になることなど考えられないのではないでしょうか。
本来こうしたことは民主党内から批判が出て当然のことです。しかも彼らが本当に政権を担おうとするなら、自浄しなければならないはずです。ところが民主党内では、目の前にぶら下がっている政権に目がくらんで、誰もまともに正論をはかずにいるのは、この政党がすでに公党ではなく小沢代表の私党になっていることを証明しています。
迷走する民主党の基本政策
ところで、民主党は何を理念としているのでしょう。彼らの出身は自民党から旧社会党まで多岐に亘り、理念や政策で一致できるものは元々なかったのです。
強いて言えば反自民であり、自民党から政権を奪えれば良いということしかないのです。自民党に勝つために選挙互助団体として結束しているのが現状でしょう。彼らが野党として政権を批判するだけならそれでもいいでしょう。しかし、次の衆議院選挙の結果次第では、彼らが政権をとることもあり得るのです。
ところが、彼らにはその認識があまりにも薄いと言わざるを得ません。基本政策が一致していない人が集まっているため、政策に一貫性・安定性がありません。
現に、小沢代表は自民党幹事長時代から一国平和主義を批判し、他国と協力して自国の安全を守ることの意義を訴え、自衛隊の海外派遣にも非常に積極的だったはずです。しかし、民主党代表になってからは一転して自衛隊の海外派遣を否定し続けています。その一方で、国連からの要請があれば例外として認めるとの見解を示しています。しかし、自衛隊を出す、出さないの判断は国連が行うべきものではなく、主権国家がすべきものです。
小沢代表の意見は日本の主権を否定するものであり詭弁でしかありません。
麻生内閣は構造改革路線から転換した

さて、去る3月27日にようやく平成21年度の予算及び税法などその関連法案が成立しました。残念ながら参議院は民主党などの野党が多数のため否決されましたが、衆議院の再可決により成立したことに安堵しています。今回の予算は先に成立した平成20年度の第一次・第二次補正予算を合わせて75兆円もの景気対策費を計上しており、事実上世界一の積極財政を推進するものです。
また、この後も景気対策を切れ目なく行うために、20兆円規模の追加対策を行うことを政府与党では検討しております。これは、完全にこれまでの構造改革路線と麻生内閣は決別したことを意味します。
先日私は、参議院の予算委員会で質問の機会を頂戴しました。(この様子は私のホームページでの「showyou動画」で見ることが出来ます。)そこで、与謝野大臣に政府の予算を出来るだけ少なくし、逆に民間に資金をまわす、それにより効率的財政運営が出来るという、いわゆる構造改革路線は、結局アメリカ発のサブプライムローン破綻のような経済危機を生み出し、都市と郡部を、あるいはお金を持てる者と持たざる者との格差を生み出すことになるのではないかと質問をしました。大臣は、あの頃の経済学の考え方は間違っていたと明言し、麻生内閣はその路線から方向転換することを答弁において明かされました。これは私が以前から主張していたことを、麻生内閣が正式に認めた訳で、政策の方向転換を明確に宣言されたことは非常に意義があります。
構造改革路線の中、政府の財政支出は年々抑えられ、その結果、地方の予算も削減され、地方都市は疲弊の極みに達しています。予算を削減するということは一見正しい様に聞こえますが、それは、その予算を削減した分を民間企業がしっかり投資するという前提があってのことです。しかし現実には、景気が悪くなると民間企業は投資に対して慎重になってしまいます。この時こそ政府が積極財政をしなければなりません。同時に、国民に対してこの経済危機を乗り越えるための処方箋を示し、官民協力して行くことが大切です。
麻生内閣の下では、積極財政へと明確に路線変更がされているにもかかわらず、その内容が国民に十分に浸透していないことが非常に残念です。その一因がマスコミの報道姿勢にあることも事実でしょう。野党の主張することにばかりに焦点をあて、公正な報道がされているとは言い難いと誰もが感じているでしょう。
定額給付金などは、その典型例です。まるで全国民が反対しているかのような報道をしておきながら、これが実行されると、これを当てこんだ商売を一斉に流すというのは、どういう神経をしているのかと思います。これに対して小沢民主党は、構造改革路線を批判しているものの、それは野党として与党の政策を否定し、反対しているに過ぎません。それが証拠に、麻生内閣の経済政策は先に述べたように完全に小泉路線とは方向転換しているにも関わらず、終始反対しています。特に、参議院では民主党が第一党として議院運営の主導権を握っているため、彼らのしたい放題です。野党ですから与党案に反対することは致仕方ないとしても、議論をすること自体を否定して、事実上審議拒否をするにも等しい対応を彼らは繰り返し行ってきました。定額給付金の支給の遅れなどはその典型でしょう。
私は、こうした小沢代表と民主党の実態を国民に正しく伝え、
「さらば小沢一郎、さらば民主党」という声を広げて行かねばならないと考えています。
瓦の独り言
-花粉症と回虫-
羅城門の瓦

横断歩道で信号待ちをしている人群れの中に、4人に一人はマスクをしています。3月がスギ花粉のピークで花粉症患者も急増しています。花粉症の8割がスギ花粉症といわれており、日本では昭和45年ごろからスギ花粉症患者が増えはじめ、昭和50年代になると患者数は急激に増加しました。
これには、日本のスギの植林事情が大きく影響しており、昭和30年代に拡大造林と呼ばれる林業政策により、日本中にスギが植林されました。この植林されたスギが成長して花粉を出す樹齢に達し、昭和の50年代にいっせいに花粉を飛ばしだしたのです。
最近京都市に編入された京北町のスギ林では山が赤くなっています。花粉を飛ばしている状態ですが、地元の方に聞きますと人手が入り、間伐が進んでいる山はそんなに赤くなっていません。スギ林の中に日光が入らないくらいスギが密集していると、隣同士の枝と枝がこすれ合って、余計に花粉を出すらしいのです。スギ林の赤さの状態で山の手入れの状態がわかるそうです。市内にはスギを始めとする人工林が約2万ヘクタール以上在りますが,半分近くの1万ヘクタールは間伐などの整備が行き届いていないそうです。市内からスギ花粉症が無くなるのは何時の事やら・・・・。
さて,この花粉症を引起すアレルギー反応と寄生虫感染の因果関係をご存知でしたか? 回虫やぎょう虫などの寄生虫に感染したとき、このアレルギー反応を抑える抗体が体内に出来るためとか。昭和30年代以降の日本では衛生環境が改善され、寄生虫感染症が激減したことも花粉症の増加に結びつく、といった学説があるそうです。
そういえば、瓦は小学校の時の検便検査でひっかかり、回虫・ぎょう虫の虫下しを飲まされた覚えがあります。 それで、京北の杉林で間伐作業をしていても何ら花粉症の影響を受けないことに、納得がいきました。この寄生虫感染説は、あらかじめ寄生虫感染を起こしていると花粉症発生は抑えられるが、花粉症になってから寄生虫感染を起こしても症状は抑制されないとのことです。
子供の頃の不衛生がどこで幸いするやら・・・。と、納得するのは瓦一人では無いような気がしていますが・・・。
お知らせ
京都南区西田後援会からのお知らせ
第40回 後援会旅行会~おいしいとこどり東北3日間の旅~
平成21年9月6日(日)~8日(火)
※お問い合せは西田事務所まで(075-661-6100)
12月補正は何故提出されなかったのか

麻生内閣の支持率が急降下しています。組閣時には50%を超えていた支持率は、その半分になり、まるで政権末期の様相です。その原因のひとつが、景気対策が第一と言いながら第2次補正予算を提出しないからだと、マスコミは述べています。しかし、何故、麻生総理が補正予算を提出しなかったかについては殆ど報道がありません。これでは国民が正しい判断をすることは出来ません。
仮に、補正予算を12月1日に提出をしていたら、どういうことになったのでしょう。憲法の規定により予算は衆院の議決が優先されますから、その議決後30日で参院の議決の成否、有無にかかわらず、自動的に成立します。従って、年内の成立は可能でしょう。しかし、予算には財源が必要です。この財源を担保する「予算関連法案」を成立させるには衆参両院の議決が必要です。現下の民主多数の状態では、参院の議決は非常に不確実です。参院で否決をすれば、衆院で3分の2の多数により再議決が可能ですが、参院で採決をしない場合には憲法により60日たってようやく参院が否決したとみなされ、再議決が可能になるのです。従って、仮に12月1日に補正予算を提出し、直ちに衆院で可決したとしても、再議決には、最短で1月30日になることが予想されます。その為臨時国会の会期を1月30日以降まで延長することが必要となるのです。ところが、国会法により通常国会は毎年1月中に開催することが定められていますから、1月31日には通常国会を開会していなければなりません。このように、日程の余裕が殆どないのです。
しかし、現実には衆院で十分に審議しないで即日可決はできないでしょう。結局、臨時国会の延長には制限があるため、補正予算成立は民主党の協力がない限り事実上不可能なのです。ところで、彼らが補正予算成立に協力する可能性があるのでしょうか。大連立構想、日銀総裁人事、揮発油税、新テロ特措法、金融機能強化法、どれをとっても当初の協力の約束を反故にし、政治を混乱させてきたのは周知の事実です。この為、麻生総理は補正予算の12月提出を断念し、年明け早々の1月5日に通常国会を召集し、ここに提出する道を選ばざるを得なかったのです。このことを是非皆様にご理解いただきたいと思います。
冷戦終結が生み出したバブル
今日の不況の原因がアメリカ発の金融恐慌にあることはご存じのことですが、その根本原因はアメリカ型社会そのものにあります。1989年のベルリンの壁崩壊により、東西冷戦は事実上終わりました。そして、共産主義・社会主義と自由主義のイデオロギー対決も自由主義の圧勝で終わりました。今まで閉ざされていた東側諸国も次々に自由主義経済を取り入れ、世界はひとつの市場にまとめられたのです。いわゆるグローバルマーケットの誕生です。その結果、共産主義や社会主義のように国が計画をしたり規制することは悪で、全てを市場に任せておくことが善だ、あとは神の見えざる手で調整してくれるはずという新自由主義がもてはやされることになりました。こうした中、政府はできるだけ小さくし、予算もどんどん削減する。民間に何でも任せることが改革だと言われてきたのです。これが構造改革です。
しかし、その結果どうなったのでしょう。アメリカは、グローバルマーケットが誕生したおかげで、世界中からお金を調達しそれを投資することにより、莫大な利益を上げました。その象徴がサブプライムローンです。本来、住宅を買うことができない低所得者に、高い金利でお金を貸し出して成り立つはずがありません。しかし、そこに保険をつけ、また証券化することにより、リスクを分散すれば大丈夫だろうという小理屈をつけ融資を実行したのです。当初は、住宅市場が一気に活性化し、土地や住宅の値段は値上がりをしました。こうなると、住宅を手に入れれば返済できなくとも値上がり益で儲かると、ますます住宅市場は活性化し、それにつられて皆がお金持ちになった気分で次々にモノを買い出します。アメリカがモノを沢山買ってくれることをあてこんで、日本も中国も世界中の国がモノを沢山製造し売ることができたのです。しかし、そもそもこれが、砂上の楼閣であったことは今や明らかでしょう。世界中の国が冷戦終結以来、20年もの間、誤った経済政策をしてきたということです。
新自由主義による構造改革の誤り
景気対策をするには、この大反省の中から議論を始めなければなりません。この20年の新自由主義的政策の失敗から学ぶべき教訓は、まず第一に、市場に何もかも任せることはできない、ということです。先に述べた様に、世界中のお金を市場に任せておくと必ずバブルを生み出します。これを避けるためには、過剰な投資を制限するためのルール作りが必要です。お金を民間市場に委ねることを規制するということは、言い換えれば、政府が投資の長期的方向性をしっかり示すということです。
例えば、国防、防災、資源・エネルギー・食糧の確保、家庭や地域社会の再生、国民教育、社会保障など、民間任せではでき得ないものが沢山あります。こうしたことに対しては、政府が率先して投資して行かなければならないのは当然のことです。しかし、この20年間はこうしたことも含め、全予算をカットすることがまるで国是かのように言われてきました。その背景にあったのは財政再建という問題です。
国・地方合わせて、778兆円にのぼる借金があると言われれば、誰もが無駄を廃し、支出を削減せよと言う気になります。官から民に任せよと言う声が出るのも、当然の話でしょう。しかし、財政を引き締めて予算をカットするだけでは政府の仕事そのものができなくなり、社会が混乱するだけで、問題の解決にはなりません。もう片方で、収入を確保する話が議論されねばならないのは自明のことです。
日本の国民負担率(税金と社会保障の負担額の国民所得に対する割合)を調べてみると40.1%で、これは他のイギリス(48.3%)、ドイツ (51.7%)、フランス(62.2%)、スウェーデン(70.7%)という先進諸国に比べて最も低い数値です。アメリカは34.5%で日本より低いですが、この国には国民皆保険制度もなく、むしろ例外として考えるべきでしょう。これからは、この国民負担率をどうするかという話をきちんとしなければなりません。
成長神話の誤り

国民負担率は低ければ良いというものではありません。それは、各国の国柄や社会状況により違うのです。また、負担が増えるということは、必ず社会保障などの給付が増えることとセットになっていることも忘れてはなりません。たとえば、日本が若く、経済成長をし続けていた時代では、国民負担率が低くても良かったのです。経済成長のお陰で国民所得は増加し、経済のパイは大きくなり、税収は毎年自然増加してきたからです。又、若い国ですから病気も介護も年金も少なくてすんできたのです。今、この大前提が壊れてきたのです。これが、いわゆる少子高齢化という問題です。そこで、移民をどんどん受け入れようと言う人がいますが、私は反対です。それは、日本の国柄を急激に変更することに対しての危惧と、そもそも人口増加が良いとは思えないからです。
たとえば、多子化により日本の人口が今後増えつづけ、やがて50~100年後には2億、3億になるとしたらどうでしょう。経済は成長し、国民負担率も低いままで良いかも知れません。しかし、その人口を賄うための食糧やエネルギーはどうなるのでしょう。今、世界のかかえる根本的問題は、人口爆発により食糧や資源エネルギーの不足が生じるということです。地球温暖化という環境問題も、このまま全世界が経済成長路線を続ければ、地球はパンクするというのが事の本質です。つまり、人口増を前提とする経済成長路線は論理的に破綻しているのです。
今日の日本の問題は、こうした根本的問題が議論されず、経済、財政、社会保障、地方分権論など、あらゆることが個別バラバラに議論されていることです。その結果、国も地方も家庭も混乱し疲弊しているのです。議論すべきは個別の政策ではなく、それらを統合した国柄の話です。そう考えた時、これから日本が目指すべきは、アメリカではなく、ヨーロッパのような成熟した社会です。
その時キーワードとなるのは、今までのような紋切り型の自由や成長ではなく、国柄のことを考えた節度や均衡という言葉だと思います。
自由と成長から節度と均衡へ
新自由主義では、日本の国柄を守れないばかりか、世界が破綻する。今日のアメリカ発の金融危機はそれを私達に教えています。国柄を守り、世界を救うためにも、「自由と成長」から「節度と均衡」へ議論と政策の方向を転換すべき時に、今さしかかっているのです。これは日本だけでなく、全世界に共通することで、そういう意味では歴史的転換点に立っていると言えるでしょう。恐らくこれから多くの国(アメリカでさえ)が行き過ぎた自由化、市場原理主義を修正し、規制と節度を求めることになるでしょう。にも関わらず、日本ではいまだに、構造改革路線に反対するのは保守派だと、過去に縛られたままです。私は、府議時代より一貫してこれに反対してきましが、自民党内でも心ある方々が基本政策の大転換を訴えています。それがマスコミには正しく報じられていないのは誠に残念です。
誤てる構造改革路線からの一日も早い脱却が必要なのです。麻生総理には、このことを国民に明確に示し、信を問うて頂きたいと思います。皆様のご賛同をよろしくお願いします。
瓦の独り言
-粢(しとぎ)とお餅つき―
羅城門の瓦

粢(しとぎ)。瓦が初めて耳にしたときは、しっとりとぽっちゃりした色白の美人を想像していました。「粢:神前に供える餅の名.古くは米粉を清水でこねて長卵形としたものを称した.(広辞苑より)」と書かれています。この粢にお砂糖を加えたモノが和菓子のルーツと言われています。
我々日本人は古来より、稲作文化を受け継いできました。「お米」の「次」に姿を変えると「粢」になる。何とも、妙を得た言葉であり、神前にお供えするお餅の原型と言われており、神前に供えるお餅のことを「しとぎ餅」とも言っています。
この、お餅と言えばお正月などのめでたい行事に欠かせない食べ物ですが、ライフスタイルの変化などでお正月ぐらいしか口にしたことがない方もいらっしゃるのでは・・・。
また、スーパーマーケットなどでは年中お餅が売られています。本来、お正月を迎えるためのお餅つきは神聖な行事で、古代から農作物の神々をあがめ奉り、お米の霊魂と人間の霊魂が渾然一体となって新年を迎える行事の一つであったようです。したがって、その餅つきに必要な臼と杵は神聖なモノとされています。農村部でも余り見掛けなくなりましたが、臼は土間の大黒柱のそばに置き、家を新築したときは一番に臼を運び入れたそうです。
瓦の家では、まだお餅つきをしており、そのための道具である臼、杵、蒸籠(もち米を蒸す道具)、餅箱などは三代つづけて使っており、50年以上の骨董品的代物で、大切に使っています。29日は苦餅といって忌み嫌い、いつも暮れの30日に一日がかりで、お餅つきをしています。
お正月にお餅を食べる意味も、お餅つきをすることも、今一度、見直してみてはいかがでしょうか。お餅つきの行事については、幸いなことに、幼稚園、小学校のPTAなどの方々のおかげで引き継がれています。この日本の伝統文化である(大層に思われるかもしれませんが)お餅つきの火を絶やさないことも瓦たちの世代の使命ではないかと思い、粢の意味を取り違えていたことを恥じ入っています。
お知らせ
京都南区西田後援会からのお知らせ
新年恒例おでん会
日時:1月11日(日)12:00~16:00
場所:西田議員宅
会費:¥1,000
第40回 後援会旅行会~おいしいとこどり東北3日間の旅~
平成21年9月6日(日)~8日(火)
※お問い合せは西田事務所まで(075-661-6100)
麻生総理誕生が意味すること

福田総理の辞任を受けて自民党総裁選挙が行われ、圧倒的多数で麻生総理が誕生しました。それは、長らく続いてきた構造改革路線に決別を告げるものです。私は、これまでも構造改革路線の不合理を一貫して訴え、断固反対をしてきました。その理由は、構造改革とは競争によりすべてのことは解決出来るという前提に立っており、競争を妨げるものはすべて排除すべきだという非常に画一的で乱暴な考え方であったからです。これでは社会が疲弊するのは当然の帰結です。麻生総理はこうした考えとは一線を画す方であると確信をしています。事実、当時小泉総理との間で行われた総裁選でも構造改革に対しては懐疑的な態度をとっておられました。構造改革の背景には、バブル崩壊による日本経済の危機的状況があり、何らかの手を打たねばならなかったのは事実です。しかし、この時、何故バブルが発生し崩壊したのかということについて、十分議論がされたでしょうか。いわゆる不動産業者や一部の金融機関の責任ばかりが追求されただけで、十分な議論のないまま、結論だけは、最初から日本をアメリカ型の競争社会に変えるということがマスコミ世論により決められていました。結局、与野党が議論したのは、その改革のスピードを競うことでしかなかったのではないでしょうか。
何故バブルが発生し、崩壊したのか
そもそも、バブルの発生から崩壊、そしてその後の構造改革という、平成日本の諸問題の背景にあるのは、この国の形をどうするのかという根本的な議論がないままに、アメリカの要求に応じ、また自ら進んで、アメリカ型社会に追随してきたということです。勿論、その責任の第一は政治家にあり、とりわけ与党である自民党の責任は極めて大きいと言えます。しかし、同時に野党やマスコミもその責任を免れるものではありません。バブル発生の背景には、1985年のプラザ合意がありました。これは、先進各国がドル安を是認し、アメリカ経済を救済しようとするものです。その結果、対米輸出に依存していた日本は円高不況に陥りました。その一方で、内需主導型の社会を作るために、10年間で430兆円の公共事業投資をするということが対米公約され、極端な金融緩和策がとられました。急激な国内投資の増加と金融緩和政策により、景気は急速に回復しました。それどころか、実体を上回る程にまで過熱してしまいました。それがバブルです。土地を持っている者は、値上がり益で大儲けするということが常態化し、日本中の土地が買い漁られました。また、持たざるものとの間に大きな格差が生じ、激しい嫉みや恨みの感情が沸き起こってきたのです。その結果、バブルを退治するとして、金融の蛇口を根本から止めるという乱暴な政策がとられ、一挙にバブルは崩壊しました。これは余りにも冷静さを欠いた政策でしたが、当時の国民は皆これに拍手喝采をしたのです。しかし、その結果残ったのは百兆円にも上る、不良債権の山でした。日本全体が大不況に陥ってしまったのです。銀行や証券会社も倒産の危機に瀕し、当時13行あった都市銀行も、整理統合され今や3行しかありません。象徴的なことは山一証券の経営破綻です。しかし、それを買収したメリルリンチが、今回のアメリカの金融危機でまた別の会社に買収されるとは何とも皮肉なことです。また当時、金融危機を乗り越えるために公的資金の導入が行われました。あの当時これに大反対をしていたのが小沢さん率いる新進党です。しかし、もし、あの時、公的資金導入がなければ、日本発の金融大恐慌が起っていたに違いありません。
構造改革の始まり
この時期の日本を振り返って、失われた10年と言われてきましたが、一方アメリカは、そんな日本を尻目に経済の大復活を遂げていました。かつて世界の工場と呼ばれていた製造業中心の国から、インターネットなどのIT産業や金融産業へと産業形態は様変わりしていきました。そこで、日本でもそれにあやかろうとする声が上がってきました。これが構造改革派です。アメリカのように日本も製造業にしがみつかず、産業構造を変えるべきだ。そのためには、今までの護送船団式といわれた業界と一体となった行政を廃し、規制の緩和や、撤廃をすべきだ。その競争に勝ち残らなければ世界には通用しないのだ。アメリカを見よ、とばかりに規制緩和、市場原理主義者のオンパレードとなったのです。その頂点に立ったのが、小泉元総理でしょう。
小泉元総理と小沢民主党は同根である

もっとも、小泉元総理は郵政民営化と自民党をぶっ潰すということばかりを叫ばれただけで、実際の改革を取り仕切ったのは竹中平蔵氏です。この人はアメリカ型の経済の仕組み、つまり市場原理を社会のあらゆる状況で適用しようとしました。しかし、福祉や医療から地方自治に至るまで、社会のすべてに市場原理主義を導入することは最初から無理があるのです。市場原理主義というのは言い換えれば、人のつながりを無視して損か得かで判断するということです。しがらみを捨て、目先の損得だけで判断することは、短期的には効率が良いかも知れません。しかし、そんなことを繰り返しておれば、人間関係は破壊され、社会の基盤を壊すことになってしまいます。結局、長期的には理に適うものではありません。今日、日本が陥っている地域間の格差や先行き不安などの様々な問題も、これが原因であることは間違いないでしょう。一方、それに対して生活が第一として構造改革路線を小沢民主党は反対しています。しかし、それは去年の参議院選挙あたりから急に路線変更したに過ぎません。事実、小沢さんは、かつてその著書「日本改造計画」の中で、アメリカを普通の国と呼び、それを国のモデルとして日本を改造しようと提言していたのです。小泉さん以上の親米主義者と言えるでしょう。そして、なによりも、かつては小泉さんと構造改革の早さを競争しようではないかと、民主党自身が訴えていたのを忘れてはなりません。
脱グローバリズムこそ日本再生
このように、バブル崩壊以後の日本は、与野党問わずアメリカ型社会へまっしぐらに改革を繰り返してきたのです。その結果、人間にとって一番大切な家族や故郷が崩壊し、人々は拠り所を失い、先行きに対する不安に怯えているのです。そして、その本家であるアメリカではサブプライムローンの破綻から金融機関が次々と倒産し、その負の連鎖は世界中を覆い尽くそうとしています。このことは、グローバリズム、即ち、アメリカ型の経済の問題点を如実に表しています。改革騒動に明け暮れた多くの政治家やマスコミ諸兄には、こうした改革騒動がもたらした経緯と結果を真摯に見つめ、多いに反省してもらいたいと思います。そして二度とこうした失敗を繰り返さないためには、国民にしっかりとこの間の経緯を知っておいていただきたいのです。その上で、今我々がすべきことは、グローバリズムの呪縛から身を解き放ち、日本の国柄を取り戻すことです。それは自分たちの歴史を取り戻すことであり、故郷や家族を再生させることでもあります、その再生のための改革こそ必要なのです。
太郎か一郎か

総裁選挙が行われた際、私は、若手議員の有志と共に、以上のようなことをまとめた提言書を麻生総理始め全候補者に手渡しました。麻生総理には我々の意見に多いに賛同していただきました。そして、総裁選で麻生総理が圧勝したことにより、構造改革路線に自民党は一応の終止符を打つことが出来ました。対する民主党は、代表選も実施されませんでした。それは、政権を取るまでは、異論を封じ込め何もかも小沢さんに任せるという、およそ民主的とは言い難い不気味な姿です。特に最近の民主党は、年金は全て税金で賄い、高速道路は無料化、おまけにガソリン税は値下げするなど単純に見積もっても20兆円はかかる政策をマニフェストと称して掲げています。しかし、その財源は示しておりません。ある時は、無駄を省いたらできると言い、またある時は、埋蔵金を使えばいいと言い、明確に財源を示しておりません。これは非常に無責任な態度であります。来るべき衆議院の総選挙は、文字通り政権選択の選挙です。本当に小沢さん率いる民主党にこの国を任せることが出来るのでしょうか。この国の顔としてふさわしいのは麻生太郎なのか、小沢一郎なのか賢明なご判断をお願いします。
瓦の独り言
-ボリビア通信―
羅城門の瓦

お久しぶりです。これからボリビアは春を迎え、雨期の前の素晴らしいひと時を迎えます。 しかし、今年の春は人々にますますの昏迷をもたらそうとしています。 現在のボリビアは社会主義化政策を進める政府と自治の拡大を求める県とが二つに割れています。 モラーレス政権は先月の信任投票で6割以上の国民の支持があるとして、地下資源や外国企業の国有化を進めており、 また、憲法改正案では土地所有の制限を行おうと目論んでいます。(信任投票では自治拡大派の知事たちも7~8割の支持を得ました。 まあ、国民はどちらにも信任を与えた格好です。)また、中南米だけを見ると中米やチリ、アルゼンチン、ヴェネズエラといった国々は反米を掲げ、 社会主義路線を選択する国は多くあります。我々にとって既に歴史が検証を行ったと思っていた「社会主義の誤謬」が、 ここ中南米の地では未だ「正義」であり「政治」なのだと感じます。 9月の半ば、サンタクルス・タリハ・ベニー・パンドの各県では自治拡大を求めたゼネストに端を発して、 政府支持派と自治拡大派の衝突が起こりました。パンド県では戒厳令が敷かれ一説に拠れば16名死亡・100名が負傷、行方不明者も100名以上とか。 また、政府はこの国内分断の背後にアメリカがいるとし、米大使の追放を決めました。このように書くと社会主義と自由主義の衝突のように聞こえますが、 ことはそんなに単純ではありません。背景を見ると、天然ガスや石油の配分の問題、白人を中心とする大土地所有の現状、 インディヘナ農民の対立、鉱山労働者を中心とした労働総同盟の先鋭化、為替レート差から来る物資不足や食糧高騰への都市住民の不満、 慢性的な失業者増大に対する若者の不安等々の問題が錯綜し、これに根強い郷党意識が加わります。 それに忘れてならないのは,「分配の不平等」です。日本の近畿地方ほどの広さを持つパンド県の土地は10家族で占有していると言われています。 また、意識の底に眠るインディヘナ蔑視の感情もあります(現大統領は初のインディヘナ出身)。 このような現象としての社会問題と人の心の底にある人種民族感情とが絡み合い、波打っているのが現状です。 また、どのような対立でも双方ともに「デモクラシア(民主主義)」を叫び、自身の正当性を語ります。 現政府は「脱植民地」を政策の根底においていますが、先住民には500年間奪われた土地と富を取り返すという気持ちにもさせます。 現実と理念の間で、未だ国有化政策以外に具体的な手を打てなかった政府が、今回の政治的緊張を経て、12月初旬に「憲法改正」の国民投票を行います。 ここでは土地所有の制限に代表される私有財産の問題に踏み込みます。 社会主義政権として装いを整えられるか、中南米諸国の左傾化の中での咲いたアダ花で終わるのか正念場が続きます。 これからボリビアは灼熱の政治の季節を迎えます。
去る6月20日に、昨年の臨時国会以来10ヶ月に及ぶ第169回通常国会が閉会致しました。昨年の参院選挙から、この一年間の国会の議論を私なりに振り返り、
皆様にお伝え (Showyou) したいと思います。
テロ特措法

元々、自衛隊の海外派遣は、民主党の小沢代表が自民党幹事長の時代に提案し、推進してきたものです。
当時は湾岸戦争の時代でした。日本が一番中東の石油に依存しながら、お金を出すだけで、汗をかくことを一切しなかったため、世界中からひんしゅくを買っていました。
このことを受け、当時の自民党幹事長だった小沢さんは、一国平和主義を批難して国際貢献の重要性を説き、成立したのが自衛隊の国際貢献活動です。その延長線にあるのがテロ特措法で、この法律が出来た時は、小沢さんも民主党も賛成していたはずです。ところが、小沢さんは突然、日本があまりにも対米追随に過ぎると、テロ特措法の延長に反対しだしたのです。そもそも対米追随外交を批判するなら、それと同時に自国の防衛力増強を訴えるべきです。自衛隊や防衛省批判ばかり繰り返す民主党には、防衛や外交といった国家の基本政策さえも政局の具でしかないということなのでしょう。
テロ特措法の期限が切れ、自衛隊は一旦インド洋より帰国しましたが、結局、衆議院での再可決によって再派遣されました。自衛官の志気が著しく低下したことは想像に難くありません。その期限がまた来年の1月に来ます。今度は民主党はどうするのでしょう。
ガソリン税と道路特定財源の一般財源化
この問題は前回のshowyouに書きました。既に福田内閣の下で一般財源化は決まりました。問題は、一般財源化しようにもガソリン税を値下げしては、その財源がないということです。
財源を示さず政策提言するのは絵に描いたもちを売るに等しく、政治家ではなく政治屋の振る舞いです。
長寿医療保険制度

あれだけ連日、マスコミが民主党のデラタメな発言ばかりを報道すれば、国民は誤解します。私の母でさえ、自民党は年寄りを見殺しにするのかと言った程です。
しかし、それまでの制度のまま放置すれば、小さな市町村の老人保険が破綻してしまうことは民主党も認めていたはずです。全国どこに住んでいても、誰もが医療を受けられる仕組みをどう守るのか。その為には、 5割を税金、4割を現役世代、1割を高齢者に負担していただくという大筋は、国民の皆さんにも納得していただけるものと思います。
このことについては、基本的に民主党も賛成をしていたはずなのです。もちろん、年金から直接天引きしたり、具体的に誰がどれだけ負担が減るのか、または増えるのかなど、きめ細かな説明や通知がなかったことは問題ですし、それは早急に改善しなければなりません。しかし、民主党のように全てを廃止してしまっては、元の木阿弥、保険制度が破綻するだけです。しかも、そんな無責任な法案を会期末に突然提出し、騒ぐだけ騒いで、結局、自らまともに審議すらせずに廃案にするというのは、自己矛盾も甚だしく、政党の体をもなしていません。
財源無視の民主党マニフェスト
去年の参院選挙で民主党は、農家の所得補償、高校・大学の授業料の無償化、
満額の基礎年金(月額6.6万円)を全員に支給、高速道路の無料化などを訴えていました。それには総額16兆円近い予算が必要ですが、その財源については税金の無駄使いを止めれば出来ると言ってきたのです。
その上、今回のガソリン税騒動の際には、2.6兆円ものガソリン税引下げを主張しています。これらを合わせれば総額20兆円近い財源が必要ですが、それはどこに求めるのでしょう。無駄使いを無くすのはもちろん大切です。
しかし、国の予算が80兆円、そのうち税収が50兆円しかない現実の中、どうして20兆円もの財源が出て来るのでしょう。この無責任極まりないマニフェストには民主党の前代表でさえ、バラマキだと批判する始末です。その他にも民主党の政策のデタラメは数え上げたらきりがありません。
私のホームページの中で、民主党提出法案についてその矛盾をただす私の質問の様子を動画で配信していますので、詳しくはそちらをご覧下さい。
これからの政治の動向

衆参ねじれ国会の下、民主党はあらゆることを政局の道具にしています。
その理由は、次の衆院選挙で勝てば衆参両院で第一党になり、政権をとることができるからです。残念ながら、その可能性も決して低いものではありません。
しかし、政権をとったとしても、彼らの政策を実現するには、膨大な増税をするか、大幅な赤字国債を出すかしか方法はありません。恐らく、政権をとった時点で民主党の中で路線が対立し、分裂する可能性が一番高いかも知れません。また一方で、自民党が政権を確保したとしても、現在のように衆議院の2/3の勢力を保持することは誰も想像し得ないでしょう。
ということは、今までのような衆議院での再可決は不可能になるということです。
民主党の提案をのまない限り、法案は成立できなくなるのです。
民主党もこの事実を重く受け止めるべきです。今までのように、衆議院で否決されることを前提にした無責任な法案の提出や、衆議院での再可決を前提にした参議院での審議拒否は厳に慎むべきです。
自民、民主ともお互いに歩みより、政局ではなく、真の政策論争をしなくてはなりません。
改革の正体
民主党の党首が元自民党幹事長であることに象徴されるように、元々民主党と自民党との間にあるのは、政策上の対立より権力奪取に向けての対立です。
実は、この背景には世界の大きな歴史の動きと密接な関係があるのです。
平成になり、東西冷戦がソ連崩壊をもって終結したことにより、アメリカ一国支配の世界が出来上がってしまいました。
同時に、日本国内においては、その影響を受け社会党が分裂し、崩壊しました。そして、それが今度は自民党の分裂をもたらしたのです。
自民党は、共産党や社会党のような教条主義ではなく、現実容認政党です。そのお陰で、党内に幅広い考えや人材を許容することができたのですが、逆に党内を統一し、まとめる思想が反共や反左翼以外、乏しかったのも事実です。冷戦終結によるソ連崩壊、国内における社会党の壊滅により、自民党内にはもはや統一の原理より、政権奪取の力学の方が強くなるのも自明の理です。
あの当時は、自民党の中でも多くの方が改革を叫んでおられました。しかしそれは結局、「改革」という錦の御旗を掲げてはいるものの、その内実は自民党内での権力闘争ではなかったでしょうか。それは民主党の小沢さんの姿そのものです。新党ブームで改革を叫んで自民党を飛び出した方々、社会党崩壊で行先を失した方々が中心となって民主党が誕生したことは周知の通りです。
郵政改革も含め、今の政界は冷戦崩壊後の政党解体騒動の後始末がまだ続いているということです。今必要なのは、こうした改革騒動に振り回されることではなく、問題の本質を説くことです。
拉致を始めとする真の問題
アメリカが北朝鮮に対するテロ支援国家の指定を解除することにより、拉致問題が大きな影響を受けています。
国内では、経済制裁の緩和は認められないとする強硬派と、制裁だけでは解決できないとする友好推進派との対立ばかりが取り沙汰されています。しかし、問題の本質は違うのです。拉致問題は、主権侵害の問題として考えるべきものなのです。国家の使命は、国民の生命、財産、名誉を守ること、つまり国民の主権を守ることです。この当り前のことが、戦後日本においては忘れられているのです。拉致問題は、主権侵害そのものです。この問題は、自国の主権を守るためには何が必要なのかということを議論せずには解決できないのです。アメリカのテロ指定解除や、経済制裁の是非は言わば二の次の問題です。根本は、今の日本には国民の生命、財産、名誉を守ることができない状態にあることをどうするのかということです。当然、防衛力の整備を含め、国防そのものについての議論が必要になります。とりわけ、北朝鮮は、日本に向けミサイルを配備し、核兵器を用意しているのです。この状態から国民を守るには何が必要なのか、このことこそ議論すべきことです。国を守ることを忘れ、アメリカに依存した仕組みでは、国民は守れないし、拉致問題も解決できないことを改めて私達は思い知らねばなりません。そして、こうした状態から脱却することこそ、真の政治課題なのです。これからも、こうした真の政治問題を解決し、国民が皆、幸せに暮らせるよう、全力で頑張りますのでよろしくお願い申し上げます。
自民党時局講演会を振り返って

皆様には、日頃より温かいご芳情とご支援を賜り、誠に有り難うございます。過日の「自民党時局講演会」には会場一杯のお運びを頂きましたこと、後援会長として心より御礼申し上げます。 さて、この度の講演会は昌司議員が国会議員になって初めての大きな国政報告会とあって、どんな話をするのか非常に楽しみでありました。
たくさんの話がありましたが、とりわけ印象的だったのは、民主党との攻防の話です。昌司議員の真っ直ぐでブレない主張もさることながら、国会対策を熱っぽく語る姿に、私は、故 西田吉宏参議院議員を思い出さずにはいられませんでした。吉宏議員が参議院国会対策委員長だったころ、私に夜遅くまで国会のことを熱っぽく語る姿を思い出し、 国会記者会見 親子二代の国会での活躍に感激したのと同時に、二人をお支え頂いた皆様に改めて感謝いたしました。

見た目は全く違う親子ですが、国政に対する思いや京都を愛する心は誰にも負けない似たもの親子だと再認識しました。吉宏議員がご存命なら、昌司議員が京都に戻ってくるたび、今のねじれ国会のことで、西田家は毎晩大激論になっていることでしょう。昌司議員の国を憂う気持ちは、府議会議員のころよりよく存じておりますが、さらに深く大きな見識をもって頂き国政に邁進して頂きたいものです。私も後期高齢者一歩手前の中期高齢者ですが、皆様と共にこれからも西田昌司議員を支えていく所存でございますので、引き続き温かいご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。
ガソリン税の暫定税率廃止は国民生活を破壊する

3月28日、夜の9時を過ぎて参議院本会議がありました。予算は、衆議院では可決、参議院では野党多数により否決されましたが、議長より憲法の規定により衆議院議決が優先し、平成21年度予算が成立した旨の報告がありました。予算は成立したものの、残念ながら、その裏付けとなる財源を保証するためのガソリン税の暫定税率の維持は今のところできない状態にあります。その結果、4月1日からガソリン税は25円/?値下がりすることが決定しました。そのことがもたらすものは、国民生活の破壊でしかありません。確かに家計や事業経費は安くなりいいように思えるかも知れませんが、2.6兆円もの歳入不足をどうやって穴埋することができるでしょう。民主党は、ガソリン税の値下げだけでなく、それを道路だけに使うのではなく、他の予算にも使えるように一般財源化するとも言っています。しかし、これは非常に矛盾したことです。つまり、暫定税率を廃したら税収が2.6兆円も減ってしまいます。一般財源化するけない、新しい道路も作るといいますが、そのお金はどこから持ってくるのでしょう。矛盾だらけの主張を繰り返すだけで、それを説明しようともしていません。道路だけでなく、福祉や教育を始めとする一般歳出にも影響が出るのは必至です。ただでさえこの所のサブプライムローン破綻の影響で急激な円高株安が進み、日本経済は回復基調から足踏み状態になっているのです。政治が混乱し、日銀総裁も決められず、予算が求めた歳入も得られないとなれば、日本の国際的信用は大きく失墜してしまいます。日本売りはますます加速し、その結果、被害を受けるのは結局国民なのです。国民の被害をできるだけ少なくするためには、速やかに衆議院で3分の2以上での再可決をするしかありません。
審議を拒否する民主党などいらない
そもそも民主党は、ガソリン税の暫定税率が反対なら、多数を制している参議院でしっかり議論して否決をすれば良いのです。しかし、彼らはこれを一切審議しませんでした。その理由は、参議院で否決をすれば直ちに与党が3分の2以上の議席を有する衆議院での再可決をすることを恐れているからです。というのも、彼らの目的はガソリン税を値下げすることではないのです。ガソリン税の値下げを通じて、国民生活を混乱させ、政局を作ることが目的なのです。そのため、本来2月29日に衆議院で可決された法案を棚ざらしにし、3月31日まで充分に時間があったにもかかわらず一切審議しなかったのです。したがって、衆議院の再可決をするにも、衆議院から参議院に議案が送られて2ヶ月が経過してもその結論が出ないときには、参議院が否決したものと見なすという憲法59条の規定を使うしかありません。このままでは、ガソリン税が衆議院から送致されてから2ヶ月が経過する4月29日まで待つほかないのです。
政局のための対立

定税率も税制改革の中で見直すということを表明しました。彼らが本当に真面目に国民生活を考えているのなら、総理の提案には十分応じられるはずではないでしょうか。結局、彼らの主張は政局を作り出すための方便でしかないのです。しかし、政権を取る結局、彼らの主張は政局を作り出すための方便でしかないのです。しかし、政権を取ることは手段であり、目的は国民生活の安定であるはずです。彼らの主張や行動はこれを忘れた、本末転倒の行為であると言わざるを得ません。民主党の行ったことは、正に、国民生活を破壊する政治テロそのものです。自分達が政権をとるためには国民生活が破壊されてもかまわないということは、断じて許せるものではありません。残念ながら参議院で自民党が過半数を持たないため、私達はこの事態を止めることができなかったのです。あとは国民生活がとんでもない事態になろうとも、2ヶ月が経過する日を待つ以外ないのです。私は、自分達の無力が悔しくてなりません。どうか私達に力を与えてください。国や地方を守り、国民生活を民主党のテロから守るために力を与えてください。おそらく近々、国民に信を問う時が来るでしょう。賢明なる国民の皆さん、必ず民主党に鉄槌を下してください。
アフリカODA調査団に参加して
私は、去る2月2日から14日まで、参議院のODA調査団の一員として、カメルーン、エチオピア、南アフリカの3ヶ国と英国を訪問しました。そのことを踏まえ、以下のようなことを3月28日に参議院ODA特別委員会で高村外務大臣に質問をしました。
今なぜアフリカなのか
今、なぜアフリカなのか、ODA実施について多くの国民が感じることではないでしょうか。それほど、日本人にとってアフリカは地理的に非常に遠い国であり、その情報も ほとんど持ち合わせていません。元々、ODAの目的は貧困撲滅などの人道的見地によるものであったはずなのですが、現実には、被援助国の経済開発を通じて援助国が直接利益を受ける、いわゆる、紐付き の経済支援が多く行われてきました。国民の税金で援助をするのですから、それもある意味では当然のことと思われます。その一方で、最近では、石油やレアメタルなどの資源確保という国益論が盛んに言われたりしています。 しかし、私は、被援助国のかかえる問題を我が国の政治にフィードバックして考えることが、本来のODAの趣旨からも意義あることではないかと考えています。というのも、 アフリカの抱える諸問題を欧米による近代化やグローバリズムのもたらしたものと考えれば、それは日本の鏡として考えることもできると思うからです。情けは人のためなら ず。自分のためと考えれば、アフリカへのODAも日本にとってもっと身近で意義のあるものになると思うのです。
近代主義がアフリカを破壊してる
例えば、学校建設等の支援を日本は実施し感謝されていますが、被援助国において必ずしも人材育成が成功しているとは思えません。その原因は、長い間の植民地支配と多 民族国家であることによる、国家としてのアイデンティティ不足が考えられます。元来、アフリカには多様な民族と言語が存在しているため、いわゆる国民国家としての概念が 乏しいように感じられます。そんな中、かつての宗主国の言語である英語やフランス語などが公用語として使われ教育されているのです。これでは国民教育が満足に行えのな いも当然でしょう。その一方で、その公用語が世界で通用するため、せっかく教育を受けた優秀な人材が旧宗主国始め、容易に海外に流出する傾向にあります。国民教育とし ての国語、歴史、道徳の重要性を痛感しました。また、アフリカ諸国では公正な所得再分配が行われていないということも気になることです。経済成長をしてもそれが一部の人だけに留まり、その結果、貧富の差がますま す拡大するという悪循環に陥っています。血縁や利権が幅を利かせているアフリカ諸国で公正や公平という価値観はほとんど絵空事のように思えます。このことも大きな問題 です。公正なルールがないままで市場原理主義が跋扈することによる悲劇がアフリカを襲っているのです。健全な市場を作るためのルールの普及が求められています。 また、安い人件費を売り物にした工業立国は合理的ではありません。それはアフリカの気候や文化に適合しているとは思えないからです。アフリカの人々がみんなネクタイ をして会社勤めをしている姿が想像できるでしょうか。それはあり得ないでしょう。グローバリズムは、アフリカの環境を破壊し貧富の格差を助長させるだけでしょう。 こうしたことから、私は、日本のアフリカへのODAはいわゆる工業化を目指した成長を促進するものではなく、貧困克服に最大の主眼を置き、農業生産の向上や教育や医療保健衛生などの分野での援助を中心に行うべきだと思います。 また、アフリカでは、第二次大戦後、多くの国が独立しましたが、近代国家としての姿はまだ確かではありません。大航海時代から数世紀にわたるヨーロッパ諸国の植民地政策がアフリカの近代化を阻害する最大の原因であることは間違いありません。さらに冷戦時代は大国の論理に振り回されてきました。そして、 冷戦後はグローバリズムにさらされ市場原理主義の中に漂流しているのです。
日本の使命とODAの意味

旧宗主国としてのヨーロッパ諸国や、覇権国としてのアメリカやロシア、さらには中国のいわゆる資源外交やビジネスとしてのアフリカ支援など、 各国の支援の在り方はさまざまです。その中で日本は、旧宗主国でない唯一の先進国であり、同時に欧米以外で自らの力で近代化をした唯一の国でもあります。 また、日本が今抱えている外交や経済、さらには環境や教育などのさまざまな問題も、その本質は、近代主義やグローバリズムがもたらしたものです。こうしたことを考えると、アフリカへの支援はアフリカのためであると同時に、日本自身の問題解決のために大いに参考となるはずです。 ODAを通して得たさまざまな知見が日本の社会に還元される仕組みを作ることが、今一番求められているのではないでしょうか。

また、見ごろはいつか?雨が降れば散ってしまう!と、一喜一憂する季節がやってきました。「はな」といえば古代では梅の花であり、平安時代の後期から櫻の花のことを言ったらしい。万葉集には四十首くらいしか歌われていない櫻が、新古今和歌集は百を超えるようになったのは、王朝人の「もののあわれ」をつたえるものと考えられています。行きくれて木の下陰を宿とせば花や今宵の主ならまし(平忠度) 願わくば花の下にて春死なむそのきさらぎの望月のころ(西行)今、櫻といえばソメイヨシノをさすようになっていますが、瓦はヤマザクラのほうが好きです。江戸時代後期に染井村の植木屋が新種のソメイヨシノを売り出すまでは、和歌に詠まれたりしている櫻はヤマザクラです。春、葉が展葉すると同時に開花し、葉桜になりますが、個体差が大きく、同じ場所に育っていても一週間ほど開花時期がずれて、ゆっくりと花見をすることができます。また、野生種では巨木になり、雑木に混じって抜きんでて、山中で人知れず、凛と咲いているヤマザクラをめでるのもよいものです。ひょっとしたらソメイヨシノが普及する前の花見文化は長期にわたって散発的に行われていたのではないでしょうか。さて、南区で皆さんのお勧めの櫻のスポットは何処でしょうか? 瓦が好きな櫻は、久世橋通の祥鳥橋(西高瀬川と鍋取川の合流地点)の下流です。その櫻並木の中に二本の櫻を接木したと思われ、二種類の花(八重と一重だったか?)をつける櫻があります。また、その櫻の木の下には「昭和治水の防人・故木下弥次郎」なる小さな碑が建っています。一度訪れてみてください。(この碑については、後日調査を行い、その結果をこの紙面を借りて紹介したく思っています。)さて、今年の花見は、何月の何日?
お知らせ
京都南区西田後援会からのお知らせ
恒例ビアパーティー
日時:7月27日(日)17:00~
場所:新都ホテル 屋上ビアガーデン
第39回 後援会旅行会~出雲大社と玉造温泉の旅~
平成20年9月7日(日)~8日(月)
※お問い合せは西田事務所まで(075-661-6100)
旧年中は大変お世話になりました。
本年もどうぞよろしくお願い致します。
※ 昨年11月19日、父 正四位 旭日重光章 前参議院議員西田吉宏が逝去いたしましたので新年のご挨拶はご遠慮させて頂きます。

昨年夏の参議院選挙での自民党の大敗を受けて、国会は混乱が続いています。衆議院と参議院の多数派がねじれのため、重要法案が可決は勿論、審議することにも支障をきたらしているのです。
確かに、参議院で自民党が敗れた以上、民意は民主党側にあるという彼らの主張には一理あるでしょう。しかし、その民主党は何を訴えていたのでしょうか。逆に言えば何が原因で自民党は敗北したのでしょうか。
年金問題、格差社会が選挙では争点のように言われ今はインド洋での給油活動の是非が問われています。しかし、本当にこれらが対立の軸になっているのでしょうか。年金問題は、社会保険庁のずさんな管理体制や制度設計の不備の問題であり、安倍内閣の責任が問われるものではなかったはずです。格差の問題は、競争至上主義のもと規制緩和一辺倒になった結果です。この点については、私も一貫して反対してきましたが、自民党に責任があるのは当然です。しかし、民主党自身もこの間、規制緩和を訴え続けてきたのではなかったのでしょうか。元を正せば、マスコミに先導される形で自民、民主とも規制緩和を競い合った結果ではなかったでしょうか。

また、新テロ特措法の争点もよく見えていません。そもそも小沢さん自身、自民党との大連立を提案したのですから、対立の軸など存在していなかったのではないでしょうか。選挙に勝ち政権を取るための手段や方法として、ことさら対立が強調されているだけで、今の自民党や民主党に根本的な対立があるとは思えません。かつての冷戦時代のような、体制選択が問われる程の対立などないのです。そのことは国民が一番よく分かっています。根本的な対立がないから国民はその時の空気や雰囲気で与党野党を自由に選択できるのです。衆議院では自民が大勝し、参議院では大敗し、国会がねじれてしまったのはそのことが原因です。これは国民の意思がねじれているのではなく与野党とも政治の方向性を示せず、本当の意味で国民の意思を問うことが出来ていなかったということでしょう。今日、日本には与野党が対立するほど問題がないのではなく、真の問題を政党が示せていないということです。
本当に問うべきことはこの国のかたちなのです。教育、外交防衛、経済から家族の姿に至るまで、戦後の日本はアメリカをモデルにした型枠の中に押し込まれてきました。当初は押し込まれたはずのものでしたが、最近では自ら進んでその枠の中に入ろうとしています。このことがジャパンプロブレム(日本の根本的問題)の本質なのです。

ところが与野党ともこのことに目をつむったまま、目先のことばかりに対立しているのです。このことを私は一貫して訴えてきましたが、安倍総理の戦後レジームからの脱却もまさにこのことを目指していたはずなのです。残念ながらこのことは自民党のなかでもきちんと議論されませんでした。国会議員になって半年足らずですが、毎朝8時から自民党本部で行われている様々な部会に参加し、議論をしています。自民党国会議員の勉強ぶりには本当に感心しています。しかし、今の自民党ですら肝心の戦後体制そのものを根本的に問い直すということが議論出来ていないのです。むしろ戦後体制を前提としているのです。そして戦後体制を前提としているのは民主党も同じです。これでは対立の軸が国民に見えるはずがありません。
私たちひとり一人の国民生活の問題を様々な部会で議論し国会の場で解決する。これは勿論大切なことです。しかし、その大前提となっている戦後の仕組みそのものについては何の議論もしない。これでは問題の解決にならないのです。
これではまさにモグラ叩きをしているようなものです。自民党が本当にすべきことは野党とモグラ叩きを競い合うことではなくモグラの正体を見極めることなのです。
父 西田吉宏を語る ?

父、西田吉宏 前参議院議員が、去る11月19日永眠致しました。生前お世話になった多くの方々に、心より御礼を申し上げます。
突然の訃報に驚かれた方もおられたかと存じます。父は平成16年の春に肺小細胞ガンの疑いがあると言われてから3年間、入退院を繰り返しながら、闘病生活を続けていたのです。
更に、その前年の平成15年の6月には、地元京都の市議の結婚式でクモ膜下出血に見舞われたこともありました。この時は、友人で当時府議の脳外科医が運良く同席していたお陰で、直ちに手術がなされ、奇跡的に何の後遺症もなく1ヵ月後には退院し、国対委員長として政治活動の第一線に復帰することができたのです。まさに九死に一生を得たのです。父本人はもとより、家族ともども天と先祖のご加護に心より感謝したものでした。
ところが、人の世は無常なものです。その1年後に肺ガンを発病したのです。肺ガンの疑いがあるという医師のことばに目の前が真っ暗になりました。それでも、正月に精密検査の結果がでればきっと疑いは晴れる、そう信じ込もうとしていました。しかし、年明けに待っていたのは厳しい現実でした。父の病名は肺小細胞ガンであり、これは手術では治せない、余命は半年もしくは1年言われた時は、心臓が凍りつく思いがしました。
その上、ガンの治療中に脳梗塞になり、その影響で転んで背骨を骨折、また脳梗塞の根本的原因であった頚動脈の狹塞をステントで広げる手術をするなど、次々に病魔が襲ってきました。たとえ万分の1の可能性でも、必ず父を治す、このまま死なせてなるものか、家族皆のそんな思いが通じたのでしょうか、どれもが死と直結する大病でしたが全てを乗り越えてきたのです。
お陰様で、父のガンは消えました。そして、また第一線に復帰し、参議院国際問題調査会長として、海外に出張することも出来たのです。まさに奇跡は起こったのです。このまま順調に回復してほしいと誰もが祈っていました。
しかし、平成18年の秋にガンが再発したのです。しかも、肝臓にも転移しており、年内も厳しいと言われた時には神をも恨みました。家族の願いも虚しく、平成19年11月19日午後8時59分、家族に見守られ、眠るように息をひきとりました。せめてもの救いは、父に私の初当選を報告でき、自らも旭日重光章の栄に浴せたことです。
父は、祖父が長い間病床にあったため、若い時代より幼い妹弟の父代わりとして働き、高校へ行くこともできませんでした。私には、父の人生はまさに戦後日本の歩みそのもののように思えてなりません。父は昭和9年生まれですから戦争には行かなかったものの、戦後の混乱と貧困の中で家族を守り必死で生きてきた世代です。私は、そうした混乱と貧困がようやく落ち着きをとりもどしつつあった、昭和33年に生まれました。ちょうど「ALWAYS三丁目の夕日」のように、貧しかったけれど希望に満ちあふれていた時代です。その時代を引っ張ってきたのが、父の世代だったのです。父の世代は、戦後の復興という大きな使命を果たしました。そして父もまた、その使命を充分に果し、満足のいく人生であったろうと確信致します。
振り返って、今日の日本はどうでしょうか。私は、また私の世代は、その使命を果しているのでしょうか。私は、父がクモ膜下出血を患ってからのこの4年間は、特にこのことが頭から離れませんでした。
貧困から脱出し、豊かな生活を皆が送れるようにする。その為に父は、働き、生きてきました。そして、日本という国もそういう時代を乗り越えてきたのです。
そのお陰で我々は、豊かな生活をしています。勿論、様々な格差や貧困があることも事実です。しかし、それはあの父たちが必死で生きてきた時代とは、根本的に違います。今日の問題は、物質的な豊かさの崩壊というより、父の世代が必死で守ろうとしてきた家族や国という人が人として生きるための根源的なものが崩壊し、涸渇してきていることではないでしょうか。それは、ある意味で人間や国家の存在意義の希薄化ではないでしょうか。
何度も死の淵に立たされ、その度にそこからはい上がってきた父。父が本当に伝えたかったのはこのことではなかったのかと思います。もう一度、人間や国家の本質を見つめ、国と人間としての力を取り戻す。これが残されたものの使命だと思うのです。

炬燵(こたつ)、火鉢(ひばち)、行火(あんか)。これらは、かって我々が冬場に暖を取っていた道具です。
炬燵(こたつ)は禅宗の僧侶が中国から持ち帰った物とされています。当時、寺院や武家では火鉢(ひばち)が客向け用の暖房器具で、炬燵(こたつ)は家庭用であって庶民の暖房器具でした。炬燵の熱源は、古くは木炭、豆炭、練炭などですが、現在では電気が主流になっています。床から足をおろせる堀炬燵(切り炬燵ともいう)タイプと、床が平面のままの置き炬燵タイプに分けられます。櫓(やぐら)の上に炬燵(こたつ)布団をかけて、布団の中に手足を入れて暖を取ったものです。3丁目の夕日の昭和30年代の冬に寝る時の暖房は、この炬燵を中心に布団を敷き、足を入れて寝たものです。
この置き炬燵(こたつ)の一種で、おおきな櫓(やぐら)の代わりに、焼物か小さな櫓で囲ったものが行火(あんか)です。写真のような形をしており、カルメラ焼きのお菓子に「おこた」が在りますが、この形を見立てたもののようです。
瓦も小学生のころ、炬燵(こたつ)を中心に十字状に布団を引いて寝た記憶があります。炬燵(こたつ)の中には炭や豆炭が入っており、むやみにけとばせん。お行儀よく寝なければならず、決して暖かかった想い出はありません。そこへ「豆炭あんか」なるものが登場してきました。豆炭1個で朝まで暖かく、おまけに蹴飛ばしても大丈夫。何よりうれしかったのは自分だけの「マイアンカ」が出来たことです。これまで炬燵の位置関係で隙間風が入る場所で寝ていたものが何処でも自由に寝る場所を選べるようになったのです。当時,「マイアンカ」は冬の暖房器具の大革命のような記憶があります。
ところで、この豆炭あんかはもう生産中止になっているだろと思っていたら、インターネットに出ており、「品川あんか」から標準価格¥2,250で出ています。
さて、この豆炭なるものですが市内ではなかなかお目にかかれませんが、郊外のホームセンタに行けば、まだ販売しています。この豆炭、1920年(大正9 年)大阪の川澄政が発明し,ミスジ豆炭の商標で売り出されました。石炭、木炭、亜炭などを粉末にして接着剤(主に石灰)に混ぜた後に、角に丸みのある正6 面体状に固めたものです。色と形がよく似たものに炭団(たどん)がありますが、こちらは木炭の粉をふのりで固めたもので歴史的には豆炭の先輩に当たります。
灯油が高騰しているこの冬、暖房機器を見直してみてはいかがなものでしょうか。部屋全体を暖める機能はありませんが、いったん足を入れるとなかなか抜け出せなくなる炬燵に、家族身を寄せ合いながら暖を取るのはいかがでしょうか。もちろん寝る時はマイ豆炭行火(あんか)で。(今回の暖房器具の漢字は,かなり難解なモノが多く,瓦も漢字検定を受けている気持ちで書きました。)
お知らせ
恒例の新春おでん会は都合により本年は中止させて頂きます。
京都南区西田後援会 第39回旅行会
~出雲大社と玉造温泉の旅~
平成20年9月7日(日)~8日(月)
第95回 昌友塾のご案内
平成20年 1月28日(月)
会場:六孫王会館 時間:PM7:00~9:00

自民党にとっては歴史的惨敗と言われた、今回の参議院選挙でした。こうした逆風にもかかわらず、362,274票という思いがけぬ得票で当選させて頂きました。
その一方で、全国では多くの同志が落選の憂き目に遭いました。特に1人区では6勝23敗と惨敗でした。何故こうした結果になったのか、また今後、自民党はどうあるべきなのか、私なりの考えを述べたいと思います。
敗因は何か
今回の選挙は、選挙前から年金問題が争点といわれてきました。確かに、年金問題は敗因の一つであると思いますが、むしろ、その背後にある政治不信が敗因ではなかったかと思います。年金に対する国民の不信は、取りも直さず、自分の老後の不安と直結します。そして老後の不安は、年金という経済的基盤の問題だけでなく、国の将来に対する不透明感、不信感に原因があったのではないでしょうか。
一人区現象と言われる様に、郡部において自民党は惨敗しました。戦後一貫して、都市部へ集中投資が行われてきましたが、時にバブル崩壊後その路線に拍車がかかり、結果として郡部の疲弊は決定的になりました。郡部の反乱はそのことに対する報いであると言えます。
一方、都市部においては、人口は増加し、一見発達している様にも見えますが、現実には多世代にわたる定住人口は少なく、地域に対する意識は希薄化するばかりであり、決して正常な姿とは言えません。このことは、戦後半世紀以上にわたって、都市部においても郡部においても、地域のコミュニティーの破壊を続けてきたということを示しているのでは、ないでしょうか。
本来、自民党は、保守政党であり、一つの階層に偏らない国民政党であります。その支持基盤は、まさにこの地域コミュニティーにあったのです。これを半世紀にわたって破壊した結果が、今日の自民党惨敗の根本的原因であると私は考えています。そして、このコミュニティー破壊が日本の将来に対する不透明感、不安感の原因になっているのです。自民党再生のためには、都市と農村のコミュニティーの再生が必要であり、それは真に日本の再生でもあります。
そのために必要なことは、都市においても農村においても、何世代にわたって暮らしてゆける仕組みの確立です。つまり、家族や地域の再生ということなのです。具体的には、都市においては、多世代住宅の建設であり、家族の再生です。農村においては、家族を養えるだけの産業基盤の確立であり、そのためには農林水産業、地場産業の振興は不可欠です。
バブルが日本の崩壊に拍車をかけた

こうした現実を考えれば、遅くとも平成に入ってからの日本では、経済復興、経済成長という路線から地域社会や家族の再生へと、政治の方向が転換されるべきであったはずなのです。
ところが残念ながら、こうした戦後政治に対する反省がないまま、日本はバブルとその崩壊の時代を迎えてしまったのです。この十数年は、その後始末のためのまさに失われた10年でした。目先の経済成長のために、またしても都市への集中投資に拍車がかかり、同じ過ちを繰り返したのです。
小泉改革もこうした考えの延長線上にありました。その意味で構造改革とはいえ、戦後の「枠組」の構造を変えるものではなく、むしろ、戦後政治の完成を意味するものではなかったでしょうか。
民主党の訴えたものは何か
こうした国民の不安や不信を察知し、選挙戦略としたのが、民主党です。民主党は結党以来、二大政党制が唯一の理念で、具体的政策では自民党との差異が少ないことが、逆に国民への「売り」であった政党です。小泉政権が「構造改革」を唱えていた頃は、改革のスピードを競おうと主張していたことでも明らかなように、小泉改革と全く同じ路線を訴えてきたのです。
ところが、先の郵政選挙では自民党が圧勝し、逆に民主党は大敗しました。そこで、同じ路線では結局、政権党に有利になるだけと判断したのか、今回の参議院選では今までの主張を変え、格差問題などの小泉改革の矛盾点を突くことに徹底したのです。もとよりこれは、保守政党として自民党が本来主張すべきことであり、戦後の経済至上主義からの脱却として必要なことでありました。これに年金問題や、さらに閣僚などのあまりにも自覚に欠ける言動が追い打ちをかけ、自民党は惨敗したのです。
安倍内閣の目指したもの
安倍総理は、当初より戦後レジームからの脱却を掲げていました。それは、私が府議会の時代より訴えてきた、戦後体制の解消と同じ意味であったと思います。戦後の占領時代、日本人に主権のなかった時代に作られた、憲法や教育基本法、自衛隊に象徴される戦後の仕組みや考え方に対し、日本人の伝統や精神を基軸にした制度に変えていくことを堂々と主張されたことは、評価に値すると私は考えます。また、それに間違いはなかったと、今も確信をしています。
しかし、こうした安倍総理の考えが国民に十分に伝わらなかったことも事実です。その原因のひとつに、自民党の中で、こうしたことが十分議論できず、生煮えの状態であったことが挙げられます。本質的には小泉内閣とは改革の方向が違うにもかかわらず、郵政選挙で大勝した後の総裁選であったため、誰も小泉改革の是非について真正面から議論できませんでした。むしろ、小泉改革の後継者としての立場を取らざるを得なかったということが、安倍内閣の最大の弱点ではなかったでしょうか。今回の選挙では、まさにこの弱点を民主党に突かれたのです。
自民党再生のために

今回の選挙で残念ながら自民党は大敗しました。我々はこの事実を真摯に受けとめなければなりません。自民党再生のために必要なものは、まず、確かな歴史観であることは言うまでもありません。目先の政局や、「改革という魔法の言葉」で思考停止をしていては、自民党のみならず、この日本の国が崩壊してしまいます。
今までタブーにされてきた小泉改革の是非はもちろん、戦後政治そのものについて、根本から問い直すことが必要なのです。また、こうした議論は、自民党のみならず民主党をも巻き込む必要があります。衆議院と参議院とで多数派が異なる現実を考えれば、こうした議論は当然必要です。むしろ、小泉改革の矛盾を民主党は訴えただけに、彼らも今まで通りの改革を叫んでいるわけにはいかないのです。
安倍総理には、今一度、戦後レジームからの脱却を掲げていただき、その現実をしっかりと国民に訴えていただきたいと思います。
「伝えよう、美しい精神(こころ)と自然(こくど)。日本の背骨を取り戻そう!」は私の府議の時代からのスローガンであり、「地方の叫びを国政へ」は、父 吉宏のスローガンでした。これが、日本の再興と自民党の再生のために、今まさに必要な言葉であることを改めて感じています。国政の場で全力でこれに取り組むことをお誓い申し上げます。今後ともよろしくお願い申し上げます。
地域の絆を育むために
京都府議会議員
昌友会 秋田 公司

7月の参議院選挙では、自由民主党にとっては、大変きびしい逆風にもかかわらず、西田昌司参議院議員を誕生させていただきました。
私は、17年前に昌司議員と一緒に、昌友会を立ち上げ、自国の歴史を大切にし、自立を考えることを活動理念として、様々な地域活動を展開してまいりました。家庭の絆や、地域の絆をもう一度取り戻すためにはどうしたらよいのかを常に考え、毎月の昌友塾でも真剣な議論してまいりました。この昌友塾もまもなく 100回目を迎えます。
こうした地道で真剣な活動を続けていく中から、私も府議会議員として送り出していただくことになり、また同志となる地方議員も誕生してまいりました。
しかし残念ながら、地域コミュニティは、グローバルな競争社会の到来とともに、崩壊の一途をたどっています。また、家族や地域の友人と共に時間を共有するも、ますます少なくなってきています。
昔より、稲荷祭り、祇園祭り、五山の送り火などの伝統行事は、多くの人たちが支えあって、幾年にもわたり伝え、守られてきました。また、各町内の地蔵盆も、隣近所のお年寄りから様々なことを教えてもらいながら、幼い子供達もいっしょになって楽しんできました。これらの地域を支えてきた人たちの多くは、お百姓さん、商店や町工場のおじさん、おばさん達でしたが、社会構造の変化が進む中で、身近にこれらの人々の姿が見られなくなってまいりました。このままでは、地域の衰退が進むばかりです。
新たに地域の活性化を図るには、現役サラリーマンや定年後の人たちに若者たちも加わった、新たなコミュニティづくりが必要だと思います。私も新しい地域の絆を再生するため、自ら行動しようとする人たちとともに、先頭に立って新たな地域づくりに取組んでいこうと考えています。
西田昌司参議院議員には、国政の場でも、家族の絆、地域の絆を大切にしながら、国と地方のバランスの取れた社会を実現し、国民ひとりひとりが幸せを実感し、若者が将来に夢と希望が持てるような国づくりを目指していただきたいと思います。そのためにも、皆様の昌友会活動への一層のご協力をよろしくお願い申し上げます。
瓦の独り言
-モノづくりの楽しさ-

団塊の世代の大量退職により「技術の伝承」という問題が騒がれています。建設業界の印刷物に「どのように技術を伝えていくのかということも大切だが,いかに若い人たちに自分でやろうという気持ちにさせることが大切」と,また「そのためには上司・先輩たちが若い人にドンドン仕事をさせ,モノづくりの喜びや仕事の楽しさを伝えてゆくことが大きな課題」と括っている。
しかし「モノづくりの楽しさ,喜びは」大上段に構えることなく,家庭での親子のふれ合いで伝えられてきたように思います。台所の母親の横でジャガイモの皮をむいたり,日曜大工の「犬小屋つくり」で父親とペンキ塗りをしたり,お爺ちゃんの畑でサツマイモを掘り出したり,色々なお手伝いをすることによってモノつくりの入り口をうろうろしていたような気がします。お手伝いが恥ずかしい思春期の中高生になってもモノつくりの楽しさは覚えていて、瓦自身もアルバイトではモノつくりに関係する事業所を選んでいました。
今,小学校ではお手伝いを薦めていますが,親はお手伝いよりも勉強している姿を喜んでいる様子です。テレビコマーシャルでよく遊び・・・。といったキャッチフレーズが流れていますが,何か取って付けたような虚しさを感じます。額に汗して働く喜びを小学生時代に植え付けておけば,冒頭のような危惧の必要は無いと思っています。
(財)日本青年研究所の「高校生の日常に関する調査」の「職業観」に関する調査結果では「日本人は平和で豊かな生活環境にあるので軟弱と思える」といった結果が報告されていますが,『高校生の職業観』(表)を見てみると、額に汗して働くことを嫌っている高校生は1/4で中国,アメリカより少ないことは,まだまだ今の高校生も捨てたモノではないと瓦は思っています。
高校生の職業観
肉体労動に就きたくない
日本:26.7
米国:46.8
中国:70.2
他人より給料の高い仕事に就きたい
日本:73.6
米国:53.3
中国:28.4
偉くなると責任が重いのでいやだ
日本:51.0
米国:16.4
中国:36.5
統一地方選挙から見えてくるもの

去る4月に施行された統一地方選挙では、私の後継者秋田公司さんをはじめ、大勢の同志の方々が議席を獲得することができました。大きなご支援を賜ったことに心より御礼申し上げます。しかし、その選挙結果は、必ずしも順風満帆というものではなく、予想外な方が落選され、大事な議席を失ってしまったものもいくつかありました。その一方で民主党は議席を増やし、共産党も地力を見せつけるものでありました。京都では、自民党とともにこれらの政党の勢力が、非常に拮抗していることを改めて思い知らされた気がいたします。
何故、民主党が躍進したのか
今回の選挙では、民主党が躍進したと云われています。確かにその通りですが、これは今回に限ったことではなく、以前から民主党が自民党と肩を並べる力を有していたと、私は考えています。現に府内選出の国会議員の数では既に同数になっているのです。むしろ、国政選挙に地方選挙の結果も近づいてきたということでしょう。地方選挙で自民党が強かったのは、民主党が若い政党ということもあり、地方議員にまで候補者を揃えることが出来なかったためであり、候補者が出そろってきたところでは、着実に議席を増やすことに成功したということでしょう。
有権者は民主党の何を支持したのか
民主党はマニフェストなのでも様々なこと主張していますが、その多くは、自民党の候補者のものと大差があるようには思われません。結局のところ、彼らの目的は政権交代であり、自民党に代われる政権政党ということが一番の売りであるし、それが彼らの立党の精神でしょう。有権者も、その政策と云うより、自民党に代われる政党がある方が日本の社会にとって健全なのだという理由で投票された方が多かったのではないかと云う気がします。そういう意味では争点なき選挙であったのかも知れません。
自民党の立党の精神は何か

では、自民党の立党の精神は何だったのでしょうか。それは、第一に戦後の貧困を克服することであり、第二に絶対に共産主義や社会主義から国民を守ることであり、第三に憲法をはじめとする戦後体制からの脱却であったと、私は思っています。このうち前二者は既にその目的が果たされ、残るのは戦後体制からの脱却であったはずなのです。ところが、この問題は、自民党の立党以来の悲願でありながら、日の目を見ることがありませんでした。長い間、憲法改正ということ自体が国民の中でタブー視されてきたこともあり、経済成長と反共という当面の課題ばかりにとらわれて、自民党自身もこの問題に封印をしてきたのです。
戦後レジームからの脱却
最近、安倍総理が「戦後レジーム」からの脱却という言葉をよく使われます。そして、それが参議院選挙の争点あるとも言われています。レジームとは制度や政体という意味ですが、これは正に、私がこのshowyouの中でも訴え続けてきた「戦後体制」からの脱却という言葉と同じ意味であろうと思います。
戦後体制とは何か
それを一言で言えば、日本はいまだに戦後の占領時代に出来た法律や制度、ものの考え方に縛られていると言うことです。そうであるにも拘わらず、殆どの国民がそのことを知らないと言うことです。つまり、国民が意識していない内に占領体制が続けられているということです。
その象徴が憲法です。かつては、改憲などは全くのタブーでありましたが、最近では改憲を支持する国民が五割を超えるとの報道もあります。またそのことを反映して、憲法改正の手続きを明確にするために国民投票法も議論され、今国会には成立をするようです。国民の意識が変わってきたことは事実です。しかし、私は、憲法の問題点が国民にきちんと示されているとは思いません。
かつては、憲法上は軍事力の放棄を明言しているのにもかかわらず、自衛隊が存在するのは問題であるというのが一般の論調でした。それが今や、北朝鮮や中国の脅威など国際情勢の現実を考えれば自衛のための軍隊を保持するのは常識で、それを憲法上明確にすべきだという風に様変わりしています。国民の意識のこうした変化は歓迎すべきことではあります。しかし、では何故、憲法と自衛隊という矛盾が存在するのかという根本的なことは何一つ論じられていません。私は、たとえ憲法を改正したとしてもここを述べなければ、全く意味がないし、戦後体制からの脱却は出来ないと考えています。
憲法や自衛隊は誰が作ったのか
Showyou紙上で何度も述べてきましたように、憲法も自衛隊もともに占領中の主権のない時代にアメリカの命を受けて作られたものです。憲法と自衛隊との矛盾はアメリカの占領政策の矛盾を示すものです。占領前期は共産主義を容認し、日本の非軍事化を目指しながら、朝鮮戦争により共産主義の脅威を知り、日本に再軍備を命ずるというアメリカの占領政策の矛盾が、今日の日本で憲法問題といわれているものの原因なのです。日本人に主権のない占領時代はいざ知らず、それが終わった今日までも続いてきたこと、さらにはこうした事実が国民の前に示されていないことが根本的な問題なのです。つまり、いまだに占領体制が続いているのです。
憲法の問題点は自衛隊だけではない
府議会議員の時代から、私はこの憲法をはじめとする戦後体制の問題を常に訴えてきました。それは、安全保障の問題だけでなく、教育や子育て福祉といった身近な問題も、根本的な考え方はすべて憲法に起因するからなのです。
教育や子育てや福祉の問題は、日本人の家庭観と密接な関係があります。健全な家庭の存在があっての教育政策であり、子育て支援であり、福祉政策なのです。問題はその家庭の姿が戦後急速に変化をしてしまい、崩壊の危機にあるということです。例えば、サザエさんやちびまる子ちゃんもかつてはどこにもあった家庭の姿です。今やあのような大家族は、都会では殆ど見られなくなりました。あのアニメが長寿番組となっているのは、国民の多くがそこに郷愁と安らぎを感じるからです。多くの国民が、幸せのかたちをそこに感じていると言うことでしょう。
家庭の崩壊と憲法との関係
ところが現実の社会では、家庭が崩壊し、殺伐とした事件が報じられています。家庭の崩壊を放置したままでは、教育も子育ても福祉もあり得ないのです。では何故、これほどまでに家庭が崩壊したのでしょうか。その原因はいろいろありますが、少なくとも、日本人の原風景である大家族や家制度を崩壊させた原因が憲法にあるのは間違いありません。第24条には「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」また、その第二項において「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。」と書かれています。
ここに書かれているのは、婚姻に必要なものは個人の尊厳と両性の平等だけで、それ以外は認めないということです。このどこにも家族の姿は出てこないのです。憲法を作ったアメリカ人には、日本の家制度は封建的で解放されるべきだと思っていたからなのです。
勿論、家族の姿は時代によって変わるものです。昔からのものがすべて正しいと言う気はありません。しかし、少なくとも他民族によって家庭はこうあるべきだなどと言われる筋合いは全くないのです。問題はこのことを国民の誰も意識をしないままに、その縛りの中で生活をし、もがき苦しんでいる人がたくさんいると言うことです。
日本人の幸せのかたちは日本人が自ら作るものであり、他国により作られるものではないのです。そのためには憲法による縛りを超えなければならないのです。
政治家の使命
国を守り、国民を幸せにするのが政治家の使命だと私は思います。国を守ることを放棄し、国民の幸せのかたちまで他国に依存していては、日本に政治は存在しないということになります。そうならないために私は頑張りたいのです。
府議会議員当選にあたり
京都府議会議員
秋田 公司
このたび皆様の大きなお支えをいただきまして、府議会議員として活動させていただくことができるようになりました。自らの主張、思いを皆様に分かっていただこうと、早くからたくさんの方々とお出会いさせていただき、毎日毎日訴えをさせていただいてまいりました。選挙を通じ、それまでにも増して多くの方々に耳を傾けいただき、ふるさとを愛し、この街を良くしたいと思う私の思いを分かっていただくことができたのではないかと思っております。
当初は、昭和46年に西田吉宏参議院議員が府議会に初当選以来、30有余年にわたり守ってこられたこの南区の地盤を西田昌司府議の後継として受け継ぐという重責に、身の引き締まる思いと何とも言えない不安で一杯でした。しかし、今では「この街と人がすき」という私自身の思いを皆様に分かっていただき、共感をいただいたことを確信いたしております。
選挙期間中は、より良い地域をつくりはどうあるべきかを訴えてまいりました。地域を自らが進んで盛り立てて行こうとする人々の力を集めるための仕組み(プラットフォーム)つくりを推進することをお約束いたしました。
この仕組みをどのように創っていくかについても多くに方々の知恵を結集して取組まなければならないと思っております。今まで中小企業経営者として、中小企業同士が高め合い支え合いながら、地域に根ざした産業の創出を実践してきましたが、今後は、これらの経験を活かして、地域社会を活性化できる新たな仕組みづくりにチャレンジしてまいります。
人々が自分たちの能力を発揮し、生き生きと暮らせる社会づくりを進めるためには、産業振興、福祉、教育などさまざまな課題があります。
これからは、自らが先頭に立って、多くの皆さんの声に耳を傾け、やってくれるのを待つのではなく、自らが始めようとする人たちと共に、より良い地域社会づくりはどうあるべきかを皆様とともに真剣に考え、活動してまいる所存でございます。
どうか、皆様のご指導、ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。
統一選挙を振り返って
南区西田後援会
会長 米田忠雄
この度の統一地方選挙は、西田昌司府会議員の後継として秋田公司君が出馬し、私も事務長として9日間を共に全力をつくして参りました。
西田吉宏議員から昌司議員と10期37年にわたり後援会として守ってきた南区の府議席を、秋田公司君に無事に継承できましたことは、ひとえに皆様の力強いご支援があってこそでございます。
今回ご支持頂きました九千二百人余りの方々に心から感謝申し上げますとともに、秋田公司君が地域住民の方々に耳を傾け、謙虚な気持ちで、南区を始め、京都府発展のため、がんばって頂くことを心から念願いたしております。
樋のひと雫
羅城門の樋
-ボリビア通信-
統一地方選挙も終わり、新たな政治地図が誕生しました。このボリビアも地方選挙で熱く燃えていますと書ければよいのでしょうが、そうは上手く行きません。1昨年大統領選と同時に地方選挙も行なわれました。現在ボリビアでは建国以来、初めて先住民出身の大統領が政治を行なっています。彼の政策の基盤は「脱植民地化」であり、経済政策では地下資源関係企業の国営化に乗り出しました。そして、ベネズエラのチャペス・キューバのカストロ・ボリビアのエボと言えばラテンアメリカの社会主義3羽烏のように言われています。
しかし,生活をしていると「社会主義」という物堅さや息苦しさは現在のところ感じません。むしろアンデス民族の文化の復興のような躍動感が感じられます。思えば、「スペインからの独立」といっても先住民にとっては経済の仕組みは何も変わりはしませんでした。独立の恩恵を受けたのは少数の白人支配層(植民地貴族やプランテーションの大農場主)であり、彼らと先住民との間の隷属関係は依然残されたままでした。欧米が工業化社会へと変身し都市労働者の権利拡大と民主化が進んでも、工業資源の原産輸出国という位置づけが変わらなかった南米では「大農場主と農奴」や「鉱山主と隷属的鉱夫」という関係は、白人支配層と先住民族という歴史的背景の中で生き続けてきたと言えます。
フェデル・カストロがバティスタ政権を武力で倒した1ヵ月後、初めて外遊した国はアメリカでした。当時、アメリカ資本のプランテーションを接収し、農地解放を行なったフェデルを「コミュニスト(共産主義者)」として拒絶し、追い返したのもアメリカでした。その後、彼は革命を守るためにソ連に近づきますが、ボリビアの資源国有化を「社会主義」の再来のように受け止めるのもどうかと思います。日本のマスコミが中南米を「左傾化」として捉え、「社会主義の復活」かのように論調しているのもどうかと思います。確かに、白人国家のチリにも社会主義を標榜する政権でき、ニカラグアにも旧サンディニスタが復権しました。しかし、このいずれもが昔のマルクス・レーニン主義の復活を画しているかとなると疑問です。
多くの国と国民がアメリカの「裏庭経済」から脱しようと意図していることは事実でしょう。その一つがベネズエラのチャベスに代表されるようなブッシュに対する「悪態」でしょう。国連総会でチャベスがブッシュを「アホ馬鹿」呼ばわりをすれば、ベネズエラの外務大臣をニューヨークの空港で手荷物検査に託けて、長時間拘束し飛行機に乗れなくするなど、どうも子どもの喧嘩と様相が似ています。いくらアンデス文化の象徴だと言っても、コカ栽培の自由化もアメリカの政策に「楯を付く」以外のものではなさそうです。(尤も、エボ大統領はコカ栽培農家の代表ですので、ゼロ政策は出来ないでしょう。彼が大統領になってから、空港での手荷物検査が厳しくなりました。)
中南米が名実共にアメリカの「裏庭」から脱するには、経済の自律と国の繁栄は欠かせません。この一つの通過点が「左傾化という名の国の独立」かもしれません。国の発展は一つの道筋だけではないのでしょう。4年後の大統領選が今から楽しみなのは,私一人ではないでしょう。
昌友塾
第91回6月12日(火)
会場:六孫王会館
時間:PM7:00~9:00
何故、教育基本法を改正しなければならなかったのか
教育基本法が改定されました。昨今のいじめやそれによる自殺、また親が我が子を虐待し死亡させるなど、日本の教育に問題があるのは誰の目にも明らかです。従って、その大本になっている教育基本法が改正されるのは当然のことです。 何故、教育基本法を改正しなければならないのかということについて、自民党のホームページには次のように書いてあります。
『連合国占領下で制定された教育基本法はGHQの影響を受けているといわれています。我が国の伝統や文化に根ざした真の日本人の育成のため、教育基本法の改正は、憲法改正と並んで自民党の結党(昭和30年)以来の悲願でした。
昭和22年の制定以来一度も改正されていません。現在までの約60年間に、教育基本法が前提としていた経済社会や国民生活の状況が、大きく変わりました。教育水準が向上し、生活が豊かになる一方、都市化や少子高齢化の進展など、教育を取り巻く環境は大きく変わりました。
また、近年、子どものモラルや学ぶ意欲の低下、家庭や地域の教育力の低下など教育全般に様々な問題が指摘されており、若者の雇用問題も深刻化しています。
更に、戦後社会や教育現場においては、個性の尊重や個人の自由が強調される一方、規律や責任、他人との協調、社会への貢献など基本的な道徳観念や「公共の精神」が、ややもすれば軽んじられてきました。
その結果、ライブドアの決算粉飾事件や耐震偽装建築問題に代表される拝金主義やルール無視の自己中心主義が、日本社会や日本人の意識の中に根深くはびこり、日本の将来を危うくする事態に陥っています。特に人口減少社会の進行、アジア諸国の台頭・発展などを鑑みれば、こうした問題に一刻も早く手を打つことが、我が国の存立のための喫緊の課題といえます。
こうした問題の根を断ち切り、我が国の社会や日本人が真に拠るべき教育を確立するためには、教育の根本にさかのぼった改革が必要です。このため、教育の根本法である教育基本法を改正し、わが国の伝統や文化に拠りつつ、今の時代にふさわしい教育の基本を確立し、これに基づき教育改革を進めていくことが、今、求められています。』
以上の理由により教育基本法は改正されたのです。私もこれには当然賛成ですし、教育基本法の改正により、教育が再生されることを大いに期待するものです。
生命至上主義が利己主義の蔓延を招いた

学校では、いじめによる自殺などの事件が起きるたびに全校集会がなされます。そして、校長先生が、命が如何にかけがえのないものか、命が如何に大切なものかということを、再三にわたり生徒に諭しておられる様子がテレビや新聞などのマスコミを通じて報じられます。私は、こうしたニュースを見るにつけ、戦後教育の限界を感じていました。何故なら命の尊さを教えるだけでは子供達は救えないと思うからです。
確かに、命はかけがえのない大切なものです。しかし、本当に教えなくてはならないものは、その大切でかけがえのない命を何のために使うかではないでしょうか。そのためには、命より大切なものがあるということを教えることが必要です。ところが、戦後教育では、命こそが大切だとしか教えてきませんでした。自分の命が何よりも一番大切だと教えられた結果、利己主義が蔓延することになったのではないでしょうか。
しかし、現実の社会はそのような考え方では成り立ちません。事実、私たちが今ここにいるのも我々に両親がいて、その両親が自分の命に代えても、との思いで私たちを育ててくれたからに他ありません。また、時として、友人が身を挺して自分を守ってくれたこともあったはずです。そして、何よりも先人が我が身を捨てても、次代の子孫を守ろうとしてくださった尊い行為の延長線上にこの国があるのではないでしょうか。正に社会はお互いが守り合い支え合うことにより成り立っているものであり、そうした命の積み重ねの上に国があるのです。
ところが、戦後社会においてはこの当たり前のことがタブーになってしまいました。先の大戦により三百万人を超える日本人が命を落としました。特に、東京や大阪の大空襲や広島・長崎への原爆投下により、一瞬で何十万人もの無辜の民の命が失われました。これは日本人にとって忘れられない恐怖体験であり、日本人の精神の上に大きな傷を与えたことも無理からぬことです。その結果として生命至上主義=平和主義として日本人に受け入れられてきたのでしょう。
徳育とは命を超える価値を教えること

いじめや虐待が行われる度、道徳教育の重要性が言われますが、子供達に教えるべき道や徳とはどのようなものを言うのでしょう。私はその中で最も尊いものは、他の人が生きるために自分の命を犠牲にする行為だと思っています。友人のためであったり、家族のためであったり社会や国のためであったり様々なケースがありますが、それらは、古今東西を問わず具体的な物語や歴史として後世に伝えられてきたはずです。従って、どの国でも徳育において最も重要なのはその国や民族の歴史・物語を教えてきたはずです。
ところが、戦後社会ではこうした当たり前のことがタブーになってしまったのです。敗戦のトラウマ(心の傷)と歴史観の喪失により、先人が何のために戦ったのか、何のために死んでいったのかという先の大戦の大義を日本人は忘れ、戦争の恐怖の記憶ばかりが強調された結果、生命至上主義に陥ってしまったのです。そして、民族の歴史や物語は忘れ去られてしまいました。
むやみに生命を奪ったり、すぐに武力に訴えたりする様な野蛮な行為には、私はもちろん反対です。しかし、単なる生命至上主義に陥ってしまっては家族や友人、社会や国を誰も守ることが出来なくなり、その結果、自分自身の存在をも否定してしまうことになるのではないでしょうか。
また、生命をかけるものとして、時として美や芸術、職業ということもあるでしょう。使命という言葉があるように、自らの生命を何のために使うか、それを見つけることが生きるということであり、それを教えることが徳育なのです。つまり、命を超える価値があることを教えることが徳育なのです。
しかし残念ながら、自分の命こそが大切だという生命至上主義に陥ってしまった結果、命は守るべきもので、かけるべきものではなくなってしまいました。その結果、家族や友人、社会や国を守る人はどこにもいなくなってしまったのです。徳育という言葉はあっても、それを具体的に教える言葉をなくした結果、この国から徳は消失してしまったのです。これが今日の教育における最大の問題ではないでしょうか。さらに問題なのは、この事実を日本人が直視しなかったことです。むしろそのことを正当化させる生命至上主義という理屈を正しいものと思い込んできたのです。しかし、それは所詮、屁理屈でしかありません。「人ひとりの命は地球より重い」などというのはその典型です。よく考えてみれば、これほど尊大で自己中心的な発想はありません。徳育をおこなうためには、こうした戦後教育の実態をまず直視することが必要なのです。
法律では価値観や精神は変えられない
真の徳育を行うためには、生命至上主義から脱却しなければなりません。しかし、これは法律ではなくて価値観、考え方の問題です。教育基本法を改正したからといって直ちに解決でき得るものではありません。日本人ひとりひとりが戦後教育の根本的問題点を知り、その呪縛から抜け出さない限り解決の方法はないのです。そのために、私はこれからも戦後の占領時代に作られた様々な法律、政策、ものの考え方などの問題点を皆様に伝えていきたいと思います。これからも、ご支援をよろしくお願い申し上げます。
活 動 報 告
自民党南支部青年局長
秋田 公司
新年明けましておめでとうございます。
皆様に健やかな新年お迎えのこととお慶び申し上げます。
2006 年10月かねてより、私が念願いたしておりました。西田昌司府議会議員の後継として、自由民主党から公認されました。私もこれまで以上に今後とも皆様と共に、南区、並びに、京都府の発展に尽力していく決意であります。平成5年から、昌友会会長として、産業振興、福祉、教育改革などの様々な課題に取り組んでまいりましたが、今年は、自ら先頭に立って、より良い地域社会づくりはどうあるべきかを真剣に考え、活動してまいる所存でございます。
そのためには、先ず、中小企業が活性化し、意欲ある起業家が育つべく地域環境が整備され、産業と人の暮らしが調和した街づくりを進めなければならないと考えております。
また、お年寄りや家族が安心して過ごせるように、行政と家庭、地域が一体となった福祉社会を構築すべきだと思います。暮らしに夢と生きがいをもって、地域のために自ら行動する人たちと共に、活力あるコミュニティづくりを進め、中高年が生きがいをもって参画できる社会を目指すことが大切です。
心の豊かさ、やさしさは、家族のふれあいの中で育まれるものですが、一方、教育施設の充実とともに、子供たちと学び、遊べる環境も整えなければならないと考えております。
その他、種々課題は、山積いたしておりますが、今後とも、地域社会に役立つべく、微力ながら活動を続けてまいる決意でありますので、ご支援ご鞭撻賜りますようお願い申し上げます。
謹んで新春のお祝いを申し上げます
参議院議員 西 田 吉 宏
皆様には日頃より温かいご芳情とご支援を賜り誠にありがとうございます。 私もこれまで府政18 年の実績のもと、参議院議員として大蔵政務次官を始め、参議院国会対策委員長、国際問題調査会長等、幾多の国政における重責を果たして参りました。過日、 165臨時国会において教育基本法等審議可決される等、多忙を極めておりますが、昨年6月、誠に残念ながら健康上の理由から本年7月までの任期をまっとうした後、政界を引退することを表明致しました。残るこの在任期間につきましては皆様の「声・思い」を国政へ届ける架け橋となり、信頼される政治と生活の安定実現に向け最大限の努力をしてまいる所存であります。なお、この度西田昌司府議会議員が昨年9月私の後継として自民党京都府参議院選挙区第四支部長として党本部において公認されました。多くの方々にご支援を賜った暁には、必ずや皆様方を始め、京都府、日本のため課題解決に向け全力を傾注しお役に立てるものと確信致しております。何卒、会員各位皆様方の温かいご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
結びに、皆様方の一層のご健勝とご多幸を祈念申し上げ、新年のご挨拶と致します。(国政報告)
来夏、自民党公認 参議院議員候補に決定!
去る9月5日、私が来年の参議院議員選挙の自民党公認として、正式に決定を致しました。以下に、私の目指す政治の在り方について簡潔に述べたいと思います。
伝えよう!美しい精神と自然日本の背骨を取り戻せ!
日本の何が問題なのか?・・・・戦後日本における歴史観の喪失
私は、現在日本が抱えている問題の多くは、戦後日本が築き上げてきた様々な仕組み(いわゆる戦後体制)の機能不全や矛盾が現れているものと考えます。ここで、私の考える戦後体制とは、次の3つのことに象徴される社会の仕組みや考え方のことです。
? 戦後憲法による平和主義と、それに基づく日米安全保障条約による外交安保体制を無条件に前提とすること。
? 個人の自由や権利を偏重し、義務や道徳、家族、社会とのつながり、公の精神など、伝統や文化、歴史に根ざすものを軽視する風潮。
? 物質的豊かさを重視する経済成長追求が、金銭中心主義へ至ったこと。
今日の日本は、戦後六十年を経たにもかかわらず、いまだに政治や外交の機軸をアメリカに依存しているだけでなく、価値観や考え方までアメリカをモデルにする仕組みになっています。言い換えれば、背骨を失い、自立できない状態にあるのです。ところが、その自覚が大方の日本人にはありません。そのため、こうした政治の本質に関わる議論ができないままに今日を迎えています。これこそが、いわゆるジャパン・プロブレム「日本問題」の本質ではないでしょうか。
こうした基本認識の下、以下に各分野における問題点と私の政策を簡略に述べます。
外交・安全保障・・・・自立自尊への道
現在の日本は、様々な面で、アメリカの従属国家に陥っています。外交・安全保障はその典型です。
もちろん、短期的視点から現実の状況を考えると、日米安保体制に依存することはやむを得ないものと考えます。しかし、長期的、根本的な視点から見れば、自立した防衛力の整備は独立国としては当然のことです。これは、アメリカとの真の友好関係を築くためにも、また、北朝鮮や中国の脅威に備えるためにも必要なことです。日本に欠けているのは、こうした長期的視点からの自主的な外交安保政策なのです。
また、守るべきものは「生命・財産」だけではありません。それ以上に「歴史や文化」とそれにもとづく国民の「自尊と自立」を守らねばなりません。憲法改正は当然のことです。憲法改正への正しい道筋をつけるために、国民に歴史を正しく伝え、憲法が作られた経緯を正確に知らせる必要があります。

教 育・・・・・・・・日本人の心を取り戻す
知育、徳育、体育のいずれも充実が必要ですが、一番大切なのは徳育です。そのためには、学校だけでなく、地域や家庭での取り組みが必要です。徳とは人間の「正しく生きようとする気力」のことであり、それゆえ徳育とは、詰まる所、日本人の心を伝えることです。具体的には、家族や国の歴史や先達の苦労話、身近な人たちの経験を子供達に聞かせることから始まります。日本人の生き様を伝えることにより、命を超える価値があることを子供達に気づかせることが必要です。それが徳育です。そのためにも、日本人としての歴史観の再興が求められます。教育基本法の改正が必要ですが、憲法同様、制定時の歴史的背景を国民に正確に知らせる必要があります。また、学校の週五日制を見直し、授業に余裕を持たせるべきと考えています。
少子化・人口減少時代への対応・・・・・少子化でも貧しくならない日本
先ず、確認しなければならないことは、少子化により人口が減少しても日本は貧しくならないということです。これを家庭にたとえて考えてみましょう。5人家族で1000万円の年収で生活していた家庭が、4人家族、3人家族になり、年収が800万円、600万円になったとしましょう。確かに年収は減ったけれど、ひとり当たりの所得は何も変わりません。つまり貧しくならないということです。
今度は財産の面から考えましょう。夫婦にひとりしか子供が生まれないということは、ひとりの孫に2組の祖父母と1組の両親がいるということです。もし彼らが家を持っていたら、このひとりの孫は、祖父母と両親合わせて3軒の家を相続することになるのです。これのどこが貧しいのでしょうか。もちろんこれは、借金より財産の方が多いと言うことが前提です。借金だらけでは、孫ひとりで祖父母や両親の借金を返済しなければなりませんから大変です。
日本は世界一の債権国です。国や地方に大きな借金があることも事実ですが、それらはすべて国内で賄われているものであり、国全体としては借金より財産の方が多いのです。ところが、財政再建を強調し過ぎたため、この基本的な事実が国民に正確に知らされていません。従って、人口減少は債権国たる日本にとっては決して深刻な問題ではありません。
問題にすべきは、団塊の世代が一挙に老齢化することによる、年金などの負担と給付のバランスの崩壊を如何にして調整するかということをはじめ、人口増加を前提にしていた社会の仕組みを、どのように再構築するかということなのです。以下にその対応について述べます。
年金・医療・福祉・・・・・・老後の保障と幸せな家族のあり方
年金や医療・介護保険などの支給は政府が絶対に保障することを確約し、国民に不安を持たせてはなりません。そのためには、税制の見直しも含めて負担と給付のあり方について根本的な見直しが必要になります。
しかし、その一方で、家族のあり方をどう考えるかということも重要です。それは、これらの問題の本質は、日本人にとって幸せとは何かということだからです。個人主義を偏重してきた社会をもう一度見直し、相互に支え合える家族や地域を取り戻す必要があるのではないでしょうか。老後を安心して暮らせる年金・医療・介護のシステムを確保するとともに、充実した老後を送れる家族や地域がなければ、国民の幸せなど望むべくもありません。財政再建論だけでなく、老後を家族や信頼できる人々と暮らせる仕組みづくりが必要だと考えています。
環境と資源エネルギー・・・・水・食糧・エネルギーの確保
今日の社会においては、環境問題は避けて通れません。日本では、地球温暖化防止のため温暖化ガスの削減や、資源のリサイクルばかり叫ばれていますが、忘れてならないのは、後進国の人口爆発と急速な近代化により地球環境が激変し、食糧や石油などの確保を巡る生存競争の時代が、目前に迫っているということです。
その意味では、少子化や人口減少はマイナスばかりではありません。我が国は、資源・エネルギー・食糧など、生存必要物資の殆どを輸入に頼っており、その確保という点では人口減少は有利なのです。先ず、こうした事実を国民に正確に知らせる必要があります。その上で、生存必要物資の自給率を増加させ、石油に変わる新エネルギーの研究開発や循環型社会の構築が求められます。ここでも、一方で国による新エネルギー開発の策定とともに、他方で地域による環境配慮型の生活に向けた政策が必要とされています。
経済・財政・・・・・・・・経済安定のためのルールづくり
少子化や人口減少を日本の危機と考えるのは、人口増加が経済成長につながるという思い込みによるものです。確かに、戦後の一時期はそういう時代がありました。しかし、地球の環境や資源が有限であるのですから、右肩上がりの人口増加や経済成長がいつまでも続くということはあり得ないのです。
人口減少時代を迎え、経済は、成長より安定を目指すべきです。そのためには、競争原理より地域社会との共生や、信頼できる人間関係の構築が必要であり、グローバルとローカルの経済ルールを分けねばなりません。地域の活力のためにも、中小企業が生き残れるようなルールづくりとそのための条件整備が必要です。そして、安定成長の下での新しいライフスタイルのモデルを政府が提示し、経済をその方向に導いていくことも必要です。
また、財政再建には更なる冗費削減が必要であり、安易な増税論には反対です。その一方で、国民の意識を行政への依存から自立、相互扶助へ変えることも不可欠です。
農業・地方自治・・・・・・・ふるさと再生
経済効率ばかりが追求され、農産物は輸入品だらけ、自治体はリストラや合併を余儀なくされました。しかし、食の安全や将来の食糧不足、さらに、防災や環境対策、何よりも国土の保全の意味でも農業は欠くことができません。農業の多角的役割に注目し、農業を守る必要があります。
地方自治を充実するためには、権限や財源を地方に委譲するだけでなく、住民の自治意識を高めることが必要です。それには故郷意識の醸成は欠かせません。そのためには、地域で何代にもわたって暮らせるための住宅と雇用の整備が必要です。
また、官民提携による民間資金の公共活動への誘導を通じての公共活動企画を各地域において具体的に立ち上げていくことも必要です。それは、市場原理主義をはじめとするアメリカ流のやり方に対して一線を画す仕事でもあります。
その他にも様々な問題がありますが、根本的にはここに述べたように、「戦後体制」を見つめ直し、伝統的な日本人の精神や文化、さらには家族、地域社会へ目を見けることによって、解決の糸口を見いだしたいと思います。戦後社会を見直し、日本人が、日本人らしく誇りを持って生きられる社会を作るため、全力で頑張ります。
ライブドア、村上ファンド事件の本質
ライブドアの堀江貴文被告と村上ファンドの村上世彰容疑者が逮捕されました。ともに東大出身で六本木ヒルズに住み、勝ち組の象徴としてマスコミにも頻繁に登場し、まさに、時代の寵児としてもてはやされていた人物でした。彼らの容疑は堀江被告が粉飾決算、村上容疑者はインサイダー取引と、ともに株式の売買に関して不正を働いたということです。村上容疑者は自らその罪を認めていますが、堀江被告は認めておらず、裁判の結果はどうなるか分かりません。しかし、判決がどうであれ、彼らの言動は決して自慢できるものではありません。彼らは、「金で買えないものはない」「お金儲けがそんなに悪いことですか」と言います。確かに、お金儲けは罪ではありません。しかし、それは決して人生の目的ではなく手段に過ぎないのです。人生を賭ける価値ある目的や目標のために必要な手段ではあっても、それ自体が目的ではないはずなのです。お金は大切なものですが、そのお金を何のために使うのかということが、彼らは分かっていないということなのです。
これは、まさに戦後教育の問題点を象徴しています。彼らは両者とも東大出身で、日本の最高学府に学んだにもかかわらず、彼らの口から人生の価値や目的は何かと言うことは、ついぞ語られなかったのです。教育とは、何が大切なことかを子供に教えることですが、戦後教育ではその肝心なことを何一つ教えてこなかったのではないでしょうか。だから、彼らはお金以外の価値を語ることが出来なかったのです。
テストでいい点を取って、東大へ行く。そして、一流企業や官庁へ就職し、お金と高い地位を得る。しかし、そのお金と高い地位は一体何のために使うのか。彼らの頭の中にはそれが抜けていたと言うことです。彼らの言葉の中で『お金』を『点数』に置き換えるとその人生観がよく見えます。「良い点数をとればどんな大学でも行ける」「良い点数を取って何が悪いのですか」
偽メール事件

この堀江被告と与党との関係を国会で激しく追求した民主党ではありましたが、その根拠としていた堀江被告のメールとされたものが、実は全くの作り物であったことが発覚しました。その結果、張本人の永田議員が衆議院議員を辞職、民主党代表の前原議員は代表を辞任するという羽目に陥りました。この二人も東大、京大という受験エリートですが、与党を追求したいという功を焦った結果、国会の本質を見失ってしまったという点で先の事件とよく似ています。
国会は国家の最高決議機関、国の根幹を議論すべき場です。与党や政府に不正があればそれを追求するのは当然ですが、それ以上に国のあり方そのものについてもっと本質的な議論をすべきではなかったでしょうか。今でこそ堀江被告や村上容疑者に対して、厳しい批判の言葉が浴びせられていますが、以前は逆に彼らを時代の寵児として歓迎する空気が非常に強く、そのため、彼らを批判するものは与野党とも殆どいなかったのが現実です。むしろ、あやかりたかったというのが本音でしょう。自民党は本当にあやかろうとしたのですから、その責任を追及されるのは当然です。しかし、民主党も同じ穴の狢だと国民は感じているのではないでしょうか。
今度の偽メール事件はそのことを湖塗するために、功を焦り自滅したという気がしてなりません。また、この人達は、マスコミの脚光を浴びることが国会議員の仕事と勘違いしているではないでしょうか。マスコミに注目されれば、知名度が上がり、選挙で非常に有利になる。こうした短絡的思考がその背景にあったのは間違いないでしょう。これも国会議員になって何をするのかという本質を見失い、国会議員になるためにはマスコミを利用することが当然、必要だという手段ばかりに気を取られた結果がもたらしたものではないでしょうか。
教育基本法の改正

今国会では見送りになりましたが、教育基本法の改正が大きな政治課題になっています。確かに、親が子を殺したり、子が親を殺したりというような報道を見るにつけ、今の教育はおかしいのではないかと誰もが感じているでしょう。また、先に述べたように、東大を出ても、まともな人間になれないと言う事実が、教育の崩壊を物語っています。そこで、教育の根幹である教育基本法の改正が必要だということになるのでしょう。しかし、聞こえてくるのは国を愛する態度、いや心だという議論ばかりで、ことの本質はなかなか見えてきません。
教育基本法を論ずるには先ず、それが出来た経緯を知る必要があります。教育基本法が出来たのは、昭和22年3月31日のことで、即日施行されました。その前年に明治憲法が改正され、現行憲法が制定されていますが、教育基本法はこの憲法の精神を実現するために作られたのです。その前文にはこのように書かれています。「われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。中略 ここに、日本国憲法 の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。」では、憲法はどういう経緯で作られたのでしょうか。
現行憲法が制定されたのは昭和21年11月3日のことです。憲法記念日は5月3日ですが、これはその半年後から施行したためで、この日には本来意味がありません。あるのは11月3日の方です。11月3日と言えば文化の日ですが、元は明治節、つまり明治天皇のお誕生日です。その日に明治憲法を葬り去った訳ですから、憲法の制定は非常に政治的意味合いが強い、ということが伺い知れると思います。
日本は、サンフランシスコ講和条約の発効により独立を果たすのですが、それは、昭和27年4月28日のことです。従って、憲法も教育基本法も日本に主権がない時代に制定されているのです。確かに、両法とも国会に上程され可決されたため、形式的には国民が制定したという形式をとっています。しかし、現実は、日本人の意思とは無関係に、占領軍の意思によって作られたことは明確な事実です。憲法を11月3日に制定したということはそのことを象徴しているのです。
では、占領していたアメリカは、当時どのようなことを考えていたのでしょうか。それは、日本の軍事的解体と精神的解体であったと言われています。つまり、二度とアメリカに対して弓を引かせない、それが占領目的であったのです。この占領目標を担保するために作られたのが憲法であり、教育基本法であったいうことを知っておく必要があります。
憲法前文で「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」と宣言させ、9条では戦争を放棄し、軍備及び交戦権の否認を誓わせたのはそのためなのです。こうしたアメリカの占領方針にのっとり、教育基本法が制定されたのです。
しかし、意外なことに、教育基本法を読んでみても、アメリカが占領をうまく行うための言葉は何も見あたりません。むしろ、「個人の尊厳」「真理と平和」「人格の完成」など、どれもうなづけるものばかりなのです。確かに、これらの言葉はどれも大切なものです。近代国家にはどれも必要とされているものばかりです。そういう意味では、万国共通の価値観と言えるかも知れません。しかし、そこには日本の文化や伝統に根ざす言葉は何一つ書いてないのです。これでは、国際人は養成できても、日本人を養成することはでないのではないでしょうか。まさに、これこそ占領政策の目指したものであり、教育基本法の問題点なのです。
教育の本質は、日本人としての心を子供に伝えることです。江戸時代は、寺子屋で論語が、戦前は、学校で教育勅語が、日本人の伝統的価値観や徳目を伝えるため教えられてきました。しかし、戦後はこうした伝統的価値観は一切排除され、学校では教えなくなってしまったのです。
その結果、日本人はどうなってしまったのでしょう。歴史を知らず、日本人としての心も無くし、国の自立など考えもしない、そんな人物ばかりを生み出してきたのです。愛国心は勿論大切なことですが、それは、歴史や伝統を知れば当然芽生えるものではないでしょうか。従って、日本人としての歴史観や伝統的価値観や徳目を教えることをタブーにしていることの方が、より根本的問題なのです。
真の政治改革

このように、現代の日本にのしかかる問題の多くは、戦後の占領施策が今なお続いていることが根本的原因なのです。しかし、残念ながら、その事実が国民に正しく伝わっていないのです。それは、アメリカが占領中に命じたものはすべて民主化政策として国民に伝えられ、こうした事実は、全く知らされなかったことが原因です。しかし、その後アメリカの公文書が公開されるにつれ、こうした事実が明らかになってきています。占領中は事実を報じることが禁止されていましたが、現在はそのような規制は何もありません。にもかかわらず、こうした事実はまだまだ国民に浸透していません。そして、その事実を知らずに、様々な議論がされています。しかし、それでは、根本的に問題を解決できるはずがないのです。
私は、今年、府議会議員になって17年目を迎えていますが、この間、一貫して訴えてきたのは正にこのことです。残念ながら、私の指摘してきた問題は一向に解決の兆しが見えません。しかし、だからこそ、私は訴え続けなければならないのです。それが、私の使命であり、真の政治改革であると思うのです。
この文章は、大演説会の講演を要約し、加筆修正したものです。
今回も再びボリビアからの報告です。昨年末,エボ・モラーレスが南米では初めて先住民から大統領に選出されました。その後,チリやペルーでも大統領選が行われ,南米全体としては反米・社会主義回帰への気運が高まっていると言われています。この中心人物がベネズエラのチャベス大統領で,キューバのフェデル・カストロと組んで米国に対する対抗軸を形成しようとしています。我がボリビアもこの軸の一翼を担うようです。
エボ政権は天然資源の国有化に乗り出し,コカ栽培の「自由化」を推し進めようとしています。このように書くと何処かの国のように麻薬を産業化するのかと思われるかもしれませんが,ボリビアやペルーのようなアンデス高地の民族には元々コカのお茶(マテ・デ・コカ)を飲んだり,仕事の際に噛む習慣があります。またお祭りや占いなど古くからの習俗の中に深く溶け込んでもいます。言わばアンデス文化の要素と言っても良いでしょう。(コカ茶を飲んでも習慣性や覚醒作用はありません。むしろ高山病の対処療法として必要なものです。しかし,コカを生成しコカイナにするとこれは明らかに麻薬の原料ですが。)さて,日本の某新聞が言ったように,此処南米では本当に社会主義の再築が行われるのでしょうか。
ボリビアでも一見するとそのようにも見えます。米国の「コカ・ゼロ化政策」に対抗する形で先住民の文化擁護の旗を降ろしていませんし,米国との貿易協定に背を向けるように,ベネズエラ・キューバと三国で貿易協定を結びました。しかし,天然資源の国有化に見られる多くの国民の願いは「自分達の資源は自分達のために使いたい」と言うものです。エボ政権も基本的にはこの考え方でしょう。一部の白人国家を除いて南米の多くの先住民は,スペインから独立した後も旧態依然とした植民地経済システムの呪縛の中にいます。この収奪から開放されたいと言うのが本当のところだと思います。

今回のボリビアの社会主義回帰への動きも,底流には「descolonizacion」という考え方があります。これは「脱植民地主義」とでも訳するのでしょうか。アンデス文化が持っているコスモポリタンの考え方を重視し,経済的にも文化的にも今までの植民地主義的な有様からの脱却を目指しています。中央省庁での機構改革や人事の一新を見ていると少し性急な気もしますが,傍目には後に戻れないという悲壮感さえ感じられます。「寄らば大樹の陰」という思考から脱却し,自分達の手で改革しようという意気込みは伝わってきます。
世界が米国一極集中型の動きをする中で,今ボリビアは自分の足でアンデスの大地に立とうとしています。そのためには「descolonizacion」が掛け声だけでなく,具体的な方法論として民衆の前に姿を現すことが必要です。日本では暑い夏を迎えるでしょうが,此処南米ではかってなかった規模と速度で世の中が動いています。ひょっとしたら,欧州でベルリンの壁が崩れたような変革が静かに進行しているのかも知れません。ボリビアは現在史上最も暑い季節が訪れようとしています。
「勝ち組」と「負け組」

最近「勝ち組」や「負け組」という言葉を良く耳にします。「勝ち組」はヒルズ族と呼ばれる様に、六本木ヒルズのような立派なビルにオフィスを構えるような IT経営者、「負け組」は、ニートと呼ばれるような、就業も就学も職業訓練もしない若者達がその典型でしょう。確かに、ニートのように単なる失業でなく、働くことも学校へ行くことも含め、社会参加に対する意欲を喪失してしまう若者には困ったものです。しかし、「勝ち組」も、その代表がホリエモンこと堀江貴文前ライブドア社長では、決して「勝ち」とは言えないでしょう。彼は時代の寵児としてもてはやされました。しかし、その実態は、新しい産業を興したと見せて投資家からお金を騙し取っただけのことでした。彼の罪とされている粉飾決算、偽計取引、風説の流布とはそういうことです。つまり、単なる虚業家に過ぎなかったということです。
しかし、そんなホリエモンを未だに改革者だと信じている人が、意外に大勢いるようです。そして、その中に「負け組」のはずのニートや、フリーターと呼ばれる定職を持たずアルバイトで生活している若者が結構いるのです。その理由は、自分たちも何処かでチャンスさえつかめば、彼の様に一攫千金を当てることができるかもしれない、と密かに信じているからなのです。また、マスコミなどの中にも彼に同情を寄せる人が結構いるようです。彼らは、ホリエモンは確かに罪を犯したけれど、彼は日本の閉塞的な社会に風穴を開けたではないか、と評価をし、挙句の果ては、彼の罪は日本の法律が未整備なことも一因ではないか、角を矯めて牛を殺すようなことをしてはならない、と言う始末です。これにはあきれてものも言えません。何故、ホリエモンに対する擁護論が根強いのでしょう。そのことを考えると、今日の日本の姿が良く見えます。
日本型経営の衰退

ほんの二十年ほど前まで、日本は、国民の殆どが自らを中流と感じるほど、均質で豊かな社会を築いていたはずでした。アメリカを追い抜いて世界一の経済大国になったと、自他ともに認めるほどの繁栄を極めていたはずでした。しかし、それもバブル(あぶく)のように束の間のものに過ぎなかったのです。バブルが崩壊した後は、不況の坂をまっ逆さまに転げ落ち、日本人は、それまでの富も自信も一瞬のうちになくしてしまったのです。
つい先日まで、日本型経営をアメリカ型経営より優れたものとして自認していたにもかかわらず、今ではそれを否定し、アメリカ型に変えることを改革と称して、社会全体が一つの方向に進んでいます。「勝ち組」「負け組」という言葉は、そうした改革の結果、日本が熾烈な競争社会になってしまったことを象徴しています。
日本型経営とは、一口で言えば、安定した長期的利益を求めるものといえるでしょう。一方、アメリカ型経営とは、短期の利益を追求するものです。その背景には、両国の会社に対する考え方の違いがあります。日本では、会社は株主より従業員のものであると考える人が多いですが、アメリカでは会社は株主のものです。従って、日本では経営者は、利益をできるだけ会社に留保し、従業員の長期的雇用を確保しようとしてきました。それに対して、アメリカでは、利益は株主のものであり、できるだけ配当をしなければなりません。従業員の雇用より株主への配当が優先されるのです。また、日本では、熾烈な競争で共倒れするより、社会全体で利益を分かち合うことが優先されてきました。護送船団方式とも呼ばれ、国が業界に行政指導をしてきたのです。銀行や保険会社がその良い例です。そのため、金利もサービスもどの銀行でも同じで代わり映えしませんでしたが、逆にそのお陰で、倒産する銀行もなく、社会が混乱することもなかったのです。
ところが、東西冷戦の終結により、事態は一変しました。アメリカがソ連に勝ったということは、自由主義経済が計画主義経済より優れているということなのだと、殆どの人が無条件に思いこんでしまいました。これは、バブルの崩壊で自信をなくしていた日本にとっては、大きな衝撃になりました。殆どまともな議論のないまま、国民の多くが、行政主導を廃止し、規制を緩和し、競争原理により社会に活力をもたらすべきだと考えたのです。この結果、日本は、この十数年間の間に一挙に競争社会に突き進んでしまったのです。
規制制をなくし自由に競争させれば、人間の能力が百パーセント発揮できるはずだ。チャンスさえ与えれば、誰だって成功できる可能性がある。政府が保証すべきはそのチャンスであり、結果ではない。こうした考え方が、この十数年で一挙に広がりました。ホリエモンも、ニートも、フリーターも、こうした社会の中から生まれてきたのです。誰もが、アメリカンドリームならぬジャパニーズドリームを夢見てきたのです。
しかし、その結果は、格差社会と言われる弱肉強食の世界を作り出しただけであったのです。アメリカ型の経営をまねれば、社会もアメリカ型になるのは当然です。これは、アメリカ型社会を簡単にまねてしまったことによる悲劇です。
ところが、それに気付いて目を覚ますどころか、未だに模倣し続けようとする人の多いのには困ってしまいます。「負け組」でも、もう一度やり直しがきくようにセーフティネットを設けるべきだというのは、その典型です。セーフティネットよりも、「勝ち組」「負け組」という熾烈な競争社会を作り出したこと自体を、見直すべきではないでしょうか。
経済という言葉は、経世済民という言葉が元になっています。その意味は、民を救済し世の中を納めると言うことです。かつて、殆どの国民が中流を意識する社会は、まさに、この言葉通りの経済政策が実現していたと言うことです。私たちは、経済という言葉の意味を、今一度見直すべきではないでしょうか。
最近、京都市内で銀行や会社の跡に、高層のマンションやホテルが目立ってきて、街中の風景も様変わりしてきました。特に主要な鉄道の駅の近くには、全国チェーンのビジネスホテルがいくつも建てられ、しかも近年の京都ブームや宿泊料の安さから高い稼働率となっています。これも、気軽な京都観光の助けになっているのかなと思っていました。

ところが、1月27日付け朝日新聞に、京都市内にも3店舗あるビジネスホテルチェーン東横インが、横浜市に今年初めオープンしたホテル建設において、法律や条令で義務付けられている身障者用設備や駐車場を設けた建物をいったん建てながら、市などの完了検査直後にこれらの設備を撤去改造して開業していた記事が掲載されまた。まだ、テレビや新聞において耐震強度偽装問題が取り上げられている最中のことでした。
東横インは、電気工事会社を経営していた西田憲正社長が昭和61年に設立した、家主から土地を借りて家賃を払い、建設と運営だけを担う方式を導入したホテル運営会社です。昭和61年に設立後、京都においても平成10年に四条大宮店、13年に五条烏丸店そして14年に四条烏丸店をオープンさせ、短期間に全国で約120店舗のビジネスホテルの全国チェーンを築いています。ローコスト経営を掲げ、シングル一泊は、朝食や新聞などが無料で4千円代からあります。ホテルの建物の建設においては、本体の工事は大手ゼネコンに発注しますが、設計及び機械設備、内装等を自社グループが行い経費を圧縮しています。
またホテルの運営においては、支配人は全て女性で、女性パートも積極的に雇用しています。 この新聞記事やその日に行われた社長の「身体障害者の利用が少ないので改造した。」「時速60キロで走るところを67,68キロで走っていいかと思っていたのは事実。これからは60キロで走りたい」等の障害者への配慮切捨ての開き直り会見を受け、国や自治体は東横インが全国に展開する120のホテルについて法令違反に当たるような不正改造が無いかどうか、立入検査を含めた本格的な調査に乗り出しました。その結果、全国にある122物件のうち77件で完了検査後に改造が行われ、うち60件で建築基準法や建築物を高齢者や身体障害者に使いやすいようにすることを目的としたハートビル法や駐車場条例の法令違反が確認されました。2月6日に、社長は一転神妙に謝罪をしましたが、調査中の2月2日に東横イン神戸三ノ宮?が身体障害者用施設の設置を定めた兵庫県の条例に違反したまま開業しています。この様な矛盾した対応には、あきれるばかりです。

さて、このように日本の企業経営者が、金銭至上主義により同種の問題を頻繁に起こしていることや、これほどあきれた経営者のホテルであることが分かっていても、利用料が安く使いやすいと利用する客が減らないことや、この様な事件が起こったとき罰則の強化で防止を行おうとする風潮などは、日本の古き良き道徳が、アメリカのグローバリズムの戦略により廃れてきた現われではないでしょうか。つまり、これからの日本の進むべき道は、このような延長ではなく、日ごろから西田府会議員が伝えようとしている「美しい精神(こころ)と自然(こくど)」の継承ではないでしょうか。
日の丸飛行体は何処へ
札幌オリンピック〔昭和47(1972)年〕のスキージャンプ70メートル級(今のノーマルヒル)で笠谷(金)、金野(銀)、青地(銅)の3名がメダルを獲得し、センターポールに日章旗が3本占めたことを覚えている方がまだ多数いらっしゃるはずです。以来、冬季オリンピックやワールドカップでは日本のジャンプ陣を「日の丸飛行隊」と呼ばれるようになっています。8年前の長野オリンピックでも団体で悲願の金メダルを獲得し、個人でもメダルを獲得しています。
ところが、トリノでは・・・・。長野オリンピック以後ルール改正が行われ、その対応がまだ出来ていないとか。若い選手が育っておらず、世界の強豪国に比べあまりにも高齢(失礼)の選手陣で臨んだようで「ロートルジャパン」と皮肉られたとか。なぜ、若い選手が育たなかったのでしょうか? オリンピックはアマチュアのスポーツです。選手は学生か企業人ですが、ウィンタースポーツは我国では北日本に限られており、地域性が出てきます。

長野オリンピックのときの原田、岡部、斉藤の3人は雪印乳業に所属をしていましたが、その雪印乳業がスキャンダルを起こすと共に日の丸飛行隊も失速していきました。企業がスポーツ選手を強化しなくなれば、選手は別の企業へ移らなければならず、環境、待遇もかなり変わってしまいますが、我国を代表するアストリートならコンデションの維持は出来るはずです。しかしトリノでは原田はバナナ1本の体重が足らず、失格となりましたがオリンピックに臨むアストリートとしてはあまりにもお粗末過ではないでしょうか? それも雪印乳業という企業から出てしまったためでしょうか? 企業単位の選手強化にはもう限界が来ているのではないでしょうか?
それに比べて、フィギュアスケートはNPO組織の連盟による新人発掘から育成が功を奏して、時間はかかったが、荒川静香の金メダルとなったようです。もしかして、「メダルがゼロ」とささやかれていただけに、静香ちゃんの金メダルを喜んでいるのはのび太君、ドラえもんだけでなく、日本中の国民でしたね。
謹 賀 新 年
本年もよろしくお願い致します
-9条と自衛隊は何故矛盾するか-
昨年、自民党は結党50年を契機に憲法改正試案を示し、9条に自衛のための武力保持を明記し、こうした矛盾を解消しようとしています。憲法改正は、自民党結党以来の党是であり、9条を改正して自衛力保持を明記することは悲願でありました。その意味では、今回の憲法改正案は自民党員としては当然賛成すべきもののように思われます。しかし、残念ながら私はこれに賛成することが出来ないのです。その理由を述べたいと思います。
そもそも、9条と自衛隊という矛盾するものが、何故存在するのでしょうか。ご承知の通り、現在の憲法は昭和21年11月3日に公布され、翌年の5月3日から施行されています。また、自衛隊は昭和25年に発足した警察予備隊を母体としています。両者とも終戦直後の時代に作られたのです。しかし、昭和27年4月28日にサンフランシスコ講和条約が発効するまでの期間は、アメリカに占領され、日本人に主権がなかった時代だったのです。主権がないということは、日本人が自らの意思で判断し、決定することができないということです。では誰の意思で物事が決められていたのでしょうか。それは言うまでもなく、占領国であるアメリカです。この時代にも国会は存在しましたが、現実はアメリカの決めたことをそのまま承認するだけのものだったのです。

終戦直後、アメリカは、日本を武装解除し、アジアにおけるスイスのような存在にしようと考えていたのです。それを担保するために憲法を作り、9条で武力放棄を明記したのです。そして武力放棄をするために、憲法前文にあるように「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意」させたのです。つまり、アメリカに安全保障は任せるという意味です。ところが、こうしたアメリカの政策が一転する大事件が起こりました。それが昭和25年の朝鮮戦争です。金日成率いる共産軍が韓国に攻め入り、朝鮮半島が共産化されてしまう事態を目の当たりにして、アメリカはそれまでの容共から反共に政策を大転換したのです。その結果、日本の占領政策も大幅に変更されることになったのです。アメリカは、日本をアジアにおける反共の砦にするために、再軍備を要求したのです。これも占領中のため、日本は従う以外ありません。ところが、既に憲法で武力放棄を謳っているため当然これと矛盾してしまいます。そこで、警察予備隊という名称を用いることにより、軍事力ではなく警察力だという口実で発足したのです。その後、保安隊そして自衛隊と名称変更して今日に至っているのです。このように9条と自衛隊の矛盾はアメリカの占領政策の変更によるものなのです。本来こうした矛盾は、主権が回復した時、直ちに改正すべきものです。正に、そうした目的で自民党が結成されたのです。つまり、占領政策の精算という意味での憲法改正が、自民党の党是であったはずなのです。
確かに、今回の憲法改正試案には防衛力の保持が明記され、表面上は自衛隊との矛盾はなくなるように思えます。しかし、憲法も自衛隊も占領中にアメリカの意向によって作られたものであり、日本のためでなくアメリカのために作られたものであるという、根本的矛盾は何ら解消されていないのです。今回の憲法改正の背景にあるのは、アメリカとの安保体制強化ということです。これこそ、日本が未だに占領体制の延長線上にあるということを示しています。そこには自立自尊の精神はなく、自民党が結党時に誓った憲法改正とは似て非なるものです。これでは、占領体制からの脱却を実現することは出来ないと思うのです。
-女性天皇問題-
同じことが女性天皇容認論についても言えます。有識者会議では女性天皇を容認する答申がされましたが、これはあまりにも短絡的ではないでしょうか。
この問題の背景にあるのは、現在の皇室には内親王(女性)ばかりで、本来の皇位継承者たる親王殿下がおられないという現実があります。このままでは皇統が絶えてしまうという問題を回避するために、女性天皇つまり愛子様が天皇となることを容認する答申をした訳です。一見するとこれで問題が解決したように見えますが、実はこれこそ将来、皇室の存在を揺るがす元になりかねないのです。

そもそも、皇統が危ぶまれる事態になった根本的問題は、占領政策により宮家が廃絶されたからに他なりません。皇室が続いてきた背景には、それを守る様々な仕組みがあったからです。そのひとつが宮家の存在です。宮家は、天皇家と同じく皇統を受け継がれた天皇家のご親族であります。皇位継承の危機が訪れた時のために用意された先人の知恵なのです。皇統を確実に安定して継承させるには、これを補完する宮家がなければならないということです。ところが、この宮家が昭和22年にGHQの指令により皇籍を離脱させられてしまったのです。ただ、当時はまだ、昭和天皇のご兄弟が宮家として残られたので、皇位継承がこれ程までに危ぶまれることはなかったのです。占領当初、GHQは皇室の廃絶を考えていたと言われています。しかし、それでは日本が大混乱に陥る恐れがあるため、これを諦めたといいます。逆にGHQは、皇室を利用することにより、占領政策を有効に行うことに方向転換したのです。しかし、皇室を認めることと引き換えに、宮家は廃絶させられてしまったのです。それから60年経ち、宮家の廃絶がまるでボディーブローのように皇室に襲いかかってきたのです。今日の皇位継承の危機は、まさに60年前にGHQによって仕掛けられた時限爆弾が爆発せんとしているようなものです。従って、この危機を回避するためには宮家の復活しかないというのは、こうした経緯を考えれば当然の結論なのです。確かに、女性天皇を認めれば一時的には皇統は守られるように見えます。しかし、もしその方が結婚されなければどうなるでしょうか。また、お子様がお生まれにならなければどうなるでしょう。結局女性天皇を容認しても問題を先送りにするだけで、何の解決にもならないということです。むしろ、皇位継承のルールを安易に変えることは、皇室の権威そのものを揺るがすことになってしまうのではないでしょうか。
-すべての原因は占領政策にある-
このように、憲法・自衛隊・皇室これらの問題は、すべてGHQによる占領政策がその根本原因なのです。このことを理解せずに議論しても何も解決できないのです。むしろ、こうした問題を契機に、占領政策が今尚、日本に影響を与えているという現実をしっかり見つめる必要があります。憲法・自衛隊・皇室これらはすべて日本の自立自尊を象徴するものであり、特に皇室は日本の文化、伝統そのものです。それが、占領政策によってどれ程貶められたものになっているか、皆さんに是非知って頂きたいのです。占領政策からの脱却はこのことを知ることから始まるのです。
受け継がれる心と独創文化
著述業・昌友塾生
大森 敦子(神戸市在住

「わあ、すごい!」
壁に掛けられた額を目にして、私は思わず感嘆の声を漏らしていた。縦60cm、巾1mと思われるくらいの大きな額の中身は折り紙アート。金と黒二色の蒔絵を思わせる色使いで、やや霞がかった満月の夜空を背景にひと番いの鶴が大きく羽を広げて美しく舞っているという情景が図案化されていた。
日本でも折り紙アートはあるが、こうした物にお目にかかったことがない私にとって大変衝撃的で、今も強く印象に残っている。
それは4年ほど前に、ハワイ島ヒロ市の日系アメリカ人三世の友人(30代半ばの笑顔の素敵なご夫婦)宅を訪れた時のことだった。
この額は、彼等の結婚祝いに贈られたものだという。金色の小さな折り紙を家族や知友人が手分けして千羽鶴を折り、それを一つずつ丁寧に重ね貼り付けて絵を完成させていくという、意外と時間のかかる作業らしい。
初め、その額を遠目に見ていた私は、てっきり「金ピカ大好き」な彼等が日本のどこぞの観光地で買い求めた漆塗りもどきの安い日本画だろうと、大して気にも留めていなかった。ところがどっこい、近くで見たらとんでもない!細部に亘って丁寧な仕上がり具合に、本来日本人が持つ手先の器用さと、彼等の中に受け継がれる日本的なる物の感覚が、こうした見事なものを作り上げたのだろうと感慨深かった。少々肥えた体型に黒く焼けた肌でハワイアンにも見える彼等も、やはり日本人なのだ。それが私には嬉しかった。額を見て大層感激している私に彼等は「日本では、こういう物を作って贈る習慣はないのか!?」とビックリして目を丸くしていた。どうやら元々は日本の習慣だと思っていたらしい。最近では、ハワイの日系人でもこうした額を贈ることが減っているようではあるが、やはり千羽鶴はとてもおめでたいもので、祝祭事には大切にされているとのこと。彼等の額は鶴が主になっているが、松や梅、亀など日本でおめでたいとされているものが図案の元になるという。いやはや、日本に住む私の方が、素晴らしいものを教えて貰った。
先日あるテレビ局で、クイズを解いていくと自分のIQの他に右脳派か左脳派かが分かるという、視聴者参加型の特別番組を放送していた。その番組が集計した結果では、日本人の多くは右脳派で、物事を想像→創造する能力に長けているという。なるほど、古事記などの古典文学、遺跡の壁画から現代芸術然り、私たちのDNAにはそうしたものが連綿と受け継がれているのである。そして、それは時代と海を渡った日系人の彼等の中にも確実に存在していると感じる。
日本の正月の中にも見られる独創文化。ハワイの彼等に負けず、いつまでも大切に守り育てていこう。
皆様のご多幸と、日本国の正しい発展を祈念して。 合掌
新春のお祝いを申し上げます
参議院国際問題調査会長
参議院議員 西 田 吉 宏

皆様には、日頃より温かいご芳情とご支援を賜り、誠に有り難うございます。
過日の第163回特別国会におきまして、第三次小泉改造内閣が誕生いたしましたが、同時に私も、参議院国際問題調査会長に任命されました。
ご承知のように、我が国に於いては内外共に諸課題が山積いたしております。その解決に向けて日夜国政に励んでおります。
今後におきましても、皆様の「声・思い」を国政へ届ける架け橋となり、信頼される政治と生活の安定の実現に向け、努力して参る決意でありますので、西田昌司府議会議員共々、変わらぬご支援、ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。
結びに、皆様方の一層のご健勝と、ご多幸を祈念申し上げまして、新年のご挨拶といたします。
西田昌司後援会の皆様へ

西田昌司府議会議員並びに後援会の皆様方には、日頃から、京都府政の推進に格別の御支援・御協力をいただき、厚く御礼を申し上げます。
西田先生におかれましては、自民党全国青年議員連盟会長とともに、府議会自由民主党議員団の代表幹事として、京都の未来を担う人づくりの問題をはじめ、府政の重要課題の解決に昼夜を分かたず積極的に取り組んでいただいており、心から感謝を申し上げます。
私達を取りまく環境は大変厳しく、目の前には多くの課題が山積していますが、府議会自民党の要である西田先生としっかりと手を携え、常に府民の目線に立ち、これからも皆様方とともに、明日に希望の持てる、夢のある「人・間(にんげん)中心の京都づくり」を目指して、邁進してまいりたいと存じます。
西田先生はもとより、皆様方のお支えがあってこそ、安心して府政に尽力できます。後援会の皆様方には、西田先生のもとにさらに強く結集され、京都府の発展のために御尽力いただきますようお願い申し上げますとともに、新しい年に当たり、皆様方の御健勝と御多幸を心からお祈り申し上げます。
-地球の裏側の激動-

皆様新年を如何お過ごしでしょう。久しぶりに「ボリビア通信」を送ります。ここボリビアの地は12月18日(12月8日寄稿)に予定されている「大統領選挙」に向け熱い政治の季節を迎えています。サンチェス・デ・ロサーダ政権が倒れ後継のメサが大統領になりましたが、天然ガス問題で辞職、その後の大統領が実質的な「選挙管理内閣」です。(大統領就任時から選挙を行なうと公言していました。)その後紆余曲折を経ながら、大統領選や県知事選(今までは大統領の任命制で、今回が実質的に始めての地方自治選。大きな県は日本と同じくらい面積がありますから地方という言葉が日本と同じであるかどうかは分かりません。)、下院議員の選挙が行なわれます。
南米は何処もそうですが、上が変われば下まで変わります。(例えば大臣が変われば、一般の行政職員まで変わります。まあ、「総入れ替え」という言葉が当てはまるほど変化します。これをsystema de politica gubernamentalと言います。)当然そうであるが故に、選挙運動は熾烈です。ここボリビアでは4名が大統領選に立候補しています。 EVO,SAMEL,TUTO,NAGATANI(日系人です。フジモリほど有名ではありませんが)の4名です。しかし、過半数を制する候補が居らず議会での決戦投票に持ち込まれ、再び熱い政治の季節(混乱とも言いますが)の幕開けと言われています。まあ、誰がなっても混乱が起こるというのが下馬評です。
こちらの混乱は文字通りの「混乱」ですから,生活の糧や手段までおかしくなります。(1カ月分程度の食料の買置きや緊急脱出への準備も必要です)3週間前まではプロパンガスの欠乏で住民の道路封鎖(bloqueoと言います)が続きました。(お陰で空港まで重い荷物を徒歩で運びました。)またこちらではダイナマイトが市販されています。ポトシ(かって世界の銀の大半を産出しスペイン帝国の台所で中世の大都市として有名)に行った際には露店のおばあさんが導火線と一緒に売っていました。これを分割し手製の「爆竹」を作ります。これがまた日本の爆竹と比べ半端じゃありません。先週も私がいる省庁がデモ隊に囲まれ何本も投げ込まれました。
ここにいますと日本の調整(調和)型の政治というのが、「先人の知恵」というのを実感します。これから望まれる政治家の資質は自分の考えを押し出し、しかもこれを協調の中で実現するという異なる価値観を併呑するような大物でしょうか。大所高所の判断などというものではなく、多次元的な発想と決断が出来る人物。そう言えば,あるセミナーで西郷従道が日本海軍を創設する際の話や逸話を話したら、大いに受けました。日本もボリビアも民が望む人物像は同じだと感嘆したひと時でした。
郵政民営化(既得権益の排除)だけが論点なのか
郵政民営化の是非を一大争点にした先の総選挙は、自民党の圧勝で幕を閉じました。自民党員の一人として、ご支援をいただいた皆様に心から御礼を申し上げます。しかし、その一方で今回の選挙には、一政治家として大いに疑問と虚しさを感じるものでもありました。そのことも含め、今回の選挙について私なりの意見を述べたいと思います。
まず、選挙の争点となった郵政の民営化についてであります。以前から申し上げてきた通り、なんでも民営化をすればよいという今日の風潮には私は反対です。ただ今回の選挙では、郵政の民営化を突破口に、いろいろなしがらみを断ち切り、改革を断行することが必要であると、私は訴えてきました。しかし、その先にあるもっと大切なことについては、郵政民営化の是非だけを問う今回の選挙では語る場さえありませんでした。
よく言われる様に、自民党には沢山の『族議員』がいます。それが、いろんな業界や団体の方々から様々な意見や要望を聞き入れるための窓口になっているのです。商売をなさっている方からサラリーマン、年金受給者の方。また、若者、お年寄り、障害をお持ちの方など、ありとあらゆる方々の意見が、自民党には届けられるのです。それを基に、朝早くから毎日の様に党本部で部会が開かれ、勉強会が行われているのです。
そして、政調会や総務会といった党の組織を通じて集約され、自民党の政策としてまとめられ内閣を通じ、みなさんの思いが実現されることになるのです。これは政党政治として非常に理にかなった仕組みであると思います。今までのような右肩上がりの時代には、毎年税収が増えるわけですから、国民の要望は時が経てば必ず実現することができたのです。
ところがこれからは右肩下がりの時代です。税収は増えるより下がることが予想される時代なのです。国民の要望は、実現されるべきものと却下されるべきものに、より厳密に区分けされねばなりません。また、今まで受け入れられていた要望も却下もしくは縮小されることにならざるを得ないのです。つまり、今までのように『族議員』の要望を全部受け入れていたら国はもたなくなるということです。
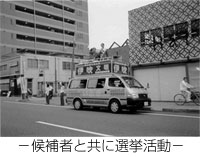
こうしたことから「郵政が改革の本丸である」と小泉首相は訴えられ、私もこの選挙戦を戦いました。つまり、自民党は税収減少の時代に備え国益を守るため自らの体にメスを入れ、『族議員』を排除し、古いしがらみを脱ぎ捨てるのだと訴えたのです。
しかし、私にとっては内心忸怩たるものがありました。『族議員』などの言う特定の業界の利益を守というのではなく、国益を守るということは当然の話です。問題は今の日本が直面しているのがそうした種類の問題ではなくて、もっと大きな根本的問題に直面しているということなのです。そのことに目をつぶり、目先のことで国民に訴えなければならないということに、自分の無力さを痛感していました。では本当の問題はなんだったのか、そのところを皆様に是非お伝えしたいのです。
サファリパークのライオン
今の日本の状態は、たとえて言うなら、サファリパークのライオンではないかと思うのです。動物園にいるライオンではなくてサファリパークのライオンというのは、囚われの身である自覚がないからです。動物園にいるライオンは目の前に鉄の柵があり、否応無しに自分が囚われの身である事を自覚せざるを得ません。しかし、サファリパークにいるライオンはどうでしょう。目の前には柵はありませんし、檻に入っているのはライオンではなく見物にくる人間達です。自由に我が物顔で走り回ることができますから、そういうことを覚できないのです。勿論、アフリカのサバンナから連れてこられた一世達はそのことを知っているでしょう。でも、サファリパークで産まれた二世や三世はどうでしょう。このサファリパークが唯一の世界だと思っている彼らには、自分の身の上に思いをはせることなど想像もつかないことです。

そもそも、毎日何不自由なく暮らしている自分たちが、囚われて飼い慣らされた存在なのだと一体誰が思うでしょう。また、最初はサファリパークに違和感を覚えていた一世達も、今では、ここでの暮らしに馴染んで しまったとしても無理もありません。考えてみれば、自由だと思っていたアフリカのサバンナでは毎日餌にありつけるわけでもなく、いつも空腹に耐えてきた、餌の取り合いでハイエナと喧嘩もしなくてはならないし、それで命を落とす仲間もいる、「こちらのほうがよっぽど居心地がいい。」そんなことを思っていてもおかしくありません。しかし、自由で豊かだと思っているサファリパークですが、それはいつまで存在するのでしょうか。どこのサファリパークかは忘れましたが、以前新聞にこんな記事が載っていました。「サファリパーク倒産で動物達が餓死!」
このサファリパークのライオンこそ、今の日本の状態を表しているのではないでしょうか。
自立心なき国は滅亡する

日本は戦争に負けた後、アメリカの占領下に置かれてしまいました。そして、その占領体制を円滑に進めるために、新たに日本国憲法が制定されたのです。この憲法のお陰で戦後の日本は戦争もなく、自由で豊かな国になったと思っている人がどれほどいることでしょう。しかし、実際はそれこそが、日本を縛るサファリパークの仕組みそのものなのです。こうした事実を今どれほどの国民が知っているのでしょうか。平和憲法が成り立っているのは、アメリカの核の傘の中にいるからであります。その代償として、日本は基地を提供し、外交や経済、歴史観などの自主権を事実上放棄しているのではないでしょうか。これは言いかえればアメリカの保護国になっているに等しいことではないでしょうか。囚われの身である自覚がなく、現実の生活にかまけている姿はまさに、サファリパークのライオンそのものではないでしょうか。
市内各地の小学校で運動会が催されていますが、最近、紅白に加えて青組だの、黄組だのが入り多極化(?)状態で対抗戦が行われています。かって瓦が小学校時代は、紅白帽(赤白帽の漢字は間違い)をかぶり騎馬戦をした記憶があります。3組対抗出で騎馬戦をしたら同盟関係だの、協力関係だのややこしくって・・・。
日本では昔から、戦う場合は二組に分かれて「紅白戦」という形が用いられていました。
運動会の玉入れも紅白戦で紅白の玉を用いるべきなのです。野球の練習試合も紅白戦、大晦日の歌合戦も紅白戦です。紅白戦とは、約800年前の平安時代末期の源氏と平氏の「源平合戦」に由来しており、源氏が「白旗」、平氏が「紅旗」を掲げて戦場を駆け巡ったことによります。広辞苑で「紅白試合」を引くと「源平試合」と書かれています。先ほどのNHK大河ドラマの「義経」の壇ノ浦の戦いでは源平最後の合戦としてあまりにも有名で、敗者である平氏の紅旗が海面を覆い尽くしている状況は、皆さんの記憶に残っていられることと思います。

平氏が紅旗を使い、彼らの衣装も紅を基調としているのは貴族社会への憧れであったようです。聖徳太子の冠位十二階以来、貴族階級では位によって衣の色が決められていました。武家である平氏は何とかして貴族の仲間入りがしたくって紅色を選んだのでしょう。一方、源氏は関東鎌倉に本拠を構え、貴族社会に俗されることなく、染める必要のない白旗を選んだのでしょう。 この様に、紅白戦の起源は源平合戦にあって800年の歳月を経ても、今なお日本人の心に生きているのです。この紅白の色に分かれて戦う民族は世界中でも珍しく、日本人の紅白意識はかなり特異なもののようです。
瓦の心の底には紅旗意識が流れており、好きな色は「紅」で幼児時の玩具の自動車から、今乗っている自動車まで色は何時も「紅」色でした。さて、皆さんの心のそこの色は紅白のどちら?

先日(9月11日~13日)2泊3日で「月岡温泉と飛騨高山」旅行がありました。1日目は、衆議院選挙の投票日と重なり、期日前投票をした後、結果が気になりつつ出発致しました。
高山祭りを再現された“高山祭りの森”にてホコ見学。夕食はバイキング料理と、のんびりと楽しい1日目でした。・・・が、やはり気になるのは選挙のこと。結果は“自民党トップの知らせ、私なりに一生懸命協力したので楽しい、うれしいの二重の喜びの1日となりました。
2日目は、朝から晴れ渡った秋空の下、赤かぶの里や北方の豪農の館を見学の後、月岡温泉到着。ジェット機で追いかけてこられた吉宏参議院議員、昌司府会議員の両先生がホテル玄関でのお出迎え。感激致しました。 夕食後、美人の湯にゆったりと入湯・・・美人になったカナ?・・・
3日目は、越後平野西端にある弥彦神社参拝。帰りの車中より田中角栄氏の家を横目に見ながらバスは一路家路に向かってひた走りました。
バス5台にての参加。車中もゆったりとリラックス出来、自民党圧勝で2倍の喜びの旅行となりました。ありがとうございました。
靖国参拝を反対する中・韓の主張
泉首相の靖国神社参拝が、外交上の大きな問題になっています。中韓の主張は、正に、先の大戦をどのように解釈するかという歴史観そのものを日本人に糺すものです。つまり、戦前の日本は、一部の軍人や政治家の妄動のため軍国主義に陥り、中韓をはじめとするアジアの国々を侵略し、多大な迷惑をかけた。東京裁判により誤った政治判断を行ったリーダー達は処刑された。また自身もその犠牲者であった日本国民は、二度とこのような悲劇を繰り返さないように心から反省した。このことを承諾して日本はサンフランシスコ講和条約を受け入れアメリカの占領は終わったはず。それならば当然、戦争の首謀者であるA級戦犯を祀っている靖国神社に、首相が参拝することは到底出来ないはずだ。というのが彼らの主張なのです。参拝するということは、東京裁判を否定することに他ならず、これは由々しき事態だと言うのです。
小泉首相の主張は?

これに対し日本側は何と答えているのでしょうか?中韓の言う歴史観に対しては、敢えて言及せず、と言うよりもそれは自明のこととして反省の言葉を繰り返すばかりです。そして、その上で国の為に亡くなった方に花をたむけるのは、日本人の伝統的精神であり、理解を賜りたいということのようです。つまり、靖国参拝は東京裁判を否定するものではないという態度であるのです。
しかし、これでは中韓が納得しないのも無理はありません。日本人が本当に東京裁判を認めているのなら、その戦争の張本人であるA級戦犯達を現職の首相がお参りすること自体、自己矛盾するからです。本当に東京裁判が正しいのなら中韓の主張の方に分があると私も思います。
東京裁判とは何だったのか
しかし、そもそも東京裁判が中韓両国の主張の根拠と成り得るような正当なものであったのでしょうか。戦勝国が敗戦国を裁き、勝てば官軍だということは世の常と言われますが、東京裁判も正にその類のものであったことは間違いありません。特に、A級戦犯にかけられた平和に対する罪などは、元々、国際法上も存在しなかったものを事後に創出したものです。事後法により処刑するなどというのは、裁判の名に到底値しないどころか、戦勝国のゴリ押しにしても、度が過ぎるというものです。そういう認識は当時から国際的にもあったはずです。しかし、当時の日本は、アメリカの占領下にあり、主権は制限され、言論も統制され、こうした暴挙に逆らうことが出来ない状況であったのです。
日本は、東京裁判を受け入れたということをサンフランスコ条約で謳っているのだから、今更、東京裁判の不当性を訴えても国際的には通用しないと主張される方もおられます。確かに、一見すると法理論上はそのようにも思えます。しかし、この理論は肝腎なことを忘れています。法律は、道徳や正義という法律以前の根本的な価値観の上に成立しているということです。国際的な条約も同じことです。そこに道義のないものは、いくら形式上有効であっても、人々を納得させることは出来ないし、その心を縛ることも出来ない。その意味で無効であるのです。そういう法律や条約はたとえ形式的には有効に見えても、長い歴史の間に必ず無効になってしまうものなのです。何故なら、そこに道義がない為、多くの人々の心を時代を超えて縛ることが出来ないからです。
維新前、当時鎖国していた日本は砲艦外交で開国を迫られました。外交上の無知につけ込まれ、関税自主権のない上、外国の治外法権を認めるという不平等条約を締結させられてしまいました。しかし、この不平等条約も先人の努力の結果、撤廃されたではありませんか。法律論争だけでは現実は何ひとつ解決できません。法律論以前に、そこに道義があるか、筋があるのかということを、冷静に考えることが必要なのです。そういう視点で東京裁判を見るとその不当性は自ら見えてくるはずです。
今後の課題

しかし、だからといってあの戦争が全て正しかったと言うつもりもありません。ただ、東京裁判で示されたように、日本が一方的に侵略行為を行ってきた訳ではないという事実を私は申し上げたいのです。中韓両国は当然反発することでしょう。特に、中国共産党にとっては、反日、抗日の戦士ということに政権の正当性を求めているだけに、相当な反発が予想されます。しかし、そうした外圧をどう調整するかということが、本来外交であったはずです。南洲翁遺訓にも次のようなものがあります。「正道を踏み国を以て斃(たお)るるの精神なくば、外国交際は全かるべからず。彼の強大に畏縮し、円滑を主として、曲げて彼の意に従順する時は、軽蔑を招き、好親却(かえ)って破れ、終(つい)に彼の制を受くるに至らん。」西郷の示したように外交には覚悟が必要なのです。覚悟のない外交は売国行為でしかない、ということを私たちは 肝に銘ずべきではないでしょうか。
しかし、外交姿勢以上に私がもっと問題だと思うのは、そもそも日本人自身があの戦争と戦後社会に対して一度もまともに総括をしたことがないということです。毎年8月15日には慰霊祭が全国で行われ、戦争の悲惨さが語られ、非戦の誓いが述べられています。しかし、それだけでどうして子供たちにあの戦争は何だったのかということを伝えることが出来るでしょうか。どうして中韓の日本に対する一方的な非難に対して、覚悟を決めて外交をするという決意ができるのでしょう。
靖国問題を語る上で一番大切なことはなにか。それは、国の歴史を次代に語り継ぐという、国としての一番の道義を亡くしてしまったことが、戦後のすべての問題の原因になっているということを国民が今一度認識するということではないでしょうか。

日本人の平均寿命は81.9歳と世界一です。一方、平均寿命から病気や寝たきりの期間を差し引いて、平均何歳まで元気で暮らせるか正味の健康な期間を示したのが平均健康寿命でこれも日本は世界一で75歳となっています。しかし平均寿命と平均健康寿命の間に6.9年の差があります。つまり、平均6.9年間病気や寝たきりになっているといえます。
PPKという言葉があります。これはピンピンコロリの略で、最後まで生き甲斐をもって元気に生きて、あまり寝込んだりせずにコロリと旅立つという意味です。これは、昔から多くの日本人が理想としてきた健康美学といえます。そのためには平均寿命と平均健康寿命との間の差をなくすことが大事で、予防医学の考え方が重要になります。これは今後、高齢社会においてより重要性を増していく考えです。
今回は日本において寝たきりの最大の原因になっている脳卒中*をはじめとする心血管病の予防を中心に健康生活の要となる事項について挙げていきます。
*脳卒中とは?脳出血(脳溢血)?脳梗塞(脳軟化症)?くも膜下出血 の総称で、中でも脳梗塞が70パーセント以上を占めている。脳卒中は心筋梗塞の3倍多く、最大の危険因子は高血圧である。
○高血圧。血圧は最も簡便に測定できる健康バロメーターです。高血圧は動脈硬化を促進し、また血圧上昇と平行して脳卒中・心疾患・腎臓病などの心血管病の死亡率が高くなります。血圧は朝高くなることが多く、朝の血圧測定が大事です。朝起床後1時間以内に安静に座って、上腕カフ型の血圧計でカフを心臓の高さにして測定するのが正しい血圧のはかり方です。家庭での血圧が135/85を超えた場合、高血圧とされますので医師に相談しましょう。
○糖尿病は動脈硬化を招き脳卒中の大危険因子であるのみならず、放置すると失明、腎不全、神経障害の原因になります。適切な治療が大事です。
○不整脈はある程度自覚可能です。脈が飛ぶ、乱れるということがあれば心電図等の検査が必要です。心房細動などの不整脈は血の固まり(血栓)を心臓につくりやすく、それが血管に乗って飛んでいくと脳梗塞や心筋梗塞を起こします。
○タバコは万病のもと。ぜひ禁煙しましょう。
○アルコールには利尿作用があり飲んだ以上の水分が尿となって出て行ってしまい結果的に脱水状態(血液ドロドロ)を引き起こし脳梗塞を起こしやすくします。ただし、少量の飲酒はむしろ脳梗塞を予防する効果があり、1日あたり0.5~1合程度がいいという統計があります。
○睡眠中に脳梗塞の40%が起こるといわれます。就寝前コップ1~2杯の水をもむことは脱水を予防し、脳梗塞の予防に役立ちます。
○高脂血症(高コレステロール、高中性脂肪)は動脈硬化を促進させ血栓を作りやすくします。食べ過ぎに注意し甘いお菓子果物ジュース類の摂りすぎに注意。肉、脂類の動物性脂肪を摂りすぎない。青魚を摂取する。などの食生活上の注意が大事です。
○お食事の塩分、脂肪を控えめに。高血圧には食塩の摂りすぎが大敵です。高血圧の人は食塩を1日10グラム以下にする必要があります。目安として、たくあん一切、奈良漬け2切はどちらも食塩約1グラムを含んでいます。
v
○体力にあった運動をしましょう。
○太りすぎは万病の引き金になります。
○脳卒中起きたらすぐ病院へ。ろれつがまわらない、力が入らない、つまずきやすい、食べ物飲み物にむせやすい、急にめまいがするなどの症状はたとえ数分で症状がなくなっても大きな脳卒中発作の前触れであることが多いので注意が必要です。
まずは朝の血圧管理から初めて、日頃の生活習慣を見直して、健康生活を維持しましょう。
昌友会にはたくさんの事業がありますが、「昌友塾」もその一つです。西田昌司の信条を聞こうと月に一度、誰言うともなく自然発生的に出来たのが発端でした。それが70回を超えました。この間、政治や経済の問題は勿論のこと、私達の身近な問題の根源は何処にあるのかを昌司流の切り口と論法で考えてきました。この中で見えてきたのが、私達は敗戦の復興の中で、また経済成長の中で、かなり矛盾を抱えたまま国の繁栄と生活の豊かさを追求してきたことです(ひょっとしたら目をつむっていたのかも知れません)。
例えば、憲法問題、歴史認識と教科書問題、日中の間にある諸問題、拉致問題等々。どうもこれらは我が国の根本、戦後日本の成り立ちの根幹に関わる問題を内包しているように思えます。そして、私達がさも当然のように享有していると考えている安全と安寧すら、どうも危うい土台の上に築かれた陽炎のようにすら思えることもあります。「だったらどうする!」。最近の昌友塾は次へのステップを目指して具体論へと歩みを進めようとしています。「現状分析と認識」から「次の具体論」へ、様々な観点と責任ある自由な発言の中からそれらは生み出されていくことでしょう。是非、みなさんものぞいて見てください。
今回私のテーマは「海外から見た日本の教育」です。別段、比較教育論を展開するつもりはありません。制度やシステムを論じても、私達は学究ではないのですから。今日本では、昭和59年に臨時教育審議会が審議して以来の教育改革への流れが俎上に上っています。それも、学力問題に端を発した教科内容の削減や時数削減を問題としています。しかし、教育改革は21世紀の国の発展を支える根幹として「創造力・表現力」や「問題解決能力」を身に付けさそうと考えたのではなかったか。また、再び学校教育を荒廃させないために自律と責任、協調といった価値を学ばせ、子どもの個性の伸長をその目的に置いたのではなかったか。

ほぼ1/4世紀に亘って論議と試行を繰り返し進めてきた教育改革を、何故か済し崩し的に押し戻そうとする風潮があるように思えます。授業時数削減を元に戻すのもいい。しかし、それは「学校に子どもを行かせれば親が安心するから」、「親の負担を軽減するために学校に行かせる」のであってはならないと思います。我が国の発展を支え、国際社会に活躍できる人材をどのように育てるか、根幹にどのような教育的価値をもってくるのかなどの目的と内容、方法が先に論議されねばならないと考えます。教科書を何ページか増やしても、それを改革とは呼ばないだろうと。
世界も教育改革に取り組んでいます。国際社会で自国の存在を揺るぎないものとするために、そして自国の発展を支える人材を養成するために。ある人が言っていました。「教育改革は立ち止まったらダメだ。常に進める中にしか改革の成果は見えてこない」と。
去る、3月18日にテルサホールで開催致しました第3回西田昌司大演説会には、多くの方々にお集まりいただき大盛会を収めることが出来ました。ここに心より御礼申し上げます。熱気あふれる2時間の内容を、以下に要約させていただきます。
ライブドア問題
ライブドアの堀江社長は「お金で買えないものはない。」という信条です。もしそうならお金より価値のあるものはないということです。しかし、これは正しいとか間違っていると言う以前に非常に下品な言葉です。
フジテレビや財界のお偉い方にすれば、「お金で買えないものは沢山ある。」ということでしょう。しかし、その彼らは何をしてきたのでしょう。今さら社会的正義や社会的責任などお金以外の価値を大上段から訴えても、実際に彼らがしてきたことはマスコミの「軽(カル)チャー路線」に代表される売らんかな主義であり、それにお金を出してきたのは財界です。フジテレビをはじめとするマスコミがしてきたことは要するに、視聴率が上がり出版部数が増えれば良いということではなかったのでしょうか。堀江社長はこの戦後社会の本音と建前の矛盾をついているのです。『報道機関は公器だと偉そうなことを言っても、結局していることは売らんかな主義ではないか。それなら、自分が株を買い取って、もっと儲かる仕組みを作りましょう。』これが彼の主張なのです。これはまた経済人の本音でしょう。お金以上の価値を経済人たちが何ひとつ示すことも守ることもしてこなかったから、堀江社長のような人物が誕生したのです。まさに彼こそ戦後社会の申し子でしょう。しかし、これで本当にいいのでしょうか。
少子化問題

日本の人口は、少子化によりこれから減ることが予想されます。日本の総人口は1億3000万から1億にやがて7500万人になると予想されます。そうすると国力が下がり日本は貧しくなる。これが少子化問題といわれるものです。しかし、私はそうは思いません。
何故なら、逆に人口がどんどん増加すればどうなるのかを想像すれば分かります。人口が増えれば、確かに経済のパイは大きくなります。しかし、地球の資源には限りがあるのです。その人口を支えるだけの食糧やエネルギーの供給は、どうするのかということです。そもそも、狭い日本の国土で人口がこれ以上増え続けたら、まともに住む所さえ無くなってしまいます。まさに、これから世界の国々が一番心配しているのは、世界的な食糧不足やエネルギー不足の時代が訪れるということです。
例えば、日本の脅威として加速的に経済発展を遂げる中国では、ひとりっ子政策を推進して何とか人口を抑制しようとしているのです。しかし、政府の期待に反して人口は増える一方です。逆に日本は人口抑制をしなくても自然と人口が調整されるのですから、本当はありがたい話なのです。つまり、少子化よりも多子化による人口増加の方がもっと大きな問題なのです。
そもそも、人口が減っても世間で言うように貧しくはならないのです。例えば5人家族で500万円の年収で生活していた家庭が、4人家族、3人家族になり、年収が400万円、300万円になったとしましょう。確かに年収は減ったけれど、ひとり当たりの所得は何も変わりません。つまり貧しくならないということです。
今度は財産の面から考えましょう。夫婦にひとりしか子供が生まれないということは、ひとりの孫に2組の祖父母と1組の両親がいるということです。もし彼らが家を持っていたら、このひとりの孫は、祖父母と両親合わせて3軒の家を相続することになるのです。どこが一体貧しいのでしょうか。このように考えると、少子化や人口減少は、多子化や人口増加より随分ましなことなのです。むしろ、限られた国土や資源の中で生活するには、人口の調整が自然にすすめられていると歓迎すべきなのです。
ただ問題は、団塊の世代と呼ばれる戦後のべビーブーマーが一度に老齢化するということです。しかし、これもこの20年間を乗り越えれば良いだけの話です。
少子化や人口減少を日本の危機と考えるのは、人口が増加することが経済成長につながるという思い込みによるものなのです。確かに、戦後の一時期はそういう時代がありました。しかし、これからの時代は全地球的に考えれば分かるように、限りある地球の環境や自然の中では、右肩上がりの人口増加や経済成長は成り立たないのです。COP3の京都議定書が意味することは、正にそのことです。日本、特に京都では、京都議定書の締結の地として環境問題を盛んに唱える人が多くいます。しかし、その人が今度は少子化は問題だと叫んでいます。これは全く矛盾したことなのです。
しかし、この京都議定書に反対し、これからも右肩上がりの経済成長を主張する国があります。それがアメリカなのです。アメリカは日本の25倍という国土に、日本の2倍の人口しか住んでいません。あまりにも国土が豊かすぎて、これが有限のものとは到底実感できないのです。しかし、それはアメリカの誤解であり、全地球的には通用しない話なのです。問題は日本人がそのことに気づいていないということです。それどころか、この不合理なアメリカのビジョンに完全に縛られているのです。
竹島問題

竹島問題も日本の固有の領土が韓国に不当に占拠され、またもや主権侵害にあっているということです。ところが北朝鮮による拉致事件と同じように、今回もまた日本人は主権侵害という認識もないし、それを守る気力もありません。さらに問題なのは、日本が抗議すると韓国が戦前の植民地時代の保障や謝罪まで求めたりするということです。歴史的に見ても、韓国の主張は、日本人には到底受け入れられない話です。しかし、それ以前に韓国の態度は、近代国家として二国間の条約を守るという当然の信義にさえ反することです。何故なら、日韓基本条約で賠償問題は既に解決済になっているからです。当然、日本国政府はそのことを訴えていますが、それが日本国民にきちんと伝わっていないようです。特にマスコミなどは日本の主張より韓国の主張ばかりを宣伝しています。どうやら日本人は、戦前の歴史を知らないだけでなく戦後の歴史も忘れているのです。
「まとめ」
以上述べてきた「お金で買えないもの」「自らの国のビジョン」「主権を守ること」「歴史」というものは全て戦後の社会の中で日本人がことごとく失ってきたものです。このように、今日の日本の問題はすべて戦後社会の問題であり、一本の糸で繋がっているのです。
今必要なのは、日本人が、この事実を知り、目を覚ますことなのです。このことに気づいた人が、家族や友人に伝えていく以外、この状態から脱出することは出来ません。私が10年以上に亘り毎朝街頭で演説をしているのも、そうした思いからなのです。是非とも、皆さんのご賛同とご協力をお願い致します。
【花灯路(はなとうろ)って?】
「はな」に一喜一憂する季節になりました。京都市内は桜の名所を求めて他府県から大勢の観光客が訪れています。京都市では年間観光客数5000万人突破を目指しているそうです。統計によると4月の桜の季節、11月の紅葉の季節は観光客がドット押し寄せますが、3月はいまいちだそうです。「冬の旅」と称して神社仏閣を特別拝観していますが・・・。そこで一昨年から「京都・花灯路」と称し、「東山山麓南へ北へ、だれと歩こう春の宵」なるイベントを企画されました。3月の観光客の底冷えを何とかしようと、京都府・市、京都商工会議所、仏教会、観光協会が主になり、各種マスコミ、JR東海などの各種団体の協力を得て、灯りと花の散策路を歩いてもらおうという企画です。
東山山麓を北は青蓮院から円山公園・八坂神社を通って、南は清水寺までの散策路約4.6kmに京焼・清水焼、京銘竹、北山杉磨丸太、京石工芸、金属工芸の5種類の露地行灯を約2,400基設置。白壁や土塀、石畳に映えるほのかな灯り、門前町の店頭に彩りをそえるはんなりとした灯りなど、京都ならではの表情を見せる企画です。途中の知恩院、高台寺などでは華舞台ステージで様々な催しが行われました。期間は3月の第2金曜日(今年は3月11日)から春分の日の21日までで、点灯時間は午後6時から9時30分まで。一昨年は95万人の観光客が、昨年は100万人を突破、今年は前半雨と寒波にたたられたものの105万人と、着実に観光客を増やしています。今年の土日にはJR東海が東京から「花灯路特別新幹線」を走らせ、車中では舞妓さんが接待をする念の入れようです。

なぜ、瓦が詳しいかといえば、一昨年・昨年と黄色のスタッフジャンパを着て花灯路の交通整理・案内などをしていたからです。東山・清水界隈でのイベントであるのに当初、地元関係者は全く参加しておらず、行政・商工会議場などが走り回っていたように思えました。初年度だけで終わるかと思えば好評につき・・・。といった様子でしたが、今年はやっと地元が御みこしを挙げたようで、瓦も無罪放免となり、「花灯路」を楽しませていただきましたが、伝統的建造物群保存地区でのイベントであっても地元住民が全くの無関心では合点がいきません。飲食・みやげ物店にはワンサカ人が入っており、ホクホク顔で・・・。
これに味を占めたか、秋には嵐山界隈で「花灯路」なるものを企画しているようです。その時は瓦にとってはお役ごめんをこうむりたい気持ちです。祭・イベントはその地区の住民が参加してこそ価値があるもので、お役所や商工会議所がやるものではない、と思っているのは瓦一人だけでしょうか? さて、南区で「花灯路」をしたら何処を見せるのかな?
あほな事を言わんと、もうじき「稲荷」・「松尾」のお祭りが始まるがな。それに住民パワーを注がんと!他所の「花灯路」なんか、ほっときよし! と、天の声に怒られました。
謹 賀 新 年
本年もよろしくお願い致します

知恵と勇気-日本に足りないものは何か-
平成17年が明けました。21世紀になって、もう5年になります。しかし、子供の頃待ち望んだ夢の21世紀に程遠いというのが実感です。景気低迷・財政赤字・年金問題・少子化などの問題が、連日報じられています。「このままでは日本は破綻してしまう。」危機感を煽るようなものも少なくありません。
また、北朝鮮問題や自衛隊のイラク派遣の問題など、日本の自立や防衛に大きな不安を感じる事件も頻発しております。こうしたことが連日、マスコミで報じられれば、日本の先行きに不安を覚えるのも無理はありません。
こうした状況の中、日本には何が必要なのでしょう。何が足りないのでしょう。お金でしょうか。確かに財政難を考えるとそれも必要でしょう。しかし、どう考えても今の日本は史上最も豊かな時代にあります。事実、財政難が叫ばれていますが、日本は世界一の債権国なのです。そして逆に、日本に規制緩和を始め、様々なことを要求するアメリカは、世界一の債務国、つまり借金国なのです。その借金に苦しんでいるアメリカを手本としようとしているのですから、財政が良くならないのも当然です。全く知恵のない話です。
また、イラクの自衛隊の派遣も、イラクの復興支援は建前で、北朝鮮問題や中国の圧力に対して、アメリカの支援を求めたいという本音がその裏にあることは、国民皆が感じていることではないでしょうか。確かにアメリカとの関係は重要です。しかし、最初からアメリカに頼り放しでは、独立国として、あまりに情けない話ではないでしょうか。これでは、勇気のかけらも感じられません。
このように今、日本で問題となっていることの殆んどは、お金が不足して起こっていることではなく、知恵と勇気が足りないことが原因なのです。本当に大切なことは何かという本質を考える知恵と、それを実行するための勇気が欠けているということなのです。
では何故、またいつから、日本人は知恵と勇気に欠けることになったのでしょう。それは、皆さんお気付きのように、敗戦が原因になっていることに間違いありません。特に、最近の日本は愚かで意気地がないように思えます。私は、その原因は教育にあると思っています。
今年で敗戦から60年になります。敗戦により日本は、国の歴史をまともに教えられなくなり、国のあらゆる制度が変革させられましたが、その最たるものは教育です。愛国心を子供に教えることなどは完全にタブーになりました。東京裁判により、大東亜戦争の大義が否定されているため、自分の国の歴史や愛国心まで否定する結果になってしまったのです。これではまともな教育など出来るはずがありません。
先日、後援会の旅行会で、沖縄へ行った時の話です。沖縄は大東亜戦争の際、国内で唯一地上戦があったところです。多くの県民が兵隊さんと一緒になって米軍と戦い、そして玉砕されました。ひめゆりの塔も、そうした物語の一つであります。今なら高校生ぐらいの女の子が、陸軍の野戦病院などに学徒動員され、国の為に献身されていたのです。米軍が沖縄に上陸し、追い詰められ逃げ場を失くした彼女たちは、無惨にも玉砕をしてしまうのです。
ひめゆりの塔には、そうした物語が年表のようにして壁に掲示してありました。そこには、日本の「侵略」により戦争が始まり、米軍の「進攻」又は「反攻」により戦争が終わったと書かれていました。まさに東京裁判史観そのものです。ここには大勢の修学旅行生が見学に来ていましたが、彼らはどの様に感じていたのでしょう。きっと、戦争の悲惨さは伝わったことでしょう。でも、何故あの戦争が起こったのか。また、彼女たち始め多くの日本人が何故戦ったのか、その当時の国民の気持ちなど理解できないでしょう。これでは亡くなった方々にあまりにも無礼なことではないでしょうか。私は非常に情けない気持ちで一杯になりました。

そんな日本であったにもかかわらず、これほど豊かな国になることが出来たのは、戦前の教育を受けてきた人々が社会の最前線で活躍してくれたからです。そうした人々の努力のお陰で、戦後復興を成し遂げることが出来たのです。しかし、そんな方々も昭和の時代の終わりと共に、次々と社会の最前線から退いてしまわれました。終戦時20才の青年も平成元年では64才です。次々と定年を迎えられたということです。そして逆に今、現役で活躍されている人々は、全て戦後教育のみを受けた年代に移ってしまったということです。バブル崩壊後の景気低迷、また、あまりに露骨なアメリカ追従姿勢などに象徴される最近の日本の体たらくは、昭和から平成に変わり、社会のリーダーが完全に戦後世代に入れ替わってしまったことと、無関係ではないと私は思います。バブル崩壊後の景気低迷、また、あまりに露骨なアメリカ追従姿勢などに象徴される最近の日本の体たらくは、昭和から平成に変わり、社会のリーダーが完全に戦後世代に入れ替わってしまったことと、無関係ではないと私は思います。
今、日本に最も足りないもの、それは、知恵と勇気です。問題は、その事実とそれが何故失われてしまったのかという歴史の過程を、誰もが忘れてしまっているということです。大切なのは、国民がこの現実を知るということなのです。それさえ分かれば、必ず日本は良くなるのです。そのことを皆さんにお伝えするため(show you)今年も頑張ります。本年もご支援とご理解を宜しくお願い致します。
京野菜とお正月料理

京野菜の美味しさに魅せられる今昔、千年の都に育まれた京野菜は、日本の食を代表する食文化の源であるのではないでしょうか。食文化を進歩させるのには、「京野菜」が、大きな影響があったと思います。
都が京都に置かれていた頃には、日本全国から各地の生産物が伝えられ、色々な形で入って来たと思われ、種苗で入洛した物もあったでしょう。又もともと京都で育てられて、変化を遂げた野菜も数多くあったでしょう。
そこで今は冬の季節でもあり、代表的な京野菜を少し紹介しましょう。九条ねぎ、水芹、聖護院かぶら、里いも(頭いも、海老いも)、くわい、金時人参、聖護院大根、堀川ごぼう、壬生菜、水菜、等々色とりどりの野菜が有ります。春夏秋冬、四季折々の野菜が生産され、人の健康を考えた食生活が営まれてきました。今では、天候異変等、様々な事柄より、旬が昔とは少し前後していますが、ほぼ昔と同じ作付がなされています。
ここで正月料理にかかせない京野菜の一部を紹介しましょう。お正月の御祝のいわれとして少々こじつけもあろうかと思いますが書いてみます。
◆ 里いも(頭いも)
京都では、白みそ仕立の、御雑煮で頭いもと丸もち、大根、金時人参等を入れられます。頭いもは、里いもの親いもで、親方(頭)になる様にと言われています。
◆ 大 根
大根は、代々家族が続く様にと言葉合わせで言われています。
◆ くわい
秀吉が御土居を築きその土を掘った場所が低湿な土地でありその場所で、くわいを作付したところ、泥の中から新しく芽を出しました。その為くわいは、逆境から芽を出すと言われています。
◆ 堀川ごぼう
堀川ごぼうは、筋があり長く繊維質が通っているので、筋の通った人になるようにと言われています。
◆ 黒 豆
黒豆は、日々まめに仕事をし、暮らす様にと言われています。
◆ 栗
栗は、勝ちぐりと言われ、何事に対してもうち勝つ様にと言われています。
◆ 郡大根、青味大根
郡大根は、昔天皇行幸の度に献上されていました。茶人や一般家庭のお祝い事に需要も増え使用されていました。輪切りにすると菊の御紋に似ていると言われています。また、青味大根も郡大根と同様にお祝い事に使用されました。
◆ 金時人参
金時人参は、「おなます料理」にはなくてはならない食材で、祝い事には欠かせません。真紅の色合いから梅の花に見立てて、形抜きされ祝料理に使われます。
正月料理のいわれ等を書きましたがこれは、とかくお酒を飲んだりおもちを食べる機会が多いので、野菜の繊維質を多く取り体調を整えるという先人の知恵なのではないでしょうか。今でも変わらずと言えるでしょう。現在の食生活でも適度なタンパク質と旬の野菜を取り入れたバランスの合った食べ物を摂ることが大切です。そして口を動かし良く噛み脳に刺激を与えれば食を通じ身心共に健康になれるのです。そのためにも、後生の人々に良い物を伝承していく事が大事だと思います。
皆様にとって、今年も健康で良い年であります様にお祈り申し上げます。
謹んで新春のお祝いを申し上げます
参議院議員 西 田 吉 宏

皆様には、おそろいで新春をお迎えのことと心よりお慶び申し上げます。
日頃皆様方には、温かいご芳情とご支援を賜り、誠に有り難うございます。お陰様で元通りの健康を取り戻し、元気に国政の場で励んでおります。
私も三期16年目を迎えました。これからも参議院が上院として国政に果たす役割の重大さを噛みしめながら、日夜諸課題の解決に向けて取り組んでおります。皆様の「声、思い」を国政へ届ける架け橋となり、信頼される政治と生活の安定の実現のため全力を傾注してまいります。今後におきましても、西田昌司府議会議員共々ご支援ご指導を賜りますようお願い申し上げます。
結びに、皆様方の一層のご健勝とご多幸を祈念申し上げまして、新年のご挨拶と致します。

みなさん新年,明けましておめでとうございます。ボリビアの地から新年のご挨拶をさせていただきます。(編集部からお正月の様子を書けと言うことで,まずその話から)
ボリビアのお正月は家族や親しい友人達と過ごすのが普通です。これは,「お正月のひと時こそ1年間自分が過ごしたいと思う最高の時を凝縮した時間」と考えるからです。大晦日の夜から始まり翌日(元旦)の朝まで,飲んだり踊ったりします。
大晦日の10時頃から集まり,久しぶりに会った友人達と話や踊ったりしながら,その時を待ちます。とにかく,この変化の時間「0時」の瞬間が大切です。花火をたくさん用意し,時計の針が「0時」を指した瞬間に一斉に打ち上げます。花火や爆竹を鳴らすことで,旧年の厄病を身体の外に追い出します。そして,全員で新年を祝い乾杯をします。この乾杯も重要です。日本のように「旧年中はお世話になりました。本年もよろしく」などの硬い挨拶は抜きです。新年に向けた願いやお祝いの言葉を話すのが多いようです。
ある家族や友人の会では,自分達が新年に向けて挑戦したい事柄を実際にやって見せます。例えば,旅行したい人は旅行バックを持って玄関を出たり,大学に入学したい青年は本やノートを持って「大学入学達成」と叫びます。子どもが欲しい夫婦は人形を抱いて見せたりなど,各人が工夫して自分の抱負を披露します。
このような儀式の後は,伝統的な料理と酒,そして何より家族や友人と時を共に過ごすことを朝まで楽しみます。豚肉ととうもろこしのスープ(フリカセ)やとうもろこしのお酒(チーチャ)がその代表的なものです。ボリビアの高地では辛子の利いた煮物やスープが昔から食べられています。フリカセは二日酔いにも利きます(念のため)。みなさん朝帰りですので,一日の街中はいたって静かなものです。
どうですか。私たちの日本のお正月と比べて。元旦の朝はどこの国も静かに明けます。日本では日の出と共に若水を汲み,お屠蘇を祝います。しかし,ボリビアでは日が変わることが重要ですから,夜中にお祝いをしてしまいます。この辺りが信仰と相まって少し違うところですかね。
ああ,そうそう。ボリビアには日本の移住地があり,日系の人達が多く住んでいます。ここではおせち料理を作ったり,お鏡もちを供えたりと,日本とまったく同じ迎春の風景です。最近はおせち料理が作れない若い人達が増え,仕出屋さんに頼む家庭が増えたと聞きました。これもよく似た話です。
8月の29日から9月4日までの1週間、ロシアを訪問してきました。京都府とロシアのレニングラード州とが友好提携を結んで今年で10年になります。レニングラード州議会の招聘を受け、京都府議会から議会運営委員会の理事が代表として訪問することになり、私もその一員として自民党の議員団を代表して訪ロすることになったのです。
ロシアには、ロシア国営航空のアエロフロートの直行便が成田から飛んでいるとのことでしたが、日程等の関係から、大韓航空で向かうことになりました。残念ながら日本の航空会社には直行便が無ないのですが、大韓航空にあるということです。それだけ韓国がロシアに対して投資をしており、多くのビジネスマンがロシアとの間を行き来しているからでしょう。事実、ロシアの空港に備え付けてある大きな薄型テレビは、LGという韓国のメーカーのものでした。また、市内のあちらこちらでも韓国企業の看板を多く見ることができました。韓国が、ロシアの投資に熱心に取り組んでいることが、こうしたことからもよく見て取れます。
ところで、大韓航空を利用するため、一度ソウルに立ち寄らねばならないのですが、ここでもまた我々は、韓国の躍進ぶりに目を奪われることになるのです。我々が乗り継ぎのため立ち寄ったのは、ソウル郊外に新たに建設されたインチェン空港です。これは、韓国が国を挙げてアジアのハブ空港とすべく建設をしたものであり、関空を遥かに凌駕するもののように見えました。関空では、民営ということが最初に決められたため、高い離発着料が課せられました。そのため、航空会社が関空への乗り入れを敬遠し、ますます関空の経営を苦しめています。これではインチェン空港を始め、国家戦略で国費を投入して作られたアジアの他の空港に遅れを取ることは必至であるとの気がしました。

さて、ロシアについてです。我々は、モスクワとサンクトペテルブルグの二つの都市を中心に訪問をしましたが、どちらの都市も経済発展という尺度で見る限りは、全く論評に値しません。日本とは比較にならないだけでなく、同じ共産圏であった中国の躍進振りと比べても、この国の停滞の状況が深刻であるということが見て取れます。
経済の面では見るべきものは殆どありませんでしたが、日本が参考にすべきものが他に多々ありました。それは歴史に対する人々の態度なのです。
ロシアでは74年間にわたる共産主義政権のため、歴史や宗教が否定されてきました。また第二次大戦ではヒトラーに国土が攻め込まれ、両都市を始め多くの街が破壊されてしまいました。ロシア帝国の長い歴史を持ちながらも、こうした事態のため歴史や伝統が破壊されるという悲惨な時代を彼らは経験してきたのです。
共産主義の行き詰まりからソ連が崩壊しました。そして、かつてのライバルであるアメリカには、経済力ではその後姿が見えないほどの差をつけられています。しかし、彼らは決して自信を失っている風には見えませんでした。特にアメリカに対しては、まるで小馬鹿にしたような態度さえとることがあります。「確かに経済ではアメリカに負けた。しかし、アメリカに文化や文明で負けたわけではない。我々は偉大な歴史を持つロシアの民である。我々はヨーロッパの起源であるギリシャやローマの歴史を受け継ぐ正当な後継者である。アメリカにはそうした歴史が無い。また、学ぶべき伝統や文化も無い。」これが彼らの本音のようです。
ロシアでは、ソビエト崩壊後、閉ざされていたロシア正教の協会が復活し、市民の精神の拠り所となっています。また、革命や戦争で破壊されていた建物も修復が行われ、昔の美しい姿を取り戻しつつあります。私の目には、彼らがそうしたことを通じて、ロシア帝国の時代の自身と誇りを取り戻そうとしているように映りました。共産主義の箍(たが)が外れて、彼らは歴史にそのアイデンティティーを求めているかのようです。
彼らは、共産主義を倒すことにより長い間の歴史否定の呪縛をとくことが出来ました。ロシアは、冷戦には負けましたが、自分たちの歴史を取り戻すことが出来たのです。そして、それが彼らの自信やエネルギーになっているのです。これはロシアだけではありません。冷戦の崩壊により、世界各地でこうした歴史が取り戻されようとしているのです。皮肉なことに、彼らの頭を悩ませているチェチェン問題も、共産主義の崩壊によりチェチェン人のアイデンティティーに火が着いたことから始まっているのです。

日本の政界でも冷戦の崩壊を受けて社会党が壊滅し、民主党が誕生するなど、大きな変動の渦の中にあります。しかしその変動の渦の焦点は何か、日本ではまだそれが明確には見えていません。ただ闇雲に、旧体制の破壊が繰り広げられているばかりです。
ロシアを始めとする冷戦崩壊後の世界の様子を見れば明らかなように、今、日本に必要なことは、私たち自身の歴史観なのです。敗戦の中で失われた日本人としての歴史観の復権以外に無いということを改めて確信した旅でもありました。
新産学連携による社会貢献型ビジネスモデルへのチャレンジ
マリアの風プロジェクト
生田産機工業株式会社
代表取締役社長 生 田 泰 宏

当社が京都試作ネット※(設立4 年目)の前身となるドラドラ会(経営勉強会)へ参画してすでに10年以上の歳月が流れている、当社の基幹事業は今でも伸銅設備機械の製造ですが、京都試作ネットへの参画を通じて従来マーケットに存在する自社顧客以外へ目を向けたり、「試作」というキーワードから大学、研究機関、大手企業との連携から新たな「創造」を考える機会が増えてきています。
そんな中、当社の技術者が有する高度な「流体力学」の専門知識を他分野へ生かせないかとの思いを長年抱いていたところ、昨今の環境学習の高まりや、自然エネルギー利用の促進、省エネ活動が身近なものとして多くの人たちの関心の対象となってきている事などを背景に、小型の風力発電機を自社開発、製作してみようと思い立ちました。
と同時に、京都試作ネットメンバーの多くが所属している機青連で地域貢献事業の一環として7年以上にわたって取り組んでいた、インターンシップにおいて(学生を職場に受け入れて職業体験をさせる)風車の製造体験させることが出来れば、より実学に近い生きた職業体験の場を学生に提供させることが出来るのではないかとの話を京都試作ネットの会議で提案したところ、京都試作ネットとの交流がすでに進んでいた京都大学機械工学科、そして三菱重工業からも賛同を得ることが出来、当社を含めた4グループ連合でのプロジェクトを組んで「新産学連携インターンシッププログラム」としてこの社会貢献型事業を推進していくこととなりました。
しかしながら世の中にはない新しい形のインターンシッププログラムですから、授業カリキュラムの作成や学生へのインターンシップ募集説明会の開催、大学側先生へのご理解と支援を得るための説明をこなし、それぞれの役割分担を明確にしながらの、手探り状態ではありましたが8月31日に無事スタートを切り、新産学連携のもとで学生達の手による風車の実像が見え隠れする状態に進んでいます。風車の完成は10月末日を予定しています。
また、「社会貢献型」としての完成された風力発電機の使い道はとっても大事なファクターであり、国際協力機構(JICA)から南米ボリビアへ教育分野での国際貢献活動で出向されている堀先生からアイデアを出していただきました。それはプログラムで完成された風力発電機を南米ボリビアにある電力事情がとても悪い貧困地域に立地する学校に寄贈し、国際貢献に一役買おうという画期的、いや冒険的?な提案でした。
そのため,このプログラムの母体となるプロジェクトを「マリアの風(El viento de Maria)」と名づけ,各社が協力することになりました。
この社会貢献型インターンシッププログラムの推進を通じて、地域に根ざし、地域で雇用を行う我々中小企業にとって、従来の発想では連携出来えなかった今回の新連携による社会貢献を前面に打ち出した新しいインターンシップモデルが社会的認知を受け、大学、企業、自治体、NGO、研究機関などとの新連携につながるモデルへと発展させていく道筋を描きたいと考えます。
そして、社会貢献事業から日本の物作りの基盤となる「人づくり」に向けた「学習モデル」の構築が工学系大学院が持つ「教育モデル」と企業側が持つ「理論と実験のモデル」とを統合させることにより可能となり、最終的には学校、地域、企業が互いに適正な利潤を上げる「社会貢献型ビジネス」のとしての成立へと発展させたいと願うものです。
今日もわが社では4名の学生達が真剣な眼差しで、「ものづくりのプロフェッショナル」達である社員から指導を受け、世界に一台しかないオリジナル風車の完成を目指して生き生きと“ものつくり”に励んでいます。アンデスから吹くマリアの風に乗ってボリビアの地で活躍する風車を夢見ながら,頭を使い、手を動かし、実学を学んでいます。
※脚注
『京都試作ネット』とは、京都に立地し加工業を営む中小企業のグループが「試作加工に特化」して仕事を請け負うための試作専門サイトを共同で運営している企業集団で、『京都を試作の一大産地にしよう』をスローガンにしています。
(着物を着て、七五三のお参りを・・・。)
七五三のレンタル衣装と記念写真の広告が目に付く季節になりました。
七五三は、三歳、五歳、七歳と成長の節目に氏神様にお参りしてこれまでのことを感謝し、これからの幸福と長寿をお祈りする行事で、もともとは宮中や公家の行事でしたが一般に広く行われるようになりました。乳幼児の死亡率の高かった昔は、七歳までは神の子とされ、七歳になって初めて社会の一員として認められたそうです。三歳の男女は共に「髪置き:髪を伸ばし始める」、五歳の男の子は「袴着:初めて袴をつける」、七歳の女の子は「帯解き:帯を使いはじめる」のお祝いが現代の七五三に定着しました。
ところで、着倒れのまち、京都では七五三の衣装は着物が似合うと思うのですが、昨今の七五三参りを見ているとそうでもないらしい。関東地方では七五三の衣装はレンタルがかなり普及していますが、京都では今ひとつ普及していないようです。理由は正絹の着物への想い入れが強すぎるためではないでしょうか。七歳以下の子供に着物を着せるのは、本人は無論のこと、両親にとっても苦痛になっているようです。朝早くから美容院で着付けをしてもらっている子供もいます。子供だけで、両親まで手が回らず、両親はTシャツ・ジーンズ姿でお参りしている家族連れも見かけます。何とも様になっていないと思っているのは瓦だけでしょうか。

室町のはじめとする呉服業界も、子供にはもちろん、大人にも着易い着物を提供できないかと思います。洋服姿の子供さんを否定するわけでは在りませんが、男の羽織袴姿には一段とりりしさが増し、女の子の着物姿にはかわいらしさが増し、子供ながらにも誇らしさが漂ってくるのではないでしょうか。ある自動車会社のコマーシャルのように「ものより、こと」。心の思い出が大切ではないでしょうか?着飾ってホテルのラウンジでの七五三のお祝いも素敵ですが、神木の生茂る神社の中で神主の「のりと」を聴くことも、子供心の思い出になるのではないでしょうか?
何?レンタル衣装を着て、記念写真とホテルの食事だけで、お参りの無い七五三を済ます家族がいるって・・・。
総理の外交手法の問題か
小泉総理の二度目の訪朝で、曽我さんの家族は残したものの、地村さんと蓮池さんの家族は帰国することができました。一方、横田さんはじめ拉致被害に遭われた方々の消息については、何ら新しい情報が得られず、米の支給など北朝鮮への人道的支援が再開されるということに、反発を覚える方もおられます。小泉総理の訪朝については、賛否両論があるようです。
当事者としての意識の欠如

しかし、よく考えてみれば、残念ながら現在の日本の安全保障体制では、誰が総理大臣であっても、拉致事件の全面的解決はあり得ないのではないでしょうか。北朝鮮は、日本に対してミサイルを配備し、核兵器まで開発を準備していると言われています。これに対して日本では、そうした事実を知った今も、北朝鮮への人道支援を見合わせたり、経済的制裁の効果を上げるために北朝鮮籍の船の入港を拒否できる法律(特定船舶入港禁止法案)が検討されたりしてきただけです。北朝鮮の攻撃から日本を守るための防衛手段については、相変わらず何も講じられていないのです。自国民が不当に拉致され、自国に向けた核兵器が準備されようとも、それに対する自主防衛策は何一つ取られていないし、そのことについて問題ありという声さえも出てこないのが現実なのです。そして、日本のこうした状況を知っているから、北朝鮮は誠意ある対応をしないのです。北朝鮮は日本を外交交渉の相手とは認めず、北朝鮮に対して攻撃能力のあるアメリカにしか目を向けていないのです。従って、北朝鮮の核開発など、安全保障上の根本的なことについては日朝間で話がされるのではなく、アメリカ・中国・ロシアそして韓国を交えた六カ国協議に委ねられているのです。
アメリカ頼みの外交・安全保障の限界
実はそのことを日本人自身もよく分かっていて、日本政府も拉致事件を六カ国協議の議題にしてほしいとアメリカにその協力を要請し、拉致被害者のご家族もアメリカの政府高官に直接陳情しています。そして、拉致事件のみならず北朝鮮の核の脅威から日本を守るためにも、アメリカとの同盟強化が一番の国益であると考えている国民が大半ではないでしょうか。
イラクの自衛隊派遣がこうした考えの延長線上にあるのは言うまでもありません。一応建前としては、イラク復興に協力をし、国際貢献をすることが大義名分とされています。しかし、そもそもイラクを破壊したアメリカがその大義名分を明らかにでき得ない状況にあるのです。大量破壊兵器は見つからず、民主化をすればするほど反米感情が高まり、アメリカは完全に隘路に陥っています。こうした状況下での自衛隊のイラク派遣の意味することは、日本がアメリカへの協力姿勢を国際的に明らかにしたということです。日本に取っては国際貢献より対米協力が重要だとほとんどの国民も思っているようです。
しかし、北朝鮮のミサイルの射程の完全な内にある日本にとって、北朝鮮問題は死活問題であっても、射程がわずかにかかる程度で、遠く離れているアメリカにとってはそれほど重要な問題ではありません。アメリカは北朝鮮よりもむしろ、そのバックにいる中国の意向に配慮しながら外交をしているのです。

ところで、北朝鮮は核兵器という大量破壊兵器の開発を準備し、間違いなく国民に圧制を敷いています。イラクにしたようにアメリカが攻撃したらどうなるでしょう。そうなれば、いくら北朝鮮でもひとたまりもないでしょう。北朝鮮は崩壊し、韓国に併合されることになるでしょう。韓国にはアメリカ軍が駐留しています。その結果、中国はアメリカ軍と直接国境を接することになるのです。こうした事態を中国は断じて認めないでしょう。また、アメリカにとっても、中国と緊張関係を高めるのは得策ではありません。北朝鮮問題に下手に関わることにより、世界最大の市場になる可能性の高い中国と敵対関係になることは、アメリカの国益を損なうことになるからです。日本にとってアメリカの軍事力は非常に頼りに見えても、それが日本のために使われるものではなく、アメリカの国益のために使われるものであるということを、私たちは知っておかねばならないのです。
大切なことは独立自尊の気概
北朝鮮による拉致事件を解決するには、まず、日本人が自分の国は自分で守るという当たり前のことに気がつかねば、根本的な解決はあり得ないのではないでしょうか。今日のように、日本人自身が、当事者としての問題意識を欠いていては、誰が訪朝しようとも拉致事件を解決できるはずがないのです。拉致事件を契機に、我が国の安全保障を、特に自主防衛という独立国にとって当たり前のことの必要性を国民世論として広げることが、拉致事件解決のただ一つの道なのです。
グローカルコンソーシアム
『京都試作ネット』がめぜすもの
京都試作ネット 代表 鈴木 三郎

『京都試作ネット』とは、京都に立地し加工業を営む中小企業のグループが、インターネット上で「試作加工に特化」して仕事を請け負うための試作専門サイトを共同で運営している企業集団です。21世紀に突入した2001年7月にサイトをオープンし、お陰さまで、全国各地からこれまでに約800件を超える引き合いを受けています。
表題のサブタイトルにも揚げました、グローカルコンソーシアムとはグローバル(地球的)な視点で考え、ローカル(地域的)に活動する企業連合という意味です。この京都試作ネットを立ち上げるにあたって、我々は、「なぜ、何のために」この活動をするのか? そして何を実現したいのかについて議論に議論を重ねました。その結果、共有できるものとして生み出したのが以下のようなものです。
【目的】
?企業としても生活者としても真に自立すること。
自立とは、自ら考え、自ら判断し、自ら決断して、自らの責任で行動すること
?これからの時代に必要とされる「モノづくり」のビジネスモデルを作り上げ、次世代の人たちが繁栄でき、「夢」をもってモノづくりができる環境を残す。
?「試作」という高度なモノづくりを通じて人が人として成長する場を提供する。
【目標・ビジョン】京都を「試作」の一大集積地にする。
【行動指針】グローカルコンソーシアム。グローバルな視点と一社で出来ないことを地域で連合を組むことで成し遂げていく。連合体(全体)が良くなることで、それぞれの企業(個)も繁栄する。
【仮説】中国が「世界の工場」なら、日本は「世界の開発センター」になり、日本の高度なモノづくり技術で世界に貢献し、繁栄すればいい。その時「試作」が重要になる。

グローバルな視点を持つということは、自分達の属する“国家”という概念を持つことにつながります。またローカルに活動するということは、自分達の生活の基盤である「地域を発展させるために自らが何をなすべきか」ということを問うことにつながります。“誰か”が何かをしてくれるという他人任せから、自らが何をなすのかを考え実行する、真の自立が必要なのではないでしょうか。
京都は、1200年を超える“みやこ”としての歴史があります。その時代々の先端技術を駆使したモノづくりの歴史があり、一流のモノづくりの感性があります。
このような地域としての共有資産をいかに活かし、これからをいかに時代にマッチしたビジネス様式に変えていくかは、我々一人ひとりに課せられた課題です。時代と共に老朽化し、閉塞状態になった事業を再生させるのは、今を生きる我々に与えられた使命ではないでしょうか。自分達のことは、自分達で考え自分達で行動することが問われているのではないでしょうか。勿論、今のような変化の激しい時代は、一人や一社でだけで新しいモデルを作り出すことは困難です。だから思いを同じくする者が集まって智恵を出し合い、果敢にチャレンジして行くことが重要になると思います。また、そうしたチャレンジする集団に対して、地域ぐるみで支援していくことも、地域の産業再生を成功に導く大きな要素となると思います。
企業も行政も政治も本来的な目的は、そこに所属する“人びと”が幸福に暮らせるようにすることではないでしょうか。それぞれがバラバラに良かれと思うことをやっていたのでは、力が分散し成果には結びつきません。非常にもったいない話です。今こそ、その共通の目的の前に、企業経営者も行政や政治に携わる人々も、垣根を越えて、オール京都で力を結集し立ち向かう時ではないでしょうか。
ものごとの始まりは全て小さなことからスタートします。それがやがては塊になり、そしてある時点で一挙に大きな集積となるときがくる。その転換点は人々の「意識の変化」であると我々は信じています。『京都試作ネット』は、今はまだ小さな組織でしかありません。我々のビジョンや取り組みに賛同していただける人々や企業が少しずつ増えてくることを信じて、日々活動をしています。
アンデスにもあった海の日
羅城門の樋
今回も南米からの報告です。ボリビアは9割がカトリック教徒で,街のいたるところに寺院があります。3月の日曜日に街の中心にある聖フランシスコ教会を訪れました。(この教会の外壁はインカ文明の面影を残しています。滅ぼされた文明の抵抗でしょうか。)この教会の広場では,日夜様々な催しが行われます。野外ロックコンサートもあれば,移動遊園地にもなります。ちょうどこの日は,集会を行っていました。いつもの野次馬根性で覗きに行くと,真っ赤な制服に着剣した銃を持った大統領府近衛連隊も参加しています。思わず隣の人に聞きました。「これは何の集会ですか。」いぶかしげに私を見た男性が,日本人だと判ると丁寧に説明してくれました。「もうすぐ海の日です。それで商工団体が集会を開いているのです。」「海の日なら日本にもあります。だけど盛大ですね。」その意味を聞こうとしたとき,軍楽隊が国歌を演奏しだしました。彼は口に指をあて姿勢を正しました。周りを見ると私に靴を磨かせとしつこく言い寄ってきた少年も「気を付け」をしています。道を歩いていた大人たちも立ち止まり,ある人は帽子を脱ぎました。(海の日とはチリとの125年前の戦争で唯一の海岸を失った日です。我が国風では臥薪嘗胆,因みに近衛兵が着ている制服は当時の軍服だそうです。この1週間は職場や学校で,失った海を取り戻すための様々な行事が行われます。国歌演奏の後で教えてもらった話です。)
そういえば,我が国にも「北方領土」の問題がありましたね。しかし,国を挙げてこの問題を考えるというのは,ついぞ聞いたことがありません。あちらは百年以上も前の話,こちらはその半分の年月です。また,国歌の演奏が流れたからといって,話しをやめたり立ち止まるという話も聞きません。(そう言えば,式の最中に国歌が流れたら座るという話は聞いたことがありますが。)近くで不動の姿勢をしている靴磨きの少年(小学校の3・4年ぐらいかな)を見ながらふと思いました。『国は君に勉学の機会さえ十分に与えていない。それでも君は国を愛するのか,国に忠誠を誓うのか』と。
夜に,財務省の友人と食事をしながら,その日の出来事について話をしました。海と開発の話は当然として,靴磨きの少年の話も出ました。彼は驚き顔で言いました。「国と個人はギブアンドテイクではない。この国はすべての国民に充分な生活を保障するほど豊かではない。」「しかし,国民の多くはこの国に生まれ,この大地で生きていくことに感謝している。これは神と国への感謝の気持ちだ。」と。権利と義務の関係でしか少年を見られなかった自分の偏狭さを思い知らされた一日でした。自分の境遇を嘆くのではなく,その中で精一杯働き,幼いながらも家族の生活を支える少年のたくましさを通して,人の誇りについて考えさせられる一日でもありました。
平成16年2月29日、船井郡丹波町の農場において高病原性鳥インフルエンザ(H5N1型)の感染が確認さました。また、3月5日には同町内で新たな感染が確認されるなど、日本中がこの問題の行方に注視しました。京都府では2月27日、直ちに山田知事を本部長とする高病原性鳥インフルエンザ京都府対策本部を設置し、発生農場から30キロメートル以内の養鶏農家等に対する鶏、鶏卵等の移動制限を発動し、徹底した防疫措置を講じて参りました。また、府議会においても24年ぶりに臨時の本会議を開き、この問題の早期解決のため、議会としても府や国に対して直ちに適切な対応を取るように決議をし、関係機関に協力を要請してまいりました。こうした結果、3月22日にはすべての防疫措置が完了致しました。鶏卵、鶏肉を食べることにより鳥インフルエンザウイルスが人に感染することは、世界的にも報告されていません。皆様には、冷静な対応をお願いします。
法の未整備が招いた悲劇
今回の事件は、様々の教訓を我々に示しました。その最たることは、法律が現状に全く対応できていないといいことです。家畜伝染病予防法は昭和26年に制定されたのですが、当時は何十万羽も飼育する養鶏場など存在せず、巨大養鶏場を念頭にした法整備が全くされていなかったということです。
浅田農産は船井農場以外に五つの農場があり、そこにはまだ175万羽の鶏が飼われています。それらは鳥インフルエンザに感染をしているわけではありませんから出荷は可能です。しかし、今回の事件により市場から締め出され、出荷は完全に止まり、毎日莫大な量の鶏卵が蓄積されています。今後もこれらの鶏卵や鶏は恐らく出荷できないでしょう。そうなるとこの鶏や鶏卵の処分は一体どうなるのでしょうか。
1羽当たり4~5円の餌代がかかるといわれていますから、175万羽では、一日800万円前後かかることになります。収入が途絶えた中でこれだけの経費を浅田農産が負担し切れるでしょうか。このままでは浅田農産の倒産や社長の逮捕という事態も当然ありうるでしょう。その場合当事者不在の状態で莫大な数の鶏や鶏卵の処分は誰がするのでしょうか。現在の法律では、鳥インフルエンザに感染していない鶏を行政が殺処分することは出来ません。このままでは最悪の場合、175万羽の鶏が餓死し、放置されることもありうるのです。莫大な量の鶏や鶏卵が放置され腐敗したらどういうことになるのかは想像に難くありません。
市場に流通出来ない鶏や鶏卵を処分するには最終的には焼くか埋めるしかないでしょう。しかし、船井農場の25万羽の鶏と鶏卵を埋却処分するだけでも大変な労力と経費がかかったのです。それが175万羽となると一体どういうことになるのでしょうか。現行の法体系の中ではこうしたことがまったく考慮されていません。

また、家畜伝染病予防法では、鳥インフルエンザの感染が確認された場合には、そこから半径三十キロの養鶏場では鶏や鶏卵の移動が禁止されることになります。これは、その地域を封鎖することによりウィルスの蔓延を防止しようとするものです。また日本では、鳥インフルエンザの予防ワクチンの接種を養鶏業者に認めていません。これは、ワクチン接種で鶏の発病を押さえることより、ウィルスの蔓延を防止するという国家防疫が優先されたからです。国家防疫の観点により、事業者に感染の通報を求め、蔓延防止のために殺処分の命令が規定されています。しかし、それを担保するための具体的方策や風評被害も含め、事後の損失の補償などは全く想定されていないのです。そのため、多くの養鶏農家が莫大な損害を蒙っているのです。
浅田農産の事件もこうした国の制度の不備が招いたものではないでしょうか。例えば、もし、浅田農産が一週間早く感染の疑いを届け出ていたら事態はどうなっていたでしょう。近隣の養鶏場への二次感染やカラスへの感染は防げていたかもしれないし、ウィルスの大量増殖も押さえられ、国家防疫上はもう少しましな状態になっていたでしょう。何よりも世間の浅田農産に対する非難はこれほど大きなことにならなかったでしょう。彼らは加害者ではなく被害者として報じられ、会長夫妻も自殺することはなかったかもしれません。しかし、それでも、船井農場の鶏はすべて殺処分され農場が閉鎖されたことは間違いないでしょう。京都産というだけで、市場から鶏卵が締め出されている現実を考えると、今と同じように浅田農産の経営する他の農場からの出荷は出来なかったのではないでしょうか。結局、彼らには破産しか道が残されていなかったのかも知れません。

現行の制度ではこうした事態は十分有り得るし、恐らくそうしたことを彼らも考えたのではないでしょうか。そう考えるとやはり彼らも被害者であることは間違いないのではないでしょうか。30キロ圏内の移動禁止圏内のある養鶏農家の方がポツリと、「明日は我が身や」と漏らされた言葉が頭を離れませんでした。こうした悲劇を二度と出さないためにも、制度の抜本的な見直しを早急にする必要があるのです。
医学研究における日米の国益意識の差異からの考察

医学博士
石上 文隆
昌友塾生
元市会議長 故 石上忠太郎先生のお孫さんです
私は外科医として10年の間、消化器外科の研究に従事してきました。海外の病院でも研修しましたが、その中で感じたのは、殊に日米間の医師、研究者のおかれている環境が、あまりにも違うことでした。日本の研究者は、実験の外、準備、試薬の購入と管理、後片付けまで自分でします。米国の研究者の主な仕事は実験の指示をすることだけで、あとはそれぞれの専門家が担当します。そうしたシステムのなかで日本の研究者が何年もかけてするところを、彼らは数ヶ月あるいは数週間で完成させてしまいます。それが米国における基礎研究の圧倒的な強さにつながっています。
研究者の環境の違いは両国における国家意識、言い換えると国益意識の差のように思います。米国の研究者と話をして痛感したのは、米国政府が自国の国民医療を向上させかつ自国の医学研究が世界一であり続けるためにはどのような研究システムがベストかという事を第一番に考えているということです。日本ではそのような国家、国益意識などありません。施設だけ建ててあとは研究者が勝手にやれというシステムです。
幸いにして国家・国益意識が無いにも拘らず、冷戦構造と日米安保のもとで日本の国際競争力はバブル時代には世界1といわれるまでになりました。しかし現在では韓国に追い抜かれ30位(平成14年)で、31位の中国に迫られています。日本の物の面での豊かさのピーク、つまり実質賃金のピークは昭和47年です。これは少し年配の方々の実感と一致するのではないでしょうか。この頃から日本は米国にならい、余剰利益を賃金に反映させることをやめその代わりに生産効率をあげ株価を上昇させるという米国的株価至上主義を採用しだしました。その結果、プラザ合意ともあいまって壮大なバブルが発生し、それを実質の国力に転換することを怖がり、マスコミのバブル叩きにけしかけられた政府が総量規制という社会主義的政策を採った結果、今日の失われた10余年という経済状況があるのではないか。採るべき政策は総量規制ではなく建築規制の緩和だったのではないか。高層建築が可能になり地価が実質の価値になりえたのではないか。バブル崩壊とその後の不況はアメリカに倣いながらも真に独立した強国たることを恐れた結果ではないか。昭和47年は同時に米国に倣い国家の財政均衡を放棄した年でもあります。その結果、現在の日本の財政状態はボツワナ以下世界最悪の状況です。政府が専守防衛、非核3原則、防衛費GNP1パーセント枠を打ち出した時期とも一致します。つまりこの頃を境に日本が真の独立国になることを捨てあるいは恐れ対米従属を強化していったといえます。バブル崩壊とその後の不況はアメリカに倣いながらも真に独立した強国たることを恐れた結果ではないか。米国の表面のみを倣い今の日本の状況があるのであれば、今後の日本の進むべき道は明らかではないでしょうか。時代は変わりつつあります。西田先生が唱えておられる日本人の精神の復興運動こそが今後の日本政治の目指すべき方向ではないでしょうか。西田議員、昌友塾、京都発言者塾に今後ともなお一層のご支持ご支援のほどよろしくお願いいたします。
-牛肉の味噌漬け-
NHKの大河ドラマ「新撰組!」が好評を呼んでいます。幕末を描いたドラマは主に勤皇の志士からの観点が中心でしたが、今回はなぜか新鮮な感じがします。坂本竜馬と近藤勇が旧知の仲だったとは意外な感じがしているのは瓦一人だけではないはずです。
あの「桜田門外の変」も水戸浪士の私生活から描かれていましたが、以外にも「牛肉の味噌漬」も一役かっていたそうです。

そのわけは、彦根藩では、江戸時代の初めから「薬食い」と称して、食用の牛を生産していました。(いつの世も抜け道はあるものですね)記録によれば、牛肉の味噌漬は将軍家への献上品だったそうです。この牛肉を食する習慣を、井伊直弼が殺生を説き領内で牛屠殺を禁止しました。ところが、水戸のお殿様の斉昭公は将軍お裾分けの牛肉の味噌漬が大好きで、井伊直弼の決断を知らずに再三再四おねだりをしたそうです。直弼は、申し出を断ったばかりか、逆に斉昭公を辱めました。これが原因で水戸藩と彦根藩の間に深い溝が生じたといわれています。これが真実ならば、食べ物の恨みは実に恐ろしいとしか言いようがありませし、「牛肉の味噌漬」が歴史を動かしたともいえるのではないでしょうか?
このように歴史の側面を、三面記事的に眺めてみるのも面白いのではないでしょうか?
さて、近藤勇ならぬ、笑わぬ香取真吾はどのような演技で、我々の知らない幕末の世相、風俗などを紹介してくれるのか、瓦は楽しみにしています。
西田議員と共に
自民党京都府参議院選挙区第三支部支部長
自民党京都府連前幹事長
二ノ湯 さとし

政治家が堂々たる論陣を張るという言葉は、今や死語になりつつあります。哲学や見識を振りかざし、議論を展開できる政治家が、政界で数少なくなってまいりました。西田昌司先生は、まさにその数少ない政治家のお一人です。先生は常に国家、民族を考え、大きい、広い立場から政治に取り組んでおられ敬服に値する政治家です。先生のご指導を頂きながら私も京都と日本のために全力を尽くす覚悟です。何卒よろしくお願い申し上げます。

プロジェクトXというNHKのテレビ番組は皆さんもよくご覧になると思います。今日の日本の社会を築いてきた、名も無き人々の懸命な生き様にスポットライトを当てた素晴らしい番組で私もいつも楽しみにしています。その中でも今まで歴代ナンバーワンの人気を誇っているのが、伏見工業高校のラグビー部の物語です。皆さんの中にもこの番組を見られた方も大勢いらっしゃると思いますが、改めてそのあらすじを紹介致します。
窓ガラスは割れ、学校の廊下にオートバイが走る。生徒は授業を平気で抜け出し、先生はそれを見て見ぬふり。とても教育を行う環境ではない、そんな荒れ果てた学校に赴任した元全日本代表の若きラガーマン。それが山口良治先生だったのです。赴任早々ラグビー部の監督になり、一生懸命生徒の指導を行うのですが、彼らはそれに全く反応しません。当時京都ナンバーワンで、全国にその名の知れた花園高校との練習試合ではなんと112対0で、大敗をしてしまいます。しかし、生徒はそれにも無気力で、「相手が強すぎるんだから仕方が無い。」「自分たちとはレベルが違う」とまったく反省する気も無い状態でした。その時、山口先生は、「お前ら、悔しくないのか。相手も同じ高校生やぞ。こんな負け方をして本当に悔しくないのか。」と涙を流しながら生徒ひとりひとりに必死に問いかけたのです。すると、ついに今まで悪ぶっていた生徒たちが先生の涙に感動して、「先生、俺は悔しい!」「おれも悔しい!」「勝ちたい!強くなりたい!」「俺達にラグビーを教えてください!」と次々に泣き出したのです。この姿を見て先生は、「こいつらはモノになる。」と確信されたそうです。その後、厳しい練習を乗り越え、伏見工業高校は宿敵花園高校を破り、終に念願の日本一になったことは皆さんご存知のとおりです。
山口先生のラグビーに対する情熱と生徒に対する愛情がこの奇跡の物語を作り出したのです。しかし、その奇跡を起こすために実際したことは、地道な練習の積み重ねでしかありません。必ず勝つと信じて、毎日毎日同じ練習を繰り返し行い、その結果が偉大な奇跡を起こしたのです。
しかし、これは頭で分かっていても、誰にでも実行出来るものではありません。そもそも、一介の名もなき学校が日本一になるなんて、誰が想像出来るでしょう。それを可能にしたのは、生徒達の「このままでは情けない、悔しい」という発憤によるエネルギーなのです。不可能を可能にするために特別なものは何もいらないのです。ただひたすら、当たり前のことを繰り返し行うこと以外ないのです。ただそれを実行するには、自分の心のスイッチをオンにすることが必要なのです。伏見工高の場合には、花園に大敗したことがそのきっかけとなったということです。
ところで、今一番の政治課題は、イラクへの自衛隊の派遣の是非でしょう。この問題を政府は、国際貢献という名の下に実施しようとしています。しかしその本音には、アメリカに日本は守ってもらっている、だから、アメリカに協力することが日本の国益なのだという打算的発想があるのは間違いありません。確かに日米同盟は重要です。しかし、もっと重要なのは、自分達で祖国を守るという気概ではないでしょうか。今の日本にそれがあるのでしょうか。それがあれば、きっと別の選択をしたはずです。日本に自国を守るという気概がないから、対米関係に対する配慮が全てに優先し、それが今日の日本の根本的問題になっているのです。自衛隊の派遣だけではなく、経済や雇用から家庭や福祉、教育に至るまであらゆる問題の根底にあるのが、アメリカに対する卑屈さからくる問題です。このことは、戦後社会を率直に振り返って考えれば誰にも分かる話です。しかし、誰もそれを何とかしようと思ってこなかったのです。そもそも、アメリカに大敗し、占領されてきたという歴史さえ知らない人も最近ではいるようですが、それを知っていても同じことです。結局、アメリカは世界最強の超大国、誰も逆らえないし、そんなことを考えても到底出来ないことと諦めてしまうからです。
しかし、この気概の欠如こそ、日本の最大の課題であり、根本的問題なのです。伏見工高ラグビー部は、山口先生の言葉によってみんながそれに気づき、そしてその悔しさの中から地道な努力を継続して行うことによって奇跡を成し遂げたのです。

政治の世界に今最も必要なのは、この日本の現状を悔しい情けないと認識し、そこから立ち上がっていこうとする気概であり、そのための努力を継続することではないでしょうか。半世紀以上の間、日本はこの問題に目をそむけ、目先の生活ばかりに気を取られて生きてきました。その結果、日本は世界一の長寿で豊かな国になりました。しかしその一方で、世界一気概の無い、負け犬根性の染み付いた国になってしまったのではないでしょうか。我々が今しなければならないのは、この情けない現実から立ち上がり、たとえ半世紀かかろうとも、必ず日本をもう一度正気の充満した世界に誇れる国にするのだと決意することです。そしてそのための努力を、子や孫の代になろうともしつづけるのだと覚悟することなのです。
これは、途方も無い話かもしれません。しかし、名も無き人々の努力の積み重ねが政治を変える、まさにこれこそ政治の世界に必要な「プロジェクトX」なのです。私は、この「政界プロジェクトX」を成し遂げるために全力で頑張ります。本年もご支援をよろしくお願い致します。
『京都発言者塾』(仮称)発足を目指して
京都発言者塾(仮称)発足準備事務局長(希望?) 南郷 良太

新年あけましておめでとうございます。本年も皆様にとりましてさらに良き年となりますよう心よりお祈り申し上げます。
このたび、古都京都発の国民運動の主体となる「京都発言者塾」(仮称)の発足の準備を、西田昌司議員が中心となって進められています。「発言者」塾は、救国誌「発言者」の実践の場として東京で評論家の西部邁先生が主宰されていますが、以前から西田議員が「暖簾分け」を受けたいと希望していたものです。設立準備から参画させていただきましたご縁で、大変僭越ながら一言ご挨拶申し上げます。
昨年は国会や政府において、イラク復興支援の自衛隊派遣を巡る様々な論議が行われていました。そんな中、昨年11月29日ついに我々の最も懸念していた日本人襲撃事件が発生してしまい、同じ日本人である外交官2名の尊い命が奪われるという痛ましい結果をむかえてしまいました。また同じ日に宇宙航空研究開発機構が国産大型ロケットH2Aによる情報収集衛星の打ち上げに失敗するという大失態を起こしました。
この二つの事件は国際社会が一段と不安定なものとなり米国との強固な同盟関係に起因する脅威のもとに曝されているにもかかわらず国内外の危機管理は一向に進んでいないことを露呈することとなり、我々が大きな岐路に立たされているといっても過言ではないでしょう。
日本人は50余年前、占領政策による「教化」によって我が国固有の日本精神を始め神話時代から脈々と受け継がれて来た歴史・政治経済体制や伝統文化を自ら放棄しました。魂を売渡したことで得たものが戦後の経済的繁栄そのものであります。結果として「全てのものを金勘定でしか見られない」地球上最も卑しく空虚な精神構造を持つ民族に成り下がろうとしています。このままでは日本民族は滅亡の時を待つのみと考えるのは私だけではないと思います。民族復興への第一歩は「戦後体制の克服」にほかなりません。
欧米列強が、「五族協和の王道楽土」を基本理念にアジアの真の独立を掲げた一等国日本を脅威として政治的経済的に追い詰めたことや、そのため日本が自存自衛のための大東亜戦争に突入したことは現代の日本人のほとんどが知らない史実となってしまいました。逆に先制攻撃を唯一の根拠として侵略国であるとの烙印を押され、現在教育現場では「自虐史観」に基づく日本民族弱体化計画が着実に進行しています。ちなみに昨今のアフガニスタン戦争・イラク戦争と9・11 自爆テロの一連の米国の言う理屈にアジア人の一人として違和感をもつのは私だけでしょうか?
戦後体制を克服するにはまず、国民個々の「心の戦後体制」を克服しなければなりません。これは既成政党や既成の組織に決して実現のできない課題で、「草の根の国民運動」による断行によってのみ達成できると考えます。
京都府を中心に近畿一円から参加者を募り、それぞれの地域での国民運動を主導していただくことのできる人材育成のために積極的に活動を展開する予定でございます。皆様の更なるご指導ご支援を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
謹んで新春のお祝いを申し上げます
参議院 自由民主党国会対策委員長
参議院議員 西 田 吉 宏

皆様には、おそろいで新春をお迎えのことと心よりお慶び申し上げます。
日頃皆様方には、温かいご芳情とご支援を賜り、私も昨年6月に突然の病魔に襲われましたが、お陰様で後遺症もなく完全回復し、元気に国会活動を続けております。
さて、最近の世情は、国の内外を問わず直面する多くの課題が山積しております。参議院自由民主党国会対策委員長として、日夜諸課題の解決に向けて取り組んでおりますが、なお、皆様の「声、思い」を国政へ届ける架け橋となり、信頼される政治と生活の安定の実現に向けて努力して参る決意であります。今後におきましても西田昌司府議会議員共々ご支援ご指導を賜りますようお願い申し上げます。
結びに、皆様方の一層のご健勝とご多幸を祈念申し上げまして、新年のご挨拶と致します。
「US版・武士道」の逆輸入

京都市が肝いりで製作に荷担した,映画「ラスト・サムライ」が人気を集めています。二条城の紹介,京都の紹介,日本の紹介,果ては「武士道」の紹介になっています。この「武士道」は,軍国主義につながる危険な思想と勘違いしている方々も居られますが,信義,名誉,廉恥を重んじ,絶対に他人を裏切らない心を持った日本人の本来の精神だと思います。
今,海外では「武士道」をあつかった出版物があらゆる言語で各国からでており,この映画が拍車をかけているようです。かって,黒船でペリーが来たときも「武士道」を探していたようです。5千円札の新渡戸稲造の「武士道」は明治時代に最初に米国で出版された本です。近年ではベネディクトの「菊と刀」がベストセラーになっています。
どうも日本人は自国の精神である「武士道」を海外からの逆輸入によって,やっと気が付いているようです。さて,今年は「甲申(こうしん・きのえさる)」の年で,猿にちなんだ鎌倉時代からの諺「みざる・いわざる・きかざる」が在りますが,反対に「しっかり見・言い・聞き」して日本の「武士道」を逆輸入ではなく,足元から見直してみたいと瓦は思っておりますが,皆様も如何なものでしょうか。(もう一度,映画を見てこよう~)
新人挨拶

新年あけましておめでとうございます。
この度、西田事務所でお世話になることになりました柿本大輔と申します。
数年前より、西田先生の主宰する「昌友塾」に参加させていただいて以来、西田先生の保守の立場からの国家観、歴史観に今の日本人が失ってしまった侍の心意気を感じ、是非ともお傍で勉強させていただきたいと思っておりましたところ、この様な機会をいただきました。
社会経験のない若輩者なので、皆様には大変ご迷惑をおかけする事と思いますが、なにとぞご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。
柿本大輔
退任挨拶

新年明けましておめでとうございます。
さて、私こと、この度新たな進路へ向かうため、西田事務所を巣立つこととなりました。
皆様にお世話になり一年半が過ぎました。この間統一地方選挙を始め、各種後援会のイベントや会合、そしてこの「show you」の発行等々、皆様には多大なるご協力とご指導を頂きました。お陰様で今日まで何とかやってくることが出来ました。
大学を卒業して初めての社会経験であったこともあり、沢山の失敗を致しました。その都度皆様にはご心配とご迷惑をおかけしたにもかかわらず、叱咤激励して頂きました。この一年半で大変貴重な経験をさせて頂いたと心から感謝致しております。
今後は私よりも若い柿本君がお世話になることになりますが、私と同様によろしくお願い申し上げます。お世話になりました皆様、本当にありがとうございました。
岡野 貴繁
総裁候補に本質的な相違点はあったの
テレビの討論番組で、自民党総裁候補の四氏がそれぞれの政権を述べていました。小泉総理は相変わらず、自らの構造改革こそが景気回復のためにも必要だという持論を展開していました。他の候補者は、現実の景気の悪さを指摘し、急激な構造改革が社会を混乱に陥れていることを批判していました。特に景気の後退期に緊縮財政を行なう愚を指摘し、小泉内閣の経済政策を変更しない限り、景気の回復はないということ強調しました。しかし、その一方で、では財政再建はしなくて良いのかと小泉総理に切り返されると、改革自体は必要なことであると言い、小泉改革はその順序が間違っているのだと言うのです。また外交姿勢において、小泉内閣がアメリカ追従に過ぎるのではないかと言う批判が、各候補から指摘されました。しかし、小泉総理から、ではアメリカとの協調以外にどんな選択肢があるのかと開き直られると、どの候補もそれに明確に反論することはできなかったように思います。各氏とも日米同盟が外交の基本であるし、日本の国益であると言うのです。
こうした各候補のやり取りを見ていて、私には各氏と小泉総理との明確な相違点は殆ど見えてきませんでした。むしろ、その類似点のほうが際立っていたように思えたくらいです。つまり、構造改革について三氏とも小泉総理を批判しているように見えますが、それは現状をあまりに無視した小泉総理の頑なさに対してであって、「国から地方へ、官から民へ」と言う小泉改革の方向性については、三氏とも基本的には異論はなかったと思います。結局、どの候補も本質の部分では殆ど相違がないと言うことなのです。もっとも、同じ政党の中での総裁選挙ですから本質的に大差が無いのは当然ではあります。しかし、小泉総理が訴え、また、行ってきたことは、まさに自民党を壊すと言うことであったはずです。その政策と他の三名が本質的に似ていると言うことは、一体どういうことなのでしょうか。
総理に必要な理念と資質とは

自民党総裁選挙とはとりもなおさず、総理大臣を選ぶことです。そのことを踏まえて司会者が各氏に、総理大臣に一番必要な理念と資質を質問をしました。それに対して、各氏は概ね次のような返答をしました。小泉総理は、「それは使命感と実行力です」と答えました。亀井氏は「人間愛です」と言いました。恐らく、人間は強者ばかりではない、小泉総理の構造改革では弱者は切り捨てだと言うことが言いたかったのでしょう。藤井氏は、「リーダーシップと決断力です」と答え、高村氏は、「使命感プラス洞察力です」と言い、さらに「いたずらに使命感ばかりが先走ると方向を見誤り、国民にとっては不幸なことです」と続けました。小泉総理に対する痛烈な皮肉を浴びせたのです。私は、この様子を見ていて唖然としました。それは、一国の総理に必要なものは聞かれて、誰一人として、「それは歴史観であり、国家観であります」ということを述べなかったからです。確かに、各氏の意見はそれぞれ政治家にとって必要なものであるには違いありません。使命感もリーダーシップも決断力も洞察力も勿論大切な資質です。しかし、それ以上に、いやそれ以前に首相として必要なものが国家観であり歴史観です。そして、小泉総理の唱える構造改革の本質的な問題こそまさに、そこに国家観や歴史観の欠如しているということなのです。経済政策の過ちも、単にマクロ経済が分っていないと言うことではありません。構造改革そのものが歴史観と国家観の欠如による病的破壊行動なのです。小泉総理にとっては破壊こそが改革なのです。だから、デフレにより企業倒産が増えようとも、それは現状を破壊している証拠であり、改革が進んでいるしるしでしかないのです。他の候補の言うように政策の順序を変えて、まず財政支出を行い、景気を回復させ、その後に財政再建をしたのでは、現状の経済の仕組みが破壊されず、それでは改革と言えないということなのです。また、小泉総理が日米追随外交に疑問を抱かないのも、日本人としての国家観や歴史観が欠如しているからなのです。靖国神社への公式参拝を訴えながら、平気でそれに代わる追悼施設の建設を検討するという姿勢が、そのことを如実に証明しています。
従って今回の自民党の総裁選挙で争点とすべきは、小泉総理には国家観と歴史観が欠如しており、それは総理としての資質を著しく欠いているということではなかったでしょうか。そして、他の候補が訴えるべきは自らの国家観と歴史観であったはずなのです。ところが、今回の議論を通じて、小泉総理のみならず、他の総裁候補も誰一人そのことを訴えていなかったのではないでしょうか。(亀井候補は多少こうしたことに触れようとしていたようですが、残念ながら明確には伝わらなかったように思います。)このことは、党員の一人としてまことに慙愧に堪えません。
巧言令色鮮(すくな)し仁

自民党の総裁選挙は予想通り小泉総理の圧勝で終わりました。恐らく、国民も小泉総理と同じく、現状を破壊することこそ改革だと信じているからなのでしょう。これでは日本の将来は心許ない限りです。先に総裁選で小泉総理と争われた三氏の主張が、結局は小泉総理と本質的には違いがないということを申しました。それどころか実は、野党の民主党とも大差がないのです。確かに民主党も小泉総理の構造改革を批判しています。彼らは、小泉内閣では抵抗勢力が邪魔をして改革が進まないが、民主党にはそういうしがらみがないから自民党より早く、且つ、徹底的に改革ができると主張しています。しかし、これもつまるところ、改革の方向性では小泉総理と変わらないということです。つまり、小泉総理も総裁選挙に立候補した他の三氏も民主党も、改革の方向性では殆ど明確な違いはなく、その手法が一番性急なのが民主党、一番慎重なのが他の三氏ということになり、結局小泉総理が一番中庸ということになってしまいます。つまり、三氏は勿論のこと民主党も構造改革を批判しているようで、実は、本質的には肯定しているということです。今の日本の問題点は、与野党ともに歴史観や国家観という根本的視点が欠如しているということなのです。そのため、目先の改革論議にしか視点が向かず、結果として現実の社会を破壊することしかできなくなっているということなのです。これでは日本は救われません。
この秋には衆議院選挙が、そして、来年には参議院選挙が予定されています。与野党ともにマニフェストという政権公約を有権者に示して支援を訴えています。マニュフェストは今までの政権公約より具体的に内容を記載し、その公約の達成年限まで明記することにより、有権者に政策の違いが理解しやすくなるはずだと各政党とも意気込んでいます。しかし、そんなものをいくら作ろうともなんの効果もないでしょう。まさに、「巧言令色すくなし仁」です。多くの言葉を並べ立てるより、たったひとつの真実の言葉が必要なのです。政治家にとって真実の言葉とは何か。それを知る政治家の登場が待たれます。そのためにはそれを知る国民が必要なのです。
(上記の論文は、西田昌司連載中の雑誌「発言者」平成15年11月号より抜粋、加筆致しました)
座談会
「"Showyou" を支える活動」
1 失われたのは10年か50年か
最近「失われた10年」という言葉をよく耳にします。しかし,「何を失ったのか」はよく検証する必要があります。デフレや個人消費の落ち込み,株価の下落等々。確かにバブル期は異常でした。だけど,不況があまりにも長く続き,これが当たり前になっている。もっと胸を張って歩けるような,そんな元気のある政治を期待します。
ノーベル賞の受賞や「千と千尋」に代表される映画などはがんばっていますよね。だけど,根本的なところで文化や伝統といったものはどうでしょう。京都と言えば,すぐに寺や神社を想像します。だけど寺の伽藍は里山の風情が背景にあって,初めて生きると思うのです。私たちの足元の文化,生活に根ざした伝統をもっと大切にしたいですよね。「伝えよう美しい精神(こころ)と自然(こくど)」は,全国すべてに通ずる普遍的な価値です。
2 新たなリーダー像として
「マニュフェスト」が喧伝されていますが,昌司議員にはもっと根底のところ,人や国,歴史といったこの日本の存在に関わるものを見据え,発言する政治家を目指しいてほしいと思います。「日本のあるべき姿」を基軸にした政策を大胆に,かつ,英知を持って取り組む。言葉だけではない,そんな「真の政治家」を期待します。
前回の選挙では,国の在り方や歴史観が,福祉や教育の政策には必要であると訴え,最高得票で当選されました。私たちはそんな先生の熱情と心意気を大切にし,これを具体化するお手伝いが出来ればと考えています。そのためには,「あるべき姿」と同時に「行動目標」として訴えることも必要と思います。Show Youはこの目標を分かりやすく伝えるために,紙面の改革やパンフレットの刊行などを模索していきたいと思います。
3 地縁を大切にした組織の発展
京都は古都であると同時に,宗教・教育・文化・産業・芸術などの側面を持った現在の主要都市としての役割を果たしています。東京遷都の後も,疎水の開削・発電・市電や小学校の建設と日本の近代化を町の人々の力で成し遂げた歴史を持っています。この活力は今も生活の中に流れていると思います。
郷土とは個人の生まれ育った地域だけでなく,先人たちが粉骨砕身した歴史を積み上げた土地でもあります。今の自分だけが居るのではない。両親祖父母が築いてきたその土地と歴史の上に今の自分が存在している。私たちはこの「バトン」を次代へと受け渡す責任がある。「郷土の叫びを国政へ」と支えた先輩たちの思いを受け継ぐ責任があると思っています。
地縁を大切にするとは,先達の思いと苦労がこもったバトンを大切にすることだと思います。
4 若者たちで京都会館をいっぱいに
政治に関心を寄せる学生達のインターンシップを受け入れ,昌司議員の身近な姿を通して,議員の人柄や政治信条に触れてもらう。こんな試みも2・3年前から行っています。先生も学生たちの集まりには必ず顔を出し,政治姿勢だけでなく生き方も語る機会も増えました。これらの話を整理し,理念と具体化の過程,批評等も盛り込んだ小さなパンフレットを発行できないかと考えています。機関紙(Show you),本の発刊(政論?・?),昌友塾,講演会と数多くの発言の機会を持ってきましたが,若い人達との膝つき合わせた討論を積極的に行いたいと思います。
このため,大学のサークル活動や研究会活動にも積極的に出向き,彼らとの心のキャッチボールを行いながら,青年達との交流を図っていきたいと思います。かつて西田事務所にインターンとして来た学生を中心に,呼びかけを行っていきます。

樋のひとしずく
羅城門の樋せ
--アンデスに生きていた団魂世代の片思い--
1年前「アンデスの国の海軍」を書きました。歴史に息づく誇りと愛着を,人々は「白い軍服」に重ねているように思いました。その際に,「ボリビアという国は何処にあるの?」と聞かれました。南米とは分かっていても,遠い国ですよね。そこで今回は,名所案内から。世界一高所にあるチチカカ湖は有名ですね。剃刀の刃も通さない石建築のプレインカ文明や塩の湖(ウユニ)も有名です。しかしなんと言っても,我々羅生門(団塊)世代には“チェ・ゲバラの終焉の地”と言う方がインパクトを持っています。(尤も,子供は彼の名前も知りません。彼の話をしたら「本棚に入っている人」と言われました。私達には現実でも,今の世代には歴史の人物ですね。少し寂しい気もします。)
この7月の末,ラパスのあるスペイン料理店に行きました。ふと壁を見ると,そこに三人の肖像画が飾られていました。シモン・ボリーバル,スクレ総督,そしてチェ・ゲバラです。先の二人は,ボリビア独立の志士です。ボリーバルは国名にも残るラテンアメリカ独立の父であり,スクレは貧弱な植民地軍を率いてスペインの大軍を撃破した英雄です。しかし,葉巻を咥えたゲバラの画は,少し違和感を与えます。

彼はアルゼンチン生まれの医者で,カストロ達と一緒にキューバ革命を戦ったことで知られています。そしてキューバ革命が成った時,カストロと袂を分かち地位と安寧を捨て,再び南米各地の軍事政権に戦いを挑みます。1960年代後半に多感な時期を送った人間にとって,ゲバラは共産主義の革命家としてよりは,むしろ軍事政権によって抑圧されていた農民や民衆を解放するというイメージがぴったりします。最後は農民による密告で,20数名の同志と共に銃撃戦の硝煙の中に消えていきました。
「え,このボリビアで!」と思った私は,同行していたボ国の友人達に聞きました。「我々の世代には英雄だが,この地ではどのような存在なんだろう?」。曰く「彼を殺したのは我々だが,この国を変えようと思う人間には,今でも英雄だ。私の心の中にも生きている。」他曰く「私にとっては,彼は共産主義者ではない。変革の人だ。」「いや,私は彼が英雄だとは思わない。この国にとって重要な人物だが。」云々。閉店まで論議は続きました。後日訪れた大学の壁には手書きの彼の肖像がありました。そして,ある先生のバイクにはステッカーが目立たないように貼ってありました。
彼が南米の地で,世界革命を夢見たのか,軍事独裁政権の抑圧や荘園制と変わらない名ばかりのプランテーションから小作農を救済したかったのか,今となっては知る由もありません。しかし,若き医者が貧しい人々を病苦から救済しようと苦悩する中で,民衆を救済するにはその背後にある大きな不条理(貧困と抑圧)からの解放こそ,自分の生きる道と信じたことは想像に難くありません。
私達の世代にとって,主義思想は違っても,この強烈なメッセージは新鮮でした。彼が斃れてから約半世紀が過ぎ,共産主義は歴史の世界へと退場しました。国際資本主義が世界金融資本に取って代わられ,米国一極集中型のグローバル社会が出現しています。彼の存在は過去のものとなりましたが,その生き方は何故か団塊世代の心を敲きます。「人生ぼちぼち日暮れ時」を迎える世代にとって,「人生どう生きるか」を考え直す一つのきっかけではありました。(「どう生きたか」には,まだ少し時間を下さい。)
私が日本に帰る前日,一つの包みが届きました。そこにはゲバラのTシャツとキューバの硬貨が入っていました。そのコインには,次のような言葉がゲバラの肖像と共に彫られています。「PATRIA o MUERTE(愛国か死か)」う~ん。彼はこのカストロの言葉を何と聞くだろう。心中複雑な思いで機上の人になりました。
去る7月19日、京都テルサホールにおいて「西田昌司大演説会」と題し、講演会が開催されました。
当日、ゲストとして国際日本文化研究センター教授・川勝平太氏による基調講演も行われ、年齢性別を問わず600人近くの方々が会場を埋め尽くしました。その一部、西田議員の講演録から抜粋したものをご報告いたします。
西郷の教え

私の尊敬する西郷隆盛は、「政の大体は文を興し、武を賑わい、農を励ますの三つにあり。他の百般の事務は皆この三つの物を助くるの具なり」という政治に対する思いを綴った言葉を遺しています。
最初の「文を興し」というのは日本人の精神や文化をしっかり振興することです。二つ目の「武を賑わい」というのは、安全保障のことですが、国を自分たちで守れる仕組みをしっかり持っていなければならないということです。三つ目の「農を励ます」というのは、農業や食糧だけでなく、今日ではエネルギーも経済も全部この中に入ります。自分たちの食い扶持(ぶち)は自分たちできちんと守っておかないと大変なことになるということなのです。
要するに西郷の言いたいことは、政治というものは精神文化を発展させ、外国からの侵略を防ぎ、国民の食糧やエネルギーを確保する、この三つが大事であり、他のことはこれらに付随するものなのだということなのです。
ではこれを今の日本で考えるとどうでしょうか。まず精神・文化面ですが、しっかり守れているのでしょうか。文化というのは心の継承のことです。心を育てる場であるべき家庭が崩壊している現状を考えれば、とても問題なしとは言えません。このことは政治が最も大切な役割を果たしていないと言う証拠でもあります。
次に安全保障の問題です。確かに自衛隊はありますが、これがあるからといって国が守れるという状態ではありません。一番大切なのは国を守るという国民の意識なのです。しかし、そういった意識が少ないのが現状です。そもそも今の自衛隊は国を守るためにあるのではなく、アメリカの軍隊を補佐するためにあるのです。自衛隊だけでは他国からの攻撃から日本を守ることはできません。残念ながら、現在の自衛隊はそういう存在でしかないということです。
三番目の「農を励ます」は農業政策だけでなく経済全体の話として考えるべきです。皆さんご承知の通り農業の現状はどうしようもありません。農作物の六割は外国から輸入している状態です。おまけに一所懸命働こうにも、田んぼの三分の一は減反で米を作らせてもらえません。最初から農業は捨てられているのです。しかし、農業は捨てられても経済は立て直した。自動車をたくさん輸出して、お金を儲けたではないかという声もあるかもしれません。確かに、お金はたくさん儲けることができたのですが、儲けたお金を自分たちのために使えているのでしょうか。また、そもそも何のためにそのお金を使うべきなのでしょうか。農業を犠牲にして、自動車等を輸出して儲けました。その儲けたお金が、約1,400兆円という個人金融資産になっているのです。しかし、そのお金が使えないのです。何故なら日本の景気を良くしようと思えば、国がその皆さんのお金を使えばいいのですが、それが出来ないのです。そんなことをすれば、アメリカに投資している資金を回収することになり、アメリカの景気の足を引っ張ることになるから駄目なのだ、ということなのです。日本の政治家が日本の国益よりアメリカの国益を優先していては、国民はたまったものではありません。

このように考えてみると、今の日本は自立しているどころか、国としての形になっていないのです。ここが一番の問題なのです。日本の経済力は優秀ですが、問題はそれを使う能力も見識も失ってしまったということなのです。国であれば絶対やらなければならない文、武、農という三つのことが、現在の日本ではどれも出来ていないということなのです。日本はお金が無くて不景気なのではなくて、文化、経済どの分野においても国を守るという意識を失ってしまったため、国の活力が落ち込んでしまったのです。そのことを考えると、今日本に必要なものはお金ではなく「国を守る心」なのだということが言えると思います。
明治維新の時には、軍隊を創設するにもお金がなかったのです。戦後の復興も外国からお金を借りてやりました。しかし今や外国にお金を貸す身分になっているのです。お金はたくさんあるのです。ところが、それを何のために使うのかを見出せず無気力になっているのです。国家としての目標を失くした結果、国全体が無気力症を患っているのです。
人生の目的と国家の目的
人生の目的は何かということは、人により様々な答えがあるかもしれません。しかし、自分が今ここに生きているということは、自分の意思ではなく親がいたからであるということは、誰も否定出来ないでしょう。自分たちの存在を考えるとき誰しも、生命のつながりを感じずにはいられません。国家もこれと同じことがいえます。我々が日本人として曲がりなりにも生活出来るのは、日本という国があればこそです。そしてこの日本という国は、先人の幾多の苦難と努力の積み重ねの上に成り立っているのです。つまり、我々の存在は個々人の生命のつながりと国家の歴史の上にあるということです。そう考えれば、まず、この生命と歴史のつながりを次の世代に伝えていくことが、この世に生を受けた者の最低限の使命ではないでしょうか。少なくとも先人たちはそう思い、今日の日本を築いて来たのではなかったでしょうか。
議員の仕事とは?
議員の仕事とは一体何でしょうか。鈴木宗男さんみたいに、たくさん地元に予算を持って来るのが仕事なのでしょうか。しかしそれだけが仕事ならばそれは非常に卑しいことではないでしょうか。何故ならそれは利己主義そのものだからです。もちろん、そうしたことも議員の仕事の一部かもしれません。しかしもう少し美しい清々しい仕事をしたい。先人たちが自分の命にかえてこの国を守ってきたように、私も自分たちの目先の利益のためでなく、自分が犠牲になっても、次の世代に何か役立つことがしたいと考えるのは、当たり前のことではないでしょうか。
もちろん、私も最初からこのようなことを考えて議員になったわけではありません。父親の参議院選出に伴い、皆様にご支援頂いたお陰で、気が付けば議員になっていたというのが本音です。しかしこの13年間、私なりに一所懸命議員活動を続けてきました。様々な経験を積む中で、私が感じたことは、「人間にとって大切なものは素直で優しい心である、それを実践するためには知恵と勇気が必要である」ということです。そして歴史を学べば学ぶほど、如何に先人達が素直で優しく知恵と勇気に満ちていたかということを感じずにはいられませんでした。
私自身は、とてもそんな偉大な先人の足下に及ぶはずもありませんが、少なくとも、そうした先人達の子孫であることは間違いありません。そう思った時に、私は自分自身に知恵と勇気が充満するのを感じたのです。
確かに今の日本では、政治は卑しく経済は醜く、美しさの感じられません。しかし、少なくとも我々の先人の中には素晴らしい人がたくさんいたのです。日本も捨てたものじゃない。そうしたことを子孫達に伝えることにより、もう一度、日本に勇気を充満させ、活力を取り戻すことが出来るのではないでしょうか。

このことは一朝一夕で出来るのもではありません。日本は戦後半世紀以上に亘り、政治の使命を忘れてきたのです。したがってこれを正常な状態に戻すためには半世紀以上かかるかもしれません。私が生きている時代にはそのことは実現しないかもしれませんが、我々のそうした思いが次の世代に少しでも伝えることが出来たら、もう後退することはありません。半世紀かかるかもしれませんが、必ず日本は素晴らしい国として甦ることが出来るのです。そうしたことの一助に、私がなることが出来れば、それこそこの世に生まれた甲斐があるというものです。そのことこそが私の使命だと信じております。
大演説会に参加して~
当日参加された方々からの感想をご紹介致します~

国民運動本部の再建を祝して南 郷 良 太
西田昌司先生の大演説会のご盛会心よりお祝い申し上げます。そしてこの演説会を企画され運営に当たられた皆様に深く敬意を表したいと存じます。
私が西田先生に始めてお目にかかったのは平成12年の総選挙後の自民党京都府連青年局の選挙総括のときでした。当時はまだ政治が好きというだけでしたが、戦後教育に毒されていた私を目覚めさせてくださったあの瞬間を生涯忘れることはないでしょう。その内容を今更申し上げる必要はないと思いますが、先生が心の底から込み上げる思いを抑えながら熱く語ってくださった「あの体験」は、人生のうち何回か巡って来るといわれる好転機の一つであったと確信しています。その後歴史認識をはじめとする教育のあり方についての問題、他国から見れば単なる占領基本法でしかない日本国憲法をわが国の憲法典へと改正する問題、家庭に倫理道徳規範を取り戻す問題など、西田先生との出会いにより可及的速やかに取り掛るべき問題に多数直面することとなりました。
この昭和・平成の御世に運命として神国日本に生を受けたこと、そして先生と出会って祖国再建への大事業の推進に関ることとなったことは天命といっても過言ではないと思います。ひとりの人間南郷良太がこの時代に生きた証として何かこの国に、そしてわれわれの社会に役立つことを成し遂げたいという思いを、この大演説会にて再認識することができました。
わが自由民主党が平成5年8月に下野する前、党に国民運動本部という内部組織があったという話を以前聞きました。辛うじて与党として国政を預かるわが党は今、新しい国民運動本部の設置が何より望まれますが、現在の小泉政権の様子から勘案すると絶望的であります。今回の大演説会を京都発「新国民運動本部」設立大会と受け止め、国難の時代といわれる現在の荒廃した社会を一刻も早く打破するために努力していきたいと決意を新たにしたいと思います。この度はおめでとうございました。 (自由民主党京都府連青年部常任幹事)

西田昌司大演説会に寄せて上 野 文 男
私が西田昌司という議員に出会ったのは今から3年程前である。ある勉強会で西田議員を知った。勤務先こそ南区吉祥院ではあるが、生まれも育ちも西京区嵐山で、今も妻と二人で住んでいる。多くの人は普段の生活の中で、他の行政区選出の議員と知り合うことも無ければ興味を持つこともまず無いであろう。
しかし、会を重ね西田議員の話や意見を聞いていくうちに私は次第に議員の考えに惹かれていった。私は今まで多くの議員に出会い話をしてきたが、ここまで情熱に溢れた議員に出会ったことは無かった。無論この京都には優秀な地方議員は沢山いるが、しかしその多くは「議員の枠を、つまり政治(地方自治)の領域を出ない」ものであった。当然といえば当然である。だが西田議員にはその枠がまったく無かった。
地方議員の枠、政治の領域を超えて自論を展開し活動する西田議員。当然のことながら世間から厳しい意見や苦言が議員に向けられていることは議員自身も承知のはずであろう。西田議員は大演説会で「これは国を良くする運動である」と言った。これについてある人は私に府会議員のくせにと嘲笑した。
しかし私はこの演説会に集まった人々の思いがいずれ大きな流れになれば本当に国が変わるような気がした。大きな川も海も元は小さな沢の流れである。
そしてこれから先、西田昌司という議員が歴史に残るような政治家に成るか否かは私には判らないが、当日テルサホールに集まった人たちの心の中にいつまでも記憶に残る政治家であるのは間違いないであろう。

大演説会を振り返って
一粒会 幹事 田 端 俊 三
「今、国難のこの時に千人の聴衆を集めて演説をしたい」という西田議員の熱き思いを受け、昌司議員後援会の一つである一粒会としても、さまざまな人たちに声をかけました。ある人は取引先の方、またある人は家族や親戚・友人と、それこそ職業・年齢・性別を超えて、さまざまな方に声をかけさせていただきました。たとえば西田議員を知っている人には声をかけやすいのですが、西田議員をまったく知らない人にはどうでしょう。
一粒会としては西田議員を知らない人に聞きに来てもらい、その人たちがまた他の人たちに西田議員の考えを広めてもらおうという気持ちがありました。「京都府の府議会議員で南区選出で・・・・こんな説明どうでもええんや。とりあえず聞きに来たら今の日本の何が間違っているか一発でわかるで。テレビなどでのチャラケタことを言う政治家とちがうで。目先の人気取りのしょうもない話とも違うし。」このような調子で声をかけさせていただきました。
今振り返ってみると、前段の「何が間違っているか」について、とてもわかりやすい演説だったと思います。演説を聞かれた方は、本当に必要なものは(showyou35号の中にも西田議員が書いていますが)「現実を正しく見つめる知恵」と「その現実に向かって立ち上がろうとする勇気」だとお気付きになったと思います。このことを皆さんの周りの人たちに真剣に話していただければ、我々一粒会は責務を果たしたと実感致します。
最後になりますが、当日会場でお手伝い頂き、また多方面に亘りお誘い、ご紹介頂いた後援会同志の方々に、ここで御礼申し上げます。ありがとうございました。
私にとって五度目の選挙を皆様方のお蔭で、勝利を収めることが出来ました。心より御礼を申し上げます。
経 世 済 民

アメリカは、80年代に完全に製造業で日本に負けたため日本に対する貿易赤字が増大し、日本に対する支払超過は莫大なものとなりました。かつては世界一の債権国であったアメリカは、世界一の債務国になり、常に外国から資金を調達しなければ国が回らなくなってしまったのです。アメリカの金利が、常に日本より高めに設定がされているのもそのためです。また、金融ビッグバンも金利の高いアメリカにお金が流れやすくするためにされたものです。一見すると、金利の高いアメリカに融資したほうが日本にとっても有利なようですが、国内の産業にとっては今まで融資してもらっていた資金が海外に流出するのですから、金融環境は大変厳しいものになります。確かに、銀行も単なる私企業と考えれば所詮は金貸しです。高い金利をもらって何処へ貸しつけても良いでしょう。しかし、銀行には、融資を通じて国民の預金を国内に再投資し産業を育てるという公的使命があったはずです。経済と言う言葉は経世済民(世を治め人々を救うこと)がその本来の意味であったように、経済政策とは私企業の金儲けを支援するものではなく、その事業を通じて国民を幸せにするためにあるはずなのです。今日のデフレ不況は、正に経世済民を忘れた経済政策が引き起こしたものなのです。
デフレの原因と対策
例えばもし、国民が自己の預貯金を1割でも引き出して消費に当てたらどうでしょう。間違い無く消費は上向き、景気は回復に向かうでしょう。でも誰もそうしません。先行きが不安な状態では消費をしようとする気になれないからです。では、その代わりに銀行が企業家に融資をしてくれればどうでしょう。これも間違い無く消費が上向き景気が回復するでしょう。でも残念ながら銀行は積極的に融資をしてくれません。景気の先行き状況を考えると、積極的に融資をして不良債権を増やすより、貸さないほうが得だからです。預金利息が事実上ゼロですから、融資をしなくても銀行は損をしないのです。こうしたことの結果、消費は伸びず、将来に備えて預金が銀行に集まることになります。資金があるにもかかわらず融資をしないものだから、ますます不況になり、消費が滞る。デフレになるのも当然です。
その一方で、預金利息ゼロと手数料(時間外手数料、振込手数料など)の増額などにより、銀行は大儲けをしています。事実、大手銀行の中には業務純益が一兆円を超えるところもあります。ところが、国内では貸し渋りのため景気が悪化し、不良債権は増え続けるばかりです。またそのために株価も下がり、不良債権処理と株の評価損でその利益は消し飛び、逆に何千億円もの赤字決算になっているのです。結局、日本では誰も得をしていないということなのです。
他方アメリカでは、日本から投資された資金がアメリカ経済の下支えをしているのです。つまり、アメリカだけが一人得をしているということなのです。しかし、そのアメリカも貿易赤字が減る訳ではなく、日本からの借金によって食いつないでいるに過ぎないわけですから、このままの状態が続けばアメリカは破産してしまいます。この事からも分かる様に借金で困っているのはアメリカのほうで、日本ではないのです。日本の問題は、国民の財産である預貯金を国内に再投資することを放棄してしまったことなのです。その結果、本来債権国であるはずの日本がデフレに苦しみ、債務国であるアメリカがわが世の春を楽しむという悪夢のような失われた十年が造り出されたのです。
こうした負の連鎖を断ち切るためには、国民の預貯金を国民に代わって国が借り上げ、将来の国民生活のための投資をする(つまり国債を発行して公共事業をする)こと以外ないのです。ところがこの当たり前の政策を誰も認めようとしないのです。逆に、公共投資は国債を増やすからダメだと否定をするのです。しかし、そもそも、国民の預金を原資とする国債はいわゆる借金ではありません。国民が自分の預金を取り崩して使っているのと本質的には同じであり、国民の預金を国内に再投資するための大切な方法です。先ほど述べたように日本は債権国なのです。自分のお金を自分で使うのになんら心配は要らないのです。むしろ心配をすべきはアメリカの方なのです。
何故国民経済を守らないのか
もし日本がしっかりとした公共計画を立案し、その実行のため国債を発行して公共事業を行えば、間違い無く景気は上向き、税収も増え、景気は回復に向かうでしょう。国債を発行すると、間違い無くその分だけの資金が国内に還流されますから、日本の景気はよくなるのです。しかし、日本に資金を戻す訳ですから、アメリカに流れ出していた資金もその一部は当然日本に還流することになります。恐らく、それを防ぐためにアメリカは金利を上げざるを得なくなるでしょう。今まで日本の資金で経済が下支えされてきたアメリカは、金融が逼迫し大変な事態になるわけです。まさに外国からの借金で景気を支えてきたつけを払うことになるのです。こうした事態はアメリカにとって悪夢のような話ですから、それをさせないように必死になって日本に圧力をかけてくるでしょう。その圧力は目に見えるものばかりではありません。むしろ、情報操作という目に見えない形で、日本人に気付かれないように巧妙に、そして確実にしかけられてくるのです。現実に今行われている小泉内閣の構造改革路線などは、完全にアメリカの情報戦略に乗せられた売国的行為であることは言うまでもありません。
デフレ克服のためには、こうした事態を国民に正確に知らせることが大切です。しかし、一番の問題はその事実を知った後の国民の態度なのです。「たとえ君の言うことが事実だとしても、アメリカに守ってもらっている以上仕方がないではないか。」必ずこうした意見が出てくるでしょう。北朝鮮の脅威の前に、アメリカの理不尽なイラク攻撃にも協力するほかないと言った小泉総理の発言もこれと同じことです。一見すると現実的に見えますが、これは、自らの責任を全く放棄した極めて卑しい言葉であると私は思います。
皆さんはどう思われるでしょうか。それで仕方がないと言うのなら、もう日本には政治など存在しません。選挙をして議員を選ぶのも税金を払うのももう止めにしたほうがいいでしょう。何故なら、それは、国民の名誉はもちろんのこと生命も財産も守るつもりはないと言うことを宣言しているに等しいからです。もう日本は国としては存在しないということです。アメリカの植民地としての地位しかない国に政治家は必要ありません。宗主国のアメリカから任命を受けたお代官様しか必要ないのです。
日本に必要なもの
今の日本に必要なのはお金ではありません。本当に必要なものは、こうした現実を正しく見つめる知恵と、それに向かって立ち上がろうとする勇気なのです。そして、このことに国も地方も関係ありません。国も地方も、外交も経済も、教育も財政もすべての問題の根本的原因は「自分の国は自分で守る」という一番の問題をなおざりにしてきたことから始まっているのです。「国を守る。そのためには命を捨てる」このことを国民も政治家も放棄していては、すべてが嘘になります。
今年は黒船が来航して150年目の年に当たります。我々の先人たちは、国難を前にしてどうしたのでしょう。決して逃げ出しはしなかった。国を守るために真正面からぶつかって行きました。そして、そのために様々な改革をしました。それが明治維新であり、そのお蔭で今の日本があるのです。そして忘れてならないのは、そうした改革に立ちあがったのは何も中央の政治家ばかりではなかったということです。むしろ地方にいた侍たちが、時の中央政治家である幕府の対応に業を煮やして立ちあがったから、維新は成し遂げられたのです。
日本はまさに国難の時代です。今こそ、歴史に学び国を守るため、国民も政治家も立ちあがらねばなりません。もちろん私一人ではどうすることも出来ないでしょう。地方議員である私がこうしたことを訴えることは、本来の仕事を逸脱しているのかもしれません。しかし、私はそんなことはもうどうでも良いのです。政治家としての成功や出世より自分の使命を果たしたいのです。私の使命は、「国を守ること」であり、それが出来て初めて、京都府や京都市の自治も家族もあるのです。私は、そのために命を使いきりたいのです。
統一選挙を振り返って
日本一の後援会に支えられて
事務長 秋田 公司

今回の選挙、事務長という重責を担い、私は身の引き締まる思いでした。
日頃の後援会、昌友会、昌友塾の活動をいかに表現し、また候補者が十年ちかく早朝毎日のように街頭演説している政論を、いかに多くの市民に訴えるか?そのことだけを考えれば結果はついてくる。
自分にそういい聞かせながら選挙に臨みました。そしてそうしたことを皆が信じ、正々堂々と臨める陣営に、誇りを感じました。
強く印象に残ったのは終盤の塔南小学校での総決起大会です。300人を越える満員の会場で、候補者の演説と会場の支持者の思いが一体となり、大きな感動を呼び、多くの人の心に強くきざみこまれました。私も目がうるうるしてしまいました。不安な先の見えない世の中、こうした感動こそが、人々の元気の源になると感じました。
結びに、日本一の後援会の皆様に支えられ、すばらしい候補者をもち、正々堂々選挙に臨めたことを事務長として衷心より御礼申し上げます。

選挙に際しましては、御支援,御助力を賜り街宣本部長として厚く御礼申し上げます。 今回の選挙は、ありのままの西田昌司を見ていただけた選挙ではないかと思います。
出陣の日、西田昌司は大上段より真正面に言論の剣を振り下ろしました。「日本が危ない!」「国民の生命・財産・名誉を守るのが政治の責任だ!」「地方から国政を変えよう!」まさに正論であり政論です。前回執筆の『政論』、今回執筆の『政論?』、毎月の『昌友塾』、弛む事のない『早朝説法』それらの集大成としてあふれる思いを語りました。
早朝よりの朝立ちコール、昼の街宣、夜の演説会と激しいスケジュールで次第に西田昌司の声は枯れてきます。しかし、逆に弁舌は冴えます。もはや言葉ではなく身体で、心で訴えました。
西田昌司の日本の将来に対する心の丈、人を愛する心の深さ、闘いの激しさは、思わず見せた熱い涙が雄弁に物語っていました。

選挙といえば昼間の華々しい「街宣活動」が印象的ですが、夜8時からは「個人演説会」が主役になります。読者の皆様の中にもお近くの集会所やご近所のお宅へお出向きいただいた方も居られるかと思います。その会場を毎夜3個所演説会場に仕立て上げるのが私たち『設営隊』の仕事です。「看板・提灯・ポスター・街灯・垂れ幕・受付道具・・・・」と手際よく飾り付け、3~40分で仕事を終えます。今回を含め3回の選挙設営隊を見守ってきましたから、そのスタッフの能力や苦労もよくわかります。今回の選挙で特筆できるものはやはり若い力でした。
柿本大輔君・秋田大輔君、二人の「ダイスケ」が大きな戦力となってくれたことです。運動期間中は「雨・風」と悩まされることが多く中でも『心臓破りの久世6個所』は時計と競争しながら久世橋の渋滞に冷や汗をかいたものです。
嬉しかったことはただ一つ、活動最終日の設営が終わり『明日は行かずに済む・・!』と安堵した時ですね(笑)。なんといっても、昌司さんがトップ当選してくれたことが何よりのねぎらいだと思っています。

私は何の取り得もない普通の会社員です。それが昌友塾に毎月参加させて頂いている縁もあり、今回の選挙では簡単なお手伝いをするつもりで打合せに参加したところ、演説会の応援弁士をすることになってしまいました。極めて貴重な経験ができる折角の機会ですので、2~3回なら頑張ってみますと返事をしましたが、フタを開けてみると私の出番は15回でした。最後まで慣れることはありませんでしたが、非常に充実した9日間でした。
初めて選挙に関わった感想としては、とにかく感動するシーンが多かったということです。特に西田候補の演説は毎回凄い迫力でした。人生で「感動する演説」を聴く機会はそう多くないはずですが、お陰様で私はほぼ毎日聴くことができました。中でも候補者・聴衆が一体となった塔南小学校の演説と最終の演説会場「大通寺」でのエンディングは恐らく一生忘れることができない素晴らしい思い出になると思います。先生には、お祝いと同時に心からお礼を申し上げたいと思います。有難う御座いました。
時代の為に何を残すか・・・
伝えよう!美しい精神(こころ)と自然(こくど)
-議員生活13年の中で感じたこと-
私が府議会に議席を得たのは平成2年4月、荒巻知事の2期目の選挙と同時に行われた補欠選挙の時であり、あれから13年の歳月が流れました。この間に東西ベルリンの壁が崩壊し、ソビエトがロシアに変わり、自民党が政権から下野するなど、歴史の大きなうねりの中で議員生活を送ってまいりました。自由主義対共産主義という時代が終わり、反共以外に何を政治の機軸にするのかが問われる時代に、私の議員生活は始まりました。
議会の中で共産党ともよく議論をしました。その中で私が気づいたのは、共産党の主張は共産主義に基づくものばかりではないということです。共産主義が間違いだということは言うまでもありません。しかし、共産主義ではなく住民の要望や要求だといわれればどうでしょうか。「共産党の主張は財源無視した無責任な政策だ」と言う議員もいます。確かにそのとおりです。では、財源があれば正しいのでしょうか。もっと根本的に、共産党の主張の何が間違っているのでしょうか。私の結論は、「共産党の主張は一部の国民の意見や要望だけで、日本全体の利益を考えていない」、また「次の世代の利益も、国の礎をつくった先人に対する敬意もない。つまり、利己主義に過ぎない」ということです。このことは共産党だけでなく、戦後政治についても言えることではないでしょうか。目先の利益ばかりに走り、歴史観に欠け、日本全体の利益をないがしろにしてはこなかったでしょうか。
例えば族議員の問題です。彼らは、確かに一部の業界や地域の利益は代弁してきたかも知れません。しかし、国全体の利益をおろそかにしてはこなかったでしょうか。民主主義が成立する為には、個々人が自分の利益を追求するだけでなく、社会全体の立場に立った議論が必要です。つまり、公の精神が欠如した要望は単なる利己主義に過ぎないということです。そういう意味では、戦後の政治は公の精神が欠け、利己主義に陥っているのではないでしょうか。公の精神無しに、一部の意見を国民の声として代弁してきたのではないでしょうか。
-戦前と戦後の違い-
公のことを議論すべき政治の場が何故、いつから、私欲代弁の場になったのでしょう。それは、敗戦により政治の世界から公の精神が消滅したからではないでしょうか。言うまでもなく、公の延長線上に国があります。従って、公の精神は当然国のことを考えることに通ずるものです。しかし、戦後社会は「国の為に戦争が起き、多くの犠牲者が出た。これからは国の為ではなく、自分の為に生きるべきだ」という倒錯した精神構造を造り出してしまいました。こうした敗戦によるトラウマ(心の傷)が戦後政治から公の精神を消滅させ、同時に、国民から歴史観を奪ったのです。戦前と戦後に歴史の大きな断絶を生み出してしまい、戦後の日本人は過去を全て否定してきた為、自らの歴史を語ることができなくなったのです。しかし、今日の日本があるのは間違いなく先人の犠牲や努力のおかげです。戦前の日本が子供のために一所懸命働き続けてきたとすれば、戦後の日本は親の恩恵にあずかっていることも知らず、その遺産の上にあぐらをかき、放蕩しているドラ息子と同じではないでしょうか。
-バブル崩壊後の日本から見えるもの-
その放蕩の象徴であるバブルが終わってから十数年が経ちました。この年月は失われた十年と言われますが、一体何を失ったのでしょう。もちろんお金や財産も無くしました。でも、一番失ったのは自信ではないでしょうか。こうすれば必ず成功するという成功の方程式を無くしてしまい、立ちすくんでいるのが日本の現状でしょう。かつては難しいことなど考えずとも、ただひたすら一所懸命に働いていれば、豊かになり、幸せになれました。しかし、今では一所懸命働いてもかつてのように豊かになれないし、幸せになれそうにもないというのが実感でしょう。ところが、現実の日本は世界有数の経済大国であり世界一の長寿国であり、更には大戦後一度の戦争も経験していない世界有数の平和な国なのです。にもかかわらず、豊かさ幸せも実感できない国になったということが本当の問題なのです。
-日本の目指すべきことと私の使命-
現代日本の問題は、結局、人生の目的や意義を飽食の中で見失ってしまい、その為の孤独感や焦燥感が引き起こしたことではないでしょうか。このことは日本だけの問題ではなく、先進国が必ず通過しなければならない問題なのです。かつてローマは、パンとサーカスに明け暮れ、生きる目的を見失った為、自ら崩壊してしまいました。日本もローマと同じ道を歩んでいるのではないでしょうか。
人生の目的や意義は、人それぞれ考えるべきことですが、私は次のように思います。 自分が生きているということは、自分の両親が存在していたことを証明しています。その両親にも両親がある訳です。例えば、仮に日本歴史を2000年、一世代を30年とすると70代に及ぶ祖先がいることになりますが、いったい何人だと思いますか。その数は2の70乗という天文学的な数字になります。そしてこのうちのただ一人が欠けても、私の存在がないというのです。このことは、果てしない生命の連続の上に自分があるということを、否が応でも教えてくれます。そして生命の連鎖の中にある自分がすべきことは、この繋がりをいかに次の世代に伝えるかということ以外にほかありません。生命の連続に感謝し、今を一所懸命に、真剣に生き抜き、次の世代に自分が生きた証をしっかり伝える、これが私にとっての人生の意義です。これを国で考えると、国の歴史の積み重ねをしっかりと受け継ぎ、次世代にそれを受け渡すということでしょう。
先祖から受け継いできたものはたくさんあります。でも、自分を自分たらしめているものは何かと問えば、やはり、肉体と精神でしょう。肉体は文字通り遺伝です。精神は遺伝と同時に、家族や友人や社会との関係が複雑に影響したもので、言い換えれば、その人の生き様が作り出したものではないでしょうか。そして、このことを国に当てはめると、我々が先人から受け継いできたものは、自然環境を含めた国土と精神の形としての文化や伝統ということではないでしょうか。
私はこうした思いから、「伝えよう!美しい精神(こころ)と自然(こくど)」と何年も前から訴えているのです。そしてこの言葉が広がることにより、政治に歴史観と公の精神がよみがえり、私たちの生活に希望と期待を取り戻すことこそが私の使命だと思うのです。
今年は統一地方選挙の年です。西田昌司先生も五期目の当選を目指し,新年から心を新たに「理想の政治」を実現するためにがんばっています。この西田昌司先生の「理念と行動」を広報するために,編集室の役割や活動の在り方を話し合いました。西田昌司先生には,西田会を母体とした「昌友会」と政治の在り方を皆様と共に語る「昌友塾」の二つの日常活動があります。このような活動をわかり易く広めて行き,皆様方に気楽にご参加いただけるようにすることも編集室の務めであると考えます。新年号を発刊するに当り,編集室がこの紙面を借り,これからの編集方針を考えることにしました。
◆編集長
この何年かを振り返ってみると,どうもこの日本社会の底流に地殻変動のような,何かが起こっているように思えます。この精神活動の活断層は,モラルハザードや家族間での個(別)化として現れてきます。「自分がよければ…」「迷惑さえかけなければ…」など個人生活だけでなく,「儲かりさえすれば…」という企業活動の責任の在り方まで含んで,日本の各世代で起きているように思いますが…。
21世紀に相応しい昌友会活動の発展を目指して
~SHOW YOU編集室~
今年は統一地方選挙の年です。西田昌司先生も五期目の当選を目指し,新年から心を新たに「理想の政治」を実現するためにがんばっています。この西田昌司先生の「理念と行動」を広報するために,編集室の役割や活動の在り方を話し合いました。西田昌司先生には,西田会を母体とした「昌友会」と政治の在り方を皆様と共に語る「昌友塾」の二つの日常活動があります。このような活動をわかり易く広めて行き,皆様方に気楽にご参加いただけるようにすることも編集室の務めであると考えます。新年号を発刊するに当り,編集室がこの紙面を借り,これからの編集方針を考えることにしました。

◆混迷と言うには論議が少なく,むしろ,混沌と言った方が良いような時代になって来たと思います。心の問題や自分の生き方が厳しく問われているのでしょうが,これを自分に問いかける作業は,やはり一人ではしんどいことです。こんな時にこそ,「昌友塾」のような話し合える場や自分の意思を表明する場があり,参加者と共にみんなで考えるという姿勢を持てることは,有意義なことです。

◆参加することで,顔の見える話し合いができます。この中で自分の生き方や考えを出し,人の意見を聞くことでまた自分に返ることが多いと参加者からよく聞きます。毎回テーマは違いますが,曼荼羅のように参加する総ての人の考えが,何か一つの大きな絵を描いているように思います。言葉だけの世界ではなく,それが西田昌司の理念となり政治の仕組みとなって表現されていくのだと思います。

◆まさにその海図というべきものが,今必要なのだと思います。西田昌司が我々府民を何処に連れて行こうとしているのか。羅針盤と言うべきかもしれませんが,理念と行動指針を明らかにし,参加していただく皆さんに自分の立場から役割を作っていただく,そんな昌友会であり昌友塾でありたいです。
◆その海図がこの新年号の役割であり,理念を明らかにするのが「政論パート?」であり,各々の行動指針はSHOW YOUの各号に載せていくことになると思います。

◆昌友会と昌友塾とでは,それぞれ結集軸が異なってきています。塾に参加している人にも意見を表現する場が必要です。会報に意見を書いたり,次回の本作りに意見として参加してもらうなど,各人が西田昌司の理念や行動の裾野を広げる役割を主体的に担ってもらう取組みを具体化できればと思っています。編集室としても具体的な行動を提案していければと思います。
今世紀は,20世紀のように経済や財政を通して世の中の仕組みを考える,そんな時代ではなくなっています。「成熟」という名の下の「経済成長の停滞」,「グローバル」という名の下の「世界経済の再編」,「国際秩序」という名の下の「一極支配」など,今までの政治や経済の仕組みが大きく転換しようとしています。この変化は政治や経済ばかりでなく,教育を初めとした我々の身近な分野でも起きています。今まで当たり前と思っていた様々な施策や福祉の分野とて例外ではありません。新たな見方や考え方・価値観を生み出すまでには多くの混乱がありますが,この“パラダイム(枠組み)の転換”の時期に,西田昌司先生が「混沌の世に海図を示す」ことは大きな意義があります。私たち編集室はこの海図を基に,初心に立ちかえり広報活動に勤めてまいります。
-豚まんに見る東京一極集中化-
一昨年は狂牛病で暮れ、昨年は牛肉の産地の偽装工作で暮れました。
さて、お肉と言えば京都では「牛肉」のことを言い、豚肉はあえて「ブタ肉」といっています。しかし、今コンビニで売っている「肉まん」には、牛肉が使われていると思っている人が多いのではないでしょうか。本来は「豚まん」」と呼ぶべきで、これが京都の、いや関西の「常識」ですが、いつの間にか日本列島の大半が「豚肉入りの中華饅頭」を「肉まん」と呼ぶようになっています。「肉まん」の名前は東京から発信され、これが全国に伝わり、東京一極集中化現象が「豚まん」にも見られ、関西人にとっては由々しき現象です。(・・たいそうな話やな)
なぜ、「豚まん」と「肉まん」の呼び方の違いがあるかといえば、関西では肉といえば「牛肉」をさすのに対して、関東では「豚肉」を好んでいるのが原因です。消費量も違いますし、1ヶ月の所帯あたりの牛肉消費量の1位は奈良県で、和歌山、滋賀、京都と上位6県は関西が占めています。それほどに、関西は「牛肉文化」なのです。この違いが、料理の世界にも現れ、「肉じゃが」は関西では「牛肉」を使いますが、関東では「豚肉」になり、この境界線は、愛知県の豊橋市あたりといわれています。カップ麺の「どん兵衛」もこの法則を遵守しています。北海道も肉といえば豚肉で、牛肉のすき焼きを食べたければ、「牛肉」と指名しなければなりません。
文明開化と「牛なべ」は切れない関係で、福沢諭吉まで明治時代に「肉食の説」なる文章をしたため、牛肉・牛乳の滋養のPRに努めたそうです。しかし、なぜ牛肉が西日本中心型で展開したかといえば、もともと西日本は水田が多く、農耕に牛が用いられていた。その関係で和牛の飼育が盛んであったことも、今日の牛肉市場を支えているのです。一方、関東以北は水田に恵まれず、放牧が盛んで、牛より馬が中心であり、馬肉を食べるよりは飼育しやすく、よく肥える豚が主流となったためです。
さて、「声に出して読みたい日本語」の中に「豚まん」は出てきませんが、「正しい日本語」から言えば東京の「肉まん」は明らかに間違っていると、ぶつぶつつぶやいているのは、瓦ひとりだけでしょうか?

去る9月17日、拉致事件の解決のため、小泉首相が北朝鮮に訪問されました。結果はご存知の通り、5人の生存が確認されたものの、8人が死亡という誠にショッキングなものでした。北朝鮮の金正日総書記は、今まで完全に否定していた拉致事件に関して、北朝鮮の特殊機関による犯行と認め、謝罪をしました。また、不審船事件も北朝鮮のものと認め共に再発させないことを約束しました。核・ミサイル問題ではミサイル発射の凍結を2003年以降も延長すると言い、核開発疑惑を払拭するため国際原子力機関の核査察を受け入れる意向を発表しました。
これは、今まで北朝鮮がとってきた態度と180度方針転換をするものでした。難交渉を予想していた私は、いささか拍子抜けの感さえあるほどでした。そういう意味では、小泉首相の決断により日朝関係は大いに進展したとも言えます。しかし今回の訪朝の結果、本音の部分で多くの日本人は、なんとも言えない憂鬱な気持ちになったのではないでしょうか。特に、25年前、13才の時拉致された横田めぐみさんのケースなど、酷過ぎて言葉もありません。娘は十年も前に既に死亡し、15才になる孫がピョンヤンに暮らしているというニュースを聴かれたご両親や家族のお気持ちを考えると、胸が詰まる思いがいたします。
しかし、その一方でいわゆる過去の問題については、首相が「痛切な反省と心からのお詫び」を表明して謝罪をし、国交正常化後、無償資金協力金協力などの経済支援を約束したのでした。そのため、北朝鮮と国交正常化した後、日本は、北朝鮮に対し経済援助など多くの支援をすることになります。これは、韓国や中国に対するものと同じです。
北朝鮮訪問を考える上で一番の大切なことは、今までの日本の外交姿勢では問題は何一つ解決できないということです。そもそも、韓国や中国との現在の関係がは果たして「正常」な外交であるのでしょうか。両国に対しては、多大の経済援助をこれまでもしてきました。その結果、両国の経済復興が成し遂げられたに間違いありません。にもかかわらず、両国から出てくる言葉は、日本への果てしない謝罪要求ではなかったでしょうか。その上、歴史認識の問題では絶えず日本に対して圧力が掛けられ、その結果、日本の歴史教科書はこの数年であまりに酷いものになってしまいました。また、国を守るために命を投げ出された先人に感謝の気持ちを表すことは、国民として当然の事です。どの国においてもそのための施設があり、英霊はそれぞれの国の伝統に従って祭られ、日本ではそれが靖国神社になっているのです。このことに対しても両国からクレームがつき、日本では国を代表する政治家が、事実上自由に参拝できない状態になっています。また、中国とは国交正常化30周年になりますが、先日の瀋陽の総領事館の事件にもあるように、完全に日本の主権を無視するような行為が相次いでいます。このように考えてみると、国交正常化と言うものの、実体は日本にとっては、まったく正常な状態とは程遠いものではないでしょうか。つまり、「正常化」という言葉が意味するものは、日本を敗戦国としての立場に押し込めることを意味するものなのです。勝者が敗者を裁くという政治的な見せしめがいわゆる東京裁判であったのですが、その枠組みの中に日本を押し込んでおくということなのです。敗戦国には、主権など認められないのでしょうか。
これでは日本人が納得できないのは当然です。勝者にとって都合のいいように歴史を語ることは、歴史上よくある話です。まさに勝てば官軍なのです。しかし、だからといってそれにいつまでも屈していたら、敗者は未来永劫に敗者であり続けなければならなくなります。これでは敗戦国には主権国としての未来はないことになります。
その上考えてみれば、そもそも日本は韓国や北朝鮮とは戦ってないのではないでしょうか。当時、ロシア南下の圧力のもと、韓国とは話し合いで日本との統合の道を選んだのではなったでしょうか。そして、彼らと一緒になって戦ったのは、アメリカであり中国でした。しかし、その中国も今の中国ではなく、蒋介石の中華民国であります。今の中国は中華人民共和国であり、中華民国と内戦に勝利した結果、大陸を支配することになった国なのです。そして、いわゆる日中戦争と言われている時代には内戦のため、蒋介石の中国は当事者能力が既に無く、毛沢東の中国は未だ国としては認められていない状態で、ある意味では日本は、こうした中国の内戦に巻き込まれたという見方も出来るのではないでしょうか。
このように考えると、「正常化」という名の下ににされてきた、韓国や中国との外交方針や歴史認識は、まったく日本側にとって一方的に不利なものであるということが分かります。それをこれから北朝鮮にまで適用して行くということでは、最初から日本人が納得できるはずが無いのです。

小泉総理は日本の総理として始めて北朝鮮の拉致問題に真正面から取り組まれました。その政治姿勢に対して国民は期待をし、小泉総理への支持率も上昇しました。しかし、この問題を解決するためには、今までの日本の外交姿勢を根本的に見直し、東京裁判による体制から脱却することを掲げる以外方法は無いのです。勿論、これはそう簡単には出来ないでしょう。北朝鮮だけでなく韓国や中国からの反発もあるでしょう。また、日本は今、連立政権であり、こういうことを掲げては、小泉総理の国内の政治基盤自体が維持できないでしょう。
だからこそ、われわれ国民一人一人が、日本の戦後体制に対して見直すべきだとの声を上げなければならないのです。小泉総理を北朝鮮に突き動かしたのもそうした国民の声であったように、われわれ一人一人が目覚めなければならないのです。そうでなければ、この先日朝間の交渉の行く着く先は、結局北朝鮮の金正日政権の延命に手を貸すだけという、われわれにとって最悪の結果になりかねないのではないでしょうか。

坂 田 晃 啓(てるひろ)
昭和40年10月12日生れ:一級建築士 洛南建設株式会社勤務 昌友会会員
若手昌友会々員を“地域でガンバル人”に取り上げました。実務に追われながらも着実に夢を実現させる所にガンバリを感じました。“独身・お嫁さん募集中!” も大きく書く事を約束して取材させて頂きました。
受注としては個人住宅が半分を占めます。その他は公共工事・工場・オフィスビル・店舗・リフォームなどを請け負っています。私の仕事は営業・設計・見積り・現場監督・不動産業務までと、あらゆる業務をこなしています。不動産部門もありますので街づくりをトータルコーディネートできるのが強みです。
お陰さまで仕事の半分は以前に何がしかお取引をいただいた方々です。これは創業以来「お客様の立場になり、思いやりを持って接する」という姿勢がご評価いただいてるのだと思います。
建物を作ると言うことは、人にどのように信頼されるかと言うことに尽きます。特に個人住宅では「施主」と呼ばれるお客様の家庭で合意がうまく行くように、タイミングを計りながら話を進めなくてはなりません。「希望通りの物が出来るのではなく、期待以上のものを御作りする」。これで「良い物を作っていただいたと」お客様にご満足いただけるのです。勿論予算がある仕事ですから、お客様が何を希望されているのかを一緒に考えていきます。お客様の言葉通りを実現するのではなくその話の中からお客様が何を求めておられるのか、聞き出す事が大切だと思うからです。工事が始まる前には現場のご近所の方々に十分ご理解をいただきます。全ては「お客様の立場になり、思いやりを持って接する」の原点に立つことから始まるように思います。

建築の仕事は分業ですので、私自身も最後まで通して現場を見ることはまれです。そんな中でも市内で建設した4階建ての診療所では、一つ一つ問題を片付けながら4ヶ月間現場監督も務めました。無事お引渡しが出来た、思い出深い仕事です。その現場も含め、全ての現場を毎日欠かさず回る社長の姿勢や事務方の支えにより普段の業務が滞りなく進んでいるのだと思います。
事務所の2階にはモデルルームを常設しております。また、お客様のイメージを形に変える為、コンピューターによる建築用キャド(CAD)の導入を準備しております。
やはり景気の話からすれば厳しい局面が続くと思います。お客様の満足がかなえられるところしか生き残れない事も確かですが、お客様に支えられているという思いは一層大切にしようと思います。私ども洛南建設が居を置く南区、殊に唐橋地区は地元の方が多く、そういう意味合いからも地元の方々に支えられているのだと思います。
昌友会に入会するきっかけは近鉄東寺駅前、早朝独り黙々と演説する西田昌司府議の姿に感銘を受けたからです。 秋田昌友会々長の勧めもあり入会いたしました。何かしら、苦境を切り抜けてゆく人や思いやりのある人に尊敬や親しみ・共感を受けます。それは、私の父を見ているからだと思います。父が18歳の時に祖父か亡くなり、祖母と父で7人の兄弟の成長を見守って来ました。その祖母が残した言葉が「倹約して活きなさい・人には思いやりをかけなさい」と言う言葉だったと聞いています。父は毎朝表を掃除します、出勤する社員の皆さんや通行する人達が少しでも気持ちいいようにと。今それを私が継がせて頂いています。
スキュウバーダイビングに興味があり始めました。まだ耳抜きもうまく出来ないくらいですが。映画も好きでよく出かけていました。「愛と青春の旅立ち」が今でも一番心に残っていますね。昨年からは唐橋消防分団に入団しましたが、まだまだ新米です。仕事を大切にしながら西田昌司府議を始め地域の方々と今後益々お付き合いいただきたく思います。
羅生門の樋のひとしずく
羅城門の樋
-アンデスの山の海軍-
この夏、海外協力援助の仕事で、、南米ボリビアのに行く機会がありました。その時見たことを少し紹介したいと思います。
私が入国した翌日は建国記念日で、街では様々なパレードが行われにぎわっています。その朝のことです。まだ早朝でしたから、ホテルの窓から見える光景は、5千メートルのアンデスの山並みと抜けるような青空だけです。その景色にウットリしていると、マーチの音が響いてきました。窓の下には、軍楽隊を先頭に純白の服にサーベルを持った士官とこれも真っ白なセーラー服を着た兵士が行進の演習をしていました。「ああ、今日の練習か」と思ったのですが何かしら心にひっかかりました。それが何か気付かないままに、知り合いの行政官との会合に出かけました。
仕事の調整の後、「今日は休日だから」と言って、私をパレード見学に連れて行ってくれました。目抜き通りは、既に沢山の人が着飾って並んでいます。パレードは、華やかなバトンフラワーを先頭にした学校の生徒や団体のものがありましたが、やはり行進となると一糸乱れない軍のものに、人々の人気は集まります。その中でも人々の拍手と声援が大きくなったのは、早朝窓から目にした白い服の一団でした。
その時ようやく心に引っかかっていたのもに気が付きました。何故、この国に海軍があるのだろうかと。エリザベス?世が、唯一征服できない国として自国の世界地図から消してしまった逸話が残っているほどです。(無敵艦隊を派遣できない海のない国という意味です)私は彼に質問してみました。彼は威厳に満ちた顔をで言いました。「私の国と国民の誇りです。今海はありませんが、昔はありました。」かつて、4度の隣国との戦いに敗れ、海はなくしたが、国としての誇りは、今も持ち続けているということでしょうか。
この話を聞いているとこんなジョークを思い出しました。まだ、ソ連があった時代のチェコスロバキアの国会での話です。
「議長同志。我が国も海軍を創設しようではないか。」
「議長同志。我が国には海がない。なぜ、海軍を持つ必要があるのか。」
「議長同志。我が友邦、ソ連を見よ。かの国には文化省があるではないか。海がないからと言って、海軍を持たざる理由はない。」
これは、「プラハの春」をソ連の戦車で蹂躙された国ならではの、ジョークです。
アンデスの5千メートルの山々がそびえる中で、(ちなみに首都ラパスは、富士山より高く3800メートルの高さにあります)海軍は国民の誇りとなっています。海軍があることが、かつての南米の大国であった証なのかもしれません。高山の国にもかかわらず、また発展途上国としての困難を抱えながら、アンデスの海軍は国民から支持され、精神的な支柱として存在しています。その純白の服に歴史の重みと国民の思いを重ねています。石油や天然ガス、鉱物資源に恵まれながら海がないために活用できない現状と栄華の歴史を、その白い服は映しているのでしょうか。

中国の武装警官が日本総領事館に入り、亡命を求めて駆け込んできた北朝鮮の親子五人を連行していくという事件がありました。中国の武装警官が領事館の中に入ってくるということ自体も問題ですが、もっとよく考えなければならないのは日本の領事館や大使館という治外法権で守られているはずの国の施設や機関をいったい誰が守るのかということです。本来大使館や領事館には、その国の警察や軍隊を派遣して守っており、その中には接受国とはいえ現地の軍隊や警察権は及ばず、今回の事件のように現地の武装警官が入ってくることなどありえないことなのです。
にもかかわらず、今回のような事件がおきたということは、つまるところ大使館や領事館という日本政府の外国での出先機関の治安の維持が、まったくもって不十分だということなのです。そして、このことが意味するところというのは、国民の生命、財産、名誉を守るというのは日本の政府として、一番の責務であるにも関わらず、それが国内においても国外においても、まったくといっていいほど機能していないということではないでしょうか。
他国の侵害から国民を守るべき国の機関というのは、当然その国の軍隊であり、日本でいえば自衛隊です。しかし、これまで、在外邦人を守るために自衛隊が海外に派遣されることは一度もなかったのです。自衛隊という日本を守る仕組みは一応あるけれども、まったく機能していないのです。
もし日本人である我々自身が、海外で何かトラブルに巻き込まれて大使館や領事館に逃げ込んだ場合、暴漢が追いかけてきても、それを食い止めて助けてくれる手立てが何も無いということです。接受国の政府の警察や軍隊が配慮してくれることはあるかもしれませんがが、大使館や領事館という、治外法権であるはずの場所が、日本人を守ってくれる仕組みになっていないというのが現実なのです。
有事というものは、いつでもどこでも起こりうるものであるということを、我々は戦後いくつも目の当たりにしてきました。例えばペルー大使公邸に武装ゲリラが立てこもった事件。国の象徴である在外公館が占拠され、人質までとられたにも関わらずペルーの警察や軍隊が助けてくれるまで、何の手出しもすることができませんでした。ゲリラが押し入ってきてもそれを排除する仕組みがなかったのです。
しかし、こういった事件というのはこれまでは幸いにも海外で起きた事件ばかりでしたが、実は舞台が日本国そのものであっても同じ話なのです。直接日本が攻められたり外国から難民がきても、日本政府として、これを守ったり、排除したりといったことすらできないというのが今回の事件の本質なのです。政治の一番の使命は何かといえば国民の生命、財産、名誉を守るということ以外にないわけですが、現在の日本というのはこの一番肝心なことができていないということであり、このことを私たちはもう一度認識する必要があると思うのです。
戦後の政治というのは、日本国憲法がそれを禁じていることもあり、国家として国民の生命、財産、名誉を守るということを国民自身がはじめから想定しておらず、誰かがやってくれるという前提で成り立っています。私には、そんな憲法自体が、憲法違反に思えて仕方がありません。憲法とは法律のもとになるものです。法律は政治同様、国民を守るためにあります。その法源にあるのが憲法なのですが。では、憲法に従わなくてはならない理由というのはいったい何でしょうか。
我々の永年にわたるいろいろな経験則の中から積み上げてきた良識や常識を成文化したもの、つまり、一番大きな我々の価値の集合体が憲法ならば、これは守らなくてはならないものです。しかしながら、今の憲法というのは良識や常識の集合体とは言えないし、それを基本とした法体系のまま五十数年間日本は戦後社会を作ってきました。現行憲法は日本人の良識や常識という強固な歴史的土台に根差しておらず、いわば砂上の楼閣という危ういバランスの上に成り立っているということをもう一度考え直さなくてはならないのではないでしょうか。
戦後の五十数年は、幸いなことに、日本人はほとんど戦争と無関係に過ごしてきました。しかし、ここのところ冷戦時代のような米ソ両国の力の均衡による世界秩序が、崩壊しています。つまりは、冷戦が終わった後、国と国との利害の衝突があちらこちらで起こるという大変な時代に突入してきています。
私たちは、今回の事件を目の当たりにして、もう一度、国を守るというのはどういうことなのか、独立した国であるというのはいったいどういうことなのかを、認識しなくてはなりません。日本が国家としての本来の責務すら守ることができない仕組みの中にあるということを、今こそなんとかしなくてはならないのです。
かつてペルーでの事件がおきたにもかかわらず、何も反省されることなく再び今回のような事件が起こった状況を考えると、日本という国はこれから先一体どうなってゆくのか不安でなりません。
国際関係というのは、外国と仲良く交際をすることだけではありません。外交という手段を通じて国家の主権や国益を背負って外国と交渉することがその本質です。そしてそのためには時として命を賭けなければならないときがある。しかし戦後の我が国では最初から主権や国益という認識が抜け落ちているのだからまともに外交などできるはずがないのです。外交に限らず経済政策、教育などの問題の根源がすべて戦後の体制にあるのだということを認識し、しっかり議論していかなくてはなりません。
戦後五十数年。遅きに失してはいますが、今、戦後体制から脱却するための一歩を踏み出さなくては日本の将来はありえませんし、その一歩を刻すべく勇を鼓すること、それが、戦後の繁栄と平和の時代に生を受けた我々の世代の使命なのではないでしょうか。
(月刊「発言者」7月号・西田昌司原稿より抜粋)

昭和15年、京都生まれ。昭和38年、京都大学経済学部卒。
三菱重工業?勤務を経て、昭和53年より綾部市議会議員を3期、昭和62年より京都府議会議員を3期務め、この間、京都府連政調会副会長、副幹事長などを歴任された。
平成10年、綾部市長に初当選。本年1月に再選され現在2期目。
ほんまもん
料理人でも大工さんでも、勿論経営者の世界でも能力のちがいは歴然としており、それに応じて給与もちがいます。
しかし、政治家の場合、必ずしもそうではありません。一度バッジをつければ、もうそれで一人前。あとは当選回数が支配する年功序列社会。エスカレータ-に乗り、そのスピ-ドは「数の力」。ともかく群れることが尊重されます。だから、一票は一票。どんな形でも選挙で勝てばよい。一票の質を高めることなど、そんな回りくどいことをやっている暇はないということになるのです。
気まずくなるような真剣な議論は避けろ、いわんや「千万人といえど、吾往かん」といったタイプは孤立する……。
これがいわゆる高度成長、田中角栄さんの政治に代表されるものでした。前尾繁三郎さんのように温故知新、哲学を尊び沈思する政治家の出番はなかったのです。それはまた、政策を依存した官僚との蜜月の時代でもありました。
しかし、21世紀は、集団よりも個の時代、個性と異能に頼らなければならない時代になってきました。暇があったら図書館に行ったという小泉純一郎首相の誕生もそうした時代の産物です。
そして、わが西田昌司兄がいよいよクローズアップされる時代にもなってきました。これが当たり前なのです。
囲碁の世界でも初投もあれば九段もある。相撲もまたプロといっても序の口から横網まであるのです。そのちがいは、個の能力のちがいであって、序の口でも何でもいい、ともかく数さえおれば、横網をつくることができる、という甘いものではありません。
政治においても相撲社会と同じく志のある人、情熱と行動力のある人、一票の質を大切にしようとする個の政治家が正当に評価される時代がやってきたのです。
要するに、私が言いたかったのは、西田昌司なる人物が、志を大切にし、深く考え、公のため真剣に議論しようとしている政治家であるということです。ほんまもんの政治家だということです。
彼の力を正当に評価し、余すところなく使いこなす良き先輩(リーダー)がいたら彼にとって何と幸せなことだと思います。
しかし、彼を私淑させるようなリーダーはそう簡単には見つからないでしょう。とすれば、彼自身がリーダーになることです。
悪貨に流されず、良貨を糾合する。大変なことですが、彼なら必ずやれるはずです。
なぜなら、何より志に魅かれて集まる昌友会の皆様がついておられるし、「継続は力」。彼を慕う人は、増えつつあります。
私もまた、微力ながら、はるかに西田昌司兄の大成を心より願っておるのです。
『正しい言葉を残していこう』
ワールドカップの嵐が日本全土を駆けめぐり,老いも若きもサッカーに夢中になり,そこから新しい文化さえ生まれる気配があります。この嵐が過ぎ去り,祇園祭のお囃子の練習が始まる頃には,京都の街も落ち着きを取り戻しているような気がします。
さて,少し前,「大文字焼き」といったせりふをTVのタレントがしゃべっているのを耳にしました。どんな煎餅かな?何処の陶器かな?と思っていると,「五山の送り火」のことを「大文字焼き」と呼んでいるではありませんか!他のタレントもそれを訂正(?)しようともせず,番組は流れていきました。子供たちに,「大文字焼きって知っている?」と尋ねたところ,ちょっと首をかしげて,「お盆の送り火のこと?」と答えが返ってきました。ホットするやら,ここまで毒されているのか,とがっかりくるやらでした。
東寺のことを「弘法さん」と呼んで南区民(いや京都市民)の方々は慣れ親しんでいますが,正式な名称は「教王護国寺(きょうおうごこくじ)」又は「真言宗総本山東寺」と呼びます。六孫王神社のことを「ろくそんさん」,六道珍皇寺を「ろくどうさん」と通称で呼んでいるのは良いのですが,「五山の送り火」を「大文字焼き」と通称するのはどうもいただけません。
通称で,気になる言葉に「宵々山」があります。祇園祭の宵山は祭の前日のことで,一般には「宵宮」といいます。同じ曳山祭を行っている大津や飛騨高山では「宵山」という呼び方はしないそうです。ましてや「宵々山」といった呼び方はしません。この名前は,確か昭和40年代,円山公園音楽堂で「永ろくすけ」が付けたものだと記憶しています。
フォークソング全盛時代に高石友也,ナターシャセブン,杉田次郎etcが集まってコンサートを開催し,そのときの司会者が「永ろくすけ」でした。
30年も経過すると市民権を得てしまうのか...。でもこれが伝統の祭の前日の呼び名として認められるのも少し悔しいような気がします。観光客に正しい名称を知ってもらうことはもちろん,若い京都市民の方々にも正しい呼び方をしてほしいものです。特に伝統文化に係わる行事にとってはなおさらで,これには行政も観光団体,まち並み保存の市民団体も立ち上がってみては如何なものでしょうか?
ワールドカップから新しい文化が生まれ,新しい言葉も生まれてきます。しかし,伝統文化,行事に係わる言葉は,通称であっても歴史の重みがあるはずで,それが千年の都たる京都の本質なのです。
このような,危惧をしているのは瓦ひとりだけではないと思いますが....。

皆さんはじめまして、本年6月より西田事務所に就職しました岡野貴繁と申します。大学卒業後はアルバイトとして働いておりましたので社会人としての経験も今回が実質初めてですので、先生や事務所の方に迷惑をかけてばかりの毎日です。しかし、今後精進していき、しっかり頑張りたいと思っております。
私は今年24歳になりますが、京都市左京区の生まれで地元の小中高を経て立命館大学を卒業しました。
学生時代から政治に関心をもっており、今回ご縁があり西田事務所で働くことになりました。
以前選挙の運動員をした時に、後援会の方々や秘書の方々の働き振りを見て私も将来機会があれば働きたいと思っておりましたところ、大学を卒業して2年経過して自分の将来について考えていたある日、西田事務所が職員を新たに募集していることを知り、西田先生のもとで勉強したいと心を固めました。
実は、学生時代から私は幾度か選挙に関わっていたにもかかわらず、西田昌司先生のことは名前を知っていた程度でした。事務所への就職を決めるにつき先生の演説を聞いたり、「政論」を拝読し鋭く、保守の立場からこの国の抱える問題点を的確に指摘されていることに共感しました。
若輩者ではありますが、西田先生の政治活動の手伝いができることに誇りと責任を感じ、精進したいと思いますので、ご指導ご鞭撻よろしくお願いいたします。
岡野貴繁拝
編集後記
1年に満たない短い期間ではありましたが、家庭の事情で帰郷することになりました。
いろいろな思い出が詰まった1年間でしたが、中でもこの「showyou」には強い思い入れがありまして、皆さんからは薄っぺらい印刷物にしか見えないかもしれませんが、原稿を依頼して、徹夜で校正をして、編集会議で議論したりして、やっとの思いで完成させています。
そういえば、人目のつかないところで様々な方の汗と知恵が集約されて完成しているこの「showyou」の姿というのが政治家の姿とかぶって見えるのは私の考えすぎでしょうか… 西田議員の今後益々の活躍と、「Showyou」読者の皆様方のご多幸を遠く鹿児島の地より見守っております。ありがとうございました。
杉尾巨樹
SHOWYOU編集室

鈴木宗男衆議院議員の問題で政界ばかりか国民世論もが紛糾しています。鈴木衆議院議員はこの問題の責任を迫られ、先日自民党を離党致しました。鈴木問題の本質は戦後政治の抱えている問題を如実にあらわしていると思います。私も含め政治家は、自分の選挙区に一番関心があるものです。しかし、一方で自分の選挙区のことばかりを政治の場で取り上げる事は、利己的で自己中心的なことだというので、普通は”卑しさ”とか”恥ずかしさ”を感じるものです。つまり、普通は自分と自分以外のもの(言いかえれば私と公)との間のバランスを保つ事によって、政治家の行動は正常なものとなります。鈴木さんの場合は残念ながらこうしたバランス感覚が全く欠けていたということです。
しかし、公とのバランスを欠いた我田引水的発想は、鈴木さんだけではなく、また、与野党問わず、戦後政治に蔓延していることではないでしょうか。例えば共産党お得意のばら色政策もその典型です。福祉や教育の充実を言うのは良いが、税金を払うのは嫌で、その財源は誰かが負担してくれれば良いというのでは、利己主義そのものです。共産党の例では、司直の場で罪を問われることは無いかもしれませんが、政治家としてモラル不足のそしりは免れないでしょう。
このように考えると鈴木さんの事件は、「公の観点」が無く、「私の利益」の代弁ばかりが、あたかも正当な主張のように議論されてきた、戦後政治の抱える問題を浮彫りにしていると言えるでしょう。では何故、こうした「私」の利益の代弁者たる「政治屋」がこうまで蔓延してきたのでしょうか。それこそ、戦後政治が公的なものを如何にないがしろにしてきたかを表すものです。
元々政治は何の為にあるかといえば、国民の生命、財産、名誉を守るためにある、と私は思います。ところが戦後政治はこの肝心の部分をアメリカに外注してきました。国防も、経済も、教育も、その根幹にかかわる肝心のものは、すべてアメリカに任せてきたのが実態です。この政治の根本が一切語られなくなったため、戦後、政治の場で話されることは結局、経済的利益の配分でしかなかったのです。鈴木さんのように地元の選挙区に如何に予算をつけるか、野党のように自分を支持する人々や団体に如何に予算を厚くするか。これらのことは形は違っても本質は同じで、どちらも自分の支持者のことしか考えていない、国のことなど考えていないということです。確かに目的と必要に応じて、利益を配分することも大切なことです。しかし、その元になる「公」のことを考えずに「私」のことがまかり通るようになれば政治が腐敗するのも当然です。
「公」を考えない私利私欲の追求は、端で見ていても、大変醜く気持ちの悪いのもです。今の政治はまさにその典型です。同じことがマスコミにも言えます。ワイドショーに代表されるマスコミの報道も、視聴率が取れれば良いというだけが目的のようです。「社会正義を糾す」という司会者の言葉もそのお飾りに過ぎないのは誰もが感じていることです。田中角栄を今太閤ともてはやし、その舌の根が乾かないうちに金権政治家とこき下ろしたり、野村克也、沙知代夫妻にしても確かに本人にその責めがあるのは事実ですが、上げたり下げたりのあの報道の熱狂ぶりは一体なんだったのかといえば、「売らんかな」の一言に尽きます。これこそエゴイズムの典型で、テレビが公器であるという自覚が全く感じられません。このように、今の日本ほど「公」という言葉が存在感を無くした時代はかつて無かったのではないでしょうか。従って、これから本当に鈴木宗男的なものを政治の世界から排除するためには、まず政治に「公」という言葉を取り戻すことから始めなければならないのです。
ところが、政治の場ではこれとはまるで方向違いの話しがされています。一部の議員の間では、今後こうした問題が出ないようにするために、国会議員が行政に接触する事を禁じたり、制限する方向で法改正をしようする議論がされています。全く馬鹿げた議論だとしか言い様がありません。これでは、官僚は、自分の所管の事柄も現実を知ることなく、蛸壺的な行政を行うだけに専念しろと言っているようなものです。これでは政治に血を通わせることも出来ません。また、民意を行政に伝える手立てが無くなってしまいます。問題は政治家が行政に関与したことが悪いのではなくて、その目的や程度があまりにも、私利私欲にすぎるということです。

結局は、政治家のモラルが問題になるのですが、これは、法律で罰則を強化してなくなるものではありません。政治家に一番求められるモラル、それは一体なんでしょうか。勿論、国民の信頼を得るためには清潔であるということも必要です。しかし、国民に信頼されて政治家は一体何をするのかといえば、国民の生命、財産、名誉を守るということではなかったでしょうか。これは言いかえれば、国家存亡の危機に、必ず国民を守ってくれるという究極の信託を国民は期待しているということです。まさに政治家の使命というのはこの一点に絞られると私は信じております。
今回の宗男騒動は、国民の究極の信託に応えるという政治家の使命を、鈴木宗男さん本人は元より、野党もマスコミも含めて果たせていないということを、私たちに見せつけたのではないでしょうか。もう一度、我々政治に携わるものが、政治家の使命として何をすべきなのかという、最低限のモラルに立ち返ること、これが一番必要なことであると私は思います。今こそ、その意味で「さらば、鈴木宗男的なるもの!」「さらば、戦後政治体制!」と国民みんなが大声で叫ぶときなのです。
Show Youをお読みの皆さん、「政論 ~保守の原点を問う~」覚えていらっしゃいますか。そうです我らが西田昌司先生が以前に出版された本です。私は、普段は新聞と週刊誌程度しか読まない者なのですが、久々に骨のあるしっかりした本を読みたいと思い、前々からじっくりと読んでみたかった「政論」を、今年の元日に、読みました。読んでいる途中で、私は、何度か涙をこぼしました。本当です。「福祉の原点とは」の章がそのひとつです。西田先生が障害者施設を訪問された時の障害者を子供にもつ母親の話です。「この子供のお陰でここまで生きてこられました。私はこの子に生かされてきたのです。」「世間の人には想像も出来ないような苦労もしてきましたが、そのかわりに多くの人との心の絆、家族の絆、地域社会の人達との大変深くて太い絆を築くことが出来ました。」私は、福祉のうわべのことだけしか見ていませんでした。福祉の本質について私なりにわかってきたように思います。
芥川龍之介の「杜子春」の話。西田先生がおっしゃるとおり、人の幸せがどこにあるのかということを考えさせられました。
私には、8歳と5歳の子供がいます。最近の新聞の社会面に載るような、少年に絡んだ事件を見るにつけ、私は、父親の不在ということを感じます。父親の不在とは、父親が子供と一緒にいる時間が短いという表面的なものではなく、父親が子供と同列になってしまい、父親が父親ではなくなってしまったということが本質なのではないかと、私も思います。実際、ここ10年程はずっと不況ですので残業で忙しくて仕方がないという状況は、バブル経済真っ盛りの頃に比べたらかなり少ないのではないかと思います。父親が家にいる時間は多くなっているはずです。それなのにもかかわらず、父親の不在を問われているということは、やはり父親の立場がしっかりとしていないということではないでしょうか。父親が真の父親たらんとしていないのではないかと思います。私が、小学生の子供の父親参観にいった時のことです。自分の子供の学年、クラスとは関係なしに、授業終了後に保護者と先生だけでテーマごとに分けての話し合いが行われました。私は、「父親と子供との関係」というテーマの部屋に行きました。父親をテーマとしているににもかかわらず、実際には母親の出席者がほとんどでした。また、昨年9月の日曜日に、京都府の教育委員会主催だったと思いますが京都教育大学の教授を講師にした「父親について考える」という一般市民向けのフォーラムがあり、私は話を聞きに行きました。そこでも大半の出席者は母親でした。男性も何人かいましたが、ほとんどは小学校の校長先生のようでした。母性の回復も重要なことですが、男が、父親が、だらしなくなってしまっているということが、社会に悪い影響を与えているように思えてなりません。私自身そのようなフォーラムに参加してみようとするのは、自分自身がだらしのない人間で子供にどのように人生を教えていったら良いのかがわからないからでした。西田先生の「子どもたちに何かを伝えたいという生き方が、徳をつむことにより、親の人生にも輝きを持つことができる。」「子どもに対して伝えるべきものを親が持てるような生き方をする。また、精一杯子どもに伝えようとする。こうした子どもに対して責任を果たそうとする努力によって、実は我々大人が、本当の大人たり得る機会を与えられているのです。」の言葉を読み、私は、先生に救いの手を差し伸べられたような気持ちです。もやもやしたもの が、すーっと晴れたような気持ちです。いわゆる優しいだけのマイームパパではなく、親は親らしく、子どもと同列にならない父親になりたいと思います。
小学校でも英語教育が盛んになってきています。別に英語を幼いうちから習うということ自体は決して悪いことだとは思いませんが、何かが欠けているように思います。なぜ英語を習うのかを一言で表わしてしまえば国際人を育てるということだと思いますが、その前に忘れてはならないことがあると私は思います。国際人である前に日本人であるということです。日本人としての心、アイデンティティをしっかり持たずに国際人になろうとすれば、日本人でもない、アメリカ人でもない無国籍な国際人になってしまうのではないかと思います。近年の犯罪、事件を見ていると、ここは本当に日本なのかと思うことがあります。政治も経済も文化も西田先生のいうアメリカ教に侵され過ぎてはいないでしょうか。所詮、日本人は日本に住んでいる限り、日本人なのです。アメリカ人にはなれないのです。今の平成の時代にもう一度、日本人の心を取り戻しておかないと、日本に住んでいながら、日本人ではない無国籍な日本人、地に足のついていない日本人になってしまうのではないでしょうか。このShow Youをお読みの皆さんはほぼ全員が、京都にお住まいの方だと思います。日本人の底流に流れる心、文化、伝統が日本で最も残っているのが、ここ京都ではないでしょうか。1200年前から日本中に文化を伝播してきたのが京都ではないでしょうか。私たちは、日本人の心、文化、伝統をもう一度よみがえらせ、再認識するのに最適な地に住んでいるのです。日本人にも平成のルネッサンスが必要なのです。そのムーヴメントを作り出し得る地に私達は住んでいるのです。
私は、西田先生のこの本の題名を初めて見た時は、「保守」なんて古臭いタイトルだなと思いました。しかし、私はこの本を読んで、「保守」の真の意味がわかっていなかったということがわかり、自分自身恥ずかしく思いました。「保守」は、「保身」ではありません。真の「保守」とは、日本人の心を守っていくことだと思います。私は、この本を読み終えて、近年にない新鮮な気持ちになりました。「古臭い」どころではなく、すごく「新しく」感じました。「保守」についての本を読んで「新鮮」になるのですよ。不思議ではありませんか。上っ面だけのアメリカ教に支配された「●●改革」「××改革」「グローバルスタンダード(=アメリカンスタンダード)」等の言葉が政治に経済に、右を見ても、左を見ても氾濫しています。そんな中で、「保守の原点を問う」と題名にハッキリど出した本を出版された西田先生に心より敬意を表します。これから、日本はいやおうがなしに高度情報化、国際化はますます進んでいくことでしょう。だからこそ、日本人が、日本人の心を失わないように、意識して「保守」していく必要があるのではないでしょうか。そうしなければ、日本人の精神は分裂し,荒廃してしまいます。
この本を読んでいて私は何度か、出版した年月を見返しました。平成11年1月なのです。3年前なのです。変化の速い政治、経済においては、普通、3年前に書かれた本を読むとだいぶ古く感じるはずです。しかし、この本は全くそう感じさせませんでした。真の保守とは、日本人の心の奥底に元々潜むものを守るものであり、普遍性のあるものだからではないでしょうか。私は、このような本に出会えたことに感謝し、この本を執筆された西田先生に感謝の念で絶えません。 Show Youをお読みの皆さん、今度の週末にでも、是非ともお読みください。新鮮な気持ちになりますよ。
桑原尚史
「政論 ~保守の原点を問う~」をご希望の方は西田事務所までお問い合わせ下さい。
この4月から、学校が土曜日も、完全に休日になるそうです。「学力低下が心配だ」「塾通いが増えるのでは」等々、どうもマスコミが煽っているように思えます。人間にとって、今まで経験したことがないことに遭遇すれば、不安な気持ちになります。これってあたりまえのことですよね。だからといって、文部大臣までもが、「宿題を出せ」と言ったとか言わないとか。果ては、「土曜日にも学校で補習を」なんてことも新聞に出ていました。これでは『学校五日制』って、何なんです。
社会の情報化や経済のグローバル化で、高齢化や少子化による人口構造の変化で、今までの教育システムが大きく変化しなければ日本は生き残れない。そのために、今までの教育体系が、『生涯学習システム』として大きく変貌する必要があったのでは。学校の五日制もその流れの中に位置づくはずだと思っているんです。そして、学校は、子ども達が生涯学ぶための基礎基本をきっちり身につける場所。家庭では躾や生き方を親が身をもって教える。地域は、活動の中から生活の伝統や社会的価値を学ぶ場所。この役割分担をしていくために、『学校五日制』はあると思っています。
これからは、なんでもかんでも学校に頼らず、親としての自信と誇りを持って、子どもに接しなければと思っているんです。親の背中を見て子は育つと言いますよね。学校と家庭や地域との役割をはっきりさせ、親としての役割を、もう一度見直さなければと思っております。
そのために、土曜日は子どもと一緒に、地域で何かボランティア的なことでもできないかと。そんなことを考えているんです。町内の溝掃除なんかを、子どもと一緒に汗を流しながらできたらいいなと。自分の子どもの頃の話や親父に作ってもらった模型飛行機が宝物やったと、話したいと思っているんです。自分は一人で生きているんやない。生まれた時から、町内の人のお世話になっているんやから、「おまえもできることは、人のために感謝しながらせいよ。」と教えたいんです。
ともだちをいじめてみたり、先生へ暴力をふるってみたり。何か、今の子どもは苛立っているように見えませんか。自分はこの世にたった一人、『もっと自分を大切にせんかい』。親にとっても、『かけがえのない宝物やで』と教えたいんです。それも一緒の汗を流しながら。これから生きていく世間は、競争だけやない。助け合っていきているんやね。それが『人の値打ち』やということを教えたいんです。地域でお世話になり、地域の人のために自分を役立てる。これを教えることが、『土曜日の親の仕事』やと思ってます。
昌友塾参加レポート
―南洲翁遺訓に学ぶ―

私は、自民党の青年政治大学校の懇親会で、西田先生が「昌友塾」を開催されていることを知り、今回はじめて参加いたしました。今回の昌友塾のテーマは「温故知新ー南洲翁遺訓に学ぶーでした。
私はボランティアに取り組んでおり、その際高齢者施設に行ったときなどに、習字の作品に「敬天愛人」という文字をよく見かけました。意味のわからなかった私は早速辞書でその言葉を調べてみて、その言葉のもつ意味の深さや、この言葉を座右の銘にしていた西郷隆盛という人間に興味をもちました。今回の昌友塾で西郷さんの子孫が初代京都市長だったことも初めて知りました。
私は今まで司馬遼太郎さん(司馬遼太郎さんの作品にも西郷隆盛はたくさん登場しますが)の愛読者でしたが今回「南洲翁遺訓」をしり、また新たな楽しみが増えたように思います。
遺訓の冒頭に「いかにも心を公平に操り、正道を踏み、広く賢人を選挙し、能く其職に任ふる人を挙げて政柄を執らしむるは、即ち天意也。」とあります。今、府知事選挙が行われていますが、この言葉を考えれば、もっとも相応しい候補者が誰であるのかは明らかではないでしょうか。
昌友塾は政治の話だけでなくこのように歴史の話もテーマにとりあげられることもあり、私にとって歴史の知識が深まることはとても幸せで癒される時間となりました。政治以外に興味のある人でも気軽に参加できるように思います。いつまでも「昌友塾」が続いていてほしいと思います。
野 田 知 子
編集後記
「経済」とは『経世(けいせい)済民(さいみん)』の略だそうだ。「世を治め、民の苦しみを救うこと。」(大辞林)が本義で、『エコノミック』の和訳だったらしい。「不況で経済が振るわない」とか「人心の荒廃」は、やはり政治の問題が根本だと言う事だ。京都府知事選真只中。「主権在民」という言葉は辞書が不要なほど解っている。新しい知事の誕生は私たちの近い未来を決めてしまう。投票は重き責任。『経世(けいせい)済民(さいみん)』を預かっているのは今、私たち260万京都府民だから。
SHOWYOU編集室 松本秀次
内親王のご誕生を心よりお慶び申しあげます

去る11月20日京都府の荒巻知事は、府議会の決算特別委員会の席上で、今年四月に施行される五選目の知事選挙に出馬しない旨を表明されました。「新しい時代は新しい知事のもと、新たな気持ちで築いて欲しい。」との退任の弁でした。突然の出馬辞退の報に私たちも大変戸惑いました。まだまだ、荒巻知事続投を望む声も多かったのですが、知事が熟慮の結果出した結論でした。4期16年間の功績とご尽力に感謝とねぎらいを申し上げるとともに、この決断を真摯に受け止め、次の時代の知事を責任を持って選出することこそが、責任政党の議員としての私の務めであると思います。
この間、自民党では府議会議員団を中心に、次の知事の擁立に向け活発に意見調整がされてきました。このSHOWYOU紙面を通して、真の知事のあるべき姿について私の意見を表明したいと思います。
振り返ってみますと、これまで京都府知事は蜷川知事が7期28年間続き、その後を受けて、林田知事が2期8年そして荒巻知事が4期16年続いてきました。荒巻知事は林田知事の誕生と共に副知事に就任され、2期8年間支えてこられました。従って林田荒巻両知事を会わせて24年というものをひとつの時代として考えるべきでしょう。蜷川知事の時代は戦後の復興が国を挙げての課題でした。おりしも朝鮮動乱に象徴される東西冷戦の緊張が高まる中で、共産主義や社会主義のメッキがまだ光り輝いていた時代でもありました。大都市で唯一戦災を免れたため、ある種のゆとりが京都にあったのではないでしょうか。それと先取の気性という「京都人気質」が、蜷川知事を生み出してきたのではなかったかと私は思います。
しかし、28年続いて分かったのは、先進地であったはずの京都が戦後復興に乗り遅れ、後発の他府県に大きく水をあけられたということでした。そこで、遅れ馳せながら京都でも戦後復興をということで、社会資本の整備を中心に林田荒巻両知事の時代が始まりました。林田知事誕生の昭和53年、日本全国で戦後復興が終わり、欧米先進国に追いつき並んだ時代になっていました。しかし、次の時代の価値観を示す言葉も無いままに、経済的問題ばかりが政治課題として取り上げられてきました。そして、その後の方向を示すまともな言葉がいまなお聞かれないというのが昨今の状況ですが、そのお蔭で京都は他府県より一周遅れにもかかわらず経済復興に着手することが出来たのです。林田・荒巻両知事の時代に、遅れていた道路や鉄道の整備が急速に進んだことはご存知の通りです。その後日本はバブル経済の時代に突入し、京都もようやく全国レベルに追い着く目途がついてきましたが、その矢先に平成大不況が始まり、財政に大打撃を受けるのです。

こうした時代背景の中、新たな知事に望むものはまさに「次の時代を示す言葉」であると考えます。蜷川知事は「憲法を暮しの中に生かそう」、林田荒巻両知事は「活力ある京都をつくろう」という言葉を残されました。まさに時代を象徴する言葉です。今、国では小泉総理が「聖域なき構造改革」と言う言葉を掲げ、次の時代を築かれようとしています。しかし、これが時代を築く言葉でないことは、もう皆さんお分かりの事と思います。
何故なら、「聖域なき構造改革」と言う言葉には、改革を断行するということ以外に何のメッセージも無いからです。これは言いかえれば、「例外なき破壊」ということであります。「こんな社会を創る」というとを示さず、現在あるものを破壊するばかりでは、社会の秩序が乱れ景気も落ち込むばかりです。また、小泉総理の中から出てくる言葉をつなぎ合わせると、見えてくる「こんな社会」とは「グローバルスタンダードの社会」以外にはありません。これは、早い話が、アメリカの属国に甘んじるということを言葉巧みに美化してきた、戦後体制そのものを完成させるということで、このような言葉に日本人が希望を抱けないのは当然でしょう。
では、次の時代を築く言葉とは一体どんな言葉でしょうか。こうした時代の流れを踏まえて日本の現状を真正面から捉えるなら、「戦後体制からの真の脱却」ということ以外には無いでしょう。つまり安全保障の面でも、経済政策の面でも、教育の面でも戦後のタブーを乗り越えるということです。「自分の国は自分で守る」「自国の利益は自国が守る」「自国の価値観は自国が守る」この当たり前のことが出来ない限り、日本の本当の存在は有り得ません。小泉総理にはこうした戦後体制からの脱却のために聖域なき改革をしてもらいたいものです。
同じ観点から、次の知事が目指すべきことは何でしょうか。今までの京都は「反共」という言葉の下に与党が結束して林田・荒巻両知事を支えてきました。共産主義を容認するつもりはありませんが、これからの京都が「反共」という言葉だけで語れないのも周知の事実です。先に述べた言葉を京都と置き換えてみると下のような府の姿が見えてきます。
安全な街造り
… 災害から府民生活を守るための危機管理体制の確立。平和で安心な暮らしを守るための警官の増強と治安の確保
府内産業の保護育成
… 一方的な市場原理から府内企業を守り雇用を確保する。(伝統産業や中小企業は市場原理では守りきれません。)
京都文化立府構想
… 単に伝統産業や観光のためだけでなく、京都人の魂を伝える
これらのことは戦後の価値観に押され廃れてきたものの、元々京都が千年の都として営々と築き上げてきたものです。何世代にもわたって府民が京都に住み続けてきたからこそ、京都の街も町衆のコミュニケーションも京都の文化も成立してきたのです。単なるスクラップ・アンド・ビルドではない積み重ねの歴史が、京都を作り上げてきたのです。今一度、京都のこうしたアイデンティティーを見つめ直し、府民に訴えることも政治家としての知事に求められる大切な使命であると考えます。

秋田公司さんは京都生まれ京都育ち。株式会社秋田製作所・株式会社アクト 代表取締役。われわれ昌友会の会長も務めていただいています。京都を世界一の「試作加工集積地」にすることを夢見て「京都試作ネット」を結成されるなど幅広い活躍をされていますが、これからの中小企業の在り方などについてお話しをお伺いしました。
不況とリストラの嵐が吹き荒れています。既に完全失業率も5%を超え、給与カットと転籍という名の片道切符が大手といわれる企業でも、リストラの手法として用いられるようになりました。言うまでもなく、リストラは企業の業務形態や生産手段、管理構造を再構築(リ・ストラクチャー)するもの、けっして働く者の首を切ることではなかったはずです。企業の構造を改革し余剰人員を再配置する中で、結果としての人員整理もあるでしょうが、それはあくまで結果であって目的ではないはずです。
企業の収益を守るための安易な「構造改革」は、働く人間の意欲を奪い、人としてのプライドを奪い、ひいては私たちが住む町の活気を奪い、地域の助け合いと慈しみの心を奪うことにつながります。これは、私たちが住む町から“安全と住みやすさ”をなくし、文化や伝統といった先人たちが築いてきた歴史までも危うくします。
この改革と不況の中で、私たちは従業員の仕事の確保と、何よりも“人としての誇り”を守り、“企業としての地域への貢献”を目的に『京都試作ネット』を立ち上げました。ここに集まったのは、伝統として培われてきた“ものづくりのハート”をもった、最新の技術・設備を駆使して創る『試作加工』のプロ集団です。京都の伝統産業のほとんどは、分業しながらその道に精通したプロが自分の工程を受け持ち、職人として責任を持って仕上げ、次の工程に手渡し完成させていくという形態で作られてきました。その一つひとつの工程が専業者として独立しています。このような土壌で京都のものづくりは、磨かれ鍛えぬかれてきました。
私たちのものづくりの心は、手作り・個づくりで今も同じです。研ぎ澄まされた『職人』としての感性で、顧客と対話しながら顧客の要求を汲み取り、そして言葉とビジュルアル化を通して要求以上のものを創り上げる。そんな京都のものづくりの伝統を受け継ぎ、発展させます。『一社ではできないが、連合することで知恵を出し合い、顧客に新しい価値を提案する。』『試作という高度なものづくりを通して、携わる人々に人としての成長の場を提供する。』が合言葉となり、地域の雇用を生み出し、地域で生きる元気な企業を目指しています。

中小企業は、地域の生活と密接につながりながら事業を行っています。グローバル化は避けて通れないものの、自ら海外へ出ていくわけにはいきません。これからも地域の文化や生活を守るためにも地場にとどまり、雇用の確保と拡大に努めることが大きな使命だと考えています。
『試作』は新たな産業を見出すための重要な情報源となります。優秀な人材による総合的な知恵が『試作』を可能にします。このことを通して、幅広い産業との連携を深め、次世代へと技術と共に文化の伝承ができれば素晴らしいことだと考えています。これからも思いを同じくする仲間を増やし、さまざまな知恵を集合する集団づくりを行い、地域に貢献していきたいと考えています。

皆様には、お揃いで新春をお迎えのこととお慶び申しあげます。
日頃、皆様方には温かいご芳情を賜り、厚くお礼申し上げます。
とりわけ、昨年の夏には、例年にない酷暑の中、皆様方お一人ひとりが言葉に表せないほどのご支援と盛夏の太陽にも勝ち、ご高配をいただきました。お陰をもちまして、京都市内並びに府内全市町村、すべて最高得票を頂戴し、三期目の当選の栄に浴することができました。私もこの度、自由民主党の人事局長並びに京都府支部連合会長という党の重責を担うことになりました。皆様方の温かいご支援のもと、我が国の発展と郷土京都の発展のため、全力を尽くす決意でございます。
さて、この世紀変遷の中、我が国の社会情勢も、多様な分野で大きな転換期をむかえております。特に雇用不安をはじめ厳しい経済状況に加えて、国際テロや狂牛病問題等々、内外を問わず、多難な課題が山積しております。一方、国政におきましても、これらの諸課題に対応すべく、昨年末には「第153回臨時国会」が開催され、「テロ対策特別法案」をはじめ深刻化する経済情勢への対策としての「第一次補正予算」や、「雇用対策」「中小企業支援のための法案」等々が審議され、成立したところであります。
特に、私たちの京都は、日本を代表する最先端技術を有する企業がある一方で、歴史と伝統を継承する様々な中小企業が経済を支えております。このような京都の活力を充実・発展させるためにも、雇用対策や中小企業のセーフティネットを、より一層確かなものにしなければならないと考えております。
京都府におきましても、それぞれの各首長さんが先頭になって活力ある街づくりのため、努力されております。今後更なる発展のため、私も荒巻知事、桝本市長、西田昌司府議会議員の方々と緊密に連携しながら、皆様方のより良い生活の安定と向上のため、一生懸命頑張ってまいる所存であります。
どうぞ、これからも変わらぬ、ご理解とご支援を賜りますようお願い致します。皆様方の一層のご健勝とご隆盛を祈念申し上げまして、新年のご挨拶とさせていただきます。
瓦の独り言
羅城門の瓦
新しい世紀になり1年がたちました。昨年の米国テロ事件以来、世の中が沈みがち、『もの』は売れず、何をどうしたらよいのかわからない。「わからない」と答える人の方が、普通の人なのです。「普通でいればよいのでは」と、申し上げたい。
高飛車にIT化を叫び、パソコンと携帯電話業界は、60歳を越えた人達までもターゲットにしていました。一方「あれは目を悪くするからやらない」と拒否できるのは信念を持った人。定年になったからといってパソコンを学ばねばならないことはないはずです。
新しい時代の空気を満喫するのも大切なことです。しかし、ワープロが使えないと時代遅れになるというのは偏った考え方ではないでしょうか。日本では昔から偏った考えより、中庸といったバランス感覚を取ることの大切さを教えています。この感覚がとれた「普通の人達」の集団がこれからの日本を支えていくものと思っております。
ITにのめり込み、上っ面の情報を追いかけているよりは、一つのことを深く掘り下げて勉強するのもいいのではないでしょうか。コンピュータに出来ないことを追求してみてはどうでしょうか。それも普通のことがたくさんあるはずです。メールでの意思伝達ではなく、便箋に日本語で手紙を書く。
そういえば、日本語をまともに喋れない、漢字すらろくに読めない青年男女に日本語を教え、日本文を書かせる訓練をしてみるのも良いのでは。確か、第二次世界大戦前までは青少年に対して『綴り方教室』・『話し方教室』という講座が設けられていたはずです。
さて、普通でいようとする貴方。今年の年賀状は何で出しましたか? パソコン? プリントごっこ?・・・・・・
さて、返事の一枚だけでも良いから筆で書いてみてはどうでしょう。かつての普通の年賀状に戻って・・・・・・。
さあ、瓦もこれから返事のために墨をすろうと思います。返事相手の顔を思い浮かべながら。
編集後記
昨年のNHKで二つ好きな番組がありました。「プロジェクト・X」は逆境を乗り越え、パイオニアスピリットに溢れた男達の生き様が描かれています。もう一つ「北条時宗」がありました。命をかけて日本を守ってきた男の生き様です。未来を支えこの日本の誇りとなる人達が、きっと今も奮闘してくれているに違いないと熱くなりながら番組を見終えるのが常でした。
編集室 松本秀次

さる9月11日アメリカで起きた同時多発テロは、世界中を震撼させました。私はこのテレビニュースを台湾高雄市のホテルで見ました。その時、台湾の次代のリーダーである馬英九台北市長(国民党 ハーバード大留学)や謝長廷高雄市長(民進党 京大留学)をはじめとする方々と積極的な交流をするために、私は京都府議会日華親善懇話会の会長として、10人の議員と一緒に台湾を訪問していました。
次の日の新聞には、「真珠湾的自殺攻撃」という大見出しが踊っており、アメリカのニュースなどでもパールハーバーという言葉がよく使われています。しかし、私は、今回のテロと真珠湾作戦とはまったく違うものだと思います。アメリカにとっては、自国の領土が他国民に攻められたという意味で、また「奇襲」という意味で、真珠湾と似ているかもしれません。しかし、真珠湾作戦は、軍事施設の破壊を目的としたものであるのに対して、今回のテロは市民社会を直接狙ったものであり、その意味では、アメリカ自身が行った原爆投下や都市への大空襲のほうが、本質は似ています。かつての日本軍の特攻と同じように、捨て身の自殺攻撃ということが日本を思い出させ、奇襲という意味で真珠湾作戦が取りざたされているだけで、まったく違うのです。このことを日本人として、認識しておくべきです。日本人がこのような無差別殺人をしたことは、歴史上ありませんし、そもそも日本人の価値観と相容れるものではないのです。
さて、このテロの原因についていろいろ取りざたされていますが、いかなる理由にしろ一般市民に対する無差別殺人は肯定しようがありません。日本はアメリカの同盟国として、また、私たちの価値観に基づいても、断固とした態度でこれに対処しなければなりません。
ところが、マスコミの中には、報復反対という意見も報じられています。その理由として、アメリカにもその責めがあるのではないかとか、日本が戦争に巻き込まれる恐れがある等々が報じられています。私はこの考え方には、到底賛成できません。確かに、暴力反対や反戦平和という言葉は、理想としては正しいかもしれません。しかし、現実問題として、世界には暴力や戦争が存在するのです。あの一瞬にして何千人の市民が殺されてしまう様子を目の当たりにしながら、この言葉を吐く人の神経を疑ってしまいます。自分の家族がこのような目に会って、この人達は同じ言葉が言えるのでしょうか。戦後半世紀、日本は世界でも例外的に平和な社会を築くことが出来ました。現実の戦争と全く無縁でいたため、戦争というものが存在することすら意識せずに暮らしてきました。そのために、現実にある戦争や暴力を、如何にして無くしていくかという思考が出来なくなったようです。そして、あってはならないものは最初から無いものとして考えてしまい、戦争や暴力があるという現実には目を向けずに、現実逃避の中で暮らす癖がついたようです。
しかし、これは、日本が自国の防衛ということすら考えなくてもいい冷戦時代だったから通じたことで、これからの時代では通用するはずもありません。そのことは、10年前の湾岸戦争を思い出せば分かります。イラクのクウェート侵略という暴力に対して、世界中が立ち上がったときに、日本は何をしたのでしょう。戦争に関わるのは絶対反対とういう世論に押されて、お金だけ出して済ませてしまいました。その結果はご存知の通り、日本は世界中から、「自分のことしか考えない利己主義者」として、物笑いの種になったのです。現実を直視できない利己主義では、国際社会の中では認められません。このことを日本は教訓としなければなりません。
しかし、今回の事件は、アメリカと協調して国際テロリズムと対峙するということとは別に、日本人として考えさせられる面があります。アメリカの唱えるグローバルスタンダードに対して、私は以前から異論を唱えてきましたが、今回の事件はまさに、イスラム過激派からのそれに対する反撃であったことは事実です。元々、今回の首謀者と目されるビンラディンなる人物は、ソビエトのアフガン侵略に対してアメリカと一緒になって戦った人物です。それが、冷戦が終わってソビエトが無くなってから、矛先がアメリカに変わったのは、何故なのでしょうか。
冷戦時代には、共産主義との対決という大きなタガがはめられていましたが、それが崩れた途端、冷戦時代には隠されていた、民族問題や宗教問題が世界中のあちこちで噴出してきたということです。ユーゴスラビアでのコソボ問題も、インドネシアの東チモール問題も同じことが言えるでしょう。つまり、世界中が今、「自分たちは何者か」という問いかけを始めているということなのです。自分たちには自分たちの歴史や文化、宗教がある。それを抜きにして今の自分たちの価値や存在意義を語れない。自分たちのこれからの幸せは無いということなのでしょう。
冒頭申し上げたように、私は訪台で、多くの台湾のリーダーと懇談の機会を得ました。その中で感じたのは、台湾もまた、「自分たちは何者か」と言う問いかけをしているという事実です。以前は、台湾も大陸の共産党と対決してもう一度大陸を取り戻すということが、政治目標でした。中華民国を建国した孫文の後継者である蒋介石にとって、台湾は大陸反抗の砦であったのです。しかし、蒋介石が大陸から台湾に来る以前から台湾は存在し、人々は生活をしていました。台湾では人口の8割以上の本省人(台湾生まれの人)に対し、2割に満たない外省人(大陸出身の人)がいます。今までは冷戦時代の共産主義との対決の中、外省人の国民党が中心となって、台湾の政治経済を牛耳ってきました。しかし、冷戦が終わり(勿論、大陸の共産党が滅んだ訳ではありませんが)、本省人を中心に「自分たちは何者か」と言う問いかけが始まったのです。大陸とは違う自分たちの歴史や文化があるということに気付き出したのです。
台湾では、初めて選挙で国民党の李登輝総統が誕生しました。その引退の後の選挙では、民進党の陳水扁総統が選ばれました。彼らは二人とも本省人です。台湾では今、国民党、民進党、国民党から分れた新党など、国民党の一党支配の時代から様変わりしています。これらの政党は政治的に色々な対立があるようですが、一番大きな問題は、台湾とは何かということのようです。今までは大陸の歴史しか教えてこなかったものが、台湾の歴史を学校の中で教えるようになったと聞いています。

こうした世界の動きを見るとき、私たち日本人が置かれている状況が見えてくるのではないでしょうか。「日本人とは何か」こんなことを考えなくても良いほど、日本人は非常に安定した社会を築いてきました。これは世界史上でも例のないことです。先の大戦に敗れた後、日本人は自らの歴史を封印して暮らしてきました。
文化や伝統を守るべき立場にあるはずの自民党ですら、共産主義との対決ばかりが政策の柱になり、歴史を守ることには非常に消極的だったのです。これも冷戦時代の世界各国に共通することです。ところが冷戦が終わって見えてきたものは、反共の盾としてアメリカと付き合ってきたつもりが、逆にアメリカ的思想に日本の文化が侵され、日本の姿が見えなくなってきたということではないでしょうか。
そこで、もう一度、日本の歴史を日本人として見つめてみようという動きがあちこちで出てきています。「新しい歴史教科書」を作る会、戦後生まれの私が、毎回このShow youで論じてきていることもそのひとつです。まさに冷戦後の世界に共通する「自分さがし」の運動と軌を一にするものです。こうした世界の大きな歴史的転換点に、今我々は立っているという認識が、一番必要なのではないでしょうか。

廣森日出夫さん
山口県出身。昭和23年6月14日のお生まれ。
本業は有限会社パイ研究所代表取締役。普段は企業向けに食品衛生検査、指導を業務とされています。社名のパイ(π)とは、生命水の「パイウォータ」や人々の輪が広がる「乾杯」から名づけられたということです。「新しい歴史教科書」を作る会京都支部長を歴任されたご経験から、教科書を通じて広くお話をお伺いいたしました。
子供達の叫び
『私は日本人に生まれるんじゃなかった。侵略戦争や慰安婦の問題。私のお祖父さんやお父さんはそんなことをしてきたんだ。歴史を学ぶほど自分まで否定せざるを得なくなってしまう。』
こんな言葉を女子中学生から聞きました。それがきっかけで教科書を読む機会を持ちました。今から3年前のことです。
作られた悲劇
私も他の父兄と同じで全く教科書に関心はありませんでした。読み出すと実にひどい内容が書かれています。小学校の教科書にも慰安婦のこと、戦時中の日本批判ポスターがさも事実のように記述されていたり、掲載されています。小学生にその様な事が理解できるはずもありません。
慰安婦問題は10年程前から、韓国や中国・東南アジアに働きかけた日本人がいて補償問題に仕立て上げられ今日に至っているのです。また新聞社も煽動してきました。
国籍不明の教科書たち
日本の歴史書籍を読むと実に面白いんです。その時代その時代の日本人の知恵や生き方、息吹がそれぞれの意味付けを通して伝わってきます。現在の多くの視点で見るとそれが伝わってきません。例えば8月15日は多くの日本人にとっては悲しい一日で、戦争に敗けて喜ぶ人はいなかったはずです。しかし多くの教科書では8月15日に「解放されて喜ぶ市民」という韓国の写真が掲載されています。これではどこの国の教科書かわかりません。勿論、日の丸の表記も無ければ君が代も載っていません。「新しい歴史教科書」が今までの本とどこが違うかと言えば、それは日本の視点に立って記述していると言う事なのです。
過去の思い出に迷走する知識人
確かに過ちを犯したことも有ります。しかし物事には必ず両面があります。インドやトルコでは今でも欧米列強に対し開戦した日本に理解と敬意を表しています。だから色々な教科書があっていいのだと思います。
ただ、「新しい歴史教科書」に対する脅迫やマスコミの偏った報道がありました。それは「正義=反権力=マルクス・レーニン主義」という青春の呪縛から未だに解き放たれていない人たちが、他の教科書出版社やマスコミの中にいかに多いかという現れなのです。
新しい公民教科書
同時に「新しい公民教科書」が検定を受けました。今まで「自由・平等・権利」を社会の主体としていましたが、義務をより明確に記述しています。例えば子供には一般的な「人権」は当てはまらないと思います。子供にあるのは「特権」なんです。だから罪を犯しても大人と同じではないし、親には養育の義務があります。これを人権・平等だけで考えると大人も子供も対等になり、家庭も教育も成立しなくなってしまいます。親子には上下関係があります。家庭の次に地域社会があり、国がある。そして「公」という考えが必要になります。この時「公」という考えがないと単に私利私欲の権利の主張に終わってしまうのです。また「公」を支えるには国民の歴史に根ざした「道徳心」が必要だということを述べているのです。
世界は待っている、日本人の感性
世論はだんだん変わってきています。日本人には誇りが必要になってきます。「地球市民」や「グローバル化」という言葉がありますが多分これからも実態は伴わないでしょう。むしろ今、日本人が世界に貢献できるのは「和の心」・「自然の中で人は生かされている」・「全てのものに神々が宿っている」など、歴史に根ざした「道徳心」や民族としての「感性」を持って外国と協調していくことなのです。公害や自然破壊が世界中の問題になればなるほどそういったものが世界から必要とされる時代になってくるでしょう。その時日本人は自信を持ち行動を伴う決断をしてゆくことが大切だと思います。
誇り高き子供たちを世界へ
3年後には小学校にも新しい教科書が生まれます。いくら教科書が変わっても先生方が変わっていただかないといけません。現在、教員の方々を交えて月1回の勉強会を行っています。実践される先生方を微力ながら応援していこうと思います。
誇り高き日本人として世界のために貢献できる子供たちを今私たちが毅然と支えてゆくことが必要だと思います。

今年ほど、教科書の採択に世間の耳目が集まったのも珍しい。
曰く、「自虐史観」。曰く「皇国史観の再来」。 私のような”教育音痴”にも、マスコミや政界を巻き込んだ論争が、毎日のように聞こえてきた。でも、其々の立場の論議を聞くほどに、私の頭は混乱した。
「アジア諸国への適正な配慮」これは、その通りだ。
「自国の歴史と伝統に対する尊敬と自信」これこそ、必要だ。
ますます、頭は混乱した。”史観までも分からないが、何故、この二つは対立する必要があるのか”と。
ここは一度、子どもにも意見を聞かずばなるまい。
「う~ん。学校の勉強やしね・・・。」
「まあ。歴史の事実は一つでも、歴史の真実はいろいろあるしね。」
どうも樋の子は、一つの「史観」にはこだわってないらしい。
それどころか、学校の勉強を割り切って考えているらしい。その上、親の論点を外すのがうまい。(親とは学校の話をするのが、うっとうしいと思っている。)
ここは踏ん張って、親の考え方というものを教えねばなるまい。
「天皇制は。日本の憲法は。グローバル化とは。」
どうも論点がかみ合わない。樋にとっては”日々の出来事”でも、子供にとっては”勉強の文言”らしい。どうも、日頃の生活とはかけ離れた「机の上の知識」らしい。
「日本の文化や伝統は、自分達の生活そのもの。食生活の中にもある。」
「夕日に感動するのも、日本人としての宗教感情が後ろにあるからこそ。」云々。
(うん。久しぶりに親の威厳を保っているぞ。)
横で、「友禅染めの着物をきたら、伝統を感じるかも・・・。」
樋の嫁さんも要らんことを言う。
今ごろの子は皇后陛下を「美智子さん」、皇太子殿下を「皇太子さん」と”さん”づけで呼ぶ。テレビでよく見る「皇室の人々」らしい。そういえば、アナウンサーまでもが「美智子さん」と呼んでいた。”身近に感じる”ことと”尊う”ことは別と気色ばんでも、埒があかない。親よりはテレビの方に、影響力があるようだ。
これは互いの「考え方や感じ方」も、話し合ったほうがよさそうだ。
そういえば、人がものごとを認識する時には、知識を知識として、その通りには受け入れないと聞いたことがある。知識は、受け入れる人の感性で脚色されるそうだ。自分の中に取り入れられた知識は、人と同じようでも自分なりの価値観や経験で編集されるらしい。そうか、知識そのものではなく、その与え方が問題ということか。
日頃、家で親が話しているものの見方や、子供の経験からくる感じ方のほうが、子供には影響するらしい。
「三つ子の魂百まで」とはよく言ったもの。子供には手遅れでも、せめて孫への躾の練習に、今から子供に「ものの感じ方」を話そうか。

みなさんこんにちは、先月より西田事務所で働いています杉尾巨樹(すぎおひろき)と申します。新しい環境に未だ右往左往する毎日を送っていますが、何事にも新鮮な気持ちで取り組み、前向きに頑張っていきたいと思っております。
私は同志社大学在学中に「政治学研究会」というサークルに所属していまして、西田先生とはこの研究会で、自民党の若手議員との交流会という企画を通じて知り合いました。実は私はそれまで政治家に対して不信感を抱いていました。しかし、自民党の若手議員の皆様との真剣な議論や政治に対する熱意に感激しました。中でも、現在日本がこのような閉塞状況に陥っている状況を的確に分析し、次の時代での役割を「保守」という方向性でわかりやすく解説された西田先生のお言葉には特に心打たれるものがありました。
それが縁で学生時代に西田先生が局長を務める自民党青年局の学生部に所属しておりましたが、在学中には学びきれなかったものを西田先生の間近で学ぶべく、一念発起して先生の下に押しかけて来た次第です。
まだまだ半人前で事務所の皆さんや、後援会の皆様の足を引っ張ってばかりおり、先生から毎日一回はピシャリとやられていますが、学ぶことの多い充実した日々を過ごしています。「杉尾巨樹」が一人前になれますようご指導ください。よろしくお願い申し上げます。
杉尾 巨樹
------------------
政治に関心のある学生は、あまりに野心が強すぎて私と相容れないことが多い中、杉尾君は現代稀に見る純粋で心優しい青年です。今後とも私同様の御指導を賜りますことをお願いいたします。
西田昌司
編集後記
先日近所のお寺を散策しているときに境内に上ろうと、うしろ向きで上履きをぬいだところ、ある婦人から「京都では履物を脱いだ後に手で向きを変えるのですよ」と教えていただいた。
私の郷里鹿児島では家に上る時は背後に敵がいるかもしれないということから、外を見て靴を脱ぐように躾けられたことを思い出しながら、また一歩京都に近づけた気がしました。

私は、連日の街頭演説や昌友塾など、いろんな機会に「教育の本質は、親が子供に伝えるべきものは何かということを考えることだ」と偉そうに述べてきました。しかし、これは中々難しいことです。まず、何を伝えるべきかという内容も大切ですが、それを伝える方法のほうがもっと難しいことを、自分自身、子育てをしながら痛感しています。「素直」「正直」「勇気」「優しさ」など子供に伝えたいことは沢山あります。どれも、目に見えるものではありません。「ほらこれが勇気だ」「これが素直さだ」と子供に手を取って教えることなど不可能です。それだけに、子供に伝えるには、親が自分の生き方で子供に示す以外に方法がありません。逆に言えば、子供によって「親になる」「一人前の大人になる」教育をされているのだとさえ思えます。
つまり、目に見えない大切なものを教えることが、教育の基本であり、それが子供を教育すると同時に、自分自身をまた教育するということなのでしょう。このことに気付いたとき、私は、「自分の両親はよく私たち四人の子供を育てたものだなあ」と感心すると同時に、感謝の気持ちと自分の未熟さに恥じ入ったものです。そこで、今回はそうした思いから、私の父について述べてみることに致します。
私の父、西田吉宏は、参議院議院をしています。私が、府議会議員になったこと自体、父の参議院転出に伴うものですから、私の政治家としてのスタートからして、父の影響をまともに受けています。
私が、父のことで一番よく覚えているのは、昔はまだ父が議員になる前、私が小学生の頃の話です。その頃、父は養鶏場を営んでおりました。私たち四人の子供のほかに、祖母や、叔父叔母が一緒に住んでおり、食事の時などは競争も激しいものでしたが、大家族の賑やかさ、楽しさのほうが印象に残っています。
祖父が病気がちであったため、父は、小学生の頃から家の手伝いをしていた話を私たちによくしました。小学生の私に自分が、お前ぐらいの年には、千本今出川まで自転車の前と後ろに籠をぶら下げて、一日に二回も卵の配達をしたものだ。」「野球が大好きで、友達と遊びたかったけれど、家にかえってきたら病気で寝ているおじいちゃんに、そんなことをして遊んでいる暇は無いと、寝床からものさしで頭をたたかれて怒られた。お前たちは幸せやな。」ということを何度も聞かされました。

父は、戦後大勢の復員者もあり、狭き門だった洛陽工業高校の電気科に入学をしました。そして、エンジニアを夢見るのですが、祖父の病がいよいよ悪化してしまい、授業料が払えなくなり二年の途中で退学せざるを得ませんでした。しかし叔父たちには高校だけは卒業しておけと、みんなを学校に行かせ、一番下の叔父は大学まで行くことが出来ました。「自分は勉強したかったけれど、出来なかった。お前たちはしっかり勉強しろよ。」とよく言っていました。
父はよく、「自分は学歴が無い。でも世の中の大切なことは大学を出た者よりわかっている。」と、お酒を飲んだときに言っていました。とても悔しそうでした。また、「お前は大学を出たからといって偉そうなことを言うな。」とよく叱られもしました。そうしたことが父のエネルギーになったことも事実です。とにかく負けてなるものかと、一生懸命に働きに働き、二十歳代半ばで三つの養鶏場を経営する、京都でもひとかどの養鶏家として知られるようになりました。
父が議員になってからは議会の話もよく聞かされました。「共産党がなんぼ福祉の話をしても、自分のほうが貧乏人の苦労はよく知っている。」「人を助けてあげるだけではダメだ。自分で生きられるようにしてあげるのが本当の政治だ。」このことを口癖のように言っていました。
養鶏場を営んでいるときから、知的障害児の方が職親として生活の自立を支援し、国会議員になってからはその親の会に当たる「京都手をつなぐ育成会」の会長も努めてきました。まさに父は、自分の考える福祉を実践してきたと言えるでしょう。
父が一番苦しかったのは、祖父が死に、姉(伯母)が心臓弁膜症で死に、一番下の小学生の弟(叔父)が腎臓摘出手術をするなど、家族の不幸が続いた二十歳前後の頃でしょう。祖父が老人性結核で寝込んでしまってから、父は文字通り一家の大黒柱として働いてきました。健康保険も無い時代です。一本一万円もするストレイプトマイシンを毎週父のために買っていた父は、ある日お医者さんに呼ばれてこう言われたそうです。「気の毒だけれど、お父さんはもう治る見込みがない。君には幼い弟たちがいるじゃないか。その子らのためにこのお金を使いなさい。」と。父は「一番下の弟はまだ、幼稚園です。一日でも長く父親と暮らさせてやりたい。どうか一日でも長く父を生かせて下さい。」と頼んだと言いました。
私はこの話を聞かされるたびに、涙が出て止まりませんでした。今もこの話を書きながら、泣いてしまいます。父の原点はまさにここにあるのだと思っています。
私が生まれたのは、こうした不幸が終わってからの時代です。別段苦労もせずに大きくなりました。でも、こうした父の体験は私の中では自分の思い出の一部のような気がしています。
養鶏場を営んでいた頃は、今から考えても、よくこれだけ始末できたものだというくらい質素な生活でした。毎日のおかずは、かしわと卵。しかしこれは、商品価値の無いひねたかしわで、いくら噛んでも噛み切れないほど硬いものばかり、卵は割れていたり、殻の無いものばかり。ご飯も麦ご飯。鶏の餌に料亭から魚のあらを貰ってくるのですが、その中から失敬して私たちの夕飯が出来上がるのです。ですから食費は殆ど使ったことが無いんじゃないかと思うほどでした。それでも不思議に、貧しいという思いはありませんでした。ただ、小学校の家庭科の時間に、本日の献立を書くのが恥ずかしくて、見栄を張って別のおかずを追加して書いたことはありましたが……。
今年の正月でしたか、久しぶりに家族がそろって食事をしていたとき、私が、子供達の贅沢三昧をみて「お父さんもあらを食べて大きくなったんだぞ。これが当たり前と思うなよ。」と言ったら、父は、「お前があらを食べて育ったことを、子供に言えるようになったんだな。」と喜んでいました。
平成元年の参議院選挙のとき、これは父の政治生活の中で一番の危機でした。リクルート事件や、反消費税の嵐の中、自民党への支持率は最低の状態でした。さすがの父もこのときばかりは「もうやめたい。」と私たちに弱音を漏らしたことがありました。しかし、いったん選挙になってからはそんな弱音は一切出しません。まるで何かに取り憑かれたかのように、一心不乱で戦いつづける父の姿は鬼気迫るものがありました。「自分が負けようが、死のうが構わない、自民党の議席を失ってしまえば、日本はどうなる。府民、国民に申し訳ない。」まさに決死の覚悟を父の後ろ姿に感じました。
いつの時代も必死で全力で生き抜いた父の姿は、敗戦から経済成長に至る戦後日本の姿と二重写しに思えてきます。バブル崩壊の閉塞感に包まれた今の日本に必要なものは、自らの人生を切り拓いて行く父のような気概と、バイタリティーであると信じています。私も自分の生き方を子供に伝えることの出来る、そんな親になりたいと努力しています。

西田昌司密着レポート No.2
去る6月5日京都テルサ大会議室で、約300人の方にお集り頂き、第二回西田昌司演説会が開かれました。参加された皆様に心より感謝申し上げます。会場から熱気のこもったたくさんの質問を受け、西田昌司本人も大変感激しておりました。
講演について、前回に引き続き京都大学経済学部三年の稲村亮(前回稲森亮と記載がありましたが、稲村亮の誤りです。失礼しました。)君にレポートをお願いしました。なかなか鋭い質問をしていますが、これらの質問は、次回以降の昌友塾でお答えしたいと思います。
第二回西田昌司講演会に参加して
京都大学経済学部三年 稲村亮
「構造改革とはなにか。」今回、西田昌司先生はこの題で講演をされました。しかし、小泉内閣(や民主党)が掲げる「構造改革」と昌司先生の言う「構造改革」はかけ離れていますので、それを前置きして言っておく必要があったのではないと思いました。
小泉内閣のかかげる「構造改革」は、財政のスリム化、規制緩和、そして郵政民営化など、政府をいわゆる小さな政府にし、民間の活動を活性化させようという、どちらかと言えば市場主義的な国家を目指すものであります。一方、昌司先生がやるべきという経済政策は、不況下、民間の活動が不活発な中、やはり財政出動を行って需要を喚起しようという。大きな政府によるケインズ的な政策(財政・金融政策により民間需要を喚起させようとする政策のこと)であります。その違いに言及しないと、演題を見て訪れた聴衆が「構造改革」について混同する可能性があると感じました。
さて、昌司先生の話そのものの内容は、非常に分かりやすいものでした。特に、現在の不況についての説明であります。今、デフレ(特に資産デフレ)が問題であること、日銀が量的緩和や低金利政策を行っているにもかかわらず市場に資金が回らないのは、不良債権の問題と、バブル期から見て今は土地の価格が10分の1にまで値下がりして担保不足が起こっているために、銀行が融資をしないこと、それによってさらに土地の値下がり(=デフレ)が進むこと……。こういった不況下における悪循環を、例えを使って語ったのは、非常に分かりやすいものでした。また、国債の金利が低い今こそ、国は国債を発行して、景気対策をすべきだというケインズ的な政策の根拠も非常に分かりやすかったと思います。
しかし、いくつかの疑問点の私には想起されました。
1. 国債の発行に対して、国民は結構不安を持っているという点。将来、増税の不安があるのであれば、景気は浮揚しないのではないかという点。また、社会契約的な考えが日本人の間に広まっているので、負担に対し、受益がどれだけあるのか、すなわち、ある世代は受益が多く、ある世代は負担が多いというアンバランスに対して、日本人は反対なのではないかということ。
2. 国債の金利は低いというが、それは危険な均衡の上に立っているのではないかという点。資本市場で株価が伸びないために国債需要が増えたり、企業の資金需要がないために、銀行が国債を買って資金を運用しているから、国債の金利が低くなっているのではないか。だから、資本市場の変化で国債金利が上がる危険性があるのではないかということ。政府による需要喚起政策は、どのように行うべきなのかという点。一般財源を使うのか、財投を使うのであれば、政府系法人以外にも融資を行うのか。また、従来型の公共事業をするのかということ。それが、どの程度産業連関効果をもつのかということ。
3. 外資が入ってくるのは危険というが、もう既にだいぶ入ってきているのではないかという点。また、危うい日本企業の元で人員削減がなされるより、健全な外資によって雇用を吸収してもらうほうがよいのではないかということ。
以上のような疑問が生まれたわけですが、時間の都合等で、そのあたりへの言及はありませんでした。またの機会にお答えいただきたく思っております。
私の感想は以上です。政策の方向としては、どれが素晴らしいのか、私は分かっておりません。自ら意欲を持って勉強することが、「思考停止」に陥らないことではないかと思っています。

また、あってはならないことが起こった。朝、「行ってきます。」と元気に家を出た子が、夕に骸になって帰って来る。それを迎えねばならない親の無念さを想えば、ただ、涙することでしかこの気持ちを表せない。
人の生命をいのちとも思わない、何故このようなことが出来るのか。容疑者の持つ特異な性格ゆえか。その生い立ちが問題か。教育が悪いのか。日本の社会がここまで来てしまったのか。いや、どうもすっきりしない。 容疑者は二つの大罪を犯した。
一つは、八名の子どもを殺し、十数名を傷つけたこと。二つ目は、詐病することによって病気に立ち向かっている人とその家族を傷つけていること。先の問題は、裁判所に委ねよう。しかし、後の問題は、私たちの地域社会がもつ相互扶助のつながりをじわりじわりと侵食する。
或る高校生が「何故、お母さんは精神病にかかったんや。」と家で泣いた。長く、鬱病で治療を受けている母親は、それを涙を流して聞く以外になかった。この子は小さな時から、母親を気遣う優しい子だった。高校で事件が話題となると悲しさでいっぱいになるという。これは現実に起きている問題である。
私たちの社会は互いに助け合う機能を持つ。しかし同時に、身を守る余りに異質なものを排除しようとする働きも、悲しいかな未だに持っている。この働きをする原動力になるのが偏見であり、無知である。この偏見や無知は、「怖い」という感情がもたらす場合もある。付属池田小の事件の容疑者は、私たちが陥りやすい、この偏見と無知を利用して罪を逃れようとした。その上、闘病する人と家族を更に苦しめている。
いま、私は付属池田小の被害に遭われた子どもとご家族に何もすることができない。ただ、京の地でご冥福を祈るのみである。しかし、容疑者が犯した二つ目の犯罪に対しては、行動することができる。それは「精神病」を知ることである。正しい知識を知ることから始めようと思う。それが私の偏見と無知を少しでも防ぎ、私たちの地域社会を守ることにもつながるから。
私たちはハンセン病への無知と偏見から、人として生きる権利を奪ってしまった。それは、昨日のことである。病に自分が犯されるという恐れと無知が偏見を生み出し、自分たちの社会から隔離することで解決しようとした。この過ちは二度と繰り返すまい。私たちの社会が安全であるためには、己の無知と偏見こそ敵であると思うから。
編集後記
いよいよ参議院選挙です。政治家と共に有権者の見識が問われているような気がします。世の中をしっかり見つめて、しっかり選びましょう。

去る3月13日、自民党の党大会が日本武道館でありました。私も、自民党全国青年議員連盟の会長としてこの大会に参加し、大会のアピールの宣言をしてまいりました。しかし、今回の大会では、開会時点で一万人近くいた参加者が閉会時には三分の一くらいに減るなど、残念ながら党再生の起爆剤とするには期待はずれの内容となってしまいました。実は8年前、私は自民党がはじめて下野した時の党大会にも参加してきました。今回の党大会を見て、改めて8年前のことをダブらせながら、何故今日の自体に自民党が陥ってしまったのか、その原因を考えていました。
8年前、下野したとき自民党は、党の体質を根本から替えて党を刷新しようと皆が必死で考えていました。私も京都府連の青年部長として、党大会や全国青年部長局長会議に何回も出席し、党の改革を訴えてきました。このとき、皆がわが党のアイデンティティ(自分は一体何者なのかということ)は何かということを真剣に論議していましたが、それにはこういう理由があったのです。この時代には、日本新党やさきがけや新生党など自民党出身者が相次いで、政治改革を訴えて新党を結成しました。政策的には元々自民党の出身ですから、そう大差はなかったのですが、イメージがまったく違っていたのです。彼らは自らを改革派と名乗り、自民党は守旧派であると決め付けていました。清新な印象の改革派に対し、薄汚い印象の守旧派というイメージ戦略がマスメディアを通じ盛んに宣伝されました。そうしたイメージ合戦の中、自民党も清新なイメージの河野洋平氏を総裁に据え、イメージの回復に躍起になったものです。しかし、そんな付け焼刃ではなく本質論をしなければならないと、党本部に行くたびに私は訴えてきました。しかし、結局まともな答えはそのとき聞かされませんでした。そのとき、私が空しく感じた答えは結局こういうことでした。「自民党とは、共産主義や社会主義者ではなく、創価学会員でもなく、かつ、政権政党だ」ということでした。こうした状況では下野をして政治離脱をしてしまったら、もう何も求心力はなくなってしまうのも無理は無い話でした。次々離党者が相次ぎ、例年年末には来年度の予算陳情でごった返しているはずの党本部にも、訪れる人が誰もいなくなり、まさに党が瓦解してゆく姿を私は目の当たりに見てきました。あのままの状態がもうしばらく続いていたら自民党は間違いなく、解党になっていたでしょう。しかし、その代わり本来の自民党のあるべき姿というものを、もう少しきちんと議論を煮詰めることができたでしょう。
ところが、幸か不幸か自民党はまもなく政権復帰をしてしまったのです。社会党との連立という予想だにしなかった現実がおきました。そして今は、公明党との連立によって政権は成り立っています。先ほど述べました、「社会主義者でない」ということ「創価学会でない」ということは、もはや自民党のアイデンティティではなくなってしまいました。最後に残ったものは、まさに「自民党とは政権政党である」ということになってしまったのです。これでは自民党から求心力がなくなってしまうのも当然です。政権を守ることだけが使命では政治になりません。確かに政権を守り、社会の秩序を安定させることは大切なことには違いありません。また、私は、一連の連立政権を一刀両断に批判するものでもありません。しかしそれでも、最近のわが党を見ていて、政権維持以外に一体何のために政治をするのかという政党としての姿勢が、私には感じられないのです。結局8年前に下野したときからの、自民党とはなんぞやという問いに、まともに答えを出さずに政権復帰したことの付けが、今来ているのではないでしょうか。
では、その答えとは何でしょうか。私はこう思うのです。そもそも自民党の立党の精神は何であったかということです。昭和30年保守合同した理由は、「反共」「経済復興」「真の独立回復」の3点に集約されると私は思います。東西冷戦の真っ只中の当時、左右両派の社会党も合同し、社会主義者の一大勢力が出来上がりました。そうした状況下、日本を西側自由主義国の一員として、共産主義から守るということは当時最大の課題でありました。また戦後経済混乱の中、貧困からの脱出は国民皆の願いでありました。経済復興を成し遂げるためにも政権の安定は欠かすことの出来ないものでした。「反共」と「経済復興」は、その後も自民党の基本政策として受け継がれてきましたが、「真の独立回復」という問題はどうなったのでしょう。立党直後は憲法改正という問題も政治の課題になりましたが、その後は触れることも全く無くなり、むしろタブー視されてきました。その結果自民党の政策は、「反共と経済」のことしか語ることが出来なくなったのです。しかし今や「反共」も冷戦が終わった後の時代に、果たしてどれだけの意味があるのでしょう。また、「経済復興」も不況とは言え世界ナンバー2の国となった今、終戦直後の時代とはその重さが違います。今むしろ語られなければならない問題は、「真の独立回復」ということではないでしょうか。それは単に憲法改正というだけではなく、戦後を通じて日本中に蔓延している「思考停止」という病的状況から抜け出すということ、我々ひとり一人が自分で本当にものを考え判断するということだと私は言いたいのです。

例えば、日本党の最後に残ったアイデンティティは政権政治であることだと自嘲をこめて述べました。政権政党が野党と違うことは、現実の政治課題に対して、野党のような理想や空論ではなく、如何にして現実的解決の手段を見出すかということです。今の日本の問題点は、こうした戦後政治の抱える根本的問題に対して、未だ目をつぶり問題を直視しようとしない人が余りにも多すぎるということです。自民党が政権政党として今果たすべきことは、現実を直視するということ。そして現実の問題の解決の為には戦後の価値観に縛られること無く本質を議論してそのための解決方法を提示すること、これ以外ありません。
の中にはその言葉を言えば誰もそれについて反対したり否定したりすることが出来ない絶対的な価値観を示す言葉がたくさんあります。憲法という言葉もそうでしょう。平和、人権、自由、平等、民主主義などたくさんの言葉があります。しかし、これらの言葉はそれ自体も勿論大事な価値を持っていますが、平和を維持するためには現実には常に軍事力のバランスがあり、人権も決して普遍的ではなく、実は時代によって大きな違いがあったり、自由も平等も常に規則や格差との間のバランスが一番肝心の問題であったり、民主主義もこれが目的ではなく、あくまで人類が幸せに暮すための手段に過ぎないものであり、現実にはさまざまな問題をその後ろに抱えているものです。ところが戦後日本では、こうした言葉が話されると誰も文句を言えない、思考停止の状態に陥っているのではないでしょうか。政治にタブーを作ってしまい現実を直視したり、論議したりすることが出来ないような仕組みが世の中のあちこちにあります。そのことが今日の一番大きな問題です。このことをもたらした最大の原因が、戦後のGHQ支配の時から続いている、日本の伝統や歴史を否定する戦後の価値観による言論体制であることは申すまでもありません。我々は意識しないうちに、戦後の価値観の中でしかものを考えたり、理想を掲げたりすることが出来なくなっているのです。これではいくら議論をしても自分自身が本当に考えているのではなく、単に考えた振りをしているに過ぎないのではないでしょうか。
先に私は、自民 しかし、この道はすぐには多くの国民からは理解できないかもしれません。それは誰もが何も考えることなしに常識として考えてきた戦後の価値観に縛られることなく本質を議論してそのための解決方法を提示すること、これ以外ありません。
しかし、この道はすぐには多くの国民からは理解できないかもしれません。それは誰もが何も考えることなしに常識として考えてきた戦後の価値感に反旗を翻すものであるからです。しかし、それであっても、問題を解決するためには敢えて訴えるという覚悟と勇気がなければ、政権政党であるというアイデンティティももはや無くなってしまうのではないでしょうか。今自民党に必要なものはそうした覚悟と勇気なのです。このことを国民に示さずに首を挿げ替えても、自民党の再生は無いと思うのです。
西田昌司密着レポート

稲村 亮(いなむら・りょう)君(20歳、愛知生まれ富山育ち、現在京都大学経済学部) 今年2月より『議員インターシップ』として西田昌司事務所に来られています。議員インターシップというのは、普段の議員活動や議員を支える人々から社会勉強をしようというのが目的の活動です。彼はこの活動に参加するに当たり、1位:前原氏(衆)・2位:福山氏(参)・3位:鈴木氏(市)・4位:(思い出せないそうです)と、民主党議員を希望されていました。西田昌司議員に至っては第5位。願い叶わぬ出会いを稲村君が、どう捕らえたのか。府議会を傍聴したり昌友塾に参加してもらったり、SHOW YOU 編集室では、この機会に西田昌司議員を密着同行された体験・感想を、稲村 亮君に報告してもらいます。
《『西田昌司』取材日記》 稲村 亮
私は、2月の末から西田昌司議員のもとで、議員インターンという形で政治その他の勉強をさせていただいております。当初は、政党や派閥レベルで動く(少なくとも私にはそう見える)今日の政治において、政治家個人は何をやっているのかということが知りたいと思って議員インターンに参加しました。極端に言えば、政治家というのは無能で無知な人間ばかりなのではないかとも思っていたわけです。しかし、少なくとも昌司さんに関してはそれは当てはまらないようです。昌司さんの活動を見ていると、驚かされるばかりです。
まず感じたのは、よく勉強しておられるということでした。私も参加させていただいたものもあるのですが、昌司さんは、様々な方面で活躍していらっしゃる方々を講師に呼んでの勉強会や講演会を開いておられます。また、特に京都市南区などは中小企業が多く、経営者の方々とも交流を持って、意見を聞いておられます。そういった活動を通じて、多くの知識を得、自分の考え方に生かされています。政治家の表舞台といえば議会ですが、そんなものは生きた議論のない場であり、それよりも議会に至るまでの過程というのもが非常に重要で、生き生きとしているということを感じさせられました。
また、昌司さんの話を聞いていると、視野が広がるように感じられました。昌司さんは、戦後一般的となった歴史の味方とは対極にある、独特の国家観や歴史観をしっかりと自分の中でもっておられます。その内容は詳しく触れませんが、私にとってはかなり鮮烈なものでした。中には拒否したくなるところもありました。とにかく言えるのは、ひとつの事実でも、見方によって評価は変わっていくということでした。歴史に限らず、物事を様々な視点で見ることは重要です。他人の言うことをそのまま受け止め、鵜呑みにするのではなく、自らものごとを考え、学ぶという姿勢が重要であると自省も含めて感じさせられました。
さて、ここからは、西田昌司という人間について感じたことを書きましょう。昌司さんは、先に書いたように国家観や歴史観をしっかりと持っており、これから日本が国家としてどうあるべきなのかというヴィジョンへとつなげておられます。国家像という根幹がしっかりしているから枝葉となる経済や教育などの分野に関する主張も、論理的で説得力があるわけです。また、昌司さんははっきりとした方です。「日本人はYes・Noはっきりさせる性格ではなく、和の心だ」とおっしゃるけれど、一番はっきりしているのは昌司さん、あんただ。このようにはっきりとものを言う(日本人的ではない)人間には、下の人間もついていきやすい。この方はリーダーシップをとれる人だと感じさせます。こうした自分の国家ヴィジョンをしっかり持って、はっきり言うことができる政治家が国政にはいないように感じられるのが残念です。それでも、地方の若手にはいるという点が救いといったところでしょうか。
昌司さんの姿勢には感心させられることが多いです。私もその姿勢を見習って勉学等に精進していきたいですね。

今日もテレビで、日頃から殴打を繰り返されていた子どもの話が報じられていました。曰く、「躾で叩いたことがある」。また、新聞では、子どもにミルクや食事を与えず、死なせてしまった話が載っていました。曰く、「放置したのは事実だが、殺すつもりはなかった」と。先の話は暴力的虐待、後の話は養育の怠慢と放棄、ネグレクストと呼ぶのだそうです。だけど、これらに類する話が、最近とみに多いと思いませんか。
親が子どもを躾る際に叩くことはあっても、それを暴行とは呼ばないでしょう。
何か己の感情に任せて子どもを叱ってみたり、自分の不安のはけ口を子どもに向けたり、どうもその結果が、日常的な虐待に現れているように思います。そう言えば、子どもの存在を無視することもあるそうです。最近は「親の在り方」や「家族の在り方」、いや「親」自体の意味が変わってきたと思いませんか。
「もう、この子はだめだから、ミルクをやっても仕方がないね。」という会話は、どのような心情から出てくるのでしょう。幼い吾が子に食事を与えず、衰弱したその生命の灯が消えようとする時に、この会話が交わされたそうです。この「親」たちの心象風景には、吾が子や家族は、どのようなものとして描かれているのでしょう。そこには、人の温もり、母子のつながりの濃密さは感じられません。ちょうどペットのような存在、子犬の頃は可愛がるが、大きくなると捨ててしまう。そんな身勝手な家族像を感じてしまいます。これはもう、「親」と言うより「人の在り方」や「人間性」の問題といった方が適切かもしれません。
児童虐待については、様々な原因追求や分析がなされるでしょう。だけど、「両親への支援体制が不充分だった行政側にも問題がある」という議論だけには納得がいきません。むしろ、子どもを育てるという行為は自然の営みであり、人としての本来の生、人格に帰属すべき事項です。マニュアル化された文言で、行政や役所が口を挟むべき筋合いのものではないのです。
とは言え、子どもを産み育てるというのは、大変重要な大仕事です。ドアを閉めれば、近所付き合いもないというのでは、孤独感が増すばかりです。子育てには自身を失った時、叱り方が間違ったかなと思う時には、近所のお年寄りに聞くのが一番です。子育てのベテランと話すことで自身の回復にもつながります。少し扉をひらいて、無駄話をしてみませんか。最近は、井戸がないので“路端会議”などというのは、どうでしょう。案外と地域のつながりや家族の不安解消には、この無駄話が役立つのではないでしょうか。

いよいよ21世紀の到来です。小学1年生のお正月に指折り数えて、「21世紀には自分は42歳、父親より年がいっているんだなあ(当時、父は31歳)。一体何をしているのだろう。」と漠然と寝床のなかで考えていたことを思い出します。その当時思い描いた21世紀の姿は、まるで鉄腕アトムの漫画に出てくるような、夢のような世界でした。今振り返ってみますと、さすがに鉄腕アトムはまだ登場していませんが、一部はアトムに出てくるように、コンピュータや携帯電話の普及で素晴らしい情報社会が実現しています。こうしたことは、今後IT(情報通信技術)革命と称してますます発展していくことでしょう。しかし、それでも当時子供心に思い描いていた世界とはずいぶん違うと感じずにはおれません。一体どうしてでしょう。私はその違いというのは、未来に向けた希望の大きさの違いだと思います。子供と大人はそれだけで未来に対する希望も当然違うと思いますが、私はもっと根本的な違いがあると思うのです。それは世のなかの空気が当時のように明るく輝いていない、よどんだ閉塞感の中にあることが、その一番の違いだと思うのです。要するに「21世紀の到来だ。明るく豊かで希望溢れる社会の到来だ。万歳!」と手放しで喜べない何かが、世界を覆っているということを申し上げたいのです。
では、その閉塞感はどこから来るのでしょう。私はそれは「戦後体制」と呼ぶべき社会の仕組みだと思うのです。例えば、経済にしても日本は今厳しい不況の中にあります。国も地方も民間も皆、借金で困っています。これをどう立て直すかが問われています。そのための方策としてアメリカを倣って規制緩和を行うことが必要だ、それがグローバルスタンダード(世界基準)だとマスコミは大合唱します。しかし冷静に考えてみれば、見本となるはずのアメリカは株高で表面上景気は良い様に見えているだけで、財務内容は依然世界一の借金国です。一方、日本は世界一の債権国なのです。日本ではこれから赤字国債の返済をどうするのかということに議論が集中し、このままでは日本は沈没してしまうと騒いでいます。しかしこれは目先の問題に過ぎません。少なくとも日本は借金が多いとはいえ、自国の中でお金を用だ立てているのです。その上まだ余ったお金を世界中に貸し出しをして、一番日本からお金を借りているのはアメリカなのです。景気の良いはずのアメリカは、いくら儲けてもその稼ぎ以上にお金を使う浪費癖があります。そのお金が積もり積もってアメリカは自国のお金だけでは首が回らなくなっているのです。その浪費癖のお陰で、日本をはじめ世界の国は、ものを沢山アメリカに買ってもらって良いお得意さんだと喜んでいるのです。しかしどんなお金持ちでもこんな状態が続けば破産してしまいます。本当に改革すべきは日本の経済ではなく、アメリカなのです。そして日本がすべきことは、アメリカ依存体質を変えることなのです。世界と強調することは勿論大切ですが、背隠語の日本は対立を恐れるあまり、自国の経済を守るということがあまりに欠けているのではないでしょうか。
また、最近よく話題になる教育改革も同じことが言えます。21世紀教育の基本は「ゆとり」と「生きる力」だそうです。これは戦後教育の反省として、子供たちを受験中心の詰め込み教育から開放し、子供たちが家庭や地域で触れ合うなかで、生きる力を考えさせようということです。その方策が、学校週5日制であり、体験学習であるのです。これもまた本末転倒の議論です。何故なら、この議論には“学校は子供に何を教えるのか”という、根本的なことが抜け落ちているのです。それは子供たちに考えてもらおうというのは大人の詭弁に過ぎません。それを教えるのが教育ではありませんか。
戦後教育の問題点は受験中心の詰め込み教育にあったのではなく、こうした肝心の教えるべきことを教えてこなかったことにあるのです。それは何かと言えば、日本人として正しく美しく生きるための知恵、言い方を換えれば、常識や良識でしょう。それはこの国を守り、この国に生きてきた我々の先祖が営々と築いてきたもの、つもり伝統であり文化なのです。この中に日本人としての真・善・美の基準をはじめ様々な知恵が詰まっているのです。そもそも、どこの国でもその国に生まれ育つことにより、自然とこうしたことは子供に受け継がれていくものです。ところが、日本においうてはこうした当たり前のことが出来ない仕組みになっているのです。その原因は学校の中で日本人の精神的支柱を教えることをしてこなかったからです。それが戦後アメリカの指導下でつくられた憲法をはじめとする戦後体制に起因していることは周知のとおりです。
経済や教育をはじめ、ありとあらゆるところに戦後体制がはびこっています。今の日本の問題点は、こうした根本的問題には身を向けようとせず、表面だけの議論に終始してしまう政治やそれを助長するマスコミの姿勢にあります。そして、それをそのまま受け容れてきた我々国民の同じ罪を負っています。
先日、靖国神社に祭られている英霊が家族に残した手紙を見る機械がありました。もう明日は必ず特攻隊で死んでいくというのに、死に対する恐れなど微塵も感じさせず、ひたすら家族のことを思いやり、祖国の安寧のために自らの命を懸けるその姿に改めて触れた時、私は思わず「恥ずかしい」泣き崩れてしまいました。「日本の現在の姿を見て、英霊はどのように感ずるのだろう」「自分たちの行き方は英霊に対して顔向けが出来るのだろうか」こうしたことを考えた時、私は嗚咽しながら涙する以外にありませんでした。
いよいよ今年から21世紀の到来です。新しい世紀を迎えるにあたり、私は日本の原点としてあの戦争をもう一度振り返り、「英霊に対して恥ずかしくないのか」ということをもう一度日本人が問いなおさなければならないと思います。歴史を真正面から見つめ、「先人に対して恥ずかしくない生き方をする」ことを、改めて自らの政治の原点として生きていくことをここに宣言します。
今後とも皆様のご指導ご支援を心からお願い致します。
川づくり 街づくり

関戸秋男さんは石川県小松市生まれ。昨年60歳を迎えられ、西田染工株式会社を定年退職されました。お住まいも会社の近く東九条北松ノ木町に構えられ、45年間の歳月をお仕事のみならず、特に高瀬川の美化活動の実践を通して街づくりに貢献されてこられました。会社へお伺いし、そのご活動を西田庄三郎社長とともにお聞きいたしました。(以下敬称略)
関戸:掃除をしたのはだいぶ前からですが、高瀬川の水は以前はしょっちゅう止まって、3日も4日も流れが止まってしまう。するとゴミなんかで、川がとても臭うんです。
高瀬川は二条の「一の舟入」あたりから鴨川の水を引いているのやけれど、五条あたりで鴨川に水をにがしてしまうようになっているんやね。
昔は上鳥羽にも水田があって、用水路としても使われてきたけども、もう水田も無くなってしまって。昔はフナやドジョウ、いろんな魚がすんでおったね。
西田社長:その頃はこのあたりの鴨川の堤も、上の植物園あたりと変わらん様に綺麗で、仕事が終わったら皆で野球をしたりして、よく遊びに出かけたもんです。今の様になったのは新幹線の建設工事が始まってからですわ。今でも、鴨川の美化運動は五条より上なんやね。
汚れていく高瀬川
西田社長:30年ほど前に染工所では自家水洗の設備をしましたから、鴨川や高瀬川でも見かけは美しくなってきましたけれど、当時、糊や染料の原料が天然もので害はなく、魚はずっと住んでいたんですよ。それよりも高瀬川は七条付近でゴミの投棄が多かったんです。京都市はその清掃のために専従員を置いていたぐらいです。昌司さんにお願いしてから九条通りから南でも、ようやく京都市の清掃が入ってくれるようになりました。
関戸:当時から同僚の熊野好影さんと2人で、毎日代わる代わる汚れた高瀬川に入っては、ゴミを拾っていました。今でも2人で週に3日は清掃をしています。嬉しいことに昨年6月、清流に育つ“クレソン”が高瀬川で自生しているのを見つけたんですよ。
高瀬川に鯉戻る
関戸:鯉を放流してみようと思ったのは偶然なんです。たまたま友達からもらった鯉を皆で食べていたんです。クレソンさえ自生するようになった高瀬川に鯉を放してみようと思ったのは、そんなところからだったんです。はじめは2匹、そして3匹と少しずつ増やしてきました。
はじめたのは昨年10月ですので、この高瀬川で育ってくれるのかどうかわかりませんが、毎日川を眺めています。高瀬川の流れが涸れないようになってから、メダカや川エビが住めるようになって、それを餌にしているのだと思います。
川に花あり魚あり
関戸:ちょうど川辺に桜の木もありましてね。はじめは小さな木でしたが30年近くになります。豪雨のときは枝を支えたり、花が終われば消毒をしたりしてきました。花が咲く頃には近所から電気をもらって証明も点けます。
西田社長:そりゃ、花が咲いたらご近所の方と毎晩、花見の宴会ですわ。この桜は早咲きなんですが、それは美しいんですよ。近所の方も楽しんでおられます。
関戸:これからの季節、カルガモやカモが高瀬川にもやってきます。
西田社長:この辺りの高瀬川も鴨川も以前と比べると、ずっと良い環境になってきましたよ。鳥の数も種類も多くなってきましたからね。
川づくり 街づくり
関戸:しかし、いまだに家の前の川でもゴミを捨てる人はいます。川を美しくすれば、いずれ皆ゴミをほかそうという気持ちにならんようになると思います。今日もゴミを揚げに行ってきましたけど、昔はほんとにゴミなんか流れるような川ではなかったんですよ。今ではご近所から「ご苦労様」と声を掛けられたり、「鯉がいるね」と喜んでもらったり。
私が長年勤めた西田染工や我が家の側を高瀬川は流れています。毎日眺める川です。「思い出」も「思い入れ」もあります。今後も出来る限り、続けていこうと思います。
謹んで新春のお祝いを申し上げます
参議院議員 議院運営委員長 西田 吉宏

皆様には、21世紀初頭の新春をお揃いでお迎えのことと、心よりお喜び申し上げます。
旧年中は、皆様方の暖かい御芳情を賜り、お陰で私も参議院議院運営委員長の任を無事果たすことができました。心から厚くお礼申し上げます。
今年は、21世紀の意義ある節目として、千年に唯一、私達が迎えた希望に満ちた新春であります。
最近の世情はインターネット、携帯電話の普及等、“IT革命”による社会環境の変化が、私達の身近に多々現れ、産業構造の変化も余儀なく去れているところでございます。 一方国政におきましても、これ等に対応すべく、総合経済対策として「IT革命の推進、高齢化対策、都市基盤整備、中小企業対策」等々、日本新生のための政策を実現するための、国家戦略として提示いたしておりますが、特に京都は、日本を代表する最先端技術産業を抱えている一方で、歴史と伝統を継承する様々な中小産業が、経済を支えております。
私はいま、“景気回復”に全力を注ぐことが、最重要課題と考え、地域にきめ細かな予算が講じられます様、努力をいたしております。これからもなお、西田昌司府議会議員と力を合わせ、皆様方の生活の安心や安定を構築するお手伝いをさせて頂き、更には、「声、思い」を国政へ届ける掛け橋として、21世紀も頑張って参る決意であります。
どうぞ、これからも皆様方の一層のご健勝、ご多幸を祈念申し上げまして、新年の挨拶と致します。
お陰様で議員在職10年を迎えました
あけましておめでとうございます。
去る12月1日、西田昌司府議会議員は議員在職10年を超えたことにより、全国当道府県議長会から表彰を受け、その伝達式が府議会で執り行われました。これもひとえに講演会の皆様方のご支援の賜物であり、深く感謝いたします。今後とも初心を忘れることなくその職責を果たしてくれることを皆様方とともに期待しております。本年も後援会ならびに昌友会活動に対しまして、ご参加ご協力をよろしくお願いいたします。
京都南区西田後援会会長 米田忠雄
昌友会会長 秋田公司
恥を知らない女達

縁あって多摩御陵の昭和天皇陵にお参りしてきました。昭和天皇といえば昭和21年の歌会始めの勅題「松上の雪」で
『ふりつもる み雪に耐えて いろ変えぬ 松ぞををしき 人もかくあれ』
と歌われ、戦争に負けても変わることのない日本人の心の丈を歌われています。
和歌といえば日本人が心の丈を、やまとことばで表現した詩歌であり、漢詩に対する「やまと歌」であります。それは心の現われで、普通なら恥ずかしくて言えないようなことであっても、自然の花鳥風月の風情を借りながら巧みに読み込んで贈り、その思いを伝えます。その状況は時にはコケティッシュで、源氏物語の「光源氏」と「源典侍」の歌の駆け引きのようになります。
和歌は日本人の心の故郷であり、「大和の国はまほろばの・・・」の精神は、今も脈々として伝えられていますが、はたしてそれは一部の人達だけで、全体の日本人がそうではないかもしれません。日本人の大半は日本語の本質を忘れ、マスメディアに動かされ、ギャグ的なことばを使い過ぎ、話し言葉さえもレベルが低下しています。
例えば、キャリアウーマンの象徴であるニュースキャスターと呼ばれる人でさえ、しっかりとアナウンス出来ていない者もいます。20代後半になればテレビ局を追い出され、週刊誌のスキャンダラスな見出しにおさまっているのでは・・・。結婚に走ったが、それも先妻を追い出して後釜に座り、不倫を不倫とも思わず、普通なら出来ないことを堂々とやってのける。
彼女達は恥を忘れたのではないでしょうか。もっと心の修行をして和歌でも学んでもらったらどうでしょう。
『しのぶれど いろにでにけり わが恋は ものや思うと 人の問うまで』
であり、女はつつしみ深く、しのび、耐えることも学ぶべきでは・・・。本能のままに行動するのではなく・・・。この傾向は男性よりは女性の方が強いように思っているのは瓦一人でしょうか?
そう言えば松坂大輔と問題になった女性もアナウンサー・・・。
編集後記
昨年、初めて老眼鏡なるものを買いました。今までメガネと言えば「虫眼鏡」だけ。二度と何不自由無い視力には戻れない、と思うとわが身が愛しく感じられました。大切に大切にこの体を使わせていただこう、今年から…
編集室 松本秀次

今から十数年前まで、「あなたは今の生活に満足をしていますか」という問いかけに対して、日本人の8割の人が「イエス」と答え、自分の生活レベルを「中の上」と感じていた時代がありました。日本人の殆どが今の生活に満足をし、幸せを実感していた時代が、つい十数年前まで確かにそこにあったのです。今、同じ質問をしたらいったいどうなるでしょう。答えはこれとまったく逆で、その殆どが「今の生活に不満を感じ、幸せの実感が乏しい」という回答が返ってくるのではないでしょうか。「バブルが崩壊して不況がこれほど長引いているのだから仕方がない」という人もいるかもしれません。しかし、本当にそうなのでしょうか。私はそうは思いません。冷静に考えてみれば、バブルがはじけて不況が続いているとは言え、私たちの生活レベルは十数年前と比べれば、やはり今のほうが豊かな生活をしていると思います。
このことからも解るように、経済的豊かさというのは幸せの実感とは必ずしも一致にないということなのです。では、何が幸せを感じるための条件なのでしょうか。この問題を解くためには、昔の日本の社会にあって今の社会にないものを考えてみれば分かります。
その一番の典型が、人間の信頼関係ではないかと、私は思っております。家族や友人をはじめとする人間関係の絆の強さ、信頼感などは昔と今とではずいぶん違うように思います。また会社に対する忠誠心、いわゆる愛社精神というものも今と昔とでは大違いではないでしょうか。昨今のリストラ騒動によって、会社を辞めさせられた人も、かろうじて残った人も会社に対する考え方は、今と昔とでは、ずいぶん違うものでしょう。私はこうした信頼の絆の希薄化が、私たちから幸せの実感を奪う一番の原因であると思っています。
例えばこのことを如実に物語るのが、いわゆる老人福祉の問題です。考えてみれば、日本人の平均寿命は男女とも世界一です。また、不況で下がったとは言え、一人当たりの国民貯蓄額や国民所得など実質上これもトップレベルです。また凶悪犯罪が増えたとは言え、やはり世界で一番平和で安全な国なのでしょう。世界で一番長生きをして、世界一金持ちで、安全な国の国民なら世界一幸せのはずなのに、そうは感じていないお年寄りが大勢いらっしゃるのです。この人たちは私にこう言われました。「確かに長生きはした、でもいっしょにご飯を食べる家族も話をしてくれる友達もいない。それがさびしい」と。先ごろ発表された総務庁の調査にも介護を施設ではなく、家庭内で受けたいという人の比率が増えてきているという結果が示されていましたが、このことをまさに物語っていると思います。
また、青少年をめぐる問題にしても、その原点が家庭にあることは誰もが感じていることです。その中でも特に親子関係の希薄化が大きな問題であると私は考えております。親が子供に自分の大切な価値観を伝えることが出来ない、むしろ伝えるべき価値観がないというほうが正解かもしれませんが、親の最低限こうした務めさえ果たせない人が、今非常に多くなっています。そしてこのような環境で育った子供が親になったら、何も伝えることが出来なくなるのは当然のことです。今こうした悪循環が次々に繰り返されているということなのでしょう。つまり親から子供へ「心の相続」が出来なくなっているということなのです。「心の相続」がなくなれば、家庭が崩壊するのも当然のことでしょう。
またこの十年、我々地方議会の合言葉は、地方時代や地方分権という言葉でありました。新しい総合計画の中でもこのことが掲げられています。しかし、そうした行政側の取り組みとは裏腹に府民の関心はさっぱりというのが現実です。
地方の時代、地方分権の時代と言われながら、なぜこのような無関心な状況が生まれてきたのでしょうか。このことに対する真剣な議論と方策が考えられないと、地方分権はまさに言葉倒れに終わってしまいます。
私はこの原因もまた、その地域に住む人間の信頼関係の希薄化がもたらしたものであると思います。というのも地方分権というのは、「自分の故郷は自分たち自身で守り育てる」という気概があることが前提です。しかし、今の時代、どれだけの人にその気概があるのでしょう。また故郷を思う気持ちというのは一体何処から出てくるものなのでしょうか。私は、故郷にいる家族や友人、また忘れがたい思い出などを抜きにしては、きっと語ることの出来ないものだと思います。そこに家族や友人、思い出がなければ故郷は存在しないのです。
また、最近はやりのITについても同じことが言えます。ITとはインフォメーションテクノロジーの略語で、コンピュータを使った情報通信技術のことですが、これにより、家族や会社や地域社会、いや国さえも乗り越えて、個人から直接世界と結びつくことが出来る社会が実現すると言われています。そして、個人の可能性が一挙に変わるのだと言われています。そこで今、IT化への対応が日本の経済再生には不可欠なものと、国を挙げての取り組みが行われようとしているのです。
しかし、ITは文字通りイット、それに過ぎないわけで、問題はコンテンツ、つまり中身の問題です。情報を流す仕組みに価値があるのではなく、流す情報自身が価値あるものかどうかが、本来問題となるのです。ところで、情報に価値があるかどうかは、その情報を得る人が判断する以外にありません。つまり同じ情報でも、或る人には価値の或るものとなり、また違う人には何の値打ちもないということになるわけです。そうすると、情報が価値あるものとして生かされるには、情報を必要とする人に利用される仕組み、「ネットワーク」が必要だということなのです。ITはこのネットワークを構築する方法や技術に過ぎないわけで、ネットワークそのものを作るものではないのです。ネットワークを作るのに必要なものは結局、仲間意識つまり、これも信頼の絆以外の何物でもないのです。この信頼の絆で結ばれていない架空のネットワークに流される情報は、真偽の程が定かでなく、結局は役に立つものではありません。つまりITもそれを現実の力とするためには、信頼の絆の確立ということが大前提になるということなのです。
今私たちは、「人+信頼=幸福」という誰もが知っていた当たり前の方程式をもう一度思い出すべきではないでしょうか。
(この原稿は平成12年10月5日の本会議での質問の抜粋です)

昨年の秋から、京都市は、各区の住民が誇りに思い、次の世代に伝えたい「区民誇りの木」の選定を行っています。いわれのある木や地域で親しまれいてる木などを区民から募集し、今年度中には、全十一区の「誇りの木」五百本以上を選定する予定です。
この事業は、市が平成十二年二月に緑化推進事業を取りまとめた「京都市緑の基本計画」の一つで、市民が身近な樹木に注目する機会をつくることで、緑化推進に向けた意識を高めてもらうためのものです。市民が見ることが出来る健康な木で、歴史や言い伝えのある木や大木・希少な木、花がきれいな木・実が見事な木といった町の誇りとなる木を、上京区、下京区から順次募集し、各区ごとに五十本程度選定し、写真集に収録したり、今後、区の花と木を制定するときの候補ともなります。

南区においても、この春から九月末まで、「誇りの木」の募集があり、これを機に南区の木を考えてみました。京都で大木を考えたとき、まず神社仏閣が考えられます。南区では、東寺、吉祥院天満宮、久世の蔵王堂などがあり、ここには大きな木も残っています。次に一般的に大木がよく残っている河川敷ですが、南区は桂川、鴨川をはじめ西高瀬川、堀川など京都を代表する河川が流れています。しかし、ここ数年は、鴨川や西高瀬川など散策路など植栽や修景も含めた改修がされていますが、以前は上流域と違い流下能力至上の改修が多かったため、大木はほとんど姿を消しました。そして、町中の道端に一本でも存在感のある大きな路傍樹も、戦前は九条通以南は田畑中心であったためか、市内でも区画整理事業がよく進んでいるためか、はたまた工場・倉庫やマンションが多いためか、ほとんどありません。そして、残っていた大木の一本が、土地所有者が変わりビルが建設されるためか、維持管理の大変さからか分かりませんが、先日も切られて無くなっていて、大変寂しい思いをしました。

さて、来年からいよいよ二十一世紀が始まります。京都においては、市街地中心部の再生、周辺部の保存、そして南部の開発という街づくりを今後も進めていくようです。街づくりの骨格は行政が行いますが、土地の大部分は民有地であり、町を実際作っていくのは住民です。今後は、開発といっても機能性重視だけではなく、より暮らしよさ、潤い、環境などが重視されると思います。大木をはじめ、緑は街に潤いを与えます。有名な明治神宮の森も木が植えられてまだ百年、されど百年。南区も、今後百年も見据えた新しい街づくりが必要だと考えます。
カラスが鳴かない日があっても、マスコミにIT(情報技術)が登場しない日はありません。政府が日本の経済再建のために掲げており、やれアメリカに立ち遅れたの、産・官・学ともにアメリカに追いつけ、追い越せであり、いつか来た道をまた辿り出しているような気がします。 日本とアメリカではその国民性も、国土も異なるのに同じ土俵に上がろうとしているのではないでしょうか。かつてのモータリゼイションにおいても、国土の広大なアメリカと日本が同じように発展するはずがなかった。歩いて5分もかからずにマーケットにいけるのに車が果たして必要か? また、目覚しい勢いで発達するインターネットなどの情報技術は、十八世紀の産業革命をしのぐものとも言われており、「国家も企業も個人もバスに乗り遅れないように・・・・・・。全国民がインターネットを使えるように、講習会の費用を・・・・・・」といった声が聞こえてきます。はたして、街角の魚屋さん、うどん屋さんにインターネットが直ぐに必要でしょうか? コンピュータが無ければ商売が出来なくなるのでしょうか? (そういえば、街角から魚屋さん。うどん屋さんが姿を消し、その跡にスーパーマーケット、ファミリーレストランが出来ていますが・・・・・・) 確かにITは生活を便利にしてくれる道具に違いありませんが、ややもすればIT革命なる言葉に踊らされて、物事の本質を見失い、コンピュータだけを追いかけている嫌いがあるのではないでしょうか。「もの作り」において「ものを作る」のは人間で、その手助けをコンピュータがしてくれる。いくら旋盤がコンピュータ化されていても、どのような物を作るかといった創造性や、出来上がった製品の評価は人間がするものです。コンピュータは、「もの作りの手助けをしてくれる道具である」と思っているのは瓦一人だけでしょうか? うどん屋さんの跡に出来たファミリーレストランの店員の注文取りは、コンピュータによるボタン操作になっています。確かにオーダーミスはなくなりましたが、「きつねうどん」が「たぬきうどん」に化けたうどん屋時代にはそれなりの風情と人情に溢れていたのでは無いでしょうか。
編集後記
地方に出かけると、新しく広い道路が次々と出来ている。しかし、わたしは傍らの旧道を走ることを楽しみにしている。
鎮守があり、寺がある。造り酒屋に醤油屋、宿屋があったりもする。何より通りに向かって佇む家並みが美しい。
わずかにカーブした在所のはずれに、常夜灯と道標が昔から行く先の安全を見守っていてくれた。南区では,西国街道・鳥羽街道等は今なお活気がある。
編集室 松本秀次

6 月25日に行われた衆議院選挙は、全国的には自民党はじめ連立与党の退潮、民主党の躍進という様にマスコミでは報道されました。しかし、我々の京都においては、小選挙区で2区以外の五つの選挙区で勝利し、また大阪では、小選挙区での当選者は倍増するなど、一概に自民党退潮という様子ではなかったと思います。しかしそれでは、自民党はじめ連立与党が勝利したのかと言えば、やはりそれは否としか言えません。それでは、民主党が勝利したのかと言えば、それも違うと思うのです。では、今回の総選挙の結果をどのように捉えればよいのでしょうか。
今回の選挙では、選挙戦中盤の予想では自民党の勝利を予想する報道がなされました。そして、終盤になってこれに対する逆アナウンス効果で、結局自民党が議席を減らすという、2年前の参議院選挙を彷彿させるような結果でした。これは、森総理大臣のいわゆる「神の国」発言に対する報道をはじめ、最近のマスコミに見られる過剰報道の影響が出たことは否定できないでしょう。
また、公明党との連立に対するアレルギー反応が出たとする意見もあります。勿論その影響も多少あるでしょう。しかし、京都の選挙区を見ていると、結果としては自民党にとっては、マイナスよりむしろプラスのほうに働いたと言えるのではないでしょうか。また、公明党との連立については、政党人としては私は、当然のこと単独で政権を目指すべきであると思います。しかし、参議院での過半数割れの現実を考えると、現実の選択として止むを得ないと思っています。むしろ、かつての新進党時代の連立政権のほうが、その中枢に公明党が完全に一体化していたのですから、当時のマスコミの態度と今回のそれを批判するマスコミの姿勢は冷静に考えれば、かなり矛盾するものです。
しかし良く考えてみれば、マスコミの姿勢はなにも変わっていないのです。彼らの姿勢は公明党・創価学会に対して反旗を翻しているというより、一貫して反自民の旗を振っているということなのです。だから、細川政権や羽田政権の時は反自民の政府にエールを送り、自公保の時は反自民の立場から非難しなければならないのです。彼らにすれば与党の場合は勿論、野党であっても自民党というのは、政・財・官を巻き込んだ権力装置そのもので、この権力に対する対抗装置としてマスコミの使命があるとでも思っているのでしょう。
結局、戦後の日本の社会では、常に「権力対反権力」という、非常に単純な構図の中でしか政治が語られていないということなのです。理念や理想が語られず、権力対反権力という構図だけで、選挙が毎回行われてきているということなのです。
その結果、政治家が語る言葉は紋切り型になってしまったのです。野党やマスコミは与党の政治家の言葉尻を捕まえ、揚げ足を取るようなことであっても、与党を徹底的に非難をします。そして、彼らが示す大衆受けを狙った奇抜なアイデアを、政策として示すのです。その時々の与党の政策に対して、対抗手段として提案しているに過ぎない俄仕立てのものですから、当然の結果、矛盾だらけのお粗末なものになってしまいます。そこを与党に突っ込まれるとたちどころに馬脚が現れてしまうのです。こうしたことは今回の選挙に限らず、戦後ずっと続いてきたことです。京都における自共対決などその典型でしょう。全国的には、自民党対社会党の対決として行われてきたのです。
しかし、今まではこの対決は最初から勝負がついていたのです。というのも、自民党に対する野党はこれまでは社会党や共産党、公明党といった特定の指示基盤の上に立つ組織政党、イデオロギー政党、宗教政党しか選択肢が無かったからです。反自民の声も、結局はそうした選択肢しかない状況の中では、形になって現れることが少なかったのです。いわゆる無党派の人にとっては、旧来の野党では受け皿たり得ず、むしろ自民党の方がその受け皿になっていたのです。つまり、国民政党として幅広く国民に支持される基盤を持つのは、自民党しか無かったということが自民党を助けてきたのです。
ところが、今はもうそんな状況では無くなっているのです。民主党の実態はその半分が旧社会党出身者で占められ、支持基盤も連合系の労働組合等がその中心をなしていることも事実です。しかし、残り半分は、いわゆる保守中道系の方々です。政党としての中身は非常にあやふやで、選挙互助会的な性格は否定できないのも事実ですが、あやふやであっても、そのウイングが広いということも事実です。かつて、自民党自身が自分たちのウイングの広さが身上であることを自慢していました。そういう意味では、民主党も同じような様相をしているのです。勿論民主党と自民党とではその実績も実態も随分違いますが、少なくとも有権者にとっては、表面上はイデオロギー政党の姿が見えなくなった民主党は、自民党に代わり得る国民政党の資格有りと見えつつあるのではないでしょうか。
幸いにして、森総理の失言に対する、鳩山代表らの執拗な発言があまりにも低レベルであったため、かえってその不寛容さが、この政党の懐の狭さを自ら証明することになってしまいました。その結果、国民の信頼感を獲得できなかったため、この程度の敗北で自民党はすんだのです。
このように自民党を取り巻く政治状況は、10年前とは全く変わっているのです。にもかかわらず、自民党が訴えてきたことは10年前と何も変わりがないのです。野党の無責任と無能力をいくら訴えていても、イデオロギー政党の共産党批判としては、その言葉は効いていても、民主党批判としてはその言葉は意味が無いのです。むしろ、その言葉はそのまま自民党に返ってくるのです。また、今回の選挙では、民主党=若者の党、自民党=年寄りの党というイメージが非常に強かったと思います。私は別に若者に迎合する必要は無いと思っていますし、経験実績を踏まえた人生の先輩方の知恵を活かすことの大切さも知っているつもりです。しかし、あまりに旧来の体制ばかりがなんの議論も無しに踏襲されてしまい、結果として、世の中の変化について行けなくなっているところがあるのではないかと思っています。そうした体質は決して保守ではなく、単なる頑迷固陋(頭が固いだけ)であり、評価できるものではありません。そうした体質が結果として、若者の受け皿に自民党がなり得ず、民主党に票を奪われた大きな原因でしょう。
国民が本当に聞きたかったのは、野党批判ばかりでなく、これからの日本の社会に対するもっと明確なビジョンなのです。勿論、各党ともそれに類したことは言っていたのかもしれません。しかしそれは、表面的な問題を述べていたに過ぎず、本質的な問題は少しも語られていませんでした。
例えば、頻発する17歳の少年の殺人事件等、この社会が完全に崩壊の危機にあるということは誰の目にも明らかです。これに対して、一体いかなる手段で対処するのかとうことになれば、各党とも教育を改革しますといっているだけで具体的なことは全く見えてこなかったのではありませんか。敢えていうなら、自民党が少年法の見直しや、徳育の重視ということを言うのに対して、民主党等らは刑罰を重くしても問題は解決しない、徳育は子どもを画一化するなど、と自民党に対して批判しました。その一方で、子どもにもっと人権教育や命の尊さを教えることが必要なのだと、相も変わらず、戦後教育そのものを守るという旧社会党体質を浮き彫りにしたにすぎません。しかし、これとて少しも本質論にはなっていません。
私に言わせれば、この問題の本質は、教育の原点は何かということがまず問われなければならないと思うのです。そういう立場から、戦後教育が結局GHQの指導の下に権利ばかりが重視され、義務があまりにも欠けてきたこと、また、国民教育としての義務教育にもかかわらず、日本人としての当然の常識やモラルや伝統といった、言わば、時代を超えた叡智の積み重ねが全くといってよいほど学校の中で教えられずにきたという戦後教育の根本的欠陥等を明らかにすることが大切です。その上で、戦後社会そのものを問い直し、次の時代にはこうした敗戦による負の遺産を一掃するということを国民に示すことが、保守政党としての自民党の務めだと思うのです。
こうした本質論なしに、表面上の課題のみを訴え、互いに批難し合っているのでは、子どもの喧嘩に等しく国民の信を得ることは出来ません。結局、今回の選挙はこうした観点から見れば、まさに全ての政党が国民から厳しいお灸が据えられたということです。「もっと本当のことを、本質を示し議論せよ。」これが「神の声」ではなかったのかと私は思っています。そして当然のことながら、その責務は自民党が一番重いと思うのです。
今、感動の政治を語る

去る6月3日、京都テルサにおいて『今、感動の政治を語る』と題し、京都府議会議員西田昌司講演会が開催されました。西田議員がかねてより街頭演説をされていました内容を「是非とも一度十分聞いてみたい。」という多くの方々の強いご要望を受け、後援会のひとつである一粒会の主催で開催されました。
当日、会場は年齢性別を問わず多くの方々で満席状態になり、初めて西田議員の話を聞く方、街頭では時折耳にされる方、また熱心な支持者の方々を交えて熱気に包まれた講演会になりました。参加されました方々からの感想をご紹介いたします。
海外を旅し異国の街を訪れたとき、その街並みによく驚かされます。過去からの街並みが見事に現代に調和し、そこに暮らす人々の伝統と歴史までもを感じとることが出来ます。しかし、日本の街の看板には中途半端な和製英語が氾濫し、街並み、風土、気候に適さない統一性のかけらもないデザインの家屋が建ち並び、まさに自由勝手気ままな人の暮らしがそこにあるように思います。今の日本人にとって必要なことは、日本の持つ伝統、文化、風習をあらためて認識し、本来の日本人の持つべき特性や気質や常識を回復することが必要なのではないでしょうか。
日本らしく日本人らしくなることが、グローバルスタンダードへの近道なのだと強く感じました。
H・K(32才 男性)
私が終戦を迎えたのは、小学校の一年生の夏でした。一学期は空襲の連続で、登校するとすぐに警報の発令があり、上級生と共に、自宅へ帰る日が多く、机に向う日は、ほとんどありませんでした。二学期になると、教科書は一変し、あちこちを墨で消され混乱した戦後教育そのものでした。政治のあり方も、教育の方法も、経済の仕組みも、敗戦の責任として、それまでの長い日本の歴史を否定することが前提でした。この結果、宗教家も教育者も、「人は如何に生きるべきか」の答えがなく、人格の形成は無視されて来たように思います。人格なき政治家や教育者、医者や公務員、会社の経営者や上司が生まれました。つまり肩書(名刺)で通る社会です。又それで世の中は動いて来たように思います。先生の講演に徳育と言う言葉を感じました。日本の国を愛し、二十一世紀を迎えた今日、その将来を案じた、勇気ある講演であったと思います。
N・N(61才 男性)

今回日頃先生が街頭遊説をされているお話の一部を聞く事が出来たという事は、私にとっても会場に集まって来られた方々にとっても大変良い機会であったのではないかと思います。
戦後の教育を受けてきた私にとって強く疑問を抱いていた事が一つあります。それは、海外の同じ世代の人達が自分の国の文化や伝統を重んじて意見を述べる事が出来るのに、私にはそれができない。関心や興味が低すぎるのはおかしいが、それが何故かまで突き止めて考えた事がなかったのです。
今日、明日急に変わる事は出来ないけれど、せっかくの歴史の古い街である京都に住んでいるのだから、もっと伝統や文化とは何かを意識して自分から少しずつ興味の持てる内容から学んでいく事、家族や友達の絆を大切にできる人間になれる様に、将来子供達に身をもって示してゆける大人になれる様に、常に意識して少しずつ実行していこうと思う。与えられるばかりでなく、与える事が出来る人間になれる様に努力していきたいです。
S・A(26才 女性)

今、「17才」が全国的に注目されている。いわずもがな、「17才の重大犯罪」である。ここ数年「少年犯罪」の増加、重大化を受けて、少年法の改正問題が議論されてきたが、それは犯罪少年の処罰と保護、犯罪被害者の保護、ひいては一般国民の安全保護と均衡を求める議論であった。すなわち刑事政策上の議論であった。これについての私の基本的な考えは、『SHOW YOU 第13号』にて述べた。
ところが、少年法改正の一応の方向が定まってきたこともあってか、先般来の「17才犯罪」については問題の焦点が教育問題に移り始めている。しかしながら、これを論じる際には、一連の「17才犯罪」の個別事情に目を向け、かつ、社会及び家庭のあり方の変化の流れを適確に読んだうえでなされることが必要である。
「17才を重大犯罪に走らせるものは何か。」
確かに、それぞれの「17才犯罪」に共通した病巣を探り、その処方箋を考えることは重要である。しかし、それはまた極めて困難な作業であり、十把一絡げに論じられるものではない。事件後も日々報道される新聞記事に接しているだけでも、それぞれの犯罪における「17才」の心の闇が違うことに気づかされる。これら個別の事情を安易に捨象してしまうことは、得てして問題の所在を「制度」に求めてしまいがちとなる。その結果得られる結論は、的のはずれた副作用の大きいものとなってしまう。
思えば、私自身、17才と言えば、初恋以上の恋の悦びを知り、社会一般にまっとうであると見られる生き方に疑問を感じ取り、それでもその社会の中に組み込まれていくことの不本意、不安にさいなまれるという、子供でもない、大人でもない、アンビバレントな存在であった。このような少年期特有の感情の揺れは、いつの時代も変わらないし、これからも変わらないであろう。そして、それ故に犯罪を犯してしまう者のあることも変わらないであろう。そのような中で、大多数の少年は、自分のそのような感情の揺れを経験しつつ、それぞれの方法でうまく自分を治めているのである。犯罪を犯してしまった少年はその治め方を見つけることができなかったのであろう。
そのような少年を犯罪に陥らないためいに、社会はどうすべきか、家庭はどうあるべきかを論じることは誠に大切なことであるが、一方で、社会や家庭自身もそのあり方は常に変化を生じているのであって、その議論もその変化の流れを読んだうえでなされなければ説得力を持たない。
編集後記
「今、西田昌司議員のホームページが面白い」との噂があるそうです。と言うのも、この機関誌「SHOWYOU」がインターネットを通じて最新版からバックナンバーまでいつでも見ることが出来るそして、「メールマガジン」に登録していただければ自動的に西田議員の時事問題に対する意見が配信される仕組みになっているからです。
またメールマガジンを通じて、ご意見がたくさん寄せられ、西田昌司議員も欠かさずご返事を差し上げております。是非、西田議員とのホットラインをご活用ください。
URLは下記
http://www.ky.xaxon.ne.jp/~showyou/
夏本番となりますが、ご自愛のほど。
編集室 松本秀次

去年7月のSHOWYOU20号で、私は、京都府の危機を訴えました。事業税等の大幅な減収により、このままでは京都府は事実上の倒産状態を意味する「財政再建団体」になってしまう危険性を指摘しました。そして、これを避けるには、もはや人件費の大幅なカット以外に策は無いと主張しました。この3月には平成12年度予算案が審議され、共産党を除く賛成多数で可決成立しましたが、私が指摘をした人件費の大幅カットということについては、まだまだ不十分であると思っています。
もっとも京都府も財政再建に手をこまねいているだけではありません。財政健全化指針を策定し、「入るを図りて出を制する」の格言通り、さまざまな方策を打ち出してもいます。今年は、取りあえず定期昇給を12ヶ月延伸をし、通年で57億円の削減が実現しました。しかし残念ながら、収支不足額が500億円規模であることを考えますと、一桁違うと言う他はありません。
私は税理士の仕事を通じて、中小企業の実態をそれなりに知っているつもりですが、それは厳しい経営環境に置かれています。バブル崩壊以来売上が極端に落ち込む一方、二信金の経営破綻の影響もあり、資金繰りには非常に窮しておられます。景気の良いときにはそれなりの給料を取っていた会社でも、こうした危機を乗り切るために自分や家族の給料を半減してまで頑張っておられます。中小企業の経営者は保証人になっているのは勿論のこと、自分の家屋敷までも担保に入れて会社の経営にあたっている訳で、文字通り命がけで経営をしているのです。
また、いわゆる大企業においても、40代になったとたん肩叩きにあい、系列の子会社に出向させられて給料は半減し、2、3年後にはその子会社が精算されて職も無くしてしまうというようなケースも見聞きする時代です。公務員だけが一人、給料も雇用も世間の風、何処吹くものぞとしていられるはずがありません。
しかしだからと言って、公務員の数を一度に半減したり、給料を半分にしたりすることを私は言っているのではありません。そんなことをしたら、かえって雇用環境が益々悪化するだけで、京都府の財政は良くなっても経済全体が冷え込んでしまいます。職員一人一人の生活自体も破綻をしてしまいます。私が言っているのは雇用はしっかり守りながら、非常事態を回避するためにみんなが少しずつ我慢し合おうということです。例えば、人件費を10%カットするだけで、年間300億円以上の節約ができることになるのです。これだけの全額のカットが出来れば後の200億円程度は、いくらでも調整することは可能です。今後こうした不況が続いたとしても京都府が沈没する心配は無くなるのです。
しかし、このことを実行するには大変な反対があり困難だとする声があります。まず、京都府が負担する人件費は約33,000人分ありますが、そのうち警察官が7,000人残りが京都市などの市町村の小中学校および府立高校などの先生で、知事部局(いわゆる府の職員)は7,500人にすぎません。それなのに府の職員のみならず、先生や警察官の給料まで減額することにみんなの理解が得られるのだろうか、特にスト権ばかりか、団体交渉権も持たない警察官などのことを考えると人事委員会勧告の趣旨に反するのではないかという意見があります。また、公務員の給料をいたずらに下げるより、まず組織を見直して、出来るだけスリムな体制を作ることのほうが、職員の士気を損なうことも無く利口ではないかという意見もあります。これは至極もっともな意見ですし、実際にこうした組織の見直しをしても、その効果が出るまでの間には5年から10年もかかるということです。例えば京都府では今年、京都市内に9箇所あった府税事務所を3箇所に削減することを決めました。これにより80人くらいの職員が減ることになりますが、実際に人件費が減るためにはこの人数の退職者が無ければなりません。悪いことをした人を懲戒免職するならいざ知らず、不要な人材を民間企業のように、首切りをすることは公務員には出来ません。また雇用の秩序を考えてもすべきで無いと思います。このため、組織のリストラは将来を見据えて必要なことですが、今すぐにその効果を期待することは現実には出来ないということです。
また財源確保ということで、東京の石原知事が、大手銀行を対象にした外形標準課税の導入を決めました。これによって1,100億円程度増収が見込まれるということでしたが、仮にこれと全く同じ税を京都で導入した場合はどうなるでしょう。試算としますと、税収は40~50億円増えますが、その増えた分の8割が地方交付税の交付が減額されるため、実際に増える金額は8億円程度だと言われています。新税導入も、京都のように交付税を受けている自治体ではその効果を期待するのはなかなか難しいということです。こうしたことを考えても今すぐに500億円の財源を調達し、しかも、それを今後10年間用立てるためには、人件費の最低10%の削減は避けて通れないことなのです。またその前提として我々の議員報酬のさらなる削減と定数の減員は当然のことです。
ところで、公務員の給料は、人事委員会の勧告によって民間給料との調達がなされています。ここで調べられている企業というのは、国の人事院の指導の下で行われていますが、昭和40年以来、従業員数100名以上の企業だけがその対象となっています。いわば中堅規模以上の企業ですが、実質は大企業だけが対象になっているということです。公務員はスト権を制限されて云々と言われますが、大企業ならともかく、中小企業の場合には実質上スト権も団体交渉権も何もありません。景気が良いときはまだしも、不況のときにはたちどころに給与が下がるどころか、首になることもざらにあります。このような中小企業に勤めておられる方が、実は日本人の大半であるということを忘れてはならないと思うのです。公務員はその職責を果たすためには有能な人材が必要ですし、そのためにはそれなりの給料も保証しなければなりません。しかし今日のような未曾有の経済状況が続いているときに、自分たちだけが雇用も給与も安定していることになんの疑問も持たないということ自体が、実は危機感の喪失であり、国家の危機であると思うのです。
日本は今、百年に一度の変革期に入っています。人口動向を始め日本の右肩上がりの経済成長を支えてきた仕組みは崩れ去り、経済も社会も新たな秩序を求めての模索の時期にさしかかっているのです。しかしそのこを決して恐れる必要はありません。冷静に考えれば、日本のような狭い国土の中で、1億2千5百万もの人口を支えてきたことが世界の中でも特異なことであり、ましてやこのまま経済も人口も右肩上がりで伸び続けること自体異常なことではないでしょうか。世間では少子化の影響で人口が減り、社会から活力がそがれてしまうということを、大変心配していますが、むしろこれは今までの異常な経済成長を調整する局面に入ったと考えれば決して心配することではありません。
例えば、今までの日本は、3人家族で300万円の所得の世帯であったものが、4人家族になり所得もそれに合わせて400万円になり、5人になれば500万円というように経済発展をし続けてきたのです。バブルのときは5人から6人に増え、所得も500万円から600万円どころか700万円にも800万円にもなると誰もが信じ、それを当て込んだ投資をしてきたのです。ところがバブルが崩壊してはっきり分かったことは、家族は5人から6人になるのではなく、5人から4人になってくるということだったのです。そこで、6人家族のために投資してきた生活をもう一度身の丈を4人家族で暮らすためのものに調整しなければならない事態になったのです。6人家族のために建てた家は売って、もう一度4人家族用の家に住み、一からやり直そうこれが、今民間で行われているリストラの意味です。6人家族から4人家族に身の丈を合わせるためには、家を売ったり多少の勇気が必要ですが、それさえ決断すれば、後は心配しなくとも家族みんなが力を合せれば十分暮らしていけるのです。しかも、もしこの決断が出来なければ、それこそ一家は離散し破滅に向かうことになってしまいます。丁度、日本も京都もこれと同じ状況に立たされているのです。
吉田松陰の言葉に「国家の大事といえども深憂するに足らず、深憂すべきは人心の正気足らざるにあり」というものがあります。激動の幕末を、国を救うために一命を賭して彼が訴えたものは、まさに国家存亡の危機に立っているのに、旧態依然とした幕府官僚の危機感のなさを打破することだったのでしょう。正気の充満したリーダーを育てれば必ず日本は救われる、じたばたすることはない。ということではなかったでしょうか。
今日本は、幕末と同じ国家の大事に遭遇しているのです。まさに人心に正気の満ち溢れんことを願うばかりです。

西田昌司議員が街頭遊説を始めてはや6年目を迎えます。毎朝、雨の日も風の日も続けておりますが忙しい朝の時間帯のせいか、立ち止まり聴く人はなかなかありません。そこで「我々昌友会だけでもじっくり西田議員の話を聴こうじゃないか。」、ということになりました。毎月1回六孫王神社におきまして、「昌友塾」と銘打ち身近な問題として教育や経済・日本のあり様を話し合っております。「二信金の破綻」をテーマに去る3月14日昌友塾を開催しましたところ、多数のご参加を頂きました。ご参加された方々のご意見を紹介いたします。
広森 日出夫(会社経営)
日本国民として誇りの持てる教育(歴史、文化、伝統他)についで塾を取り上げ、子供たちに伝えていただきたく思います。平和、権利、自由、人権について取り上げ、その基礎となるもの、「真にあるもの」について塾で討論したく思います。
《西田昌司:まさに、日本の国柄を考えるということだと思います。》
谷口 広和(会社員)
私が昌友塾に参加させていただくきっかけは当事、橋本内閣が景気が良くないのに、どうして経済対策をしないのだろうかと思い、西田先生に手紙を出したのがはじまりです。早速録音テープで御返事をいただき、なんと政治を身近に感じさせてくれる政治家なんだろうと感動したものです。もっと自分自身、政治のことを勉強しなければならないと思いました。まだまだ勉強不足ですが、先生、昌友塾の皆さん、よろしくお願いします。
先生は、大事にしなければならないのは、家族の絆、友達の絆、ご近所との絆であると熱弁されていますが、私は感動すら覚えます。
しかし、先生のおっしゃる府職員の給料を10%カットするという考えには反対です。
財政難の責任を府職員の人達だけにとらせるのはおかしいと思います。それならば、公的資金の入っている銀行の給料を下げたり、損失を出したトップ達の私的財産もとらなければならないし、身売りして買い取られた銀行からも公的資金を回収しなければならないのではないでしょうか。
私は府職員が責任をとらされる前に、責任をとらなければならない人達がたくさんいると思います。大事な事は、先生のおっしゃる大和魂ではないでしょうか。私が責任をとろうと、自分から進んで責任をとる精神、そういう人が増えていく事が大事なのではないでしょうか。
《西田昌司:リーダーの大和魂こそ、今一番求められているものです。》
柿本 大輔(高校生)

私のような高校生が、府議会議員の先生や立派な社会人の方々に意見するのはおこがましいと思いますが、未成年の主張と受け止めてください。
今回初めて「昌友塾」に参加しましたが、皆様方の前で私は唯々理解したような振りをするのが精一杯でした。京都みやこ信用金庫の破綻の原因、これから先の京都の経済、学校では学べない多くの事に触れられたと思います。
そこで、私一個人の見解を述べさせていただきますと、「子孫の為に美田は買わず」ならまだしも、負の遺産を押し付けるのはやめていただきたいと思います。大人達がバブルに踊った付けを私達に精算させるのは、お門違いではないでしょうか、というのが私の考えです。
学校ではこのような生きた社会科学習を一切しません。歴史の授業では、第二次世界大戦終了までしかやっていません。大抵授業では「日本は戦争ばかりしていて悪い国である。」程度の事しか私達は学習しないのです。これでは今の日本、延いては日本経済に興味を持てというのは無茶な話です。戦後から現在までの流れを知ってこそ、これからの私達の時代が作れる筈なのに、入試に出るから歴史の年号を覚える、これでは再び今のような不景気に陥った原因を繰り返すのは必至です。歴史の授業とは、そもそも過去と同じ過ちを繰り返さないために学ぶものではないでしょうか。
ここで私は提案をします。私と同じ年代の人達にも、皆様方のお話、ご意見を聞かせてやってほしいのです。そうする事によって、私達は、もしこのような不景気に陥った時、最小限のリスクで不景気を乗り越えられると思うのです。
《西田昌司:若い世代の参加を待っています。一緒にこの国を背負って行きましょう。》
田端 俊三(会社経営)
この塾に参加してつくづく思い知らされたのは、「われわれの社会の現状」を余りにも知らなすぎる自分でした。
教育、家族、経済など、私はその基本である「あり方について」ここで初めて考える場を得ました。もし、西田先生や塾の皆さんと出会っていなかったら、耳触りの良い話を信じ込み、「いまのままでいいじゃないの。なぁ、みんなもしんどいのイヤじゃない。・・・・・・」の調子でいたと思います。それを考えればぞっとします。
これからも、辛口で真剣な思いをぶつけられる場としての塾にしていけるよう協力したいです。
《西田昌司:素直な心で、真剣に現状を見る。そこから全ては始まるのです。》
中路 雅之(自営業)
西田さんの活動報告の後、各回ごとにテーマに沿って意見交換がされますが、出席者の見識の広さと理解の早さには驚きます。
新聞等の政治や経済、教育などの雑多な記事が、どう結びついてどう形を変えて我々に関わってくるのか、テーマ選択の理由やその論理と対応する速やかな行動力には言葉もありません。
今回の「信金破綻と京都経済」では、一言では済まない複雑な広がりを持つ問題ということに気がつきました。
この塾が西田さんの手を離れ、逆にオブザーバーとして招き、活動の提言などできるような会にまで発展されることを期待します。
日頃、芸能と三面記事を主たる会話としている身には、話の内容は理解の範囲を超えていますが、TV討論会の観戦者ぐらいの軽い気構えでまたおじゃましたいと思います。
《西田昌司:是非、昌友塾をそういう形で広げてください。私達一人一人が本気になれば、必ず社会は変わります。》
-インターネットで商売?-
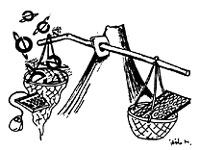
景気が低迷しているなかで、もうけるためには手段を選ばない人達が増えてきています。それもインターネットという怪物で「商い」をつぶそうとしています。
例を挙げると和装品です。和装品は長い歴史と伝統により産地や室町といった流通機関を築き上げてきたのです。それだけに複雑な商取引、生産形態を持ち、そのことが和装品の消費者不信を招いているのも事実です。だからと言って、染屋さん、織屋さんが問屋も小売店も経由せずに「うちで買えば市価の三分の一で買えます。」と、インターネットで直接消費者に着物を売ったらどうなるでしょう。流通機関をかき回したとも思われない。一枚でも着物が売れればそれでいい。結果がすべてで、生き残っていくためには・・・・・・。
また、最近話題のソニーの新ゲーム機「プレイステーション2」はインターネットで注文を受けたため小売店では「これが広がると既存店の首を締めかねないし、インターネット上で値引き交渉でも始まれば・・・・・・」と危機感を募らせています。
棟割長屋、井戸端会議が見られなくなった今、人はパソコンに向かいインターネット上で「商い」をしようとしています。本来、「商い」は作り手のピッチャーが使い手のキャッチャーにボールを投げるのと同じで、単に商品を動かすだけで利益を稼ぐものではないはずです。そこには「商人」としての使命感と責任感があるはずです。かつて孔子様は「おべんちゃらを言って商いをするのは恥ずべき行為」と言っています。江戸時代の儒学者・石田梅岩先生は、働くことと「商い」の使命感をもちなさいと教えています。梅岩先生は室町の呉服屋で丁稚奉公をしながら商いの実践を説いており、この教えは滋賀県の近江に伝わり西武、大丸、高島屋、伊藤忠などの近江商人の原動力になったそうです。
今の流通機構に問題がないわけではありませんが、さりとて不要とは思いません。インターネット商法が台頭してきた今、「商い」とは何か、室町の問屋筋をはじめ皆で考えようではありませんか。
それには近江八幡で作られた「天秤棒のうた」のビデオも参考となるでしょう。(レンタル店でも手に入ります。)
4月という語からは、新緑や息吹き等の冬の間に蓄えられたエネルギーが花開く希望という言葉を連想します。九条中学校にも今年も多くの”若い希望の芽” が入学してきます。昨年には『ふれ合いコンサート九条の心を歌う』と題して、地域の皆様やOBの方々とスクラムを組み、九条の地で育つ”喜びの歌”を合唱しました。この歌声は、地域と家庭・学校が一体となって、子どもを育み慈しむ喜びを体現したものと思っております。また、学校行事としての参加授業ではなく、ご両親に日頃の学校生活を見てもらうために、度々授業参観を行ってもらいました。これは生の姿を見て、親として家庭で何が出来るのか、保護者として学校にどう関わるのかを考えていただく目的でした。これからもこのような機会を設けていきたいと思っております。
ある会合で、どんな子どもに育てたいかという話題が出ました。その時には『人に迷惑をかけず、やりたいことをして欲しい。』という意見が大勢を占めたように思います。しかし、人に迷惑をかけず自分のしたいことをするというのは、生きていく上での社会のルールであって最低限の約束事だと思うのです。やはり『育って欲しい』中味には、子どもの大志や理想を期待したいものです。地域での社会のルールを学び、家庭では社会に貢献する人となるように大志を親子で話し合う。これも地域と家庭の役割の一つだと思います。
親としての望みや期待を話し合い、子どもに「生きる知恵」と「人としての道」を教え、親の姿勢を見せるのも、昔から日本の家庭教育の役割でした。いたわりや慈しみを土台に、『よりよく生きる』ことを子どもと話し合って欲しいと思います。”若い希望の芽”が、大志という社会に貢献できる力と人格を備えた大木となるよう、共に努力したいと思います。
編集後記
すっかり春めいてまいりました。私は先日、『結婚』という春を迎えました。西田議員にもご出席賜わり、ご祝辞を頂きました。今号に掲載した写真はそのときのものです。
私たちへのはなむけとしてイギリスのチャーチルの、『もし神が許されるなら、あの母の胎内から出てこの妻とともに人生を送りたい。』という言葉を頂きました。心に残るとても素晴らしい言葉です。
いつまでもこのような気持ちを忘れずに、幸せな家庭を築きたいと思っています。
私事で大変失礼致しました。
編集室 木村和久

平成12年1月元旦
今年はいよいよ2000年、20世紀最後の年でもあります。新たな出発の年であると同時に、締めくくりの年ということです。戦後の日本の有様をもう一度見つめ直し、日本の原点をしっかり見据えた、未来像を皆様に提案できますように、本年も頑張ります。どうぞよろしくお願い致します。
さて、私は、去る11月8日から15日まで、ドイツに視察に行ってまいりました。もっとも本年度京都府では議員の海外視察を中止致しましたので、自費での視察になりました。しかし、ドイツの日本大使館や総領事館並びに京都府のドイツ駐在員等のご協力のお陰で、非常に多くの貴重な経験と情報を得ることが出来ました。
私がドイツを訪問致しました時は、丁度ベルリンの壁崩壊10周年の真っ只中で、ブッシュ、ゴルバチョフなどベルリンの壁崩壊の立役者が招かれており、様々な式典が開催されていました。森鴎外の舞姫にも出てくる有名なブランデンブルグ門、ウンターデンリンデン通りは、かつては東西の壁に阻まれ近づくことも出来ませんでした。しかし、これらの地域にはもはや壁は泣く、わずかに道路上に市電の軌道のような物がその記念碑として埋められているだけで、従事を偲ばせるものは何もありません。ベルリンの壁があった地域は今や再開発の真っ最中で、町中のあちこちで槌音が聞こえてくるような状況で、ヨーロッパ随一のビジネス街に生まれ変わることを目指して、莫大な資金が投資されていました。毎年1兆円を超える金額が、10年以上にわたってベルリンを始め旧東ドイツ地域に投資され、遅れていた社会資本整備につぎ込まれているということでした。ところが、これほど大規模な投資をしても、まだ西側との差は完全に埋まったとは言いきれないのが現実です。事実、私のようなよそ者でさえも、ベルリンの壁が無くても、東側と西側の違いがすぐに分かるのです。その違いは雰囲気にも現れてきます。同じような建物でも何処か薄暗くて彩りが感じられず、道行く人も何となく活力の無い様子で、裏寂れた雰囲気が漂っています。これは雰囲気だけのものではなく、社会資本の整備の状況にもはっきり差となって現れています。例えばアウトバーンと言えばドイツを縦横に結ぶ速度無制限の高速道路として有名ですが、東側のアウトバーンを走ると、とんでもなく車が振動してびっくりしてしまいます。ヒットラーが作って以来、殆ど整備をしたことが無かったのでしょうか。道路が荒れ果てており、とても高速で走れるような状態ではありません。あちこちで舗装の整備工事が行われていましたが、西側と比べるまでもありません。そう言えばかつて京都でも共産党が政権を取っていた時代には、京都の道路の悪さは有名で、他府県から車で京都に来る場合には車のガタガタいい出したら、そこが県境だと言われたものでした。府政の転換した今ではそのような事はなくなりましたが、洋の東西を問わず、共産党の政権を取った町では社会資本整備は全く出来ていないということを今更ながら実感した次第です。

今年の京都市長選挙をにらんで、共産党が何やら聞こえのいいことばかりを宣伝しているようですが、政治の本質は”言っている事”ではなくて、”してきたこと”で判断をしなければなりません。京都では22年前まで実際に共産党が政権を担っていましたが、いったい彼らは何をしてきたのでしょうか。他の都道府県が、高度成長時代に社会資本整備を次々に行ってきたのに、本府では全くと言ってよいほど、それが手付かずの状態であったのは府民みんなが知るところです。ところが、そうした時代から22年も経ってしまうと、段々そうした事実も風化してしまいます。特に若い年代の方にとっては、殆どその実態を知らずに暮らしておられるのも事実です。現実に府議会を見ても、私を含め、蜷川知事の時代に議席を得ていた者はほとんどおりません。
私のドイツの現状を知るにつけ、京都においても共産党支配の時代にいったい何が行われてきたのか、もう一度みんなが思い出す必要があると感じました。
ところで私のドイツ訪問の目的のひとつは老人ホームの視察にありました。ドイツでは今から3年前に介護保険制度ができ、日本もドイツの制度を参考にして法整備をしてきと聞いています。そこで、先進国の取り組みの様子を現場に出向いて、教えていただこうと考えたからです。日本では、今年4月からの施行を控えて、与党から介護保険の手直しが提案されました。その中のひとつに家族介護に対する介護手当の支給というものがあります。
これは、自分の親の面倒を見ても1円の支給も無いけれど、他人に見てもらう場合にはお金が支給されるというのでは、親不孝を助長してしまうことになりかねない、という国民感情に配慮したものです。しかし、これは反対される方もおられます。その理由は、家族介護への支給を認めたら、女性を介護に縛り付けてしまうことになるから、反対だというのです。

しかし、私はこの考えには根本的誤りがあると思っています。この考えの前提には、社会を抑圧する側と抑圧される側という風に、二極対立として捉える、唯物史観が根底にあるのは明らかです。ところが現実には彼らが言うように、決して対立するものばかりではないのです。介護保険のモデルとなったドイツではいったい家族介護についてどう考えているのでしょう。私は訪れたベルリン市内の住宅地のど真ん中にある老人ホームの園長さんに質問してみました。するとこういう答えが返ってきました。
「ドイツにおいても介護の基本は勿論家族にある思っています。まず家族が家族の面倒を見る。これは当然のことです。従って家族介護にも手当を支給しています。しかし、その家族の介護もおのずと限界があります。末期になれば、家族だけではとても見きれない状況も出てきます。そうしたときのためにこのような施設があるのです。しかし施設に入られても家族の絆を如何にして守ることが出来るのか、ということを一番に考えています。例えば、家族が少しでも訪問しやすいように、出来るだけ便利の良い場所にこうした施設を作ったり、子供が孫を連れて遊びにくることが出来るように、ミニ動物園を老人ホームの中に作ったり、いろいろな仕掛けを作っているのです。・・・・・・」
このように、ドイツの老人ホームで伺った話はいたって常識的なものでありました。ドイツにおける介護保険も巷間言われるような、女性の解放のために社会による介護をするのではなくて、家族の絆を守るためのものであったのです。私も非常に納得のいくものでした。こうしたことを考えれば、今日政府が家族介護に対しても、手当を支給するという方向に転換したのも肯けるわけです。このように洋の東西を問わず、介護保険の基本は家族の絆をどのように守るかというところにあるのは明らかです。
私は、平均寿命が大幅に伸びたことにより、90歳の親の面倒を70歳の子供がみるという老人介護の実態を考えると、介護保険や介護サービスの必要性は勿論のこと、その前提となる家族あるいは地域社会という「人間の絆」をこの際点検をしておくべきだと考えています。つまり、介護保険により介護サービスの提供を受けることができて、家族は救えても、本当にお年寄りが一番ほしがっているのは、家族や友人との心の絆であって、介護保険は決してこれに変わるものではないということです。
例えば、一人暮らしのお年寄りは、介護保険が適用されれば、身の回りの世話をしてもらえるので、確かに生活はし易くなることでしょう。しかし、このお年寄りが本当に求めているのは、単に身の回りの世話のサービスをしてもらうことではなくて、自分の話を聞いてくれたり、一緒にご飯を食べたりしてくれる家族や友人なのです。介護保険はこうした心のケアまで面倒を見てくれるものではないのです。不自由な体の面倒を見てくれても、心の世話まですることは出来ないということなのです。この心のケアは、家族や友人しかできないのです。
問題は、家族や友人から疎外されたお年寄りが、これから益々増えていくにもかかわらず、この家族や近隣地域をどう守って行くかということについての、議論が殆どされていないことです。介護保険の円滑な適用を行うためにも、この問題は避けて通れない問題であると思います。
そのためには、福祉に対する基本的姿勢について、見直しをしなければならないと思います。今では福祉と言うと、共産党に代表されるように、国や自治体の義務ばかりを追求し、国民に対しては不平不満を煽り立てる人々がいます。福祉の拡大は権利の追及で当然のことだと主張する人もいます。しかしこれは、先ほども述べたように、社会を搾取するものとされるものという対立で捉えるマルクス主義特有の考え方であって、決して国民を幸せにするものではありません。どんなに政策が充実しても、これでは満足することが無く、後には不平不満しか残りません。こうした誤った福祉や行政に対する考え方では、行政需要は止まるところを知らず、また国民は不満ばかりで誰も感謝せずということになってしまうのです。この考え方では、借金と不平不満しか残らず、社会は崩壊してしまいます。

私はこうした社会を対立させ不満を煽る考え方から、社会を自分を含め一体のものとして捉える必要があると思っています。そのためには家族や友人に対してと同じように、社会に対して感謝と寛容の気持ちを持つようにしなければなりません。これは、日本人としてはいたって常識的で、当たり前の感覚だと思います。以前はこのようなことを議論せずとも皆当たり前であったのですが、戦後社会の中では、権利意識を追求することばかりが優先され、自分たちの社会を守る義務があるということを教えられずにきたために、利己主義者が横行し、家族や地域社会の崩壊に拍車がかかってきたのです。
今、介護保険の導入を機に議論しなければならないのは、こうした福祉に対する根本的な姿勢をもう一度見つめ直し、皆様に訴えるということではないでしょうか。ドイツを訪問してこのことをより一層強く感じたものでした。
新年あけましておめでとうございます
参議院 議院運営委員長 西 田 吉 宏

皆様には御家族お揃いで新春をお迎えのことと、心からお慶び申しあげます。
21世紀の夜明けともいうべき本年に私も皆様のお力添えに支えられながら、11年目という門出にあたる新年を迎えることができました。
これも偏に皆様方の格別の御支援、御指導の賜ものと深く感謝申しあげます。
御承知のように最近の社会情勢は、経済問題を始め、著しく進む少子高齢化社会、家族の絆がうすれゆく核家族時代など、社会保障に関する課題が山積いたしております。
このような背景のもと、国政におきましても従来の”経済再生”から、”理念ある経済新生対策”を掲げて、わが国の経済を支えている基礎ともいうべき、中小企業の経営強化に向けた施策や、介護保険法の特別対策などの審議を重ねて参ったところであります。
なお御承知のように、昨年末の146回臨時国会におきまして、新しい試みとして、わが国初の「クエスチョンタイム」の導入を実施し、各党首による諸課題解決に向けての論戦が行われました。
私も、皆様のあたたかい御支援をいただきながら、参議院議院運営委員長として、諸課題の取組を致しておりますが、「皆様の声と思い」を、国政へ届ける架け橋とさせていただき、微力ではございますが、全力を傾けてまいる決意であります。
今年は、2月に京都市長選挙もございます。西田昌司府会議員と協力しながら、ゆとりと潤いのある住民生活が実現できる安定した政治情勢の実現に向け、懸命の努力を致しますことをお誓い致しますとともに、是非皆様のご理解とあたたかい御協力をお願い申し上げます。
今年は”辰年”。古来より”龍の雲を得る如し”と申しますが、皆様方が雲を得て天に昇る龍のように、お元気にご活躍されますことを祈念申しあげまして、新年の挨拶といたします。
-2000年のお正月の過ごし方-

「きもので始まる2000年」といった写真コンテストの広告のキャッチフレーズが目につきました。そういえばレディメイドの男物のきものが百貨店で展示販売されていました。
しかし男のきもの姿はなぜか世間の目をはばかっているようです。きものを着ていて笑われないのは噺家、囲碁将棋の棋士、相撲の力士、結婚式の新郎と父親ぐらいなものです。男がきものを着て町を歩くのは何か気恥ずかしいものがあります。儀式の時でさえ男がきものを着ることはめったにありません。世間の目が冷たいような気がします。「何か特別な事があるのかな」「一人目立とうとしているんでは」と勘ぐられてしまいます。
でも20年前までは男はきもの姿は当たり前だったんです。確かに男女問わずきものは機能的ではありません。車を運転するのも不便だし、雨の日に濡れると後の始末に困るし・・・・・・などの理由できもの離れが進んでいったように思われます。しかし、それ以上にきもの業界の姿勢に問題があったのではないでしょうか。製品の高級化・高額化でしのぎ、きものについては高額高級品でなければきものでないといった意識を植え付けてしまったのではないでしょうか。ハレの儀式の日に低額実用きもので出ていったらバカにされ、高額高級のきもので出ていったらうわべの賞賛とはウラハラにきびしい視線にされされる。これでは「きものなんか着るものか」と思うのは当然のことです。だれもきものを着ないから世間の目が冷たくなる。世間の目が冷たいからだれもきものを着なくなる。この悪循環を断ち切らねば、きもの離れは防げません。
これはきものだけではなく、米離れ、魚離れ、畳離れ、日本酒離れ、旅館離れなど総じて和風の生活様式に「離れ」現象が生じているのではないでしょうか。これはひいては日本文化を否定することになるのではないでしょうか。米を食べ、日本酒を飲み、畳の部屋で寝ていても白い目で見られないのに、男のきものだけは白い目で見られる。このようなことでは日本における伝統文化と父権の継承もおぼつきません。
民族衣装でもあるきものを普及させるキャンペーンが展開されて久しいですが、いよいよ実行に移す時ではないでしょうか。この秋、立命館中学校の文化祭では、ゆかたによるきもの体験を中学生が取り組んでいました。新入社員の研修にきものの着付けをとりいれている企業もあります。
さあ、奮起して2000年お正月は男のきものを流行らそうではありませんか。タンスの奥からウール着物を引張り出して初詣に出かけてみては。男がきものを着れば凛々しい物があり、世の女性たちもほれ直し、彼女らもきものを着る機会が増えるのではと願っています。
編集後記
明けましておめでとうございます。
昨年も変わらず暗い話題が続きました。商工ローン・新興宗教や「お受験殺人」等、人の弱みに付け込んだ様々な事件が噴出いたしました。
『……目出度くもあり、目出度くも無し』と言う言葉が強くよみがえります。
機関誌【Show You】は今年も、『教育』や『経済の仕組み』・『社会の有り様』に「鳥の目・虫の目」を心しながら取り組んでまいります。
編集室 松本秀次
国旗国家方に寄せて

先ごろ、いわゆる国旗国歌法が成立致しました。これにより、法律上正式に日の丸が国旗に、君が代が国歌となったわけです。もともと、この法案が提出されたきっかけは、ご存知のように広島県の世羅高校で、卒業式に日の丸を掲揚し君が代を斉唱すると言うことを巡って、教育委員会と教職員組合が対立し、その間に立たされた校長先生が、その立場に苦しみ、自殺をしてしまったことに端を発しています。こうした混乱の原因は法律上国旗と国歌の定めがないから、こうした混乱が生じてしまうからなのだ。だからこうした混乱を防ぐためにも、正式に法律上の定めを設けておくべきだ、と言うわけで今回の成立となったのです。なるほどこうした世羅高校のような混乱は、全国何処に行っても良く聞くことでした。
私たちの地元の南区でも、こんなことがありました。ある小学校の6年生の授業で、日章旗、星条旗、ユニオンジャックの下にその旗の国の名を書きなさいというテストが行われました。当然のことながら、それぞれの旗の下に、日本、アメリカ合衆国、イギリスと書くのですが、採点をされて返ってきた答案用紙を見ると、バツがついてあります。みなさん、何か間違いが分かりますか。何と日の丸の下に日本と書いたことが間違いになっているのです。正解は日の丸は法律で日本の国旗とは決まっていない、従って、どこの国の旗でもないというのです。こんな信じられないような授業が、実際に行われていたのです。
また、ある中学校では、こんなことがありました。卒業式を前の日に控えて、卒業式の練習が行われているところへ、ある先生がやってきて涙ながらに訴えました。「明日は卒業式です。教育委員会から君が代を唱えと命令されています。でも先生は、君が代と日の丸の名のもとに、あの戦争で多くの人が死に殺されたことを思うと、とても君たちにそれを命じることはできません。君たちももう大人だから、自分の判断で歌いたい人は歌いなさい。でも歌いたくない人は歌わなくても構いません。」いったいこんな話を聞いて誰が歌うことができるでしょう。
もちろん、こうした事態は現在では無くなっていますが、広島だけでなく、京都においても教育の現場では、法制化していかないことをよいことに、まさに反国家教育とでも言うべき事がまかり通っていたのです。さて、日の丸や君が代の法制化に反対した人々の意見を伺っていると、大別して次の二つに絞られると思います。そのひとつは、要するに日本の過去を否定すると言うものであり、今一つは思想信条を個人に押し付けるなと言うものでしょう。
過去を否定するような人は次のように言います。日本は過去にアジア諸国を侵略した。敗戦によって日本はまた新たに生まれ変わったのだ。従って、血塗られた過去につながる一切のものは当然否定すべきである。こうした三段論法のもとに、日の丸や君が代は当然否定されるべきものと彼らは主張します。
なるほど、戦後の社会のあり方を考えてみればまさにこの意見は、的を得ていると言えます。日本の過去が本当に、侵略国家で血塗られたものかは別として、(もちろん私はそうは思っていませんが)あの敗戦により日本は過去と決別して生まれ変わったのだ、とする人は結構多いのではないでしょうか。これは、日本の原点を昭和20年8月15日として考えるもので、マスコミ始め多くの日本人が、理屈抜きにそう思い込んでしまっていると言ってもよいかもしれません。戦争が終わって、日本は平和国家として生まれ変わったのだ。そのお陰で、日本は自由で、豊かな国になることができた。過去をきちんと反省することが、日本の平和国家としての原点だ。その象徴が現在の憲法だ。改憲なんてとんでもない。このようにお考えの人も結構おられます。またそのように教育をされてきたのです。
確かにあの戦争により日本が過去を否定し、決別したのなら当然のことながら、日の丸や君が代は廃棄されるべきです。また8月15日を建国の日とすべきだとも思います。しかし本当に日本人は過去を否定して、日本人として生きて行くことができるでしょうか。人間が生きて行く上で「自分は何者か」ということほど大切なことはありません。自分の原点やルーツをしっかり認識して初めて、生きる力や生き方について価値観を持つことができるのです。そして「自分は何者か」ということを示してくれるものが、個人で言えば、先祖であるし、国で言えば歴史と言うものでしょう。我々が日本人として生きて行くには良いも悪いも含め、まず歴史を否定するのではなく、肯定することから始めなければならないのです。それは親を否定しては自分の存在が無いのと同じことです。日本の国の過去を否定する人に愛国者がいないのは、親を否定するものに親孝行ができないのとまったく同じで、要するに大人になりきれていない子供と同じです。過去否定の上には未来は築けないのです。 また、日の丸君が代の強制はすべきで無いと言う人は、このように言います。君が代を歌う自由があるのなら歌わない自由もあるはずだ。その自由を奪うべきで無い。それが真の自由主義であり、民主主義だ。 なるほどこれも一理ありそうです。しかし、これもつまるところ詭弁であるとしか言いようがありません。実は国旗国歌法が審議されていたときに、私は昌友塾(毎月六孫王会館で開いています)でこのことについての討論会を行いました。このときある20代の女性の方はこんな話をされました。「オリンピックやサッカーの試合を見ていて日の丸がセンターポールにあがるのをとても誇らしく見ていました。君が代が流れてきたとき、私は自分も一緒に歌いたいと思いました。でも私は歌うことができなかったのです。何故なら今では私は只の一度もまともに君が代を教えてもらったことが無いからです。これに反対をされる人は、歌うのも自由、歌わないのも自由だと言われます。だけどこれは大嘘です。だって私は君が代を歌う権利さえも与えられずに来たのですから。」いったいこの言葉に、学校の先生方はどんな反論をするのでしょうか。
今回の国旗国歌法の議論によって明らかになったのは、野党やマスコミの中にはまだまだ戦後の呪縛に縛られたままの方が結構多いということと、マスコミ等の報道にもかかわらず一般の国民は良識のある方が結構多かったということです。「こんな法律をいまさら作らなくても、明治以来ずっと、日の丸や君が代を国旗国歌として扱ってきたのですし、その起源をさかのぼれば、千年を超える歴史がどちらもあるわけで、いまさら何を言うのでしょう。また、日の丸君が代が国旗国歌でないなら、どんな旗や歌がそれにふさわしいと言うのでしょう。」こう言う声の方が多かったのは大変うれしいことでした。事実マスコミなどのアンケートを見てみても、圧倒的多数の国民がこれを支持していました。しかしこれは歴史や伝統は理屈を超えて国民に浸透していくものなのだと理解しても良いのでしょう。むしろ、敗戦から今日どんな時代に在っても、常に、これを守り伝えようとしていた人々一途な努力がそこにあったと考えるべきではないでしょうか。そうした努力に感謝しつつ、私も次代に向けてその責任を果たしたいと思うのでした。
前号の「子育て奮闘記」には、多くの読者の皆様から様々なご意見が寄せられました。お読みになって親と子の関係のある部分が垣間見えたようにお感じになったことと思います。編集室があの記事を掲載した一つの理由は、今の親子の”関係の在り方”を皆様に考えていただきたいと思ったからでもあります。
世の中には、テレビのホームドラマのように仲のよい友達関係や個性や権利の尊重の余りに互いに干渉し合わない関係、また子どもをペット化するような一方的な溺愛やその反対の放任など、様々な親子の関係があります。このような関係が健全な日本の親子だとは思えないのです。21世紀を迎えようとする中で、どにょうな親子関係を結んでいけばいいのか、どのような価値観を地域は子ども達に伝えていけばいいのか。ShowYou編集室ではこの点についても様々な議論の機会を設けたいと思い、「昌友塾」(月に一度開催)でもメインの主題にしております(一度お出かけください。六孫王会館で第三火曜日です。)
前号の記事もこの塾での話題の中から出てきたものです。そのため、話の最初の部分だけを掲載しました(記事をお寄せいただいた方にもご迷惑をお掛けいたしました)。また、お読みいただいた読者の方から多くのご意見をいただきました。その中から、一部を編集室の責任で再構成し、記事として(投書ではありません)掲載することにいたしました。またご意見を頂ければ今後とも、この欄でご紹介したいと思います。
私は、高校生のバイクの問題については、「子供の命は親が守る」が第一だと思います。それゆえ、「子供の命は親に任せればいい」とも思います。したがって基本的に学校は出来るだけこのような問題には、関わる必要はないのではとも思います。しかし、これを家庭や学校、地域社会とのつながりで考えてみればどうでしょう。まったく違った観点が出てくるのではと思うのです。”バイクの問題は校則に違反しているが、社会では問題がないから”という考え方は一面的に過ぎないかと思います。(もっとも、お子さんとの話し合いの中で悩まれた末の、苦悩の決断だったと思います。短い会話文の中に、お母さんの苦悩があったこと、それはよく分かります。私も実際の場面ではどうするだろうかと思います。)
それでも、私は学校や地域社会と家庭は、子供を育てるという面でもつながっていると思うのです。世のお母さん方にはそこのところも考えて欲しいと思うのです。というのも、そのつながりの原点は、価値観だと思うからです。家庭や学校そして社会(特に、我々が住んでいるこの南区ですが)は、健やかで伸び伸びとした中味が、市民社会の形成者として人から尊敬を受け、よりよい家庭を築く人になって欲しいということだろうと思うのです。親は世の常識を押し付け、子供はそれに反抗する。この関係の中で、子供たちは私達の社会が持つ価値観に気づき、伝えていってくれることと思います。物分かりがいいだけでは、社会の価値観や伝統は子ども達に残せないと思うのです。
家庭と学校そして地域が、子育てにおける関係を見直し、互いの責任と役割をどのように果たしていけばいいのか。私はどうすればいいのか、子供はまだ小さいですが寝顔を見ながら考えています。考えるきっかけを与えていただきまして感謝しています。
戸田修三 9月5,6日の信州一泊二日旅行に唐橋の一員として参加し、天候にも恵まれ、楽しい時間を過ごさせていただきました。残暑の厳しい京都に比べると、さすがに信州は朝晩涼しく、広々とした山の険しさ、広がる田園地帯など、その自然の豊かさを再認識しました。
信州へ入る前に観光客で賑わっている飛騨高山を車中より見学し、少年時代に自分の育った町のことなどふと懐かしく思い出されました。
上高地では河童橋、梓川、穂高と自然の雄大さや梓川の清らかな流れと水の冷たさに驚かされました。ここでは自家用車の規制がされていましたが、バスの出す排気ガスの方にも問題があるのでは・・・・・・と少し考えさせられました。宿泊した白樺湖のホテルは、前がスキー場になっており、その向こうは蓼科山などのとてもなだらかな山々があり、険しい山の多い信州にしては数少ない風景ではないかと思われました。
夜の宴会ではカラオケもあり大変盛り上がりました。「数は力なり」「継続は力なり」という言葉があるように、私を含め庶民の力も集まれば大したもので、大切にすべきだということを再認識させられたと同時に、西田会と昌友会の友好、親善の益々の必要性を実感いたしました。
二日目はビーナスラインから岡谷IC、梓川SAから須逆長野東ICを通って善光寺へと行きました。ビーナスラインからは富士山も見え、それはまるで一服の清涼剤のような感じを受けました。
長野冬季オリンピック会場を車中より見学し、善光寺の見学ではその立派な建物と歴史、信仰、伝統の重みを感じ、心洗われる思いがしました。
立派なホテルでの昼食の後、野沢菜センターで見学と買い物をしましたが、そこで野沢菜が元々京都から持ってきたものが始まりだったことを知り、京都に住む私には少しの驚きと嬉しさを感じました。
その後、無事京都まで帰りましたが、今後は昌友会の方々も参加されてはいかがでしょうか?きっと何か得るものがあると思います。
最後になりましたが、今回の旅行にあたりお世話になりました皆様方に厚く感謝申し上げます。
-ゆかたを着てパープルサンガを応援しよう-
今年の夏は露出ファッションが大流行。キャミソールとショートパンツの女の子がゾロゾロと四条河原町、京都駅、北山通を歩いていました。このショートパンツの丈は、今年は一段と短くなった様な気がします。どこまで見せれば、あなたたちは気が済むんですか、と言いたくなる様なスタイルです。
高校生から20歳前後までこのようなスタイルをしており、さすがに23歳ぐらいになるとやめますが、こんな女の子に、反対に包み隠すことの美しさを教えるにはどうしたらいいのでしょうか。
そうです。彼女たちにきものを着せればいいのです。包み隠す美の代表的なきものを。それにはゆかたから始めていってはどうでしょうか。若い女性にゆかたを着せていって、包み隠すという「ゆかしさ」「上品さ」を教えていけばいいのではないでしょうか。今、若い女性が生涯で初めて着るきものが振り袖になっているのではないでしょうか。最高位にランクされている振り袖を着るには、それなりの着付け方と小物などの約束事があり、窮屈な思いをしているのではないでしょうか。身体的にも、経済的にも締め付けられて着たきものを再び楽しんで着ることはないでしょう。それよりも自由にゆかたから着はじめて、小紋や紬を楽しむ様にしたらいいのではないでしょうか。
さて、この夏、京都染織青年団体協議会による粋なイベントが行われました。『ゆかたを着てパープルサンガを応援しよう』といった企画です。当日、ゆかたを着て西京極グラウンドへ行くと、入場料が\800になるのです(通常は\3,000)。8月26日、新たに加茂監督と三浦知をむかえ、快進撃のパープルサンガを応援しようと、グラウンドには15,000人が集まりました、もちろんゆかた姿の女性、カップルも多く、和装振興(?)、いや、ゆかたを着るチャンスを増やしてくれました。そこで見た女性のゆかたの色・柄は様々なものがあり、白地に紺だけではありませんでした。バリエーションがうんと増え、チャパツ・ガングロの若い女の子にも素直に受け入れられ、人気の的となっています。これをどこまで長続きさせて、つぎのきものを着せていくか。ほっとけば直ぐに脱ぎたがる女の子をいかに引きつけていくかが、今後の日本文化の和装を見直す大きなキーワードとなるのではないでしょうか。
でも、「ゆかたの下にはブラジャーを着けてほしくないな」と、思いつつブラジャーとショートパンツが丸見えのシースルーのゆかたにど肝を抜かしているのは瓦一人だけでしょうか。

私は今日の京都府の財政状況は、待ったなしの状態になっていると思います。今の段階で、来年度すでに四百六十億円に上る収支不足が指摘され、さらにこの状態が今後数年間も続くことが予想されているのです。その一方で、収支不足の穴を埋める収入の予定もつかず、頼みの綱の財政調整基金も事実上底を尽いています。その他の基金を合わせても来年度の収支不足分を埋めるのが精一杯の状態になっています。自治省の管理状態になることを意味する財政再建団体には、標準財政規模の五パーセントを超える赤字を出したら指定されるということですが、京都府では凡そ二百数十億円の赤字がその目安です。つまり本年度中に何らかの抜本的な方策を立てない限り、京都府は来年度にもその指定を受けることになるのです。
ところで、共産党は大型公共工事をしたことが府の借金を増やし、財政危機を招いたと主張しています。しかしこれは財政の仕組みそのものを理解していないことの現われでもあります。公共事業に伴う府債の債還については国からその大部分が交付税措置されており、実質的に府の財政を圧迫させるものではありません。むしろ急激な税収減のため基金だけでは対応し切れなくなったということなのです。このことから考えてみても、共産党は何ら知事を攻める立場にないのは明らかです。なぜなら、彼らこそバブルの絶頂期に、今頼みの綱となっている基金の積み立てを盛んに非難していた張本人だからです。共産党のこうした無責任な主張は、まさに天につばするものであり、彼らの主張通りに予算を執行していたら、もっと早い時期に京都府は財政破綻を来していただろうということは疑うまでもありません。
今日の財政危機は、京都府のみならず、東京都、大阪府、神奈川県などいわゆる大都市を抱える自治体に共通した問題であります。それは都道府県の税収の一番の柱である、法人府民税や法人事業税など企業の取得に対して課税される税が、ここ数年来の不況により著しく落ち込んでいることがその一番の原因です。大都市を抱える都道府県では、好況時には企業の業績が良いため、税収も大幅に伸びてまいりますが、不況がこうも続きますと、毎年の税収は減る一方なのです。いわゆる過疎県では、もともと企業課税に頼れる税金の割合自体が少ないため、不況で税収が落ち込むといってもその変動の幅は、案外少なくてすむのです。しかし企業課税の割合の大きい大都市圏の都道府県ほどその落ち込みが大きいのです。もっとも、そうした税収の変動を補填するために地方交付税などで調整される仕組みになっているのですが、政府自身もそれ以上に財政困難な状態になっており、その全てが補填されるとは言えません。したがって根本的には、こうした税制や自治体の財政の仕組みそのものを、政府が検討し直さなければなりません。しかしだからといって、政府が財政改革をするまで待っていたのでは、府の財政は破綻してしまうのです。
今必要なのは共産党のような無責任な財政運営批判ではなく、これから如何にしてこの危機を乗り切るかということなのです。バブル時代に共産党の主張していたような政策をそのまま知事が実行していたのならともかく、現在の財政難を招いたのは、知事の責任というよりも、むしろ日本全体が大きな転換点に差し掛かっていることから生じる問題であると私は思っています。したがって問題は、この転換点をどれだけ真剣に捉え、改革するかという知事の姿勢(今後の決意)こそ、問われるべきものであると思うのです。
これから京都府では今後数年間、経常的に毎年四百から六百億円単位の歳入不足が予測されています。収入の増加は国の抜本的な地方財政の改革が行われない限り、これに見合う分の増加を見込むことは出来ません。そこで、残る方法は、歳出面を如何に削ってこれを確保するかということ以外にありません。しかもこの状態が数年間は続くと見られるため、一過性の見直し策ではなく根本的な改革をしなければならないのです。そしてその金額も、十億や二十億ではなく、数百億円単位の歳出カットをしなければ意味がありません。もちろん、ちりも積もれば山となるという言葉があるように公共事業の一時凍結を含め、一つ一つの事業の見直しをしなければならないのは当然です。しかしその結果の削減金額が数百億円単位になるためには、京都府全体で三千二百億円に上ると言われる人件費の見直しに手をつけることは避けられないと思うのです。また、公共事業や様々な助成金など、予算のうちに占める割合の大きなものほど、その見直しはシビアなものにならざるを得ないと思います。もちろん議会とてその例外でいられるとは考えられません。このこともこれから各党で議論をしなければならないものと思います。問題は我々政治家がこうした状況を認識し、いち早く府民に知らせ、この危機を脱出するためのリーダーシップを如何にして発揮するかということです。状況認識を誤り、後手後手を打っていたのでは危機はますます拡大してしまいます。民間の企業経営者も皆京都府と同じような厳しい状況の中で経営改善に努力を致しています。その要諦はまずこれ以上赤字が出ないように、一挙に構造改革をするという事です。売上が落ちたら、自分の身の丈に応じた経営規模に合わせなければ、どんな大企業でもつぶれてしまいます。
前門の虎、後門の狼と言う言葉があるように、まさに進退きわまった状況下にあります。こうした状況から脱出させるものは、まさにリーダーの見識と勇気以外ありません。歴史を振り返っても、新しい歴史を築いてきたのはリーダーの献身的な努力と勇気の積み重ねではなかったでしょうか。今日のようにありとあらゆる情報が行き交い、価値観の多様化した時代になるほど、リーダーの決断は鈍ってしまいます。それは必要以上に情報が入り込み、何が正しいことかという基準が曖昧になってしまうからです。その結果、決断が遅れ事態はますます取り返しのつかない方向に流れてしまいます。
ではそのリーダーの決断を曇らせる情報とは何でしょう。それは大局を見ようとしない無責任な声でしょう。共産党の主張など、まさに然りです。また、先の大戦の時のマスコミの報道なども冷静な視点からではなく、国民の意識を煽り立てるだけのものでしたし、近くでは三年前の住専に対する公的資金の投入に対する報道の仕方も、もう少し冷静にしていたら今日の金融危機を未然に防ぐこともできたのではないでしょうか。少なくともこれだけの公的資金を投入せずに済んだでしょう。
危機はいつも我々の身の回りに存在します。しかし危機があることが危険なことではなく、危機を危機と感じずにいることが本当に危険なのです。そしてリーダーの役割とはまさにこうした本当の危機を知ることであり、危機回避の為の勇気ある決断をすることだと思います。皆様のご理解をよろしくお願い致します。
(平成11年7月1日の本会議での質問の抜粋を加筆)
本当の幸せとは
- 西田昌司著「政論」によせて -
黒野 實男

私は、現在、宇治田原にてアルミ鋳物工場を経営している者です。先日、西田先生とお話しする機会があり、その中で「今の生活は、決して楽ではありませんが、辛いばかりでもありませんよ!」と申しました時に、西田先生が、「そのお話しを短い文章に書いていただけませんか」とおっしゃられました。人様に読んで戴ける文章など到底書き表す事などできませんが、小市民の極々小さなこぼれ話しとして書き記してみます。
私は昭和11年生れです。少年期は多感な時を、戦後の物の無い時代に過ごしました。両親は8人の子供達を育てるため、昼は海に漁に出て、夜は、父親は、漁のための道具の手入れ、母親は縫い物をしたり、家事をしたり、休みなく、昼夜を問わず、働いておりました。それでも、お腹いっぱいになった記憶はあまりありませんし、家族で、旅行したり、おもちゃを買ってもらったという記憶もありません。この様な事ばかりを書けば暗くて、辛い事ばかりの様ですが、決してそうではありませんでした。父親が少しの酒に酔いながら話す、ウダ話しが好きでしたし、母親の手伝いをして、褒めてもらうのも、とても嬉しかった。友達同志で、創意工夫をこらして、遊んでいる時には、時間を忘れてしまう程でした。周りの皆が同じ様な、境遇だったので、空腹というものを除けば、貧困もそれ程辛くなかったものでしょう。
それ。から、私は中学を卒業すると仕事に就きました。私の上の兄3人と、すぐ下の弟までは、同じ様に、高等学校に通わせてはもらえませんでした。それから、男兄弟5人が、それぞれで仕事をしていましたけれど、どうせなら、皆で集まって、商売をしようと話し合いまして、鋳物屋を始めました。昭和37年でした。その頃は一生懸命やれば、仕事には事欠きませんでした。ですから、兄弟皆昼夜を問わず働きました。幼い頃に、両親の姿を見て育ったので、何も辛い事はありませんでした。それよりも、自分達が頑張った分だけ、物や、形になって残っていきましたので、その喜びは、何ものにも変えられませんでした。そして、作れば売れるという高度成長期にささえられ、商売も順調に行きました。
今考えますと、昭和の終り頃には、物や、金だけが不変の尺度の様になり、それとひきかえに失ったものも大きいと思います。
それからバブル景気が始まりました。その頃には、物の価値すら、金だけが尺度になってしまいました。例えば、ポロシャツ1枚にしましても、スーパーでは2千円で買える物が、胸の辺りに、小さなマークがあるというだけで1万円していました。でも多くの人達が、1万円のシャツを好み、2千円のものは、シャツではないと言っていました。無論私もその中の1人でありました。
不動産や、株に投資している人達は、何故儲かるのにしないのかと、投資しない人達を変人扱いしておりました。この頃、バブル景気の末期には、日本経済の拡大は、未来永劫に続く不変の真理だと多くの人達が信じ、物と金を、競い合って追求し、真の価値を見る目を失ってしまいました。ゴッホの『ひまわり』が、バブル絶頂期にいくらの値段が付いたのでしょうか?10年程しか経っていない現在、いくらで売れるのでしょうか。
それから、バブルが崩壊し、物の値段が、どんどん下がりました。所得もどんどん下がり、街は仕事を探す人達であふれております。一家の主の家出、自殺が急増しています。
だけど現在も、暗くて辛い事ばかりではないと思います。空腹を満たそうとして、パンを買う事ができない人達が、どれ程いるのでしょうか。酒が飲みたいと、二級酒、発泡酒が買えない人達がどれ程いるのでしょうか。
私は、良く有料道路を利用しますが、以前にも増して、料金所の方々が、おはようございます。ありがとうございます。と声を掛けて下さいます。一生懸命やらないと、職も失うという危機感もありましょうが、どうせやるなら、楽しそうにやる方がいいし、その方が気分がいいとおっしゃられます。生きる事の価値をそこに見いだされているのではないでしょうか。
大企業のエリートの中でも、多くの人が、大企業病にかかりました。企業のバッチを胸に付けているだけで、廻りの人達から敬まわれ、下請企業からは、特別の処遇を受け、傲慢になった人たちも、不況風の中、様々な要因で、職を失いました。その時に、自分が虎の威を借る狐であった事に気づかれました。そして、つまらない自尊心を傷つけられ、墜落して行く人たちもありましょうが、その辛さをバネに、他人に頭を下げて助けてもらう人、家族で協力し合い、新しい価値を見つけていく人、色々な物、事に感動し、心を豊かにしていく人達が、増していっているとしたら、また昔の良さを取り戻し、現在の豊かさを享受できるとしたら、これは神様が自惚れた日本人の頭に冷水をかけて下さったくらいの事ではないでしょうか。ここまで、書き綴っていきますと、西田先生のおっしゃる「児孫のために美田を買わず、ただ志を残すのみ」という言葉を思い出さずにはいられません。私には残してやる程の美田もありませんし、僅かな財産を他人のために使う勇気もありません。
しかし、人を大切に思い、人に大切に思っていただける喜びを孫や子に話つづける事の大切さを思う私にとって、その言葉は、まさに私に勇気を与えて下さいました。
子育て奮闘記
- 昌友塾に参加して -
昌友会 柿本 祐子

「教育問題について」むずかしそうなタイトル、6月15日に行われた昌友塾に初めて参加させていただきました。都合が付かず遅刻してしまい昌司先生の最初のお話は聞かせていただけなかったですが、参加されていた方々からの活発なご意見をお聞きしていました。
(---場違いかもしれん・・・・・・レベルが違う・・・・・・等々と思いながら・・・・・・)
その中で「切れる子供の低年齢化」という報告がありました。小学校の2年生のクラスで授業ができない状態になる、教室内を歩き回る、教壇を蹴りたおす、教室から出る。一人の子供だけでなく、複数の児童達が・・・・・・。
想像もつかない!!なぜそんなことが起こるの?と様々な原因が上げられていましたが、先生がやさし過ぎてあまり怒らない、先生を先生と思ってない、お兄さんの感じでしかないのも原因の一つとして上っていました。
低学年で恐そうな先生も困りますが、先生を何やと思てんのかな?と考えさせられてしまう報告でした。
話は変わりますが、長男が一昨年あたりから「16になったらバイクの免許取っていい?」と再三言っていました。「何考えてるの法律上は認められてても学校は禁止やろ、止めとき」と、誕生日が近づくにつれ「なあ免許取るだけやったら・・・・・・あかんの?」「止めとき、取ったら乗りたなるし、バイクも欲しくなる」と十数回そんな会話が交わされ、そのうち何も言わなくなり、昨年「お母さん用事済んでからでいいし話しがあるし・・・・・・」と切り出され、何となく-バイクのことかも・・・・・・と思っていると彼の言い出した言葉は「とにかく最後まで話聞いてな!!あのな僕バイクの免許取ってん、ほんでな先輩からバイクゆずってもらってもう買うてん、名義変更も保険も全部手続き済んで置くとこもあるし、怒るやろし、だまっとこと思ったけどやっぱりちゃんと話しときたかったし、バイト代溜めて買ったし・・・・・・」と・・・・・・。言いたいことは山ほど、滝の流れ程有ったけど「知ってたで、教習所の冊子も置いてあったし足にすごい傷作ってたこともあったし・・・・・・。今、自分が何しなあかんのか、これからどうしたいんか、君も何か目標持ってるはずやし、それさえしっかり解ってるんやったらいい、まあ無免許で人身事故でも起こされるより免許持ってた方が責任が持てていいかもしれんして思とくわ・・・・・・でも君、甲斐性あるやん、それは認めるは・・・・・・」と、チョット理解有る親になってしまいました。特に何かに優れているわけでもなく、フツーの高校生と思っていたのに、なかなかやるやん、と、たのもしくさえも思えたのはやはり、親バカと言うものでしょうか・・・・・・。
ルールは守らなければペナルティを与えられるのは当たり前のこと、今の彼(長男)は学校の校則に対してイハンした生徒になるけれども、社会に対してはそうではないことになります。矛盾してますが、今回彼のしたことで-ホンマはどうしたら良かったんですかネェ?ともう少しつっ込んで皆様のご意見をいただけば良かった・・・・・・と後から思っているバカ親です。
教育というと、学校という枠にはめがちですが、教えて育てるのは社会であり、小さくは地域であり、そして根本は親、大人達。友人から学ぶことも、同年代以下の子供達から教えられることも教育、その中に学校も含まれる。と、考えてる母親も居るんですよね。

「国民個人の行動については国家は干渉しない。」これは、自由主義国家の根本です。言論の自由、表現の自由、思想・信条の自由、政治活動の自由、経済活動の自由、その他諸々の自由。これらは、すべて国民がこられの行動を行うことについての国家の不干渉を意味しています。それゆえ、国民は、自分の能力に応じて、学び、働き、財産を作り、国のあり方さえ決めることができるのです。
他方、国家は国民の生命・身体・財産の安全を確保することが基本的な役割です。そのためには、国家は、国民の行動に対して干渉し、一定の行動を犯罪と定めて禁止したり、行動を制限することが必要となります。つまり、自由を制限する必要が生じるのです。
近現代の自由主義諸国家は、このような二つの相反する利益を調和させることに腐心してきたのです。刑事手続きにおける厳格な要件や令状主義もその成果の一つです。
最近、政府は、組織犯罪等の捜査の必要性から通信傍受法案を国会に提案しました。これについては、「通信の秘密」(これも自由権の一つ)を侵すとする反対論もあります。しかし、その反対論は、「自由権を侵すものはすべて絶対反対!」という感じのものが多く、通信傍受法を「盗聴法」とわざわざ言い換えて報道するマスコミに至っては、扇情的過ぎてオピニオンリーダーとしての資質を疑わざるをえません。
わが国においても、オウム真理教事件や薬物銃器密輸入、集団的密入国、企業対象暴力事件など組織的犯罪は増加しています。組織的犯罪は、いわば犯罪のプロによる犯罪であり、証拠を残さず、かつ確実に実行します。したがって、検挙は困難であり、社会に対する危険性は極めて高いのです。組織的犯罪を検挙できなければ、国民は国家や法に対して無力感を抱き、国家は法ではなく暴力によって支配されてしまうことになります。
通信傍受はそのような組織的犯罪を検挙するために有効な捜査手段の一つです。そのような現実を直視したときに私達がとるべき態度は、通信傍受の必要性を考慮し、それが不必要な不当な「盗聴」とならないように、つまり、通信の秘密の制限が必要最小限となるように、その要件をどのように定めるのかが適当であるかを考えることです。

梅雨明けが近いある日、新聞の折り込み広告に「ふとん打直し」のチラシが入っていました。幼い頃、土用になると母が打直しから帰ってきた綿でふとんを作るのを手伝いました。新聞紙を挟み込んで作るので、それを小さい体でふとんの中に潜って取ってくるのが楽しみでした。
今、ふとん綿を打直して新たなふとんを作られる家庭はどれほどあるのでしょうか。中にはフトンとはお店で買って、使い捨てるのが当たり前と思っておられる家庭の方が多いのではないでしょうか。ではそのフトンはどこに捨てるのでしょうか?
そう、大型粗大ゴミとして京都市環境局に処分をお願いしているのです。有料になる前は毎月30,000点が大型粗大ゴミとして出されいました。有料化になって、数は1/10になりましたが、それでもフトンによみがえっていたはずですが、それは今は毎月3000枚が焼却処分されているのが現状です。でも、これらの大型繊維製品である布団やカーペットをリサイクルしようとする動きが起こっています。
さて、地球温暖化防止京都会議が一昨年開かれましたが、繊維製品におけるリサイクルについて、我々はもう少し真剣に受け止める必要があるのではないでしょうか、ペットボトル13本でポリエステルの体育のユニフォーム1着が出来ます。これは、おおよそ石油4lの節約になります。でも、その取組にはペットボトルの回収を始め様々な問題が残っています。かつて、繊維製品のリサイクルには古くからリユースとして古着や、ウエスとしての再利用がはかられていました。「弘法さん」での古着市はおなじみでしたが、今は誰も手を付けていません。古着のリサイクルショップがボランティアの手で各地に出来ますが、直ぐに閉鎖され、集まった商品(古着だがまだ十分使えて、きれいな衣類。流行遅れだが新品の衣類)は焼却処分されてしまいます。
まだまだ日本の社会にはリサイクルの概念が根付いていないのではないか?消費は美徳といって、いつまでもキリギリスの生活をしていてよいのでしょうか?ついこの前まで当たり前であった侘・寂の心を理解し、「足るを知る」を尊重すれば何でもないことだがな~、と嘆いているのは瓦独りだけでしょうか。
編集後記
統一地方選挙後の府議会で西田昌司議員は新たに警察常任委員会の委員長と、府議会自民党議員団の政務調査会長に就任されました。また、自民党全国青年議員連盟会長や府連の青年局長も引き続き引き受けられるとのこと。こうした要職にあるのも皆様方のご支援のお陰であり心より感謝申し上げます。
松本 秀次

去る4月11日に行われました第14回統一地方選挙に、皆様方の大きなご支援のおかげで、四回目の当選をさせて頂きました。しかも、四期連続トップ当選という栄誉も頂戴し、その責任の重さに身の引き締まる思いが致します。皆様方のご信頼に違うことのないよう、初心を忘れず全力で頑張る決意でございます。今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を心よりお願い申し上げます。
ところで、今回の選挙戦で私は四期連続トップ当選をさせて頂ましたが、自民党全体で見れば、府議会議員が2人、市議会議員が1人、いずれも現職の議員が落選してしまいました。自民党にとっては決して順風満帆というものではありませんでした。一方共産党は府会では前回を2議席上回る15議席になり、市会ともども共産党にとっては最高の選挙結果になりました。また当初、そんなに風が吹いていないと言われていましたが、結果的には府議会・市会ともに、民主党の新人が僅かな選挙運動で当選するなど、民主党の善戦が目立った選挙結果でもありました。
こうした選挙結果を振り返ってみますと、今回の選挙では長引く不況など、現状に対する不満票が、民主党や共産党に流れたものと思います。また、その一方で、公明党が地域振興券の導入を盛んに宣伝していましたが、結果的には議席を伸ばすことができず、地域振興券は必ずしも公明党に有利には働かなかったということが言えると思います。このことは多くの国民が目先の政策よりも、もっと根本的な日本社会の将来について、漠然とした不安感を今なお強く持っていることの表れでもあると思います。
今回の選挙戦でも、先行きの不安感が不況の原因だと盛んに言われました。こうした不安の一番は老後に対する不安である。だから、介護保険や医療保険の充実を行えば老後の不安が無くなり、個人消費も増えるのだと、共産党などは訴えておりました。しかし、本当にこうしたことで、先行きの不安感が無くなり、景気が良くなるのでしょうか。私にはとてもそう思えません。
日本の社会は不況だと言うものの、冷静に考えれば世界トップクラスの経済大国であります。また日本は世界一の長寿の国でもあります。つまり日本は、世界一お金持ちで長生きが出来る国なのです。世界一お金持ちで長生きの国なら、本当は誰もが幸せを感じるはずではないでしょうか。しかし現実にはそうした実感が乏しいのが実態です。それは何故なのでしょうか。
確かにお金持ちで長生きしたいけれども、一緒に御飯を食べる家族がいない。話を聞いてくれる友達がいない。自分の帰るべき家庭や故郷がない。それが、多くのお年寄りの実態だからであります。人間にとって一番大切な心の拠り所となる家庭や故郷から孤立してしまう、そのような仕組に日本の社会はなってしまったからではないでしょうか。
例えば、戦後の日本では、若者が農村から次々に都市へ出て行き、産業を支える労働力として、日本の経済を牽引してきました。彼らは、故郷を出て郊外のニュータウンに家を建て、子供を育ててきました。そして今、その子供たちもまた家を出て自分達で新しい家庭を持つようになりました。かつてのニュータウンもオールドタウンになり、このままではゴーストタウンにさえなりかねないようになっています。日本ではモノだけでなく、家族や友人、故郷さえも消費財になってしまったように思えるのです。退職して初めて、自分には帰るべき家庭と故郷が無いことに気づいても、もう後の祭りになっているのです。これは幸せを実感できないのも当然です。今必要なのは、家族や友人や故郷を消費するのではなく、守り育てて行くことを一番の眼目に置いた政策であると思うのです。
しかし、故郷や家族と言う言葉にみんな憧れますが、現実はなかなか厄介なもので、田舎の風習を守ったり、近所付き合いをするだけで大変です。自分の家族が100パーセント自分の家族だと胸をはれる者ばかりではありませんし、逆にそのために胸を痛めることも多々あります。いっそのこと、こんな厄介な家族や故郷から縁を切って自分のしたいように生きたいものだと思うことは誰だってあることです。逆にお金で済むことならお金で済ましてしまうことの方が、便利で楽だということも事実だと思います。戦後の日本はこうしたことを、社会全体が組織的に行ってきました。しかし、その結果は先に述べた様に、自分の帰るべき家族と故郷から孤立してしまったお年寄りを増やし、人々から幸せの実感をなくしてしまうのです。このことが先行き不安をもたらす大きな原因になっているのです。

私はこの選挙戦を通じて次の5つのことを訴えてまいりました。1つは個人主義から家族主義に政策転換をする。2つ目に競争原理より共存共栄の経済政策の実現。3つ目に徳育の充実による教育改革。4番目に多者よりも弱者の救済を旨とする福祉政策の実現。そして5番目に、郷土愛を育てることにより地方分権よりもむしろ地方自治の推進ということです。以上のことは私が会長しております自民党全国青年議員連盟の統一政策として、この選挙戦で全国の同志が訴えてきたことでもあります。私は、こうした政策を通じて日本社会の方向性をはっきり示すことが、現在の日本が抱えるなんとも言えない先行き不安感から抜け出す唯一の方法だと思うのです。
今までと同じように経済成長ばかりを追い求めた政策を柱にしてしまうと、最後は人間にとって一番大切な家族や友人さえ、金で必要なときだけ買えば良いということになってしまいます。現に、介護保険制度も考えてみればお金で、家族や友人を買うものだと言う意見もあるくらいです。私は、家族や友人を守るためにこそ、この制度を活かしたいと思っていますが、現在の様に便利さと豊かさばかりが政策の指標になっていたのでは、結果は私の期待通りにはならないでしょう。同じ政策を行うにしても、その目的意識の違いによって結果は大きく変わるものです。「帰るべき家庭と故郷を守り育てる」こうした目的をしっかり掲げた政策論議が、これから一番必要になるでしょう。今後もこうした思いをぶつけて頑張ります。よろしくお願い致します。

テレビが開票速報を伝えている。西田昌司トップ当選の報と同時に大歓声が上がる。いつものことながら心からホッとする瞬間である。『なにしろ、親父さんから数えて9回連続してのトップ当選やからなぁ』・・・・・・後ろの方で話しておられる。聞くともなしに耳にしてやがて感慨にふける。西田後援会は京都府妓会議員を抱える団体として絶妙の緊張感を擁し、その時々の要求と特徴をしっかり見据え、先輩役員の方々と協議をしながら32年の歳月を経てきたことを・・・・・・。
昭和43年に府会議員補欠選挙で2議席あった南区の自民党の議席がゼロとなりました。この選挙から、共産党、公明党の両党が台頭してきました。西田後援会はこの時期に発足活動を開始しましたが当初は本当に厳しい道のりでした。それを関係各位のご努力とご協力によって、現在の京都南区西田後援会にまで成長しました。
今回の選挙では、南区の14学区に選挙対策委員会を設置して頂、昌友会が選挙力一、個人演説の弁士や設営等に中心となって活動頂きました。他にも多数の事務所に応援にかけつけて頂きました皆さまと候補者が三位一体となって選挙活動をしてきた結果が、今回のトップ当選への大きな勝因といえましょう。
今回ご支持頂きました1万2千人余りの方々に心から感謝申し上げるとともに、西田昌司府会議員が地域住民に耳を傾け、謙虚な気持ちで、選挙公約実現のために、がんばって頂くことを、心から願います。
「選挙、それは感動と感謝」
昌友会会長 秋田 公司

「皆様、大変おさわがせ致しております。景気に喝、自信を持て日本。自民党の府会候補西田昌司でございます。最終最後のお願いにまいりました。後ひと押し、もうひと押し、西田昌司をよろしくお願い致します。府会は西田、自民党の西田、絶対西田とお願い致します。」最終日、候補者の食事中にウグイス嬢と共に、私も思わずマイクを持ってウグイスならぬカラスをしてまいりました。今回の統一地方選挙、共産党の躍進する中にもかかわらず、お蔭様で我が陣営がトップ当選をさせて頂きました。たくさんの皆様からお励ましや御支援を賜り、本当にありがとうございました。
今回の選挙では後援会青年部の昌友会が、街宣、演説会を担当させて頂きました。初めての経験であり、当初は不安と緊張で大変なプレッシャーでした。しかし、連日早朝より朝立ちに始まり、昼間の自転車部隊、夜の個人演説会、すべての活動をこなした後、事務所で反省会を行う中で、熱気と若さとチームワーク、大いなるパワーを感じてきました。自宅に戻ると日付けが変わります。それでも、疲れも口にしないすばらしい仲間と感動する活動を共有できたことを、なにより私達がその気になる候補者を生涯の友として持てたことを、大変うれしくおもいます。最後になりましたが、あたたかく、御指導、御支援賜りました西田後援会、一粒会、事務所スタッフの皆様本当にありがとうございました。
ありがとう
個人演説会会場設営隊統括責任者
昌友会 八幡 利明

設営隊とは看板・照明・受付所・演壇・垂幕など個人演説会場ごとに、おおよそ考えられる準備を一手に引受ける、選挙活動の縁の下の力持ちといった部隊です。連日夕刻6:00より3部隊が演説会場入りをし、同時に3会場の設営をこなして行きます。
今回の選挙では昌友会が初めて選挙活動の運営を任されたこともあり、部隊もなかなか思うように稼動せず試行錯誤を繰り返す毎日でした。
私達が設営を済ませたその会場で、4年前にもお見かけした後援会の方々の熱心なお姿を拝見し、この選挙もきっと良い結果が得られるだろうと確信していました。ただ、場内を見渡すとどうしても若い世代の人たちが少ない。我々昌友会の普段の活動に大きな課題を残された思いが致しました。
中盤戦を過ぎるころより設営隊の士気も上がり、豪雨の中も皆一心に役目を果たして頂きました。
ご自宅を会場にご提供いただいた方々、また地域会場借用にご尽力頂いた方々に御礼を申し上げます。そして全会場無事設営を果たして頂いた設営隊の皆様に、心より”ありがとう”。
体力の限界まで
街宣活動統括責任者・昌友会
中山 重光 / 辻 繁信

選挙期間中は街宣活動にご支援ご協力いただき誠にありがとうございました。
恐いもの知らずと申しましょうか、選挙運動を一度も経験していない2人が、大胆にも『街宣』を引き受けてしまいました。
まず、第一に選挙期間中の「街宣プラン」をたてることから始めました。基本方針は西田昌司候補が自ら『体力の限界まで活動したい』とおっしゃったことでした。
1日目、2日3日目といろいろありましたが、いよいよ4日目からが嵐の選挙活動です。
朝7時にターミナルで朝立ち、8時より選挙車で街宣、午後は候補者自ら自転車に乗り、夕方には「Show youの旗」を先頭に歩いての桃太郎作戦です。あわただしい1日が終わりましたが、5日目は雨。午後からの自転車、桃太郎は中止と決定し関係者に連絡しましたところが、2時ごろから雨は止みました。もしやと思い選挙事務所へ駆け付けると、やはり候補者はすでに自転車に乗り換えて、事務所に居合わせた昌友会員と共に自転車で街宣活動に出発されていました。自転車の活動性と親近感を生かした銀輪部隊の発足の瞬間でした。

選挙戦の最終日も雨でした。銀輪部隊は出動できません。でも素晴らしいことが起こりました。ウグイス嬢をはじめとしてみんなが雨にもかかわらず、選挙車の窓から身を乗り出して最後のお願いに回っているのです。候補者西田昌司の『今の日本を良くしなければ!』という気迫が全員を動かせ、訴えさせたのです。
私たちの初めての選挙戦は恐いもの知らずの日々でしたが貴重な体験でした。
若干29歳、選挙活動に参加して
演説会場担当・昌友会 木村 和久

昌司先生、最高得票当選おめでとうございます!!
私が選挙活動のお手伝いをさせていただいたのは今回で2回目になります。2回目と言っても前回は右も左もわからない子供のように言われるままに動いていただけでした。この4年間昌友会の色々な活動に参加し、(失礼な言い方かもしれませんが)昌司先生がとても近い存在になってきたせいか、その分前以上に応援にも力が入り準備の段階から、参加させて頂きました。今回は演説会場の担当となり、昌友会の松本秀次さんのもとで仕事をしました。演説会場の場所設定や弁士の割り振り等、主要な仕事は松本さんの担当で、私に与えられたのは演説会場用の垂れビラ、つまり弁士の名前書きでした。慣れない太筆に振り回され、環境保全が叫ばれる中で多くの紙を無駄にしながら、毎晩遅くまで書いていました。書きながらSyow you編集長の書道家!? 川並さんに字の指導をして頂き、終わりの頃には筆の使い方がわかり字がうまくなったのは言うまでもありません。職業がら字を書くことの多い私にとって、とても役に立つ仕事でした。
また、選挙期間中には主に演説会場の設営の仕事に汗を流しました。ここでは4年前の勘が残っていたのでスムーズに動くことができました。昌友会以外の方々にもいろいろな面で助けて頂き、4年前に2~3人で設営にまわっていたころとはうってかわって活気がある選挙戦でした。色々な面で参加させていただいた今回、『トップ当選』という結果で幕を閉じました。様々な人と出会い、選挙の話やそれぞれの仕事の話など様々な会話を通して、それぞれの人生観などを垣間見ることができ、若干29歳の私にとってとてもプラスになった9日間でした。皆様、お疲れさまでした。本当にありがとうございました。
編集後記
選挙戦も終わり、これからいよいよ昌友会が何をどうしてゆくのか、そういった奮闘記で紙面を埋めて行きたく思います。御期待下さい。
松本 秀次
1.統一地方選挙(4月11日)に当選すること

今年は言うまでもなく、統一地方選挙の年です。本年で、平成2年に当選させていただいて以来3期9年になります。4月の選挙にも全力で戦い、皆様方のご支援を得て是非とも当選をと思っております。
ところで、私が議員にならせていただいてからのこの9年間は、国の内外においても、大変な激動の時代だったと思います。国外においてはソビエトの崩壊という大きな歴史のうねりが、社会主義を終焉させ、冷戦終結をもたらしました。そして、国内においてもいわゆる55年体制といわれた自民党と社会党との対立構造が、支持基盤を失った社会党の崩壊により終わりを告げました。
今年は言うまでもなく、統一地方選挙の年です。本年で、平成2年に当選させていただいて以来3期9年になります。4月の選挙にも全力で戦い、皆様方のご支援を得て是非とも当選をと思っております。
ところで、私が議員にならせていただいてからのこの9年間は、国の内外においても、大変な激動の時代だったと思います。国外においてはソビエトの崩壊という大きな歴史のうねりが、社会主義を終焉させ、冷戦終結をもたらしました。そして、国内においてもいわゆる55年体制といわれた自民党と社会党との対立構造が、支持基盤を失った社会党の崩壊により終わりを告げました。
さて、現在は自民党と自由党が連立するという時代になっています。これは、昨年の衆議院選挙で敗北したことにより、非常に不安定な状態になった政局を少しでも安定させなければ、景気の回復はおろか、政治課題が何一つ解決できないという現状を考えると、背に腹は替えられないぎりぎりの選択であったと思います。しかし、その選択については説明不足の感が否めません。また連立したところで、依然参議院においては過半数に届かないのですから、不安定な政局は今後もしばらくの間続くでしょう。
バブル経済崩壊以来深刻な不況が、今なお続いております。しかしその一方で不況というものの日本が、世界でも有数の、また日本の歴史の中でも一番豊かな時代を迎えていることは違いありません。
こうした、日本社会のアンバランスな状態が、私たちになんとも言えない閉塞感をもたらしています。このことは、物質的には豊かになっているにもかかわらず、幸せを感じられない日本人が増えてきたということの証しではないでしょうか。つまり、物質的な豊かさよりも心の豊かさを求める時代に変化をしてきているのだと思うのです。こうした時代にこそ、「国のあり方」 「人のあり方」など、物質的豊かさ以上に大切なものを自分の言葉で国民に語りかけることが、政治には必要であると思っております。これからも生意気ではありますがこの紙面を通して自分の言葉で国を語り、政治を語っていきたいと思っております。そして現実の政策に反映させた結果、皆様方のご支援をいただいて、当選できるように頑張りたいと思います。
2.本の出版「政論」-保守の原点を問う-

(自照社出版1月10日発売1200円)
今年の1月10日、いよいよ私の本が出版される運びとなりました。私は約4年間にわたりまして毎日街頭遊説を続けてきましたが、この本はその内容をまとめ上げたものです。朝7時半から8時半までの間、近鉄の東寺駅やJRの西大路駅そして京都駅八条口と街頭遊説を続けてきました。しかし朝の通勤時間帯ですので、誰も足を止めて聞いているほど時間をお持ちではありません。街頭遊説中はほとんど無反応な状態ですが、たまに「街頭遊説をやってたのを見たよ。頑張ってるな。」という声をかけていただくことが後であるのです。そういう言葉に支えられて今日まで続けてきました。
私は、街頭遊説は政治家の基本であると思っています。それは、自分の言葉で自分の価値観や思いを語る訓練の場であると思っています。したがってその場では誰も聞いていなくても、いずれ思いは通じる自分自身を鍛えているんだ、そういう気持ちで毎朝頑張ってきました。今回そうした思いをまとめ一冊の本に致しました。朝の時間はお忙しいでしょうから私の演説を聞く時間もないと思いますが、お時間の取れます時に是非ともこの本を読んでいただきたいと思うのです。この本は実は去年の秋には、原稿もまとまり上がっていたのですが、出版をするということで大変苦労してまいりました。つまり、原稿があれば本を印刷することは出来るのですが、これを書店に並べていただくこのことがなかなか出来ないのです。しかし、今回色々な方のご支援のお陰で、全国の書店で取り扱っていただける態勢をとることができました。店頭に本が置いてなくても必ず取り次いでくれるはずです。是非ご近所の本屋さんに注文に行っていただきたいと思います。
3.昌友塾の充実
昨年から、本の出版に合わせて、私の政治的なものの考え方を、単にこちらから一方的に話すのではなく、お互いの意見を出し合い皆様方とどんどん議論していく新しいタイプの討論会を、昌友塾と名付け活動を始めてまいりました。原則として、毎月第3火曜日に六孫王会館で午後7時から9時までの間、開催する予定となっています。毎回テーマを決めて、政治にかかわる問題、教育にかかわる問題等、色々なジャンルについて、皆様方と討論を重ねていきたいと思っています。
政治の基本は、国民一人ひとりが、政治にかかわる問題を自分たちの問題だとして捉え、考えていくことです。その延長線上に我われ議員があるのだと思っております。私が政治活動していくためにも、皆様方との議論や討論にその出発点があるべきだと思っています。今年はこの昌友塾の輪をもっともっと広げて、たくさんの方に参加していただき、その議論の輪が広がることを期待しております。是非ともご参加いただきますようにお願い申し上げます。
4.政治に言葉を取り戻す
私は、今年こそ景気が回復して日本経済に活力を取り戻さねばならない、またそのために、私も全力を尽くさなければならないと思っております。私は、経済はちょうど一年前が一番危機的な状態であったと思っております。しかしこれも公的資金の投入や信用保証協会の保証枠の拡大により、一時のパニック的な状況は脱出したと思います。おそらく本年中には、景気回復の兆しが現れてくるものと確信しております。
こうした目の前にある景気問題も大切ですが、もっと大きな問題も日本には山積みしています。今まで、日本は欧米列強に、特にアメリカに追いつけ追い越せということを主眼に国づくりをしてきました。しかしこれはバブル経済前にすでに達成をしていたのです。バブル経済の崩壊は、ある意味で急激な経済発展をしてきたことの調整局面と言うことも出来ます。いずれに致しましても、この景気が回復する事によって物質的豊かさばかりに主眼を置いた国づくりは、その役目を終えることになるはずです。
それでは、これから一体日本の国づくりは、どうするべきなのでしょうか。「いやいや、まだまだ日本は遅れている。アメリカのように規制緩和を行って、情報化時代に対応し、産業の最先端を行く国づくりをしなければならない」等々。相変わらずアメリカに見習うことを主眼とした議論がされています。しかし、私はもうこのあたりで方向修正をすべきだと考えております。戦後、アメリカ化の流れの中で日本の価値観、文化伝統など、日本人が日本人であるための根本的なものを、次々に喪失してきました。物質的な豊かさと引き換えに、こうしたものを次々に犠牲にしてきたのです。その結果もたらされたものは幸福感ではなく、なんとも言えない喪失感、閉塞感ではないでしょうか。未曾有の不況ではあるものの、史上最も豊かな時代を送り、消費不況が叫ばれていても、買いたいものが何も無い。こうした現代の状況は、まさに日本人の喪失感、閉塞感がもたらしたものです。そして、この原因が、日本人にとっての「しあわせ」とは一体何かという根本的なことをまともに考えることなしに、いたずらに社会をアメリカ化してきたためであるのは言を待ちません。
日本人のしあわせを守ることが、我われ日本の政治家の使命です。そうであるならば、今一度、日本人にとってのしあわせは一体何なのか。この原点に戻るべきではないでしょうか。そしてそれは、物質的豊かさをしあわせの一番の条件と考え、社会をアメリカ化させることに夢中になったために忘れ去られた言葉を、取り戻すことに通ずるのではないでしょうか。例えばそれは、自由という言葉の影で忘れられた「節度」や「道」であったり、権利義務に対しては、「徳を積む」「正気を養う」であったり、どれも日本人が昔から大切にしてきた言葉なのです。そしてそれは、今でも我われが無意識のうちに行動の基準とする言葉です。こうした言葉をもう一度正面から捉えて、あるべき日本人像を語ることが、これからの政治に一番必要なことであると思うのです。

11月17日、午後7:00より六孫会館で行われた、第一回昌友塾に参加しました。今回出版される「政論」(保守の原点を問う)を軸にして、その内容をもっと多くの人達と話し合い、意見を交わし、みんなで行動しようと、昌友編集委員長が企画したものです。ご夫婦、友人同志の方々など、誘い合せのうえ約30名の出席者があり、熱気のある討論会となりました。前半は、西田府議のお話で、現代社会が、かかえる様々な問題を提起、そのことを踏まえどう生きれば、幸せにかつ、すばらしい人生を送ることができるのか、という内容でした。参加者のなかに「なにか新しい生きる価値観を発見したように思えました。」と言っていただける方もいらっしゃいました。また後半は、討議形式で、参加者の方々より発言していただき、私達の周りの様々な問題を具体的に取り上げ、西田府議を中心に、全員で、熱っぽく情報交換をしました。なかでも大変印象深かったのが、「今日我が国が抱える問題に対し、マスコミや、人々は、あまりにも批判、評論ばかりで、自分達でこう取り組もう、行動して国や地域に積極的に貢献しようという活動が見えてこない。」という府議の話でした。ぜひ昌友塾を通じ共通した熱い思いで、たくさんの仲間とともに、この国や地域に貢献できる活動の輪を広げてゆきたいと思っております。ぜひご参加ください。
■開催予定日のご案内 1月19日、3月16日、4月20日
六孫会館にて、午後7:00より9:00
シルクよ永遠なれ(シルクルネッサンス)
安い輸入生糸や和装需要の低迷で、大幅に生産を減少した国内の繭と生糸。戦前まで日本の基幹産業だった養蚕業は厳しい状況に追い込まれています。その中で「シルクよ再び」を合い言葉に、国内の養蚕産地では生き残りに懸命です。
なかでも、「伊予カメリア」の名前で皇室の衣冠束帯(最近では皇太子ご成婚の際、雅子様がお召しになった十二ひとえに使われた)や伊勢神宮の御料糸に用いられていた生糸を生産していた愛知県・野村町がシルク博物館を建て、町をあげて絹文化復興(シルクルネッサンス)に積極的に取り組んでいます。
「シルクとミルクのまち」をキャッチフレーズに農業を中心に発展していった町で、最盛期の1970年代には西日本最大の製糸工場を持っていました。しかし、繭価格の低迷、就労者の高齢化、後継者不足などにより、養蚕、製糸ともに衰退の道をたどり、平成2年には養蚕農家個数、生糸生産高も最盛期の1/5になり、平成6年4月ついに製糸工場の廃業となりました。養蚕農家数は製糸工場の廃業を期に急激に減少し、町では基幹産業である養蚕を何とかしなければ、養蚕・製糸業を歴史として後世に正しく伝えなければ、といった気運が起こってきました。絹の消費量は増えているのに、国内の養蚕は消滅しようとしており、養蚕は割りの合う産業で無くなってきました。しかし野村町は養蚕で生きてきた町で、まだ養蚕農家は残っており、養蚕が好きだといっています。「養蚕農家を守れないようでは、他の産業も守れない」といった気概が、これら養蚕農家の応援と、指導者を招いて繭づくりから、製糸、糸染め、製織までの一貫生産をおこなうシステムを作り上げ、野村町でしか作れない生糸で日本の断絶した絹文化を復活させたい。このような思いでシルク博物館などの施設が建設されました。
さて、秦氏が6世紀に渡来し、養蚕の技術を伝えた京都はどうなのでしょうか。西陣、丹後といった和装絹産地、室町という和装の日本最大の集散地を抱えていながら余りにも無為無策ではないでしょうか。絹を西陣、丹後の産地の為のものと考えるのではなく、茶道、華道、表装具など日本文化のさまざまな分野の重要な役割を持っていることに気が付いてもらいたいのです。
現状の施策では日本の養蚕・製糸が無くなってしまう危機に直面しています。特に京都は絹を用いた日本の伝統文化を継承、発展させていく責任があるのです。現在の農林水産省の方針では、日本に生糸生産がなくなっても中国他の海外の生糸を安く輸入する事が可能であるから、織物をはじめとする絹業界は日本に存続すると考えています。日本文化の根幹に重要な位置を占める絹を外国からの輸入施策に頼るのは非常に危険な事ではないでしょうか。日本独自の文化の為に、日本独自の生糸が必要です。フランスでは文化省がゴブラン織を残し、フランス文化を継承する為に、ジュネーブ郊外に小規模ではありますが、養蚕・製糸を保存しています。日本文化の中心地である京都において養蚕・製糸を存続させる事は責務ではないでしょうか。幸いな事に綾部には京都府養蚕センターがあります。ここを日本文化の生糸の生産拠点と位置付け、フランスがジュネーブ郊外に養蚕・製糸を存続させているようにすればどうでしょうか。火種さえ残しておけば、経済状況の変化により養蚕・製糸を復活する事は可能ですが、一度その火を消してしまうと復活はほとんど絶望的です。今なら、京都府養蚕センターに明治以来日本が形作ってきた製糸の技術を継承している人達がいると聞いています。
明けましておめでとうございます。
参議院議員 西 田 吉 宏

皆様にはお揃いで元気に新しい年をお迎えの事とお慶び申し上げます。
私も皆様の力強いご支援に支えられて、昨年に引き続き参議院議院運営委員会筆頭理事として、極めて元気で国会活動を続けております。
ところで政治は、経済・外交・防衛など多くの課題を抱えておりますが、現下の最重要課題は何といっても金融システムを早期に安定させ、経済の再生を図ることです。長引く景気の低迷は国民生活に少なからず不安と閉塞感を与えております。特に中小企業や自営業者などの生活を守り、雇用不安を解消する即効性のある政策の実行が緊急課題であり、政府はさきの第143、144臨時国会において相次いで緊急経済対策を盛り込んだ大型補正予算を成立させ、景気の早期回復のためにあらゆる努力を傾注しているところでございます。
また今後は、21世紀の長寿社会へ向けて、福祉の充実とこれに伴う国民負担の在り方等も早急に検討しなければならない問題であります。そのためには、国においても地方自治体においても政治の安定が急務であります。
今年は統一地方選挙の年でもあります。私も微力ではありますが、京都府・市並びに西田昌司府会議員とも協力しながら、住民に信頼される政治、ゆとりと潤いのある住民生活を実現できる安定した政治情勢の実現に懸命の努力をしたいと決意しております。是非皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。「ウサギ」の年です、お互いに希望を持って大いに跳ねて、不況の山も谷も飛び越えるよう頑張りましょう。皆様の限りないご健勝ご多幸をお祈り申し上げます。
待望! !『政論』(保守の原点を問う)出版

自照社出版 1,200円 平成11年1月10日発売
自由民主党全国青年議員連盟会長
京都府議会議員 西 田 昌 司 著
「朝まで生テレビ」でお馴染の評論家西部 邁氏 絶賛!
政治・経済・社会の不安な現代を、守るべき日本の家族像を通して鮮明に解き明かす警鐘と同時に希望を読者に伝える待望の書
私が会長を務めている自民党全国青年議員連盟では、去る7月の参議院選挙敗北をうけ、加藤幹事長(当時)に対して申し入れを致しました。一聞報道されましたが、その内容を正しくお伝えするために、以下にその全文(抄)を掲載致します。
自由民主党再生のため

去る7月12日に行われた、参議院選挙におきまして、自民党はかつてない大敗を喫しました。
特に私の地元の京都選挙区におきましては、共産党の候補がかつてない得票を上げ、自民党の支持率もかつてないほど低いものとなりました。また無所属の若い候補が39万票を上回る大量得票で一位当選するなど、まさに自民党にとって逆風、そして共産党や野党にとって追い風の選挙だったことがうかがえます。こうした状況を踏まえて、今回の選挙の敗北の原因を考えますと何よりも私は、自民党が保守政党として本来の政策をしっかりと訴えていなかったことが、最大の原因であると思います。
例えば、今回の不況を受けて自民党は六大改革ということを盛んに訴え、その中で経済の改革を行うには、規制緩和を行って競争力を高めていく、また大店舗法も廃止にする、こうした日本の社会全体におおなたをふるうようなことを、盛んに訴えてまいりました。しかし私は常々、こうした社会全体をアメリカ化していくような政策は決して、保守を標榜する自民党には本来そぐわない政策ではと思っております。ではなぜ保守政党であるはずの自民党がアメリカに追随してきたのかといえば、その背景には、東西冷戦構造の中、アメリカ=保守ということが当然視されてきたという事情がありました。しかし、東西冷戦構造が崩壊してから後というものは、次第にアメリカ型社会の本質が見えて来ました。確かに共産主義、社会主義というものは世界の政治状況からはすでに葬られました。また日本の中でも社会党自身が崩壊してしまいました。しかし、実現にはより広範に左翼思想は国民生活の中に広まってきています。またアメリカ化ということが保守と思われたのは、相対的にはということで、それは、ソビエトという対立軸があったからであり、アメリカの社会や政治の現実の姿が、保守であるかどうかということを考えれば、むしろアメリカは本来の保守政治とは異質な政治体質であると言えます。保守というより進歩主義、理想主義という意味ではソビエトが全体主義であるのに対して、アメリカが個人主義であることを除いて、両者は近い体質を持っているのです。例えば、保守とは確かな政治理論とか理想というものがあるわけではありません。むしろ現状を肯定しながら徐々に社会を変革していく、そしてその変革の道筋というのは、自分たちの国の状況、それは歴史であるし、また気候風土でもあるし、さまざまな民族の状況にもよりますし、いろいろな要素が融合して、つまりいろんな歴史や伝統を背負い、その延長線上に新しい時代をつくっていこうとする、これが保守であります。ところがアメリカの場合は新大陸の発見以来、イギリス人やフランス人等、主にその当時の体制の恩恵に浴していなかったヨーロッパの人々が次々に移住してきました。その為、それぞれの国の伝統というものもある種受け継ぎながらも、アメリカという新しい大陸で、新しい気候の中で、今までの伝統や文化とは違う、自分たち自身の理想国家を作り上げていこうとする大きな流れがそこにありました。そういう意味ではアメリカという国は非常に理想主義的な、また実験国家として非常に冒険的な、また若くて活力がある国でもあります。しかしこれらすべてが、人間にとって素晴らしいことかといえば、決してそうとばかりも言えません。あまりにも理想主義に走り過ぎ、時として大きな過ちを犯すことがあります。例えば禁酒法の例などがそれの良い例でありましょう。また実験国家として非常にダイナミックな行動を起こしますが、時として大変に愚かな行動に走る事もあります。例えば抗戦力の既に低下している日本に対して原子爆弾を落とすなどというのは、まさに、日本人を核実験の道具にしたということです。そしてまた若く活力のある分、貧富の格差があまりにも大きくなっております。つまり国としての歴史がまだまだ浅いために、アメリカという国そのものが揺藍期にあり、変動の揺れ幅が大きく、従って生身の人間にとっては非常に変動の大きく、厳しい世界であるということが言えるでしょう。またそれが一面、アメリカンドリームという大きな成功をもたらすこともあるのです。しかしいずれに致しましても、文化も経済も社会全体の仕組みも、すべてをアメリカ化することは、日本人にとって決して幸せでばかりないことは、日本人もすでに気付いていると思います。
ところが戦後半世紀、日本人はこうしたことを心のどこかでは感じながらも、半ば強制的に、また半ば自主的に、アメリカ化するような方向で国を作ってきました。半ば強制的にというのは、戦争に負けて、徹底的に社会の仕組を日本の伝統的なものから、アメリカ型へ強制的に変換されてきたということです。そして半ば自主的にというのは、そういう思いを持ちながらも、アメリカの豊かな生活というものに憧れて、自分たちの理想郷としてアメリカの社会を雛型と見て、社会を変革してきたということであります。またそうすることが、無条件に正しいことだと日本人は信じてきたのです。

こうした流れの中、自民党の戦後政治は、冷戦時代にはアメリカ側につくという意味で保守陣営側ではあるものの、その政治的スタンスは、極めて理想主義的かつ進歩的なアメリカの政治姿勢をそのまま受け入れてきてきたのです。従って、草創期から自民党は真の保守政治とは言えなかったのです。そして東西冷戦構造が終焉を迎えると同時に、左翼勢力やマスコミは、かつてはアメリカに対して向けていた矛先を、日本の伝統的な文化や習慣と言うものに向け始めました。これが、マスコミ各社に共通するスタンスではないでしょうか。従って、こうしたマスコミが作り出す世論というものは、当然のこととして反日本的であり、かつ、親アメリカ的なものにならざるを得ないのです。その上にバブル崩壊以来の大不況が続いています。経済界においても、かつては日本的経営というものに絶対的な自信を持っていた方たちも、この不況の中その自信を失われ、また自信を失わないまでも、否応なしにリストラに取り組まざるをえなくなりました。特に大企業では、バブル時に大幅に採用を増やしたため、この整理をしなくては会社の屋台骨が崩れてしまうという危機に瀕したのです。その方便として使われたのがアメリカ型社会への移行、つまり規制緩和による市場原理中心の競争社会への移行ということであります。そして、アメリカ型社会に移行することが経営者の利益だけではなく、消費者の利益にもなるということを唱えだしたのです。その結果、こうした大企業の経営者の声と、マスコミの反日親米的な視点とが奇妙な協調関係を作り、不況を契機に反日親米の規制緩和路線に向けての大合唱が日本中で唱え出されたのです。
こうした、いわゆるマスコミ世論の大合唱を背景に、自民党が打ち出したのが最初に述べた六大改革であります。しかしこれは自民党の本来の政策ではなく、連立政権であるが故に、その政策基盤の弱さのために、常にマスコミ世論に対して迎合しなければ政権基盤を保てないという、政治的圧力の下に行われたものだと私は思っております。したがって、これは自民党の政策というよりも、かつての細川内閣の延長線上にある政策であると私は思います。しかしたとえそうであっても、マスコミ世論が本当に日本の長期的利益を守るため正しいならば、これを受け入れることも仕方ないと思います。しかしこれは、日本の長期的利益を守るという観点から作られた政策ではなく、アメリカやマスコミの圧力によって本質的なことを考えることなしに提案されてきたものです。従って、そうした政策が成功するはずがありません。当然の結果として、ますます経済状態は悪くなりました。また、今まで日本経済を支えてきた一番の柱である人間の信頼関係というものを、次々に破壊してきました。
規制緩和論者が言うようにアメリカ型社会への移行によって、今まで100有った雇用が50に減っても新たに50以上の雇用がそこに創出されれば、こうした主張も理にかなっているかもしれません。しかし、実際には50減った雇用が規制緩和によって新たな雇用を生み出したとしても、それはわずか10や20にとどまっており、後の30はその先の見通しがつかないというのが、現実の状況ではないでしょうか。結局それは先行きに対する不安感というものを作り出したにすぎなかったのです。従って、長引く不況の原因はいろいろあります。その原因の一つが、あまりにも早急な社会変革を無節操に、無秩序に、将来展望なしに行ってきたことであることは間違いないと思います。
私の選挙区は京都ですが、京都では共産党が以前から大変大きな勢力を持っております。今回ついに、自民党をその得票数で抜き、府内第一党の地位を獲得するに及びました。その原因について私は、共産党の主張するような消費税の5%を、3%に戻すとかいう政策だけが受け入れられたからではないと考えております。共産党の主張してきたことは、本来自民党が主張しなければならないことの代弁をしていたということなのです。例えば共産党は大店舗法の廃止により、商店街がなくなってしまうことに対する矛盾を訴え、また、徒に規制緩和をすることは、弱肉強食社会を作り出し、経済秩序を崩壊し、中小企業の生き残れない商環境をつくり出してしまう等、まさに保守政党として自民党が主張し、守らなければならない大切なものを、共産党が訴えていたのでした。そう言えば共産党の候補者は京都では、キャッチフレーズに「家族色の政治」ということを掲げてきました。そして自民党はどうだったかといえば、マスコミが作り出した世論に引きずられて、改革という言葉を意味もなく使うのが精いっぱいでした。これでは本来の自民党の支持者が、共産党に回ってしまうのも無理のないところです。共産党の主張は結局のところ、現代社会の矛盾をついているだけにすぎず、彼らが自由主義社会を本当に守る気がないのは明らかでありますが、有権者はそんなことより、共産党の主張の方が、保守党の立場を忘れた自民党の主張より、日本の良き伝統を守る主張として頼りになるものと感じ、評価したのではないでしょうか。
参議院選挙の敗北を受け、橋本総裁から新たな総裁に変わられます。どなたが総理総裁になられても、是非ともお願いしたいということは、こうした大敗北の原因を真剣に考えるならば、われわれ自民党が取らなければならない政策というのは、まさに、目先の問題だけではなく、長期的な日本の利益を守るということです。そのためには、戦後日本が避けて通ってきた日本の国のありようを真剣に考えるということが必要です。そして、日本人にとっての幸せとは一体何なのかということを、真剣に論議しなければなりません。そうするならば、日本人の幸せが必ずしもアメリカ人の幸せとは一致しないということが、明らかになるはずです。日本人はこの国土に生まれ、この風土の中で生活をし、ほぼ単一民族という環境の中で暮らしてきました。そうした中で培われてきた歴史や伝統というものが、われわれの幸せに対する価値観を決定付けているのです。こうした伝統文化を無視して、日本人の幸せを守ることはできないということに、われわれは気づかなければなりません。まさに真の保守政策としての使命を果たすことこそが、これからわれわれが一番にすべきことではないでしょうか。是非とも、新しく総裁になられる方にお願いしたいのは、徒にマスコミ世論に迎合しアメリカ社会に傾斜するのではなく、しっかりと足元を見つめ、保守政党としての政策を貫いていただきたいということです。心からそのことをお願い致します。
真の保守政治の再生へ向け、勇気とご英断を期待しております。
平成10年7月16日
自由民主党全国青年議員連盟
会長 西田昌司

シルクよ永遠なれ(シルクルネッサンス)
5本指の絹の靴下のおかげで、今年の夏は水虫の繁殖がだいぶん治まりました。5本指健康法というのがあり、足の指間を広げると健康に良く、通気性も良く水虫退治にも良いとのことですが、やはり絹という素材が水虫退治に良いのではないでしょうか。
科学的に調べても絹は綿や合成繊維と比較して吸湿、放湿性に優れており、最近では肌着に良く用いられています。かつて絹は繊維の女王と呼ばれ、和装品をはじめ、嫁ぐ花嫁に持たせた反物や着物、豪華な打ち掛け衣装に用いられていました。正倉院の御物を始め文化財の衣装の素材はほとんどが絹で出来ています。近年、これら絹素材が消費生活の多様化により身近な処に用いられるようになってきました。JR伊勢丹百貨店にも西陣織りの絹のコースターやボトルカバー、日用品が『絹千年』とネイミングし出回っています。
ところがこれらの原材料の絹は大半が中国から輸入され、円高、ガット・ウルグアイラウンド協定などの政策により安価で国内に入ってきています。
絹は昆虫の蚕が幼虫から蛹になるときに作る繭を生糸にして得られる繊維です。絹は中国が原産で四千年の歴史を誇り、わが国へは二千年前に伝えられましたが、養蚕が飛躍的に発展したのは明治以降です。明治時代の生糸は輸出産業の花形で、日本の富国強兵・殖産産業振興のため養蚕も中山間地域の花形農業として持てはやされました。全国各地に生糸を作るための製糸工場も建ち並びました。代表的な地域が関東甲信越地域ですが、京都府下においてもグンゼで代表されるように綾部を中心に製糸、養蚕が栄えていました。さらに、かつては我が南区の久世地区においても養蚕が行われていて、つい最近まで養蚕を行っている農家が一軒だけ残っていました。
ところが安い生糸が輸入され、和装需要の低迷で国内の繭、生糸の生産量が大幅に減少してきていました。農村が都市になり、労働力集約型な養蚕は敬遠され、国内の養蚕農業は激減しています。最盛期 1975年・養蚕農家24万8千戸、生産量9万1千トン、1997年養蚕農家6310戸、生産量1920トンと農家個数で2.5%、生産量で2.1%になっています。(農水省調査)これに伴い、製糸工場は429工場(1975)から11工場になってしまいました。こうした状況を受けて国は繭検定や蚕糸業の許可制を定めた蚕糸業法と、製糸の免許制などを定めた製糸業法を1998年に廃止いたしました。これを受けて各都道府県の蚕糸や繭関係の機関も廃止の方向になり、国産の絹糸が消えるか、残せるか、各都道府県の決断でその方向性を決めることになりました。
日本の絹がなくなることは京都の伝統産業である西陣織や京友禅の存続さえも危うくするのではないでしょうか。西陣織の帯の原材料である絹が中国製、薪の能の衣装の原料が外国産では・・・・・・。これではいけないと思い各地の残っている養蚕地が絹文化復興(シルクルネッサンス)を目指して独自の取り組みを始めました。それは田舎が都会に迎合しないで、『繭つくり(養蚕)』を中心に町村の再生に取り組んでいる姿です。それについては次号で紹介いたします。

第29回の旅行会は、広島・山口(萩・津和野)山陽方面で今までにない豪華・感動グルメ2宿3日の旅でした。
1日目:江田島旧海軍兵学校と広島平和記念資料館を見学し、戦争で数多くの若い命が失われたことや、原子爆弾による被爆者の遺品や写真を見て、何か胸に込み上げるものが有りました。
2日目:SL山口号に乗り、小郡駅から津和野駅までのゆっくり2時間、明治・大正・昭和にわたって全国を駆け抜けた客車を見て回り、時代の変化を感じ、又車中で食べた駅弁も大変味わい有るものでした。
3日目:日本三景安芸の宮島(厳島神社)を参拝し、蒼い海に浮かぶ雄大な鳥居を後にして帰路につきました。
三日間、ハードスケジュールでしたが、天候にも恵まれ、ご一緒させて頂いた方々との親睦も深まり、思い出に残る旅行になりました。来年の旅行会は、日本の代表的な山岳景勝地「上高地」の予定です。その前にある地方選挙で、西田昌司先生を皆さんの手で勝利に導き上高地で祝杯をあげたいと思います。
編集後記
虫の音に秋を感じる頃となりました。秋といえば、食欲の秋、芸術の秋、読書の秋などといろいろ言われていますが、私は今、テニスに、はまっています。そう、スポーツの秋です。先日、コーチに「汗だけは一人前やなあ!」と、からかわれました。全く下手の横好きとはこのことでしょう。涼しい間になんとか格好がつくようにしたいものです。゛退屈の秋″を過ごしている方、こんな私と一緒にテニスを楽しみませんか?
編集委員 木村 和久
景気回復のために
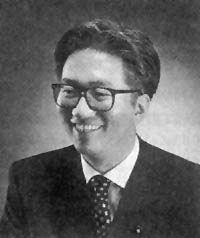
4月の知事選では、皆様方のお陰をもちまして50万票を超える得票で、荒巻知事が4選をいたしました。皆様方のご支援に心からお礼申し上げます。しかし、その一方で共産党の推薦する候補者が得票を大きく伸ばしたのも事実であります。その原因は、なによりも現在の深刻な不況をはじめ、社会全体に蔓延している閉塞感があまりに、大きかったため、相手候補に批判票が投じられたものと思います。京都府知事選挙とは直接的には、関係のないことが批判票になったわけです。それほど、現在の不況による閉塞感というものが大きいということの表れだと思います。
さてこの戦後最悪の不況の緊急対策として、政府は16兆円を越える巨額な補正予算を組みました。景気回復のカンフル剤としてその執行が期待をされております。こうした政府の補正予算を受け、京都府におきましても、640兆円に上る6月補正としては、史上最大の補正予算を組み、不況対策に力を注いでまいりました。
その主な項目を述べますと、まず一番は、470億円に上る公共事業投資です。また中小企業への貸し渋り対策として、府の制度融資の枠を680億円から780億円へと大幅に増額いたしました。そして私が常々訴えてきたことですが、信用保証協会に対する出えん金を増やすことにより、その融資の保証枠を約100億円分増額させました。このほか伝統産業等につきましても木目細かな政策を行っております。こうした予算が執行されることにより、必ず景気は上向きになってくるものと確信致します。
ところで、公共事業について野党は、無駄なものと決めつけ、景気回復には、公共事業よりも恒久減税を実施すべきだと言います。しかし私は、今、景気回復のためにすべきことは、減税よりも公共事業投資だと、考えております。景気回復策として、3つの主な政策が考えられます。ひとつが金利政策であり、2つ目が減税であり、そして3つ目が公共投資です。前の2つの政策が景気に効果を上げるためには、大きな前提があります。それは、低金利や減税により家計や企業の負担が軽減された分だけ、消費や投資にお金が使われるということです。ところが現在の経済情勢の中で、こうしたことが期待できるでしょうか。金利政策では、すでに公定歩合が、0.5%という史上最低の金利水準になっております。不良債権問題等による貸し渋りなど、他にも原因が考えられましょうが、これほどの低金利であっても、先行きに対する不安感というものが強いため、投資にお金を使おうという方が非常に少ないのが現実です。その為にいくら金利を下げても、市場に資金が還流されないのです。また減税についても、多少税金が戻ってきたとしても、現在の情勢の中でどれほどの方が消費にお金を使われるでしょうか。むしろ先行き不安のためにお金を使わないで貯めておかれる方が多いのではないでしょうか。
こうしたことを考えますと、金利政策や減税では今回の不況を、脱出することはできないのではないでしょうか。それではいったいどうすればいいのでしょう。もう後残っている政策は一つしかありません。それが公共事業投資です。いくら金利を下げても、減税をしても、民間ではお金を使おうとしない。それなら国や地方自治体が民間に代わって市場に資金を投入する、これが公共事業投資です。
公共事業投資は、金利政策や減税のように間接的に市場に資金を投入するのではなくて、直接、事業を行うことによって、資金を市場に投入します。したがって事業をした資金は間違いなく市場に投入されますから、景気に直接的な効果が期待できるのです。これが一斉に前倒しで、実施されますと、必ず景気は上向きに転じてくるはずです。しかし本当に景気を回復するためには、もうひとつ大きな条件が必要です。それは、景気停滞の原因である、社会に対する先行き不安感というものを、払拭するということです。この先行き不安感は、政権基盤が非常に不安定な連立政権がここ数年間続いてきたことから生じています。そして、それは、9年前、平成元年の衆議院選挙で自民党が大敗をし、以来参議院では、どの政党も過半数を占めることができなくなったということが問題なのです。参議院選挙はご存知のように、衆議院と違い、解散総選挙をすることができません。一度選ばれた議席は、6年の任期の間変わりません。3年に1度その定数の半分が改選されますが、いったん過半数を割った参議院の議席は、なかなか簡単に回復できないことは、この9年間の政治状況を見ても、お分かりいただけることと思います。参議院での過半数割れが連立政権を作り出し、中、長期的な政権基盤を不安定な物にしたのです。
連立政権は、民意が反映されやすいと言われます。しかし、現実の社会では民意はマスコミを通して伝えられることになります。その結果、民意もマスコミがそのフィルターを通して作り上げ、増幅した、マスコミ世論というものに変えられてしまいます。マスコミはその商業主義のため、非常にセンセーショナルな話題を追う傾向にあります。そのためマスコミ世論というものは、結局のところ、目新しい目先のことしか考えないものになってしまうのです。
こうしたことから連立政権においては、政治の一番の目的である国民の長期的な利益、すなわち国益を守るということより、目先の政治課題を処理することばかりに、終始するのです。そして、そのことを国民は一番不安に思っており、それが先行き不安の根本原因になり、不況を長引かせているのです。こうしたことを考えると、今回の参議院選挙は非常に重要な意味を持つと私は思います。皆様方の賢明なご判断をお願いいたします。
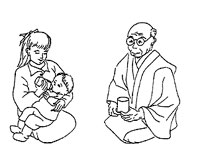
私は、税理士という仕事もしておりますから、相続についてどうすれば一番税金が少なくて財産を子供たちに遺す事が出来るんだろうか、という相談をよく受けます。また、そうした事は子どもを持つ親なら誰もが考える事だと思います。
しかし、残念ながら、なかなか良い方法というのは無いのが現実です。そんな時私は半ば冗談、半ば本気でこういう事を申し上げます。人間の残す財産というのは、どの道多かれ、少なかれ、税金がかかって取られてしまいます。しかしまったく税金のかからない財産を子どもに残す事も出来るんです。それは何かといえば「親の信用」と言うもの、また「親の思い」・「価値観」と言うものです。つまり、親が財産を造ってきた基となったこれらのものなら子どもにいくら残しても税金はかかりません。従って、同じ残すなら税金のかかる有形の財産よりも、むしろ無形のこうしたものを子供に相続させる事が一番の得策になるのです・・・。
「親しんど、子楽、孫乞食」と言う諺を私も良く親から聞かされました。これは、親が創業者として一所懸命に働いて財産をまず作ります、そして次の子供の時代になりますと、その財産の上に胡座をかいて大変豊かな生活が出来ます、しかし創業者の苦労を知らない孫の世代になってしまいますと、もうその財産も食い潰してしまい結局乞食のような暮らしになってしまうものだという、たとえ話です。まさに、そのたとえの通り、親の思いがなかなか次の世代に伝わりにくい、財産だけ残しても、それが子供たちのプラスになって行かない、ということが現実の社会ではないでしょうか。
ところで明治の元勲西郷隆盛の残した言葉で有名なものに「児孫の為に美田を買わず」というものが有ります。この言葉の意味は「孫や子供のために立派な田畑と言うような財産を敢えて残したり買ったりしない。それは、そうする事でかえって子供たちが自分で努力をしなくなってしまうからだ。だから子供たちのためにはむしろ財産を残さない方が良いんだ。」こういう風に私たちは教えられてきたと思います。しかし、私はこの言葉はそういう表面上の意味だけではなくて、本当はもう少し深いところにその意味が有るのではないか、と思うのです。たとえば、次の言葉を最初の句の後に付けるとその深い意味がもっと解ると思います。「児孫の為に美田を買わず、『ただ志を残すのみ』」。この『ただ志を残すのみ』という言葉を加えて考えてみますと正に、西郷南洲が本当に伝えたかったその思いと言うものが鮮やかになってくると思うのです。
「児孫の為に美田を買わず、ただ志しを残すのみ」つまり、子供たちに田畑という立派な財産を残すんじゃなくて自分が残そうとするのは私のこの思いである、この思いと言うものを子供たちに残してやりたい、これが子供たちへの唯一の財産だし、私の残すべき本当の財産なんだ、子供たちに受け継がすべき財産なんだ、とこういう風に西郷は言いたかったのではないでしょうか。わたしは、まさにこれこそ親から子へ世代を超えた本当の相続だと思うんです。そしてまた、家庭というものを通じて本当に私たちが子供に伝えなければならないのは、こうした思いであるし、また、そういう子供たちに伝えるべき思いというものを、我々親が持っているのだろうか、そのことを自問自答して行かなければならない、と思うのです。そう思ったときに、現在の家庭というものが、あまりにも急激な世の中の流れの中で、自分が守るべきもの、子供に何を残すかということを全く考えないまま、ただ時流に流されていただけだということに、初めて気がつくのではないでしょうか。こうした子供たちに残すべき思いが伝えられて始めて、わたしは本当の相続が出来たのだと思います。また是非ともそういう思いを子供たちに残したいし、また、残すべき思いを持ちたいと思うのです。皆さんはどうでしょうか、本当の財産をお持ちでしょうか。

私たちの住む南区の歴史なんて考えたことありますか? 通りの名前の由来やその地域の言い伝えなど興味深い話はきっとあるはず・・・街を歩いて所々にこんな歴史の案内板があったら面白いのではないかと、お話を聞いて、ふと思いました。
「うちはまだ新しくって、5代目くらいです。まあ母屋も入れると13代目くらいに成りますね。」という、西九条にお住まいの原田禎三さんに九条界隈のお話を聞きました。
* * *
最近のことです。昔の古い資料なんか集めていると御輿仲間で関心が高まって、広まってきたんですよ。
明治のころ、九条界隈大宮あたりは、みな百姓でね、朝は肥え汲みに行くんです。大宮通りには東海道線の踏み切りがあって、それを渡って上へ行くんですが、午前8時までにこちらへ戻らんと罰金を取られましたんです。重たい天秤棒を肩に担いで行くんです。だから御輿を担ぐにしても肩の強い人が多かったんですよ。それで東寺の東門あたりが朝早ようこちらに戻ってくる人の一服場所になってね、食べ物屋なんかが出てにぎやかになってきたそうです。今の東門の消防署の少し南くらい、埃だらけの大宮通西側に水飲み場が有りまして、牛や馬、人まで飲めるほどきれいな水が沸いててね、いつのまにか出ん様になりましたけれど、つい最近まで石段があって、下へ下りられる様になっとったんですよ。
東寺東門の大宮通り東側には「震いの神さん」が奉ってあってね、渡辺綱(わたなべのつな:平安中期の武人)が羅城門の鬼退治に来たとき、針ヶ小路で馬が震えて動かんようになってね、ここで炬(かがりび)を焚いて一服しやはったそうです。それで針ヶ小路を俗に「炬(かがり)の辻」と言う様になったそうです。
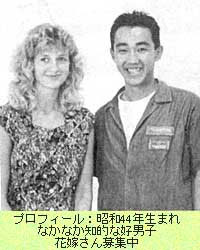
5月、お店に伺った。花の香りと当然だが美しい花で一杯の店内。陶化学区の木村花店の若き店主、木村和久さんにお邪魔した。見慣れぬ花のことを親切に教えていただいた。
「この花はカラー(和名:海芋=かいゆ)と言って普通は白いんですがちょっと冒険をしてクリーム色を仕入れてみたんです。」
いつも何か小さくとも、冒険をしながら仕事をしていたい、とおっしゃる。実は5年前にご尊父を亡くされ、勤めていたホテルを退社して花店をお継ぎになったとか。お話をお聞きした。

当初は分からないことばかりで、かなりの不安が有りましたが、花の美しさや作品を作る楽しみを実感できる、フラワーデザインに出会い、新しい道を開くことができました。勉強しはじめて約4年になりますが教わることばかりで、フラワーデザインを通して芸術の奥深さをひしひしと感じています。
花の世界には数々のコンテストが有ります。ワールドカップが有るほどです。その中にはブライダルブーケを規定時間内にその場で制作し美しさを競うものや、 "サプライズ方式"といって、競技開始直前にしか資材の内容が明らかにされず、その中の80~90%を使ってテーマ(例えば、花のささやき等漠然としたもの)に沿って時間内に規定の作品を作る、装飾技術を競うものなどの少し変わったコンテストも有ります。5月にも"花と緑の市民フェア"(於:みやこめっせ)にも花き装飾のコンテスト部門が有りました。これは毎年行われており、ギフトアレンジ、テーブルアレンジ、自由花(大作)の3種類、70数作品が京都市内の花屋から出展されます。私は4年前から毎年出品しており、昨年から2年連続で全体の5位に値する、「京都農業振興競技会会長賞」を受賞する事が出来ました。ファッションに、色やスタイルの流行があるように、フラワーデザインにも流行が有り、新しい技術が常に考えられています。今後も前向きに勉強を続けていきたいと思っています。
余談になりますが、昨年より友人と一緒に花の個展を開いています。今年も四条「虎屋」3Fにて9月26・27・28日の予定で開催します。機会が有れば是非一度、ご覧ください。
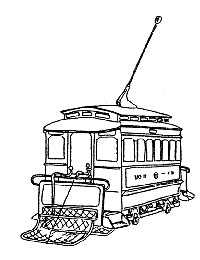
1: 6:3 これは現在の水力発電:火力発電:原子力発電の発電エネルギー源別割合の比率です。かつてわが国の発電は、山岳地形を利用した水力発電が主でしたが、1960年代の重化学工業の発展と各家庭での電気機器の普及のため電力需要が大幅に増えました。これをまかなうため、水力発電より建設費が安く、大都市や工場地域の近くでも電力の供給が可能な火力発電所が主に建設され、最近では原子力発電所も建設されています。
これと同じような水力発電から火力発電に切り換える社会現象が明治時代に京都駅南の東九条村で起こっていたのです。明治28年に日本で始めての市街電車、京都電気鉄道が塩小路高倉から伏見を経て中書島まで開通しました。これは明治初期の京都産業の起死回生事業である琵琶湖疎水のたまもので、蹴上発電所の電力の確保によるものでした。当事、電気は主に電燈用として供給され、電力が余っていたため電車の開通となったのです。しかしながら、当事の琵琶湖疎水は、定期的な水路の清掃や、琵琶湖の水位の低下、疎水運河の改修など、さまざまな理由で発電が止まることがあり、そのたびに電車が止まっていました。そうなると京都電気鉄道(株)としては自前の発電所を建設することが緊急の課題となり、水力に頼らない火力発電所を京都駅南の東九条に建設することにしました。
明治32年に東九条村山王に建設費12万円で火力発電所の工事が着工されました。米国ゼネラル社の250KWと言えば微々たるものですが、当事わが国の総発電力が50,000KWですから全国でも最新式の発電所として注目を集めていたそうです。これを機会に京都電気鉄道(株)は京都市水利事務所からの電力購入を全廃し、完全に電力を自給していきました。
現在、規制緩和に伴い家庭でのソーラ発電で余った電気を関西電力などに売ることができますが、電気という公益性の強い産業において、必要とあらば自前で電力供給を行うパイオニア精神が明治時代に育っていました。これは現代人の我々も見習う必要があるのではないでしょうか。
西田昌司府会議員が自治功労者表彰

去る5月13日、西田昌司府議会議員が議員在籍8年になったことを受け、自治功労者表彰を受彰致しました。「これもひとえに、皆様方のご指導ご鞭撻のおかげでございます。これからも、初心を忘れず、地元南区と京都の発展のため、そして日本のために、全力を尽くして頑張りますので、変わらぬご支援をよろしくお願いいたします。」
編集後記
いよいよ夏本番です。夏風邪の咳と鼻水に苦しむ私に、今まで読者という立場でしかなかった「Show you」の編集長より編集参加の思わぬお誘い。今まで何気なしに読んでいましたが、こんなに時間と労力が費やされているとは思いもしませんでした。なにはともあれ、今回もいいものができ、おかげで風邪も治り、元気になりました。皆様、これからもがんばりますので、よろしくお願いします。
編集委員 木村 和久

私は、安心して暮らせる京都府づくりのために、社会に対する信頼の回復と伝統を守りつつも時代に適した社会システムの構築が、一番肝要であると考えています。 私は現在の大不況の原因は、バブル崩壊後の需要調整であると思っています。ただ、山高ければ谷探しという言葉があるように、バブルの時期に膨れ上がりましたから、その谷も大変深く長かったのです。その為に日本の経済システムを根本から構造改革すべきだと、叫ばれるようになりました。その結果、日本的経営が否定されてしまったのです。日本的経営とは、終身雇用や協力会社・家族的経営に代表される「長期的な信頼関係を基板とする」経営の安定が最大の特徴であります。反省しなければならない点も多いのですが、根本からだめだというのでは何の解決にもなりません。
こうしたことから働いているものは、何時自分が首を切られるかわからないという不安を持ちます。お金も使わずに貯めることに必死になります。また、中小企業の経営者にとっても、いつ系列からはずれるかわからないという仕事の不安がありますから、設備投資に回せない。銀行も貸しても回収できないのではと、貸さなくなる。貯金者も銀行に預けても大丈夫なのかと不安になり、箪笥預金に回してしまう。何か悪い方に循環している。この結果不況が長引く。これでは構造不況ではなく、一面で「構造改革不況」ではないかと思っております。
ではどうすればいいのでしょう。私は、日本的経営のよさをもう一度見直すなど、急激な改革をやめ、もう少し冷静な目で判断していかなければならないと思っています。「長期的な視点から、雇用と仕事を守る」という、安定と信頼の回復が第一に必要だと思っております。社会の秩序と皆さんの信頼が回復して初めて、消費や投資が回復し、景気の回復が実現できると、このように思っております。そして、これが府民の安心・安全な暮らしと社会を築く基本だと思っております。
ところで、「公共事業をやめて減税を」という意見も聞きますが、所得税減税は箪笥預金という形で、今の状況では効果が出にくいという面があります。また消費減税では、消費税率のアップの際の駆け込み需要と反対に、減税までの消費の手控えという状況が考えられます。結局、景気に刺激を与えることなく、財政赤字が増えるだけで、的外れの論議だといわねばなりません。
まず早急に手をつけねばならないのは、企業の雇用秩序を乱す急激なリストラと金融機関の貸し渋りなどの問題です。自由民主党でも昨年末から貸し渋り対策本部を設け、私も相談員として多くの方の相談を受けましたが、この不況で土地の値段が下がり中小企業の方の信用保証能力や担保能力が低下し、お金を貸してもらえないという相談を多く受けました。先の府議会でも、一般質問で提言しましたが、信用保証協会が中小企業に対する保証枠を拡大すること、無担保無保証人保証の充実を図り、中小企業の借り入れ枠を増やすことなどの政策か緊急に必要で重要だと考えております。
また、長期的に見ますと大企業が、下請けの中小企業を切り捨てるリストラは、一見効率化を図っているように見えますが、自分の首を絞めているのと同じで、日本の工業生産全体の生産性を自ら落としていることにもなります。中小企業総合センターの経営・技術指導や中小企業進行公社の仕事の斡旋など具体的で今必要な手だてを打つことだと考え、附に対しまして強力な働きかけをしております。

次に、福祉も安心な府づくりには、重要な柱です。高齢者福祉は新ゴールドプラン等により徐々に向上してきました。しかし現実には、特別養護老人ホームに入ってしまうと、家族が誰も見舞いにこないとか、お葬式にも顔を出さないという話を視察に訪れますと良く見聞きします。結局体のいい姥捨て山のようなことも実際にはあります。本来、家族や家庭を守るためにできた施設が、皮肉な結果をもたらせることにもなっています。また一方で、生涯のある人を抱えている家庭の場合には、家族の絆が非常に強いことを肌で感じることが多くあります。僅かな補助の中で、家族の絆を守り励まし合い頑張っておられる姿をよく見ております。親の立場にしますと、自分が生きている間は何とかしよう、だけど私が死んだらという不安の中で、日々子供に接しているわけです。
私は、常々福祉の基本は多者よりも弱者の救済にあると思っております。つまり、数は少ないかもしれないが一番困っている人にこそ、必要な手を差し伸べることが、基本であろうと思っております。こうした政策を充実することは、福祉という観点からだけでなく、地域や共同体を守る上からも重要な視点であります。自分が住んでいる社会が、弱者を大切に守り育てる社会であるという思いや経験は、とりもなおさず、自分の周りの人々や社会に対する信頼を生み育てることになります。この社会への信頼は、また家族や家庭の安定と信頼無くしてはあり得ません。こういう意味からも、家庭や家族を守るという観点から福祉を考えていくべきだと思っております。
以上述べましたように安心安全な京都を築くには、私は信頼の創造と回復が何より重要だと思っております。この信頼の創造こそ、教育の重要な使命であると思っております。未来を託せる信頼のおける人間の育成こそが、教育の最大の責務であると思うのです。それでは、人間としての信頼の源はどのようにして作られるのだろうと考えますと、やはり知育・徳育・体育のなかでも徳育が今日的にも大きな課題であるといえます。徳育とは、何だろうと考えますと、字の通り人間にとっての徳、つまり人が人として生きていく上での価値を学んでいくことだと考えます。
じゃ、人間にとって何が価値のある大切なことなんだろう。私は、人のために身を尽くす、自分の利益だけではなく社会や公共のために身を尽くせる、そういった人間になるように学ぶこと、そういう価値観を持った人間を育てることではないかと思います。これは、いつの時代も、どこの国も変わらない不変の教育の目的であろうと思っています。
日本では、こうしたことが家族との生活の中で、米作りを通して培われてきました。米作りは、村人総出で協力し合って、互いに力を合わせなければ、立派なお米はできません。自分が力を出し協力することで、村の利益にもなり、自分の利益にもつながる。このように、共同体の皆の利益と個人の利益が共に一致することの大切さとすばらしさを、米作りを通して文化として私たちは培ってきたと思います。
ところが、現在の社会では、こうした地域や公共ということよりも、個人や個性ということを随分重視します。私のように公益や公共ということを言いますと、戦前の滅私奉公や封建的な人間と短絡して考え、議論を封殺する風潮もあります。私は、個人と公共が天秤にかけられ、個人の利益が追求されるのがおかしい。個人の利益がまずありきで、公共の利益より優先する考え方が少し違うのではないかと言っているのです。公共の利益に反するような個の利益追求はおかしいのであって、共にこれらを守る考え方や追求の仕方をしなければならないと考えております。先に言いましたように、日本では昔からこのような考え方は、人として当然のことと受け取ってきました。この私たちの考え方のよさを、もっと大切にしようといいたいのです。この考え方は、もの作りにも言えることです。
よく日本とアメリカでは、ものづくりへの考え方の違いがあると言われます。日本の場合は、良いものを作ってその結果儲かれば良いという考え方をします。そのためには、協力して頑張ろうという、米作りの伝統に根ざした考え方があります。アメリカの場合には、まず儲かる品物を作る、儲かるものを売る。そのためには独創的なアイデアで、競争して勝っていくという考え方です。これは、どちらが良い悪いの問題ではなく、互いの文化や伝統の違いといえます。この互いのよさや違いを認め合うことが、真の国際化につながっていくと思います。
しかし、昨今の改革騒ぎでは、こうした互いの考え方の違いや文化や伝統の違いを認めない、特に日本の文化や伝統が、非常に遅れているというように、全面的に否定する風潮があるように思います。このような自己否定につながる考え方が、信頼の喪失の根本的な原因につながっていくように思います。人を信頼する・社会を信頼する前提である自己の信頼を否定するのですから、それこそ、自分を見失ってしまい信頼の社会が作れないのも当然だと思います。私は、安心・安全な京都府をつくるために、こうした社会風潮を正していく、日本のよき伝統を守り育てていくという声が上がってこなければだめだと思っております。
最近、新聞やテレビでは、景気が悪いからまず改革だというようなことばかりが言われています。しかし、急激な改革は、逆に景気の失速の原因ともなりかねません。政治に携わる者は、心してかからねばならないことですが、日本の本来のよき伝統や文化を守っていくための仕組みを新たに築き上げていく努力が必要だと考えます。人の信頼が回復でき、秩序が回復でき景気が回復する。私はこのような「言葉」を訴えていきたいと考えています。
ロマンチック・ダンサー
前野幸男さん
昭和6年 南区唐橋 血液型:O型

「私たちがダンスを覚えた頃はやはり不良やったね。世間からはやっぱり違う目で見られた時代でした。今では、ダンスを楽しんだり、また皆さんに教える機会を得るのが一番の生きがいです。」
昌友会主催の「第1回春のダンスパーティ」に先立ち、まったくの初心者、西田昌司府会議員をはじめ15名もの昌友会員にステップのイロハから御教授いただいた前野幸男さんを取材させていただきました。
名曲は残る
私らの青年時代はええ曲が多かったね。ダンスよりも先に素晴らしい曲に惚れたもんです。映画音楽もものすごく好きやったね。「第三の男」、「ビギン・ザ・ビギン」、「枯葉」、「セ・シボン」、「ツー・ヤング」、「ラ・クンパルシータ」、名曲は残っているし、今の曲でもいい曲は残ります。部屋は今でもダンスのええ曲でいっぱいです。
青年時代
40 数年もの前、「鶴清」が進駐軍の保養所になっていて、そこで始めてダンスの素晴らしさを知りました。そうやね私らがダンスを始めた自分、ダンスをしているのは男が殆どやったね。そらジャズを聴いたり、映画に凝ったり、ダンスをしたり、ビリヤードもしたけど、やっぱり、そんなんやっている者は世間から不良扱いされたね。そやさかい私も不良ですわ。その頃京都の大学の軽音楽クラブでも盛んにダンスパーティを催ししていてね。今こそダンスをする人は圧倒的に女性が多いけど、そら、その時、ダンスのパートナーを探すのは大変なことでしたよ。女性の取り合いで、随分振られました。それが私の青春時代やね。
妻も知らぬダンス狂時代
そんなことで結婚するとき、妻の両親の心象を考えてピタッとダンスはやめました。そして仕事一本でした。また、ダンスを始めるまでの30年間ほど、仕事仲間は無論、妻ですら私がダンスを踊れるなんて知りませんでしたね。
再び踊るきっかけ
私のお客さんで女性の社長さんが居られます。今ダンスを習っているけどと言うお話から、それではお教えしましょうと言うことで始まりました。統治は4個所も受け持ち、それからもう15年になりますが、今でも西京極で教えていますよ。ようやく2年半前から妻と一緒に踊れるようになりました。
ダンスは見も心も躍る
ダンスに歳は関係ありません。そやから絶対相手の女性の歳なんか聞いたらあきません。私は今もボランティアでダンスを教えていますが、皆「ここのダンス教室の曲はええね。」といってくれます。いろんな曲があるけど、その曲のイメージを心の中で膨らませて踊ることが大切やね。ワルツなら花から花へチョウチョが飛んで行く気持ちになる。若い頃の曲では思い出がよみがえる。そんな曲でダンスをしたら、体も心も踊るわけ、中でも私はラテンが好きでチャチャやキューバルンバは体が浮いてくるようやね。
男性よ老けるな
今この歳でダンスができる事は最高の幸せやね。音楽を聴きながらリズムに合わせて体を動かしてみる、これは老人ボケの予防にもなりますね。ダンスを始めてから随分若返った方が多いですよ。女性は特にそうですね。どうしても男は照れくさがりで、ほんとはやってみたいけれど、習ってみるチャンスが少ないからね。大勢で一緒にするといいかも知れませんね。女性は一人でも習いに来ますしね。腹が据わっていますよ。男性は歳をとると外に出て何かしようというと尻込みをしてしまう。奥さんがダンスでも習ってみようと言っても反対する。それでも女性は習いに来ますが、やはりご主人の理解が大切やね。一度奥さんがダンス教室にご主人を連れてこられると自分の妻の美しさに喜んで夫婦でダンスを始められる方が多いです。
踊る幸せを贈る
今のダンスはスポーツダンスやから、子育ての終わった女性や無論男性も健康のたいめに始めて欲しいね。私の目標は、そんな方に一人でも多くダンスの面白さを知ってもらうことです。初心者の方なら絶対にダンスを楽しく教える自信がありますよ。歳を重ねると女性でも自分の美しさに気づかない方が多い。女性が常に美しく自分を見せることに気を遣っていると、ご主人は決して悪い気はしません。家庭も円満と言う訳です。ただ上手になっても楽しいダンスを絶対に忘れないで欲しいね。あくまでも自分のダンスを楽しむということやね。
昌友会主催 第1回春のダンスパーティ

去る3月21日、昌友会主催の「第1回春のダンスパーティ」がオーシャン会館において百五十余名の参加者を得て開催されました。生バンドの演奏、カラオケの披露、ゲームも交えて楽しいダンスパーティでした。ご参加いただいた皆さんは、ダンス衣装に身を包み、しばし時のたつのを忘れ音楽と一つになって踊っておられました。ダンスは自分が自分を主役にする不思議で楽しいもの。昌友会のメンバーもダンスの持つ楽しさに巡り会ったようです。西尾康孝開催委員長は、ダンスのステップ一つすら知らなかったが我々が今回、盛会裏に催せた事に「次回の予定は早くなりそうやな。」と檄を飛ばしておりました。
(文:編集室)
地域で頑張っています
九条少年柔剣道愛好会
会長 辻 和雄

去る3月23日、全国少年柔道大会京都予選会で九条愛好会が優勝しました。5月5日東京・講堂館での大会で京都の代表としてがんばってきます。
九条署の道場ではちびっ子達が元気一パイ、がんばっています。それは九条少年柔剣道愛好会の活動の場です。日本古来の武道であります柔道・剣道を習うことで、今一番世間でもとめられている、礼儀・お行儀・明るく健全な心・健康な体をそなえた少年少女を一人でも多く育てたく、顧問の西田昌司さん始め、南区内の大勢のお父さんお母さんのお力をかりて活動をしています。おかげさまで柔剣道の交流の場では愛好会の評判はなかなかのものです。ちびっ子やわらチャンやチビッコ剣士の練習の指導は九条警察署の署長さん始め、たくさんのお巡りさんのご理解ご協力のもと行っています。どなたも有段者ばかりです。夜昼なしの大変なお仕事ですが、私達の活動にご賛同いただき、勤務のあい間を縫って道場で子供達と共に汗をかいてもらっています。
昨今毎日のように、新聞・テレビ等で少年たちの非行問題がトップニュースとして報道されています。大変な世の中になりました。まことに憂うべき事態です。このようなときこそ、私たちの活動の柔道・剣道を通じて少年たちが、あやまった道に進まぬよう、微力ですが、少しでも貢献できるよう頑張って行きたいと思います。区内の皆さん、ご興味のある方は子供さん共々、一度見に来て下さい。月曜日と木曜日が柔道です。火曜日と金曜日が剣道です。共に夕方5時30 分より九条署4階の道場で練習をしています。たくさんのお越しをお持ちしています。
瓦の独り言
羅城門の瓦
アメリカ人が「国民の服」として誇るのに、「ブルー・ジーンズ」がありますが、我が国でもこれに匹敵する衣服があったのです。
「紺のもんぺ」です。いまはほとんど見かけなくなりましたが、藍染めの紺のもんぺは最良の農作業衣だったのです。防虫効果はあるし、マムシなどのヘビは藍染めの紺の生地を嫌ったいわれています。
この日本伝統染色技術である藍染めの原料となる藍は、全国各地で栽培されていましたが、南区においてもかつて東九条村付近を中心に室町時代から栽培されていました。江戸時代の木綿の着物の普及に伴い、「洛南の藍」として「洛中の藍染屋」に珍重されていました。藍の値段も良く、換金作物として村人の生活を潤していましたし、時の江戸幕府も抜け目なく、洛南の藍に着目し、特別に藍年貢として課税していました。明治の初期には京都府紀伊郡東九条村には10軒の大きな藍農家がありました。当時の京都の染織業界は、幕末の激動から、東京への遷都をへてかなり低迷はしていましたが、それでも日本の染織業界のリーダでした。明治5年の調査では11,000件の染織業者の中で100軒弱の藍染めの専業者があったと報告されています。当時、京都の染織業界では材料をほとんど地方に頼っていましたが、唯一、藍だけは地元で材料が調達できていました。しかしながら、明治の文明開化とともにインディゴビューアとよばれる合成藍が輸入されてきました。これを契機に東九条村付近では藍の栽培が消滅し、農家も藍に変わる九条葱、海老芋などの換金農作物へ転作していったのです。
明治以前の藍の栽培は、京都の染織業界のキーポイントであり、当時のファッション産業を支えていたといっても言い過ぎではないでしょう。現在、南区を見渡せば、世界のブランドとして通じる下着メーカーがあり、十条通にはプリントなどの染色工場が、京都駅付近にはアパレルメーカーがあります。これらの繊維関連企業は南区が全国に誇れる企業であり、育てて行った土壌は明治以前の洛南の藍栽培にさかのぼるのではないかと、羅城門の瓦は一人でつぶやいています。
編集後記
「Show you」では、地域でご活躍しておられる方々をご紹介させていただきます。情報をお寄せください。お待ちしております。
松本 秀次
旧年中は格別のご高配を賜り誠に有り難うございました。
バブル崩壊以来、何とも言えないような閉塞感が日本中を覆っております。しかし、冷静に考えてみますと、他の国に比べ、日本は経済面でも文化の面でも決して劣っていません。敗戦以来の過去の否定の風潮が、自信喪失をさせたのです。私は、未来に対して勇気と自信を持つ為にも今年こそ正しい歴史認識を持つべきだと考えております。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
新春対談 荒巻知事と語る
1.教育について

西田議員
最近の青少年に関する様々な事件などを見ていて私は、子供たちが自分の人生をどう生きて良いのか分からないという叫び声を、彼らのメッセージとして感じます。
「君たちの人生なんだから自分の好きなように生きなさい」
「個性を伸ばしなさい」
という言葉は学校や家庭で教えても
「公のために役に立つ人になりなさい」
「公のためには自分が犠牲になることがあっても我慢しなさい」
とはなかなか教えていないではないでしょうか。私益の追求だけではなく、公益を優先させる。またそのバランスの中で自分の個性をいうものを発揮することが出来て始めて人生が異議のあるものになると私は思うのです。こうしたことを具体的に教えるには、歴史上の人物などの生き方を教えることも大切だと思います。最近の子供たちに尊敬する人物は、と聞いても歴史上の人物を答えるものは極僅かです。大半の子供たちは答えるものが無いので仕方無しに両親と答えています。子供達は歴史上の人物の名前は知っていても、どんな生き方をした人かは教わっていないので尊敬しようが無いのです。私は子供達に人生いかに生きるべきかということを教えるためにも歴史上の人物の生き方を学ぶことは大変重要だと思います。

荒巻知事
月並みではありますが、青年は「志」を持つことが大切、それも大志であるほどよいと思います。大志を抱くことによって、何を為すべきか、どのように生きるべきカが明確になります。
志をもって生きるとき、人間や社会、自然、文化等とのかかわりやつながりを自覚し、それらとの共生・共存や相互依存の関係をよりよいもの、より価値の高いものに変容していく努力を続ける青年を作り、こうした生き方が人の心を動かし、自己の成長とともに、社会に有益な人材として育っていくものです。「青年よ大志を抱け」です。
今日の学校教育が、知識重視の教育や受験過多から、児童生徒の評価の尺度が一元化し、不登校や問題行動の増加の反省の結果、人間としての生き方在り方を重心がおかれてきていることは歓迎すべきことであると考えております。
また、教育は、児童生徒の希望を育て、能力と人格を磨き、国の発展や世界の平和の確立に寄与する国民的事業です。
これからの教育の方向は、生涯学習社会への移行、変化への対応、個性重視の教育にあります。
従って、学校教育において、まず、生涯学びつづける態度、エネルギーのようなものを培ってほしいと願っています。2つめは、「知・徳・体」調和の取れた発達が極めて大切であると思っています。
特に、子供たちの現状を見るときに、知・徳・体の中でも「徳育」に力を入れていく必要があると強く感じています。
たとえば、小学校の社会科(歴史)においては、これまでの「時代」中心の学習から、歴史上の人物を取り上げていきます。これらの人物が、世のため、人のために尽くした高い志は、子供たちの生き方や人物形成に大きな影響を与えることになると思います。これらの人々が、いかに個性的であったか、豊かな感性を身につけていたか、時代の変化への情熱を持っていたか、さらには国際的な視野を有していたかなどを学習することは、よい生き方の手本であるとともに、あるべき人間像を考える上で極めて意義があると思います。私の子供のころは、少年には偉人伝など伝記ものを読み与えたものです。それが多感な少年の夢を育て、励みの源になっていたように思います。私自身、多くの英雄偉人伝により、それぞれの生き様を吸収しました。
(例えば、太閤秀吉、リンカーン、ワシントン、ジェンナーなどです。)
2.福祉問題
西田議員
私も多くの特別養護老人ホームを視察いたしましたが、共通して聞くことは入所者と家族の関係が希薄であるということです。入所させたきり一度も訪ねてこなかったり、酷いものになるとお葬式にも出てこない者まであるということです。正に「仏造って魂入れず」とはこのことです。核家族化、高齢化、少子化等様々な要因のため、こうした施設や、介護保険等が必要なことは私も理解できますが、こう一つ大切なことは家族の絆をいかにして守るか、ということではないでしょうか。また、福祉政策というものは人々を幸せにするためのものですが、我々にとっての幸せというものはいったい何なのでしょうか。マスコミなどでは自由、平等、人権を守ることが大切なのだといわれます。確かにこれらを守ることは大切なことです。しかし、これらを守ることは幸せになるための手段の一つであって決してそのこと自体が目的ではないと私は思います。そのことをしっかり認識しておかないと福祉政策は、人に決して幸せを与えないばかりか、新たな不幸を生むことになると思うのです。
荒巻知事
戦後、日本が経済的には申し分の無い国になったにもかかわらず、国民が豊かさを実感できないというのはどうしてなのかと考えますと、ひとつには経済活動に専念すると共に、アメリカ型の自由や民主主義、個人主義の確立に一生懸命になっている中で、日本の持つ古き良き伝統や慣習といったものを、いわば「悪しきもの」として、すみっこに追いやってきたのではないかと思うわけです。西田先生からご指摘のあった「家族の絆」ということも、その一つなのかもしれません。
京都府においては、介護保険で提供されることとなる、特別養護老人ホームをはじめとする施設の整備ホームペルパーやデイサービスセンターなど在宅福祉サービスの充実など、施設と在宅の在宅のサービスをバランスよく整備していくことを基本に取り組みを進めております。お蔭様で順調に整備が進んでいるところですが、西田先生からもご指摘のありましたとおり、これらの整備を進めるのは、あくまで高齢者に適切なサービスを提供することが目的でございまして、施設を整備すること自体が目的ではないということは、十分踏まえておかなければならない点だろうと思います。
さて、ご家庭の中でお年寄りが介護を要する状態になられた。これは、その御家庭にとりましては非常に深刻な問題だろうと思います。いくつかの調査結果を見ましても、精神的な負担が大きいと回答される方が最も多いようですし、まさに家庭が崩壊してしまうような場面もあろうかと思うわけです。
福祉政策と申しますのは、こうした方々の負担を少しでも軽減すると共に、そのお年寄りに、家族を支えていくことが私どもの役割であろうと思います。
また、こうした点を、サービスを提供するものと提供を受けるものが十分理解しあってはじめて、真の幸福が実現できるのだろうと思います。今後とも、府民の皆様の「安心・安全」の確保に全力を尽くしてまいりたいと存じますので、西田先生のより一層のご支援をお願いいたします。
3.産業経済
西田議員
大企業と中小企業とでは根本的に社会的使命が違います。大企業にはまず第一に沢山税金を納めて頂かねばなりません。京都府でも法人事業税、法人府民税が税収全体の4割り強、そのうち上位10社の大企業がその3割り近くの税金を納めています。このことを見ても財政の安定のためにはいかにして、大企業を京都府の中に誘致するかが重要になります。また反対に雇用状況をみると京都府の労働人口のうち大企業で働いておられる方の割合は2割、中小企業の方は8割であり、雇用を守るためには中小企業を守ることがいかに大切か、ということがわかります。また、雇用だけでなく、町内会に代表される地域社会を守っているのも中小企業なのであります。ところが今流行の規制緩和により、これらの中小企業が存亡の危機に立たされています。税収を伸ばすためには大企業に有利な規制緩和は必要かもしれませんが、そのため中小企業が倒産し、雇用を無くし、地域社会を破壊してしまっては、かえって高いものになってしまいます。世界企業のためのルールである規制緩和を認めるのなら、地域に根差した中小企業を守るためのルールも必要だと思います。
荒巻知事
私も全く同感です。日本製品が世界的に高い評価を受けるようになったのも、下請けや孫請の町工場の皆さんが頑張って高い技術力で、もの作りを支えてこられたからこそです。
また、和装をはじめ伝統産業は、事業所数や雇用の面で京都経済に大きなウェートを占めるだけでなく、日本文化を継承・発展していく上でも大変大きな役割を果たしています。歴史的な地球温暖化防止京都会議が開催されましたが、環境との共生を大切にしてきた京都文化、日本文化を世界に発信していくことは、ややオーバーな言い方かもしれませんが、人類の生存の上でも非常に重要なことで、こうした側面からもしっかり見ていかなければいけません。
それから、商店街の皆さん。商店街は、消費者の皆さんの日常生活を支える買い物の場であることはもちろんですが、同時に住民の方々のコミュニケーションの場であったり、防犯の役目を果たしたり、文字通り、地域社会の中心になってきたわけです。
規制緩和という名目で、このように大切な役割を持っている中小企業がなくなってしまったら日本は崩壊してしまう。日本は弱肉強食が当たり前の社会であってはならないと考えます。そのような危機感を特に強く持っていますので、私も、国に対していうべきことはきちんと言って、また、京都府としてできることは精いっぱいやっていきたい。そう考えて府政を進めているところです。
4.産業経済
西田議員
これまでの3期を振り返っての感想と自己採点、4期目に向けての抱負を語って下さい。
荒巻知事
昭和61年に林田知事さんの後を受けて、知事に就任させていただきましたが、就任した年に急激な円高が始まり、そのあとのバブルの崩壊による不況、世界はというと東西冷戦の終結と、21世紀を目前にして政治・経済はめまぐるしく変動してきました。また、記憶に新しいところでは、阪神淡路大震災やサリン事件、O-157なども府民の不安を増大させました。
私は、就任当初から
「地方自治体というものは、地域総合保険会社のような立場で仕事をするもの」
と考えておりまして、
”困ったことが起こったら、苦しい立場に置かれたとき”、いかに府民の皆様の生活を守るか、中小企業の経営を守るか、に苦心した大変厳しい12年間だったと思います。
そんな中で、平成2年に
「豊かさが実感できる京都府にしたい。また地域の均衡である発展を遂げる京都府にしたい」
という目標を掲げて、第4次京都府総合開発計画(4府総)を策定しました。この間、財政が非常に厳しい中ではありましたが、悲願であった山陰本線、KTRの天橋立までの電化・高速化や京都縦貫自動車道の丹波町までの開通など、鉄道とか、道路とか、あるいは下水道とか、川とか、遅れていた社会資本の整備を進めることができましたし、関西文化学術研究都市の建設も第2ステージに乗せることができました。また、府民の皆様の「安心・安全」を守ということで、「福祉のまちづくり条例」などを制定することができました。
自分では、この12年間、大変厳しい中で精一杯やったつもりですが、これから実現させなければならないこともたくさんあります。自己採点は手前味噌になりますので、評価は府民の皆様にしていただきたいと思います。
4期目に向けての抱負ということですが、多くの府民の皆様から来年4月の知事選挙に出馬せよとの温かいお言葉を賜り、さる12月府議会で出馬表明をさせていただきました。まず、4府総ですが、これは2000年までの計画になっており、残された期間は約3年ですので、総仕上げに向けて取り組んでいきたいと思っております。
ただ、これからの豊かさというのは「もの」だけでなく「こころ」の豊かさや「やさしさ」が求められていると思うのです。西田先生は、府議会で教育問題をよく取り上げて御質問されておられますが、21世紀をになってもらう青少年をどう育てていくか、高齢化社会の中で病気や老後の生活、あるいは地域環境の安心・安全などいろいろな点での「安心・安全」が必要ですし、また、体の不自由な方や高齢者の方が十分に社会生活が出来る、社会で活躍できる、さらには男女間の平等など「公平・公正」な社会でなければなりません。そういう、府民一人一人を大切にする京都府作りを進めていきたいと考えております。
もう一つは、地方分権ですが、これからは、地方自治体は画一的なお仕着せではなく、それぞれの地域の特性を生かし、住民の気持ちを、早く、木目細かく生かしていけるようにすべきです。国は、外交、防衛、司法など基本的な問題に限って所管し、それ以外のことは地方自治体がやる方が早く、木目細かく職員の意欲も湧いてくる。こういう思想のもとで地方分権の流れが出てきたと思っております。京都府としては、この機会に、府民の方々の目で見てやはり分権した方がよかったと思っていただけるよう、市町村長さんと協力しながら、また、西田先生は、今、府議会の地方分権特別委員会の副委員長をやっていただいておりますので、その中でも御相談させていただきながら、地方分権を進めていきたいと考えております。
5.座右の銘

西田議員
西田昌司 知事の座右の銘をお聞かせください。
荒巻知事
無信不立 - 信なくんば立たず。
府政を進める元は、府民の信頼です。
西田議員
今後とも一生懸命やっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。
明けましておめでとうございます。
参議院議員 西田吉宏

西田吉宏参議院議員 皆様にはお揃いで佳い年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
私も皆様の力強いお力添えに支えられて現在、参議院議員運営委員会で自民党筆頭理事として元気に国会活動を続けております。
政治は、日米・日中・日露関係をはじめとする外交問題、安全保障・沖縄の問題など山積みする課題に直面していますが、とりわけ最大の課題は何といっても景気対策であります。
国内の景気は依然として足踏み状態が続いており、加えて株式市場の動揺や金融機関の経営破綻がこれに追い打ちをかけております。
私どもは一日も早い金融システムの安定に努め、特に中小企業や自営業者の方の生活を守り、かつ豊かな次世代を切り拓くためにいろいろな痛みを伴いながらも、社会・経済システムの大胆な改革に取り組み、21世紀の子供たちに確実に引き継いで行きたいと考えています。
京都府におきましても、荒巻知事や桝本市長を先頭に活力ある街づくりに懸命の努力をしておられますが、今後更なる伸展のために私も知事・市長・及び西田昌司府議会議員等と緊密に連携しながら一生懸命に頑張って参ります。どうぞ皆様の変わらぬご協力をお願いし、皆様方の一層のご健勝とご多幸をお祈りして新年のご挨拶と致します。
文芸春秋社「諸君!」から取材!!
文芸春秋社の発行しているオピニオン誌「諸君!」2月号から西田昌司議員が桂高校制服導入問題について取材を受けました。桂高校では一部の生徒が制服問題で国連に提訴するという騒ぎにまで発展し、これまでもマスコミなどでも度々取り上げられてきました。「諸君!」ではこれらの問題を真正面から見据え「一体制服導入の何が悪いのか、少しも悪くないではないか」という視点に立ち、この問題を府議会で取り上げ、議論に一石を投じた西田議員に意見を求めたものです。西田議員は取材の中で以下のように述べました。
「桂高校の問題は、組合の活動家教師と保護者に一部の生徒が扇動されたという特殊事情はあるものの、その根本には全国どこの学校でも共通する問題があります。それは親や教師が子供に迎合するばかりになったということです。親や教師という大人は子供に対して大人としての良識常識を教える義務があります。とりわけ親の責任は重く、子供の教育には全責任を負わねばなりません。しかしその義務を全うするためには子供と衝突し、ボロボロになるまで向き合う覚悟が必要です。こうしたことは親にとっても大変な労力と情熱を要するものですからできたら逃れたい、そこまで子供に関わりたくないという気持ちになる人もあるものです。しかし、こうした気持ちにはどこか後ろめたさが付きまとうものですが、この後ろめたさから逃れるためにこうした人たちは、子供には子供の人権があるという美しい言葉を述べることにより、親の責任を放棄している自分の後ろめたさを糊塗しているのではないでしょうか。しかも問題はそうしたことに当の本人が全く無自覚な親が多いということです。しかし、そのつけは必ず親に子供の反逆という形で現れてくることを忘れてはなりません。昨今の子供に関わる様々な問題は大人になりきれなかった人間が子供を作り、親の責任を果たさないままにその子供がまた子供を作るという、悪循環に陥っていることから生じているのではないでしょうか。つまり、社会に親としての責任を果たしているまともな大人の存在が、少なくなってきてしまったということなのです。子供に迎合しているだけのことを、物分かりのよい親だと勘違いしている大人の精神構造こそ問題なのです。」
編集後記
明けましておめでとうございます。
まもなく、長野オリンピックが開催されます。少年の頃ブラウン管の中、札幌で繰り広げられたあの感動が蘇るのかと思う反面、あの時ほどの期待感はないようにもおもえます。むしろ家庭や友人のことや地域で起きる本の些細なことに一喜一憂している毎日がいとおしく思えます。そしてこんなにも多くの幸せに気がつく歳になったことにむしろ喜びを感じます。日本選手の健闘とこも一年の皆様のご健勝をお祈りします。
松本 秀次

わが国は、明治維新以来、欧米の列強に一日でも早く追いつくように、地方分権的な幕藩体制から中央集権的な明治政府を作り上げてきました。こうした方式は、大東亜戦争、そして敗戦と続くのですが、戦後のアメリカ軍の占領時代に地方自治法がつくられ、官選知事の時代から選挙で選ぶという方法に変えられました。しかし、中央政府が様々な形で、地方自治体に指導監督することには変化がありませんでした。それは戦後の復興という、なによりも優先すべき課題の表現のためには中央集権的な体制の方が有効とされたからです。しかし、今や飽食の時代を迎え、豊かさの基準も変わってきました。多様な価値観を大切にし、住民のニーズに的確にそして即座に対応するためには、中央集権より地方分権型社会の方が適しているという考えから、今日、地方分権という言葉が盛んに言われるようになりました。
この考え方は、消費者の求めに応じて、なにもかも市場競争原理によって配分すればよいとする規制緩和の議論と軌を一にしています。両者ともに共通しているのは、住民を消費者と同じ尺度で捕らえていることです。望みのままにやすくて良い品をいつまでもどこでも手に入れることが消費者の利益を守ることになるのと同じように、納税者の納めた税金を効率よく運用して、住民の望みのままの行政サービスを行うことが自治体の役割だとする考え方です。つまり中央集権という規制を緩和して、住民と一番身近なところにいる自治体に財源と権限を渡すことによって、税金の効率的運用を図ろうとするものです。
確かにこうしたことは、財政構造改革を図る上でも非常に重要な考え方であります。しかし、この考え方の一番の問題点は、住民は税金さえ納めれば、後は役人や政治家にその効率的運用とサービスの向上を任せておけばよいとするところです。これは、納税者はお客さん、自治体はサービス産業という考え方であり、消費者と事業者との関係をそのまま地方自治体に当てはめたものです。この考え方では行き着く先は、行政サービスもすべて民営化して行かざるを得なくなります。そして、お客である納税者は税金さえ払っておけば、後は行政に対して要求だけを突きつけておけばよいということになります。これでは、自らのふるさとを自らが納めるという自治意識はみじんも育てることにはなりません。
大切なことは、中央集権であろうが、地方分権であろうが自分の国やふるさとは自分が守り育てて行かねばならないという一人一人の気概ではないでしょうか。今のような、住民の自治意識を育てない行政の効率化だけでは、中央と地方の役人の権限のぶんどり合戦にしかすぎなくなります。このままでは、「地方分権論は、五右衛門風呂と同じで上ばかり熱く中は冷えたまま」といわれても仕方がありません。
それでは、地方自治の確立のためにはなにが一番必要なのでしょうか。
一つは、教育の問題です。昔は郷学と言われるように、自分の住む地域や街の歴史、経済、人としての生き方を考える学問が盛んでした。今日では生涯学習や学校教育で、地域社会のためになにをすべきか、誇りやボランティア精神を共に学ぶことが必要です。もう一つは、新しい経済・地域に根ざした産業の育成です。子供達が出て行かなくても生活できる職業の多様化と、地方の足腰を強めるための地方独自の産業基盤の創出です。
この二つが地方自治のためには絶対に必要なことではないでしょうか。今日の地方分権議論は、知事や市長がまず権限、財源を譲ってくれといっているばかりで、肝心の住民の声というのは殆どあがっておりません。自治意識の向上のため、特に私は、郷学の振興に代表される教育の問題をもっと腰を据えて考えないと地方自治どころか日本の国としての自治もできなくなると思うのです。そして、このことを訴え共に考え実行するのが、、住民の代表たる議員の仕事だと思うのです。
福祉のあり方を考える

去る8月28日、西田昌司議員がじゅらく共同作業所に視察に参りました。この作業所は社団法人京都市身体障害児者父母の会連合会が運営する民間の施設です。共同作業というのは障害者が集まって共同で事業をするということが建前です。しかし、実際にはこの作業所のように重度の障害のために全く仕事ができず、作業者と言うよりデイケアセンターとしての役割を果たしているところも少なくありません。しかし、その運営については、国の制度の隙間にあるために、非常に厳しい財政上を余儀なくされています。こうした状況を一人でも多くの方に知っていただくために父母の会と西田議員との間の往復書簡を紹介いたします。
---------------------------
西田昌司議員殿
先日は先日はお忙しい中「じゅらく共同作業所」を見学していただき、また保護者や職員の生の声を長時間に亘り傾聴して頂き関係者一同大変感謝しております。
ともすれば、通り一遍の見学が多い中で、自ら足を運び、現状を認識理解しようとする議員の姿勢は私たちの胸を打ち、大変感激いたしました。
ご覧の通り「じゅらく共同作業所」は、重度重複の障害を持ちながら公的施設に入ることのできない子供達を持つ同じ様な親の集まりである「社団法人幸年身体障害児者父母の会連合会」が、独自で管理運営している民間の施設です。年間の運営費は約3,000万円強を要しますが、内1,800万円を京都市より補助金としていただき、後の1,200万円を運営母体の父母の会連合会の助成金、保護者の負担金、バザー収益金、後援会費等で補っております。限界を越えんがばかりの大変な運営であります。送迎用の車両一つをとっても、耐用年数が遙かに過ぎ、走行キロ13万キロで故障が続き、大変な経費がかかります。保護者の負担を少しでも軽減すべく現在の賃貸料(70坪ほどの倉庫25万円/月で借用)を軽くする場所も探しております。入所生は、年々重度重複化し職員の肉体的負担も相当なものですが、増員も財政が許さず、日々、火の車の状態と言っても過言ではありません。保護者をはじめ関係者は公的施設が一日も早くでき、皆が入所できる日を待ち望んでおります。
「何時、自分が、子供が、障害者や障害を持つ子供の親になるか。皆その可能性を抱えている。自分の立場で少しでもお役に立つことができるなら。」
この先生の言葉に、私たちは議員の並々ならぬ御決意と真剣に取り組む心のある姿を拝見できたように思います。
先生が、子供達と同じ目線で見聞し、学ぶという姿で自分を位置づけられ、更に保護者、職員と話し合っていただいたことは、私たちとっても確かな次への躍動を感じることができました。
体験した親しか解らない想像を絶するような苦しみを乗り越えてきた私たちに、議会を通して、また先生個人の活動を通して、行政や社会により一層理解をしてもらう橋渡し役を化って出ていただいたことに心より敬意と感謝の意を表します。
山積みする問題を解決するには、どれも時間を要するものと思いますが、身近にできるものから積極的に取り組んで頂けるように私たちも頑張りますので、末永くお力添えをくださいますようお願い申しあげます。
社団法人京都市身体障害児者父母の会
連合会会長 関 五郎
---------------------------
社団法人京都市身体障害児者父母の会
連合会会長 関 五郎様
お手紙を頂き有り難うございました。先日、そちらの「じゅらく共同作業所」にお伺い致しまして私自身多くのことを学ばせて頂きました。
私は当初、その会のお名前から、交通事故などで肢体障害を受けられた方々の会というイメージをしておりましたが、実際は、生まれた時から障害を背負ってきた子供たちが殆どで、そのうちの大部分のか方が知的障害と、肢体不自由という重度障害のある方々でした。言葉も話せない、食事も一人では食べることができないという姿を目の当たりにいたしまして、正直かける言葉を失ってしまいました。私も議員として、様々な福祉の施設に視察を致しましたが、これほど重い障害の方は初めてでありました。しかしそんな中でも、父母の会の皆様方が子供達のために我身も忘れ必死で生きておられる様子を見て、父母というものの有難さと偉大さに心を打たれる思いをいたしました。もしこれが逆の立場で、子供が障害のある親の面倒を見るということであったら、果たしてこんなに献身的にできるのだろうかと、しみじみと感じました。といいますのは、老人ホームに親を預け放しで、一度も面会に来ない方が少なからずおられるという話をよく耳にするからです。
共同作業所に対する補助の問題は基本的には国の制度が変わらなければ、どうにもならない部分があります。特に京都市のような政令指定都市は府県並の権限と財源が与えられているため、京都市内の施設に府が助成することには制度上の大きな壁があります。最近では高齢者に対する福祉の充実はずいぶん進んできました。これは、高齢という誰もが辿る道であるため、大きな世論の盛り上がりを背景に国も一挙に進めることができたのです。
しかし、本来国や行政が真っ先に手を差し出さなければならないのは、皆様のような非常に重い障害をお持ちの方に対してではないかと思います。そのためにも、一人でも多くの方に皆様方の実態を知って頂き、大きく世論をうごかすことが必要だと思います。そういう観点から議会や後援会を通じて活動を進めで行きたいと思っております。
一人の声は小さいものですが、多くの声が集まれば必ず、制度も変えてゆけると思っています。皆様と共に一つずつ問題を解決していけるよう私も全力を尽くしたいと思っています。皆様のご健康とご活躍をお祈り申し上げます。
京都府議会議員 西田 昌司
銭湯における福祉介助入浴実施の試み
柳井湯 村谷 順一
平成7年11月より南区開ヶ町の柳井湯において介助入浴を始めまして、はや2年を迎えます。福祉介助入浴というのは、入浴はしたいが一人では不安がる高齢者や障害者の方を対象として、銭湯において医療、福祉、保険所、病院、看護学校生、地域のボランティアなどの関係者がスタッフとして集まり、入浴のお手伝いをするものです。
利用者のお迎えから始まり、入浴前に体温、血圧、脈拍などのバイタルチェックを行ない、その日の体調が良ければ、衣服の着脱、浴槽の出入り、体を洗うお手伝いを行なっています。そして、入浴後にはお茶を飲んでいただき、徒歩帰宅または車でお送りしています。また、終了後には反省会を開き、次回に備えます。
使用者の反応は非常に良く、大変喜ばれており、それがスタッフのやりがいとなって現在まで事故なく続いている一因だと思います。
「地域を地域で守る」ということを基本として、人々が豊かさを実感できる地域にしたいという願いから、身近な事から取り組みを行なっています。高齢者や障害者に関わる医療、食事、介護、入浴などのうち、浴場を社会資源の一つとして活用し、入浴に関して設備を提供し、スタッフを集めてどれほどのことが出来るのか、行政が実施しているデイサービスの補完事業として位置付け、実験的に行なっております。
この企画には多くの方の協力がなければ続けていくことができません。この紙面をご覧になった方で、少しでも関心をお持ちの方は是非見学からでも参加してみて下さい。心よりお待ち申し上げております。
「国」は何のためにある?
弁護士 森田 雅之
犯罪は犯せば罰せられる。これは、国が被害者に代わって犯罪者を処罰することによって、被害者の報復感情を和らげ、私的な報復を防止して、法秩序を維持するためである。国がこのようにして法秩序を維持するのは、国民の生命、身体、財産を守るためである。
一方、犯罪者が少年である場合には、罰せられないことがある。一口に少年と言っても、生まれたての者から明日20歳となる者まで含む。この中には、未だ事の善悪を判断するまでに精神が発育していない者もいる。刑法はこれを14歳未満の者とした。また、14歳以上の者であっても、少年は精神的な未熟さの故に犯罪に陥ることが多く、他方その未熟さ故に将来の矯正・更正を期待することができるから、成人と同じ刑罰処罰を科すことが適当でないと考えられる場合がある。そこで、少年法は、16歳未満の者には刑事処罰を科さないこととした。16歳以上の者は、刑事処罰を科される場合があるが、それでも同様の理由で成人とは異なる刑が科される。これは、少年の将来を保護することによって、立派な成人となり、国を支えてもらうことを期待したものです。
上の二つは、どちらも国の役割として重要なものであることは間違いない。しかし、どちらがより基本的な役割であるかといえば、前者であることも間違いないことであろう。国民が安全に暮らせる国であってこそ、安定した将来もあると言える。少年法は、それを間接的に支えるものである。もし、少年法の故に、日本が国民の安全を守れない国となろうとしているのなら、少年法自体もその役割を果たせていないと言わざるを得ない。
少年法の見直しに関しては、枝葉末節まで様々な点が取り上げられているが、根本的には国のあり方をどう考えるかという視点を忘れてはならない。そして、すでにお判りのとおり、それは少年法に限った問題ではないのである。
西田昌司議員が全国青年議員連盟会長に就任!!

去る8月21日、大阪市において自由民主党全国青年議員連盟(青議連)の全国大会が開催され、西2田昌司議員が第16代の会長に選任されました。青議連は今から34年前、当時大阪府議会議員だった中山太郎元外相らが中心になって作られた自民党籍を有する50歳までの地方議員の会で、国や党に対して青年議員の立場から常に正論を主張することを旨に活動してきました。
また、本年度の上記大会で西尾幹二電通大教授、藤岡信勝東大教授、高橋史朗明星大教授との歴史教育の問題点等に関する討論会が行われました。マスコミ等で見られる「従軍慰安婦」問題や現代の歴史教科書問題などが議論されました。この模様を収めたビデオも貸し出ししておりますので、ご利用の方は Showyou編集室までご一報ください。
編集後記
『秋色』。最近、母の里へ帰ることがあった。30数年前この畦道でこの小川で、随分遊んだことを思い出した。今、近くにバイパス道ができ、川はコンクリートの用水路になっている。子供達が遊んでいた。ザリガニを採っているらしい。キャッキャッとさわぐ声につい思い出が蘇った。
松本 秀次
今年の12月に「地球温暖化防止京都会議(COP3)」が開催されます。今回のSHOWYOUでも,これにあわせて環境問題を様々な角度から考えていきたいと思います。
現在の私たちの生活は,多くのエネルギーや資源の消費の上に成り立っています。特に,石油や石炭といった地球が生み出した化石燃料を燃やすことにより,膨大なエネルギーと物質的な豊かさを得ました。しかし,これは二酸化炭素という気体を大量に空気中に放出する結果となりました。この二酸化炭素には地球の熱を宇宙に逃がさない(温室効果と言います)性質があるため,このまま増えつづけると100年後には,地球全体の平均気温が2~3度上昇することになります。わずか2~3度ですが,恐竜が絶滅した氷河期でさえ,地球全体の平均気温は今より2~3度低いぐらいであったと言われています。
このことからも,平均気温が2~3度上がるということは,地球環境にとってどれほどの驚異であるか想像していただけると思います。気温が上昇することにより極点の氷が溶け,海面が数メートル上がります。平地が水没し,地球上の人間を養うだけの田畑がなくなり,深刻な飢饉が続きます。その上,マラリア等の熱帯性伝染病が大発生するなど人類にとっての最悪のシナリオが,多くの科学者に指摘されております。
そこで,このような事態を回避し地球環境を守るために,世界各国が協力して二酸化炭素の排出や増加を抑制しようとするのが,今回京都で行われるCOP3の大きな目的となっています。
KBSの討論番組でも言いましたが,私は環境問題を考える上で,次のような3つの視点が重要であると思っています。
まず第1に,環境問題は私たちに直接関わる問題であるという認識を持つことだと考えています。地球環境などと聞くと自分の生活には余り関係ないと思いがちですが,ゴミを始め環境汚染の大半は,実は私たちの生活から出されるものなのです。政府や自治体に任せておけばいいという性質のものではないと思います。
かって,オイルショックの時に「省エネ」という言葉が流行りました。深夜のテレビ番組は自粛され,日曜日にはガソリンスタンドが休業となり,国を挙げて石油の消費を削減しようとした時期がありました。しかし,“喉もと過ぎれば熱さを忘れる”の諺のように石油の安定供給が続くと,私たちもついつい生活の心地よさを求めるようになりました。地球温暖化の原因を生み出しているのは,私たちのこの生活スタイルにあるのですが,その影響を受けるのは,私たちの子どもや孫子になるのです。その影響も,オイルショックの時は便利さ・豊かさでしたが,子孫の生存に関わる深刻な問題なのです。それだけに,私たちは,オイルショックの時以上に生活のスタイル・習慣の見直しを行い,しかも継続していかねばならないと思うのです。
第2は,国際協力体制の確立ということです。例えば,酸性雨による松の木の立ち枯れの問題をみますと,この原因はどうも中国の工業化と関係がありそうだと言われています。中国では近年の門戸開放や経済の自由化により,上海を初めとして沿岸部の工業化は著しい発展を遂げています。沢山の工場が建ち,火力発電所が建設され,二酸化炭素の排出量も急激に増加してきました。これが偏西風に乗り日本の上空で水蒸気と同化することにより酸性雨となって降ってくると言われています。このこと一つを取ってみても,環境問題は日本だけでなく広く外国との協力が必要なことがわかります。この諸外国との協力という点からも,COP3の意義は大きいのです。
第3の問題は,1番目と関係しますが,私たちの価値観を「競争・効率」から,「競争と共生のバランスの重視」へと変えていく必要があります。今の日本は何事にも規制の緩和と自由競争の拡大の声が聞こえますが,地球温暖化や環境汚染の原因は経済の自由競争の行き過ぎがもたらしたものと考えられます。大量生産,大量消費,大量廃棄が繰り返され,地球の資源の枯渇と環境破壊がもたらされました。つまり,自由な競争だけでは,環境汚染や破壊は改善されないどころか,益々悪化させてしまうことにつながります。
環境問題の先進国であるヨーロッパでは,この悪循環から抜け出すために,経済成長よりは雇用や環境保全を優先する考え方が広く支持されるようになってきました。つまり,マーケットニーズよりソシアルニーズを優先する考え方が常識となってきました。
戦後日本の経済発展を支え,高度経済成長の中で発展してきた「効率型社会システム」は,生活面では,私たちに家電や車の便利さと引換えに環境汚染をもたらし,教育面では行き過ぎた偏差値教育を生み,いじめや自殺を引き起こしています。もう,そろそろこの辺りで,効率追求型の社会から脱皮をすることが必要なのではないでしょうか。
私はこのような信念で、京都の産業経済の問題や教育福祉の問題に取り組んでおります。
COP3 私はこう考える
~エコロジー総体へ向けての私の提案~
五十嵐正幸
本年8月、地球にやさしい大会運営を目指した「全国高校総合体育大会」が開催されます。また、12月には、「気候変動に関する国際連合枠組み条約締結国会議」通称COP3が開催されます。
これと関連して、今回の高校総体では、エコロジー総体と称し、観光客を含め60万人と見込まれる人々に、リサイクル意識の高揚を始め、環境問題に対する京都市民の姿勢をアピールするように、以下のような提案をいたしました。
(1) 競技会場から排出されるごみの分別収集・再資源化
運営上生じるごみについては、発生量を極力抑えるとともに、可能な限り分別収集・再資源化を行い、環境への負荷を低減する。
(2) 低公害車の使用
大会参加者の計画輸送等に使用するバスは、市交通局等の協力を得て、可能な限り低公害車を用いる。
(3) マイカー利用の抑制、公共交通機関の利用促進
二酸化炭素、NOX排出量の抑制を図るため、大会参加者への公共交通機関による来場の呼びかけ、市民への会期中のマイカー利用抑制を促す。
(4) 歓迎草花プランターのリサイクル利用
競技会場等を装飾するプランターは大会終了後、小中学校の教育活動に活用する。
(5) エコ対応品(環境負荷の少ない商品)の使用
大会において使用する紙類等の消耗品類は、可能な限り環境負荷の少ない商品を使用する。
これらの活動のうち、ごみの再資源化の効果をCOP3のテーマである「地球温暖化」に与える影響の大きい二酸化炭素量でみると、空きかん、空き瓶、ペットボトルを資源化するだけでも8,6t(炭素換算)もの二酸化炭素の排出削減につながります。この削減量は、一世帯あたりの一日の冷房による排出量(49g炭素換算)で換算すると約17万五千世帯分に相当いたします。このように「地球にやさしい大会運営を目指す」ことは、COP3の目的である「地球温暖化防止」に直接的に貢献することです。
日本の二酸化炭素排出量は、世界第四位(1アメリカ、2ロシア、3中国)であり、その責任は重く、温暖化防止に果たすべき役割も大きいものがあります。そのためにも私たちがやらなくてはならないことは、国や市単位の活動はもとより、個人レベルでの活動がもっとも重要となります。
やさしい環境を次世代の子供達に残すために、今すぐに私たちにできることを考えてみました。
(1) 省エネルギーでは
1. テレビの使用時間を短くしたり、見ないときは主電源を切っておく。
2. 不要な照明はやめる。
3. 冷蔵庫は詰めすぎないようにする。
4. 調理の時、炎が鍋の底からはみ出さないようにする。食器洗いは低めの温度でする。
5. 入浴は風呂が沸いたら家族続けて入り、入らないときは、こまめに蓋をする。
6. 自動車の不要なアイドリング、急発進、空ぶかしなどをやめる。
7. 徒歩や自転車を活用し、遠いところは公共交通機関を利用する。
(2) 省資源リサイクルでは
1. 空きかん、空き瓶は分別収集に出し、古紙など再生できるものはリサイクルに出す。
2. 買い物は手提げ袋を持参したり、過剰包装は断る。
3. エコマーク使用品などの環境保全型商品を積極的に選ぶ。
4. 使い捨て商品は使わない。
5. シャンプー、洗剤などは詰め替え用を利用する。
6. メモなどは、広告の裏面を利用する。
(3) 緑化では
二酸化炭素を吸収し酸素を生成するなど、緑の持つ環境にやさしい機能を活かすため、ブロックの代わりに生け垣を設置するなど緑化に努める。
今回開催されるエコロジー総体、COP3の共通の目的である「地球環境破壊の防止」に京都市民として、一人ひとりの知恵や工夫で世の中を動かし、温暖化を防ぐ努力をしなければならないと痛切に考えています。
都会のオアシス?
川口観正
家の西側に隣接する土地が、畑でなくなって五年ほどになるだろうか。ほとんど手付かずのままされているせいか、そこだけ時間の流れが周りとは違っているかのようだ。
三、四年前からだと思うが、春先の明け方、「ホーホケキョ」という鳴き声を聞くようになった。うぐいすのモーニングコールというものもなかなか趣のあることだが、同時に都市環境の皮肉さも感じられ、驚きと苦笑の入り交じった心境になる。
その涼しげな声を聞いて思ったこと。
人の手の入っていない、人には荒れた土地としてしか見えなくても、うぐいすにとっては居心地の良い場所なのだろう、と。
近ごろ「関係」という言葉をよく考える。人と人との関係、人と動物、植物との関係。人と物との関係。本来、何かと関わろうとした時生じる煩わしさというものを、できるだけ省いていこうとする、世の中の流れを感じる・・・。
安易に手にいれられる物は、安易に捨てられ、より便利な物へとすげ替えられていく。
手のかかること、不便なことが、そぎ落とされ個と個の間にある関係がぶつ切れになってバラバラに存在している。
間にある物が見えなくなってはいないか。
つながり、関わりに対するイマジネイションがどれだけ発揮できるか。
うぐいすの声はあくまで軽やかに人家の林を吹き抜けていく。
環境を守ることは「関係」を守ることにもつながるのだと思う今日この頃である。
生花の包装を考える
木村和久
現在、日本の生花流通において、段ボール箱が必要不可欠なものとなっている。花の鮮度をよりよいものに保つため、内側がコーテイングされたものなど年々、質の良い物に変わりつつある。勿論われわれ小売業者にとっても、新鮮な物を仕入れることは、最大の願いであるが、廃棄物が増えている現代社会において、この出荷方法(段ボール使用)に感じていた。
花の国、オランダの例をあげてみる。オランダには観光スポットにもなっている世界最大のアルスメール花市場がある。ここで出荷される80%が輸出されており、買参人のほとんどが輸出業者や仲卸といった大口客である。(日本ではほとんどが小売業者)このような市場形態をはじめ、日本との相違点をあげるときりがないが、その出荷方法に注目してみると、花はほとんどが、再利用できるバケツに水の浸かった状態で、セリ場におくられる。段ボールの使用は、最低限に抑えられているため、小売店から出るごみのほとんどが、花のきりくずのみですむのである。
日本人の生活における花の需要は徐々に増えつつあるが、花を飾る、贈る習慣が定着しているオランダに比べると、まだまだ及ばないものである。しかし、今後、需要が増えるにしたがって、オランダの無駄のない、また、資源を大切にする姿勢は見習うべき点であり、大きな課題であると考えるのである。
COP3について
袋布幸信
先日、昌友会の勉強会でCOP3の話を聞き、私の周りにいる人がどれだけこの会議について認識しているか問いかけたところ、私の予想していた通り「COP3て何や」という言葉が全体の90%近くの人からの返事として帰ってきました。
今年の12月に、京都国際会議場で世界の170ヶ国を超える国・地域の代表・NGO・報道関係者などを合わせると5000人以上が参加して行われる会議のことで、地球温暖化を防止するための条約「機構変動枠組み条約」の第三回の会議がこの京都で開催されると説明すると約半数近くの人から「それやったら知ってるわ」と返事が帰ってきました。
私自信、COP3という文字は街の中で所々に張ってあるポスターでは見ていましたが、会議の内容の重要性を勉強会で聞き、21世紀の地球がどの様に変化していくのかを考えると、今どの様に環境を整えていくのかをまず考えてしまいます。
子供たちのために、今私たちが出来ることを一つずつ考えて行かなければならないと思います。不要品のリサイクル、電気、ガス、水道の省エネ等、身近に出来ることから少しずつ実行し、子孫の末代まで環境維持できるように考えていきたいと思います。
8月に行われる全国高校総体で初めての試みとして取り組まれるごみの分別収集、低公害車の使用、装飾に使用する花のリサイクル等、大会関係者のみなさんへのリサイクル意識の高揚と、高校生に対する実践的な教育によるエコロジー総体を成功させるためにも、京都市民の皆様の努力と協力でふたつの事業が成功することを願っています。 これからも昌友会の会員の皆様にいろんな意見を聞かせてもらい、勉強させていただきたいと思っております。
瓦の独り言
羅城門の瓦
地球温暖化防止京都会議がこの12月開催されます。もしこれが平安時代に開催されていたらどうなったことでしょう?まず、食料の確保と、し尿処理が問題になるのではないでしょうか。
かつて昭和3年秋の即位大礼前後の4カ月間に京都市の人口が数万人増加し、様々な問題が持ち上がりました。し尿処理もそのひとつで、水洗が普及していない時代にし尿処理はには人海戦術に頼ったとされています。まして、秋の収穫が終わった時期で、肥料としてのし尿需要が少なく、京都近郊農家の汲み取りには限度がありました。それで、やむなく西九条仏現寺町(近鉄十条下がる)の塵芥処理場は伏見区の横大路に清掃工場として移転し、し尿処理場も昭和14年に上鳥羽に移転をしました。このように南区から伏見区にかけて、大都市にとっては不可欠な処理施設が存在するのはただ土地が低く収集しやすかったからでしょうか。
その要因は江戸時代にまで遡らなければなりません。当時、南区の洛南地域は米作りのほかにそ菜栽培に力をいれ、今日の京伝統野菜が生まれました。これらの商品作物の栽培には肥料が必要となり、人ぷん尿が前時代以上に重要視されるようになりました。当時の京都など大都市では都市化が進めば市中の塵芥処理が大きな問題になるのですが、これらの廃棄物を争うようにして求めたのは洛南の近郊農家でした。
当時、洛南の河川と街道は肥料(人ぷん尿)の流通路として大きな役割を果たしていました。特に、洛南地域には鴨川、高瀬川、天神川、桂川が流れており、市中からの運搬水路高瀬川が担っていました。この当時の高瀬船のし尿の運搬は洛南の村村だけにと止まらず、伏見の下三栖村をさらに飛び越して、摂津、河内の国々まで及んでいたといいます。現金お魅力に引かれて、京都のし尿が洛南の村村を飛び越えて他国に流れ、そ菜栽培に支障をきたし、奉行所に訴える事態が生じました。その結果、東九条村を筆頭とする、高瀬川筋の11ヶ村が主導権を握るようになりました。これが童歌の「九条の肥えたご」となっている由縁です。この時代のし尿処理はまさにリサイクルの見本ではないでしょうか。今日、われわれはリサイクルにはコスト高が伴うため、経済効率を優先させて、真剣に取り組もうとはしていません。ある学者が「ごみは宝の山」といっています。限りある資源を使い尽くした人類は、そのうちにごみを取り合いするようになるのではないでしょうか。その時、我々南区の住民は先人達が築き上げていった「九条肥えたご」のプライドを持って対処していけるのではないでしょうか。
自民党京都府連青年局青年部
中央研修会に参加して
京都府連南支部青年局長昌友会会長 秋田公司
中央研修会の中で1995年1月に世界37ヶ国で調査された「世界価値観調査レポート」のことが話されました。その中で、「仮に戦争になった場合、あなたは進んで国のために戦いますか」という問があります。「はい」と答えたのは、日本は10.3%これは世界最低です。アメリカは70%、韓国は85%、中国は90%以上で、日本と同じように敗戦後経済発展をしたドイツも低い方ですが、30%となっています。
次に、「国民すべてが安心して暮らせるよう、国がもっと責任を持つべき」という設問では、日本が63,2%で37ヶ国中最高の数字となっています。今の日本人は安定した暮らしについては、どの国にも負けないほどの要求を国家に求めながら、他方、有時の時、自国のために戦うというのは10人にひとりしかいないという世界でも飛び抜けて低い責任感しか持っていないということがよくわかります。利己主義の国民、国家になってしまっているのです。
安心で安全な国家を次代へ引き渡すために、自分が果たすべき役割の再確認をしたいものだと思います。そのためには自分と国との関わりを考えてみることが大切だと思います。自分が国になにかを求めるとき、J・F・ケネディが言った「自分が国家のために何をすべきか」という言葉も頭の片隅には置いておきたいものです。
年明け早々の1月2日に発生した、ロシア船籍のナホトカ号沈没事故は、京都府始め、日本海側の多くの府県に大きな被害をもたらしました。京都府では1月8日に警戒本部を設置し、重油が漂着しだした1月9日には、事故対策本部に切り替え、被害を最小限に食い止めるための措置をとって参りました。また、われわれ自由民主党も事故発生直後から地元の丹後選出議員が中心となって、現地を視察、激励し、行政機関に対しましても適切な措置を迅速に行うよう要望をしてきたところであります。私自身も府議会の警察常任委員会、環境対策特別委員会を通して直ちに現地に直行し、現場を調査視察をするとともに、ボランテイアとして重油回収作業に力を注いできたところであります。
そうしたことを踏まえまして、私は2月11日(建国記念日)に当初予定しておりました党の全国統一街頭演説を中止し、自民党の青年局長として京都府下の青年党員に、重油回収作業への参加の呼びかけを致しました。最初はどれほどの参加者があるかと心配しておりましたが、大型バスと乗用車を乗り合わせて青年党員を中心に約70人が参加をし、猛吹雪の琴引き浜で重油回収作業に微力を尽くして参りました。重油回収に先立ちまして、網野町の浜岡町長から、これまでの被害の状況や回収作業の問題点などについて説明を受け、新聞やテレビなどでは伝わらない現地の人々の悩みを知ることができました。

こうした経験から私は今後の教訓とすべきものとしていくつかのことを感じました。1つは、一昨年の阪神淡路大震災でも言われたことですが、まさかの災害に備えての危機管理体制がまだまだ十分とは言えないというこであります。関係の市町や舞鶴にあります第八管区海上保安本部や、海上自衛隊との連絡体制は大震災の教訓が生かされましたが、問題は重油の回収は海上にしろ、陸上にしろ、最終的に手作業によらざるをえなかったことです。今後も日本海には老朽化したタンカーの往来が多いことから、いつ同じような事故が起きるやも知れませんし、いつ海底に沈んでいる重油が船から流出し漂着するとも限りません。京都府が開発をした砂油離(さゆり)号は1台で300人分の働きをすると言われていますが、今後は重油回収船など海上での回収装置の設置が早急に必要となります。
2つめは、ボランテイアのあり方です。今回の重油回収作業には延べ何万人もの方にご協力を頂きました。その協力がなければこれほど早く重油回収はできなかったと思います。しかし、そのボランテイアの方々が円滑な作業ができるように、地元では受け入れ体制をつくるのに、大変な負担をしています。大震災の時もそうでしたが、自衛隊や、機動隊という部隊が災害復旧に来てくれるのと、一般のボランテイアが来てくれるのとでは、地元の負担も全然違うのです。前者の場合は放っておいても仕事をしてくれますが、後者の場合には仕事ができるように段取りをしておかねばなりません。いわば、ボランテイアの世話をするボランテイアが必要なわけです。それは一体誰がしているのかと言えば、地元の町役場の職員であったり、漁協の職員であったり、まさに地元の人間が昼夜兼行でボランテイアの受け入れ体制づくりを行っているのです。今後はそういうことも頭にいれながら、地元に負担をさせないボランテイアのあり方というものも、考えておく必要があると痛切に感じました。今学校では、ボランテイア教育を盛んに取り上げていますが、このことにも目を向けるよう府とも話し合うつもりです。
最後に地元の町長さんたちが是非とも皆様に、お願いをしておいてほしいと異口同音に言われたことをご紹介致します。「重油の回収では大変お世話になりました。今度は是非ボランテイアではなく観光客として、蟹を食べに、また、海水浴に来て下さい。それが何よりのボランテイアです。」皆様のご協力、ご理解をお願い致します。
シリーズ教育 -制服の是非-
先日(2月25日)京都府議会本会議で,桂高校の制服導入問題を取り上げ,府知事・教育長に質問をしました。いくつかの新聞にも取り上げられましたので,お読みいただいている皆様もおられることと思います。しかし,残念なことに余りにはしょった記事だったために,私の教育に対する質問が何か「制服」の導入という形のみにとらわれているかのような印象になっていました。そこで,質問の内容を振り返りながら,教育の何を問い正したかったのかをまとめてみました。
桂高校ではここ最近,茶髪やピアスでの登校や遅刻の増加などの問題が多く,地域や地元保護者からも改善を望む意見が多く寄せられていました。新しく就任した校長先生は,生徒指導・学習・進路指導の充実を図るためには,まず,生徒の生活の乱れを直し,規律ある生活を送らせることが至上命題であると考え,その方策の一つとして制服の導入を提案し,職員会議や部長会議等で検討討議し,生徒会や全校生徒にも説明し,一年以上の時間をかけ準備をされてきました。昨年の2学期の終業式の際に制服導入の決定を伝えたところ,式後に一部生徒が校長に詰め寄るなどの行為があり,新聞にも報道されました。また,3学期の始業式でも再度校長は制服導入を伝えたのですが,その後に壇上に上がった生徒指導部長は,「校長に負けないで,みんな生徒会としてもっと反対の意見を盛り上げよう。」という趣旨の発言を行い,会場は混乱に陥りました。またこのような中で,一部の保護者の方々からは,説明が不十分で拙速であり,もっと時間をかけるようにという要望書も出されました。
生徒指導部長が生徒を煽動し,対立を助長させるような言動はもっての外ですが,私は次の3点から,この問題を考えてみたいと思います。
1. 制服そのものに対する是非の問題。
2. 学校の組織運営をどう捉えるかの問題。
3. 導入の際の手続きの問題。
1番目の制服の問題は後で述べるとして,2・3番目の問題について先に触れたいと思います。
府や教育委員会は,学校運営は校長を中心として円滑に行われるものと考えていますが,組合や共産党は,学校は生徒や職員会議が中心であると言っています。学校は子どもに教育を行う場であり,教育活動の主人公は生徒や子どもであることは当然です。

しかし,学校は生徒を教育する目的を持った組織であり,学習活動の主体としての生徒や子どもと,教育という目的意識を持ち,計画的・系統的な目標と内容を,組織的に行うための運営体制とは別の次元の問題であります。
これを意識的に混同し,「場としての学校」と「組織としての学校」を同列に論じるのは,為にする論議,混乱を意図した論議と言われても仕方がないことであると思います。
学習がおこなわれるプロセスの中で生徒が主役となり,自分の考えを述べ,検証を行うのと教育目的に沿って計画的・意図的にこれを行うのとは大きな違いがあります。学校が組織的に行う教育計画や系統的運営で校長の姿勢に反対だからと言って,生徒を煽動するような態度は,教師としての己の指導責任を捨て去るものと言っても過言ではないでしょう。私は,学校運営は校長を頂点として円滑に運営されるものと考えています。そのため,校長は学校で行われる教育活動に際して,法に沿って施行された学校の管理運営規則に則り,自己の教育信念を貫き,また,学校の最高責任者としての位置にあるのです。学校組織という運営の中で校長は最終責任を負いますが,それは部下である教員は何をしていてもいい,責任は校長にあるのだからというものではないはずです。
次に,手続きが拙速ではという意見がありますが,これも少し的外れの問題だと言えます。桂高校では,校長就任以来1年半の時間をかけて論議がされてきました。なるほど,公式発表は昨年の12月かもしれませんが,これも一部の教職員組合に属する教師が,徹底的に校長に抵抗し発表を遅らせたといいます。また,この手続き問題を指摘される方々の意見では,現実の生徒の服装や目に余る遅刻,生活の乱れなどの改善に向けた指針や意見には何も触れず,単に説明が不十分と言っているにしか過ぎず,現実の問題を解決する方法には目をつむっているとも言えます。
さて,高校に「制服」を導入する意味は何でしょう。勿論,企業や工場で安全や衛生のことから制服を着るのとは意味が違います。先日,テレビで高校生の制服着用を取り上げ街頭でインタビューしている様子を放送していましたが,外国人からは「奇異に感じる」や「日本の文化」などの意見に対して,女子高生からは,「私服では華美になる」や「高校時代にしか着れないから」などの意見が出ていました。また,新聞報道でアメリカの或る州では,子どもたちの安全(事故や麻薬売買等に巻き込まれない)のために,制服を導入する話が報じられていましたが,今の日本ではこれは考えられない話です。では,制服の導入にはどんな意味が有るのでしょう。
桂高校の制服導入の際の校長の考えは次のようなことです。
1. 見られている学校,見られている自分を意識させる。
2. 桂高校生であることを意識し,桂高校生としての一体感を養う。
3. 学校生活にけじめ・めりはりをつけ,授業での集中力と意欲を喚起する。
以上3点をあげ,ここ数年の茶髪やピアス遅刻といった生活態度の乱れに対して指導の第一歩にしたいということでした。
勿論、制服導入が万能の特効薬ではありません。しかし、現実に学校運営の先頭に立ちがんばっている校長や生徒指導や授業の前面で取り組んでおられる先生方の立場からすれば、これに勝る改善策がないのも事実であります。私も、PTA会長をしていた経験から,今の教育のしんどさもある程度は分かっています。今後も,府議会では先頭に立って質問もし,学校の正常化のためには支援を惜しまないつもりです。
或る高校の先生から,茶髪やピアス以上に問題はポケベル・携帯電話の使用であるという話を聞きました。授業中の電話の使用を注意したら,「掛かってきたから仕方がない」という返答だったそうです。また,或る先生が茶髪を注意したら,「煙草と違って体に悪いことはないし,そんな法律も規則もない。これも私の個性だからいいじゃない。」と言われて,はたと返事に困ったという話も聞きました。
このような話を聞くにつれ制服の導入以上に何か先生と生徒の関係に問題があるのではないか,価値観の問題や価値判断の混沌が学校にあるのではないかと疑問に思いました。子どもたちには,集団における個性の在り方やその発揮の仕方を取り違え,指導すべき先生方にも,集団の規範やルールという問題を,個人のレベルと混同視する誤りがあるのではないかと思います。
先ほどの先生も,生徒の態度がいいとは少しも思っていないでしょう。しかし自分の価値観に自信が持てない,何故いけないのかを教える自信がないのだと思います。昨年の中教審第1次答申では,「生きる力」を身につけることが今後の教育に必要であると述べておりますが,何のために「生きるのか」は触れられておりません。この何のためという目的が無ければ,生きる力は個々ばらばらな,単なる方法になってしまうでしょう。そのため,この何のためにを身を持って教えるのが先生であろうと思います。
子どもたちが,何のために生きるのかを考える力を身につけているのなら,先生が困惑するほど子どもたちの生活が乱れたり,意欲の無い生活を送ることもないでょう。
制服を着るのは,子どもたちに自らのアイデンティティを考えさせる機会であるかもしれませんが,子どもたちを「管理」する手段ではないはずです。子どもたちの生活の乱れは,子どもたちに自らの生活を判断する価値基準を何ら育て得なかった学校の責任も大きいはずです。一見すると,物分かりが良いように見えても,自分の価値観を語らず,迎合するだけの大人には子どもは信を置くことはないでしょう。桂高校の問題も,制服の導入に際して、校長先生が自らの人生観や教育観を先生や生徒に一年半掛け話し合ったと言うことは、その意味で評価できることです。規則や校則だけでは,教育と無縁な管理になり,表面を繕うことだけを教えることになるでしょう。
教育は結局のところ,社会の価値を,先生や親の人生観・信念を通して子どもたちに伝えていくことだと思っています。数学や理科の知識は,それだけに価値があるのではなく,それを生み出し育ててきた文化を共に伝えてこそ価値があるものと思っています。教育は単なる知識のみを子どもたちに伝えるのではなく,それを育んだ文化を伝えてこそ教育としての価値があるのです。学校は子どもたちの良き社会人として道徳や価値観,日本の文化や伝統を守り次代に伝えていく力を育て,社会の一員としての善な資質を育てていく責務があると言えます。先生や親はこの最前線に立っていると言えるのではないでしょうか。
さて、年末のクリスマスシーズンになるとどこの家庭でも小さな子供たちが、サンタクロースに今度のクリスマスには何が欲しいと、お願いをしています。わが家においても例にもれず、小学4年生と2年生の息子達が、新聞に折込まれている大型玩具店のチラシを見ながら、あれがいいとか、これがいいとかいう話をしておりました。兄の方は、サンタクロースの正体を、自分の両親であると知っているらしいのですが、弟の方はまだ半信半疑の状態で、一所懸命に何処にいるとも分からないサンタクロースにプレゼントのお願いをしております。
それを見ていて兄の方も、弟の夢をこわしてやってはいけないと一緒になって、サンタクロースにお願いをしておりました。そして、そばにいる私達に聞こえるようにわざと大きな声でお願いしている様を見ていて、私はとてもほほえましく、又、 幸せを感じたものでした。
さて、考えてみると、たわいもない、こんなことが、人間の幸せであるかもしれません。正月に初詣をして、神様や仏様にお参りをするときも、人々が願うのは、家内安全であったり商売繁盛であったり、ほんのささやかな幸せをお願いしているのではないでしょうか。

そしてそんなことを願う私達が、幸せの一番典型的な光景として想い浮かべるのが夏休みの家族旅行であったり、田舎に墓参りに帰ったときに一族皆が集ったことであったり、家族だんらんの様子ではないでしょうか。家族だんらん、これ程、ささやかで大きな幸せは(我々にとって他に)無いのではないでしょうか。
ところが最近の人間社会の中でこの一番大切な幸せの基準が、非常にわからなくなってきてしまいました。一体人間にとって、何が一番幸せの基かが分からなくなってきてしまったのです。
マスコミなどは21世紀の日本はこんな便利ですばらしい世界になるといいます。例えば、コンピュータネットワークにより家に居ながらにして世界の物品が買物できたり、見知らぬ外国の人と話ができたりなど云々・・・・・・。しかし、確かに、これは便利な社会だとは思いますが、これが幸せな社会だとは私には思えないのです。むしろ、この便利さが反対に我々の幸せの根本を知らないうちに蝕んでしまうのではないかと危惧してしまうのです。
産業革命以降、世界の先進国で便利で豊かな社会を目指してまいりました。
そして確かにそのことが私達の幸せの基準と一致してきました。しかし、近年、こうした豊かさや便利さというものが人間の幸せとは必ずしも一致しない、いやむしろ、便利な世の中が、かえって不幸な人々をつくり出しているのかも知れないといった、近代社会に対する懐疑の念が世界中から湧き出してもきています。
日本の社会は、戦後半世紀の間に急激な近代化を遂げた為、こうした矛盾もいたるところで出てきていると思います。
人間は皆、幸せになりたいと願ってきました。そしてその為に働き、頑張ってきたのです。しかし、それでは何が一体幸せなのかということを、真剣に考えること無しに、便利な世の中・豊かな社会というものばかりに憧れてきたのではないでしょうか。
幸せの青い鳥を探して歩いた挙げ句の果てに、帰ってきた家の中に青い鳥がいるのを見つけたという童話の「青い鳥」のように、結局、幸せというのは、私達の家庭の中に、また私達自身の中に有るものではないでしょうか。また幸せというのは何が自分達にとって本当の幸せなのかということを知っている人間にしか決して訪れないものなのではないでしょうか。私自身、家族全員で迎えるこの幸せをかみしめながら、新春を迎えたいと思います。
これからも、生きて良かった長生きをして良かったと本当に皆さんが実感できるような社会になるよう微力を尽くしたいと思います。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
シリーズ教育 -家庭の教育-
21世紀を担う子供たちをどう育てるのか、ということで昨年の6月に中央教育審議会が第1次の答申を出しました。ここには「生きる力」をキーワードとして、21世紀を生きる子供たちに必要な学力やこれをどう育成するのか等の内容が盛り込まれています。そこには、学校教育の改革に触れ家庭や地域と学校が手を携えどのように子どもを育てていくべきか、また、その役割が今後どのように進められるのが望ましいのかが答申されております。今回はシリーズの最初であり、この答申を引用しながら家庭での教育、特に子どもの育て方を皆さんと一緒に考えたいと思います。
(1)これからの家庭教育とは
少し話が固くなると思いますが、今は個人主義の時代だといわれています。戦後、昔の価値観が崩壊する中で、欧米から様々な価値が入りましたが、これが日本人に与えた精神的ショックは凄いものがあると思います。今の子供たち、我々大人も含めてこの個人主義や自由主義を、「何をしてもいいんだ」という形で理解していないでしょうか。欧米では、この個人主義の基盤には宗教という大きな道徳観があります。日曜日には教会に出かけ、常に教会という精神的な縛りが、個人の生活や行動を内面から規制しています。ここのところが少し、日本の多くの人々とは違うところではないでしょうか。ところで、家庭とはどんなものでしょうか。男女が結婚し社会的にも認められ、子どもを育てる。この我々が営んでいる「家庭」には、どんな教育的な意味があるのでしょうか。
先の答申では、家庭教育こそすべての教育の出発点であると言っています。そして、21世紀を生きる子供たちの基礎的な資質や能力を育成することは、親子の愛情を基礎にした家庭教育においてこそ可能であるとしています。ところが、現実は受験競争や過度の学校依存のため、昔から家庭が行っていた子どもへの躾や、他の人への思いやりや情操の涵養、といったものまで学校に押しつける傾向があることが指摘されております。更に、子どもの教育や人格形成には家庭が最終責任を負うものであり、この責任を自覚し、家庭が本来果たすべき役割を見つめ直す必要があるとも言っています。
これを言い過ぎだという考え方もあるでしょう。しかし、やはりここは今一度自分の足元を見つめるいい機会だと思います。先に個人主義の例を出しましたが、今の子どもの多くはこれを更に、利己主義と一緒にしている傾向がないでしょうか。また、親の方でも子どもの価値観を育てることに何か自信を無くしている、そんなことがないではないでしょうか。東京都の調査ですと高校生の3割がテレホンクラブを利用した経験があるといっています。実にショッキングな調査です。今のように情報が氾濫している時代には、子どもたちは興味本位から様々なことに反応します。しかし、それに染まってしまうか、踏み止まるかは子どもの価値観や自分の生き方をしっかり持っているかどうかに係わってきます。この生き方、人としての価値観を育てるところが、親と子の愛情であり家庭であろうと思います。
(2)家庭の「守・破・離」
子どもを取り巻く環境も随分と変わってきました。学校で出来ること、家庭で育てること、この役割をしっかりと考え、互いに力を合わせることが必要です。 21世紀は情報化の時代とか超高齢社会、成熟の社会とか言われています。進歩のスピードは早く、子どもたちが学校で習う知識は10年も待たずに陳腐化し、社会に出てからも必要に応じて勉強しなければならない生涯学習の時代になります。このような時代に生きる子供たちに必要なのは、自分自身の力で課題を見つけ、解決していく力です。自分のよさを認め、これを伸ばしていく姿勢を育てることこそ重要であろうと思います。これは学校にだけ任せておくべき問題ではありません。よく親が子育ての自信をなくしているのでは、という話を耳にしますが、いま言ったようなことは、なにもそんなに難しいことではないと思います。親として許さないことは毅然として許さない、一線を引くべきとこは引くといった言葉だけではなく、態度で示す。こんな親子のコミュニケーションこそ、家庭の道徳感や人の生きかたを学ばせる一番大事なことだと思っております。
例えば、「自分で好きなように考えてやりなさい」と言われるほど不安なことはありません。ゲーム機を買う、髪を染める、何か行動を起こすときは子どもはやはり不安です。何をどう考えるのかが不安なんです。この考えかたの基準を示すのが親の規範であり、考え方だと思います。何か形ある価値を親が示し、これに反発して乗り越えていくことがなければ、子どもの成長もありません。この親の価値こそ家庭の教育の根本であろうと思います。
「守・破・離」という言葉があります。これは一つの型をまず勉強する。そして、自分のものにしてその殻を破り、更に自分の型を作っていくという意味ですが、家庭での親子の関係もこれと同じものだと思います。自分の子どもはこうあって欲しい。これを一つの形として与える、この形を破ることから子どもの個性が生まれると思います。中学生が髪を染める問題なんかも、これとよく似ています。それは校則、学校の規則で決められているからいけないと言うことしか言えなければ、親と子のある種の対決を親が避けていると言わねばなりません。家庭の価値観、親の価値観と子どもとぶつかり合い初めて、親の生き方や考え方が子どもに伝えられるだろうと考えます。
(3)親のハートと家庭のルール
テレビなどで子どもの様々な問題がよく報道されます。何でそんなことが起きるのか、と思うのは私ばかりではないと思います。しかし、子どもが事件に巻き込まれる前には何らかの信号が送られていたのではないでしょうか。家庭で子どもの態度や言葉、服装行動にも様々な前兆があったのではないでしょうか。子どもから様々なサインがあったにもかかわらず、親が見逃していたということではないでしょうか。
最近家庭の中で、親子の対話が無くなったなどはよく聞く話です。本当にそうでしょうか。会話のない親子などあるでしょうか。私はむしろ、子供たちがサインを出す場が少なくなってきたのだと思います。父親の多くは遅くまで会社で頑張ります。母親も子どもの塾や教育費等のためにパートに出かけざるをえません。家には1人1台のテレビの普及。当然親子で見る内容も違ってくるでしょう。親の願い・親のハートを感じる場が少なくなってきたと思うのです。親のハートを感じる場、それは言葉だけではないと思います。自分の横に親がいるという存在の安心感、これが大切だと思います。私がPTAの会長をしていて聞いた話ですが、大都市の子どもの3割近くが朝食も取らず登校しているそうです。近所のファーストフード店で、親子で朝食を済まし出かける現実があると聞きます。たまには仕方ないことかもしれません。それでも首を傾げることを禁じえません。最近家庭にはルールが無くなってきたのかなとも思います。子どもは父親を通して社会を見ます、社会の規範・ルールを見ます、母親を通して安心と心の安定を得ます。1年の初めに家庭のルールを話し合ってみてはいかがでしょうか。
「SHOWYOU」では、これからも様々な話題を取り上げ私の考え方・価値観を皆様にお伝えしたいと思います。よく、政治家は公約を訴え、それを守らなくてはならないと言われます。しかし残念ながら最近ではそれを守られないのが政治家だとも言われます。しかし、私はどちらにも賛成できません。何故なら、政治家が本当に訴え、守らなくてはならないもの、それは個々の公約というよりむしろ、自分自身の信念そのものであると思うからです。これからも毎日の街頭演説や、この紙面を通して私の考え方・価値観を訴え、これを信念として磨き、確立させてゆきたいと思います。今後とも宜しくお願い致します。
大蔵政務次官
参議院議員 西田吉宏
明けましておめでとうございます。
皆様にはお揃いで佳いお年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
私も皆様のお力添えに支えられながら、参議院議員として八度目の新年を厳粛な気持ちで迎えました。
新年にあたりまして、まず昨年10月の参議院議員選挙に際し、新しい選挙制度のもとで大変厳しい選挙でありましたが、自由民主党に対して皆様方から暖かい、そして力強いご支援をいただき、立派な成果をあげることができましたことに対し、深く感謝とお礼を申し上げます。
また、昨年11月第二次橋本内閣の誕生にあたり、私は大蔵政務次官を拝命いたしました。いまわが国経済はようやく明るい兆しが見えてきたものの、依然として低迷をつづけており、景気の回復を早急に図って行く必要があります。さらに大蔵省改革が強く望まれている時、その責務の重大さを痛感し、職務の遂行のために全力をあげて頑張っているところであります。
21世紀を目前にして、国際社会はさまざまな問題を抱えて低迷をつづけています。このような中で、わが国はいよいよ超高齢化社会を迎えるのであります。もうこれまでのような右肩上がりの経済成長は望めない状況の中で、今日の危機的財政を立て直し、安全で安心した生活を送ることの出来る社会をつくり上げていくために、山積する困難な問題を一つ一つ解決していかなければなりません。
そのためには、広く国民の理解を得ながら行財政改革を断行し、21世紀に対応できる国づくりを、推し進めていかなければならないのであります。第二次橋本内閣は「行政内閣」といわれております。私もその一員として微力ではありますが全力を傾注して期待に応えていく決意であります。
わが郷土京都も、荒巻知事を先頭にして、活力ある府政を展開されておりますが、今後さらなる進展のために、私も西田昌司府議会議員と緊密な連携をとりながら一生懸命に努力いたして参ります。
結びに、皆様方のご健勝・ご多幸をお祈りし、新年のご挨拶といたします。
平成9年 元旦
瓦の独り言
羅城門の瓦
工事のカバーが取れて、新しい「京都駅」がその全容を現しました。およそ地上60m、東西500m、まさに平成の羅城門の感が在ります。
かつて平安京のモデルとなった中国長安の朱雀門(羅城門)には高さ5mもの城壁が長く続いていました。しかし異国民族の侵入の危険にいつもさらされていた中国と異なり、平安京は平和で羅城門は城壁を持つ必要がなかったのです。羅城門はフランス・パリの凱旋門のように交通の起点であり、平安時代に坂上田村麻呂が蝦夷征伐から帰ったときに通った凱旋門でした。
ところが現代の羅城門たる「京都駅」はJR東海道線といった城壁を備え、下京区と南区を洛中、洛外の様に分断しています。この現象は今に始まったわけではなく、明治10年に鉄道が開通し、京都駅が今の場所に設置されてからです。当時「七条ステンショ」と呼ばれ、烏丸通りの南端に位置し都の南正面を守る形と取ったのです。鉄道の開通によりかっての八条村、九条村、唐橋村の村域は分断され、六孫神社や偏照心院の庭園が消えてしまいました。当初、北側にだけ出入口が在り、南側は大正時代になるまで出入口が在りませんでした。南北の往来は狭い 道や踏切りで、ここを通れない荷車などは随分と迂回したようです。
鉄道線路は南側の住民にとって市内への大きな障害物になっていました。大正11年3月京都市会において「市南部の発展についての建議書」が提案され南北道路の確保を訴えていました。
さて、大正10年に国鉄東海道線が伏見大亀台を越えるルートから今の東山トンネルを通る直線に変更されるとき立体交差の話が在ったと聞き及んでおります。東山の峰を越えて京都駅を高架にし、桂川辺りで平地に下ろす計画だったようです。それを実行しておけば南北分断の問題点はないのですが、当時「汽車から他人の家を覗くとはけしからん」との反対に遭い、やむなく長いトンネルを掘って現在の状態になったそうです。
さて、新しい「京都駅」は国際化に向けたCAT(シティ・エア・ターミナル)機能や、文化ホール・ホテル、デパート、専門店などの入ったアミューズメント広場が出現しますが、全国何処にでもある駅前と、何処が違うのでしょうか。平成の羅城門たる「京都駅」は平安京のような機能を持つことが出来るのでしょうか。21世紀に向けての京都のランドマークになりうるのでしょうか。JR東海道線で洛外に分断された南区の住民にとって、非常に関心のあるところですが、こんな心配をしているのは羅城門の瓦一人だけでしょうか。
沖縄に関する報道を見ていると、沖縄では知花昌一さんのような反基地、反アメリカの活動家ばかりであると言うような印象を受けますが、これは正しく沖縄を伝えてません。実際に沖縄の人に話を聞いてみると随分現実は違います。
まず、沖縄の米軍用地のうち民有地については地主約32000名のうち90%以上の約29000名の方々と既に賃貸契約を交わしており、面積で言うと 99%以上になっています。未契約の方、約3000名のうち約2900名がいわゆる一坪地主と呼ばれる方であります。例えば普天間飛行場では20坪ほどの土地を約600名の方が共有しており、一人あたりの面積は約30センチ四方になります。また、嘉手納飛行場では600坪ほどの土地に約2300名の地主がおられ一人あたりの面積は約95センチ四方、座布団一枚分にしかなりません。しかもこの方々の大半は本土におられる方であり、その中には中核派や革マル派などの反政府活動を繰り返し行っている運動家やその支援者の方も大勢いるといわれています。知花さんもその一人であるわけですが、このような一般市民と呼べないような方の意見をさも沖縄を代表するかのような報道では物事の真実は見えません。沖縄では決して反米意識は高くないのです。
ではあの沖縄の叫びは何なのかといえば反日、反大和という感情が非常に根強いということであります。それは遠く琉球王国と薩摩との朝貢外交に始まり大東亜戦争末期の沖縄での地上戦、さらには戦後の米軍の占領、そして今日の安保条約に基づく基地問題など、常に沖縄は本土の犠牲になってきた、また捨て石にされてきたという思いが多くの県民にあるということを私たちは知らねばなりません。そして、沖縄の人々のこうした思いに対して私たちは何も答えることができないというのが現実ではないでしょうか。
日米安全保障条約はこうした事実を前提に考えねばなりません。安保条約が日本の安全と繁栄に不可欠であるということは、今や誰もが認めるところであります。しかし、この条約によって日本はアメリカに基地の提供を義務づけられているのですが、こうした負担の部分については誰も感じることがなかったのです。それは日本における米軍基地の75%が沖縄に集中しているからです。日本人は安全と水はただで手にいれているということがよく言われますが、それは本土にすむ人間に限ってのことで、沖縄の人々にとっては決してそうではなかったのです。
日本の平和は安保条約によって支えられている。しかし、その負担の大部分は沖縄一県に強いてきた。にもかかわらず、本土にはそういう意識がない。そして、沖縄は日本で一番貧しい(県民所得や社会資本の整備率は最下位、失業率は本土の2~3倍)ままである。こうした事実を私たちは認識しなければなりません。
考えてみれば自分達の生命や財産は自分達で守るということは国家の最大の役割であり、政治の最大の使命であるはずであります。しかしそうしたことを我々はほとんどこの50年間意識すらせずに暮らしてきたのです。この国民にとって一番大切なことを他人任せでアメリカに任せっきりにしたり、沖縄だけに押しつけたままできたのです。そしてその上に私たちは豊かな社会を築いてきたのです。しかしそれは国として、また政治としての役割も使命も放棄したままの危うい土台の上に建ついわば砂上の楼閣にすぎないのではないでしょうか。
今、巷間ではいろんな方が改革ということを口にされていますが、その多くがこうした本質の問題に触れないまま、いかにして日本の持続的繁栄を守るかということばかりに終始しているのが現実です。しかし、そのような論議は砂上の楼閣の上に虚構の繁栄を重ねようとするのと同じで、たとえ嵐がこなくても、自らの矛盾という重みで崩れることでしょう。
沖絶問題を契機に、国と政治の役割と使命をもう一度深く認識し、国のゆく末に誤りのない選択をしようではありませんか。
先頃公表された中央教育審議会審議のまとめでは「子供にゆとりと生きる力を」ということを大きなテーマに据えた上で「すべての教育の出発点は家庭」と、その重要性を指摘し、週休2日制や育児休暇などの整備と同時に、父親の責任の自覚と企業の協力を呼びかけています。

また、審議のまとめでは個性尊重の教育ということを全面に押し出して、生きる力を育むためにも家庭の教育力の一層の促進をうたっています。確かに、多様な価値観を認める上でもまた、自ら学び、考え、主体的に判断し、行動するという「生きる力」を育てるためには個性尊重は重要なことであります。しかし、その一方で日本人としての伝統や慣習に基づく価値観や株序の大切さを学ぶということについてはまったく触れられておりません。私にはこの点が非常に遺憾であります。
と申しますのも、欧米の自由主義、個人主義という価値観にたって戦後の教育は推進されてきたはずであります。その一方で戦前の日本の伝統的な儒教的な価値観はすべて封建的なものとして葬り去られてきたのが、今日までの現実ではなかったでしょうか。そしてその結果どうなったかといえば、経済の面では、自由主義経済体制のもと大いに発展し、物質的な豊かさを手にいれて参りました。しかしその一方子供の教育環境の面では、いじめの問題、家庭の教育力の低下など子供の健全な発達を歪めているのが現実であります。しかも、その原因は「行き過ぎた自由主義・個人主義」が蔓延してしまったためで、他人や社会のことを考えない勝手気ままな利己主義者を生み出してしまったからです。また、経済の面でも社会の秩序を考えず、欲望のままに行動するとどうなるか。それはただバブルが膨れ上がり、崩壊するだけだということもついこの前に経験したところであります。
これらの教訓が教えるところは、「確かに自由主義・個人主義は大切な価値観であるけれども、何の規制もない自由主義や個人主義は結局のところ勝手気ままな利己主義に陥るだけである。本当の意味での自由主義・個人主義は伝統や慣習という秩序とのバランスの上にあるのだ」ということではないでしょうか。そしてこのバランスの大切さを教えることが自ら学び、考え、判断し、行動するという「生きる力」そのものではないでしょうか。
従って、これからの個性化の教育をすればするほど、本当に教えなければならないのは、伝統や慣習、言い替えれば、日本人としての伝統的価値観や良識でありましょう。にもかかわらず、この本質の部分に触れずに「生きる力」だの「家庭の回復」だの並び立てても、私は魂のない空念仏にすぎないと思うのであります。
私はこれからの教育、とりわけ初等・中等教育を考える上では個性化と同時に、日本人としての伝統的価値観や良識を教えることがとりわけ重要であると思っております。いじめ問題を始め、現代の子供達の抱えるさまざまな問題の原点は家庭にあり、家庭の回復こそが問題の解決であると思います。
また、高齢化社会の福祉について考える上でも家族や地域社会とのつながりということが前提となるのですが、現代社会というものはそのつながりをどんどん崩壊させる方向に流されているのではないでしょうか。元来、欧米の個人主義に対して日本では伝統的に家族主義でありました。しかし、家を守る=封建的制度という非常に安直な考えから、家族主義を唱えること自体「封建的」「保守反動」という形で、特に公の上では日本人の価値観の中から排除されてきました。
しかしこれからは、互いの立場と役割を認め合い、健全な子供を育み、父や母としての尊厳と自信に満ちた健全な家を再度作ることが大切です。社会の基本的な構成の礎としての家を回復することが必要です。そのことは日本の伝統的価値観の回復と表裏一体のものになっているのではないでしょうか。
個人主義の原理を家庭の中にそのまま持ち込めば、家庭が崩壊するのは当然の帰結であります。家庭の回復のためには、まさに行き過ぎた個人主義を是正し、戦後50年間封殺されてきた家族主義に代表される伝統的価値観に回帰し、そのバランスをとること以外無いのであります.そして大切なことはこうしたことを国民の中で論議し考える環境を作ることだと私は思います。特に、日本的価値観は政治によって抹殺されたものであるだけに、その回復は政治の責任ではないでしょうか。
(この原稿は、6月28日、本会議での質問の大意です。)
2月25日に施行されました京都市長選挙におきましては、皆様方に多大のご協力ご支援を賜りまして、誠に有難うございました。お陰をもちまして、私達が推薦をしておりました、桝本頼兼さんが新市長になることができました。しかし、その内容は、共産党の推薦する候補者とわずか4000票余りという薄氷を渡る思いの勝利でした。私はその原因について分析と反省をしなければならないと思います。
私は大きく2つの原因があると思っています。1つは、自民党はじめ市長与党の相乗り体制に対する批判、もう1つは住専問題の影響があると思っています。
第一点目の問題は、船橋・今川市長の時代には、共産党をも含む、オール与党体制の中で市政が進められてきたことへの不満感や今、国会では住専問題で与野党が対決しているにもかかわらず、京都で手を握っているという不信感が、有権者の皆様にはあったと思います。そして何よりも、与党対共産党という、選択肢の少なさが、多くの府民にしらけムードを持たらせたと考えております。

京都の場合は他都市に比べて、共産党が非常に強いという事情はあるものの、政党の使命として、地方議会においても、もう少し政党色を出して、有権者の皆様に選択をして頂ける土壌を作っていくべきだと思っております。
第二点目の問題については、本来京都の21世紀のリーダーを選ぶ選挙であるのに、住専問題の是非を問う国民投票であるかのような共産党の選挙戦術に乗せられてしまったことが考えられます。しかし、私たち自民党も、もう少し真正面からこの問題を市民に訴えるべきではなかったかと反省しております。
住専問題につきましては、次のページに私の考えをまとめさせて頂きましたが、今回の市長選挙を振り返って私が一番痛感したことは、「政治家が有権者に日頃から、概策や考えを訴えていないがために、政治への判断材料をなくし、ひいては関心もなくなってしまう」ということです。
政治家の使命は、京都や日本の将来を見据えた政策提言を行い、議論をしていく材料、即ち指針を示すことにあると思います。目先の問題ばかりを論議していては将来に対する指針を提示できないばかりか、有権者の皆様に政策の違いを判断して頂くこともできません。また昨今の住専問題のようにマスコミ調の感情的な議論だけでは、有権者の皆様に日本の国の将来の姿から現在の問題を見つめるという政策提言はできません。
選挙の時だけでなく、日頃から自らを磨きその考えを常に皆様に訴えていくことの大切さを今更ながら痛感致しました。
今年は1月から各学区でミニ懇談会をお願いし、毎朝、宗教法人法の問題から最近では、住専問題に対する私の考え方を訴える街頭遊説も続けております。これからも地道な日常の積み重ねを大切にしてゆきたいと考えております。
非常事態の日本
住専問題の本質
住尋問題については大きく、2つの問題点が指摘されております。
まず第一点目はバブルの発生崩壊の責任はどこにあるのか、借手責任、貸手責任の明確化など原因と責任の徹底糾明ということ。
第二点目は、6850億円という税金を何故投入しなければならないのかということでありましょう。
第一点日の指摘については、私も全く同感であります。国会の参考人質問を見ていても、住専から多額の借入をし、焦げつかせている人物が「我々の取引に第三者が口を出すな」という発言をしたり、自分自身がかつて大蔵省のOBであった住専の社長が「責任は国にある」ということを平然と発言したりしている様子を見ていると、その思いは益々強いものとなります。
法律を改正してでも、逆さにして鼻血も出なくなるまで徹底的に債権を回収して、絶対に借得を許してはなりません。そして、貸手責任、借手責任を明確にしなければなりません。
二点目の税金投入の問題には、世論の大きな反対の声があると報道されております。バブル期にしこたま儲けて、バブル崩壊後、損失が出たからといって民間会社の損失の補填を何故国がみなければならないのかということが、述べられています。私もこれについても全く同感であります。個別の企業の問題としてとらえるなら税金投入の根拠は無いと思います。
しかし、問題は今回の税金投入は個別の企業の救済を意味するものでないということです。住専会社は全てつぶしてしまいます。そして、残った不良債権を確実に回収する為に、警察や国税出身者の方にご協力頂いて、別会社を作るのです。従って決して住専会社や損失を出した借手を救済するものではありません。
住専問題を語る上で一番肝心なことは、今の日本の経済の状態は、「非常事態」であるということを認識しているかどうかということです。
「家に火がついた」「さあ皆で火を消そう」と言っている時に「燃えているのは誰の家だ」「誰が火をつけたのか」と騒ぎたてるだけでは、家は全焼してしまいます。火事の時、一番にしなければならないことは「まず、皆で火を消す」こと以外ありません。そして、騒ぎたてているだけの野次馬を鎮め、皆で協力して火を消すことがリーダーの役割でしょう。今の日本の経済はまさにこの様な状態なのです。そしてそのことを知らないのは私達日本人だけなのです。
岡目入目、今、ジャパンプレミアムと言って、海外の投資家が、日本にお金を貸す場合は、通常の利息より高い利息を要求するようです。つまり、海外の目からは「日本は危ない」と思われているのです。もし、公的資金を投入しない為に金融機関が倒産したら、取り付けさわぎが発生したら、文字通り日本の経済はつぶれてしまいます。昭和の初めの金融恐慌や、オイルショックの時のトイレットペーパー騎動も、ほんのちょっとしたことがきっかけでパニックが発生したということを忘れてはなりません。公的資金の投入はこうした最悪の状態を避ける為であり、政府が金融枚関は倒産させないということを内外に保障し、表明することを意味するものなのです。
新進党の国会議員は、ピケをはって国会の開催を妨害し、言論の場であるはずの国会をじゅうりんしてきました。しかしその彼らでさえ「公的資金投入」以外に、日本の経済を混乱させない方法を提案できないのが現実であります。このことは、まさに火事場で騒ぐだけの無責任な野次馬にも劣る行為であります。かつて、東京の青島知事が選挙の際、「東京協和」「安全」の二つの信用組合の損失処理に都民の税金は使わないということを掲げて当選されました。しかし当選後青島知事は、二つの信用組合を守るのではなく、都民の生活を守るためには300億の税金を投入する以外ないとして公約を破棄されました。「無責任男」でならした青島知事でさえ、都民の生活を守るために公的資金導入を決意されたのです。まともな代替案なしに、公的資金投入を反対するだけの新進党は一体このことをどの様に考えているのでしょう。皆様の賢明なご判断をお願い致します。
昨年は、阪神大震災、オウム事件という社会の基盤や秩序を根底から覆すような災害や事件が頻発しました。また政治や経済の面でも、国会の中の第三党の社会党の委員長を総理大臣にして第一党の自民党がこれを支えるという、非常に不自然で不安定な政治状況が続き、景気もなかなか回復基調にならない状況が続いております。世の中のすべてのことが混沌としたこうした社会背景の中で、このような状況から脱出するためには、改革、変革こそが必要ということで、政治面では政治改革の断行、経済面では規制緩和の実現ということこそが必要なのだと連日報じられております。そして、政治改革では小選挙区制という、政党が全面に出て競いあう方法が採用され、経済面では、市場原理こそが唯一の普遍的な経済原理なのだということが絶対視されようとしております。これらの一連の流れはすべて、同じ価値観で書かれております。それは政治面でも経済面でもアメリカ型の仕組みをそのまま導入し、これこそが世界の基準なのだという考え方です。

しかし、私はこうした考え方に少なからず疑問を持っております。なぜなら、アメリカ型の政治経済の特徴は自由競争を通じて経済的な豊かさを万民が享受するということに一番の価値を置いております。また、このことこそ戦後の日本がアメリカを一番のお手本として追求してきたことでもありました。
しかし、そうした競争第一、経済第一という考え方が、日本の社会を空疎なものにし、オウム真理教を生み出す背景にあったのではなかったでしょうか。そして、政治や経済界を含めた様々な不祥事もこうした背景によるところが大きかったと思います。つまり、現在の日本の抱える様々なゆがみやひずみはすべてこうしたアメリカニズムとでもいうべき、競争と経済第一主義が原因になっているといっても過言ではありません。
にもかかわらず、規制緩和、市場原理をはじめとした激しい競争の道を選び、かつその目指すべきものがより一層の経済的豊かさのみであるというのなら、そこには戦後50年間の反省が何にも見られないのではないでしょうか。
これから日本が目指すべきは、物質的豊かさへの憧れとそのために他のことを犠牲にして、ひたすら自由競争の中を駆け抜けてきた、その姿勢を反省することが土台となると思います。そして、競争と同時に共生を考え、物質的豊かさと同時に精神的豊かさにも重きを置くということではないでしょうか。このことはつまり我々一人ひとりが、一体何のために生きているのか、ということを自らに問直すことでもあります。世間がどんなに騒いでも揺らぐことのない自らの価値観をしっかり持つことが変革の時代、不確実性の時代を生き抜くためには不可欠の要件となります。今年も私の信ずる信念をSHOWYOU(お伝え)していきます。本年も宜しくお願い申し上げます。
7月の参議院選挙におきましては、皆様方に絶大なご支援を賜りまして誠にありがとうこざいました.お陰様で、全国的な自民党の退潮の中にもかかわらす、西日よしひろ参議院議員はトップ当選で再選を果たすことができ、ここ南区では市内最高の得票率をあげることができました。
しかし、一方比例区では比較第一党の座を新進党に奪われるという結果に終わってしまいました。こうした自民党の敗北という事態を我々は真摯に受けとめ、再び国民の信頼を得るために、何が必要であるかを自らに問い直す必要があろうと思います。そのためにも自民党総裁選挙は、広く国民の皆様に自民党の政策を知っていただくための意義あるものであります。新進党との違いを明らかにし、「国民に開かれた政党」ということをアピールするためにも総裁公選はたいへん重要なものです。そこで、私が政策審議会会長をつとめています自民党全国青年議員連盟におきましても、総裁選の傾補者同士による公開討論会の実施を三塚幹事長に要求し、連日この準備のため奔走をしてまいりました。一時は無くなったかに見えた総裁選ではありますが、小泉純一郎議員と橋本龍太郎議員による街頭演説会やテレビでの討論会など広くその政策を訴えることにより国民政党としての責務をなんとか果したところです。我々地方議員も大変微力ではありますが囲民に開かれた「分かりやすい政治」をめざして努力をしていかねばと肝に命じているところです。
4月の選挙の後、私は府議会では総務常任委員会(財政や税制をはじめ府政全般を総轄的に所管する)の委員長と同和対策特別委員会の委員を拝命致しました。また、前述いたしましたように自民党の若い地方議員の会であります全国青年議員連盟(初代会長 中山太郎衆議院議員)の政策審議会会長を去年に引き続き選任され、この9月からは京都府連の青年局長に就任いたしました。

そして、この6月には自民党議員団を代表して荒事知事に対して代表質問を行いました。その中で、地方分権や京都府の産業政策、また教育問題などについて日頃から皆様方にお話している私の思いを、知事にぶつけて参りました.その結果、知事や役人のつくった答弁書を読む、通り一遍の答弁ではなく、知事の思いをそのまま言葉にして答えて頂き、先輩同僚議員のみならず、とかく議論が少なく単調だと批判していた新聞記者からも、この日の私と知事との論戦には、久しぶりに本会議らしい風景を見たと評価を頂いた次第です。
この「Show you」にも私の様々な思いや政策なとを書いていきたいと思います。是非ご一読していただき、こ意見をお寄せ下さい。次頁には私の教育に対する考え方をまとめました。
「心豊かな子供達を育てる」ために
戦後の日本では、すべての子ども達に「教育の機会均等を図る」ということが大命題となりました。その結果、門地閨閥にとらわれず能力を等しく身につけさせることが求められ、その客観性を高めるために数字で表される評価が中心となりました。それがいつしか学科試験の成績の良い者が優秀な人間だという考えが定着し、ここに偏差値教育の土台が出来上がったものと思います。
これは日本が復興から高度経済成長を遂げていた時期には、一定の役割があったかも知れません。しかし、21世紀を迎え経済も諸外国との協調や円高の時代にあって、この「成績が良い者が教養も豊かで、優秀である」という尺度を見直す時期に来ていると思います。あのオウム事件にも現れたように、いい大学に入るための学力と人間としての豊かさとは何の関係も無いことを我々は知ることが出来ました。
そこで私はもう一度、教育の原点である豊かな子とも達の育成は何かを問い直すことが必要であると思います。私は子ども達の教育の原点は、心の教育であろうと思います。これは、学校教育では徳育の重視であり、家庭では親子関係の中で育っていくものだと考えています。昔は1台のテレビを囲み家庭の団欒がありました。今は個人の部屋でテレビを見ています。子どもの教育は学校と家庭・地域とが両輪の輪となって進めるものです。家庭では家族の絆を再び取り戻す努力をすることも必要でしょう。そのための親子の共通体験や親としての役割を果たすことが、これからはますます必要になってくると思います。
私は先の府議会で、これからの教育改革の核は徳育であり、その根底には競争と共生のバランス感覚が大切であると訴えました。競争は自由社会を活性化させ、個人の能力を伸ばすために必要なものであります。それと同時に皆んなで共に生きる、手をたずさえて共に地域社会を形造っていくという公正・共生の考え方も忘れてはなりません。
私達の子どもが生きる社会は、高度情報化社会だと言われています。例えば、インターネットを通して、子ども達は全世界と情報のやり取りをします。学校ではコンピュータを使って授業をします。これらコンピュータを活用した新しい教育・マルチメディア教育には、私は努力を惜しむものではありません。むしろ積極的に推進すべき充分な予算もつけてまいりました。しかし、それだけでは不十分だと考えています。コンピュータを使った経験は疑似体験であり、これの積極的な活用と同じ位に、学校や社会での直接体験は重要であります。情報を操り、これに長けるのみでなく、生み出された情報の裏にある人間の労働の汗と苦労を感じとれなければ、真の教育とは言えないでしょう。あのオウム事件でも分かるように大学や大学院で得た高等知識を利用して、無差別に人を殺戮するのであれば、何故に教育と言えましょう。
私はここでも、授業でのコンピュータ活用と道徳や芸術などの心の教育や地域での清掃活動や老人のデイケアなどのボランティア活動なとのバランスの取れた教育が必要であると考えています。新しい未来志向の知識や技術の教育と日本の歴史に自分を位置つけ、我々の祖先が築いてきた優れた文化や社会を受け継ぐ、そんな心の豊かさを持った知性ある子ども達を育てなければなりません。
大局的見地から、このバランスを取って行くのが政治の任務であり、一方に偏たることなく行われているかをチェックするのが議会の努めだと考えています。自民党全国青年議員連盟政審会長としても、創造性溢れる人間性豊かな教育を実現するための政策を立案し、実行してまいります。
皆様方のご支援のお蔭で3回目の当選を果たすことができました。心より御礼申し上げます.今回の選挙は私にとって3回目とは申せ、4年間の任期を全うした初めての選挙であるだけに、大変緊張もし、また備えて参りました。その上、皆様の日夜にわたるご協力を得まして、選挙事務所の体制もかつて無いほどの強力な布陣を以って臨むことができました。
その結果、悪天順によって投票率が10%もタウンしたにも関わらず、11,527票にものぼる沢山の票を頂き、トップ当選を果たすことができました。この得票数は、市内選挙区で4番目、得率数も前回よリ3.4%も多い39.9%を占めるに至りました。

これも皆様方のご支援のお蔭と改めて感謝申し上げるとともに、その責任の大きさに身の引き締まる思いでおります。
これからも一層の精進と努力を行い、選挙期間中に申しておりました公約実現のため、全力を傾けがんばる所存でございます。今後とも変わらぬご指導とご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。
さて、今回の選挙は、東京・大阪の知事選挙に見られたように、「無党派層」といわれる人達の存在の大きさがクローズアップされました。われわれ議員の仕事は、常識と良識に裏うちされた皆様の声を議会に反映させることであります。そのためには、皆様とわれわれ議員の双方とが、
同じ常識と良識を共有していることが前提となります。しかし、東京・大阪の知事選の結果は、有権者と政党との間に明らかに大きな常識のずれがあることを証明しました。このことは、既成政党に対する不信感がいかに大きいかということでもあり、われわれ議員の一人ひとりが他山の石として肝に命じておかねばならないことだと思います。
私は、この日本という社会と文化の中で、社会人として暮らしておれば誰もが、「当たり前」と共感できるものが必すあると思っております.そう考えるとわれわれ政治家が、最も大切にすべきは、この「当たり前」を感じられる感覚であり、それこそ「無党派層」と言われる人々が望まれる政治家の感性でもあると考えます。今回の東京・大阪の有権者の選択は、この「当たり前」の通じる社会を作るための逆説的選択と考えることはできないでしようか。
東西の冷戦構造が崩壊して以来、何が真実であるか、何を基準として考えればよいか、その物差しとなるものが無くなってしまったように思います。私はこんな時代にこそ、もう一度原点に戻って考えるべきだと考えています。この戻るべき原点こそ「当たり前」の感覚であり、その元をなすものは、日本という社会の歴史と文化伝統ではないでしょうか。“Be Trad”.政治家として私がやるべきことは、目新しいものを探すのでは無く、ます足元を見つめ直し深く修養すること以外にないものと思います。これからもこの原点を忘れずがんばっていきますので宜しくお願い申し上げます。
昨年一年間日本中が「政治改革」という言葉で終始しましたが、今年は「規制緩和」という言葉がこれに取って代わりそうな気配です。しかし、今回の規制緩和論では、庶民の暮らしという基本的な問題には一向に触れられず、大企業は勿論、中小企業や消費者も含め、ありとあらゆる立場の人々が自分達もその受益者になれるという幻想の中で、諸手を挙げて賛成をされている様に思えてなりません。本当にそうなのでしょうか。
たとえば、規制緩和の例として、大店舗法の改正があげられます。この南区にもダイエーやジャスコなとの出店が計画されています。確かに、これらのスーパーが出来ると、様々の品物が、安くて便利に買うことが出来るかも知れません。しかし、一方で、今までの既存の商店は間違いなく打撃を受けることになるでしょう。「これも、自由競争の世界では仕方がない」かも知れません。しかし、今まで自分達の近所にあったお店が無くなってしまうと、身の回りの買い物が不便になるだけでなく、街の様子も一変してしまうことになります。とりわけ対面販売という人と人とのコミニケーションを媒介として成り立っていた小売店への打撃は地域社会の在り様にも大きな変化を与えることになります。また、廃業に追い込まれに方の生活の保障は、税金で手当するということになるでしょう。
このように考えるとスーパーの進出は、一見物価は安くなり、街も活性化したように見えても、そのマイナス面も決して忘れてはなりません。そもそも、一番利益を受けるはずのスーパーでさえ、今までの大店舗法によって守られていた訳で、今後競争が激化すれば、アメリカの例を見るまでもなく、大手2、3社しか生き残れなくなるでしょう。
弱肉強食と言われる動物の社会でも、共に生きていく一つのルールがあります。ライオンだって満腹の時にはシマウマをむやみにおそうことはしません。自然社会では弱肉強食と同時に共生というルールが一体となって秩序が保たれているのです。同じ様に、経済が発展し成熟した社会では、大企業や強者の論理だけではなく、中小の企業や資本力が弱い企業とも、いかに共生していくかということを考えなければ、経済的にも社会的にもバランスを欠いた、一部の者の為の社会になるのではないでしょうか。
今論じなければならないのは、単なる規制緩和ではなく、我々が目指すバランスのとれた社会には、「どの様な新しいルールが必要なのか」ということではないでしょうか。アメリカのように歴史が浅く、今も新しい移民を受け入れている国では、何よりも自由競争(規制緩和)こそが「公正」の第一条件になることは分かります。しかし、これが国の成り立ちや、歴史も違う日本でも絶対に正しいという考えには疑問を感ぜずにはおれません。今回の規制緩和論も元を質せば、あの小沢さんの言うアメリカのような「普通の国」に成ろうということが始まりでした。しかし、世界をじっくり見回してみると、アメリカのような歴史と文化を持った国が決して、世界の基準となるべき「普通の国」とも思えません。我々は、規制緩和の大合唱を唱える前に、一体どんな国や社会を目指すのか、もっと徹底的に論議すべきではないでしょうか。
本年もまた、私の信ずる「政論」を皆様方にSHOW YOU(しょうゆう お伝えしたい)と思います。本年も宜しくお願いいたします。
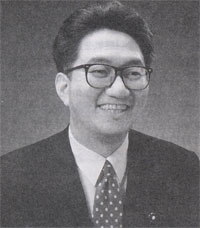
私が、会員の皆様のご支援により府議会に議席をいただいて、はや、4年半になろうとしています。
この 間の政治情勢は囲の内外を問わず、めまぐるしい変化を遂げてきました。そしてその際、合い言葉のように口にされたのが、ロシアではペレストロイカであり、アメリカではチェンジであります。さらに、日本では「改革」という言葉でした。奇しくも、同じ意味の言 葉が、世界中の多くの人々を引きつけたのです。しかし残念ながら、実際にその言葉通り、改革に成功した国はありません。これには色々な理由が考えられますが、こと日本においては、戦後50年間の歴史と過去をどの様に評価するのか、何を何のために、どの様に改革するのか、ということが何も論議されてきませんでした。
むしろ、手前勝手なだけの論議が行われ、それも政権をとるための手段としてしか利用されていないのが現実であります。マスコミもこれを煽ることばかりに終始し、結果としてイメージだけが先行する、そんな改革論議に多くの国民市民が巻き込まれてしまっているのが現実ではないでしょうか。
このような空虚な論議を繰り返すときにも、「それでも世界はまわっている」のであります。そしてこれをまわしているのは、我々一人ひとりにほかならないことを忘れてはならないと思います。「政治は、自分達とは別の遠い世界のものだ」とか、「悪いのは政治家だ」とか、他人任せで、自分を正当化するのは易しいですが、結局のところ、この社会を動かすのも、社会の安定により利益を受けるのも、また、混乱により損失を受けるのも、我々一人ひとりなのです。
マスコミの報道やイメージに踊らされるのではなく、自分の信する政治家としての道や、本質をつく論議や考えを、この紙面を通じて皆さん方にShow you(お披露目)させていただきたいと考えております。そしてそれが少しでも、皆様方の政治参加の一助になればこれほど幸せなことはないと思っております。
さて、本年京都は建都1200年の節目の年を迎えておりますが、そのとりまく環境は、府も市も税収不足による財政難等大変厳しいものがあります。府民市民の生活と福祉の向上をもたらすものは共産党の言うような耳障りがいいだけの政策ではなくて、京都経済の活性化をおいて語れません。府民市民一人ひとりの家計や事業が発展してはじめて、府や市の財政も潤い、府民市民の生活と福祉の向上を実現することができるのであります。そしてそのためには、京都経済の中心である中小企業の発展が必要不可欠なのであります。
今、戦後最悪の不況の中苦しんでおられる中小企業にもう-度息を吹き返していただくためには、今までのような制度融資の充実だけでなく、経営者の企業家精神を目覚めさせ、やる気を起こさせるような、新しいチャンスを提供しなければなりません。そして新しいビジネスを創り出すために、規制緩和、情報の公開、企業家の情報ネットワーク作り、これから来るべきソフト社会への対応など、これまでからも府議会で荒巻知事に要望をして参りました。また特に南区は中小企業の多い地域であります。これからも中小企業の発展と何よりも府民市民の生活と福祉の向上のため頑張る所存であります。 来年には政治家として3回日の審判を受けることになりますが、初心を忘れることなく、正論を語れる政治家になりたいと考えております。皆様方の変らぬご理解の程を心よりお願い致します。
板門店を訪ねて
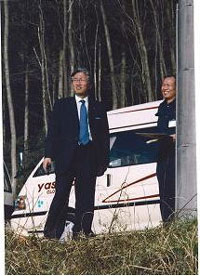
去る7月26日から28日までの日程で、帝国のソウルと板門店に自民党府連青年局海外研修団の副団長として訪問をしてきました。ときあたかも、北朝鮮の核疑惑に世界中の緊張が高まる中、金日成主席の突然の死去の直後の韓国の視察は、日本の平和の成り立ちというものの本質を考える上で大変有意義であったと思っております。
私が一番強く感じたことは、「平和は口で唱えるだけで叶えられる」ものではなく、現実には世界各国のパワーバランスで成り立っているのだということであります。いわゆる38度線、朝鮮半島を南北に分断する軍事境界線上の唯一の南北の対話の窓口となっている板門店に行くと、まさに、そうした感を強く抱くことになりました。僅か数十メートル前の境界線をはさんで同じ民族同士の南北の兵士が銃をもって対じする様を目の当たりにして、「第二次大戦後、世界中の地域や紛争は終戦を迎えました。しかし、只一つ休戦中という地域がある。それがここ朝鮮半島なのです。」というガイドの言葉が私の胸を強く締め付けました。
韓国の首都ソウルは今年、定都600年という記念すへき年を迎え、さまざまな観光キャンペーンを展開しています。街中に車が溢れ、まさに「漢江の奇跡」と呼ぶにふさわしい繁栄ぶりを見せでいますが、ここから直線距離でわずか40キロ余りのところに、板門店はあるのです。同じ民族・兄弟が銃を向け合い、親・兄弟・親族が敵味方に分かれて殺し合った民族の悲劇が、過去の歴史ではなく、今日までも続く現実としてあるのです。この国ではまさに戦争と平和が隣り合わせで存在しているのです。そして、実は日本もこの国から飛行機で僅か1時間半もあれば行くことのできる距離にあるのです。戦争と平和が同居する国と隣同士で住んでいるのが、我が日本なのだということを一体どれだけの日本人が実感として自覚しているのだろうか、とふと考え込んでしまいました。
平成の大不況と言われながらも、世界一の自由と繁栄を享受し続ける日本人。世界の外交官の間では日本人のことを「アヒルみたいな奴」と言っているということを聞きました。アヒルはなにかに驚くと、ギヤーギヤーと騒いで逃げ回った後、頭を土の中に隠して目と耳を塞いでしまいます。そうすることによって、あたかも恐ろしいもの、恐いものが何もないかの如く錯覚してしまう、否、錯覚しようと努力をするのです。しかし、すぐに捕まってしまうのですが、捕まらなければ、また同じように餌を求めて歩いていくのです。事件が起きるとすぐに大騒ぎをするくせに、喉もとを過ぎると、問題を解決するより、その事実から目を背け、まるで何もなかったかのように振る舞う日本人が、彼らには、臆病で利己的な肥ったアヒルに映るのでありましょう。
太古より日本は大陸から多くのことを学んできました。朝鮮半島はその大陸との窓口であり、我々の文化のいわばルーツとも言えるところでもあります。しかし、実際には我々はこの最も近いこの国のことをあまりにも知らずに、いや知ろうともせずにきたのではないでしょうか。朝鮮半島の平和は日本の安全と平和に欠くべからざるものであり、日韓両国は否応なしに運命共同体としての位置にあるという現実を、認識しなければなりません。その国が、実はまだ終戦ではなく休戦状態であり、しかも今、北の核の脅威にさらされているということは、韓国の人々にとってはまさに自分達の生命の問題であり、日本の我々にとっても、生活の安定と平和に即結びつく重大事でもあります。

ところが、マスコミがセンセーショナルに取り上げ、北の核が手すぐにでも日本の平和を脅かすかのような連日の過剰な報道のまっただ中では必要以上にヒステリックな反応を示した我々日本人も、-ケ月も経てばそれはもう昔のこと、北の核の問題よりは近頃の天候の異常さ加減の方に興味が向いてしまう有り様です。マスコミの報道が少なくなると我々は次の出来事に関心を向けてしまいます。しかし、問題は何も解決していないのです。現実を直視すること、問題を解決すること、問題を解決する努力をすることなく、目と耳を塞いだまま只々、現実が過ぎるのを待っているだけで飽食の時代にかまけていては、アヒルと呼ばれても仕方がないのかも知れません。
今回の韓国視察を通して私は、改めて囲際社会の厳しさを痛感すると同時に、戦後半世紀の間、国際社会の現実を直視せず、ひたすらお題目を唱えるだけに終止してきた日本の現状にうすら寒いものを感じたものです。国際化の時代とか、改革の時代とか言われていますが、今、国際化の時代に一番改革をしなければならないものは、現実を直視せず、また、本質を考えようとしない我々のものの見方そのものではないかと考え込んでしまいました。